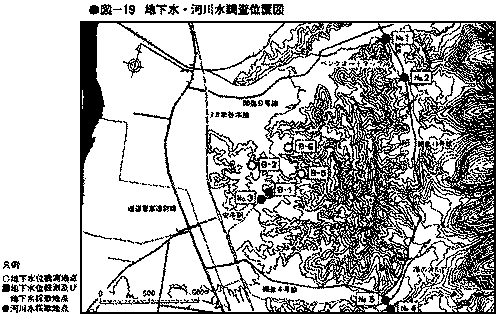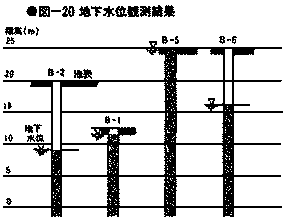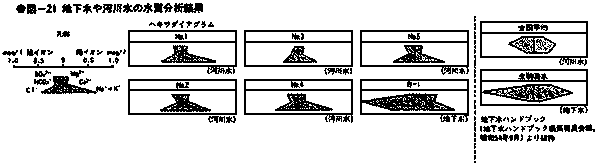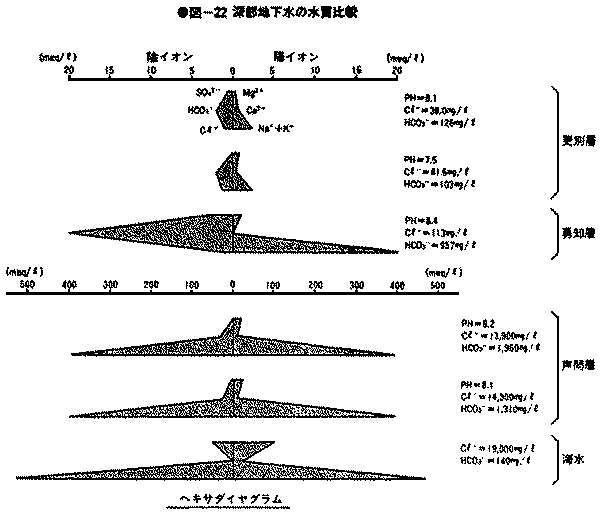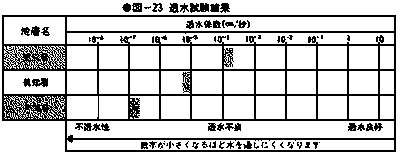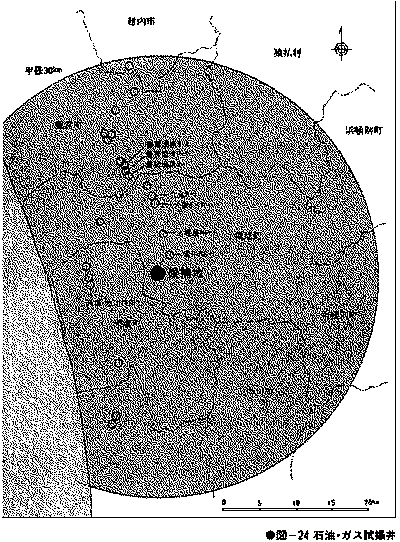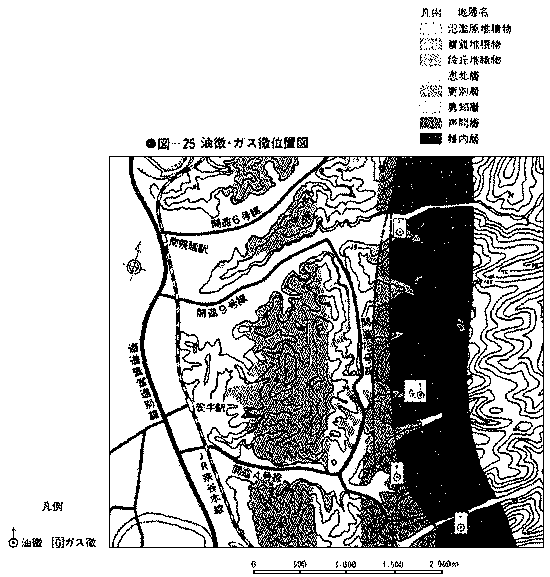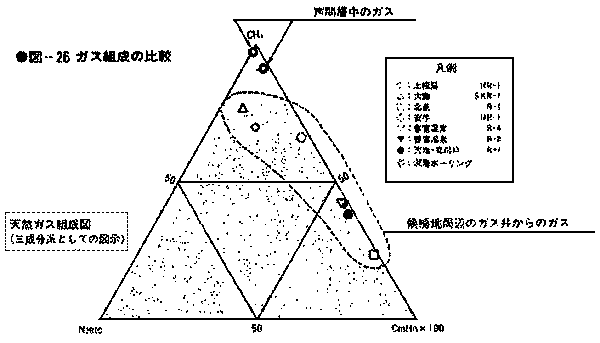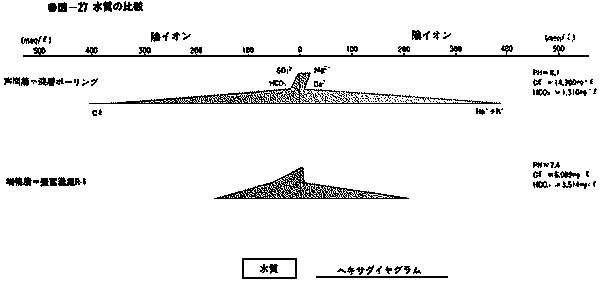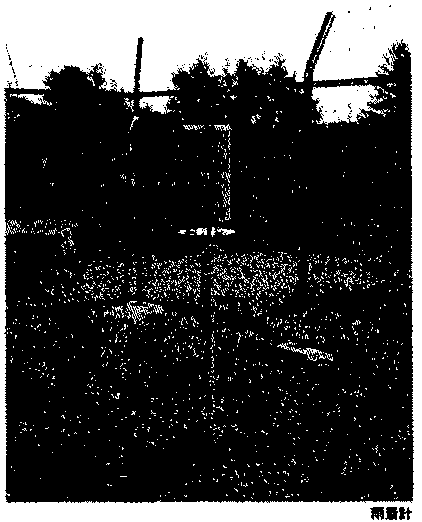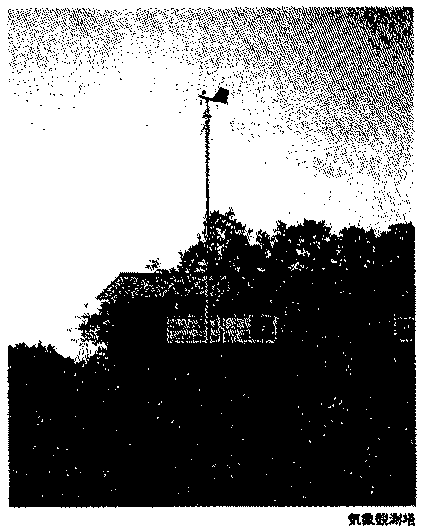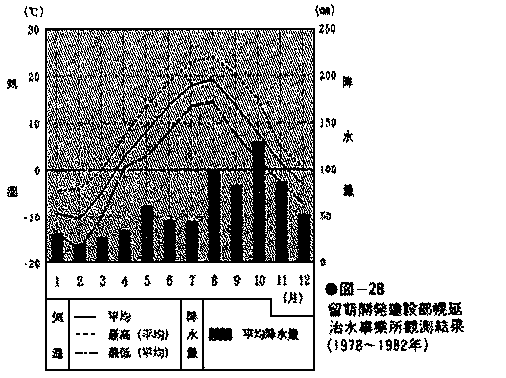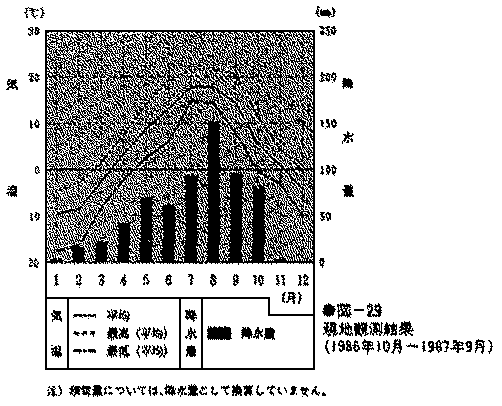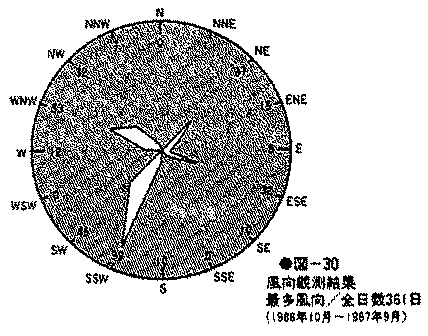| 前頁 |目次 |次頁 | |||
|
貯蔵工学センターに関する調査のとりまとめ(2) 昭和63年4月
●調査の概要 地下水の水位や水質などを調べました。地下水位は浅層ポーリング孔を用いて調べ、水質はボーリング孔(浅層ポーリング、深層ポーリング)から地下水を採取して調べました。 また、河川水についても水質を調べました。
〈河川水と地表付近の地下水について〉 図−20は、浅層ポーリング孔を用いて地下水位の観測を行った結果です。地下水位は場所によって異なりますが、地表から10m程度の範囲内にあるという結果が出ています。また、地下水位は現在も継続して計測していますが、年間を通じて大きな変動はありません。 図−21は、河川水と浅層ポーリング孔から採取した地下水の水質の分析結果を示したものです。この図は、ヘキサダイヤグラムと呼びます。水の中に含まれるさまざまな成分を整理し、六角形にグラフ化したもので、グラフの形状や大ききから水室の特徴を読みとります。河川水と地下水で含まれる成分が若干異なりますが、含まれる塩素イオン(Cl−)の量は通常の河川水や地下水とかわりません。 ●図−19 地下水・河川水調査位置図 深層ポーリング孔から地下水を採収し、水質の分析を行いました。図−22が分析結果を示しています。 図−22によると、深さ約900mまでの更別層や勇知層の地下水は地表付近の地下水と同じような性質をもっていることがわかります。一方、最も深い声問層中の地下水については、これに比べ塩分濃度が高いことがわかりました。 海岸地域では、過大な地下水の汲み上げにより地下水位が低下し海水面と同じ程度の高さになると、地盤中に海水が入ってくる現象がみられますが、候補地では地下水位は海水面より10m程度高く、また海岸から遠く離れているため、このような現象によって現在の海水が声問層中に入り込んでいるものではないと考えられます。 このことは、図−22に示すように声問層の地下水の成分と現在の海水の成分が違うことからも明らかです。 声問層は海成堆積層と呼ばれていますが、新第三紀と呼ばれる年代に、海底に堆積し、高い圧力を受けて岩盤になったものであると考えられます。声問層の中の地下水は、このときにとり込まれた海水が現在まであまり動かずに存在しているものであると推定されます。 なお、声問層のような海成堆積層はわが国に広く分布しており、これらの岩盤中の地下水は一般に地表付近の地下水に比べ塩分濃度が高いことが知られています。 また、各地層の透水性を調べるために深層ポーリング孔を用いて試験を行いました。図−28は、この結果を示したものですが、声問層についてはほとんど水を通さない岩盤であることがわかりました。 ●図−22 深層地下水の水質比較
主に日本の白亜紀や第三紀の堆積岩の分布地域では、地下深部において天然ガスの発生の可能性があることが知られています。 図−24に示すように候補地の周辺ではいくつかのガスポーリングが実施されていました。そこで、地表踏査や深層ポーリングで、ガスについても調べました。 〈地表のガスや油〉 地表踏査によって地表にガスや油がしみ出ているところがないかどうかを調べました。 図−25に示すように、候補地東方の稚内層の分布しているところで、極めて小規模で間欠的なガスの発生が1か所認められました。また同様の地域でうっすらとした油膜程度の油が数か所認められました。 これは、天北地方による従来の調査・研究によれば、稚内層のさらに深部にある増幌層で主として生成されたガスや油が、稚内層に発達する割れ目に沿って地表近くまで上がってきているものと推定されています。 一方、候補地内では、ガスや油は認められませんでした。 ●図−24 石油・ガス試掘井 深層ボーリング孔を用いたガス調査も行いました。 その結果、深度約900メートルより深いところの声問層からガスが検出されました。このガスの主成分はメタンで、地下深部の圧力下では声問層の地下水に溶けた状態でガスが含まれていることがわかりました。含まれるガスの量は、地下水1リットルに対し1.5g程度でした。 周辺のガスポーリングは、主に増幌層という、声問層より深く年代の古い地層を対象として行われていました。声問層に含まれるガス成分や地下水成分と増幌層のものを比較すると、図−26、27に示すように明らかに違いがみられます。このことから、今回検出されたガスは、増幌層で生成されたものが岩盤の割れ目を通って声問層中に入り込んだものではなく、声問層の堆積時から長い期間をかけて声問層中に生成したものであると推定されます。 候補地の地下では、声問層と増幌層の間に稚内層と呼ばれる地層が存在すると推定されますが、この稚内層が増幌層のガスや地下水に対して蓋をした形になっていると考えられます。 地下の掘削にあたっては、この声問層は水を通しにくいため、ガスの発生量はごくわずかであると考えられます。 ●図−26 ガス組成の比較
●調査の概要 気象、風向、風速、降水量などを調べました。 ●調査の結果 図−29が今回観測された気温と降水量のデータですが、図−28の幌延治水事業所での1978年から1982年の観測記録とくらべて特に異なるものではありませんでした。また、図−30に示すように風向については南南西の風と西北西の風が多いことがわかりました。
雨量計
気象観測塔 ●図−28 おわりに…… 以上、貯蔵工学センターに関する調査のとりまとめについて紹介しました。 動燃事業団は今後とも、貯蔵工学センター計画について地元の方々になお一層ご理解をいただくために、努力を続けてまいりたいと考えております。 |
|||
前頁 |目次 |次頁 |