| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
ダブレットⅢ研究協力の延長について 原子力局技術振興課
日本原子力研究所は、日米核融合研究協力の一環として、昭和54年8月から5ケ年計画で実施しているダブレットⅢ研究協力を更に4年間延長し、大型非円形プラズマに関する研究(新容器計画)を日米共同で推進することとし、7月末に協力協定の所要の改定を行った。 (1) 経緯
ダブレットⅢ研究協力計画は、米国GAテクノロジー社(GAT社)が米国エネルギー省との契約により運営しているダブレットⅢ装置を用いて非円形トカマクに関する研究開発を原研と米国エネルギー省が共同で実施しているものである。 核融合炉においてプラズマを自己点火させ、燃焼を継続させるには、超高温プラズマを炉心に閉込める必要があるが、トカマク炉のような磁気閉込め装置においては、高温プラズマを磁場を利用して閉込め(プラズマ圧力/磁場の圧力をベータ値という。)る方法を採っている。ベータ値の大きな炉心では、弱い磁場での閉込めが不能となり、装置の小型化、低廉化など、装置の効率化が図られることとなる。ベータ値を高めるには、プラズマ断面を楕円あるいはD字形などの非円形形状にするのが有効であるとの理論があり、非円形プラズマによる高ベータ化の実証が核融合研究開発の主要な課題の1つとなっている。 ダブレットⅢ研究協力計画は、この課題と取組み、非円形プラズマによる高ベータ化の実証を行ってきた。その結果、57年8月に世界最高のプラズマ・ベータ値4.6%を達成し、将来の核融合実験炉に必要なベータ値(約5%)について、その実現の見通しを得るなど数々の優れた成果を挙げてきている。これらの成果は、臨界プラズマ試験装置JT-60及びJT-60の次の装置等の実験や設計などに反映される。 (2) 新容器計画
今回、協力期間を延長し、共同研究を行おうとしている新容器計画とは、現在のダブレットⅢ装置の真空容器をD型の大型真空容器(プラズマ容積25m3)に置き換え、核融合実験炉規模に近い高温大型非円形プラズマの諸特性に関する研究を日米共同で実施し、炉の小型化、効率化等に関するデータ等を得ることを目的とした計画である。 なお、現在のダブレットⅢ装置による実験は昭和59年8月まで継続され、9月から新真空容器の据え付け工事が行われ、新ダブレットⅢによる日米共同実験が開始されるのは、昭和60年11月の予定である。 ダブレットⅢ装置の諸元 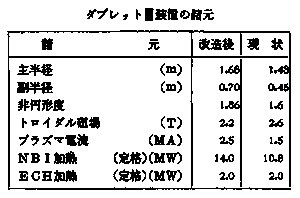 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |