| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
建設省建築研究所の原子力研究の現況 建設省 建築研究所
1. 建築研究所の研究課題
現在、建築研究所が実施している原子力関連の主要な研究は次の3課題である。 (1) 地震の実測データの収集・分類・分析に関する研究
(2) 原子炉建屋の復元力特性に関する研究
(3) 上下動の応答解析に関する研究
上記の研究課題は、本研究所が建築構造物を対象とする研究機関という事もあり、3課題とも原子力施設の構造物としての安全性、その中でも施設の耐震安全性の向上を主要な研究目的として実施されている。 原子力施設は破壊的な巨大地震に対しても、放射線の漏洩防止等の機能維持を含めた安全性の確保がなされる設計が行われ、一般の建築構造物に比して高いレベルの耐震安全性を有する。近年、地震学および地震工学などの耐震関連研究分野において、大型の実験施設や電算機の開発に伴い、基礎理論、実験・解析手法等が進歩し、耐震安全性についてより正確な定量評価を行う事が可能となりつつある。今後、このより精度の高い評価を通じ、原子力施設の耐震安全性の定量的な把握による安全性の確認とその一層の向上を図る事が可能である。 以下、当研究所に於ける各研究課題について、その概況の紹介をさせて頂く。 2. 各研究課題の概況* 2.1 地震の実測データの収集・分類・分析に関する研究
(概要)本研究は2つの小課題よりなる。 第1の課題は、地震と地震応答に関する実測データの収集を行い、統一されたフォーマットにより分類・分析を施し、地震動の特性を把握し、より適切な設計用地震動の評価および策定を行う基礎資料を作成する。設計用地震動のより合理的な策定には、地震および地震動の特性を実測記録を用いた解析により明らかにする事が不可欠である。然しながら、これらの地震実測データは各研究機関毎に収集、保管され、充分には活用されていないのが現状である。本課題はこれらの貴重な実測データを系統だてて収集・分類・分析し、整理された形の地震実測資料を作成し、かつ地震動策定の研究等への資料の広範な活用を企る。 第2の課題は、集中的な地震観測システムを整備し、実測データの拡充を企るととも、強震地震時の隣接する地点での地動の特性を特に波形の位相差に重点をおいて検討する。原子力施設は剛な大型基礎版上に構築され、波長の短い短周期成分波形は位相差によりそのままの形では入力しない。原子炉建屋の床スラブの上下振動等の短周期領域での振動性状を明らかにするためには、波の位相差による入力損失を評価する事が必要である。本課題は強震地動の位相差を観測により実証的に把え、大規模剛基礎構造物に対する入力機構を明らかにする。 (成果の概要)強震計による地震波形記録、震災構造物の被害写真等の実測データを国内外の範囲で収集し、系統だてた様式により分類、分析を施しデータライブラリー化した。収集された実測データ数は、波形記録については表1に示す計35発生地震について475成分記録、被害写真記録については表2に示す計42発生地震について478事例(1事例に複数のデータを含む)の資料を収集した。収集された実測データの広範な活用を企る為、研究資料として必要なデータを検索するシステムの設計、作成を併わせて行った。検索システムは図1に示す小型電算機より構成され、収集された資料をデータベースとする。これにより、数多くの資料より必要なものを遺漏なく効率的に選びだす事が可能になり、整理された形での地震実測資料の活用がなされるようになった。 * 各研究課題の報告は、建設省建築研究所建築研究所年度、昭和56年度、昭和57年1月に詳しくなされている。 表1 強震計波形実測データ収集地震 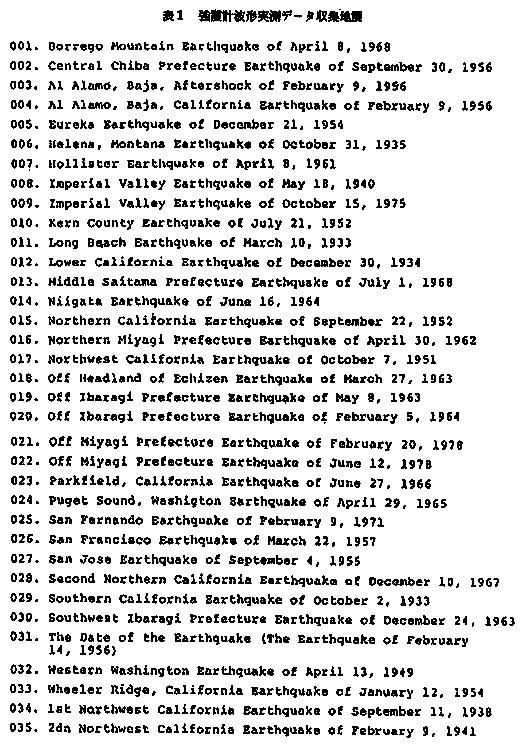 表2 被害写真実測データ収集地震 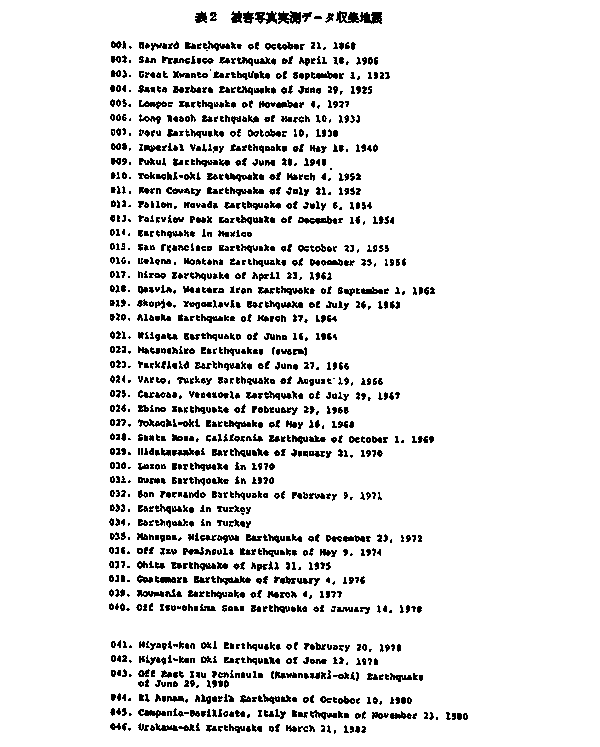 図1 実測データ検索システム機器構成 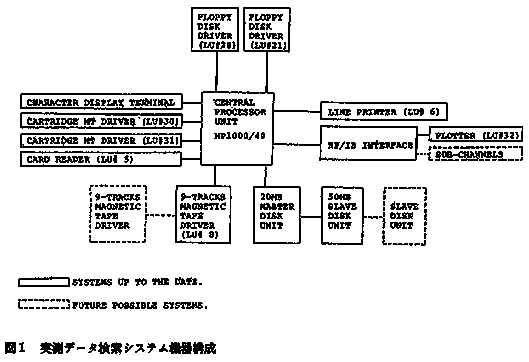 第2の課題については、観測システムの整備が始められた時点である。12観測点より構成される基本観測網計画が立案され、うち4観測地点の設置がなされた。数個の地震記録が採取され解析されたが、現段階では当初の目的を達する観測網の整備の途上にある現状である。 (今後の計画)第1の課題については、未だ遺漏されているもの及び定常的に得られる実測データの収集を継続し、実測地震データライブラリーの拡充を進めるとともに、検索システムの一層の整備を行い、実測資料の耐震関連研究へのより広範な利用を推し進める。第2の課題については、基本観測網の整備を進めるとともに、観測波形の解析により短周期波形の位相差、大型剛基礎構造物への入力機構および敷地地盤と地震波形の関連性等の課題について実証的な研究を進める予定である。 2.2 原子炉建屋の復元力特性に関する研究<
(概要)耐震規定に関する法令改正により、建築構造物に対し保有耐力、変形性能等を算定し、終局時に於ける耐震性能評価より設計の検討がなされる事となった。充分な安全性を見込んで行われる原子力施設の耐震設計についても、その終局時の性能を評価し、外力に対する余裕度の評価を行って耐震安全性の定量的な確認を行う必要性が高まりつつある。本課題は、原子炉容器、蒸気発生器等の重要施設・機器を格納・支持する原子炉建屋の弾塑性域での挙動を終局迄の範囲にわたり、解析的並びに実験的の両面より明らかにする。 (成果の概要)加圧水型と沸騰水型の2種の原子炉建屋構造により先ず加圧水型建屋を対象に研究は実施された。研究は概ね次のフローに従う。先ず、耐震解析コードを用いた電算地震応答計算により建屋全体の弾塑性挙動を解析する。次いで得られた解析結果に基づき、実験を行う対象部位を選びだし、模型試験体による加力実験を行い、更に詳細にその弾塑性挙動を明らかにする。実験結果より、解析計算上設定された条件の妥当性を再検討し、耐震コードに反映し、解析手法をより合理化されたものにする。 対象を軽水炉改良標準型建屋**とし、限界地震動(S2地震)を応答計算用入力地震動とする。標準建屋の振動系質点モデル化の結果を図2に示す。振動の基本性状を示す固有値解析の結果、1次モードは建屋全体の並進、2次モードは格納容器と内部コンクリートが逆位相、3次モードでは内部コンクリートの振動が励起される。限界地震動に対する弾塑性地震応答解析、および限界地震の振幅を拡大して考えた仮想的な地震動に対する弾塑性地震応答解析より得られた主要な検討事項は次の点である。 (1) 限界地震動に対しても、原子炉建屋は格納容器基部、内部コンクリート基部を除き弾性範囲内の応答挙動を示す(図3)。 (2) 拡大限界地震動に対し格納容器基部でのせん断変形は大きい。せん断に対する余裕度は曲げに比較して小さい(図4)。 (3) 拡大限界地震動に対し内部コンクリート基部での曲げ変形は曲げひび割れ変形をこえる。せん断と比較すると曲げに対する余裕度は小さいが、充分な大きさの余裕度がある(図4)。 (4) 周辺建屋は他の二つの構造体に比べ、せん断、曲げの両者に対し大きな余裕度を有す。 (今後の計画)加圧水型建屋に対する地震応答解析結果、ならびに文献調査結果に基づき、格納容器構造体をモデル化した円筒耐震壁および建屋の主要な耐震要素である高配筋耐震壁の模型加力実験が実施され、現時点実験が終了した段階である。今後、加圧水型建屋については実験結果の解析を継続して行い、その結果を耐震コードに反映させるとともに、沸騰水型建屋についても耐震解析コードによる全体系の地震応答解析を実施する等同様な手法により解析・実験の両面より研究を進める。建屋の弾塑性域での性状を明らかにする事により、大型振動台による機器・配管系の耐震実証試験に用いる床応答スペクトル、振動台入力波策定の研究資料の作成も可能となる。 ** 通商産業省軽水炉改良標準化耐震設計小委員会“耐震設計の標準化に関する調査報告書”昭和56年6月 図2 加圧水型標準建屋の振動モデル 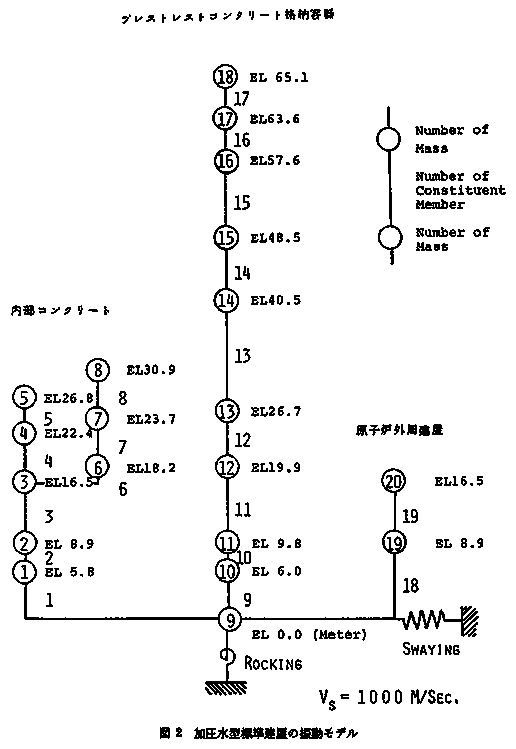 図3 限界地震に対する弾塑性最大応答値 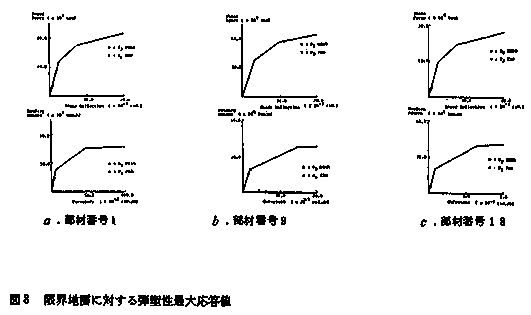 図4 拡大限界地震に対する弾塑性最大応答値 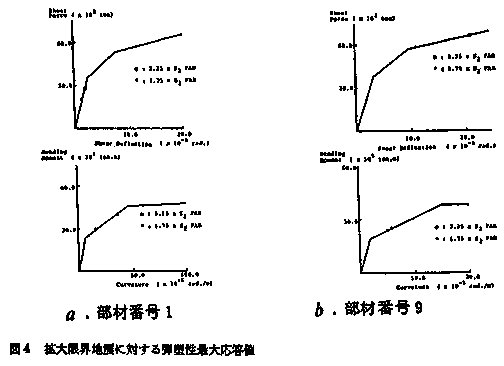 2.3 上下動の応答解析に関する研究
(概要)原子力施設の耐震性の検討に当って、震源距離の小さい近地・直下型地震が最近問題視されるようになってきた。特に硬質地盤上に建設される原子力施設に対し、直下型地震等の上下動成分が卓越した地震入力を考慮した場合の機器・配管類への入力評価が大きな研究テーマとされる。本課題は、上下動成分が卓越する地震動が入力する場合の建屋等の施設の上下方向の振動応答性状を加振実験等によって明らかにし、既往の解析手法の妥当性を検討し、機器類を含めた原子炉建屋の耐震安全性を実証的に確認する。 (研究の成果)本課題は研究実施の初年度に当り、加振実験計画の立案および実験に必要な機器類の整備がなされた。 (研究の計画)原子炉建屋のなかで、特に上下動による影響が大きい建屋頂部部位およびクレーンガーダーについて、実長スパン屋根トラスおよび大型クレーン支持装置について上下方向の加振実験を行い、既存の解析コードの妥当性を実証する。更に、機器類・配管系等を支持する原子炉建屋の床スラブについて起振実験を行い、機器据付点での地震応答を把え、上下動成分による影響ならびに水平・連上下の成効果等を明らかにする。 3. おわりに
建設省建築研究所で実施されている原子力関連の研究課題の現況について概略の紹介を行った。実施課題は、原子力施設への耐震設計用地震動の策定および施設の耐震解析に関する研究等、いずれも原子力施設の建築構造物としての安全性、特に耐震安全性に関するものである。現在の3つの研究課題はそれぞれに有機的な関連をもって行われており、それらの研究成果は互いの入力、出力となりながら設計用入力地震動および入力地動による施設の耐震性状、性能をより精度高く、合理的、定量的に評価する事に資せられており、原子力施設の耐震安全性のより一層の向上に寄与するものである。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |