| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
船舶技術研究所の原子力研究の近況 運輸省船舶技術研究所
1. はじめに
現在船研が実施している原子力研究は次の6課題である。 (1) 原子力船の事故解析の研究
(2) 反応度事故の研究
(3) 放射線遮蔽の研究
(4) 使用済核燃料輸送の研究
(5) 原子炉圧力容器の研究
(6) 超音波探傷試験の研究
原子力船の研究は、原子炉を船舶に応用する場合に船舶であるために特に問題となる課題について行っている。すなわち、波浪により船体が動揺することに起因する問題、急激な負荷変動に関連した反応度事故、重量軽減に関連した遮蔽の研究である。 使用済核燃料輸送の研究は、船舶輸送時の乗組員等の被曝を低減させるために、専用船内における放射線々量率分布を明らかにすることを目的としたものである。 船舶技術における船体用鋼板及び溶接継手の研究成果を原子力に応用したものが、原子炉圧力容器等の研究であり、圧力容器等の脆性破壊強度と、検査技術に関する研究を実施している。 2. 原子力船の事故解析の研究
この研究は、海難時の原子力船の安全性に関連するもので、原子力船が座礁した場合の船体挙動を明らかにすると共に、傾斜して停止した舶用炉の崩壊熱除去能力へ及ぼす傾斜角度の影響を解明することを目的としている。座礁事故時の船体傾斜の進行速度は、原子炉の熱除去経過に大きな影響を与える。浅海域で岩礁に接触して大傾斜している場合の運動計算法を確立し、これと浸水復原性計算法とを組み合せて、船体挙動の時間的経過を予測するシミュレーション計算プログラムを作成した。この計算結果の信頼性を水槽模型実験の結果と比較することにより確かめた。また、座礁事故の際に岩礁が原子炉格納容器を破損しないように、原子炉区画の船底を耐座礁構造にしておく必要がある。このために、まず座礁船体に加わる岩礁から荷重と潮位の変化との関係を数値計算によって求め、ついで船底構造の圧壊機構を模型実験によって明らかにした。 原子力船が座礁等の大きな海難事故を起した時には原子炉はただちに停止するが、その際にも崩壊熱を除去しなければならない。原子力船の炉心と蒸気発生器を模擬し、傾斜させることが可能でかつ炉心と蒸気発生器の相対位置を変化させることが出来る崩壊熱除去特性実験装置(第1図)を製作し、冷却水の自然循環特性を明らかにした。また傾斜時崩壊熱除去のための計算コードを作り計算と実験から傾斜時の崩壊熱除去の様相を明らかにした。 第1図 崩壊熱除去特性実験装置 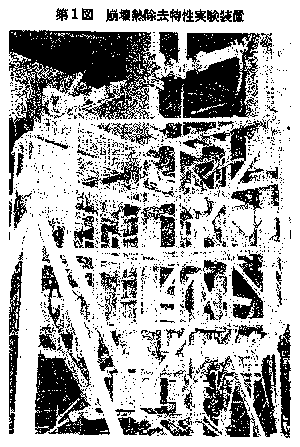 3. 反応度事故の研究
原子力船の特色として、入出港時等に出力をひんぱんに変えなければならない。このように負荷変動の多い場合には出力が急激に増加する反応度事故は重要な研究課題であり、その際も燃料の健全性は保たれねばならない。反応度事故時に最も壊れ易いのは何らかの欠陥のある燃料であるから、燃料破覆管にフレッティング腐触のある燃料についての破損限界を求めた。 4. 放射線遮蔽の研究
舶用炉遮蔽はその重量が舶用炉プラントの大半を占めるので、遮蔽設計は乗組員の安全性に加えて重量軽減の上からも重要な課題であり、船研では遮蔽の研究に特に力を入れてきた。日本原子力研究所に設置された遮蔽研究炉JRR−4に関してはその計画の時から参加し、完成後はこれを利用して遮蔽研究を積極的に行ってきた。「むつ」の放射線漏洩に際しては、その原因究明のため解析計算を行った。その後「むつ」の遮蔽は設計をやりなおし遮蔽改修を行ったが、その遮蔽性能の確認のためモックアップ実験を日本原子力船開発事業団、日本原子力研究所と船研の三者共同研究で行なった。その後もJRR−4を利用して、遮蔽の研究を実施してきている。 原子炉圧力容器を直接取り囲む一次遮蔽は最も遮蔽効果が大きく、これを対象とし精度の良い遮蔽計算法を開発した。実験はJRR−4等を利用して行い、放射線減衰の様相を明らかにしたが、計算、実験ともに遮蔽効果の小さい間隙部からの放射線漏洩に力を入れた。二次遮蔽は重量が大きいので効率の良い設計が要求され、二次遮蔽固有の問題である放射線々源等の研究を行っている。また船体構造も遮蔽効果を有するので、この効果を明らかにするための研究を行った。 5. 使用済核燃料輸送の研究
使用済核燃料は再処理をしてウランやプルトニウムを回収するために国内外の再処理工場へ海上輸送される。使用済核燃料は多量の放射能を含んでいるため遮蔽効果のある輸送容器に収納し、輸送も遮蔽構造を有している専用船で行う。乗組員の安全性の上から、これ等の遮蔽効果を精度良く求めることが必要である。 輸送容器の遮蔽は遮蔽材の欠落している複雑形状部があり、その遮蔽計算を精度良く行うにはモンテカルロ法が適している。モンテカルロ法による遮蔽計算は計算時間が長いのが欠点であるが、モンテカルロ法固有の手法を考案し、有効な計算を短時間で行えるように改良した。これにより、三次元解析を行ない、極めて精度の良い結果が得られた。 専用船は、複数の輸送容器を積載して運行する。船内の放射線は輸送容器相互の干渉効果に加え、船体構造の遮蔽効果もあって複雑な分布をしている。そこで専用船の船内放射線分布を測定する実船実験を行うとともに、解析計算を行ない、放射線分布の様相を明らかにした。 6. 原子炉圧力容器の研究
原子炉圧力容器は大型化するとともに、より厳しい環境で使用されるようになってきている。また鋼材の脆性破壊や、不安定延性破壊などの急速破壊は、静的な負荷条件よりも衡撃的な荷重条件の方が起こり易いと考えられており、負荷エネルギーが大きいほど構造物全体に急速破壊が波及する危険性がある。 これ等の課題に対処する動的破壊靱性試験は、負荷速度、荷重方式等の影響をはじめとして、多くの解決すべき問題が残されている。このため船研では、負荷速度2〜100m/sec、負荷荷重8〜100トンの動的破壊試験ができる装置として、回転円板式衝撃試験装置と、大型高速引張試験装置を完成した。現在までに、高速衝撃荷重の計測技術として衝撃応答解析等による荷重測定、動的破壊靱性値の負荷速度による影響、温度依存性、試験片形状の影響等に関し、多くの研究成果をあげている。 7. 超音波探傷試験の研究
供用期間中の検査は、原子炉圧力容器等の安全性を考える上で非常に重要な要因である。表面に開口していない欠陥を対象とする時は放射線透過試験と超音波探傷試験があるが、前者は高放射線々量の環境では使用できず、自動化された超音波探傷試験に頼らざるを得ない。 定角度の斜角探触子では欠陥を見逃す恐れがあるため、現在では屈折角の異なる2つの斜角探触子と垂直探触子を組合せて、探傷試験を行っているが、広角度の探触子を用いた画像処理方式とすれば、画像処理方式が含む情報蓄積の効果に加えて、有利な角度からも探傷することになり、検出精度も向上することが期待される。 そこで、欠陥の三次元画像表示機能の開発、ついで焦点探触子等を用いた場合の欠陥評価精度の検討を行っている。さらには実際の欠陥の進展状況の評価を行う予定である。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |