| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原子力モニターの声(昭和56年度) 昭和57年11月
振興局
原子力局
原子力安全局
原子力モニターは、原子力開発利用に関して、広く一般国民から率直な意見等を聴取し、原子力行政に反映させることを目的とした制度であり、昭和52年度に開始された。昭和56年度の原子力モニターは、各都道府県知事より推薦を受けた候補者のうち、本人の同意を得た504名に委嘱を行った。昭和57年3月に実施したアンケート調査及び昭和56年度中に寄せられた随時報告の概要は以下のとおりである。 Ⅰ アンケート調査 1 調査の概要
(参考) 男女別、職業別、年代別モニター数及び回答者数
(注) この報告で使われる記号の説明
1. Nは比率算出の基数であり、100%が何人の回答に相当するかを示す。特に示していない場合はN=355人(回答者)である。 2. LQ(追加質問):前問で特定の回答をした一部の回答者に対して行った質問。 3. MA(多数回答):1回答者が2以上の回答をすることができる質問、このときのMT(回答合計)は回答者数(100%)を越える。 2 調査結果の概要
(1) エネルギーの将来について
石油に代わるエネルギー供給源として、今世紀内で原子力が一番多く利用されると考えている者が59%ある。さらに21世紀では原子力が利用されるとする者が70%ある。(MA(多数回答))
(2) 原子力発電所の建設について
原子力発電所の建設については、61%の者が「安全性を十分確認しながら慎重に建設すべきである」と考えており、次いで29%の者が「安全性を確認しながら積極的に建設すべきである」としており、これらに「安全性は確立しているので積極的に建設すべきである」とする者4%を併せると「建設の必要性を認める」者は94%となっている。自分の居住地近くに建設することについては、「安全性に十分納得できれば賛成する」者は68%、「積極的に賛成する」者は10%で、併せて78%の者が理解を示している。 (3) 原子力発電所の立地推進について
原子力発電施設の立地が難航している理由として、70%の者が「安全性に不安があるから」とし、次いで18%の者が「放射性廃棄物の処理処分に不安があるから」としている。また、この立地難の有効な解決策としては、61%の者が「原子力発電所の安全性、安全対策、防災対策等について、地元で一層丁寧に説明する」ことと考えており、21%者が「安全運転の実績を積み上げる」ことと考えている。 (4) 核燃料サイクルについての認識
国が核燃料サイクルの確立を目指していることについて、84%の者が「知っている」としている。さらに知っていると答えた者の27%が「現在の政府の施策をもっと強化すべきである」としている。 (5) 新型動力炉の開発についての認識
国が新型動力炉の開発を進めていることについて、72%の者が「知っている」としており、さらに知っていると答えた者の71%が、現在の政府の施策を「もっと強化すべきである」としている。 (6) 原子力安全行政の考え
原子力をめぐる立地問題、安全問題について政府の施策のうち最も重要と考えられるものについては、26%の者が「安全性、信頼性等に関する研究開発の推進」としており、同じく26%の者が「厳正な安全規制の実施」としている。 (7) 原子力安全委員会の再審査についての認識
原子力発電所の設置許可に当たり、原子力安全委員会が再審査(ダブル・チェック)していることについては、63%の者が「知っている」としている。また、知っていると答えた者の57%の者が「再審査は機能している」と考えている。 (8) 原子力安全委員会について
原子力安全委員会の機能のうち最も期待していることとしては、31%の者が「行政部局の行った安全審査を、より高度な立場からダブル・チェックすること」としており、次いで30%の者が「安全審査に当たり、公開ヒアリングなどにより、地元住民等の意見を十分に安全行政に反映させること」としている。 (9) 原子力委員会の公開ヒアリングについて
原子力安全委員会が公開ヒアリングを開催していることについて、68%の者が「知っている」としており、また、そのうち45%の者が「機能している」と考えており、37%の者は「改善すべき点がある」としている。 なお、公開ヒアリングに関する具体的意見として、
◎ 広く参加できるよう回数、時間に配慮する。 ◎ 政府広報を一段と強化する。 ◎ 運営の秩序維持をはかる。 などの意見が寄せられた。 (10) 我が国の原子力安全行政についての意見として、
「安全を第一とし、原子力の研究・開発利用を進めてほしい」などの意見が多く寄せられた。 (11) 「原子力の日」に関する広報や記事について
「原子力の日」の前後に、政府などによる広報を見た者は88%となっている。また、その中で、59%の者が「政府による広報」に接し、次いで49%の者が「電力会社の広報」に接している。(MA(多数回答))これらの広報媒体としては、68%の者が「新聞」、次いで62%の者が「パンフレット」、53%の者が「テレビ」を通じて接している。(MA(多数回答))
なお、「原子力の日」に関連した記事については、86%の者が「見た」としている。 (12) 「原子力の日のポスター」について
「健康的で、大変分かり易い」、「感じが良い」などの意見が多く寄せられた。 (13) パンフレット「日本の原子力開発利用」について
92%の者が「読んだ」としている。 なお、このパンフレットについての感想、意見としては、
◎ 分かり易く、工夫もあり、要領よくできている。 ◎ 少々むずかしい。 ◎ 広く学校、図書館にも配布されたい。 ◎ 児童向き、老人向き等年代別のものがほしい。 などの意見が寄せられた。 また、原子力について特に詳しく知りたいこととして、38%の者が「放射性廃棄物の処理処分対策」を、次いで37%の者が「原子力の長期的な展望」を、24%の者が「原子力発電所の安全対策」をあげている。(MA(多数回答))
(14) 原子力広報の媒体について
希望する原子力広報媒体として、43%の者が「テレビ」を、次いで40%の者が「見学会」を、27%の者が「各種の講習会や説明会」を、25%の者が「新聞」をあげている。(MA(多数回答))
また、新聞、テレビ、ラジオ等の広報の頻度としては、43%の者が「月に1、2回程度」、次いで41%の者が「週に1、2回程度」がよいとしている。 また、原子力広報についての具体的意見としては、「国民の関心を高めるため、原子力広報の一層の拡充を望む」、「テレビの放映時間帯に一層の工夫をしてほしい」、「子供、老人、婦人向きの易しいパンフレット等をつくってほしい」などの意見が寄せられた。 (15) 原子力モニターについての感想
原子力モニターの経験についての感想としては、「原子力について関心が生れ、知識を得て大変有意義であった」、「原子力の必要性を痛感した」、「巾広い原子力広報の推進に期待する」などの感想が多かった。 3 集計結果
問1. エネルギーの将来について 1. あなたは石油に代わる大量のエネルギー供給源として、今世紀内はどのようなエネルギーが一番多く利用されると思いますか。
2. 長期的観点から、石油に代わるエネルギー源として21世紀にはどのようなエネルギーが利用されると思いますか。(M.A(多数質問))
問2. 原子力の開発について 1. わが国の原子力発電の規模については、現在の約1,551万KW(全発電設備の約12%、全発電量の約13%)から、さらに拡大する目標が立てられています。あなたは、原子力発電所の建設についてどのようにお考えですか。
2. もし仮に、あなたの居住地の近くに原子力発電所の建設計画が発表されるとしたら、あなたはどうしますか。
3. 原子力発電の立地推進について
原子力発電施設等の立地に際しては、必ずしも十分な地元住民の協力が得られず立地が難航する面があります。その理由は、次のうちどれが最も大きく影響していると思いますか。(M.A)
(2) これらの立地難を解決するには、どのような方法が最も有効であるとお考えですか。
(3) その他有効と思われるご意見がありましたらお書き下さい。(回答数102件)
4. 核燃料サイクルについて
(1) 原子力発電規模の拡大を図っていくため、政府としては、ウラン濃縮、使用済燃料の再処理等の核燃料サイクルの確立を目指しています。あなたは、このことをご在知ですか。
SQ、知っていると答えた方に〔対象者283名〕
(2) 現在の政府の施策について、どのようにお考えですか。
5. 新型炉の開発について
(1) ウラン資源の有効利用を図るため、政府としては、新型炉(新型転換炉、高速増殖炉)の開発を進ています。あなたは、このことをご存知ですか。
SQ、知っていると答えた方に〔対象者250名〕
(2) 現在の政府の施策について、どのようにお考えですか。
問3. 原子力安全行政について
1. 近年、原子力をめぐって、特に立地問題、安全問題等については、国民の理解を得ることが不可欠の課題となっており、政府としては、現在次のようないろいろな施策を講じています。あなたは、このうち、どれが最も重要であるとお考えになりますか。
2. 原子力発電所の安全規制については、通商産業省が設置許可から運転管理に至るまで、一貫して規制を行うこととなっており、通商産業省が行う設置許可等に関する安全審査について、原子力安全委員会が最新の科学技術的知見に基づいて客観的立場から再審査(ダブル・チェック)する体制になっています。
(1) あなたは、このような体制をご存知ですか。
SQ.知っていると答えた方に 〔対象者211名〕
(2) あなたは、このような体制について、どのようにお考えですか。
3.原子力安全委員会は下記(1)~(5)の機能を有していますが、あなたはこの中のどれに最も期待していますか。
4. 原子力安全委員会は、再審査(ダブル・チェック)に当たって、これまで5回の公開ヒアリングを開催しましたが、この公開ヒアリングについてお尋ねします。
(1) あなたは、公開ヒアリングをご存知ですか。
SQ.知っていると答えた方に〔対象者229名〕
(2) あなたは、このような体制について、どのようにお考えですか。
(3) 公開ヒアリングについて、何か意見、ご提言がありましたらお書き下さい。
5. わが国の原子力安全行政について、何かご意見、ご提言がありましたらお書き下さい。
問4. 原子力広報について
1. 原子力の日に関する広報について
SQ.ご覧になられた方に〔対象者293名〕
(ⅰ) どこの広報をご覧になりましたか。(M.A(多数質問))
ご覧になったものすべてに○印をご記入下さい。
(ⅱ)また、その広報は何でご覧になりましたか。(M.A(多数質問))
(2) 「原子力の日」に関連した記事はご覧になりましたか。
2. 先にお送りいたしました「原子力の日のポスター」についてご感想、ご意見等がありましたらお書き下さい。
3. ところで、先にお送りいたしましたパンフレット「日本の原子力開発利用」はお読みいただけましたでしょうか。
4. 前記のパンフレットについて、ご感想、ご意見等がありましたらお書き下さい。
5. あなたは、原子力について、特にどのようなことを詳しくお知りになりたいですか。(M.A(多数質問))
6. その他詳しくお知りになりたいことがありましたらお書き下さい。
7. あなたは、原子力広報についてどのような手段媒体をお望みになりますか。(M.A(多数質問))
8. あなたは、新聞、テレビ、ラジオ等の媒体で、どのくらいの頻度で広報をした方がよいと思いますか。
9. 原子力広報について何かご意見、ご提言がありましたらお書き下さい。
問5. この一年間、原子力モニターのご経験は、あなたにとっていかがでしたか。お感じになりましたことをお書き下さい。
Ⅱ 随時報告 1 意見の内訳
原子力モニターから、昭和56年9月から昭和57年3月までに寄せられた随時報告の件数は150件であり、これを事項別にみると、原子力広報についての意見が48件と最も多く、次いで開発利用についての意見が26件、安全性・事故についての意見が25件などとなっている。(表1参照)。 職業別の報告件数をみると主婦等が37件と最も多く、次いで農林漁業が36件となっている(表2参照)
また、年代別の報告件数では、60代が44件と最も多く、次いで50代が43件、40代が29件などとなっている(表3参照)。 男女別の報告件数をみると、男性が102件、女性が48件となっている(表4参照)
2 意見の概要
原子力開発の必要性については、「生活向上のためには原子力の開発利用の強力な推進が大切である。」「目前にせまっていると思われるエネルギー危機打開のためには、今後も十分安全性に留意しつつ開発利用を進めていただきたい。」「安全性をも含め基礎研究の一層の強化を期待している。」など原子力開発利用の必要性及び推進を訴える意見が多かった。 また、「国土が狭く人口の多い我が国では、大電力集中型を推進してほしい」との意見が見られた。 原子力行政に関しては、
「地元(立地地域)の振興・発展にも配慮した施策の充実を望む。」など地域振興に対する要望、「原子力発電所等の管理・監督を従来にも増して一層強化し、二度と事故の起らないようにしてほしい。」など、56年の敦賀発電所事故を機として万全の安全確保を求める意見が多かった。 放射性廃棄物処理・処分に関しては、
「低レベル放射性廃棄物の海洋処分は十分安全性を確めてから実施してほしい。」「当面は陸地処分として炭坑の廃坑を利用したら良いと思うがどうか。」「環境への影響に十分配慮して検討してほしい。」など、放射性廃棄物の処理・処分方法について、環境への影響を配慮した処分方法を求める意見が多かった。 安全性・事故に関しては、
「官民一体となって原子力発電所等の事故の絶滅を目ざし、格段の防止のための努力をされたい。」「絶対に事故を起さないように、安全性確保についての基礎研究等を強力に進めてほしい。」など、原子力発電所等の安全の確保について、厳しい管理・監督を要望する意見が多かった。 石油代替エネルギー開発に関しては、
「波力、太陽熱、潮流、風力、地熱などの開発を進めてほしい。」「核融合の利用実現に期待する。」など、現在の原子力の開発利用と併行して、各種の石油代替エネルギーの研究開発を進めてほしいとの意見が多かった。 原子力教育に関しては、
「学校教育(小・中)において、原子力の正しい基礎知識を教えてほしい。」「原子力施設の見学、講演等を活発に行い、広く国民に安全性、必要性を理解してもらうことが大切である。」など、原子力について正しい理解を得るためには、学校教育、社会教育の場において基礎知識を普及することが大切であるとの意見が多かった。 その他、
「原子力船の開発にあたっては、国民が必要性を理解し合った上、一日も早く実用化に向けて進めてほしい。」など、原子力船の開発に期待を寄せる意見が見られた。 また、「原子力モニターの経験を機会に今後も我が国の原子力開発利用の進展を温かい心で見守っていきたい。」など、原子力モニターを機に原子力の重要性に関心を持つに至ったとの報告が寄せられた。 参考Ⅰ 報告(150件)の内訳
表1 事項別の内訳 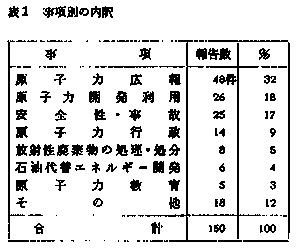 表2 職業別の内訳 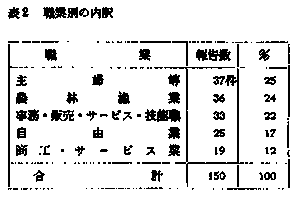 表3 年代別の内訳 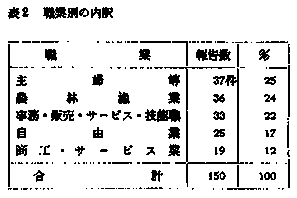 表4 男女別の内訳 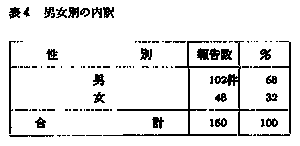 Ⅲ 参考 昭和56年度原子力モニター構成 1. 職業別 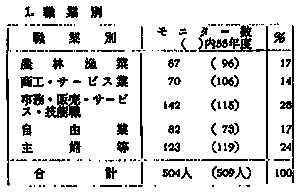 2. 年代別 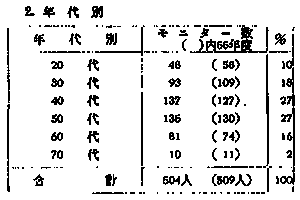 3. 男女別 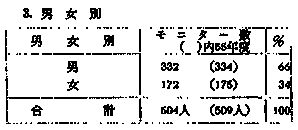 4. 都道府県別 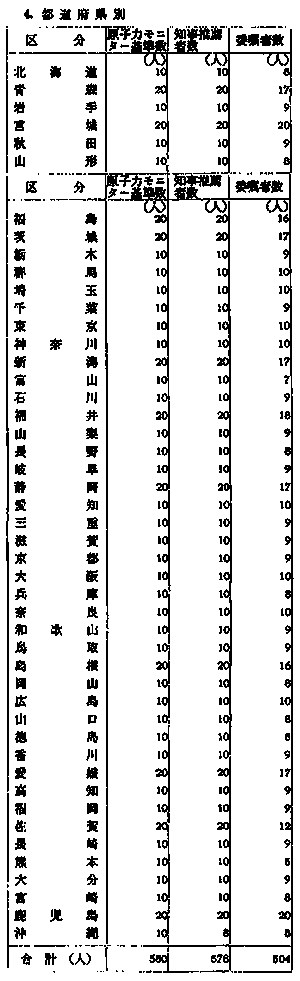 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |









