| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
原子力発電施設耐震信頼性実証試験 資源エネルギー庁原子力発電課
はじめに
11月6日、世界で最大規模の大型高性能振動台が完成し、竣工式が行われる日だ。6年を超える年月をかけて製作されたこの振動台設備を用いて、原子力発電施設の耐震信頼性について世界でも例のない大規模なデモンストレーション試験が開始されようとしている。そこで、この試験開始を前にして、原子力発電施設の実証試験について紹介することとする。 信頼性の実証試験とは
原子力発電は、石油に代替するエネルギーの主要な供給源として、今後とも積極的な開発を進めていくことが必要である。しかしながら、原子力技術は高度かつ複雑なものであり、一般には理解しにくいことなどから、原子力発電所でときおり発生するトラブルなどでも、たとえそれが軽微で、外部の環境や住民に支障を与えるおそれがないものであっても、国民に安全性についての不安を持たれがちとなっているのが現実である。 耐震性を例にとろう。原子力発電所の設置にあたっては、当該地域の地震活動、地盤条件の調査を実施するほか、十分な耐震設計、厳しい品質管理、さらには使用前の検査を行うなど、一般の建物・構造物に比べてはるかに厳しい解析検討が加えられている。しかし耐震性については、自然力を相手とする関係上、実際の発電所が巨大地震に遭遇したときの安全性について疑問を持つ向きもあり、広く一般の理解を得るのは必ずしも容易ではない。最も有効なのは、実際の発電所が巨大地震に耐えて安全性を証明してみせることであるが、そのような巨大地震が原子力発電所のサイトに発生する蓋然性は極めて小さい。 このため、かかる不安感を払拭するための現実的な証明手段として考えられるのは、原子力発電所の耐震安全上重要な機器について、実物大ないしそれに近い大きさにモデル化した試験体を用いて厳しい条件で加振試験を行い、巨大地震時においても十分な余裕をもって信頼性を保持し得ることを実証的に明らかにすることである。 このように実証試験は技術開発において解析、実験などを通じて十分な安全性、信頼性を確保していても、実際の運転経験上証明してみせることが困難なものを、供試体モデルなどを使用して、より直視的、経験的に実証することを目的としているといえよう。 振動台テーブル上のPWR原子炉格納容器試験体 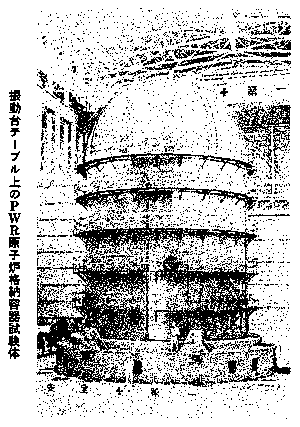 多度津工学試験所 全景 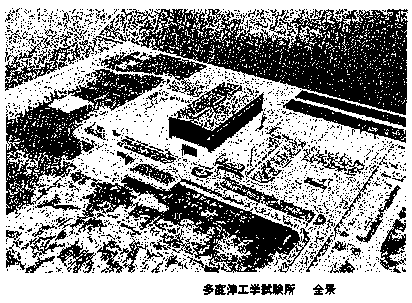 第1表 大型高性能振動台の主要性能仕様 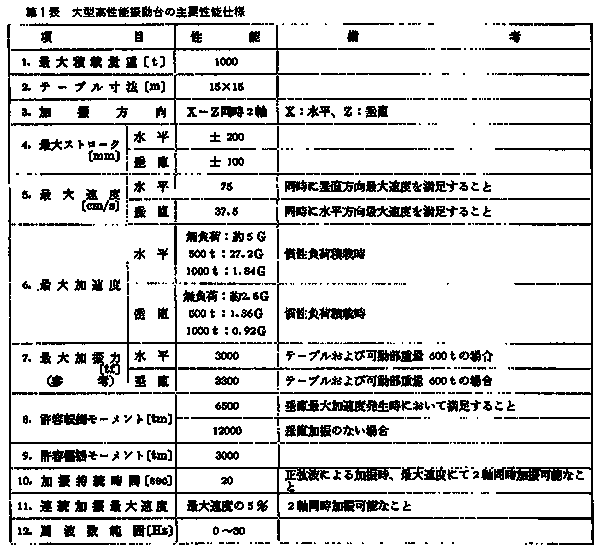 大型高性能振動台設備について
まず、原子力発電施設の耐震実証試験に使用する大型高性能振動台設備について紹介しよう。この振動台は、通産省の補助事業として、財団法人原子力工学試験センターが総額300億円程度の資金を投じて香川県多度津町において昭和51年より建設を進め、本年7月に完成したものである。 (1) 振動台設備の仕様
この振動台設備は、世界最大規模のもの(現在、最大のものは国立防災科学技術センターの振動台)であり、15メートル×15メートルのテーブル上に、最大1,000トンまでの重量物(試験用模型)を載せて地震の時の地盤や床の揺れと同様に、左右および上下の振動を行うことが可能である。この時テーブルに加えられる加振力は、3,000トン・fであり、現存の振動台に比べて約8倍の能力を持っている。 このために、水平方向の加振機7台と垂直方向の加振機12台とによって水平・上下の2方向に同時に加振を行うものである。水平、垂直加振機は、油圧を利用した電気油圧サーボ機構により、油を制御して時々刻々変化する入力信号に対応して作動し、必要な運動をテーブルに与える。また、油は油槽に貯えられており、油ポンプで加圧(210㎏/㎡)され、アキュムレータ(蓄圧を一定時間かけて行い、その中に封入した高圧窒素ガスの圧縮膨張を利用して必要時に多量の油を放出できる機能を有する)に蓄圧された後に、必要量が加振機に送られる(第1表参照)。 この大きなテーブルの上に、原子力発電所の大型機器の実物大ないしそれに近いレベルの模型を据えつけて振動させるわけであるが、縮尺サイズの模型の実機模擬性について若干触れておきたい。通常、大型の機器や構造物の振動台による振動試験を行う場合には、縮尺模型が用いられる。この場合の実機との対応は、相似則が適用される。仮に、実機を同一材料でつくる場合、模型の縮尺を10分の1にすれば、時間は10分の1に短縮され、たとえば20秒の地震は2秒で試験することになる。しかし、実機が受ける応力を模型に与えるには10倍の加速度で加振する必要がある。時間をあまり短縮せず、かつ小さな加振力で試験をするため、通常は実物よりもやわらかいプラスチック製の縮小模型が使われる。 今回の試験では、極力実機並みの特性を維持することとし、実機と同様の材料を使用しているため、実機相当の応力を与えるような振動試験を行うためには、模型の大幅な縮小は困難であり、約5分の1程度が限界とされている。第1表にある振動台の主要性能については、このような条件を考慮して、実際の原子力発電用機器と耐震実証試験の模型の大きさ、必要加速度を検討し技術的水準を踏まえて決定したものである。また、振動台の性能として周波数特性が重要であり、加振周波数によって能力の限界が定められる。 (2) 計測データ処理システム
振動試験による取得データの処理システムとして300チャンネルの同時計測ができる高速データ集録機能と集録されたデータの簡単な1次処理機能を持たせているが、本格的なデータ解析は大型コンピュータに送って処理することとしている。 (3) 振動台施設
振動台施設は原子力工学試験センター多度津工学試験所(敷地面積33万平方メートル)内に設置されている。振動台テーブルは、実験棟の中央に位置し、その下にある垂直・水平加振機により加振される。振動台の反力を支えるのは重量15万トンのコンクリート基礎で、これは旧海底よりも堀り下げられた洪積砂礫層上に築かれ、実験棟全体の基礎を兼ねている。 実験棟は、幅45メートル、長さ90メートル、軒高36メートルで、17メートル×15メートルの出入口2個を有し、クレーンは250トンのもの2台を備えている。実験棟に隣接して油圧源棟が配されており、その中には加振機に高圧油を供給するための油圧ポンプおよびアキュムレータが設置されている。また、油圧源棟の脇には油タンク、冷却塔および特高変電所がある。 計測制御棟には、振動台の試験時の運転操作、制御、計測を行う計測制御室がある。 耐震信頼性実証試験について
先述した実証試験の考え方を踏まえて、耐震実証試験としては、高地震地帯における耐震設計を行った機器について、設計用基準地震動S1およびS2に基づく地震力に対する耐震安全性、信頼性を確認することとしている。 ここで、設計用基準地震動S1(最強地震)というのはその地方で過去に起こった地震や周辺の活断層を考え合わせて、将来起こると予想される最強の地震の地震動であり、S2(限界地震)は、起こることは考えられないが、地震学的にはその地方で起こることが否定できない限界的な地震による地震動のうち最大のものをいう。 この実証試験により、確認される事項を具体的にあげれば、次のとおりである。 ①原子力発電所の安全上重要な設備については、耐震設計上強度的に十分な余裕を持たせてあるが、試験体について巨大地震時に相当する加振試験を実施することにより余裕度が確認される。 ②巨大地震の際に、機能維持を必要とする安全上重要な機器配管、構造物を模擬した試験体を加震中に機能させて所要の機能が発揮できることを確認する。 ③複雑化、大型化している原子力発電所は、大型計算機による各種振動解析技術などを用いた耐震設計が行われているが、試験体の加振試験結果と数値計算モデルによる計算結果を照合することにより、耐震設計の妥当性を確認する。原子力発電施設の耐震信頼性実
証試験は、国からの委託を受けて同センターで55年度から進められてきている。この試験の概要については、次のとおりである。 (1) 試験供試体
原子力発電所においては、その設備の破損による周辺環境への放射線障害の影響の観点から、重要度の分類が行われている。安全対策上重要な設備として原子炉一次冷却材圧力バウンダリー(原子炉圧力容器、一次系配管、蒸気発生器、加圧器など)、原子炉緊急停止装置(制御棒、駆動機構など)、原子炉格納容器、原子炉建屋などがあげられる。本実証試験ではわが国の110万キロワット級の改良標準型原子力発電施設(PWR、BWR)のうち、上記のカテゴリーに属するものから選んでいる。具体的には、①原子炉格納容器(エアロック、PWRのポーラクレーンなどの慣性付加質量やBWRの圧力抑制室内水などを模擬)、②PWR一次冷却設備(主冷却材管、蒸気発生器、ポンプなど)、BWR再循環系配管(ポンプ、弁、圧力容器の一部を含む)、③原子炉圧力容器(振動性状模擬の炉内構造物を含む)、④炉内構造物(実寸大模型の燃料集合体群、炉心支持構造物を含む。制御棒と駆動装置を装着)の実物大ないし実物に近い大きさの模型が試験対象として予定されている(第2表参照)。 (2) 試験内容
実証試験の実施にあっては、設計用基準地震動を用いて原子炉建屋の地震応答解析を行い、実際の機器の据え付け位置の振動(床応答地震波)をつくり出して、これと同じ波(実証試験用入力地震波)で試験体の載った振動台テーブルを加振することにしている。 試験項目としては、主として正弦波加振試験、地震応答波加振試験および機能試験が行われる。正弦波加振試験では、振動台テーブルを正弦波により加振して、機器の振動性状(固有周期、モード、減衰量)などを確認する。 第2表 試験体の種類・規模 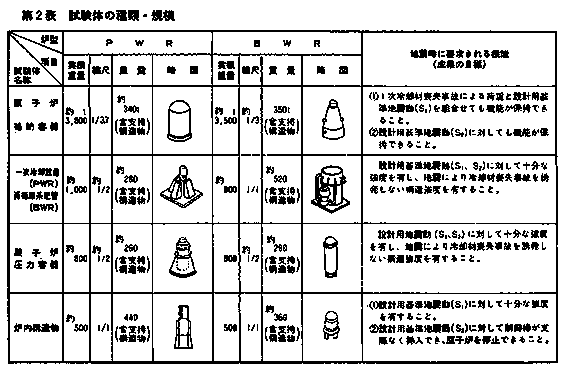 地震応答波加震試験では、床地震応答波により振動台テーブルを加振して、設計用基準地震動S1、S2に関して、①主要部の応答加速度、ひずみ(応力)、変位の測定、②対象機器、支持構造物の健全性の確認、を行う。機能試験では、格納容器の気密性の確認、プール水の揺動による影響評価(BWR)、炉内構造物はその健全性、制御棒そう入機能の確認などを予定としている(第2図参照)。 第2図 試験の流れ 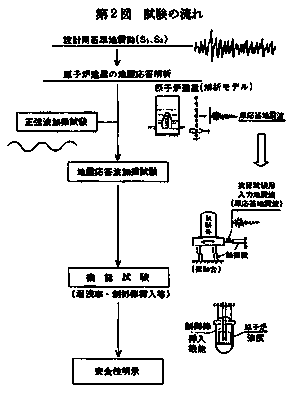 (3) 試験結果の評価
試験結果について、構造・強度の面から、①試験データ(固有値、応答値、応力など)の評価、②試験体の数値解析モデルによる結果と試験結果との対応の評価、③相似律による振動特性の実機換算値と設計値との対応評価、④振動試験方法の評価(設計用地震応答波と振動台上地震との相異、支持構造物の影響も考慮)を行い、これらを総合的に評価を行い、実機の安全性、信頼性を実証することにしている。 (4) 試験スケジュール
試験スケジュールとしては、55年度よりPWR格納容器の設計が開始され、56年度においては、PWR格納容器およびBWR再循環系配管の試験体の設計、製作ならびにPWR炉内構造物の設計が行われてきた。 加振試験としては、57年度にPWR格納容器について実施されるほか、次年度以降、毎年原則として1供試体の割合で試験を実施していく予定としている。 (5) その他の実証試験
原子力発電施設の信頼性実証試験としては、耐震信頼性実証試験のほか、安全上特に重要な機器や、これまでトラブルを生じたことのある機器などについての実証試験が進められてきている。これまでに、蒸気発生器の信頼性実証試験が実施され、その安全性、信頼性が確認された。また現在、バルブ、ポンプ、燃料集合体、溶接部熱影響部、電気計装機器などについての試験を実施中である。 おわりに
本稿で紹介した実証試験については、今後、原子力発電所の安全性、信頼性についての一般の理解を深め、原子力発電の促進について国民の円滑な合意形成を図るうえで大いに役立っていくことが望まれている。 また、この試験データなどについては、わが国の軽水炉技術を高めていくうえで活用していくことが期待されるほか、これらの試験成果は広く海外からも注目されており、国際協力にも役立つものと思われる。 さらに、今次完成した大型振動台設備は、世界でも有数の地震国であるわが国においては、原子力施設のみならず、その他の安全上重要な大型施設の耐震性の試験にも大いに活用していくことが望まれよう。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |