| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||
|
第5回遠心分離法濃縮施設保障措置プロジェクト(Hexapartite Safeguards Project)全体会合の結果について 原子力安全局
保障措置課
1. 開催期日
昭和57年3月31日~4月2日
(なお、これに先立ち、3月26日から31日にかけて評価グループ会合が開催された)
2. 出席者
全体会合の議長は、英国のF.Brown(エネルギー省)が勤めた。 3. 今次会合の主要結果
(1) 評価グループ会合
昭和56年11月東京会合決定に基づき、主として、カスケードヘの立入り査察(アクセス方式)についての保障措置戦略を検討した第4チームの結果を踏え、アクセス方式とノン・アクセス方式についての5ヵ月にわたる比較結果を報告書としてとりまとめた。(報告書「結論部分」は参考1,「比較評価の要点」は参考2)
(2) 全体会合
(イ) 評価グループ報告及び第3チーム報告(物質計量管理)を採択
(ロ) 今後の作業計画につき、日本のノン・アクセスを含めての検討という主張にもかかわらず、アクセスの前提条件である
(ⅰ) カスケード内外での査察活動の明確化
(ⅱ) 機微な情報の保護対策
について詳細な検討を行うこととなった。
(ハ) 作業手順としては、以下を指針とすることとなった。 (ⅰ) IAEAがアクセス方式を採用するに当って、役立つと思われる査察活動及び設計情報に関する技術保有国の見解を各国知らせあった上で、6月26日までに提出する。 (ⅱ) IAEAは、特定のタスクフォースを設け,個別に各技術保有国と詳細な検討を8月上旬までに行う。 (ⅲ) 次回会合までに上記(ⅰ)及び(ⅱ)を完成させる。 (ⅳ) 次回会合に,IAEAは各技術保有国の同意を得た情報を含めてのgenera-l paperを提出する。 (ニ)上記(ハ)のタイミングから、次回第6回HSP会合は、次により行うこととなった。 9月6日~8日 主要メンバー会合(バイを含む)
8日~10日 第6回全体会合
場所 西ドイツ アーヘン市
4. 今次会合の特記事項
(1) 米国が、従来から米国よりのアクセス方式を主張していたオランダと協調し、トロイカ3国をアクセス方式に傾けさせるよう働きかけたと見られ(独研究技術省ルーシュと米、IAEA代表ケネディとの協議など)、会合当初は、我が国の主張に対し、米、英、蘭、豪が強い難色を示したが、会合間の日-米、日-英、日-トロイカとの協議を続けるうちに、米国が我が方の立場に理解を示し、当初の強硬なアクセス方式一辺倒の案から妥協を見せるにしたがい、アクセスの程度についての米-トロイカ間の不一致点、独と英・蘭の考え方の差が現われ、結果として報告書の表現では我が方の立場がある程度反映されることとなった。 (2) 米及びトロイカの共通の認識は、何らかのアクセスがIAEA保障措置の政治的かつ技術的信頼性を高めるという点にあり、この点からみて極めて政治的な妥協が両者間でなされたものと見られる。 (3) 米国が最終的にアクセス方式を選択した理由は、エネルギー省及び濃縮工場を受託運転するUCC社の検討結果であることが、米代表(軍縮庁)より明かにされた。また,ノン・アクセスを主張する我が方の主張に終始反論したのはエネルギー省代表のブレナーであった。 (4) トロイカ内部では、独がアクセス方式に最後まで抵抗したが押切られたと我が方に述べるとともに、会合では、アクセスとノン・アクセスのバランスのとれた検討をすべきとの理由で我が方の主張を支持してくれたが、「評価グループ報告」第7章でのアクセス方式採用の3つ、とくに(7.2.1)の条件に重きをおいて米とトロイカ内で妥協した経緯があったようでその支持にも限界があった。 (5) 英は、保障措置の政治的信頼性のためと割切っている節が随所にうかがわれる発言ぶりであった。当方との非公式協議では、アクセスの度合をできる限り減らし、名目的にとどめるという条件斗争を考えている旨述べるとともに、技術保有国の考え方をIAEAにのませるとの立場から、カスケード内部での査察ポイント内に関し、IAEAを十分に教育していく方針であることを明かにした。 (6) 蘭は無条件アクセスで、豪とともに米を常に支持していた。 (7) トロイカの今後の作業は英が主導権をもっているようで、5月初旬には当初見解をとりまとめ、トロイカ内部で協議する予定である旨述べたが、独は他の国とも歩調をあわせるべきで、トロイカがトップランナーになる必要はないと反対していた。 (8) IAEA職員の国籍を考慮して、検討に当るタスクフォース及びインスペクターも少数共通の職員で構成するという点を各国とも重要要件としている。 (参考1)
評価グループ報告
第7章 結論と勧告
7.1. HSPにおける全ての調査検討は、核兵器国及び非核兵器国のINFCIRC/153タイプの協定の規定を受ける遠心分離法濃縮施設に限って行われた。 7.2. 当グループの評価では、遠心分離法濃縮施設へのIAEA保障措置の適用において、「限定された頻度での無通知によるカスケード区域への立入り」による方法が保障措置目標を満たしうるものである。また、この方式が受入れられるかは、以下の諸条件が完全に満たれるか否かにかかっている。 (7.2.1.) HSPの全参加者が受入れかつ、HSPの全技術保有国に適用されること。 (7.2.2.) 査察当局による検認活動の質と範囲についての明白でかつ疑いのない定義と解説。 (7.2.3.) 機微な情報の保護に関し、安全保障上の懸念に係わる諸問題の満足できる解決。 7.3. 加えて、参加者の中には、「カスケード区域へ立入らない方式」も同様に保障措置目標を達成しうると考えるものもいる。 7.4. 「立入り方式」は「立入らない方式」にくらべて、主に3つの利点を有している。 (7.4.1.) 施設運転者及び査察当局の両者にとって施設運転の妨げとなることが少く、かつ計装費・人件費が低い。 (7.4.2.) この方式の適用は、とくに既存もしくは建設中の施設に関しては容易である。 (7.4.3.) HSPの期間内で、「立入り方式」に関する計測技術の利用可能性がより信頼がおけるよう実証されうる。 7.5. 「立入り方式」の主要な不利な点は、機微な情報が曝露する危険をより高めることにある。 7.6. 評価グループは、上記の諸条件がいかにして適用されるかを知るため「立入り方式」につき、詳細に調査すべきであると考える。 (参考2)
ノン・アクセスとアクセス方式の比較一覧(評価グループ報告 第6章の要約) 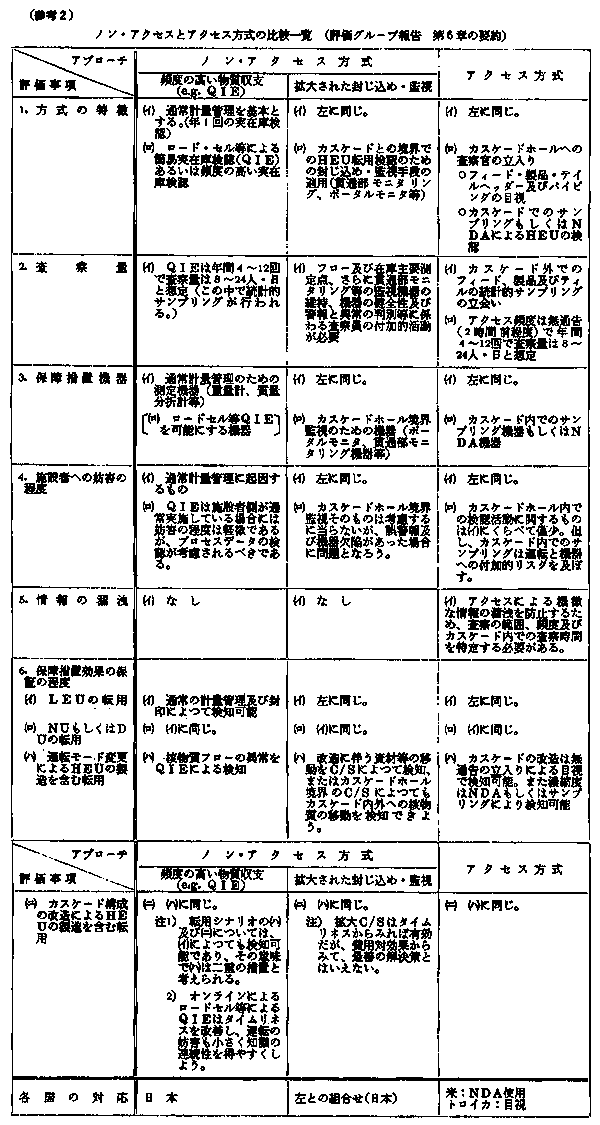 | ||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |