| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(高中性子束炉の増設)について(答申) 53原委第490号
昭和53年9月29日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和51年10月12日付け51安(原規)第116号(昭和53年7月17日付け53安(原規)第215号及び昭和53年8月18日付け53安(原規)第270号で一部補正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。 記 標記に係る変更の許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項で準用する第24条第1項各号に掲げる承認の基準に係る適合性に関する意見は次のとおりであり、各基準に適合しているものと認める。 (別紙)
核原力物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる承認の基準の適合に関する意見
(平和利用)
1. この原子炉は、学術研究、教育訓練及び医療照射のために用いるものであって、平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認める。 (計画的遂行)
2. この原子炉の設置は「原子力開発利用長期計画」に定める方針にのっとっており、原子力の研究開発活動の基盤をなすものとして十分な意義を有するものであると考えられるので、この原子炉の設置が我が国の原子力開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないものと認める。 (経理的基礎)
3. 本原子炉の設置については、昭和50年度より予算措置を得て計画されてきたものであり、設置に必要な資金は全額国庫金で調達される計画となっていることから、原子炉を設置するために必要な経理的基礎があるものと認める。 (技術的能力)
4. 別添の原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉を設置し、かつ、その運転を的確に遂行するに足りる技術能力があるものと認める。 (災害防止)
5. 原子炉安全専門審査会の審査結果のとおり、この原子炉の位置、構造及び設備は、核原料物質、核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上支障がないものと認める。 (別添)
昭和53年8月23日
原子力委員会
委員長 熊谷太三郎殿
原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄
京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更(高中性子束炉の増設)に係る安全性について
当審査会は、昭和51年10月12日付け51原委第863号(昭和53年7月17日付け53原委第422号及び昭和53年8月19日付け53原委第481号をもって一部補正)をもって審査を求められた標記の件について結論を得たので報告する。 Ⅰ 審査結果 京都大学原子炉実験所の原子炉の設置変更に関し、同大学が提出した「原子炉設置変更承認申請書(高中性子束炉増設)」(昭和51年10月1日付け申請、昭和53年7月10日付け及び昭和53年8月14日付け一部補正)に基づき審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は、十分確保し得るものと認める。 Ⅱ 変更の内容 本原子炉の設置変更に関し、京都大学が提出した原子炉設置変更承認申請書及び同添付書類に基づく申請の概要は次のとおりである。 1 概要
この変更は、大阪府泉南郡熊取町大字野田(国有地)にある京都大学原子炉実験所の既設の原子炉(研究炉(KUR)及び臨界実験装置(KUCR))に加え、同実験所内に新たに高中性子束炉(熱出力30,000kW)を大学の共同利用施設として、学術研究、医療照射及び教育訓練用に設置するものである。 本原子炉は、軽水減速冷却、重水反射体型2分割炉心で、高濃縮ウラン板状燃料を使用する非均質型の原子炉である。その特徴は、炉心が2分割されていることで、すなわち同型の分割炉心をそれぞれ内蔵する2つの炉心容器が重水を入れた反射体容器の中にあり、分割炉心が重水反射体を介して互に核的結合をしていることである。この構造を採用することにより、2分割炉心の間で1015n/cm2・s程度の熱中性子束を確保しようとしている。 京都大学原子炉実験所の敷地は、面積約326,000m2で、府道に長辺を接するほぼ長方形に近い形状を有している。また、敷地西側にある潅漑用池には地上権を得てその一部に周辺監視区域を設定している。 本原子炉は、敷地の南西端近くの丘陵地に位置し、原子炉室1階床面は標高約50mになる。炉心位置から敷地境界までの最短距離は、東南方向約100mであるが、その先の潅漑用池等も地上権を得て周辺監視区域を設定する予定にしているのでこの地も含めると、約160mになる。また、炉心位置から既設の原子炉までの距離は約250mである。なお、排気口は通常時は既設の原子炉のスタックを共用する。既設のスタックから設定予定の周辺監視区域境界までの最短距離は西方向約120mである。一方、非常排気用スタックは原子炉室に付設されるので、炉心位置とほぼ同位置にあり、同スタックから周辺監視区域境界迄の最短距離は約160mとなる。 原子炉施設は、原子炉本体、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質の取扱・貯蔵施設、放射線管理施設、原子炉格納施設、実験設備等から構成され、既設の原子炉施設の一部も共用することにしている。 2 原子炉施設の構造及び設備の概要
2.1 原子炉施設の耐震構造
原子炉施設は、原則として剛構造とし、耐震設計上の重要度に従って3段階に分類し、それぞれの重要度に応じた耐震設計が行われる。 耐震設計法としては、建築基準法に基づく震度法による静的解析が全施設に対して用いられ、安全上特に重要な施設等については、更に、原子炉室基礎底面における最大加速度300Galの地震波が発生しても十分安全性を確保できるように動的解析も併用される。 更に、原子炉室及び原子炉停止系については、原子炉室基礎底面における最大加速度450Galの地震動に対し、その安全保護機能が保持されることが確認される。 2.2 原子炉本体
原子炉本体は、燃料体及び炉心構造物と、これらを収納する2組の炉心容器、更に、炉心容器が貫通する反射体容器、反射体容器の外周を取り囲む熱遮蔽及び生体遮蔽、炉心容器及び反射体容器の上にある炉頂プール等から構成される。 (1) 炉心
炉心は、ほぼ同型の2組の炉心部が互に核的結合をした2分割炉心で、炉心部の燃料部分は二重の円環状をしている。 制御棒は円環の間隙部に挿入し、また、減速材を兼ねた冷却水は強制循環時は上部から下部へ流れ、自然循環時は逆方向に流れるようにする。
(2) 燃料体
燃料要素は円弧状に曲げた板状の燃料板を側板にはめ込み、断面が扇形になるようにした一種のMTR型燃料要素で、バウムクーヘン型燃料要素と称される。炉心は、この内側と外側の2種類の燃料要素を二重円環状に組みあわせて構成される。燃料板は、ウラン・アルミニウム合金をアルミニウム合金で被覆したもので、側板には、ほう素を可燃性毒物として入れる。
(3) 原子炉容器
原子炉容器は2組の炉心容器と反射体容器からなる。炉心容器はアルミニウム合金製の二重円筒型容器で、使用期間中に容器の交換も可能なように設計される。 1) 炉心容器
2) 反射体容器
(4) 放射線遮蔽体
反射体容器中央球形部の周囲に鉄製の熱遮蔽層とその外側に重コンクリート製の生体遮蔽が設けられる。 更に、炉頂プール水及び実験室の遮蔽は2次遮蔽の役目を果たしている。 1) 熱遮蔽
2) 生体遮蔽
(5) 炉頂プール
炉頂プールは、炉心容器及び反射体容器の上に設けられ、そのプール水は使用済燃料の取り扱いの際の遮蔽、非常用炉心冷却水源等に用いられる。
2) 使用済燃料プール及び同プール内燃料貯蔵設備
3) 炉頂プール内燃料貯蔵設備
貯蔵能力 約8炉心分
2.4 原子炉冷却系統施設
原子炉冷却系統施設は、炉心、反射体、生体遮蔽等で発生する熱を除去するための1次冷却設備、2次冷却設備、非常用冷却設備、重水冷却設備等から構成される。 (1) 1次冷却設備
1次冷却設備は、ほぼ独立の2つの閉回路からなり、それぞれの回路に1次循環ポンプ、主熱交換器、配管及び弁類、また、共通にリザーブタンク、ヘッダ等が設けられる。 1) 1次循環ポンプ
2) 主熱交換器
型式 シェルアンドチューブ式(直管型)
基数 2基/回路
3) リザーブタンク及びヘッダ
型式 円筒型
機能 水圧変動の吸収、水量監視及びガスの分離
4) 1次冷却水遮断弁
個数 1個/回路
機能 1次冷却水の喪失防止
(2) 2次冷却設備
2次冷却設備は、1次冷却設備の主熱交換器から熱を受け冷却塔から大気に放散させる設備で、2次循環ポンプ、冷却塔、2次加圧ポンプ等から構成される。 1) 2次循環ポンプ
型式 横型遠心式グランドシールポンプ
台数 4台
容量 約750m3/h/台
2) 冷却塔
形式 通風冷却式
基数 1基
3) 2次加圧ポンプ
形式 遠心式
台数 1台
(3) 非常用冷却設備
非常用冷却設備は、1次循環ポンプの故障や自然冷却のため1次冷却設備が停止した場合に、崩壊熱除去弁が自動的に自重により開き、炉頂プール水が同プールの水位差により1次冷却系内に流入し、炉心を下方から自然循環により冷却する機能を有し、一方、1次冷却系配管破断時に崩壊熱除去弁を通り、炉心へ水頭圧により炉頂プール水を注入する機能を有する。炉頂プールは通常3区分し、約1mの水位差を保つようにしており、この水位差は、プール水循環ポンプを使い維持する。 プール水排水槽に導かれた排水等はプール水再汲上げポンプで炉頂プールに戻すことができる。 1) プール水循環ポンプ
型式 遠心式メカニカルシールポンプ
台数 3台(うち1台は予備)
容量 約60m3/h(予備は約40m3/h/台)
2) 炉頂プール熱交換器
型式 シエルアンドチューブ式
基数 1基
3) 崩壊熱除去弁
型式 空気圧作動(閉)、自重落下(開)方式
数量 8個(プール水注入管注入側、戻り側各2個で2回路)
4) プール水再汲上げポンプ
型式 水中モータポンプ
台数 2台(うち1台は予備)
(4) 重水冷却設備
反射体容器内で発生した重水の熱を熱交換器を経て、中間冷却設備に伝え除去する設備であって、重水1次冷却設備、中間冷却設備により構成される。本設備にはトリチウム等の放射性物質の漏洩低減をはかるためカバーガス供給系を有する。 (5) 生体遮蔽冷却設備
反射体容器に近い生体遮蔽内で発生する熱を除去する設備であって、生体遮蔽冷却ポンプ、生体遮蔽熱交換器等から構成される。 2.5 計測制御系統施設
計測制御系統施設は、計装設備、安全保護回路、制御設備等から構成される。 (1) 計装設備
計装設備として、核計装設備、プロセス計装設備、制御棒位置表示装置等が設けられる。 (2) 安全保護回路
安全保護回路は、計装設備から送られる信号により異常状態を検知し、警報、スクラム等必要な動作を起させるものであり、原子炉停止回路、警報回路、制御棒引抜インターロック、自動制御インターロック等が組まれる。 (3) 制御設備
原子炉の制御は、主として制御棒の位置調整によって行われる。この制御設備に加え、非常用制御設備として炉心内空洞部落下設備及び制御液注入設備が設けられる。 なお、燃料要素の側板に可燃性毒物を入れ、燃料装荷初期の超過反応度等を抑える。 1) 制御棒
2) 可燃性毒物
3) 炉心内空洞部落下設備
4) 制御液注入設備
(4) その他主要な設備
原子炉施設の監視と制御に必要な設備は、原子炉管理棟に置く原子炉制御室に設けられる。また、制御室外でも原子炉停止、非常用炉心冷却等の操作を可能とする設備が設けられる。 2.6 放射性廃棄物の廃棄施設
放射性廃棄物の廃棄施設としては、気体、液体、固体廃棄物処理施設があり、一部の施設は既設の原子炉と共用される。 (1) 気体廃棄物処理施設
気体廃棄物処理施設は、原子炉室の系統、原子炉機器調整室等の系統等からなり、排気チェンバ、排気筒等で構成される。なお、原子炉室の系統は通常用と非常用に分けられる。 1) 原子炉室付帯の排気チェンバ
2) 原子炉室付帯気体廃棄物の排気筒
通常用
排気筒位置 KURのスタックと共用
排気口高さ 地上高約36m(標高約95m)
非常用
排気筒位置 原子炉室外壁面
排気口高さ 地上高約36m(標高約90m)
3) 原子炉機器調整室等付帯の排気チェンバ
台数 1台
構造 プレフィルタ、中間フィルタ及び高性能フィルタを内蔵
4) 原子炉機器調整室等付帯気体廃棄物の排気筒
原子炉機器調整室等の排気用
排気筒位置 原子炉室に隣接した建家の屋上
排気口高さ 地上高約6m(標高約67m)
ホットケープ等の排気用
KURのスタックと共用
(2) 液体廃棄物処理設備
液体廃棄物処理設備は、中放射性廃水処理系統と弱放射性廃水処理系統からなり、原子炉付帯の放射性排水槽から廃棄物処理場の廃水貯槽に送られた廃水を処理するため、蒸発濃縮処理装置、凝集沈殿ろ過処理装置等から構成される既設の設備の他に、廃棄物第2処理棟を新設し、以下の設備を設ける。 1) 廃水貯槽
基数 3基(監視貯留槽及び緊急時貯槽を含む)
容量 約40m3/基
2) 蒸発濃縮処理装置
基数 1基
容量 約16m3/日
(3) 固体廃棄物処理設備
固体廃棄物処理設備は、既設の設備の固体廃棄物減容装置及び固体廃棄物貯蔵施設を増設する。 1) 固体廃棄物減容装置
基数 1基
容量 約0.1m3/日
2) 固体廃棄物貯蔵施設
2.7 放射線管理施設
放射線管理施設は、屋内管理用設備、屋外管理用設備等から構成され、一部の設備は既設の原子炉と共用される。 (1) 屋内管理用設備
屋内管理用設備は、放射線監視設備、出入管理設備、汚染管理設備、試料分析関係設備等から構成される。 (2) 屋外管理用設備
屋外管理用設備は、環境モニタリング設備、気象観測設備等から構成される。 2.8 原子炉格納施設として原子炉室が設けられる。 (1) 原子炉室
原子炉室は、内部中央部に原子炉本体を設置した地上3階地下2階の鉄筋コンクリート構造物で、屋根及び壁面を鋼板張りとして気密性を有する。
(2) その他の主要な設備
原子炉室内で空気中のアルゴンが放射化される場所へは、アルゴン含有量を低減した人工空気を供給し、放射性アルゴンの発生を抑制するため人工空気供給設備をもった空気調和換気設備が設けられる。 2.9 その他原子炉の付属施設
原子炉の主要な付属施設として、非常用電源設備及び実験設備が設けられる。 (1) 非常用電源設備
通常電源の他に非常用電源設備として、非常用発電機、後備発電機及び無停電電源が設けられる。このうち、非常用発電機については既設の原子炉にも給電を可能にする。 1) 非常用発電機
2) 後備発電機
3) 無停電電源
組数 1組
容量 100V、120AH以上
型式 蓄電池式
(2) 実験設備
反射体容器のノズルや同容器周辺には、実験設備として、各種実験孔、照射孔、重水熱中性子設備等が設けられ、また、各分割炉心の中心部で照射を行うため重照射設備が設けられる。 なお、重水熱中性子設備は医療用照射にも用いられる。 参考図
参考図1. 京都大学原子炉実験所敷地
参考図2. 高中性子束炉概念図
参考図3. 原子炉本体配置立面図
参考図4. 炉心部の構造
参考図5. 冷却設備系統図
参考図1. 京都大学原子炉実験所敷地 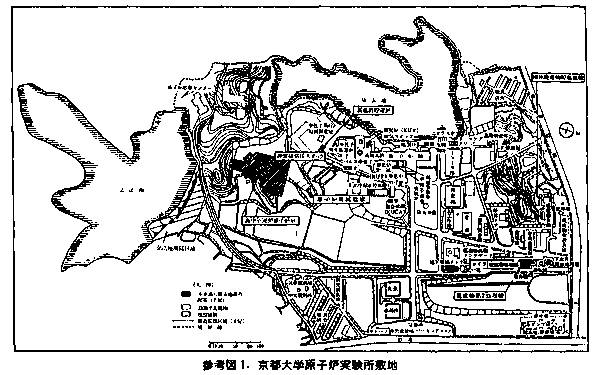 参考図2. 高中性子束炉概念図 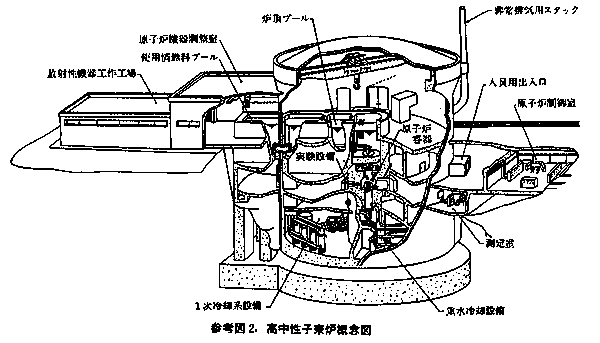 参考図3. 原子炉本体配置立面図 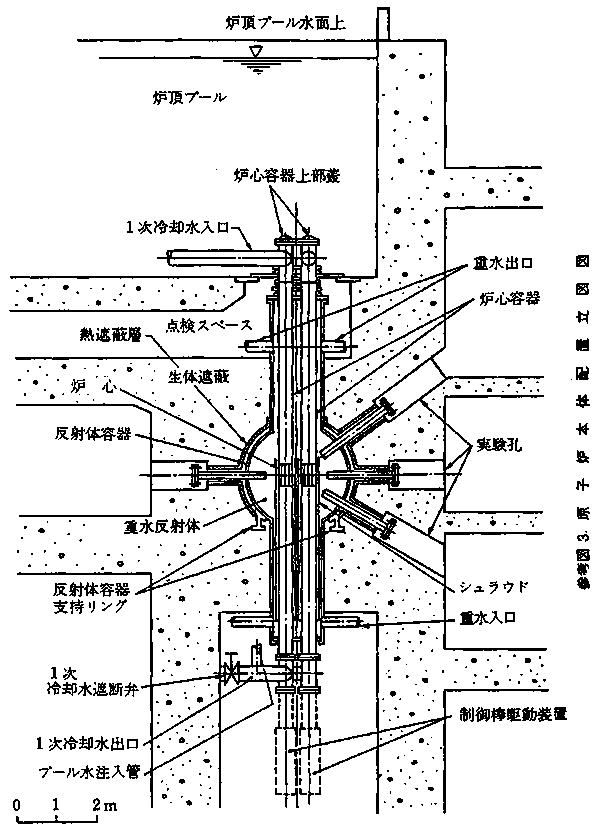 参考図4. 炉心部の構造 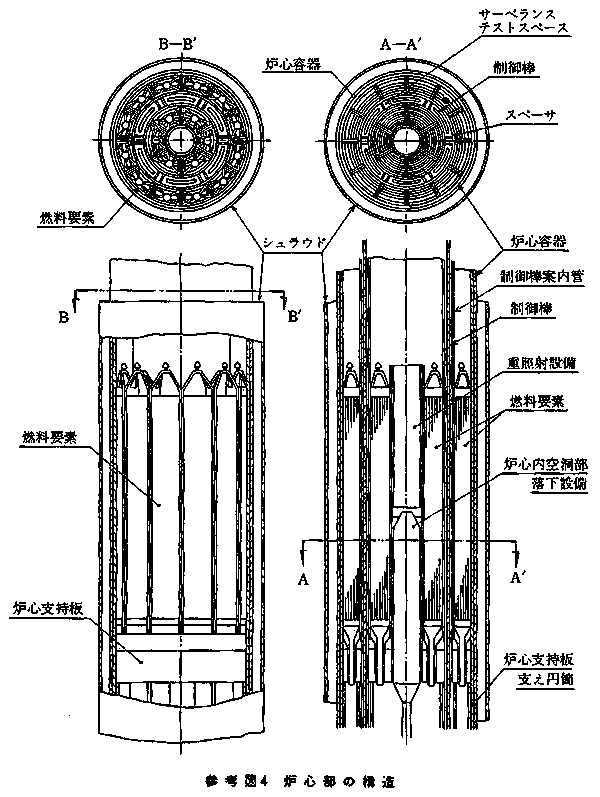 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考図5. 冷却設備系統図 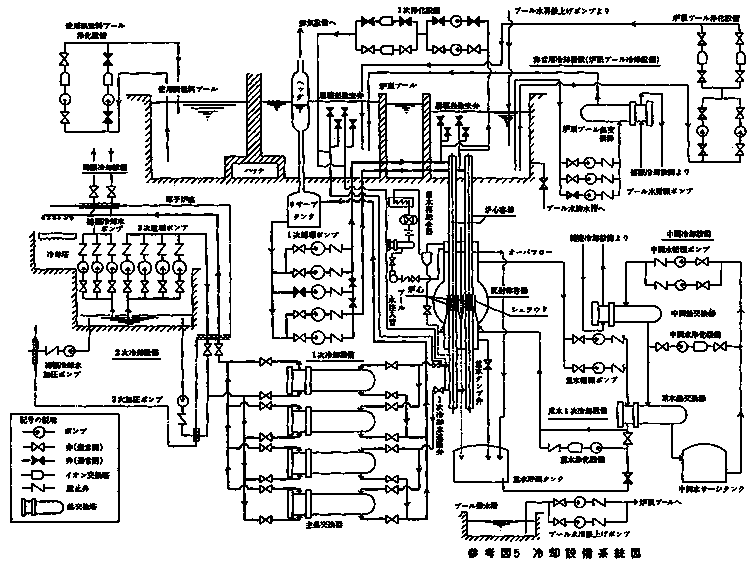 |
|
Ⅲ 審査方針 1 審査の基本方針
本審査会は、京都大学が大阪府泉南郡熊取町にある京都大学原子炉実験所内に研究用原子炉を増設することに対し、各種特性試験や照射試験も含んだ通常運転時はもとより、万一の事故を想定した場合にも、一般公衆、従事者等の安全が確保されるように所要の安全設計がなされることを確認するため、次の事項を基本方針として審査することにした。 (1) 原子炉施設が設置される場所の地震、気象、水理等の自然事象、交通等の人為事象によって原子炉施設の安全性が損なわれないような安全設計がなされること。 (2) 平常運転時に放出される放射性物質による一般公衆の被曝線量が許容被曝線量以下に抑えられることはもちろんのこと、更に、それを実用可能な限り少なくするような安全設計がなされること。 (3) 平常運転時において従事者等が許容被曝線量を超える線量を受けないような放射線の防護及び管理がなされること。 (4) 原子炉の運転に際し、異常の発生を早期に発見し、その拡大を未然に防止するような安全設計がなされること。 (5) 原子炉の運転に際し、機器の故障、誤操作等が発生しても燃料の健全性、原子炉冷却材バウンダリの健全性等が損なわれないような安全設計がなされること。 (6) 原子炉冷却材を包含している原子炉冷却材バウンダリの健全性が損なわれ、冷却材が喪失するような事故、炉心の反応度を制御している制御系の健全性が損なわれ、反応度が異常に上昇するような事故等の発生を仮定しても、事故の拡大を防止し、放射性物質の放出を抑制できるような安全設計がなされること。 (7) 重大事故及び仮想事故を想定しても、その安全防護施設との関連において、一般公衆の安全が確保されるような立地条件を有すること。 2 審査方法
(1) 審査は、申請者が提出した「京都大学研究用原子炉の設置変更の承認申請書及び同添付書類」に基づき行うこととした。 また、必要に応じて申請内容の補足資料及び参考文献の提出を求め審査を行うこととした。 本申請内容の基本的設計方針は、今後の詳細設計、施行、検査及び運転の段階においても堅持されることが法令上前提となっているものである。 (2) 立地条件の評価に際し、敷地の地質、地盤、水理、大気等の自然環境及び社会環境については書類による審査のほか、書類上の内容と照合するため、必要な事項について現地調査を実施することにした。 (3) 申請者が、KUCAを用いて行った実験結果、制御棒駆動機構の開発試験等の結果は、本審査で必要と判断される場合には提出を求め審査に反映させることにした。 (4) 事故評価に当たっては、申請者が行った解析を評価するほか、別途、チェック解析を行い審査の参考とすることにした。 (5) 審査に当たっては、原子力委員会がこれによるべきであると指示した「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」(昭和39年5月)への適合性を検討する。また、平常時の許容被曝線量及び放射性物質の放出管理については、「原子炉の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき許容被曝線量等を定める件」(昭和35年科学技術庁告示第21号)に適合することのほか、国際放射線防護委員会の勧告に基づき実用可能な限り放射性物質の放出を低くすることを目標とすべきであることを放針とする。 (6) 審査に当たっては、原子力委員会が発電用軽水型原子炉施設の審査を行うに際し、これによるべきであると指示した各種指針のうち以下については、本研究用原子炉施設でも個々に判断し可能な限り参考とすることにした。 ① 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について」(昭和50年5月)
② 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針(昭和51年9月)
③ 「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」(昭和52年6月)
④ 「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針)(昭和52年6月)
(7) また、当審査会が原子炉施設の安全審査に当たり、解析条件、判断基準等を内規として運用するために作成した報告書のうち以下については、使用又は参考とすることにした。 ① 「被曝計算に用いる放射線エネルギー等について」(昭和50年11月)
② 「発電用軽水型原子炉の反応度事故に対する評価手法について」(昭和52年5月)
③ 「取替炉心検討会報告書」(昭和52年5月)
④ 「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の被ばく線量評価について」(昭和52年6月)
(8) そのほか、同型炉の運転経験等も参考として行うこととした。 Ⅳ 審査内容 本原子炉の設置変更に関する立地条件、安全設計の基本方針、平常運転時における被曝管理等について検討した結果は、次のとおりである。 1. 立地条件
1.1 敷地
京都大学原子炉実験所の敷地には、すでに研究用原子炉1基(熱出力5.000kW)と臨界実験装置1基(熱出力100W、短時間最大熱出力1kW)が設置されており、敷地中央から東端にかけこれら原子炉施設と研究施設及び管理施設が設けられている。 本設置変更は、この敷地の南西端にある丘陵地を造成して高中性子束炉の原子炉室及び付属建家等を設置し、また、既設の廃棄物処理施設の付近に処理施設を増設するものである。 排気筒から周辺監視区域境界までの最短距離は敷地の西側の地上権を得ている潅漑用池の対岸の地点で約120mである。また、原子炉室及び非常排気用スタックから敷地境界までの最短距離は敷地の南東側で約100mあるが、この地点の先にある潅漑用池等についても地上権を得て周辺監視区域を設定する予定にしているので、この地域も含めると約160mになる。 従ってⅣ.4に後述するように周辺監視区域の設定に十分な条件を有しており、また「原子炉立地審査指針」に示される非居住区域は周辺監視区域に、低人口地帯は地上権設定区域を含む敷地に含まれているので、本敷地の広さは妥当であると判断する。 1.2 地盤
敷地周辺の地質については、古くから多くの調査研究が行われている。そして1975年には、大阪市立大学の市原実らによって、敷地及びその周辺を含めて、泉南-泉北地区について詳細な地質図並びに総括的な報告が発表されており、これに基づいて敷地付近の地質及び地質構造について考察が行われている。 この地質図によれば、敷地周辺には領家花崗岩(古生代-中生代)、泉南酸性火砕岩類(初期白亜紀後葉)、和泉層群(白亜紀末)、甘南備層(中新世)及び鍋山玄武岩(中新世-鮮新世)からなる基盤岩類、大阪層群(鮮新世-洪積世)、段丘堆積物及び沖積層が分布するとされている。 基盤岩類は、甘南備層を除いて、主として敷地周辺南部の和泉山脈に分布するほか、一部その北方の孤立した山地に認められる。甘南備層及び鍋山玄武岩は局所的に分布するにすぎない。大阪層群は、前述の基盤岩を不整合に覆って、和泉山脈の北に接する丘陵地に広く分布する。段丘堆積物は、大阪層群及び基盤岩類を不整合に覆って各河川の中下流域及び丘陵地に広く分布し、沖積層は河川に沿う氾濫原及び海岸平野を構成する。 敷地周辺の大局的な地質構造は、基本的には基盤岩類の東北東-西南西方向によって規制される。大阪層群は大局的にみて東北東-西南西走向で3°~5°の角度で北北西へ傾斜し、南南東方向基盤岩に近づくに従って漸時傾斜を増すとされている。 敷地付近の断層としては、敷地から東南東約5kmに存在する神於山断層及び内畑断層と、南方約1.5kmの所に存在する成合断層がある。神於山断層は、神於山山塊の南縁を通り北側の花崗岩類を大阪層群の上に押上げた衝上断層であり、内畑断層はその南側に並行して、南側の基盤岩類を同じく大阪層群の上に衝上させている。成合断層は、東西に走り、北側の基盤岩である花崗岩類を南に大阪層群の上に衝上させている。このほかに、これらの断層と同時期に形成されたと考えられるいくつかの撓曲構造が大阪層群中に設められる。これら3断層及び撓曲構造の活動は、高位段丘堆積物、中位段丘堆積物に及んでいないものと地質図上から読みとることができる。また、成合断層は現地調査の結果、中位段丘堆積物の堆積以前(更新世前期)に活動を停止していることが確認された。 上記3断層及び撓曲構造は、何れも延長2~5kmからそれ以下でありかつ現在活動していないのに対し、敷地の南方約12km付近を東西に走る中央構造線は一般的には活断層とされている。この中央構造線による地震活動が敷地に及ぼす影響については、1.3に後述するように耐震設計上配慮されている。 高中性子束炉の設置予定地及びその周辺敷地内の地質調査並びに地盤調査はボーリングを中心として実施されている。設置予定地は大阪層群下部層が分布し、これらのボーリングの地質柱状図から、高中性子束炉設置予定地付近の東-西、南-北・両方向地質断面を作成し、基礎地盤について地層の鉛直方向の詳細な分布並びに、水平方向の連続性が進められている。これら地質断面図から、設置予定地点の大阪層群は、主として厚さ数mの固結した粘土及び砂の規則的な互層からなり、北西-北北西方向に5℃~10℃で緩やかに傾斜し、地層の乱れもなく連続し安定した分布状態を示していることが確められている。なお、花崗岩類からなる基盤岩類は、深井戸の掘削から、地表面下約250m付近に存在するものと判断されている。 更に、各地層から撹乱及び不撹乱試料を採取し室内土質試験(比重、含水量、液性限界、塑性限界、1軸、3軸圧縮試験)を行い、支持力等を計算している。高中性子束炉の基礎として予定される砂層(地表面下16.5~22.7m)における長期許容支持力を建築基礎構造物設計基準に基づき計算した結果、約700t/m2なり十分な地耐力を有する地層であるとしている。基礎地盤の内部摩擦角は地表面下7.3~12.6mは35°、16.5~22.7mは43°と算定され、地層傾斜角が5°~10°であることを考慮すると安定であり、地すべりや破壊の恐れはない。また、原子炉室及び原子炉機器調整室は大阪層群下部層中に基礎をおくことにしているが、ボーリング調査に伴う標準貫入試験の結果から同下部層はN値35~50以上と十分な地耐力を有することを確設している。 なお、水平方向の剪断力に対しては必要により基礎盤を広げる等の対策を行うことになっている。 以上のことから本敷地の地盤は安定なものと判断する。 1.3 地震
敷地周辺の地震活動性については、「日本被害地震総覧」等をもとに調査されている。 耐震設計用地震動の算定に当たっては、地震の規模(マグニチュード)、震央距離、再現期間等を重視した吉川らが提案している統計処理方法を採用している。すなわち、地震費料を内陸性(近距離地震)と海洋性(遠距離地震)に分け、再現期間1,000年をとると考慮すべき最強地震は、それぞれマグニチュード6.8、8.5、震央距離30km、150kmとしている。地震基盤における最大加速度はSeedらの図表と岩崎の補正図を用いて評価し、近距離及び遠距離地震に対してそれぞれ160Gal及び75Galとしている。これらの値は、金井式-Seed図の組合せから計算された値ともほぼ一致しており妥当と判断する。 原子炉室基礎底面における最強地震は、表層の存在を考慮して修正すると近距離及び遠距離地震に対して最大加速度はそれぞれ300Gal及び140Galとなり、耐震設計用地震動の最大加速度としてはそれらの大きい方の300Galを選んである。 なお、中央構造線が敷地に最も近接する部分(敷地の南方約12km)は、同線中央部の東端、中央部と東部との境界部分に近いところにあり、中央構造線中央部及び東部にそれぞれマグニチュード8.5及び7程度の地震を想定すると震央距離は100km、30kmとなり、上述の手法から原子炉室基礎底面における最大加速度は300Gal程度となる。 以上から、300Galを原子炉室基礎底面における耐震設計用地震動の最大加速度として採用していることは妥当と判断する。 1.4 気象
敷地及びその周辺の気象については、原子炉施設を設計するに当たって考慮する気象条件及び原子炉施設の安全解析に用いる気象条件がそれぞれ調査されている。 前者の気象条件については、京都大学原子炉実験所における気象観測の他に最寄りの気象官署である大阪管区気象台及び和歌山地方気象台における長期間の観測記録から調査している。それによると、大阪又は和歌山における気象極値は、最大瞬間風速60m/s、最低気温-7.5℃、日最大降水量30cm、最深積雪40cmとなっている。京都大学原子炉実験所における1965年から1975年までに観測された気象極値も上記の極値をしのぐ値は見出されておらず、これらを参考に原子炉施設を設計することは妥当であると判断する。 後者の気象条件は、敷地内の上記京都大学原子炉実験所中央観測所で高さ35mの気象観測塔(排気筒から約311m離れ、観測塔頂上は排気口より約4m高い)を用いて風向、風速、日射量等を観測し、そのうちから1974年から1975年までの1年間を統計処理したものである。この統計期間は、和歌山地方気象台における1964年から1973年までの10年間にわたる気象資料の解析結果から特に異常な年ではないことを確認している。また、この期間の気象要素の欠測率2%は問題となるものではない。 大気拡散の解析は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に従い、平常運転時及び想定事故時について分けて行われている。すなわち、平常運転時の大気拡散の解析に使用する気象資料は、風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均が用いられている。放出源の高さは吹き上げ高さを無視して排気用スタックの高さを採っている。なお、静穏時(0.5m/s未満)については、3杯風速計の測定結果から年間発生頻度8%で風速は0.5m/sとして処理しているが、より優れた性能をもつ超音波風向風速計を設置して、観測した結果と比較検討すると、このうちのほとんどが0.5m/s~2m/sであることが確認されている。 また、想定事故時の大気拡散の解析に当たっては、上記1年間の気象資料をもとに想定事故継続時間に対応する相対濃度(χ/Q)及び相対線量(D/Q)が計算されている。計算では、事故時の放出口となる非常用スタックが原子炉室屋根から約5mしか突出していないため、放出高さの低減を考慮して安全側に地上放出とし、建家の拡散に対する効果は考慮している。χ/Q、D/Qは、周辺監視区域境界上の各方位毎の着目地点に対し累積出現頻度が97%に当たる値を算出し、それらの中の最大の値を求めている。 その結果、χ/Q、D/Qは非常用排気スタックの西方向でそれぞれ2.1×10-7h/m3、10μrem/Ciと評価されている。 以上、本原子炉施設の安全解析に使用されている大気拡散のパラメータ、気象観測方法、統計処理方法、大気拡散の解析方法等は妥当なものと判断する。 1.5 水理
敷地の周辺には、潅漑用貯水池である坊主池と弘法地があり、河川では雨山川があるが、過去の記録を調べても顕著な水害の記録はない。これら貯水池の溢水又は堤防の決壊によって原子炉施設に災害が生じないよう堤等の施工管理に当たり注意することになっており、また、たとえ決壊しても地形的条件から原子炉室が浸水する恐れはないと判断する。 敷地内の地下水は、ボーリング調査によると最も地表に近い砂層内に現われており、北西方向へ流れていると推定されている。また、透水試験結果からその流速、水量とも非常に小さいと判断する。しかし、地下水が原子炉室地下部分に浮力として働くのを防止するため、止水壁を設けるとともに一定水位以上の場合、揚水井戸から地下水を排水し地下水位を下げることにしている。 なお、敷地周辺の地下水の利用については、地元熊取町、泉佐野市の上水道が高い普及率を示し、浅井戸は飲用水としてはほとんど使用されていない。 敷地から出る排水は、敷地の北端から約500mの開渠を経て雨山川に放流される。雨山川は佐野川に合流し泉佐野市で大阪湾に注ぐ。この雨山川からは貯水池と同様に農業用水が取水される。 実験所用水については、高中性子束炉が完成した時点で全体で約2,500m3/日(このうち、高中性子束炉の2次冷却用補給水が一番多く約1,500m3/日)と見積られている。現在、敷地境界沿い又はその周辺に深井戸を設けており、そのうちの可動井2本からは最大約2,400m3/日取水可能であり、更に、深井戸の増設及び長期的には府営水道の導入を行うことにしている。 以上、水理に関し、問題となる点はないと判断する。 1.6 社会環境
敷地付近の社会環境については、排気筒を中心とする5km以内の集落及び公共施設、産業活動、交通の状況及び開発計画等について行政機関が作成した統計資料等によって調査されている。 最寄りの居住地としては、排気筒の東北東方向約300m及び北西方向約250mに京都大学の職員宿舎があり、集落としては東北東方向約400mに朝代地区がある。また、公共施設では、南々西方向約350mの地点に養識学校があり、更に500mまでに2つの保育所がある。最も近い病院は約2.2kmの地点にある。 産業活動については、北方向400mの敷地境界に接して電気メーカーの研究所及び原子炉燃料の製造所があり、更に以遠には主として繊維工業の工場が分布している。しかし、これら産業活動が高中性子束炉の安全性に影響を与えることはないと判断する。 交通機関では、敷地の西方向約1~5kmの範囲に国鉄、私鉄の各鉄道と国道二本が並行に走っており、また、敷地北側の境界に沿って府道が走っている。敷地付近には飛行場はないが、西方向約4km、東方向約3kmの各地点上空に直行経路(離着陸用ルート)があるので、敷地は各々の保護空域には入っている。しかし、航空機の墜落等の飛来物による原子炉施設への影響については発生確率からみて少ないものと判断する。 2. 原子炉施設の安全評価
2.1 原子炉施設全般
本原子炉施設の安全上重要な構築物、系統及び機器(以下重要な構築物等という。)は、安全上適切と認められる規格及び基準に準拠することが必要である。また、重要な構築物等は、人為事象、飛来物、火災等により、それらの安全機能が喪失しないように、設計上の考慮が必要である。更に、原子炉施設には、適切な避難通路及び通信連絡設備が必要である。 本原子炉施設は設計、製作、建設、試験検査を通じ、関連法規、日本工業規格その他の適切な規格及び基準に準拠し、かつ既設の原子炉の経験を生かして信頼性の高いものとしている。 重要な構築物等を含む区域は、それを取り囲む物的障壁を持つ防護された区域とし、これらの区域への接近管理、出入管理の徹底を図るとともに、探知設備、外部との通信連絡設備等が設けられるので、第三者による不法な接近等を未然に防止できるものと判断する。 本原子炉施設には、高温、高圧となる系統及び機器はなく、飛来物となると想定されるものは存在しない。また、敷地周辺には爆発に起因する飛来物の発生が想定し得ないことを確認した。 重要な構築物等は、火災の発生防止、火災の早期検知及び早期消火の対策を講ずるとともに、不燃性あるいは難燃性の材料を使用する設計がなされる。更に、安全上重要な計装設備及び機器等を可能な限り、分離して配置している。したがって、火災により重要な構築物、計装設備等が安全機能を損なうことはないと判断する。 本原子炉施設には、短時間の全動力電源喪失に対してガスタービン駆動による非常用発電機が設置され、その後備としてガソリンエンジン駆動による後備発電機があり、また蓄電池による無停電電源が設置される。更に、電源喪失で原子炉はスクラムにより安全に停止できること、1次循環ポンプ停止によって崩壊熱除去弁が開放して、炉頂プール水による非常冷却が開始するので、停止後の冷却が確保できる設計であると判断する。 非常用発電機は、既設の研究炉及び臨界実験装置にも給電できるように原子炉施設間で共用される設計である。しかしながら、この非常用発電機に接続する配置方式がループ式であること、非常用電源設備として設置される後備発電機及び無停電電源は高中性子束炉専用であること等から、たとえ原子炉施設間で共用されても、それによって本非常用電源設備が安全機能を失うおそれはないと判断する。 スクラムあるいは制御棒の一斉挿入に接続する安全上重要な計装設備は、“2 out of 3”方式を採用して、運転中の試験及び保修が可能である。更に重要な構築物等は、運転中できるだけ点検ができるか、あるいはそれが困難なものは、定期点検時、燃料取替停止時等において、適切な方法により試験及び検査ができる設計であり、それらの健全性は維持されると判断する。 本原子炉施設では、原子炉室1階及び2階に原子炉室出入口があり、それらのインターロック等は非常用発電機に接続される。原子炉室3階には非常用脱出口が設けられ、更に原子炉室内には非常用照明が設けられ、非常用発電機にも接続されている。また、原子炉室内に避難通路の標識が設けられる。したがって、安全な避難通路が確保できる設計であると判断する。 事故時に原子炉施設内の従事者等に対して、原子炉制御室及び中央管理室から指示できるように放送設備、電話設備、インターホン設備等が設置され、それらは、いずれも非常用発電機にも接続されている。したがって、これらの通信連絡設備は妥当であると判断する。 2.2 耐震設計
原子炉施設は地震に遭遇した場合にも重大な事故を起さないように、十分な耐震性を有する構造とする。 原子炉格納施設(原子炉室)等の重要な建家、構築物は、原則として剛構造として、十分な地耐力を有する地耐の上に設けられた基礎の上に建設する。機器、配管類はそれらを支持する建家、構築物と一体となるような剛あるいは強靭な構造とする。 (1) 重要度による分類
原子炉施設は耐震設計上の重要度にしたがって、3段階(a、b、c)に分類され、それぞれの重要度に応じた耐震設計が行われる。 aに属する安全上特に重要な施設は、その機能喪失が原子炉事故をひき起す可能性のある施設及び周辺公衆の災害を防止するために必要な施設であり、原子炉格納施設、原子炉本体、非常用冷却設備等を同分類に含めている。 bに属する安全上重要な施設は、原子炉の安全上重要な施設及び高放射性物質に関連するもののうち、a以外の施設であり、原子炉制御室、2次冷却設備等を同分類に含めている。 cに属する施設は、a,b以外の施設である。 施設の分類に当たって、上位の分類に属するものは、下位の分類に属するものと破損によって波及的事故が起らないことを確めることとしている。 以上述べた施設の分類は、原子炉施設の安全性を保持する上で適切なものであり、波及的事故に対する設計上の考慮方針と合わせ、原子炉施設の安全設計上妥当なものと判断する。 (2) 耐震設計法
各施設は、重要度に応じ適切な設計法によって耐震設計されるが、基本的には、建築基準法に定められた震度に基く静的解析により得られる地震力、又は、基盤に設計用地震動を与え、各施設の固有の動特性を考慮する動的解析によって求められる地震力に対して安全であるように設計される。 静的解析によって算定する水平地震力は、建築基準法に基づき建家・構造物の基礎底面における基準震度を0.2とし、高さ方向に所定の割増しを行い、地盤種別及び構造種別による係数を乗じた水平震度(以下「水平震度」という。)から求めるものである。また、鉛直地震力は、建家・構造物の基礎底面における「水平震度」の1/2を鉛直震度(高さ方向には一定とする。以下「鉛直震度」という。)として求められる。 静的解析に用いる静的震度は、建家、構造物と機器、配管類によりa、b、cの施設で異なる値を用いている。aに属する建家、構築物は「水平震度」、「鉛直震度」の3倍を静的震度として用い、機器、配管類では、建家、構造物に対する静的震度の1.2倍を用いている。 b及びcに属するものの静的震度については、建家、構築物と機器、配管類との関係はaの場合と同一であるが、「水平震度」については、bはaの1/2、cはaの1/3としている。なお、b、cに属するものについては「鉛直震度」は考慮していない。 動的解析に用いる設計用地震動は、原子炉室基礎底面における最大加速度を300Galとして、エルセントロ、タフトで記録された地震波及び人工的に合成した設計用地震波の3波が用いられる。 動的解析は、aに属する施設とbに属する機器、配管類のうち、支持構造物の振動と共振するおそれのあるものに対して、検討が行われる。 aに属する施設は、静的解析又は動的解析により得られる水平地震力のうちいずれか大きい方の水平震力と静的解析により求める鉛直地震力とが同時に不利な組合せで作用するものとしてこれに耐えるよう設計される。 b、cに属する施設は、静的解析により得られる水平地震力に耐えるよう設計される。 なお、aに属する施設のうち、特に一般公衆の安全を確保するために、安全対策上、緊要な施設である原子炉室、原子炉停止系(制御棒、炉心内空洞部及び制御液注入設備)については、原子炉室基礎底面において設計用地震動の最大加速度の1.5倍(450Gal)の地震が生じた場合でもその安全機能が保持できることを確めることとしている。 また、地震に対する配慮として約20Galの地震が起こった場合に原子炉を自動的に停止させるために、地震感知器が設置される。 以上の耐震設計によって、原子炉施設の耐震安全性は十分確保し得るものであり、この耐震設計法は、原子炉施設の安全設計上妥当なものと判断する。 2.3 炉心設計
(1) 核設計
本炉心の核設計においては、以下に示す事項を満足することが必要である。 ① 反応度制御設備は燃料及び可燃性毒物の燃焼、核分裂生成物による毒作用、その他の運転に伴う反応度の変化を十分補償できるとともに、最大の反応度価値を有する制御棒が完全に引抜かれた状態であっても、常に原子炉を臨界未満にできること。 ② 運転中の過渡状態に対して、固有の負の反応度フィードバックにより、自己制御性を有すること。 ③ 原子炉出力に対して、利用可能な熱中性子束ができるだけ大きく炉心部では出力分布がなるべく平坦化すること。 そのため審査に当たっては、反応度の制御能力、反応度温度係数、使用した計算コード、中性子束分布等について検討した。 反応度制御設備は、12本の制御棒のほかに、炉心内空洞部落下設備(分割炉心ごとに0.5%Δk/k以上)、制御液注入設備(1%Δk/k以上)等から構成される。制御棒1本当たりの反応度制御能力は、0.7ないし2%Δk/kであり、制御棒全体として12%Δk/k以上の反応度制御能力を持っている。反応度停止余裕は、いかなる炉心構成でも4%Δk/k以上あり、最大の反応度を有する制御棒が完全に引抜かれた状態であっても、2%Δk/k以上の反応度停止余裕があることを確認した。 KUCAの実験結果から2分割炉心体系では炉心部は負の温度係数を有するが、反射体部は正の値となる。しかし、定格出力運転時において、炉心部の温度係数は約-1.4×10-4(Δk/k)/℃、反射体部の温度係数は約0.7×10-4(Δk/k)/℃であり、全体としては負となる。また、運転時の異常な過渡変化時においても、炉心部での負の温度係数の方が反射体部のものと比較して支配的となるので原子炉は自己制御性を有し、運転制御上、問題がないと判断する。 使用した2次元拡散計算コード(KAK)及び用いた群定数の妥当性はKUCAでの臨界量等の実験値と比較して確認された。中性子束分布及び出力分布は、重照射設備に挿入される照射試料、燃料及び可燃性毒物の燃焼、制御棒の位置等によって異なる。2次元拡散コード及び臨界実験装置を用いた各種の比較検討の結果から、出力ピーキング係数が最も厳しくなる場所、制御棒挿入高さ等を確認した。 その他、最大超過反応度、反応度添加率、最高燃焼度等についても検討を行い、炉心の核特性上、問題がないことを確認した。 なお、初回起動時に、温度係数、制御棒の反応度制御能力等を測定することにより、核特性の妥当性を確めることとしている。 以上のことから、本原子炉の核設計は、妥当なものと判断する。 (2) 熱水力設計
本炉心の熱水力設計においては、通常運転時はもちろん、運転時の異常な過渡変化時においても燃料が損傷しないように、以下に示す事項を満足することが必要である。 ① 定格出力運転時に1次冷却水出口平均温度が65℃以下であり、燃料板表面の最高温度が130℃以下であること。 ② 燃料板表面における最小DNBRは、Bernathの式による評価値が1.5以下にならないこと。 このため、審査に当たっては、1次冷却水出口平均温度、燃料板最高温度、熱水路係数、DNB熱流束等について検討した。また、重水1次冷却設備等についても検討を加えた。 1次冷却水は炉心の冷却水流路を上から下へ強制循環し、炉心内の発生熱を除去する。定格出力運転時における炉心入口の冷却水温度は約50℃圧力は約5.3㎏/cm2Gで、炉心出口の平均温度は約58℃である。 燃料板最高温度は、1次冷却水の平均温度上昇、熱流束、熱伝達率、燃料板表面温度等から計算される。後述する熱水路係数を採用すると、高温点での燃料板表面最高温度は約117℃である。燃料板冷却流路出口での冷却材圧力は約4.4㎏/cm2Gであり、それに対応する冷却水の飽和温度は約154℃である。したがって、高温点においても局所沸騰が起こらないことを確認した。 熱水路係数は、核的係数と工学的係数に分類されて、更に工学的熱水路係数は、冷却水温度上昇、熱流束及び熱伝達率に対するものに分類され、設計上考慮されている。 サブクール領域でのDNB熱流束を予測するために、各種の式が吟味検討された結果、本原子炉の運転条件に最も適合している適用範囲を有するBernathの式が用いられた。その式により計算された値に安全率1.4を見込んだ値がDNB熱流束として採用されている。通常運転時において熱的に最も厳しいと予想される燃料板における最小DNBRは、約3.6であり、制限値1.5に対して十分な余裕を持って炉心冷却が行われることを確認した。 運転時の異常な過渡変化時における最小DNBRは、次の5で検討される。 その他、炉心内の流量分布と重水1次冷却設備による炉心容器最高温度等についても検討を加え、炉心の熱水力特性上問題がないことを確認した。 以上のことから、本原子炉の熱水力設計は妥当なものと判断する。 (3) 動特性
原子炉を安定に運転するためには、運転中の外乱に対して燃料の許容設計限界を超える状態となる過大な出力振動が生じないように十分な減衰特性を持たせる設計であるか、又はたとえ出力振動が生じても、それを確実に検出して抑制できる設計であることが必要である。 そのため、審査に当たっては、2分割炉心の安定性等について検討した。 2分割炉心の動特性に関して、KUCAを用いたパイルオッシレータによる反応度-熱中性子束の伝達関数の測定を行い、その振巾特性及び位相特性から2分割炉心に基づく不安定現象が実験的に生じないことを確認した。2分割炉心は、炉心部と反射体部という2つのフィードバック回路を有する系であり、その安定性とナイキストの安定判別条件を用いることによって確認した。 また、2分割炉心の核的結合が動特性に及ぼす影響についてアナログ解析を行って、2分割炉心は適当な核的結合を有し、ほぼ、単一の炉心として振舞うことを確認した。 以上のことから、本原子炉の動特性解析は妥当なものと判断する。 2.4 原子炉本体
(1) 炉心及び炉心構造物
燃料板、燃料要素等は、原子炉内における使用期間中を通じ他の炉心構造物との関係を含め、その健全性を失うことがなく、炉心の性能を十分に発揮し得る必要があり、更に使用材料、使用温度、圧力条件、照射効果等を考慮した設計である必要がある。 そのため審査に当たっては、燃料板、燃料要素等について材料特性、機械設計等の観点から検討を加えた。 炉心及び炉心構造物には、耐食性に優れ、かつ放射線損傷の少ないアルミニウム合金が使用されるのは妥当であると判断する。 ウラン・アルミニウム合金板をアルミニウム合金で被覆した類似の燃料板は、KURを始め、原研のJMTR、米国のHFBR等の国内、外における多くの研究用原子炉で使用され、安定な運転実績を有していることを確認した。 燃料被覆材の腐食は、冷却材のpH、燃料板の表面温度、照射量等に関係する。アルミニウム合金で被覆された燃料板の典型的な運転条件下では、被覆材の腐食層の厚さを算定したが、被覆材の厚さに比べ十分小さいので、被覆材の腐食は実際の運転上問題がないと判断した。 燃料要素の側板の内部に可燃性毒物用のほう素を含むアルミニウム合金が入れられ、そのアルミニウム合金は側板のアルミニウム合金で被覆された形となり、直接1次冷却水に触れることはない。側板の機械的強度については念のために、強度試験をすることとなっている。 本原子炉は研究炉であるため、研究遂行上の目的から、重水以外にアルミヌウム、ベリリウム等の反射体を用いる場合及び燃料要素の代りに燃料要素状プラグを用いる場合がある。この場合、あらかじめ熱除去、制御棒反応度制御能力等に問題がないことを、KUCA又は本原子炉の特性試験により確め、必要に応じて炉出力を下げて運転する等の措置をとることとしているのは妥当であると判断する。 その他、炉心支持板、制御棒案内管等の炉内構造物についての機械設計について検討して問題がないことを確認した。 以上のことから、炉心及び炉心構造物の設計は妥当であると判断する。 (2) 炉心容器及び反射体容器
炉心容器、反射体容器等は、破損の発生する可能性が極めて小さくなるように考慮された設計であり、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、保修時、試験時及び事故時に脆性的挙動を示さず、かつ急速な伝播型破断を生じない設計である必要がある。 そのため審査に当たっては、炉心容器、反射体容器等について材料特性、機械設計等の観点から検討を加えた。 炉心容器の材料として使用されるアルミニウム合金は、耐食性に優れ、かつ放射線損傷上問題が少ないために1023n/cm2程度の高速中性子フルエンス(E<0.1MeV)までの使用に十分耐えるものとされている。 炉心容器材料の照射効果としては、ボイド形成、シリコン析出転位等によるスウェリング、降伏点及び引張り強さの変化等が考えられているが、それらの効果はほとんど影響がないことを確認した。 更に炉心容器の使用期間は定格出力運転換算で5年を目途としているが、これに拘わらず照射試験片を用いた各種のサーベイランス試験を行い、その結果、材料の諸特性の変化が著しく、使用に耐えられないと判断される場合には、炉心容器を適切な方法と手順で交換することとしているのは妥当であると判断する。 なお、炉心容器は二重管として、その間隙に漏洩検知器を取付け、漏水があった場合には早期に検出できるようになっている。 ステンレス鋼製である反射体容器に関しては、運転温度が約80℃(最高使用温度110℃)であり、定格出力運転30年として、SUS316L熱処理材の降伏応力、引張強度、伸びに対する照射効果を考慮しても反射体容器の延性は保持され、機械的損傷が起こることはないと判断する。 なお、反射体容器の製作に当たり、実機と同じ溶接条件で溶接した継手試験片を作り、同じ炉中で、最終熱処理を行った後、継手の組織観察を行って応力腐食割れの原因となるような組織その他の問題点がないことを確認することとなっているのは妥当である。 以上のことから、炉心容器及び反射体容器の設計は妥当であると判断する。 2.5 原子炉冷却系
2.5.1 1次冷却設備
1次冷却設備は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時において炉心を冷却し、その健全性を保つと共に、事故時においては非常用炉心冷却設備の作動とあいまって炉心を冷却する必要がある。 また、1次冷却水中の放射性物質が外部へ直接漏洩するのを防ぐ障壁の機能を持つ必要があるので、系統の機器及び配管の健全性が確保できるように、漏洩の検知、破壊の防止及び定期的な試験・検査を行って健全性の維持を図らなければならない。 このため審査に当たっては運転時の異常な過渡変化時及び事故時に予想される過圧に対する健全性、照射脆化、漏洩検知対策及び運転開始後における定期的な試験の可能性について検討を加えた。 1次冷却設備は、ほぼ独立の2つの閉回路から成り、それぞれの回路に1次循環ポンプ、主熱交換器等が設けられる。1次冷却水は、炉心を上から下に向かって流れ、炉心内で発生した熱を除去する設計である。 1次冷却系の最高使用圧力は9㎏/cm2Gに設計されており、冷却水の炉心容器入口圧力は約5.3㎏/cm2Gと比較的低圧である。 系統には自由液面を持つヘッダが設置され、この液面の変化により冷却水の熱膨脹が吸収されると共に、ポンプの起動に伴う系内の圧力変動は緩和されるものと考える。 なお、1次循環ポンプ運転中に1次冷却水遮断弁が閉鎖して、1次冷却系の圧力が異常に上昇するを防ぐためにポンプトリップ等のインターロックが設けられる。更に、万一の過圧現象に備えて薄板安全弁が設置される。 1次冷却設備を構成する機器及び配管のうち、1次冷却材に直接触れる部分は、腐食防止の観点から使用材料としてステンレス鋼及びアルミニウム合金が主に使用されているが、高中性子束炉であるので、その照射脆化について検討を加えた。 炉心容器は、2.4(2)で述べたように5年をめやすに交換され、その健全性は維持されるものと考える。 また、炉心容器に持続されるステンレス鋼製の1次冷却系配管は、その位置が炉心から遠ざかるので、中性子照射線量は少なく照射脆化について問題はないものと考える。 1次冷却設備の機器、配管からの漏水はヘッダ水位の低下により検知することができるが、漏洩検知器等による検知も可能であるので、漏洩検知対策は多重性を有し、また、漏洩の早期検知もできるものと考える。 更に、原子炉の運転開始後、1次冷却設備の健全性を確認するため、定期的に検査が行えるよう機器、配管等の設計に当たっては、検査箇所へ接近できるように考慮されており、特に反射体容器と炉頂プール下部の間に点検スペースが設けられる。 以上のことから、1次冷却設備は妥当なものと判断する。 2.5.2 非常用炉心冷却設備
非常用炉心冷却設備は、1次冷却材流量喪失及び1次冷却材喪失事故を想定した場合、非常用電源系のみの運転下で単一故障を仮定しても、炉心冷却能力を損なうような燃料の大きな損傷を生じることのないようにするとともに、崩壊熱を長期にわたって除去できる能力が必要である。 このため、非常用炉心冷却設備が電源系も含めて多重性及び試験検査の可能性が確保されているかについて検討を行った。 また、1次冷却材喪失事故に関連し、1次冷却水遮断弁の機能についての検討も加えた。 非常用炉心冷却設備は炉頂プール、プール水循環ポンプ、崩壊熱除去弁、プール水再汲上げポンプ等により構成され、非常時の炉心冷却と崩壊熱除去との機能を兼ねている。 炉頂プールは通常はゲートにより三つに仕切られ、各部分の間に水位差をつけている。通常停止時には1次循環ポンプを停止することにより、1次冷却系の圧力が降下すると崩壊熱除去弁が自重で自動的に開き、高水位側の炉頂プール水がプール水注入管から炉心容器に流入して、炉心の崩壊熱を除去し、低水位側の炉頂プールに戻る設計である。 崩壊熱除去弁は炉心容器上部及び下部のプール水注入管にそれぞれ複数個設けられる。 また、炉頂プールの3つの部分の水位差は特殊な低出力運転時を除き、プール水循環ポンプにより常時維持される。この系統には、予備ポンプを有すると共に電源も商用電源の他に非常用発電機及び後備発電機に接続されている。 更に、プール水循環ポンプが使用不能になり炉頂プールの水位差が維持できなくなった場合に備えて低水位側のプール水を排水して水位差を保つ系統を設けている。 1次冷却系主配管破断後の長時間の炉心冷却を保証するには炉心を冠水させる必要があるが、このため、炉心容器下部に接続する1次冷却系主配管に遮断弁を設け、サブパイル・ルームを水密構造にする。 また、多量の漏水が生じた場合、漏水は原子炉室地下のプール水排水槽へ導かれるプール水再汲上げポンプで炉頂プールに戻せるように設計される。このため、ポンプは水中モーターポンプ式とし、電源は商用電源の他、非常用発電機及び後備発電機に接続される。 1次冷却水遮断弁は配管破断等による炉心内の冷却水の流出を防止する目的で設けられるが、漏水でヘッダ水位が低下し、更に、1次循環ポンプが停止すると自動的に全閉する。この弁は、電動操作が不能になった場合でも原子炉室3階において手動によって閉止操作ができるようになっている。 非常用炉心冷却設備の試験・検査の可能性については、通常の炉停止時の崩壊熱除去で常に使用すること及びポンプの試験運転を行うこととしているのでその機能を十分確認できるものと考える。 また、1次冷却水遮断弁についても運転毎の起動前点検等により健全性を確認することになっている。 非常用炉心冷却設備の機能及び性能については6.2に後述するように、1次冷却水主配管破断事故時の解析では炉心を著しく損傷しないことを確認した。 以上のことから、非常用炉心冷却設備及び1次冷却水遮断弁の設計は妥当なものと判断する。 2.5.3 重水1次冷却設備
重水冷却設備は、反射体容器と重水熱交換器の間に重水を循環させ、反射体内で発生する熱を中間冷却設備に伝え重水を冷却する設備である。本設備は発生する熱を安全に除去できる設計であることはもちろん重水中に発生するトリチウムやその他の放射性物質が外部へ直接漏洩するのを防ぐ障壁の機能を持つ必要がある。 このため審査に当たっては重水の漏洩防止対策及び検知についての検討を加えた。 重水1次冷却設備は重水を約360m3/hで循環させ、反射体容器出口での平均温度を約60℃とする設計である。 原子炉容器を構成している反射体容器はステンレス鋼で製作されるが、多数のノズルを有することもあり、製作技術及び照射脆化についての検討を行った。検討の結果は、2.4.(2)で前述した通り、漏洩を伴うような損傷は生じないものと考える。 重水1次冷却設備内の圧力変動は、ヘリウムのカバーガスにより調節し、過圧されることがないように設計される。 なお、カバーガス中のトリチウムが外部へ漏洩するのを防ぐため反射体容器は密閉構造としている。 重水の漏洩に対しては基本的にはフランジ部を可能な限り少なくし、ポンプをキャンドタイプとするなど漏洩しにくい構造に設計される。また、漏洩を検知するためには重水の保有量の監視を行うことになっているが2.4(2)で前述したように炉心容器の重水と軽水との隔壁を二重にして、その間隙に漏洩検知器を取付け重水又は軽水の漏洩を検知する設計である。また、フランジ継手による接続部は二重ガスケットを用い、内外ガスケット間に漏洩検知器を取付ける等の漏洩検知対策を行うこととしている。 なお、実験孔等の破損による漏洩事故など多量の重水漏洩が考えられる場合の対策としては漏洩量を最小限にとどめるために重水を貯蔵タンクにダンプできるようになっている。 以上のことから、重水1次冷却設備は妥当なものと判断する。 2.5.4 その他の冷却設備
冷却設備は原子炉施設の各部で発生する熱負荷を最終的な熱の逃し場に確実に伝達できるとともに、その際、冷却設備から放射性物質が直接外部へ漏洩することも防ぐ必要がある。 このため審査に当たっては各冷却経路及び放射性物質の漏洩対策について検討を加えた。 炉心での発生熱は、1次冷却設備から主熱交換器を通して2次冷却系に伝えられ、更に冷却塔に運ばれ、大気に放出される。 2次冷却系の圧力は、主熱交換器内において1次冷却系の圧力よりも高く保ち、主熱交換器の細管破損時に1次冷却水中の放射性物質が2次冷却水中へ流入することを防止する設計となっている。 重水熱交換器での漏洩については、重水1次冷却系と補機冷却系との間にこれらより低圧の中間冷却系を設けることにより、トリチウム等の放射性物質を含む重水が直接外部に漏洩したり、あるいは補機冷却水が重水中に混入して重水の純度が下がることを防ぐ設計となっている。 生体遮蔽冷却設備は生体遮蔽内で発生する熱を除去し、補機冷却設備に熱を伝達するが、冷却用配管群は万一、漏洩した場合でも個々に盲プラグを施すことが可能な設計である。 その他に補機冷却設備、実験設備冷却設備等についての検討を加え、問題ないことを確認した。 以上のことから冷却設備の設計は妥当なものと判断する。 2.6 計測及び制御設備
2.6.1 原子炉制御室
原子炉制御室は、通常運転時の操作はもちろん、事故時にも従事者がとどまり、事故処置が可能であるように換気設計、遮蔽設計及び不燃設計がなされる必要がある。 このため審査に当たっては事故時の居住性、主要ケーブル及び制御盤等の火災対策並びに制御室外緊急停止装置の機能について検討を加えた。 原子炉制御室には通常運転、事故処置等に必要な原子炉制御系、安全保護系、核計装設備、プロセス計装設備等の計測制御装置が設置され、集中的な監視及び制御を行えるように設計される。 原子炉制御室は原子炉と離れた管理区域外に設置することになっている。また、その換気系は他の換気系とは独立して設けられる。したがって、事故時にも従事者が原子炉制御室内にとどまり必要な操作を行うことができるものと判断する。 原子炉制御室で火災の発生する可能性を極力少なくするため、ケーブル、制御盤等は不燃性、難燃性材料を使用する設計である。 万一、火災が生じた場合に備えて熱、ガスを検出する火災検知設備及び消火設備が常備される。 なお、原子炉制御室において火災等により操作が困難な場合にも、制御室外緊急停止装置により外部から手動スクラム、非常警報、原子炉室給排気口の封鎖、非常用冷却、炉心内空洞部落下等の操作が可能なように設計される。 以上のことから、原子炉制御室は所定の機能を果たす能力を有しているものと判断する。 2.6.2 安全保護系
安全保護系は以下に示す事項を満足することが必要である。 (1) 運転時の異常な過渡変化又は事故を検知し、原子炉停止系を含む適切な系の安全保護動作を自動的に開始させる機能を有すること。 (2) 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、保修時、試験時及び事故時において、その保護機能を喪失しないようにチャンネル相互を分離し、多重性を持たせたチャンネル間の独立性を確保できること。 (3) 原子炉運転中における定期的試験により、その健全性を確認できること。 このため審査に当たっては多重性、独立性、計測制御系との分離等について検討を加えた。 安全保護系はその系を構成する機器等を可能な限り分離し、相互に独立性を配慮した多重構造とし、単一故障によって保護機能を喪失しないような設計となっている。大部分のスクラムあるいは制御棒の一斉挿入につながる安全保護系は“2 out of 3”構成となっているので、この系を構成する機器又はチャンネルの単一故障あるいは使用状態から単一の取外しを行っても安全保護機能が損なわれることはないと判断する。 安全保護系は駆動源の喪失、系の遮断等不利な状態になっても、最終的に安全な状態に落着くように設計される。すなわち本系統によって作動される弁等はフェイル・セイフとしている。 安全保護系を構成する機器は信頼性の高いものを使用するが、計測チャンネル等に多重性、独立性を持たせることにより原子炉運転中にも試験を行うことができ、残りのチャンネルで保護機能を果たせるように設計される。 以上のことから安全保護系は十分な信頼性を有していると判断する。 2.6.3 原子炉停止系
原子炉停止系は多重性を有し、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時において、炉心を臨界未満にできることが必要である。 このため審査に当たっては反応度停止余裕、後備停止装置及び制御棒落下時間について検討を加えた。 本原子炉停止系では制御棒が安全棒としての機能を兼備しているが、後備停止装置として制御棒とは原理の異なる炉心内空洞部落下設備及び制御液注入設備が設けられている。 炉心内空洞部落下設備は、空洞部を持つ装置を炉心中央部に挿入しておき、これを落下させ、炉心外へ引抜くことによって原子炉に負の反応度を添加する。また、制御液注入設備は高濃度のほう酸水溶液を炉心容器に注入することにより原子炉に負の反応度を加える設計である。 制御棒においては最も反応度効果の大きい制御棒1本が完全引抜位置のまま挿入できない場合でも2%Δk/k以上の反応度停止余裕を与える設計となっている。 制御棒が動作不能になった場合でも、炉心内空洞部落下設備の落下及び制御液注入設備によるほう酸注入によって原子炉を未臨界にできるので、原子炉停止系は多重性を持つものと考える。 スクラム時の制御棒挿入時間については全ストロークの90%挿入までを1秒以内としているが、この値は試作装置による落下試験によって十分満足することが確認されている。 以上のことから原子炉停止系の設計は妥当なものと判断する。 2.6.4 反応度制御系
反応度制御系は、キセノン濃度変化、燃焼等の反応度変化を調整するとともにその最大反応度価値及び添加率は想定される反応度事故に対し燃料等の損傷が生じないような設計であることが必要である。 このため審査に当たっては反応度制御系の健全性と制御能力及び可燃性毒物について検討を加えた。 制御棒は分割炉心ごとに6体を有すが、その構造はステンレス鋼管内に炭化ほう素のペレットを入れたものを断面が円弧状になるように並べて固定したものである。 制御材として使用する炭化ほう素は、ほう素の燃焼によりヘリウムを放出するので被覆管の設計にはガス圧を考慮する必要がある。設計では蓄積ヘリウムの圧力を100㎏/cm2Gとしているが、この場合、被覆管内外の温度差を加味した応力評価をしても、ステンレス鋼管の許容応力以下であることを確認した。 また、制御棒は、炉頂部より交換可能なように設計上の配慮がなされており、約2年間の運転日数で交換されるが、その時点での制御棒内に蓄積されるヘリウム圧力は、前述の設計圧力以下である。 なお、制御棒の流動試験、駆動機構の試作等を行い、制御棒の健全性を充分確認することになっている。 制御棒はすべての炉心構成において停止状態からの全出力までの反応度変化の調整を行うほか、キセノンの濃度変化、軽水及び重水の温度変化並びに燃料及び可燃性毒物の燃焼に伴う反応度変化の調整を行う設計となっているので、所要の運転状態は維持できるものと考える。 制御棒の反応度制御能力は0.7~2%Δk/kで、反応度印加速度も2本で約0.02%(Δk/k)/s以内に制限されている。制御棒の駆動は電磁石を用いて、電磁的結合により行われる。したがって、制御棒の上方への急激な引抜きの可能性は少ないものと考える。なお、制御棒挿入限界をシムレンジと称する1/3等価反応度に設定することにより、制御棒の挿入を制限しており、たとえ、急激な引抜き事故があったとしても過大な反応度が添加されないような設計である。 また、制御棒下部案内管にスリットを設けることにより制御棒の落下飛び出しを防ぐような設計となっている。 なお、本原子炉で使用される燃料は、超過反応度を抑え、高い燃焼度を得る等の目的で燃料要素の各側板に1グラム以下のほう素を入れる設計であるので、製作、検査方法、核特性等について検討を加え、問題のないことを確認した。 以上のことから反応度制御系の設計は妥当なものと判断する。 2.7 核燃料物質の取扱い及び貯蔵施設
核燃料取扱い及び貯蔵設備の設計においては以下に示す事項を満足することが必要である。 (1) 燃料貯蔵設備は適切な格納機能、貯蔵容量及び未臨界性を有すること。 (2) 核燃料取扱機器は試験・検査機能を有し、かつ燃料落下防止対策が講じられていること。 (3) 使用済燃料貯蔵設備は放射線遮蔽、プール水の冷却、浄化並びに漏洩防止及び検知機能を有し、燃料の取扱中の想定される落下時にも損傷しないこと。 (4) 核燃料の取扱場所は、残留熱の除去能力の喪失に至る状態及び過度の放射線レベルが検出できるとともに、その事態を適切に従事者に伝えるか、又は自動的に対処できること。 これらの事項を考慮して検討を行った結果は、次のとおりである。 新燃料及び使用済燃料貯蔵ラックは、所定の位置以外には燃料要素を挿入できない構造とされ、各ラックに1体ずつ適切に収納される。なお、内側燃料要素用ラックと外側燃料要素用ラックでは、燃料要素が相互に挿入されない構造となっている。 新燃料貯蔵設備の貯蔵能力は約12炉心分を収納できる設計である。使用済燃料については炉頂プール内燃料貯蔵設備で約8炉心分、使用済燃料プール燃料貯蔵設備では約12炉心分の貯蔵能力を有するように設計されるので、通常運転時には全炉心の燃料を貯蔵できる容量が常に確保され得るものと考える。 新燃料貯蔵設備は独立した建屋で鉄筋コンクリート造耐火構造とし入口には鉄製耐火扉を設ける。また、火災等で水が充満するのを防止するために排水口が設けられるが、容量一杯の新燃料を貯蔵した状態で、貯蔵室内が純水で満たされるという厳しい異常状態を想定しても実効増倍率は0.95以下に保たれるように設計されている。なお、新燃料貯蔵室には水消火設備を設置しないことになっている。 使用済燃料貯蔵ラックは、貯蔵燃料の臨界を防止するために適切な燃料要素間距離をとることにより、容量一杯の新燃料を貯蔵し常温の純水で満たされた場合を想定しても、実効増倍率は0.95以下に保たれるよう設計されている。 したがって新燃料貯蔵設備、炉頂プール内燃料貯蔵設備及び使用済燃料プール内貯蔵設備は予想される、いかなる状態においても臨界に達することはないものと判断する。 燃料取扱機器、炉頂プール浄化及び冷却設備等の安全上重要な機器は定期的な試験、検査が可能な設計となっている。炉頂プール及び使用済燃料プールは側面にはコンクリート壁による遮蔽が設けられ、使用済燃料の上部には十分な水深が確保されることから、燃料取扱い及び貯蔵時に適切な遮蔽効果を有するものと判断する。 使用済燃料の崩壊熱による炉頂プールの水温の上昇は、全貯蔵容量の燃料要素を貯蔵したとしても、炉頂プール冷却設備により充分低い温度に抑えることができる。 プール水の漏洩検知については、プール水位低下警報の他に炉頂プール下の点検スペース内にピットを設け、水位検知器による警報を出すことも考慮されている。なお、プール水排水管は開口部位置を高くし、仮にプール水が排出されても炉頂プール内に貯蔵されている使用済燃料の冠水が失われるようなことのないように配慮されている。 使用済燃料を取扱う炉頂プール及び使用済燃料プール付近には放射線監視のためのエリアモニタが設置され、放射線レベルが異常に上昇した場合には、制御室に警報を発し、運転員が対処できるようになっている。したがって、燃料取扱場所の放射線レベルの検出は適切に行えるものと考える。 なお、使用済燃料要素が万一、損傷を起こした場合には使用済燃料プールに隣接したホットケーブで検査などの取扱いができるようになっている。 以上のことから本設備は十分安全であり、所要の貯蔵能力を有しているものと判断する。 2.8 放射性廃棄物廃棄施設
2.8.1 気体廃棄物処理設備
気体廃棄物処理設備は、適切なろ過、貯留、管理等を行うことにより、周辺環境に放出される放射性物質の濃度及び量を実用可能な限り低減できる設計であることが必要である。 このため審査に当たっては気体廃棄物の発生量、換気設備の性能、放出管理及び人工空気供給設備について検討を加えた。 原子炉室の換気方式は第1種及び第2種管理区域では一部循環方式、特別管理区域では全換気方式をとっている。いずれの場合も排気はそれぞれの高性能粒子用フイルタを有する排気チェンバで処理してからKURの排気口のスタックを経て排出されるので、粒子状の放射性物質は十分除去できると考える。 また、一部循環方式の場合は循環系浄化用チェンバを通して粒子状の放射性物質は十分除去し、放射性物質濃度を監視しながら循環するので問題はないものと考える。 事故が発生して原子炉室内の放射性ガス濃度が、異常に上昇するおそれがある場合は気密ダンパが密閉され、原子炉室の空気は非常用排風機により活性炭フィルタを備えた非常用排気チェンバを通して処理され、非常排気用スタックから放出される。 非常排気用スタックは高中性子束炉専用であり、原子炉室側壁に沿って支持される。 原子炉室内で放射性アルゴンの発生源と考えられる区域にはアルゴンの含有量をあらかじめ0.03%以下に低減させた人工空気を供給できる設計になっている。また、それらの区域は区画し、出入口には気密扉を設けることにより可能な限り、密閉される。この場合、放射性アルゴンの発生量は普通の空気を使用する場合の約1/30となる。このように、周辺環境に放出される気体廃棄物の低減対策が施されている。 なお、人工空気は液化窒素、液化酸素及び液化炭酸ガスを蒸発、混合する人工空気供給設備により供給されるが、人工空気のガス成分比は混合後のガス分析及び貯留槽でのガス分析により、供給元で十分に管理されることになっている。 以上のことから気体廃棄物処理設備の設計及び処理方法は妥当なものと判断する。 2.8.2 液体廃棄物処理設備
液体廃棄物処理設備は適切な凝集沈殿ろ過、蒸発処理、イオン交換、貯留、減衰及び管理を行うことにより、周辺環境に放出される放射性物質の濃度及び量を実用可能な限り低減できる設計であることが必要である。 このため審査に当たっては液体廃棄物の発生量と処理能力、放出管理等について検討を加えた。 液体廃棄物処理設備は、放射性廃液の性状に応じて処理できるように貯留タンク、凝集沈殿ろ過処理装置、イオン交換処理装置及び蒸発濃縮処理装置がすでに設けられており、これらの設備の性能については実証済である。更に、弱放射性廃水については凝集沈殿処理の他に新設の蒸発濃縮処理装置で処理することができるので処理能力は強化されることになる。 個々の装置の処理容量については京都大学原子炉実験所での実績等を基に推定した廃液の発生予想量に対して、十分な処理能力を有しており、妥当なものと考える。 処理済の液体廃棄物はろ過器の逆洗水等廃棄物処理場内で再使用するか、放射性物質の濃度が十分低いことが確認されたもので排水口から排水する場合でも、更に、最終貯留槽に貯留してから所外に放出される。 このように、周辺環境へ放出される液体廃棄物の低減対策が施されている。 以上のことから、液体廃棄物処理設備の設計及び処理方法は妥当なものと判断する。 2.8.3 固体廃棄物処理設備及び貯蔵設備
固体廃棄物処理設備は遮蔽、遠隔操作等によって従事者等の被曝線量を十分低くするとともに、固体廃棄物の貯蔵による敷地周辺の空間線量率を実用可能な限り低減できる設計であることが必要である。 このため審査に当たっては、従事者等の被曝低減対策、固体廃棄物貯蔵庫の貯蔵及び遮蔽能力について検討を加えた。 固体廃棄物処理設備は減容等の操作に際し、作業者の被曝をできるだけ少なくするような設計となっている。 個体廃棄物貯蔵施設は増設を行い、200lドラム缶換算で合計2,000本の貯蔵能力を有することになる。これは放射性固体廃棄物の発生量をKURの実績等から推定すると、約8年分の貯蔵容量に相当する。 固体廃棄物貯蔵設備からの敷地周辺の直接線量及びスカイシャイン線量は、人の居住の可能性のある敷地境界外において、年間5mR以下となることを目標に遮蔽等が行われ管理されることになっている。 以上のことから個体廃棄物処理設備及び固体廃棄物貯蔵設備の設計は妥当なものと判断する。 2.9 放射線管理施設
2.9.1 放射線防護設備
放射線防護設備は、従事者等が立入場所において不必要な放射線被曝を受けないように作業性等を考慮して所要の措置を講じた設計であることが必要である。 このため審査に当たっては遮蔽能力、機器の配置、放射性物質の漏洩防止対策及び換気能力について検討を加えた。 遮蔽については原子炉本体遮蔽(ビーム実験室遮蔽を含む)、原子炉室コンクリート壁、燃料取扱設備遮蔽、一時的遮蔽等が設けられるので通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時において従事者等の被曝線量は低く抑えられると考える。 機器の配置に当たっては浄化系樹脂塔、高放射性物質を内蔵するタンク、1次冷却系配管等は原則として遮蔽壁により隔離をする設計である。 炉頂プール及び使用済燃料プールでの燃料操作時には、従事者の被曝を可能な限り少なくするために、操作はすべて水中で行われる。また、燃料の検査等の高放射性物質の取扱には十分な遮蔽能力を有するホットケーブが使用される。したがって、機器の配置については放射線レベル、操作方法等が考慮されている。 漏洩防止対策については、1次冷却材及び重水等の放射性物質濃度の高い流体が漏洩しないような構造設計がなされ、万一、漏洩が生じた場合でも早期発見が可能な箇所に検知器を設置し、更に汚染が拡大しないように機器の周辺には堰が設けられる。 換気設備は原子炉室、原子炉機器調整室、原子炉制御室等の各区域の換気に必要な容量を有し、作業環境の空気を清浄に保つことができる設計となっている。 なお、原子炉室内は空気汚染の拡大を防ぐため予想される汚染の種類又は汚染の可能性により2.8.1で述べたように区分して換気を行っており、また、各換気設備のフィルタは点検及び交換ができる設計となっている。 以上のことから放射線防護設備の設計は妥当なものと判断する。 2.9.2 放射線監視及び管理設備
放射線管理設備は従事者等を放射線被曝から防護するため、放射線被曝を十分に監視及び管理できるとともに、必要な情報を原子炉制御室又は適当な管理場所に通報できる設計であることが必要である。 また、敷地周辺の放射線を監視するため、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び事故時において原子炉室、放射性物質の放出経路、敷地周辺を適切にモニタリングできることが必要である。 これらの事項を考慮して検討を行った結果は次のとおりである。 放射線被曝の監視及び管理については管理区域を設定し、人の出入管理を行うとともに、これらの区域においては外部放射量及び空気中若しくは水中の放射性物質の濃度等を測定監視することとしている。 管理区域内への立入り及び物品の運出入を管理するための出入管理設備及び汚染管理設備が設けられるほか、施設モニタリング設備、プロセスモニタリング設備、放射線サーベイ設備及び個人管理関係設備が設けられる。 施設モニタリング設備は、原子炉施設等の空間線量率及び空気中の粒子状の放射性物質濃度を測定、監視し、また、プロセスモニタリング設備は主要系統の放射性物質濃度を測定、監視する。これらは保健物理管理室(中央管理室)及び原子炉制御室において指示記録され、異常時には警報を発する設計となっている。 敷地周辺の放射線監視については放出源の監視用として原子炉施設内にプロセスモニタリング設備が設けられる。すなわち、放射性物質の放出経路であるスタックでは排出される放射性物質濃度の監視を行うためにガス及びダストモニタ並びによう素及びトリチウムサンプラが設けられる。高中性子束炉からの排気はKURからの排気と合流する前に別に測定するような配慮がなされている。また、非常排気用スタックにおける放射性物質放出監視も前述のモニタ及びサンプラを用いて行われる。 液体廃棄物については液体廃棄物処理設備により処理された廃液が放射性物質の監視貯留槽に貯留され、放射性物質濃度を測定した後、排水される。また、排水ラインにある屋外の集合槽には連続監視の水モニタが設けられている。 野外監視用としては周辺監視区域境界付近の空間線量率を連続測定するためにモニタリングポストが数箇所設けられるほか、集積線量を測定するために、線量計が配置される。更に、環境試料の採取測定が定期的に行われる。 放射性物質の異常放出等があった場合にはモニタリングカーにより放射線測定を行うことになっている。これらにより放出放射性物質の周辺環境に及ぼす影響を監視できるものと考える。 以上のことから放射線監視及び管理設備の設計は妥当なものと判断する。 2.10 原子炉格納施設(原子炉室)
原子炉室の設計においては以下に示す事項を満足することが必要である。 (1) 原子炉室は想定される事故の場合にも所定の漏洩率を超えることなく従事者及び公衆の安全を確保すること。 (2) 原子炉室は定期的に漏洩率試験及び検査ができること。 (3) 原子炉室を貫通する配管系は隔離機能を有すこと。 これらの事項を考慮して検討を行った結果は次のとおりである。 原子炉室は鉄筋コンクリート造でその外壁及び屋根は鋼板張りにし、気密性を持たせる構造であり、水柱約50cmの内圧上昇及び低下に対し十分安全なように設計される。 なお、使用する鋼材は脆性遷移温度が最低気温に対して十分低いものが用いられることになっており、また、原子炉室の内圧を上昇させる事象も特にない。 原子炉室の空気漏洩率は水柱3cmの差圧のとき、常温で1日に原子炉室体積の約2%以下になるように設計されるが、この値はⅣ7に後述する災害評価の結果からみて妥当なものと判断する。 原子炉室は漏洩率試験ができるような設計であり、また、原子炉室を貫通する配管系の主要配管には炉室内、外に各1個の隔離弁を設け閉鎖できるように設計される。 更に、給排気口には炉室内側に隔離弁(ダンパー)を設け、事故時には閉鎖できるようになっている。 以上のことから、原子炉室は事故時にその健全性を保持し放射性物質の外部への放出を抑制する機能を有すものと判断する。 2.11 非常用電源設備及び実験設備
2.11.1 非常用電源設備
非常用電源設備は外部電源喪失時に1系統が作動しないと仮定しても燃料の許容設計限界を超えることなく炉心を冷却でき、1次冷却材喪失事故が同時に起ったと仮定しても炉心の冷却とともに安全上重要な系統及び機器の機能を確保できる容量と機能を有すことが必要である。 このため審査に当たっては非常用電源設備の多重性及び信頼性並びに無停電電源の信頼性について検討を加えた。 非常用電源設備としては非常用発電機、後備発電機が各1台、無停電電源(蓄電池)が1組設けられる。 非常用発電機からKUR及びKUCAにも給電するものとしている。その為、共用について検討を加えたが、2.1で述べたように給電ケーブルの一部損傷があっても支障なく各施設へ給電できるようにループ配電方式をとることとしているので、断線事故対策としては妥当なものと考える。 非常用発電機のバックアップとして高中性子束炉専用の後備発電機を設け、非常用冷却設備、非常用排気設備等に給電する設計となっているので、多重性を持つものと考える。 なお、非常用発電機が万一、作動しなかった場合のKUR及びKUCAの崩壊熱の除去は自然循環で十分可能である。 非常用電源設備は非常用がガスタービン、後備用がガソリンエンジンと駆動方式を異にしていること及び設置場所を異にしていること等から、同一原因による起動渋滞、起動不能の生じる可能性は少ないものと考える。 両発電機については定期的にその起動試験が行われ、信頼性が確保され、高中性子束炉専用である無停電電源についても定期的にその健全性が確認される。 更に、本原子炉施設は制御棒が電磁駆動方式であるため全動力電源喪失を想定した場合でも、制御棒の自重落下により原子炉を安全に停止できる。この場合、蓄電池(無停電電源)を電源とする非常用照明、原子炉核計装及びプロセス計装により、必要な監視を行うことができる。また、原子炉の崩壊熱除去は駆動電源を必要としない崩壊熱除去弁の開放により行うことができる。 以上のことから、非常用電源設備は安全上重要な系統及び機器が所定の機能を果たすのに十分な電力を供給できる能力を有するものと判断する。 2.11.2 実験照射設備
本施設の実験照射設備は大別すると実験照射孔、重照射設備及び重水熱中性子設備が設けられるが、設計においては以下に示す事項を満足することが必要である。 (1) 実験照射設備は原子炉の安全性を損なうことなく使用できるように設計すること。 (2) 反射体容器ノズルとの接合部は重水漏洩に対して万全を期し、万一漏洩した場合でも検出可能な構造とすること。 (3) 実験照射設備で発生する熱を安全に除去し得るように設計すること。 これらの事項を考慮して検討を行った結果は次のとおりである。 重照射設備はアルミニウム合金製カプセルに入れた試料を炉心容器の中心部で照射するために設けられるもので、カプセルの出し入れは炉心容器の蓋を開けて行い、照射試料の反応度の絶対値は、分割炉心あたり0.5%Δk/k以内とすることになっている。なお、KUCAで反応度及び中性子束の歪等の測定確認を行い、更に、発熱の解析を行ってから照射試料を挿入するので原子炉の安全性は、損なわれないものと考える。 実験照射孔については、それらの空隙部に重水又は軽水が漏洩し充満した場合の反応度上昇を2%Δk/k以内にするように設計される。 また、実験照射孔のフランジと反射体容器のノズルとの接合部は重水漏洩検知装置を設け、その健全性を確認することになっている。 実験孔内で発生する熱は、必要に応じて軽水又は重水等を循環させて除去するように設計される。 重水熱中性子設備は高速中性子やγ線混入の少ない熱中性子を大量に取出すための設備であり、反射体容器に外接して重水タンクを設ける方式である。この重水は反射体容器の重水とは独立した系統とし、実験設備重水冷却設備により冷却し、重水熱中性子設備の外側に遮蔽室を設ける設計であり、これらは妥当なものと考える。 なお、実験照射設備は原子炉の定格連続運転を行い、その特性を十分把握した後に使用されることになっている。 以上のことから実験照射設備の設計は妥当なものと判断する。 3 従事者の放射線防護及び被曝管理
従事者の放射線防護及び被曝管理は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び人事院規則「職員の放射線障害の防止」を遵守し、更に従事者の被曝線量を低減するように努めることが必要である。 放射線の防護は、基本的には外部放射線に対しては遮蔽により、空気汚染に対しては換気設備によりこれを無視できる程度に下げる方針で設計し運用することにより行われる。 このほか監視・点検、または操作を必要とする機器で高線量区域にあるものや、それ自体高放射能であるものについては遠隔化が図られ、また、トリチウムを含む重水系は漏洩防止対策が特に講じられることになっている。 作業時の被曝管理は、設備及び作業環境の管理を十分に行うと共に、各作業に当たっては作業担当者が予想される被曝線量を推定し、かつ、放射線管理者がそのチェックを行い、また、必要に応じて適切な防護具の着用等の被曝低減対策が施される。 従事者の被曝線量については、定期的にはフィルムバッチ等により外部被曝線量の評価を行い、体内摂取のおそれが生じた場合にはホールボディカウンタ等により内部被曝線量の評価が行われる。また、定期的に健康診断を実施し、従事者の身体の状態を把握することとしている。 以上のことから従事者の放射線防護及び被曝管理は妥当なものと判断する。 4 原子炉施設周辺の一般公衆の被曝線量評価
4.1 被曝線量評価の概要
一般公衆の被曝線量評価は、原子炉施設の平常運転時に環境へ放出される放射性物質の量を推定し、これらの放射性物質による一般公衆の被曝線量が現行法令に定める許容被曝線量を下まわること、更に、それができるだけ少なくなるように安全設計がなされていることを示すために行われる。 放射性物質の環境への放出量については、高中性子束炉における発生源から排気口又は排水口に至るまでの過程を解析して求め、さらに既設の原子炉施設からの寄与を加えている。 大気中に放出された放射性物質による被曝量は、敷地における1年間の気象資料を用いて算出された空気中の放射性物質濃度をもとに計算されている。なお、排水口から放出される放射性物質は、総量が少なく、人体への被曝は問題とならないので被曝評価上無視している。 4.2 大気中に放出される放射性物質の年間放出量
高中性子束炉の平常運転時に放出される放射性気体廃棄物は、主として、実験孔等の空気中に含まれるアルゴンが照射されて生ずる41Ar、反射体中の重水素が照射されて生ずる3H及び空気中あるいは、冷却水等の中の窒素や酸素が照射されて生ずる14Cが考えられ、これらに着目して評価している。燃料体中に生成される核分裂生成物は、1次冷却水中への漏洩の可能性が低く、かつ、燃料板の破損を検知した場合には燃料交換等を実施するので核分裂生成物による環境への影響は無視できる。一方、実験用核燃料物質を高中性子束炉で使用することを考慮してその影響については評価している。 また、既設のKURについては41Arの寄与を評価しているが、既設のKUCA及び放射性廃棄物処理施設からの放射性気体廃棄物は、先行炉の実績等から考えてもわずかなため被曝評価上無視している。 なお、放出量の算定に当たっては、41Arの発生量を減らすためにアルゴン含有量を低減した人工空気供給系を備え効果を期待できる場所には使用することにしており、その効果を見ている。 4.2.1 高中性子束炉による41Arの放出量
41Arの放出過程として、実験孔内等の中性子束が高い所で放射化されたアルゴンが原子炉室へ漏洩し、同室の換気とともに放出される場合及び1次冷却水が炉心通過中に水中の空気が放射化され炉頂プール水面からの拡散、ヘッダの排気、又は1次冷却系からの漏水によって換気系へ入る場合の2経路を想定している。 すなわち、前者については、ビーム実験孔、照射用孔、重水熱中性子設備等の着目個所や反射体容器と熱遮蔽層の間の空隙部等における平均熱中性子束を仮定し、その場所において飽和濃度に達した41Arが実験孔等の開閉や原子炉室の換気に応じて原子炉室内に漏洩するものとすると、放出量は年間約176Ciになる。また、後者については、炉心及び炉心容器内の平均熱中性子束を仮定し、1次冷却水が炉心を通過し、炉心容器内に滞在する間に飽和濃度に達した41Arが、冷却水の蒸発又は漏水とともに原子炉室内に広がるか、直接ヘッダから排気系へ出るものとすると、放出量は年間約24Ciになる。 以上、2経路の放出量は合計約200Ciとなるが、平均熱中性子束の見積り等の誤差を考慮して、被曝評価では安全率2をかけ放出量を年間約400Ciとしている。 4.2.2 KURによる41Arの放出量
最近5年間の放出量の実績をみると年平均約480Ciである。被曝評価に当たっては、この間の最大放出量である年間690CiをKURの放出量として用いている。 4.2.3 3Hの放出量
高中性子束炉の反射体中の重水素が放射化され、発生した3Hが重水系の漏洩とともに放出されるものと仮定すると、放出量は年間約90Ciとなる。さらに実験設備で使用される重水の漏洩や、LiFタイルの照射に伴い3Hが発生すると仮定しても年間約170Ciである。 4.2.4 14Cの放出量
高中性子束炉の反射体容器と熱遮蔽層間の空隙部あるいは1次冷却水中の空気の照射により発生した14Cが原子炉室内に漏洩し、放出されると仮定すると、放出量は年間約4Ciになる。 4.2.5 実験用核燃料物質による核分裂生成物の放出量
高中性子束炉の実験孔等で実験に用いる核燃料物質から放出される核分裂生成物は年間希ガス約1.34Ci(γ線実効エネルギ1.3MeV換算)、131I約7.1mCi、133I約34mCiになる。 以上、各放出量の算出については余裕が見込まれているので妥当なものと判断する。 4.3 排水中に放出される放射性物質の年間放出量
放射性廃水は、レベルに応じて容器保管ないしは、蒸発濃縮、イオン交換、凝集沈澱等の各種処理又は稀釈処理をして許容濃度以下にして排水口から放出される。 京都大学原子炉実験所全体の放出量は、過去の実績等から過大に評価しても10mCi(3Hを除く)、3H10Ciである。 4.4. 被曝線量の計算
4.4.1 気体廃棄物による全身被曝線量
周辺監視区域境界におけるγ線による外部被曝線量評価は、既設の排気筒(吹き上げ高さは無視する)から放出された前記の41Arの放出量について行っている。なお、核分裂生成物の放出量は41Arに比べ小さいため解析では無視している。それによると、被曝は排気筒の西南西方向約120mで最大となり、年間約1.0mremである。 4.4.2 気体廃棄物による甲状腺被曝線量
気体廃棄物中のよう素が呼吸、葉菜、牛乳の各被曝経路を介して摂取された場合の甲状腺被曝線量を評価すると、排気筒の東南東方向約280mの周辺監視区域内で最大となり幼児で年間約0.2mremである。 4.5 評価
前述の計算方法は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」(昭和51年9月)及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」(昭和52年6月)を参考に行われている。 このように計算された全身被曝線量は年間約1.0mrem、甲状腺被曝線量は年間約0.2mrem(幼児)であり、一般公衆の被曝線量を実用可能な限り少くするような安全設計がなされていると判断する。 なお、3Hによる全身の内部被曝線量は年間約0.03mrem(乳児)であり極めて小さい値である。 以上のほかに、原子炉施設からの直接線量及びスカイシャイン線量、β線による皮膚被曝線量等がある。直接線量及びスカイシャイン線量は、人の居住の可能性のある敷地外で年間5mR以下となることを目標に抑えられる。また、β線による皮膚被曝線量等については極めて小さい寄与しか与えない。 したがって、これらによる線量などを考慮しても周辺監視区域外における被曝線量は、現行法令に定める許容被曝線量(年間500mrem)を十分下まわっていると判断する。 5 運転時の異常な過渡変化の解析
運転時の異常な過渡変化とは、原子炉の運転状態において原子炉施設寿命期間中に予想される機器の単一故障又は誤動作あるいは運転員の単一誤操作によって、原子炉施設が通常運転状態から外れる場合をいう。 これらの原因となるものとしては
(1) 弁1個の誤開放又は誤閉止
(2) 単一の機器の誤始動又は誤停止
(3) 単一の制御機器の誤動作
(4) 単一の電気系故障
(5) 単一の運転員誤操作
が考えられるが、これらの原因により1次冷却材温度、1次冷却材流量、1次冷却系圧力、原子炉出力及び炉心応度に変動を生ずる。 このような運転時の異常な過渡変化時においても、原子炉の炉心及びこれに関連する1次冷却系、計測制御系及び安全保護系は燃料が許容設計限界を超えることなく、それぞれの機能を果たし得るような設計になっていることが必要である。 これらのプラント各系統の設計の妥当性を確認するため、以下に示す項目を具体的な判断基準として運転時の異常な過渡変化の解析の評価を行った。 (1) 燃料の健全性に対しては、
① 最小DNBRが1.5以上であること。 ② 燃料板最高温度が400℃以下であること。 (2) 1次冷却系の健全性に対しては、1次冷却圧力が最高使用圧力の1.1倍(9.9㎏/cm2G)を超えないこと。 以下に示す申請者の解析においては運転時の異常な過渡変化として、反応度の異常、1次及び2次冷却材流量喪失により1次冷却材温度に異常を生ずる過渡変化及びその他に分類し、それぞれに対して過渡変化の結果が厳しくなる事象及び条件を選定している。 なお、機器の設計の妥当性を評価するために運転時の異常な過渡変化の定義を超えて想定されている事象もこの中に含まれている。 これらの事象の選定は炉心への種々の影響を生ずる過渡変化を代表し、包含するものが選ばれていることから、妥当である判断する。 5.1 反応度の異常を生ずる過渡変化
反応度の異常を生ずる原因としては制御棒の移動、照射試料の炉心への挿入及び炉心温度の変化すなわち冷水の導入が考えられる。 5.1.1 未臨界状態からの制御棒引抜き
制御棒制御系又は制御棒駆動装置の誤動作により、制御棒が連続的に引抜かれると、急速に中性子束が上昇する。 解析では、制御棒引抜き前の原子炉は臨界に近い未臨界状態にあり、出力は1Wとしている。 この状態から、一度に引抜き可能な本数で最大である2本の制御棒が同時に炉心から連続して引抜かれるものとして、かつ、その2本の制御棒は最大の反応度を有するものと仮定する。 この場合、反応度添加率は評価上設計値の20%増の値である2.4×10-4(Δk/k)/sが用いられている。 解析の結果によれば、出力は約63秒後に12Wのスクラム設定点に達し、原子炉は自動停止されるが、この間、スクラム遅れ時間があるため、出力は13.3Wまで上昇した後、下降する。 この過渡期間中においても、燃料板最高温度、1次冷却材温度及び反射体温度はほとんど上昇しない。 5.1.2 出力運転中制御棒引抜き
前述の未臨界状態からの制御棒引抜きと同様な事態が出力運転中に生じた場合を仮定している。 本原子炉における出力運転中の冷却方式は、出力300kWまでを自然循環とし、300kWを超える場合を強制循環としている。 解析では、それぞれの冷却方式で最も条件の厳しくなる300kW及び30MWの2ケースについて評価を行っている。 反応度添加率としては最大の反応度効果を有する2本の制御棒が同時に引抜かれる場合として2.4×10-4(Δk/k)/s(前述と同様20%増の反応度)を仮定している。 解析の結果によれば、各出力の120%に設定したスクラム信号によって、それぞれ約3.7秒、約4.1秒後に原子炉は自動停止され、燃料板の温度上昇は抑制される。 過渡期間中の1次冷却材温度及び反射体温度の上昇は少なく、最小DNBRは厳しくなる30MWの場合でも2.9であり、燃料板の損傷は起こらず、また、燃料板最高温度は原子炉出力300kWの場合で約88℃であり、30MWの場合でも約138℃であるので、いずれも燃料板の健全性は損なわれない。 5.1.3 実験に伴う反応度印加
照射実験設備の中で、原子炉に対して反応度的に比較的大きな影響を与えるものとして、重照射設備への照射試料の急激な挿入取出しを想定した。 解析では、重照射設備への試料の出し入れにより、照射試料の制限値である反応度0.5%Δk/kがステップ状に印加されるものと仮定している。また、この時の原子炉状態は出力1Wで、臨界に近い未臨界状態にあるとしている。 解析の結果によれば、12Wで設定されているスクラム信号により制御棒が挿入されて、出力の上昇は抑制される。この間、スクラム遅れ時間があるため、出力は約3.7秒後に17Wに達した後、急速に減少する。 この過渡期間中の燃料板最高温度、1次冷却材温度及び反射体温度はほとんど変化しない。 5.1.4 冷水導入
出力が300kWで自然循環冷却による運転中に、誤って、弁の操作及びポンプの起動を行い、冷水を炉心部に導入のする状態を仮定した。その場合、減速材温度係数が負であるので正の反応度が添加され、出力が上昇する。 解析では冷水導入による温度差によって引起こされる反応度印加量は、本原子炉の核設計に使用されている値よりも厳しく見積って0.75%Δk/kとしている。 解析の結果によれば、出力は300kWから急激に上昇し、約0.03秒でスクラム設定点に達するが、スクラム遅れ時間があるので出力は約35.8MWまで上昇する。 この過渡期間中の最小DNBRは1.8であり燃料板の損傷は起こらず、また、燃料板最高温度は163℃であり燃料板の健全性は損なわれない。 5.2 1次冷却材の流量又は温度に異常を生ずる渡変化
1次冷却材の流量に異常を生ずる原因として、1次循環ポンプの故障及び電源の異常が考えられる。また、1次冷却材温度を炉心外から上昇させるものとして、2次冷却材流量喪失を仮定した。 5.2.1 1次冷却材流量喪失
原子炉の運転中に1次循環ポンプ全数が電源異常等により停止すると炉心の冷却能力が損なわれる。 解析では、最も厳しい場合として定格出力運転中に1次循環ポンプが4台全数停止し、1次冷却材の流量が喪失することを仮定している。 この場合、1次循環ポンプの電源異常によるスクラム信号が作動するが、厳しい結果を与える1次冷却材流量低の信号により原子炉は自動停止されるとしている。 解析の結果によれば、この過渡期間中の最小DNBRは2.1であり、また、燃料板の最高温度は約158℃であるので燃料板の健全性は損なわれない。 なお、炉心流量はポンプのコーストダウン特性に従って、減少するので、スクラムにより一度低下した燃料板温度は再び上昇するが、最大でも131℃程度である。 5.2.2 2次冷却材流量喪失
原子炉の運転中に、2次循環ポンプ全数が電源異常等により、停止すると、1次冷却材温度の上昇を引き起こす。 解析では、定格出力運転中に2次循環ポンプの全数が停止し、同時に主熱交換器内の2次冷却材流量が完全に喪失して、主熱交換器の冷却能力を失うという厳しい結果の出る条件を仮定している。 また、原子炉の停止は2次冷却材流量低のスクラム信号によるものと考えられるが、ここではより停止に時間を要する炉心容器出口平均温度が65℃に達した時の制御棒一斉挿入によるものとしている。 解析の結果によれば約48秒後に炉心容器出口平均温度が65℃の設定値に達し、制御棒一斉挿入が開始される。 この過渡期間中の最小DNBRは3.4であり、燃料板の温度上昇も低くその健全性は損なわれない。 5.3 その他の過渡変化
5.3.1 重水流量喪失
原子炉の運転中に反射材である重水の循環ポンプが電源異常等により停止すると、重水及び炉心容器の温度が上昇する。 解析では、定格出力運転中に重水循環ポンプの全数が停止し、同時に重水熱交換器は断熱状態になるという厳しい結果を与える条件を仮定している。 解析の結果によれば、重水循環ポンプの停止により約3秒後に重水流量最低の信号で原子炉はスクラムする。 この過渡期間中に炉心容器の温度は数度上昇するが、スクラムによる原子炉出力の低下に伴い下降する。また、反射体容器内では重水の対流による熱の放散が起こるので、重水の温度上昇は抑制される。 5.3.2 電源喪失
送電系統又は所内電気設備の故障等により所内機器の電力が喪失すると原子炉施設の運転状態が乱される。ここではこの最も厳しい状態として外部電源が喪失した場合を仮定している。 電源喪失に関しては、すでに前述した5.2.1 1次冷却材流量喪失5.2.2 2次冷却材流量喪失及び5.3.1 重水流量喪失の評価結果より厳しくなることはない。すなわち、これらの解析での原子炉停止は流量の低下によるスクラムや冷却水温度の上昇による制御棒挿入であり、電源喪失によるスクラムに比して、原子炉停止に、より時間を要するので、これらの評価の範囲内に入るものと考える。 5.4 評価
以上の検討結果から解析では種々の厳しい仮定においているにもかかわらず、本原子炉は原子炉が持つ自己制御性と種々の安全保護機能の動作とがあいまって、運転時の異常な過渡変化を安全に抑制し、燃料の健全性を保持することが確認された。 すなわち、最小DNBRは、最も厳しい過渡現象である原子炉運転中の冷却方式を、自然循環から強制循環へ誤って切替た時の冷水導入でも1.8であり、制限値の1.5を下回ることはない。 また、燃料板最高温度は最も厳しい過渡変化である冷水導入においても最高163℃であり、制限値である400℃を上回ることはない。 したがって、いかなる運転時の異常な過渡変化時においても燃料板の健全性は損われないものと判断する。 なお、1次冷却系については過圧状態になる過渡変化事象はなく、その健全性は損わなれないものと考える。 6. 事故解析
ここで想定する事故とは、運転時の異常な過渡変化を超える異常状態であって、現実に起こる可能性は極めて少ないが、装置の故障や操作上の過失等があった場合に技術的に起こると考えられる状態であって、この状態を想定することにより、安全防護施設の設計の妥当性を検討するためのものである。 事故の想定に当たっては、炉心に異常な反応度が加えられることによって生ずる反応度事故と、設備の故障、破損等によって生ずる冷却能力喪失事故等を評価して以下の代表的な事象を選び解析している。 (1) 原子炉出力が異常に上昇する事故として「燃料要素誤装荷事故」
(2) 1次冷却系保有水量の減少を生ずる事故として「1次冷却系主配管破断事故」
(3) 炉心内の1次冷却水流量の減少を生ずる事故として「炉心流路閉塞事故」及び「1次冷却水遮断弁誤動作事故」
(4) 1次冷却水中の放射性物質が2次冷却水中へ漏洩する事故として「主熱交換器伝熱管破損事故」
(5) 原子炉出力分布に異常をもたらす事故として「炉心容器二重管間隙部への漏水反応度事故」
(6) 重水中の放射性物質が原子炉室内へ漏洩し、あるいは原子炉出力に異常をもたらす事故として「重水漏洩事故」
これらを代表事故として選定したことは妥当なものと判断する。 なお、これらの事故は、以下の各項目でも述べるように、その発生の可能性が極めて小さくなるように十分な防止対策がとられることを確認した。 6.1 燃料要素誤装荷事故
炉心変更操作中に炉心部へ燃料要素を急激に挿入するか、あるいは誤って落とした場合、零出力状態から出力が急上昇し、燃料要素等に影響を与える可能性がある。 このような事故に対しては、炉心配置変更計画書に従い訓練を積んだ操作員が監視員の立合いのもとに燃料装荷を行うことで誤装荷を防止するとともに、十分な停止余裕を確保して装荷を行うので事故発生の可能性はきわめて少ないものと考える。 事故は、臨界近傍にあるにもかかわらず、外側燃料要素を外側装荷領域の最大反応度位置へ、燃料装荷中に吊具の故障により誤って落下させた場合を考える。事故解析に当たっては次の前提条件が用いられている。 (1) 誤装荷した燃料要素の持つ印加反応度は、装荷手順上外側燃料要素の最大値をとり1.83%Δk/kとする。投入時間は落下実験の結果を評価して0.6秒とする。 (2) 原子炉の初期状態は臨界に近い状態とし、実効増倍係数は0.991であるとする。また、出力は1Wで、線形出力計は10Wレンジを選択している。 (3) 誤装荷による反応度の印加により線形出力高、炉周期短による制御棒の一斉挿入及びスクラムがかかるが、これらは作動しないものとし、線形出力高(レンジの120%)でスクラムすると仮定する。 (4) 最大反応度を有する制御棒1本を除く全制御棒が、スクラム遅れ時間0.45秒、全駆動長を挿入する時間は1秒で挿入されるとする。抑制反応度曲線は厳しい側に評価した値を用いるものとする。 (5) ポイド係数及び温度係数はいずれもKUCAによって得た実験結果を評価して厳しい側の値を使用する。 なお、1次冷却水は、自然循環冷却(流速1cm/s)とし、燃料板温度、1次冷却水温度及び反射体温度は45℃とする。 解析の結果によると、原子炉出力12Wでスクラム信号が発せられるが、スクラム時間の遅れがあるため、約1秒後に約162MWに達し、燃料板最高温度は約141℃である。 一方、上記解析結果の妥当性を評価するためEUREKAコードを改良したコードを使用して別途チェック計算した結果からも上記解析は妥当であり、燃料の溶融には至らないと判断する。 6.2 1次冷却系主配管破断事故
原子炉運転中に1次冷却系配管に亀裂や破断が生ずると、1次冷却水が流出し、炉心冷却能力の低下から燃料温度の上昇を生ずる可能性が考えられる。 このような事故の発生を防止するために配管等の設計に当たっては原子炉の使用条件下の各種の応力を考慮し、材料の選定及び製作過程において十分な品質管理を行うことにしている。また、原子炉は低温、低圧で運転され定期的に主要個所の健全性を確認するための検査を行うので、発生の可能性は極めて低いと考える。更に、各種の漏洩検知器で、万一の漏水が検知された場合には、原子炉を速やかに停止させると同時に炉心の冷却水の喪失を防ぐ手段を講ずる。 事故は、原子炉出力運転中に1次冷却系主配管が破断した場合を想定し、解析に当たっては次の前提条件が用いられている。 (1) 原子炉は出力運転状態とし、出力は余裕をみて炉心部の出力で30MWとする。 (2) 1次冷却系破断による冷却水圧力降下から崩壊熱除去弁は内外差圧が0.2㎏/cm2以下になったとき開き始め3秒で全開になるものとする。 (3) 崩壊熱除去弁開により1次循環ポンプは停止する。 (4) 原子炉停止後の崩壊熱は、Shureの式により計算される値の1.2倍とする。 (5) 崩壊熱除去弁はプール水注水管注入側、戻り側各2個ある弁のそれぞれ1個が作動しないとする。 (6) 1次冷却水遮断弁は1次循環ポンプ停止後1分で全閉するものとする。 (7) 破断箇所は、事故の結果を厳しくする観点から、炉心容器の上部又は下部につながる1次系主配管の破断と高水位側炉頂プール内の1次系主配管の破断を想定する。その際、破断口面積は、1次系主配管断面積の0.18倍から2倍を考える。 解析の結果、燃料板最高温度はスクラム開始直後と炉心内冷却水の流れ方向が逆転する時の2つの時点でピークを示す。後者のピークは、炉心部圧力及び出力が低下しているので、サブクール核沸騰により約130℃程度に抑えられる。これに対し、前者のピークは、破断場所及び破断口の大きさに依存しており、炉心容器上部につながる1次系主配管の両端破断又は高水位側炉頂プール水中の1次系主配管の両端破断の場合、破断側炉心部で高い値を示し後者の値より厳しくなる。 スクラム直後の燃料板最高温度は、出力、炉心部流量及び圧力に影響されるため、解析では、熱流束が最大の際に、圧力が低下することなく流量は低下し、核沸騰が生じているという厳しい条件を仮定して評価している。 これによると燃料板最高温度は約237℃になり、また、この時の最小DNBRは約1.1である。 一方、本事故について別途、RELAP-4コードを用いてチェック計算した。これら両計算を比較検討した結果、上記解析は妥当であり、燃料は溶融には至らないと判断する。 6.3 炉心流路閉塞事故
原子炉運転中に炉心容器内に異物が入った場合、炉心内の流路を閉塞し、1次冷却水流量の減少により燃料板温度が上昇し燃料板の損傷に至る可能性が考えられる。 このような事故に対しては、1次冷却系配管にストレーナを取り付け、冷却水中の異物を取り除くようにしており、炉心変更操作時における炉心容器内点検や運転前の1次冷却設備の状態の点検により異常の有無を確認し、未然に防ぐことにしている。 また、完全な流路閉塞を防ぐため、燃料板上部に切り欠き等を設けることになっている。 事故は、何らかの原因により炉心内に異物(巾5㎜、長さ5cm)が入り流路を閉塞した場合を考え、事故解析に当たっては次の前提条件が用いられている。 (1) 異物は熱的に最も厳しくなる内側燃料要素の内側から2番目の流路を閉塞したとする。 (2) 閉塞された流路に面する燃料板面での熱除去は無視し、健全な流路に面する燃料板面での熱除去のみを考慮して燃料板温度を計算する。 (3) 原子炉の出力は余裕をみて炉心部のみの発熱を30MWとする。 解析の結果、燃料板温度は流路閉塞と同時に上昇を始め約195℃で平衡に達し、この時の最小DNBRは1.8である。 本事故について別途チェック計算をした結果からも上記解析は妥当であり、燃料の溶融には至らないと判断する。 6.4 主熱交換器伝熱管破損事故
主熱交換器の伝熱管にピンホール、亀裂等が生ずると1次冷却水中の放射性物質が2次冷却水中に漏洩し周辺環境へ出る可能性がある。 このような事故に対しては、熱交換器の2次側の圧力を1次側より高く保ち2次側へ冷却水が漏洩しないようにし、更に、万一漏洩が生じた場合でも主熱交換器の差圧及びヘッダ水位の異常並びに2次冷却水モニタにより検知し、2次冷却系を隔離するので、その可能性は少ない。 事故は何らかの原因で伝熱管に穴があき、1次冷却水が2次側へ漏洩した場合を考え、事故解析に当たっては次の前提条件が用いられている。 (1) 直径25㎜の伝熱管が破断して、差圧が維持されていなかったため1次側から2次側へ漏洩する。 (2) ヘッダ水位が零でスクラムし、1次循環ポンプが停止する。1次冷却水遮断弁はその後1分で閉鎖されると仮定する。 (3) 2次冷却系の隔離は2次循環ポンプ停止15分後に行われる。 (4) 1次冷却水中の放射能濃度は定格出力運転中の平衡放射能濃度を仮定する。 解析の結果、2次系へ放出される放射性物質は約110mCiであり、そのほとんどが短半減期の核種であるので、周辺環境への影響は無視できると判断する。 6.5 炉心容器二重管間隙部への漏水反応度事故
炉心容器の二重管間隙部へ反射体容器内の重水あるいは1次冷却水が入り、炉心へ反応度を印加することが考えられる。 炉心容器の設計、製作は安全上適切と認められる規格及び基準に従って行われ、十分な品質管理がなされること、並びに、間隙部への漏洩に備えて漏水検出器を設け、万一の漏水に対処すること等からこのような事故の発生の可能性は極めて低いと考えられる。 事故は、間隙部に重水あるいは軽水が満たされた場合を仮定する。事故解析に当たっては次の前提条件が用いられている。 (1) 二重管の間隙を3㎜とし、その間隙部の炉心上部迄重水又は軽水が満たされたとする。その場合、印加反応度はステップ状に入り、0.07%Δk/kとする。 (2) 原子炉は炉心部出力30MWで運転していたとし、線形出力高によりスクラムするとする。その以前に出る炉周期短による制御棒の一斉挿入、スクラム及び線形出力高による制御棒の一斉挿入は無視する。 (3) スクラム時間遅れは0.4秒とする。 この事故は次に述べる重水漏洩事故より反応度印加が小さいため燃料の溶融に至ることはないと判断する。 6.6 重水漏洩事故
反射体容器等の重水が原子炉室内へ漏洩して放射能汚染を引起す場合及び実験孔あるいは照射孔にピンホール等ができて重水が流入し、反応度印加によって原子炉出力が上昇する場合が考えられる。 反射体容器は、炉心容器と同様に設計、製作には万全を期し、かつ、実験孔や照射孔等の空隙部への漏水による反応度印加も考慮して設計するので、炉心へ過大な反応度を印加することはなく、万一、印加された場合にも炉周期短、線形出力高等のスクラム信号により原子炉を停止でき、また、反射体容器内の重水水位低でもスクラム信号により原子炉は停止する。 一方、重水が漏洩した場合、漏洩検知器により検知し、程度に応じて反射体容器内の重水を地下の重水貯蔵タンクへ移したり、炉室内床面上に流出した重水を重水排水槽に貯蔵することが可能である。 従って、重水漏洩が生ずる可能性は低く、生じても影響は小さいと判断するが、事故評価は、原子炉室内へ重水が流出した場合と、炉心に反応度が印加された場合について、次の前提条件を用いて行われている。 (i) 原子炉室内に漏洩する場合
(1) 反射体容器等の保有する射放射性物質の量は3Hの平衡濃度を考え、3H320,000Ciとする。 (2) 実験孔あるいは照射孔のひび割れによる重水漏洩が発生するが、重水ダンプ弁が開かず反射体容器内の重水の移し換えが不可能であるとする。 (3) 漏洩した重水のうち10lが回収されず、その中に含まれる3Hが炉室内へ蒸発すると仮定する。 (ii) 炉心に反応度を印加する場合
(1) 反応度印加が最大となる実験孔として集束型ビーム孔を選びこの実験孔に重水が30秒間で流入したとする。印加反応度はKUCAの実験結果をもとに2%Δk/kと仮定する。 (2) 原子炉は炉心部出力30MWで運転していたとし、線形出力高により、スクラムすると仮定する。その前に出る炉周期短による制御棒の一斉挿入、スクラム及び線形出力高の制御棒の一斉挿入は無視する。 (3) スクラムの時間遅れは0.4秒とする。 解析の結果は次のとおりである。 (i) 原子炉室内へ漏洩する場合
回収不可能な3Hが炉室内へ充満し、2%/日の放出率で周辺環境へ放出されたとすると、放射性物質の量は約156Ciで、周辺監視区域外での被曝線量は十分小さい。 (ii) 炉心に反応度を印加する場合
原子炉出力は約2.1秒後に約38MWまで上昇するが燃料板最高温度は約140℃、最小DNBRは2.8である。 以上解析により周辺環境への影響はほとんど問題とならず、かつ、燃料は溶融に至らないと判断する。 6.7 1次冷却水遮断弁誤動作事故
1次循環ポンプ運転中に1次冷却水遮断弁が故障等により閉鎖された場合、1次冷却系の圧力が上昇することが考えられる。 この事故に対しては、1次冷却水遮断弁は1次循環ポンプの運転中には閉じられないようにし、かつ、閉鎖に要する時間を長くとるように設計される。また、万一、1次冷却系の内圧が異常に上昇した場合に備え1次系主配管に薄板安全弁が設けられる。 事故は何らかの原因で1次冷却水遮断弁が定格出力運転中に閉となった場合を考え、事故解析に当たっては、次の前提条件が用いられている。 (1) 1次循環ポンプ運転中は1次冷却水遮断弁が閉とならないインターロックに故障があったとする。 (2) 1次冷却水遮断弁閉によるスクラムを無視する。 (3) 1次循環ポンプは1次冷却水遮断弁閉により停止し、原子炉は1次冷却水流量低によりスクラムするものとする。 (4)スクラム時間遅れは0.6秒とする。 解析の結果、1次循環ポンプは1次冷却水遮断弁が閉じ始めて約1秒後に停止して約2.3秒後に原子炉はスクラムする。1次冷却系の圧力は定格運転時の圧力を超えず、燃料板最高温度はスクラム直前に最高値約195℃に達し、また、最小DNBRは2.1である。従って燃料が溶融することはないと判断する。 6.8 評価
以上、各事故評価で述べたとおり厳しい事故をとりあげて評価しても燃料の溶融には至らない。また、周辺環境へ漏洩する放射性物質の量はわずかであり、周辺公衆に対する被曝の影響は無視できると判断する。 7 災害評価
7.1 災害評価の概要
災害評価は、「原子炉立地審査指針」に基づき重大事故及び仮想事故を想定し、これらの事故による被曝線量が、非居住区域、低人口地帯及び人口密集地帯に係るめやす線量を下回ることを示すために行われている。 重大事故及び仮想事故の種類については、核分裂生成物の大気中への放出量が大きくなるような事象として、燃料板が破損し内蔵されている核分裂生成物が原子炉室外に放出される事故が想定されている。 重大事故の解析は、核分裂生成物が燃料板から大気中に放出されるまでの過程について行われており、核分裂生成物の大気中への放出量は、厳しい評価となるような仮定を用いて解析されている。 仮想事故の解析は、重大事故の解析と同様に行われているが、核分裂生成物の大気中への放出量については、燃料板から放出される核分裂生成物の割合等が重大事故の場合に比べ、より大きくなるような仮定を用いて解析されている。 また、事故時における核分裂生成物は非常排気用スタックから放出されるが、厳しい評価となる地上放出として解析されている。 大気中に放出された核分裂生成物の大気拡散は、これらの事故が任意の時刻に起こるものとし、更に実効的な放出継続時間が短いことを考慮して、敷地における気象条件の出現頻度からみて、厳しい気象条件を用いて解析されている。 解析の対象とした核分裂生成物は、外部全身被曝に対しては、希ガスとし、また、甲状腺被曝に対しては、よう素としている。 なお、そのほかの核分裂生成物の放出量も算出されたが、被曝線量に与える寄与が小さいものとして線量計算上無視されている。 被曝線量は、放射性雲からのγ線による外部全身被曝線量及びよう素の吸入による内部甲状腺被曝線量がそれぞれ計算されている。 更に、仮想事故時においては、原子炉室内に充満したγ線源によるスカイシャイン線量及び直接線量についても計算されている。 7.2 重大事故の解析
7.2.1 重大事故
重大事故としては、技術的見地からみて最悪の場合には起こるかもしれないと考えられる重大な事故を想定する。すなわち、核分裂生成物の外部放出が最大になる可能性を持つ、燃料要素誤装荷事故及び炉心流路閉塞事故を想定する。 (1) 燃料要素誤装荷事故
燃料装荷時に炉心が臨界状態であるにもかかわらず、外側燃料要素を最大反応度1.83%Δk/kとなる位置に誤装荷するものとする。その時、燃料取扱器具の故障により、燃料要素は0.6秒で炉心に自由落下したものとする。 解析では、燃料板最高温度が400℃を超える部分では被覆が剥離し、その部分のウラン・アルミニウム合金内に蓄積された核分裂生成物のうち、ウラン・アルミニウム合金の両面から核分裂生成物の飛程に相当する深さまでに含まれる量が放出に寄与するものとする。 また、燃料板最高温度が550℃を超える部分では、その部分に蓄積される核分裂生成物の全量が放出に寄与するものとする。 以上の仮定に基づいて評価すると、燃料要素誤装荷事故による核分裂生成物の放出の寄与量は、炉心内蔵量の約9%となる。 (2) 炉心流路閉塞事故
原子炉の定格出力運転中に、炉心内異物により部分的流路閉塞が起こり、炉心内全燃料板588枚の内、5枚の燃料板に含まれる核分裂生成物の全量が放出に寄与するものとする。 以上の仮定に基づいて評価すると、炉心流路閉塞事故による核分裂生成物の放出の寄与量は、炉心内蔵量の約1%となる。 (3) 核分裂生成物の放出量
核分裂生成物の放出の寄与量は、(1)及ビ(2)で述べた重大事故の内、放出の寄与量が多い燃料要素誤装荷事故を考慮して9%とする。 以下、次の仮定を聴いて解析されている。 ① 事故発生の直前まで、原子炉は定格出力で十分長い時間(84日間)運転していたものとする。 ② ウラン・アルミニウム合金中から1次冷却水に放出される核分裂生成物は上記寄与量のうち、希ガスは100%、よう素は58%とする。 これらの値は、ORNLのG.W.Parkerらのウラン・ウルミニウム合金板状燃料に関する実験結果を採用している。 なお、よう素のうち、10%は有機よう素とする。 ③ 1次冷却水中から空気中への移行率は、希ガスは100%、よう素は1%とする。 ④ よう素が建家の壁面や配管などにプレートアウト及びフォールアウトする割合は50%とする。 ⑤ 燃料板の破損を破損燃料検出器あるいは排気ガスモニタの放射性物質濃度高などにより検知した場合、給気口及び排気口の気密ダンパを閉鎖し、通常排気設備の排風機を停止して、原子炉室内の気密を保つ。原子炉室内の空気は非常用排気設備により非常排気用スタックから放出されるが、ここでは、厳しい評価となる地上放出とする。また、放出率は設計値の50%増の3%/日とし、放出は無限時間続くものとする。 ⑥ 非常用排気設備は、活性炭フィルタなどを用いて、無機よう素は90%、有機よう素は50%の除去効率を有するものとする。 解析の結果、希ガス及びよう素の大気中への放出量は、希ガス約4,700Ci(0.5MeV換算値、以下同様)、よう素約7.2Ci(I-131換算値、以下同様)である。 被曝線量の計算は、上記の希ガス及びよう素の大気中への放出量をもとに、Ⅳ、1.4に述べた相対濃度(χ/Q)及び相対線量(D/Q)を用いて行われている。 よう素による甲状腺被曝線量は、χ/Qの値によう素の放出量を乗じて周辺監視区域境界の地表空気中濃度を求め、その濃度の空気を人が呼吸した場合の被曝線量をICRP勧告の計算方法によって計算している。 希ガスのγ線による外部全身被曝線量は、希ガスの放出量に周辺監視区域境界のD/Qの値を乗じて計算している。 この結果、重大事故による被曝線量は、周辺監視区域外で最大となる場所(非常排気用スタックから西方向240mの位置)において、よう素による幼児甲状腺被曝線量は約3.6rem、希ガスのγ線による外部全身被曝線量は約0.047remである。 7.3 仮想事故の解析
7.3.1 仮想事故
仮想事故は、重大事故を超えるような技術的見地からは起るとは考えられない事故を仮想する。すなわち、重大事故の際に想定した核分裂生成物の放出量を上回る同種の事故を仮想し、放出の寄与量として炉心に内蔵されている核分裂生成物の全量を考慮する。その他の解析条件は重大事故と同様とする。 解析の結果、希ガス及びよう素の大気中への放出量は、希ガス約52,600Ci、よう素約80Ciである。 被曝線量の計算は、重大事故の場合と同様に行われている。 この結果、仮想事故による被曝線量は、地上権設定区域を含む敷地境界外で最大となる場所(非常排気用スタックから西方向240mの位置)において、よう素による成人甲状腺被曝線量は約21rem、希ガスのγ線による外部全身被曝線量は約0.53remである。 また、スカイシャイン線量及び直接線量による外部全身被曝線量は原子炉室から東南東方向160mの位置で、それぞれ約1.9rem及び、約1.4remである。 7.3.2 全身被曝線量の積算値
国民遺伝線量の見地からみた全身被曝線量の積算値は、仮想事故として、炉心に内蔵する核分裂生成物の全属が放出に寄与する事故について、次の仮定を用いて解析されている。 (1) 大気中に放出される核分裂生成物の量は7.3.1に述べた解析結果を用いる。 (2) 拡散条件は風速1.5m/s、大気安定度F型、水平方向拡散幅30°とする。 (3) 拡散方向は最も人口の多い北北東方向を中心とする。 (4) 人口は、1975年の人口のほか、「地域人口の将来展望」及び「第3次全国総合開発計画」等に示された資料により求めた2000年の推定人口を用いる。 以上の仮定に基づいて計算された全身被曝線量の積算値は、1975年の人口に対して約14,700人・rem、2000年の人口に対して約22,400人・remである。 7.4 評価
重大事故及び仮想事故の解析は「原子炉立地審査指針」に基づき、立地条件の適否をみるため、核分裂生成物の大気中への放出に着目して行われたものである。 核分裂生成物の大気中への放出量の解析は、重大事故及び仮想事故の趣旨に照らして、それぞれ評価結果が十分厳しくなるような仮定を用いて行われており妥当なものと判断する。 また、以上の仮定に基づいて解析された核分裂生成物の大気中への放出量と、厳しい気象条件を用いて計算された甲状腺及び全身の被曝線量並びに全身被曝線量の積算値は、「原子炉立地審査指針を適用する際に必要な暫定的な判断のめやす」に示されるめやす線量を十分下回っているので、本原子炉施設の立地条件は、「原子炉立地審査指針」に十分適合しているものと判断する。 8 技術的能力
申請者である京都大学は、昭和39年にKUR、昭和49年にはKUCAを完成させ、これらによる共同研究等を実施して豊富な運転、実験操作の実績を有している。 京都大学原子炉実験所では、技術室が中心となって原子炉施設の運転・管理に当たり、原子炉研究部門の他に15の研究部門がこれに協力する体制となっているが、各部門には原子炉物理、原子炉工学、放射線管理、放射性廃棄物処理等の原子力関係分野に深い知識、経験を持つ研究者、技術者等を擁している。 また、法令上必要な原子炉主任技術者等についても、所内には原子炉主任技術者免状を有する者7名、核燃料取扱主任者免状を有する者4名、放射線取扱主任者免状を有する者40名がおり、十分に確保されている。 本高中性子束炉HFRの増設計画については、学内外から有識者の参加を求めHFR専門研究会、HFR計画調査研究会等を設けて検討を重ねてきたものであるが、更に本原子炉の建設に当たっては、全所内の人材を集めて建設本部を設置し、建設を推進することとしている。 また、本原子炉の完成時には、所組織を改正して原子炉施設の運転管理面における充実を図ると共に、その運転管理を担当する職員に対しては、既設の等KUR等を用いて十分な教育と訓練を行うこととしている。 Ⅴ 審査経過 本審査会は、昭和51年10月18日第152回審査会において、次の委員からなる第127部会を設置した。 (審査委員)
(調査委員)
同部会は、昭和51年11月5日に第1回部会を開催し、審査方針を検討するとともに、主として原子炉施設を担当するAグループ、主として環境、地質、地盤を担当するBグループを設け審査を開始した。 以後、部会及び審査会において審査を行ってきたが、昭和53年8月18日の部会において、部会報告書を決定し、本審査会はこれを受け、昭和53年8月23日第173回審査会において本報告書を決定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||
 夫
夫