| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
我が国における使用済燃料の海上輸送に係る安全性について(報告) 昭和53年9月21日
核燃料安全専門審査会
原子力委員会
委員長 熊谷太三郎殿
核燃料安全専門審査会
会長 山本 寛
本審査会は、核燃料物質等の輸送の安全対策に関し昭和51年7月から鋭意調査審議を進めてきたが、このほど別紙のとおり報告書をとりまとめたので、報告する。 (別紙)
我が国における使用済燃料の海上輸送に係る安全性について
Ⅰ 序 核燃料サイクル活動の一部を占める使用済燃料の輸送の安全性を確保することは、重要な課題である。我が国では、動力炉・核燃料開発事業団東海事業所再処理工場で再処理するため、使用済燃料の輸送が本格的に行われる見通しであり、地理的特殊条件から海上輸送に大幅に頼らぜるを得ないことが予想されていた。 このため、昭和48年以来、原子力委員会、科学技術庁及び運輸省は、通常輸送時の安全性はもとより使用済燃料専門運搬船の沈没防止策及び万が一沈没した場合の輸送容器(以下「キャスク」という)の海中における安全性評価等を内容とする使用済燃料の輸送時の安全性を確認するため以下のような4項目の輸送の安全性の評価、対策及びそれに必要な調査研究を多面的、かつ並行的に推進してきた。 (1) 使用済燃料専門運搬船の基準の策定
(2) 使用済燃料用キャスクの安全性に関する調査研究等
イ. キャスクの耐圧強度、浸水挙動、腐食等の海没時のキャスクの安全性評価、キャスク海没時の一般公衆の被ばく線量評価
ロ. キャスクの海没時の被壊防止のための圧力平衡弁の開発研究
(3) 海上輸送事故の実態調査
(4) 「放射性物質等の輸送に関する安全基準」(昭和50年1月原子力委員会決定)に基づく科学技術庁及び運輸省による輸送関係法令の整備(昭和53年1月1日施行)及びその運用
イ. キャスクの設計審査、キャスクの登録制度、輸送物の確認制度
ロ. 使用済燃料専門運搬船の構造基準に基づく審査、使用済燃料の輸送の安全確認制度
一方、昭和51年4月に発足した原子力委員会核燃料安全専門審査会においては、同年5月より核燃料物質の輸送に関する安全対策の調査審議を同審査会輸送部会において行うことを決定し、同年7月、同部会は、近い将来において使用済燃料の国内原子力発電所から再処理工場への海上輸送が始まり、またその輸送の機会の増加も予測されたので、使用済燃料の海上輸送に係る安全性について調査検討を開始した。さらに昭和52年6月本審査会は、核燃料物質の輸送に係る各輸送形態毎の調査検討事項を「核燃料物質の輸送の安全対策について」(経過報告)としてまとめ、原子力委員会に報告した。その中で
(1) 核燃料物質の各輸送モードに関する実態調査及び将来予測
(2) 輸送の環境影響評価
(3) 交通事故モードと確率の調査
(4) 仮想事故時の安全評価
(5) 緊急時対応プログラムの調査
(6) 緊急時協力体制の検討
(7) 輸送物に関する試験研究の実施
について逐次検討してゆくこととした。 本審査会は、使用済燃料の海上輸送の安全性についてはその後引きつづき調査検討を進め、本報告書をまとめるにいたった。本報告書において、使用済燃料の海上輸送に関して、先ずキャスクの海没時の安全評価結果を示し、さらに海没時のキャスクの安全性に関する圧力平衡弁に関する試験研究の評価結果、海上輸送の安全対策、海上輸送に関する法制の整備について述べ、最後に海上輸送に係る安全性について総合的に評価を行う。 Ⅱ 我が国における使用済燃料海上輸送の安全評価 1 安全評価の概要及び考え方
使用済燃料海上輸送の安全評価については、使用済燃料専用運搬船「日の浦丸」(総トン数約1,280トン)による国内の海上輸送について①輸送の実態、事故モード及び沈没確率の調査、②キャスク海没時の海水中への放射性物質漏洩挙動及び濃度予測と安全評価を行った。 調査については、まず輸送時に遭遇する各種の事故に対し、専用運搬船の構造、設備とキャスク性能から、キャスク及び専用運搬船の安全がどのように確保されているかを明らかにし、次に船舶の衝突事故について海難統計等の資料に基づき調査を行い、船舶沈没確率を明らかにした。 ついで放射性物質漏洩挙動及び安全評価については、我が国で当面使用されるキャスタ及びそれに収納する燃料体を想定し、キャスクが海没した場合のキャスク及び燃料体の水圧による破損挙動、ならびに腐食挙動を解析し、放射性物質漏洩のメカニズムを設定した。さらにキャスクから漏洩する放射性物質の海洋拡散モデルを設定し、海水中の放射能濃度を予測し、これより公衆の被ばく線量の評価を行った。 上述の調査、解析を進めるにあたっては、多数の条条設定を必要としたが、既に知見があり成熟している事項については、合理的な条件設定を行い、従来必ずしも解明されていない事項については、厳しい条件を設定して評価を行った。 2 海上輸送の事故及びサルベージ技術の調査
(1) 海難事故調査
船舶の海難事故には、衝突、座礁、火災、機関故障等が考えられるが、専用運搬船の輸送実態及び想定事故モードの調査から、専用運搬船は、いずれの二区画に同時に浸水しても十分な浮揚性、復原性が確保されていること、座礁及びT-2タンカーとの衝突からキャスクを防護するための耐座礁及び耐衝突構造が施されていること、キャスク船倉に非常漲水装置が施されていること、十分な安全運航対策が図られていることなどにより、キャスク及び専用運搬船の各種事故時の安全性は十分確保されているものと判断される。 しかしながら、国内における使用済燃料の海上輸送の安全性の評価に万全を期するためには、キャスクの耐圧性能の研究と並行してその海没確率及び影響を検討評価しておくことが適当であると判断されたので、専用運搬船と同規模の一般船舶で最も多く発生している海難事故(衝突事故)調査を行いこの結果に基づき安定対策の施された専用運搬船の沈没確率の推定を試みた。 海難事故調査にあたっては、距岸5~10海里を変針点とする直線の航路を専用運搬船の輸送区間上に設定し、この航路における船舶の交通量、沖合方向の船舶分布などを船舶統計により調査し、衝突事故を種類別、トン数別に海難統計資料に基づいて整理し、後述の(2)に示す沈没確率を推定するうえでの根拠を導いた。 (2) 沈没確率
沈没は、専用運搬船の航路における船船行会い時の衝突確率、衝突船が総トン数1,000トン以上である確率、衝突により船舶に破口のできる確率及び生じた破口により沈没の起こる確率の総合結果として起こるものと仮定した。 専用運搬船は、機関室を含む全ての区画に対し、二区画可浸性を満足する船体配置となっているので上述の仮定のもとでは破口による沈没確率が殆んど零となることが明らかである。 このため専用運搬船と船体主要寸法がほぼ同一で、かつ、二区画可浸性についても機関室を除き同等の条件にある一般船舶について沈没確率を求めた。 沈没確率を求めるにあたっては、前述の(1)の調査を専用運搬船の航行距離の比較的長い若狭湾地区から東海地区までの輸送を例にとり、津軽海峡経由の北廻りと大隅海峡経由の南廻りについて実施した。 これらの結果、航行距離が長くかつ船舶行会い回数の多い距岸5海里の南廻りを年間10航海すると仮定しても、この種の船舶の沈没確率は、たかだか7.6×10-7回/年である。したがって耐衝突防護構造をもち、かつ全ての船倉及び機関室に対し二区画可浸性を満足している専用運搬船についての沈没確率は、これよりも十分小さくなるものと推定できる。 (3) サルベージ技術
現在の国内のサルベージ技術では、水深200m程度までは我が国が現有している作業船、機材によってサルベージ作業が可能であるが、200m以上の水深になると、作業船、ウインチ、ワイヤー等の機材を特別に製作する必要があるとの調査結果が得られている。(万が一船が200m以深に沈没した場合でも後述のように相当期間、放射性物質の漏洩はないので、今後の技術進歩を待てば更に深い水深からのサルベージが期待される。)
3 キャスク海没想定時の環境影響評価
(1) 放射性物質漏洩のメカニズム
万が一キャスクが海没した場合においては、可能な範囲でキャスクを回収して放射性物質の漏洩による環境への影響を未然に防止することを原則と考える。技術的には、前述のとおり水深200m程度まではサルベージが可能である。 キャスクが海没した場合の放射性物質のキャスクからの漏洩は、キャスク及び燃料体の損傷が水圧及び腐食により生じた結果起こると考えられるので、キャスク及び燃料体の水圧並びに腐食による影響を調べた。 イ キャスク及び燃料体の水圧による影響
水圧によるキャスクの変形を調べるため、我が国で使用される代表的なキャスクについて弾塑性解析を行った結果、キャスクの変形は約2,300mから顕著となるが、約3,000mまでは、燃料体に影響を及ぼすキャスクの変形はなく、直ちに放射性物質の漏洩は起こらない。また水圧による燃料体の変形について理論解析を行った結果、燃料体は5,000m程度の水深に耐えることが明らかになった。 調査結果によれば国内海上輸送においては、専用運搬船の航路の水深は、最大2,700mであるので万が一キャスクが海没しても、キャスク及び燃料体から瞬時に放射性物質が漏洩することはない。 なお、国内輸送航路において、北廻りについては水深2,000m以深はなく、南廻りについては水深2,000m以深は全航路の1.6%を占めるにすぎない。 ロ キャスク及び燃料体の腐食
キャスク外胴部分は厚い鉄(ステンレス鋼、炭素鋼)で作られており、腐食に対して十分の寿命をもっているが、キャスクの蓋と本体の密封性保持のためのパッキングと蓋面及び本体フランジ面との間に部分腐食、いわゆる隙間腐食が生ずることが実験結果により明らかとなっており、腐食率より推定すれば、20数年で密封性が失われる可能性があるとの解析結果が得られている。 燃料体の被覆管には、ジルコニウムに少量の錫等の元素が添加されたジルカロイ-2又はジルカロイ-4が用いられており、被覆管の腐食についてジルコニウムの腐食に関するデータを用いると、被覆管は、数百年程度の耐食性をもっと推定される。 ハ 放射性物質漏洩モデル
以上の結果に基づけ、放射性物質の漏洩のモードをキャスクの海没水深をパラメータとして設定し次のとおり分類した。 (i) 水深200m以浅については、キャスクの変形による放射性物質の漏洩はなく、キャスクの部分腐食による放射性物質の漏洩が始まる前にサルベージが可能である。(ii)水深200m~2,300mについては、キャスクの変形による放射性物質の漏洩はなく、キャスクの部分腐食によりキャスクの密封性が破れて放射性物質の漏洩は徐々に進行する。(iii)水深2,300m以深についても上記(ii)と同じであるがキャスクの変形は、(ii)よりも著しくなる。 公衆被ばく線量を評価するため、上記放射性物質漏洩のモードより次の2つのケースの放射性物質漏洩モデルを設定した。 ケース1については、キャスクが水深200mに海没し腐食により密封性が破れて放射性物質の漏洩が起こるとする。放射性物質の海水中への漏洩は、使用済燃料ペレットは、実際には燃料被覆管に保護されているが、被覆管はないものとし、キャスクからの放射性物質の漏洩は実際に徐々に起こると考えられるが、キャスクもないものとし、燃料破覆管及びキャスクによる放射性物質の閉じ込めの効果を無視し、全燃料ペレットから滲出(リーチング)により起こるものとした。 ケース2については、キャスクの変形が著しくなるものは水深約2,300mであるが厳しい条件設定として水深2,000mで放射性物質が瞬時にキャスクから海水中へ漏洩するものとした。 (2) 公衆被ばく線量の評価
放射性物質の海水中への漏洩による、公衆被ばく線量を評価するにあたっては、前述の2ケースについて次のような条件のもとに評価を行った。 まずキャスク1体に収納される使用済燃料については、軽水型原子炉で約3~4年間燃料し燃焼度約33,000MWD/MTU、ウラン量約3.2トンとし、専用運搬船には、キャスク4体が積載されるものとした。 放射能濃度とその時間的推移の予測については、水深200m及び2,000mを評価する深度とし、海水の流動特性を考慮した3次元海洋拡散モデルを設定して計算を行った。予測した放射能濃度のうち最も高くなる時点を含む1年間の放射能濃度の平均値を用い海産物摂取に起因する内部被ばく線量について算定するとともに砂浜への放射性物質の蓄積に起因する外部被ばく線量も評価した。 内部被ばく線量については、海産物の摂取量、濃縮係数等は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針(昭和51年9月、原子力委員会)」に示されている数値を用いて算出した。その結果ケース1の場合個人被ばく線量は、全身に対して9mrem/y、骨に対して90mrem/yであり、ケース2の場合、全身に対して4mrem/y、骨に対して40mrem/yである。 外部被ばく線量については、砂浜における海浜作業、汐干狩等の実態調査データに基づいて算出した。その結果、ケース1の場合3mrem/yであり、ケース2の場合2mrem/yである。 なお、我が国以外では米国エネルギー省)DOE)の契約研究として米国バッテル研究所においてもキャスク海没時において放射性物質の漏洩による公衆被ばく線量が計算されている。我が国と同等の使用済燃料がキャスクに収納されている場合を推定して、我が国の計算結果と比較すると、計算手法の基本的考え方は同じであるが、我が国の計算条件が十分厳しい条件をとっているので、公衆被ばく線量は、我が国の方が高めの値となっている。 4 評価結果
我が国における使用済燃料専用運搬船の航路における船舶の海難統計調査結果に基づく検討結果によると専用運搬船の沈没確率は小さい。さらに専用運搬船の航路における水路調査、サルベージ技術、キャスク及び燃料体への水圧及び腐食の影響等を総合的に検討した結果、万が一キャスクが海没しても放射性物質が瞬時に海水中へ漏洩することはない。 放射性物質漏洩モデルをキャスクが水深200m及び2,000mに海没した場合の2ケースについて設定し、公衆被ばく線量を評価した結果、個人被ばく線量は全身で200mの場合12mrem/y、2,000mの場合6mrem/yであり、国際放射線防護委員会(ICRP)の平常時の公衆に対する許容被ばく線量に比べていずれも十分低い値である。 平常時における専用運搬船の一般乗組員の被ばく線量についても、乗組員の勤務時間、勤務態様等を考慮して評価した結果、ICRPの平常時の公衆に対する許容被ばく線量に比べて十分低い値である。 なお、分析用試料、研究炉用等比較的少量の使用済燃料を一般船によって輸送する場合のキャスクの海没時の公衆被ばく線量は、今回対象としている大型キャスクに比べて放射能量は少ないので上記の値に比べて十分低い。 Ⅲ キャスク用圧力平衡弁の研究開発 1 キャスク用圧力平衡弁の試作研究及び性能試験
キャスクが海没した場合の安全性の調査試験研究の一つとして実施した圧力平衡弁に関する試験研究は、キャスクが海没した場合、キャスクの内圧を海水圧と同等の圧力にすることにより容器の圧潰を防止し同時に一定差圧により閉止し内容物の流出を防止するためのものである。 この圧力平衡弁は、我が国が世界に先立って軽水炉使用済燃料輸送用の80トン級キャスク装備用として試作研究したものである。圧力平衡弁は、8.7m/secの海中落下速度において必要流量300l/min、作動圧10㎏/cm2の仕様で試作された。 平衡弁試験体は、水深5,000m(~500㎏/cm2に相当)までの性能について耐圧水槽を用いて弁の作動、流量、閉止性能について試験を行い、上記試験に加えて輸送中の振動、衝撃、熱を考慮した試験を行った結果、作動、流量、閉止性能については、500㎏/cm2までの外圧に対し十分な性能を示すことがわかった。振動試験は、船舶輸送時に想定される周波数の繰返し振動を与えているが、問題は生じない。衝撃試験は、キャスクが技術基準である9m落下相当の衝撃力を受けた場合の圧力平衡弁への影響について解析により検討を行い問題はない。熱試験は、同じく技術基準である800℃30分間の加熱試験を行っているが、平衡弁に対する熱しゃへいのための防護板を付加させることにより熱しゃへいを十分行うことができるので問題ない。 2 今後の問題
現在実用に供されている使用済燃料用キャスクは、解析によれば水深約2,300mに海没するとキャスクの変形が顕著となるものがあるが、この変形は3,000mに至っても燃料体に影響を及ぼすものではないので瞬時の放射性物質の漏洩及び臨界の問題は生じない。したがって現状では国内海上輸送においては、圧力平衡弁の装備は必要ないと考えられる。 しかしながら今後キャスクの種類によっては変形が燃料体へ影響を与えることも考えられるので、このようなキャスクに対しては、変形防止の観点から圧力平衡弁のキャスクへの装備は、有効な手段と考えられる。 キャスク用圧力平衡弁については、上記のとおり、昭和51年からの研究開発により平衡弁自体の実用の見通しがついているので、今後はその装備すべきキャスクと一体化した形で実用化が図られてゆくことが期待される。 Ⅳ 海上輸送の安全対策 国内再処理工場への使用済燃料の輸送については、陸上輸送と海上輸送の方法があるが、橋梁の強度、道路巾、発電所立地点が沿岸であること等の事由から、我が国では海上輸送が主に考えられる傾向にあり、現在使用済燃料を専用に輸送する「日の浦丸」が、昭和53年1月より運航に従事している。 本船は、Ⅴ2において述べる使用済燃料専用運搬船の安全基準に十分適合するよう改造されたものであり、かつ、安全運航の面からもきめ細い対策が図られている。 これらの審査検討にあたっては、学識経験者から構成された「使用済燃料の船舶運送に関する検討会」(運輸省船舶局)の意見を聴しつつ行ったものである。 本船に関する安全対策の概要は以下各項のとおりである。 1 船体構造、設備の安全強化
(1) 船体構造の強化
本船は、船体構造を極力不沈性のものにすることに主眼をおき、衝突及び座礁からキャスクを保護するために船体を二重船殻構造及び耐衝突・座礁構造としており、かつ、隔壁をはさむいずれの二区画に同時に浸水しても十分な浮揚性、復原性が確保されるような船体構造配置となっている。 (2) 安全設備の強化
本船は、使用済燃料を専ら輸送する船舶であり、したがって他の貨物が積載されていないため、一般貨物船に比べて、船倉火災の危険性は殆んど考えられないが、万が一、火災が起こった場合でも、キャスクが直ちに放水によって保護されるよう船倉内非常漲水装置が設けられている。 また、沿岸区域を航行するこのクラスの船舶に通常設置される各種航海設備のほか、本船の航行安全を更に高めるために、予備のレーダー、エコーサウンダー、航跡自画装置が設けられている。 なお事故時においても安全設備の機能が確保されるよう主電源装置のほか非常電源装置を設置し、非常漲水装置、通信設備、航海灯などの電源の二重化を図っている。 2 安全運航対策
(1) 安全運航管理体制の整備
イ 運航マニュアルの整備
危険物の船舶輸送にあたっては、輸送されるものの性状、荷役作業の方法、災害発生時の措置を記載したマニュアルが整備され、船長がこれを乗組員に周知徹底させることが義務づけられているが、本船についても具体的かつ詳細な運航マニュアルが整備されている。 ロ 運航管理、連絡体制の整備
航行の安全及び事故防止のため、総括的な管理者として運航管理者を配置し、運航業務を適正に処理させている。 また、連絡体制を整備し、本船の動静を定時に連絡させることにしているほか、入出港に際しては原則としてタグボートの使用、パイロットの乗船、港湾管理責任者等陸上関係機関との十分な協議等によりその安全を図っている。 ハ 保安管理者の乗船
使用済燃料輸送物を積卸する荷役作業中及び積載された輸送物の輸送中における状態監視及び船内放射線管理に必要な措置につき、船長を補佐し、その専門的職務を逐行する保安管理者を乗船させ、運航業務の安全を図っている。 (2) 乗組員に対する放射線被ばく防止
キャスクが積載される船倉以外の区域において、乗組員が一般船舶と同様、特別の制約なしに船内活動ができ、かつ、本船に通年乗船した場合においても、公衆に対するICRPに示す許容被ばく線量を十分下まわるよう遮へい構造が施されている。 また、キャスクが積載される船倉の周辺には立入制限区域を設け、関係者以外の者の入域が制限されている。更に船内の各所に放射線モニターが設置され、放射線量率が常時チエックされることになっているほか、立入制限区域の入域者に対してはポケット線量計等により被ばく線量が確認されることとなっている。 なお、船員等に対するこれらの記録は、保安管理者によって定期的に検閲され、放射線被ばく管理体制に万全を期している。 (3) 輸送物等の安全確認及び積付検査の実施
使用済燃料の船舶輸送にあたっては、当該輸送物が安全に作成されているか否か及び当該輸送計画が適当か否かにつき、法令に基づき当該輸送の都度、運諭大臣の安全確認を事前に受けることとなっている。 更に、実際の船舶への積付にあたっては、当該輸送物が確実に固縛されているか否か等、その積載方法につき検査が実施されることとなっている。 3 緊急時対策
(1) 非常設備
キャスクはその基準に従って衝撃等の試験条件を満足し安全性が確認されたものであり、輸送開始前にその気密性は検証されているが、万が一の事態に対処するため、防護マスク、防護服の他、局所排風機、除染剤等の除染用具を備えている。 (2) 緊急時対策
気象、海象の急変等により船舶が予定航路を変更する場合、事故が発生した場合等の連絡体制は、船長を中心に関係事業者及び関係官庁へすみやかに連絡されるよう組織されている。 緊急時における具体的対応プログラムは、当面第一責任者である事業者等の準備措置に依存せざるを得ないが、今後国等の公共組織と事業者、専門家等が相互に協力参加して、その支援にあたることが望ましく、現在このような有機的な連絡協力体制につき検討が続けられている。 (3) 定期訓練
消防、救命に関する定期操練を各種の事故モードを想定し、その処置方法、責任分担の徹底を図るなどの点から実施しているほか、放射線事故訓練についても積極的にこれを実施している。 Ⅴ 海上輸送に関する法制の整備について 核燃料物質等の海上輸送については、現在「原子炉等規制法」(昭和32年法律第166号)に基づく総理府令及び「船舶安全法」(昭和8年法律第11号)に基づく運輸省令によって規制されることとなっている。 科学技術庁及び運輸省は、最近の国内における核燃料サイクルに関連する事業活動の活発化と国際輸送の増大に対応して、安全規制の強化を図る観点から、昭和50年1月原子力委員会によって、決定された「放射性物質等の輸送に関する安全基準について」に従い、放射線審議会の審議を経て上記総理府令及び運輸省令の改正を行い本年1月1日から、施行している。さらに、科学技術庁は、昭和52年3月、核燃料物質等の輸送に関する行政分担の明確化及び行政措置の新設を内容の一部とした原子炉規制法の改正を含む、原子力基本法等の一部改正法案を第80国会に提出し、同法案はさる6月7日可決成立した。 一方、運輸省においては、後述の経緯に基づき、昭和49年10月、使用済燃料専用運搬船の構造設備に関する安全基準を策定している。 1 改正の概要
総理府令及び運輸省令の改正は、上述のとおり原子力委員会決定に沿って行われており、その内容は、国際的に定められた「IAEA放射性物質安全輸送規則(1973年版)」にも準処しているものである。 なお、改正法令全体の系統図は、別図に示すとおりである。 輸送関係法令系統図 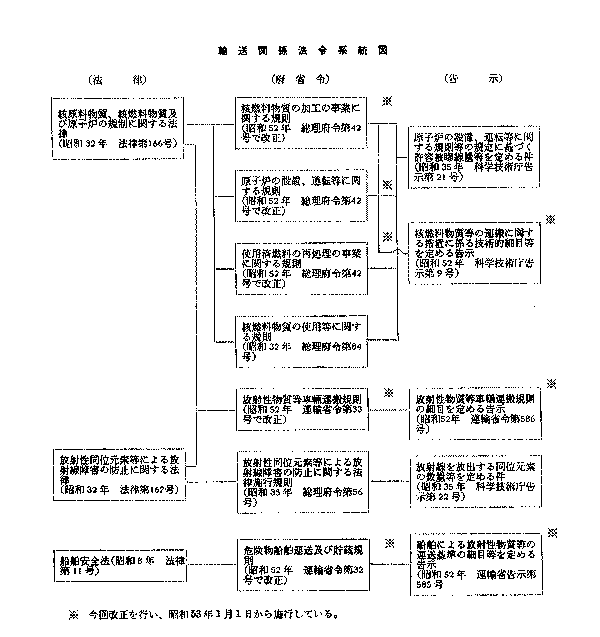 (1) 輸送物の基準
イ 核燃料物質等の輸送物(以下単に「輸送物」という。)を放射線被ばく防止の観点からL型、A型、BM型及びBU型の四種類に区分することとし、
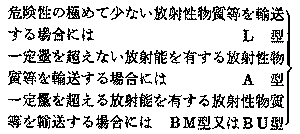 として輸送しなければならないこと。 ロ 輸送物を臨界の防止の観点からその臨界に達する危険性の程度に応じ、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂性輸送物及び第三種核分裂性輸送物の三種類に区分し、そのいずれかの形態で輸送しなければならないこと。 (2) 輸送の基準
イ 輸送物及びそれを収納したコンテナについて、それらの表面から一定の距離における最大放射線量率及び臨界に達する危険性の両方を考慮して一定の指数(輸送指数)を定めること。 ロ 輸送物及びそれを収納したコンテナには、それらの表面の放射線量率及び臨界の危険性に応じ、特定のラベル及び表示を付し、又は行うこと。 ハ 積載方法等の基準として、輸送物は移動、転倒等のないように積載すること、旅客等が通常立入る場所には積載しないこと、他危険物との混載を制限すること、取扱方法等を記載した書面を携行すること、被ばく管理に関すること等、輸送方法として遵守すべき事項を定めること。 ニ 輸送物又はそれを収納したコンテナの輸送指数の合計が、船舶内の一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域につき一定数を超えないように輸送物の積載限度を定めること。 (3) 輸送物及び輸送の確認
BM型輸送物、BU型輸送物及び核分裂性輸送物を輸送しようとするときは、輸送前に輸送物としての安全性の確認を受けなければならないとするほか、BM型輸送物及びBU型輸送物並びに第三種核分裂性輸送物については、個々の輸送の安全性についても運輸大臣の確認を受けることとなっている。 このような確認に関する行政上の円滑な運用を図るため科学技術庁は、これら特定の輸送物に対する安全性の確認制度を運用通達(昭和52年12月8日付け52安局第405号)により実施している。この確認は輸送物の設計承認、容器の登録、輸送物の確認、輸送計画書の届出、発送時検査等によって行うものである。 なお、前述のように原子炉等規制法が改正されたので、同法に基づく確認制度が陸上輸送部分についても新設されることとなり、輸送物の安全規制が海陸に亘ってより円滑に行われることとなる。 2 使用済燃料専用運搬船の安全基準の策定
危険物の海上輸送については、海上人命安全条約により、国際的に安全確保を図ることとされており、IMCO(政府間海事協議機関)は、国際海上危険物規則により放射性物質の容器包装、積載方法等について、IAEAの国際規則をとり入れた基準を定めている。 しかしながら大量の使用済燃料を専用に輸送する船舶の構造、設備については、未だ国際的なモデルが存在していない。 このため、運輸省は、動燃再処理工場の本格的稼動に伴う使用済燃料の国内海上輸送について、その安全対策をより強固なものとするとの観点から、昭和49年2月、省内に専門家からなる「使用済燃料運搬船検討会」を設置し、かかる船舶の構造設備基準の策定に着手した。その結果、同年10月船舶安全法に基づく船舶検査を実施するにあたり、この船舶の取扱いに関し船舶局長通達(昭和49年舶査第610号)を定めるに至った。 この基準においては、この種の船舶はまず何よりも衝突、設備の機能低下等を回避し、かつ、万が一の不測の事故に対しても被害が極限されるよう、可能な限りの構造設備が設けられるべき旨の基本構想が貫かれており、二重船殻構造、耐衝突構造、耐座礁構造、船倉内非常漲水装置、各種放射線防護機器等、従来の危険物運搬船にはみられない厳しい安全対策が盛り込まれている。 なお、国内原子力発電所から外国再処理工場へ使用済燃料を輸送する専用運搬船についても上記基準と同様の措置がとられることになっている。 また、分析用試料、研究炉用等比較的少量の使用済燃料を輸送する場合については上記のような専用運搬船の基準が適用されないが、輸送量、航路等の具体的内容に応じて必要な安全性が確保されることとなっている。 3 原子力基本法等の一部改正法による改正
現在、船舶による核燃料物質等の法規制は、輸送主体によって異っており、原子力事業者(加工事業者、原子炉設置者及び再処理事業者)が自ら輸送するときは、原子炉等規制法に基づくそれぞれの事業規則と、船舶安全法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規制が適用され、その他の場合(原子力事業者から運搬の委託を受けた者等が輸送する場合)は、船舶安全法が適用されることになっている。 さる6月7日成立した原子力基本法等の一部改正法においては、輸送の規制に関する所管を明確にするため事業所外運搬の場合であって、陸上輸送については原子炉等規制法(輸送物に関する規制は総理府令、輸送方法に関する規制は運輸省令(放射性物質等車輛運搬規則)及び海上輸送については船舶安全法で規制することとなっている。したがって、改正法の施行(公布の日から6ケ月以内の政令で定める日)後は、これら法令の区分に従って、輸送物及び輸送方法がそれぞれの基準に適合することについて所管大臣の確認制度が整備(海上輸送については、既に船舶安全法に基づき実施されている。)されることとなる。 このほか、陸上輸送の際の都道府県公安委員会への輸送計画の届出制度の新設等の改正が行われる。 Ⅵ 総合評価 本審査会は、使用済燃料の海上輸送の安全性について昭和51年7月より審議を開始し、更に昭和52年6月「核燃料物質の輸送の安全対策について」経過報告を行ったが、引きつづき海没時のキャスクの安全性、環境影響評価及び海上輸送の安全対策等について調査検討した結果、以下のように評価される。 使用済燃料用キャスクは、落下衝撃試験、火災試験等各種の試験条件を満足するよう法令に定められた厳重な基準により設計されている。 我が国における使用済燃料専用運搬船の航路における船舶の海難統計調査に基づく検討結果によると専用運搬船の沈没確率は極めて小さい。さらに専用運搬船の航路における水路調査、サルベージ技術、キャスク及び燃料体への水圧及び腐食の影響等を総合的に検討した結果、万が一キャスクが海没しても放射性物質が瞬時に海水中へ漏洩することはない。 しかし、キャスクは、海没後年数を経ると部分腐食等によりキャスク内の放射性物質が漏洩することも考えられるので放射性物質の漏洩モデルを2ケース仮定し(キャスクが水深200m及び2,000mに海没した場合)、公衆の被ばく線量を評価した結果、被ばく線量は国際放射線防護委員会(ICRP)の平常時の公衆に対する許容被ばく線量に比べていずれの場合も十分低い値である。 一方専用運搬船については、船体構造、設備に対する十分安全な設計の配慮、また海上輸送方法については、安全輸送に関する関係省庁の法制整備、安全運航の指導、連絡体制の完備等により専用運搬船が事故に遭遇し、かつ、沈没することがないように十分な安全対策がとられている。 したがって我が国における使用済燃料の国内海上輸送については、十分安全が確保されるものと認められる。なお、国際間海上輸送の安全確保については、国際的な合意形成が重要であるので、圧力平衡弁の開発利用を含めてIAEA等国際機関の場で率先して提言してゆくことが望まれる。 Ⅶ 審議経過 本報告書は、本審査会輸送部会で下記の審議を行い、昭和53年8月21日第11回及び9月21日第12回審査会における審議を経てとりまとめられたものである。 記
なお、審議を行った同部会の構成は次のとおりである。
(参考)
核燃料安全専門審査会の設置について
昭和51年4月9日
原子力委員会
Ⅰ 設置の趣旨 核燃料サイクル関連施設のうち、製錬、加工及び原子炉の各施設の安全性については、その設置の許可等に際し、原子炉等規制法により、当委員会がその審議を行うこととなっており、とくに原子炉施設については、「原子炉安全専門審査会」において安全審査を行っている。 また、再処理施設についても、従来その重要性にかんがみ、当委員会において安全性を審議することとし、このため「再処理施設安全審査専門部会」を設置して安全審査を行ってきた。 しかしながら、原子力発電の進展に伴い、使用済燃料の輸送及び再処理、生成するプルトニウムの利用等の事業が急速に展開する段階を迎え、核燃料サイクル全般に係る総合的な安全対策の確立が必要となっている。 このような状況にかんがみ、原子炉施設を除く核燃料サイクル関連施設について、従来の再処理施設に加え、製錬、加工及び核燃料物質使用の各施設に関しても安全対策上重要なものについては専門部会において安全審査を行うこととし、併せて核燃料物質等の輸送に関する安全対策の調査審議等をも行うため、当委員会の専門部会として「核燃料安全専門審査会」を設置するものとする。 なお、これに伴い従来の「再処理施設安全審査専門部会」を新設の審査会に吸収することとし、審査会の発足をもって同専門部会は廃止する。 Ⅱ 審議事項 1. 原子力委員会が指示する核燃料サイクル関連施設(原子炉施設を除く。以下同じ。)に係る安全性に関する事項の調査審議
2. 核燃料物質等の輸送に関する安全対策についての調査審議
3. 核燃料サイクル関連施設に関する安全規制の実施についての評価
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |