| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||
|
原子力研究開発利用長期計画について 昭和53年9月12日
原子力委員会決定
1. 原子力委員会は、昭和47年6月、原子力開発利用長期計画を改訂し、これに基づき、原子力の研究、開発及び利用を推進してきたところであるが、その後、我が国の原子力研究開発利用を巡る諸情勢が大きく変化したことから、この長期計画の中には、原子力研究開発利用を推進する上での指針として、必ずしも実態にそぐわない面も見られるに至った。 このため、当委員会としては、52年4月、長期計画の改訂を行うことを決定し、同年5月、長期計画専門部会を設置して、新しい長期計画について、審議を進めてきたところである。 2. このたび、同部会から「原子力研究開発利用長期計画案」の報告を受けたので、同報告に基づいて、別添により、新しい原子力研究開発利用長期計画を決定する。当委員会としては、今後、本長期計画に基づく施策を強力に推進していくものとする。なお、現下の内外情勢は極めて流動的であるので、今後必要がある場合には、本長期計画を柔軟に見直していくものとする。 3. 長期計画専門部会は、本日をもって廃止する。 (別添)
原子力研究開発利用長期計画
はじめに
原子力は、石油代替エネルギーの中心的役割を担う重要なエネルギー源であり、また原子力利用の一分野である放射線の利用が、医療、農業、工業等広い分野で進められている。他面、先端技術としての原子力研究開発利用を進める過程において、科学技術水準の向上、産業構造の高度化等の波及効果がもたらされている。このように、原子力研究開発利用は、一国の国民生活及び社会経済のなかで重要な地位を占めてきている。 ところで、原子力研究開発利用という巨大科学技術を使いこなしていくためには、多くの人材と多額の資金を投じて進める各種の研究開発及びその実用化のための施策を長期間にわたって継続していく、息の長い努力の積重ねが必要であり、このため、原子力研究開発利用は、長期的視点に立った総合的な計画に基づいて推進されることが肝要である。また、原子力研究開発利用は、多くの国民に直接的または間接的に大きな係わり合いを持つことから、原子力研究開発利用に関する明確なビジョンを国民に提示し、国民の理解と協力を得て、これを推進していくことが必要である。 以上のような観点から、原子力委員会は、従来から、原子力研究開発利用を進めるに当っての長期的指針となるべき長期計画を策定し、これを公表してきたところであるが、今般、前回の長期計画策定(昭和47年6月)以降の内外諸情勢の変化を踏まえつつ、今後約10年間における原子力研究開発利用に関する施策の重点と、その推進計画を示す新たな長期計画を策定した。 前回の長期計画策定以降、我が国の原子力研究開発利用をとりまく内外情勢は、大きく変化しているが、これらの変化のうちにあって、特に今回の長期計画策定の背景となった諸事情をあげてみれば、次のとおりである。 第一は、エネルギー源としての原子力の地位が一層高まったことである。すなわち、石油危機以降原子力発電は、各国のエネルギー政策のうちにあって、石油代替エネルギーの中心たる位置を与えられたが、我が国の場合も、原子力発電規模は、昭和52年度末で既に800万kWに達し、総電源の7%強を占めているほか、今後その比重が急速に増大することが期待されている。このように、原子力は、今や我が国エネルギー総供給のうちの重要な柱の一つであり、原子力研究開発利用は、国のエネルギー政策の要請のもとに、着実に推進されるべきものとなった。 なお、これに関していえば、我が国の原子力政策の既定路線として、軽水炉の定着化を図りつつ、自主的な新型動力炉開発を進め、またウラン濃縮、使用済燃料の再処理等の各段階を通じて、自主的な核燃料サイクルを確立することがその基本となってきたが、近年の内外情勢の変化によっても、この既定路線は何ら変える必要は認められず、むしろ、準国産エネルギーとしてのプロトニウム利用の必要性等からみて、今後一層強く推進されるべきものとなっている。 第二は、原子力研究開発利用が進展するに伴って、克服すべき現実の課題が多くなり、かつその厳しさが深まっていることである。 例えば軽水炉については、近年各種の故障やトラブルの発生があり、またそれとの関連もあって定期検査が長期化したことなどから、その稼働率の低下がみられた。これが、原子力発電に対する国民の不信感を招く有力な一因ともなっており、早急にその抜本的解決が望まれる。また、核燃料サイクルの面では、使用済燃料の再処理、放射性廃棄物の処理処分等が、逐次実験段階から実施の段階に入ろうとしており、その技術的な完成や事業実施の態勢確立が急がれる。また、原子力研究開発利用が進むにつれ、各種研究開発プロジェクトが一層巨大化しており、これらに要する研究開発資金をいかに調達していくかが、焦眉の課題となってきた。 一方、世界的な傾向として、原子力の将来に対する素朴な信頼と期待の時期を過ぎて、その安全性への不安を中心に、原子力研究開発利用に対する批判と反対の動きがあり、原子力発電所等の立地に際して、地域社会の強い反対を受けるなどの現象が一般化している。このようなうちにあって、主要各国と同様、我が国においても前回の長期計画に示した原子力発電規模の見通しの達成は不可能と見込まれるに至り、これを引き下げざるを得なくなっている。 今後、原子力研究開発利用を推進していくに際しては、立地円滑化の見地からはもとより、原子力研究開発利用という巨大科学技術が社会に積極的に受容されるよう、国としての確固たる方針を表明するとともに、原子力技術の安全性、信頼性、原子力利用の必要性等について、国民一般と地域社会の認識を飛躍的に高めていく必要がある。 第三は、原子力研究開発利用をとりまく国際環境の変化である。元来原子力研究開発利用には、資源及び技術の両面を通じ、国際的な係わり合いをもつ要因が多く、我が国として、今後とも原子力分野における二国間・多数国間の協力、資源国との開発協力等を進めて行くべき立場にある。 他方、原子力をめぐる国際問題のうち、核不拡散強化を目的とする国際的制約が、近年とみに強まったことが注目される。これは、例えば昭和52年における東海再処理施設の運転に関する日米交渉に端的に現われたところであって、今後我が国の原子力研究開発利用の推進に当たり、このような国際的制約が生ずる可能性があることに常に留意していく必要がある。かつ、我が国としては、国際的な核不拡散政策には十分な協力を惜しまないが、同時にそれが、我が国の原子力研究開発利用を妨げることとなってはならないことを政策の基本とするものであり、この姿勢を現実に貫くためには、国際場裡において、進んで我が国の方針が受け入れられるよう努力する必要があり、またそれを可能にするだけの自主的な技術を確立することが必要となってきている。 原子力委員会は、以上の諸点に十分留意しつつ、新たに以下の長期計画を策定したが、現下の内外情勢はなお流動的であり、今回結論の得られなかった問題もあるので、今後の内外情勢の変化と施策の進展を十分に踏まえ、この長期計画を柔軟に見直し、要すれば、適時これに修正を加えるなどの弾力的措置を行いつつ、我が国の原子力研究開発利用の適切かつ積極的な推進を図っていくものとする。 第1章 原子力研究開発利用の基本方針
我が国における原子力研究開発利用は、過去20余年間にわたる関係各界の努力により、着実な進展をみ、原子力発電をはじめとする各分野で、本格的実用化の段階を迎えている。国民の生活水準の維持向上及び社会経済の発展に大きく寄与し得る原子力研究開発利用は、今後とも一層これを進めていくべきものである。 特にその際、我が国が既に世界でも有数の原子力発電規模を持ち、かつ自主的な核燃料サイクルの確立をめざすなど、原子力研究開発利用の先進的立場に立つようになってきたことにもかんがみ、原子力研究開発利用における国際的な関連に、十分な配慮を払っていくことが重要になってきている。 原子力委員会は、我が国の原子力研究開発利用の開始当初から、原子力基本法の精神に基づき、その推進を図ってきており、その理念は、当初から一貫しているところであるが、特に最近における内外情勢の進展を考慮して、今後の原子力研究開発利用における基本方針を示せば、次のとおりである。 1 原子力平和利用の確保
原子力研究開発利用を平和の目的に限るとする理念は、原子力基本法制定以来、一貫して堅持されてきたところであり、これを確保するため、原子炉等規制法をはじめとする関係法令に基づく厳重な規制を実施してきたところである。 また、我が国は、昭和51年、核兵器の不拡散に関する条約(NPT)を批准したが、これは、同条約の精神が、我が国の平和理念に基本的に合致するものであるとの認識に基づくものであり、今後とも、原子力研究開発利用は、原子力基本法及びNPTの精神に立脚し、平和目的に徹してこれを進めるものとする。 ただ最近に至り、核兵器の拡散に対する懸念から、NPTをさらに補強するための核不拡散政策が、大国によってとられるようになって、原子力に関する資材や技術の移転等に対する規制が強化される傾向にあり、これが国際政治上も重要な意味をもつ問題となってきた。 このような国際情勢下において、我が国は、まず、原子力研究開発利用は平和目的に限るとの我が国の基本姿勢を明確にして、これを諸外国に十分理解させるよう努めることが必要である。かつ、NPT第4条に規定されているように、すべての締約国は、平等に原子力平和利用からの利益を享受し得るとの考え方を堅持して、原子力平和利用と核不拡散とは両立し得るし、また両立させなければならないことを、国際場裡において積極的に主張し、各国のコンセンサスを得るよう努める必要がある。 既に我が国としては、このような目的のための国際的努力の一環である国際核燃料サイクル評価(INFCE)に、積極的に参加してきたところであり、今後とも、原子力平和利用を推進していくための新たな国際的秩序の形成に、積極的に貢献していくものとする。その意味においてプルトニウム利用、使用済燃料の再処理等について、より効果的な保障措置技術の研究開発を推進するなどの国際的協力を進めるとともに、国内的には、国内保障措置体制の一層の充実及び核物質防護体制の強化を図っていくことが重要な課題である。 2 安全の確保と原子力に対する国民の支持
原子力研究開発利用は、従来から安全の確保を大前提として進められてきたところであるが、原子力の安全性に対する国民の不安感は、まだ完全に払拭されているとはいい難く、これが一部に見られる原子力発電に対する反対運動の契機となり、また原子力行政への不信の一因ともなってきた。そのため、今次、原子力安全委員会の新設と安全規制の一貫化を内容とする、原子力行政体制の改革が行われることとなっている。この新体制のもとにおいて、今後とも、安全規制の厳重な実施とともに、原子力施設の安全性、放射線障害の防止等に関する安全研究の推進、安全基準の整備、環境保全対策の強化等の一層の充実を図り、安全の確保に万全の措置を講ずることが必要である。特に、今日、安全問題は、原子炉の設置・運転はもとより、核燃料等の輸送、放射性廃棄物の処理処分、廃炉等広く原子力利用のあらゆる分野に及び、また核物質防護対策もその主要な要素となりつつあり、これら全領域にわたって安全確保のための技術開発、法令を含めた体制整備等に努め、原子力の安全の確保について万全の態勢を確立することが急務である。 そして、このような安全確保の上に立って、エネルギー問題解決のためには、原子力研究開発利用が不可欠であることについて、国民一般及び地域住民の理解を深めるとともに、様々な場を通じて、国民と地域住民の声を原子力政策に反映させることにより、原子力研究開発利用に対する広い国民的支持を得るものとする。 3 原子力研究開発利用における自主制の確保と国際協力
我が国は、従来から原子力の研究開発につき、積極的に国際協力を行って来たが、今後も、核融合、安全研究等各種の研究開発プロジェクトにつき、二国間・多数国間の協力の機会が増加している。また、発展途上国に対する協力も進められつつある。 ただ、このような国際社会における協力を効果的に進める上からも、我が国として、借り物でない独自の技術蓄積や開発態勢を持っている必要があり、かつ最近の国際情勢からみても、このような原子力研究開発利用における自主性の確保の必要性が強まっている。 すなわち、我が国として原子力研究開発利用の初期段階においては、軽水炉をはじめ多くを導入技術に頼ったが、これを消化吸収して我が国に適合した技術体系とするためには独自の研究開発を要した経験からしても、今後の新型炉の開発等には、我が国独自の研究開発が不可欠である。 また、特に近年、核不拡散との関連において、原子力に関する重要技術の国際間移転は、とみに制約されてきており、安易な導入期待は許されなくなってきている。今後、原子力の研究開発における自主性を確立していくことは、単に技術水準において先進国に遅れをとることを防ぐのみならず、我が国研究開発の成果を国際社会に提供して、国際協力を有効に進めるためにも必要であり、また核不拡散に関する我が国の基本方針にのっとって、機器の輸出、発展途上国への技術援助等が可能となるまでに、我が国の原子力技術と関連産業を発展せしめるためにも必要である。 他方、核燃料サイクルについては、当面我が国として技術面のみならず、資源、ウラン濃縮、使用済燃料の再処理等の各段階で外国に依存することが多いが、今後は、技術的には我が国の自主的研究開発の成果を生かし、資源的には資源国との協力や供給源の多角化を図っていくなど、外的制約を極力減少させるよう努力し、真に自主的な核燃料サイクルの確立を期す必要がある。 4 原子力研究開発プロジェクトの計画的推進と政策運営上の配慮
原子力研究開発利用は、巨大な科学技術体系であって、個々の研究開発プロジェクトが大規模であるのみならず、基礎的研究段階から実用化まで長期間を要し、また関連する分野も広範である。原子力の利用は、このような原子力研究開発の努力を広範囲にわたって積み上げていくことによって、初めて可能となるものである。そこで、原子力研究開発プロジェクトを進めるに当たっては、関連する諸課題を総合的に把握し、かつ、長期間を通じて誤らない方向付けを行うことが不可欠であり、このための総合的な計画が確立されなければならない。この長期計画は、このような要請に応えることを一つの目的とするものである。 今や、原子力研究開発利用の急速な進展のうちにあって、この長期計画のもとに、新型動力炉の開発、核融合の研究、ウラン濃縮技術開発、放射性廃棄物処理処分技術の研究開発等、実験段階から実用段階まで及ぶ多岐にわたる研究開発プロジェクトが進められている。これらの研究開発プロジェクトは、相互に密接に関連しているものであり、そのいずれを欠いても、原子力研究開発利用の計画的推進に支障の生ずる可能性があることに留意し、今後これらの原子力研究開発プロジェクトを総合的、体系的に進めていくことによって、諸外国の技術進歩に遅れをとらず、将来のエネルギー政策に悔いを残さないようにしていく必要がある。 このような状況において、国が、これらのプロジェクト推進の諸条件の整備、なかんずく、研究開発資金と、人材確保の面に配慮することが望まれるのであって、原子力研究開発利用のもつ意義を十分に認識し、政策運営全体のうちにおける調和に努めつつも、原子力政策について重点的な配慮がなされることが期待される。なお、民間においても、これらのプロジェクトの推進に対し、一層積極的な協力を行うべきことはいうまでもない。 第2章 原子力研究開発利用の進め方
1 原子力発電
(1) 原子力発電の開発規模
原子力利用の主要形態は、いうまでもなく原子力発電であり、その発電規模、炉型等の将来のあり方は、今後の原子力研究開発利用に関する諸施策に少なからぬ影響を与える。 原子力発電は、その燃料であるウランの安定供給が期待できること、燃料の輸送、備蓄が容易であること、使用済燃料の再処理を通じて燃料の再利用が可能であることなどにより、国産エレルギーに準じた供給の安定性を有しており、また、発電コストに占める燃料費の比率が小さいため、燃料価格の上昇による発電コストへの影響が少ないという特徴を有している。このため、石油に代る将来のエネルギー源の大宗を占めるものと考えられる。 本長期計画の計画期間に見合う昭和60年代までの原子力発電の開発規模としては、総合的なエネルギー需給バランスの観点から、昭和60年度において3,300万キロワット、65年度において6,000万キロワットを目標とするとの総合エネルギー調査会基本問題懇談会の検討結果が、総合エネルギー対策推進閣僚会議に報告されている。 この目標は、我が国の長期的なエネルギー需給を展望した場合、石油への依存度は極力抑えなければならないとの認識のもとに、その代替エネルギーを最大限に開発する必要があるとの観点から得られたものであり、我が国の将来のエネルギー供給構造を安定的なものとするためには、上記の原子力発電規模を大きな遅れなく実現させる必要がある。このため、政府及び民間の最大限の努力と協力が望まれる。 原子力発電の開発規模は、経済的及び資源的な面によっても制約され得るものであるが、今日、原子力発電は、他の電源に比べ勝るとも劣らぬ経済性を持っているし、また、資源的にみても、昭和65年頃までの発電規模を賄うに必要な、ウラン資源の供給とウラン濃縮及び使用済燃料の再処理のサービスは手当て済みであり、更に、今後核燃料サイクル関係施策の推進を図ることにより、ウラン資源の有効利用も可能となるので、これも上記の発電規模の実現を阻むものではない。 当面の最大の問題は立地問題であって、従来、原子力発電所の建設は、原子力発電の安全問題、環境問題に対する地元住民の不安等の諸要因のため、少なからぬ遅延を招いており、今後ともこの傾向は続くものと思われる。原子力発電所及びその関連施設の立地が円滑に進めば、前述の昭和60年度及び65年度の開発規模の目標は、支障なく実現されるのであって、政府及び民間の努力は、当面、主として立地難打開に向けられる必要があり、原子力発電について安全の確保と環境の保全に万全を期し、地点に即したきめ細かい対策を配慮するなどの対策を講じていくことが要請される。 (2) 軽水炉の改良・標準化
軽水炉は、発電用原子炉として、世界で最も一般的に実用化され、利用されている炉型である。また、その設計、建設、運転に至る諸技術データが完備し、かつ安全研究の進んだ信頼度の高い炉型とされている。 我が国においても、軽水炉が原子力発電の大部分を占めており、今後とも、高速増殖炉が実用段階に入るとみられる昭和70年代までの間は、原子力発電の基幹を占めることが予想される。 我が国は、米国からのプラント輸入及びライセンス生産を通じて、軽水炉技術の消化習得に努め、鋭意国産化を進めてきた。今日、軽水炉の安全性は十分に確保されているが、信頼性向上、保守点検作業性の向上等の面からは、なお改良の余地がある。 このような観点から、我が国では、信頼性、稼働率の一層の向上、従業員の被ばく低減、保守点検作業性の向上等を図るべく、自主技術による改良を加え、更に標準化を行うための改良標準化計画を、昭和50年度から進めてきている。既に、昭和52年度までに従業員の被ばく低減、作業性の向上等を目的とした第一次の改良・標準化の作業が終わったところであるが、今後、昭和55年度までに一層の信頼性向上、検査の効率化等を目的とした第二次の改良・標準化を進めるものとする。この改良・標準化を進めるに当たっては、今後とも、政府、電気事業者、機器メーカーが一体となって、強力に推進することを期待する。 これらの改良・標準化により、我が国の軽水炉技術の向上は当初の目的を達することとなるが、それ以降においても、関連企業を中心に、更に一層の技術開発努力を断続することが望まれる。このような成果を、電気事業者において新たに設置する原子力発電所に積極的に取り入れることにより、我が国に適した軽水炉として定着化させていく必要がある。 2 将来の炉型選択と新型炉開発
(1) 将来の炉型選択
我が国の原子力発電は、これまで軽水炉に中心が置かれてきたが、軽水炉のみに依存する限り、長期的には、ウラン資源の制約から、原子力発電規模に限界が生ずることは避けられない。従って、原子力発電規模を長期にわたって拡大していくためには、使用済燃料から回収されるプルトニウム及びウランを有効に利用できるなど核燃料の利用効率のよい新型動力炉に期待することとなる。このため、プルトニウムを燃料とし、かつ、消費した以上のプルトニウムを生成する高速増殖炉を開発し、これを将来の発電用原子炉の本命として導入していくという、ウラン・プルトニウム・サイクルによる炉型戦略が、従来からとられてきている。 より遠い将来を展望すれば、トリウム・サイクルの導入の可能性についても検討を進めておく必要があるが、トリウム資源も我が国には賦存せず、また、現在のところトリウム・サイクルに関する技術的見通しも明確でないので、基本路線としては、現在定着化しつつある軽水炉から高速増殖炉への移行を引き続き推進すべきである。 また、この基本路線を補完する炉として、新型転換炉の開発が進められ、既にその原型炉の試運転が順調に行われている。この炉は、ウラン濃縮作業量を節減し、又は不要とする当初の構想から進んで、後述のようなプルトニウムの積極的利用による核燃料経済上の優位性、弾力性が注目されているところであり、その実証炉以降の開発の進め方につき、早急に方針を決定するものとする。 更に、カナダ等において、既に相当程度実用炉としての運転実績を有するCANDU炉は、天然ウランを燃料とし、ウラン資源の有効利用、濃縮作業量の節減等の特長を有しており、その導入が検討課題となっている。このため、その安全性、信頼性についての調査が進められているところであり、引き続き、新型炉の自主開発、核燃料サイクル等の関連性及び経済性をも含めて評価検討のうえ、その導入に関し、結論を得るものとする。 他方、多目的高温ガス炉は、電力部門だけでなく、将来エネルギー需要の増大が予想される非電力部門においても、核熱エネルギーを多面的かつ多段的に利用可能とするものであり、この実用化により、エネルギー多消費産業における化石燃料への依存度の低下に貢献し得るものと期待され、その研究開発を推進するものとする。 (2) 新型炉開発
(イ) 高速増殖炉
高速増殖炉は、消費した以上の核燃料を生成する画期的な原子炉であり、ウランのもつエネルギーの最高限度の利用を可能とするものである。ウラン資源の制約を考慮すれば、できる限り早期に高速増殖炉を実用化することが望まれ、昭和70年代に本格的実用化を図ることを目標として、その開発を進めることとする。 高速増殖炉の開発に当たっては、プルトニウムとウランの混合酸化物系燃料を用いるナトリウム冷却型炉を対象として、実験炉の運転等を通じて、基礎的技術の蓄積を図り、その成果をもとに、電気出力30万キロワット程度の原型炉を昭和60年代初頭に臨界に至らしめることとする。 更に、原型炉の建設、運転経験の評価を十分に反映しつつ、実用炉の経済性の見通しの確立と技術的諸性能の実証を目的とする実証炉を、昭和60年代後半に臨界に至らしめることを想定して、必要な研究開発を進める。 また、高速増殖炉の開発と合わせて、高速増殖炉の核燃料サイクルを確立する必要があり、このため、高速増殖炉の核燃料サイクルに関し、使用済燃料の再処理等の必要な研究開発を進める。 なお、高速増殖炉の開発については、海外においても意欲的に取り組まれており、米国、英国、フランス、西ドイツ、ソ連等の諸外国との技術情報の交換、共同研究の実施等の国際協力を積極的に推進することとする。 (ロ) 新型転換炉
新型転換炉は、軽水炉の使用済燃料を再処理して回収されるプルトニウム、減損ウラン等を有効に利用できる炉であり、その核燃料特性からみて、ウラン資源消費量及び濃縮作業量の節減、核燃料資源の弾力的活用等に優れた性能が期待できる。従って、新型転換炉は、高速増殖炉の実用化との関連において、特に重要な意義をもつと考えられるので、その実用化へ向けて努力することとする。このため、当面、原型炉の運転を進め、技術的諸性能の確認、安全性評価データの蓄積、経済性の評価等に努力を傾注するとともに、実証炉の設計及びこれに必要な研究開発を進めるものとする。実証炉の建設については、原型炉の建設・運転経験及び大型炉の設計研究を通じての技術的、経済的評価に基づき、我が国の核燃料サイクルにおける効果、高速増殖炉の開発の進捗状況、重水の供給体制等を十分に勘案して総合的な評価検討を行い、昭和50年代半ばまでに決定することとする。 (ハ) 多目的高温ガス炉
我が国の原子力利用は、これまで原子力発電を主軸に展開されてきているが、より長期的には、核熱エネルギーを製鉄、水素製造、石炭ガス化、石炭液化等に用いる、いわゆる原子炉の多目的利用を実現していく必要がある。これが実現されれば、我が国のエネルギー供給の安定化に寄与するとともに、エネルギー多消費産業等において問題となっている環境汚染問題の軽減を図るなど、国民経済への貢献が期待される。 このため、核熱エネルギーを産業に供給する原子炉として、多目的高温ガス炉を開発することとし、その第一段階として、発生高温ガスの温度1,000℃を目標とする実験炉を、昭和60年代前半の運転を目途に建設するものとする。 また、利用系技術に関しては、高温還元ガス利用による直接製鉄技術、水素製造技術等の開発が推進されているので、これら利用系の技術開発と上記実験炉の建設とが、緊密な関連のもとに推進されるよう配慮するものとする。 3 核燃料サイクル
原子力発電が、将来の安定したエネルギー供給源としての役割を果たしていくためには、今後必要となる核燃料を安定的に確保し、その有効利用を図ることが極めて重要である。このため、天然ウラン及び濃縮ウランの確保はもとより、再処理体制の確立、プルトニウム利用の推進及び放射性廃棄物の処理処分対策について、積極的な施策を講じ、原子力発電システムとして整合性のとれた核燃料サイクルを早期に確立する必要がある。 その際、特に留意すべきことは、我が国の核燃料サイクルの現状は、天然ウランの供給及びウラン濃縮役務を全面的に海外に依存せざるを得ないなど、資源供給の面でも、技術的にも、外国との深い係わり合いの上に成り立っていることであり、更に、核燃料サイクルを巡り、最近の国際的動向が厳しくなってきたことである。 このような諸情勢に対処し、我が国の自主性を確保できるような核燃料サイクルを確立していくためには、保障措置・核物質防護対策の強化及び核拡散防止のための技術開発、制度的検討等を通じて、原子力平和利用と核拡散防止との両立をめざす国際的努力に協力していくことが必要であり、他方では、自らの手によるウラン資源の探鉱開発、濃縮技術の自主開発、再処理工場の国内立地等を進め、供給源を多様化するとともに、放射性廃棄物の処理処分対策を確立することにより、我が国の核燃料サイクルの自主性の向上を図ることが重要である。 (1) 天然ウランの確保
ウラン資源に乏しい我が国は、必要な天然ウランのほとんどすべてを海外に求めざるを得ないので、電気事業者が海外からの長期購入契約を中心として天然ウランを引き続き確保することを期待するが、長期的には、開発輸入の比率を高め、年間所要量の3分の1程度を開発輸入により確保することを目標として、海外における探鉱開発を引き続き行う。このため、動力炉・核燃料開発事業団による調査探鉱活動を推進するとともに、民間企業による海外探鉱開発を促進するための金属鉱業事業団の成功払い融資等の助成制度の強化を図る一方、我が国企業が開発に成功したプロジェクトからの生産品は、原則として電気事業者が引き取ることとし、その具体的方策について関係者間の協議を進め、これらの施策を通じて天然ウランの供給源の多角化を図る。また、供給の不安定等の事態に備えるためウラン資源を、天然ウラン又は濃縮ウランの形で備蓄することとし、その具体的進め方についての検討を進めることとする。 更に、ウラン資源国との友好関係を強化するとともに、ウランの安定供給が損われることのないよう、国際的な合意を得ることに努めるものとする。 (2) 濃縮ウランの確保
我が国の原子力発電に必要な濃縮ウランは、現在のところ、全面的に海外に依存しているが、近年、核不拡散の強化を目的として、濃縮ウランの供給に際して厳しい条件が付けられるようになってきており、自主性の確保、供給の安定化の観点から、濃縮ウランの国産化の必要性がますます高まっている。 このような要請に対応して、自主技術による国産工場を建設し、新規需要の相当部分を国内で賄うことを目標として、ウラン濃縮技術の開発を進めるものとする。 このため、我が国に適した技術として、遠心分離法によるウラン濃縮技術の開発を引き続き推進することとし、当面のプロジェクトであるパイロットプラントの建設・運転を進め、国産技術の確立を図るとともに、昭和60年代中頃までに我が国において実用工場を稼動させることを目標に、その経済性を確認するため、実証プラントの建設を行うものとし、その実施体制について早急に検討を進めるものとする。 (3) 使用済燃料の再処理
原子力発電所からの使用済燃料を、計画的かつ安全に再処理するとともに、回収されたウラン及びプルトニウムを再び核燃料として利用することは、ウラン資源に乏しい我が国にとって、必要不可欠である。このため、核燃料サイクル確立の一環として、再処理は国内で行うことを原則とし、我が国における再処理体制を早急に確立することとする。 このような基本的考え方のもとに、東海再処理施設の運転を通じ、我が国における再処理技術の確立を図るとともに、再処理需要の一部を賄うものとする。 さらに、今後増大する再処理需要に対処するため、より大規模な再処理施設、いわゆる第二再処理工場を建設するものとする。この第二再処理工場は、本格的な商業施設として、その建設・運転は、電気事業者を中心とする民間が行うものとし、昭和65年頃の運転開始を目途に、速やかに建設に着手することが必要である。 このため、関係法令の整備、立地対策の推進等必要な措置を講ずるとともに、再処理技術の改良等の研究開発を進め、また、環境に放出される放射性物質をできる限り少なくするために必要な技術、高レベル放射性廃棄物処理処分技術等の関連技術の研究開発を推進するものとする。 また、再処理施設の建設計画を進めるに当たっては、核物質防護等の見地から、同一敷地内にプルトニウム燃料の加工、高レベル放射性廃棄物処理等の施設を建設する立地方式(いわゆるコ・ロケーション方式)の採用も考慮する必要がある。なお、第二再処理工場の運転開始までの措置としては、海外への委託によって対処するものとする。 一方、昭和52年の東海再処理施設の運転に関する日米原子力交渉等にみられるように、核不拡散強化の見地から、我が国の再処理について厳しい国際的要求があり、また、INFCEでは、現行の再処理技術、代替再処理技術(混合抽出、部分再処理等)、多数国間あるいは地域的な再処理センター等の制度的代替案等、広い範囲にわたって再処理の評価を行っている。我が国としては、この際、より有効な保障措置技術の開発等、核不拡散に貢献し得るような技術の研究開発を進め、これらの検討に積極的に協力する一方、再処理を中心とした自主的核燃料サイクルの早期確立を図るという我が国の基本的考え方を、国際的に強く主張していくこととする。 (4) プルトニウム利用
再処理によって回収されるプルトニウムの利用については、将来実用化される高速増殖炉への利用が最も有効であるが、ウラン資源に乏しい我が国としては、その実用化までの間、プルトニウムを熱中性子炉にリサイクルすることにより、天然ウラン及び濃縮ウランの所要量の軽減を図ることが重要な課題である。このため、新型転換炉の原型炉の運転等を通じ、プルトニウム利用のための実証を行うとともに、軽水炉へのプルトニウムリサイクルについての実証試験を進めるものとする。 プルトニウム燃料の加工については、その実用化のために必要な研究開発を進め、プルトニウム加工の実証を行うとともに、その事業化についての検討を行うこととする。 また、プルトニウムの利用に当たっては、その安全性の確保に万全を期する必要があるため、生物学的安全性の研究を一層推進するとともに、核不拡散の見地からより効果的な核物質防護及び保障措置を実施するため、これに必要な研究開発、制度面の検討を進めるものとする。 (5) 放射性廃棄物の処理処分
原子力施設において発生する放射性廃棄物のうち、放射能レベルの極く低い気体・液体状の放射性廃棄物は、その放出低減化方針のもとに、それぞれ環境へ放出している。 その他の放射性廃棄物については、適切な処理を行い、施設内に安全に保管されているが、今後は、これら保管されている放射性廃棄物の最終的な処分を行うことが重要な課題である。 原子力発電所等原子力施設において発生する低レベル放射性廃棄物については、これを安定な形態に固化処理し、海洋処分と陸地処分を組み合わせて実施することとする。海洋処分としては、固化体を深海底に投棄することとし、これまで実施してきた海洋調査等の調査研究に基づき、環境への影響評価を十分行い、実施の条件が整い次第、国民の理解と協力を得つつ、国際的な協調のもとに試験的海洋処分を実施し、この結果を評価することによって安全性を確認したうえで、本格的な海洋処分へ移行することとする。 また、陸地処分のうち、長期的に貯蔵する方式については、原子力施設での経験を踏まえ、50年代後半より本格的に実施することを目標として、諸準備を進める。これと並行して、地中処分についても模擬廃棄物を用いたフィルド試験を行い、引き続き試験的陸地処分を実施し、その結果を踏まえつつ、本格的処分に移行することとする。 原子力施設で発生するイオン交換樹脂等中レベルの放射性廃棄物は、発生量が少ないため、処理技術が確立するまでの間施設内に保管することとし、その処分は、高レベル又は低レベルのものの処分に準じて行うこととする。 再処理施設から発生する高レベル放射性廃棄物は、半減期が長く、かつ、高い放射能を有しているため環境汚染を防止する見地から、半永久的にこれを安全に管理することが必要であるので、安定な形態に固化処理し、一時貯蔵したのち処分するものとする。高レベル放射性廃棄物の処理処分の当面の目標としては、固化処理及び貯蔵については、昭和60年代初頭に実証試験を行うこととし、また処分については、当面地層処分に重点を置き、調査研究を進め、我が国の社会的地理的条件に適した処分方法の方向づけを行い、昭和60年代から実証試験を行うこととする。 以上の放射性廃棄物の処理処分対策を推進するに当たっては、国及び民間の役割を明確にして官民が一体となって国民の理解と協力を得、国際協調のもとに総合的にこれを推進することが必要である。 このうち、最終的な処分については、国民の安全を保証する立場から、国が中心となって計画的に試験的海洋処分等の試験研究を推進し、国は安全確保に係る技術的基準等の整備を行い、厳重な安全規制を実施するものとする。 なお、高レベル放射性廃棄物の処分については、今後行われる研究開発の進展に応じ、国が行う安全管理の具体的内容及び方策について検討するものとする。 4 核融合
核融合エネルギーは、それが実用化された暁には半永久的なエネルギーの供給を可能とするものであり、人類の未来を担う究極のエネルギー源として、その実現に大きな期待が寄せられているものである。特に、資源・エネルギーに恵まれない我が国としては、その研究開発を推進する必要がある。 世界の核融合研究開発は、約20年前に開始され、以後着実に成果を積み上げてきたが、この数年来、トカマク方式によるプラズマの閉込めに関する研究が著しい進歩を遂げ、この方式による大型核融合実験装置の建設が、米国、EC及びソ連において進められており、数年以内には、核融合反応の臨界プラズマ条件が達成されるものと考えられている。我が国としても、これら諸国と雁行して、昭和50年代後半完成を目途に臨界プラズマ試験装置(JT−60)を建設するものとする。 これと同時に、プラズマの閉込めの効率化を図るため、非円形断面プラズマ、高ベータプラズマ、プラズマ加熱の諸方式の研究等を行うとともに、将来の核融合炉の技術的基礎として、超電導マグネット、トリチウムの取扱い方法、炉材料等の工学技術を確立するための研究開発を行うものとする。 臨界プラズマ試験装置の次段階としては、上記の研究開発の成果を基礎に、昭和60年代の完成を目途として炉心工学試験装置を建設することについて、検討するものとする。この装置では、当面トカマク方式を想定し、実験炉の前段階としての核融合反応実験(重水素・トリチウム燃焼実験)及び炉心工学技術の総合試験を行うものとする。 一方、核融合の研究開発は、多くの未踏分野を残しており、ある分野の研究成果が、他の分野の研究開発を大きく進展させることも予想され、また、今後の研究の進展如何によっては、トカマク方式以外の方式によって実用化が進められる可能性もあるので、プラズマに関する基礎研究あるいはヘリオトロン、慣性閉込め等のトカマク方式以外のプラズマ閉込めに関する研究についても、その一層の推進を図るものとする。 これらの研究開発に当たっては、核融合の安全性に関する研究を同時並行して進めることとし、特にトリチウムの生物影響については、関係機関の緊密な連携のもとに研究を実施するものとする。 また、核融合研究開発は、21世紀の実用化を目標とした長期的な研究開発であり、広範囲の人材や物的資源の集約を必要とする巨大科学技術であるので、研究開発を進めるに当たっては、ナショナルプロジェクトとして、政府関係研究機関、大学及び産業界が、総力を結集して研究開発に取り組むとともに、研究開発の進展に応じて、研究開発体制のあり方について検討するものとする。 核融合研究開発の国際協力に関しては、自主開発の原則を守りつつ、人的物的資源の効率的利用及び国際協調による相互啓発の観点から、OECD−IEA、IAEA等の多数国間協力及び日米間等の二国間協力を、積極的に推進するものとする。 5 原子力船
世界経済の発展に伴う国際貿易量の増加傾向は、今後も持続し、大量かつ低廉な海上輸送に対する社会的、経済的要請は、ますます増大していくものと考えられ、国際海運界においては、経済的な船舶の開発が進められている。 近年の石油価格の高騰、将来の石油の供給不安に対処し、船舶輸送の経済性の向上とエネルギー源の多様化を図る観点から、少量の核燃料で長期間にわたって運航でき、高出力になる程経済性がよくなるなど特長を有する原子力船に対する期待は大きい。 現在までに建造された諸外国の平和目的の原子力船は5隻であるが、これらは、実験船的色彩が強く、経済性の面で在来船に勝るものではないが、原子力船の安全性、信頼性については、これらの運航により既に実証されている。 世界的な造船、海運国である我が国としても、将来に予想される原子力船時代に備え、エネルギー政策のみならず造船、海運政策の観点からも、原子力船の開発を推進し、世界の大勢に遅れることのないよう配慮すべきである。 このため、原子力第1船「むつ」については、遮蔽改修及び安全性総点検を行い、建造をできるだけ早期に完了し、実験航海等において、出入港、航行等に関する十分な経験を積むことにより、原子力船の総合的な安全性、信頼性を確認するための技術の蓄積を図るものとする。 また、原子力第1船「むつ」の開発と並行して、基礎研究、設計研究等原子力船開発のための基盤を固めるために必要な研究を継続するとともに、安全性、信頼性のより一層の向上に配慮しつつ、改良舶用炉、関連機器等の舶用炉プラントを中心とする広範な研究開発、原子力船についての経済性の解明等を進めることとし、このための十分な研究開発体制の整備を図るものとする。 今後の原子力船の研究開発は、長期間にわたり、かつ、多額の資金を必要とするものであり、政府及び民間が一体となって、原子力船の研究開発を効果的に進めることとし、これらの成果を受けて、将来民間企業における実用原子力船の建造に円滑に移行することが望ましい。 また、原子力船の国際航海への就航を円滑に行うための、国際的な基準策定に関する検討に対し、我が国としても必要な貢献を行っていくことについて配慮するものとする。 6 放射線利用
放射線は、医療、工業、農業、放射線化学、食品照射等多くの分野で利用されており、今後ますますその発展が期待される。 放射線の医療分野での利用については、速中性子等によるガン治療の成果を踏まえ、今後、陽子、重イオン、パイマイナス中間子等の粒子につき、より優れたガン治療効果の可能性を総合的に評価しつつ、その研究開発を進めていくこととする。また、極短寿命ラジオアイソトープの生産、及びこれを用いる診断治療技術並びに放射線滅菌の利用分野の拡大に関しても、その研究開発を推進するものとする。 放射線の工業分野での利用については、装置や手法の標準化、規格化等を推進し、利用分野の一層の拡大に努めるものとする。また、放射線利用による新高分子材料製造技術の研究開発等、放射線化学の分野についても、引き続き研究開発を推進するものとする。 放射線の農業分野での利用については、食品照射の研究を引き続き推進するとともに、家畜飼料の殺菌・殺虫への利用の実用化について研究を進めるものとする。また、育種については、照射線源及び照射法の多様化等により、育種研究の一層の充実を図るものとする。 以上の放射線の利用は、今後、より一層利用の多様化、高度化が期待できる分野であるので、引き続き政府関係研究機関を中心として、大学、民間機関等の協力のもとに、総合的な研究開発を推進することとする。 また、放射線利用技術は、今後、開発途上国との国際協力の分野として進展することが考えられるので、開発途上国との技術協力について、今後とも配慮するものとする。 ラジオアイソトープの供給については、外国からの輸入のほか、国内生産を進めることとする。 また、ラジオアイソトープの利用拡大に伴う放射性廃棄物の増大に対処して、実態に即した処理対策を講ずることとする。 7 安全研究
原子力研究開発利用は、工学的安全性を高め、高度の信頼性を確保するとともに、放射能を安全に管理することによって、はじめてその正しい発展が期待されるものである。このような観点から、従来より、環境との調和を図りつつ、安全性の確保に特段の配慮がなされてきたところである。今後とも原子力研究開発利用の推進に当たっては、国民の健康の保持、環境の保全等安全の確保に万全の措置を講ずるとともに、核物質等の効果的な管理体制を確立し、信頼性の高い安全性の確保を図っていかなければならない。 原子力発電をはじめとする大規模な原子力研究開発利用を、多面的に推進していくに伴い、原子炉施設に加え、核燃料加工施設、再処理施設等の核燃料サイクル関連施設が増大することとなり、国内における核燃料物質等の取扱い量も増加する。これとともに、放射性廃棄物の発生量も増大するので、国民及び放射線従事者が、放射線を受ける可能性も高くなることを十分考慮しておかなければならない。 このような事態に対処して、軽水炉、新型炉、プルトニウム取扱施設、使用済燃料再処理施設等の核燃料サイクル諸施設、更に長期的には、核融合炉に関し、工学的安全研究を進めるとともに、特に軽水炉については、安全余裕度を実証データにより確認するための大規模な安全性実証試験及び改良標準化のための研究開発の推進を図る。 また、放射性廃棄物の処理処分に関し、処理技術及び最終処分技術の研究開発を推進する。 放射線の環境への影響に関しては、環境の放射能レベル監視の充実とその結果の評価が必要である。また、低レベル放射線の生物学的影響に関する研究の推進を図り、低レベル放射線の人体に及ぼすリスクの分析評価を進める必要がある。 施設、設備の工学的安全研究については、大規模な研究施設を要するものが多く、また、環境放射能の影響及び放射性廃棄物の最終処分に関する安全研究については、長期間にわたるものが多いため、具体的な実施計画に基づき、政府関係研究機関、大学等が、それぞれの分担のもとに研究を推進し、将来の原子力研究開発利用の展開に対応していくことが重要である。 以上の安全研究の成果については、これを原子力施設の管理と安全規制の中に適切に反映するよう、努力を傾注することとし、また蓄積された成果を広く国民に明らかにすることにより、安全問題に対する国民の理解を得るよう努めるものとする。 8 基礎研究及び科学技術者養成
基礎研究は、研究開発活動の基盤として、また、新しい技術開発の源泉として、原子力の各分野の研究開発を推進するうえにおいて不可欠のものである。 現在、原子力研究開発利用は、多くの分野において実用化の段階に達しつつある一方、新型炉、核融合等に関しては、なお基礎研究から開発研究へ至る広範な研究活動を必要としている。また、原子力施設の環境安全対策を確立するうえにおいても、さらに放射線の医療、農業、工業等への利用に関する新利用技術を開発するうえにおいても、基礎研究の重要性は大きいので、大型の研究開発の推進と並行して、基礎研究の充実強化を図るものとする。 これまで、大学、日本原子力研究所、理化学研究所及び国立試験研究機関は、これら原子力研究開発利用における基礎研究の推進に主要な役割を果してきており、今後も一層その重要性を増すものと考えられる。とくに、上記大学及び研究機関等における加速器、研究炉等の大型共同実験研究施設に関しては、その十分な活用を図る必要がある。 なお、これらの基礎研究の推進に当たっては、大学、政府関係研究機関及び民間機関が、適宜人材交流、共同研究を行うなど密接に協力し、効率的に実施するものとする。 また、基礎研究は、一般に国際協力を積極的に行いうる部門であるので、我が国としても諸外国との情報交流、学術的研究集会への参加等の国際協力を進めることとする。 他方、原子力研究開発利用の進展にともない、原子力に係わる科学技術者、特に安全性、環境保全などの分野でおける科学技術者の必要性が増大しているので、その養成を推進する必要がある。かつ、今後は、人材の量の面よりも質の面に特に重点をおいていくべきであろう。 このため、日本原子力研究所、放射線医学総合研究所等において実施している原子炉研修・アイソトープ研修等については、教科課程及び施設の一層の充実を図り、組織的、体系的な養成訓練を行うものとする。 また、開発途上国の科学技術者の養成、指導等についても配慮していくものとする。 9 原子力産業
我が国における原子力研究開発利用の着実な進展を図るためには、信頼性の高い原子力関連機器、核燃料等を、経済的かつ安定的に供給することができるような原子力産業の発展が不可欠である。また、原子力産業は、研究開発要素の多い知識集的型産業であり、その発展は、我が国の産業構造の高度化にも貢献するところが大きい。 原子力産業は、今後の発電規模の増大に伴い、我が国における主要な産業分野の一つに成長することが期待されており、関係企業においても、これに備えた一層の企業努力が要請されている。原子力の研究開発利用は、自主技術により進める必要があることは、既に述べたところであり、産業界においても、この点を踏まえ、自ら開発するとの姿勢を一層強めることが必要である。 我が国の原子力産業は、近年急速に成長してきており、原子力関係機器の売上げは、大きな伸びをみせている。また、原子炉機器の製造能力も、技術的に高い水準に達し、この結果、新たに建設される原子力発電設備の国産化率も、95パーセントを超えるまでになっている。 しかしながら、原子力産業のこのような成長にもかかわらず、その産業基盤は、未だ十分なものとは言い難い。これは、特に原子炉機器製造分野において、多くの研究開発や技術蓄積と多額の設備投資を要するにもかかわらず、近年の原子力発電所の立地の難航等のため、受注が安定しないことが一つの原因となっている。今後、原子力発電の立地が円滑に進み、原子炉の建設基数が増加すれば、逐次、原子炉製造企業の収支も改善され、産業基盤も安定していくものと考えられるが、原子炉受注の一層の安定化を図るとの観点からは、経済面、技術面で海外企業との競争力を養うべく、自主技術開発等一層の企業努力が必要である。また、併せて各企業による共同研究、共同受注等の体制についても検討する必要がある。 なお、本格的な輸出産業として発展させるためには、核燃料サイクルの分野での海外への役務供給体制を、併せ確立することが前提となると考えられ、この面での関連産業の努力が必要である。この場合、核不拡散の観点にも、十分配慮する必要がある。 また、現在進めまれている軽水炉の改良・標準化は、機器の信頼性の向上、設計・製作の規格化の促進を通じ、総合的な技術蓄積と生産の合理化を図ることができるなど、産業面における大きな効果が期待されるので、かかる観点からも、政府及び民間は、協力して軽水炉の改良・標準化に一層の努力を払うものとする。 核燃料加工の分野については、既に産業として定着しつつあり、今後は技術の一層の向上と、核燃料の安定供給が行われることを期待する。 高速増殖炉やウラン濃縮機器の製造等、新しい技術の産業分野については、関連企業においても、研究開発努力が払われる必要があることはもちろん、より有効な産業体制の整備について検討する必要がある。また、これらの分野においては、動力炉・核燃料開発事業団等が中心となって国のプロジェクトとして進めている研究開発の成果が、円滑に産業界に吸収されるよう配慮するものとする。 なお、電気事業者は、ユーザーとして原子力産業界において極めて重要な役割を果しており、今後とも自主技術開発の推進及びその成果の採用について、一層積極的な姿勢が望まれる。 第3章 原子力研究開発プロジェクトの推進
1 原子力研究開発プロジェクトの推進計画
(1) 我が国の原子力研究開発利用の基本方針は第1章に、その進め方は第2章にそれぞれ示したところであるが、これらに即して今後10年間に推進すべき原子力研究開発の主要なプロジェクトは、付表に示すとおりである。 (2) これらの各プロジェクトの推進に当っては、原子力研究開発利用全体との関連において、総合的、体系的に進めていく必要があることに留意すべきである。 我が国の原子力利用は当面、軽水炉の定着化による発電規模の拡大を図るとともに、昭和70年代には高速増殖炉の実用化を実現し、更に、21世紀早期に究極のエネルギー源である核融合の実用化を目指すことを基軸としている。また、発電以外の分野についても、多目的高温ガス炉の開発、放射線利用の推進等により、原子力利用の裾野を広げることを政策の目標としている。 原子力発電の当面の主力である軽水炉を定着化させ、発電規模の拡大を図っていくためには、工学的側面及び環境的側面双方からの安全研究を推進し、安全の確保に万全を期するとともに、天然ウラン及び濃縮ウランの確保、再処理体制及び放射性廃棄物処理処分体制の確立等の各分野にわたり、発電規模の拡大にみあった核燃料サイクルの確実な整備が必要であり、このような核燃料サイクルのどの要素の一つが欠けても、発電規模の円滑な拡大に支障の生ずる恐れがある。 更に、高速増殖炉の実用化段階に進むに当たっても、高速増殖炉そのものの開発に加えて、プルトニウム燃料の転換、加工、再処理等、高速増殖炉の核燃料サイクルの確立が必要であり、このためには、新型転換炉や軽水炉におけるプルトニウム利用の技術経験が大きく寄与することになる。 発電以外の分野への原子力利用の拡大についても、基礎研究分野での積重ねが重要であるとともに、多目的高温ガス炉、舶用炉の開発は、他の型の動力炉と技術的に関連するばかりでなく、製鉄技術、船舶技術等とも密接に関連するなど、関連する範囲は極めて広範となる。 付表に示す各プロジェクトは、上記のような各プロジェクトの内容的、技術的な相互関連性を十分に考慮して課題が選定されているものであり、これらの推進に当たっては、一つのプロジェクトが遅延した場合に他のプロジェクト、ひいては原子力研究開発利用全体に与える影響について十分評価するなど、総合的、体系的な管理を行い、全体として跛行の生じないようにする必要がある。 (3) ただ、研究開発は、常にチェック・アンド・レビューを行いつつ一歩一歩前進し、それまでに得られた成果を踏まえて、その後の進め方を決めるという性格のものであるため、必ずしも付表に示した計画を今後10年間固定するというものではなく、また、国際的な核不拡散政策の動向や国際的な研究開発の進展等に上じ、既定の計画を変更すべき事情が生ずることもあろう。このため、付表に示した計画は、今後の研究開発の進展、国際環境の変化等を踏まえ、適時にこれを見直し、必要な修正を加えていくべきものとする。 2 原子力研究開発資金の確保
(1)付表の推進計画に基づき、今後の原子力研究開発を進めていった場合、その所要資金は、今後10年間(昭和53年度から昭和62年度まで)で、ウラン資源・ウラン濃縮関係、再処理・放射性廃棄物処理処分関係でそれぞれ約4,000億円、新型動力炉開発関係で約1兆6,000億円、核融合・原子力多目的利用関係で約9,000億円、その他安全研究等で約7,000億円、以上を合計して総額約4兆円(昭和52年度価格)程度にのぼることが見込まれる。 この所要資金推計は、例えば高速増殖炉原型炉建設費のように政府及び民間で分担すべきものについても総額で算入していること、及びこれらの所要資金推計は一つの目安として示したものであって、今後の計画の具体化及び計画の見直しに応じて変動する性格のものであることに留意する必要がある。 また、大型施設の建設が集中する前期5ケ年は、所要資金の伸び率も高いものと見込まれる。 (2) 今後の原子力研究開発資金の確保については、研究開発という基本的性格から、財政面について適切な配慮がなされることを期待する。 他方、その量的制約もあり、原子力研究開発プロジェクトのそれぞれの性格に応じ各種の財源を考慮する必要がある。すなわち。プロジェクトの性格に応じ、民間資金の一層の活用あるいは多様な金融手段の活用について配慮する必要があるほか、原子力を含むエネルギーの研究開発による受益するエネルギー消費者に、その受益に応じた負担を期待する考え方もある。 今後、このような見地を含めて総合的な検討を進め、急増する原子力研究開発資金の確保を図り、もって原子力研究開発利用の計画的遂行を期するものとする。 付表
原子力研究開発プロジェクトの推進計画
1 以下の表は、主要な研究開発プロジェクトについて、今後10年間の研究開発課題、そのスケジュール等を示したものである。 2 表では、国が関与する研究開発に限っており、民間が独自に進める研究開発は含めていない。但し、研究開発プロジエクトの実用化の段階で必要になると考えられている実証のための各種施設(実証炉等)については、その実施主体が未定であり、今後その検討が必要であるが、とりあえず以下の表に含めてある。 1 ウラン資源開発
天然ウランの安定供給を確保するため、海外におけるウラン資源の調査探鉱を引き続き進めるとともに、製錬技術、転換技術等の研究開発を行う。 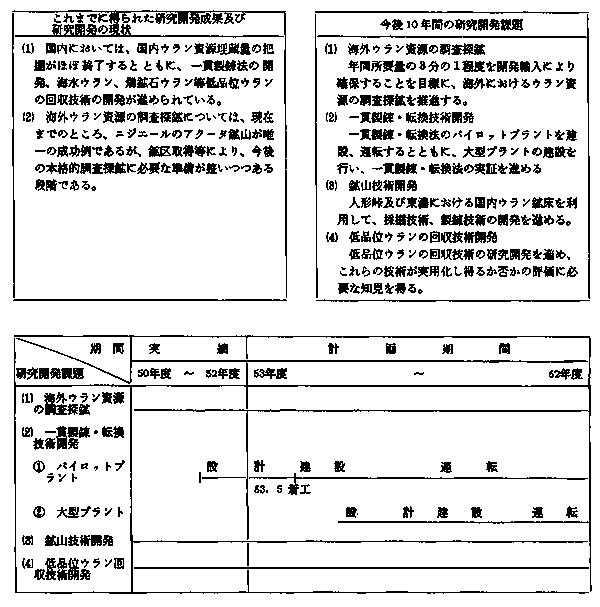 2 ウラン濃縮
自主技術によるウラン濃縮工場を建設するため、遠心分離法によるウラン濃縮技術の開発を進める。また、レーザー法等遠心分離法以外の技術についても所要の研究を行う。 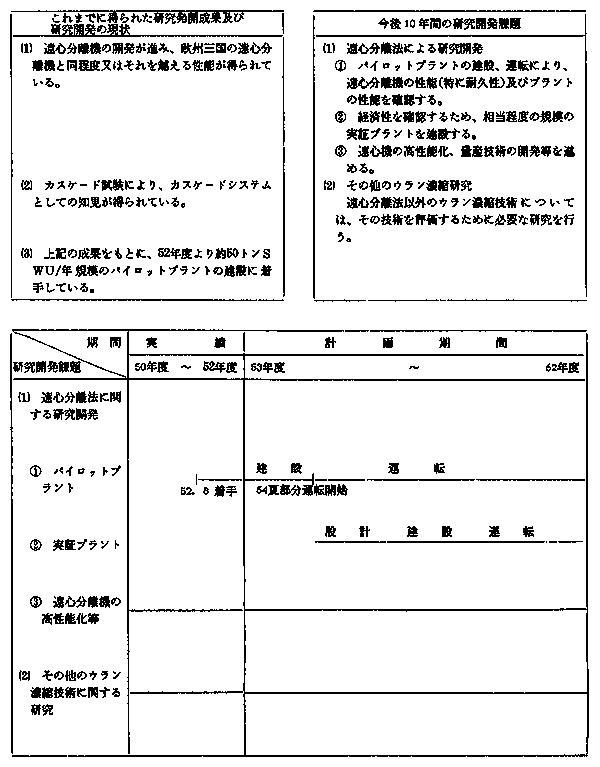 3 再処理及びプルトニウム利用
東海再処理施設の運転を通じて、我が国における再処理技術の確立を図るとともに、放出低減化技術等の再処理関連技術の研究開発を進める。 また、再処理によって回収されたプルトニウムの有効利用を図るため、プルトニウムの軽水炉利用に関する研究開発を進める。(高速増殖炉及び新型転換炉へのプルトニウム利用については、5及び6を参照。)
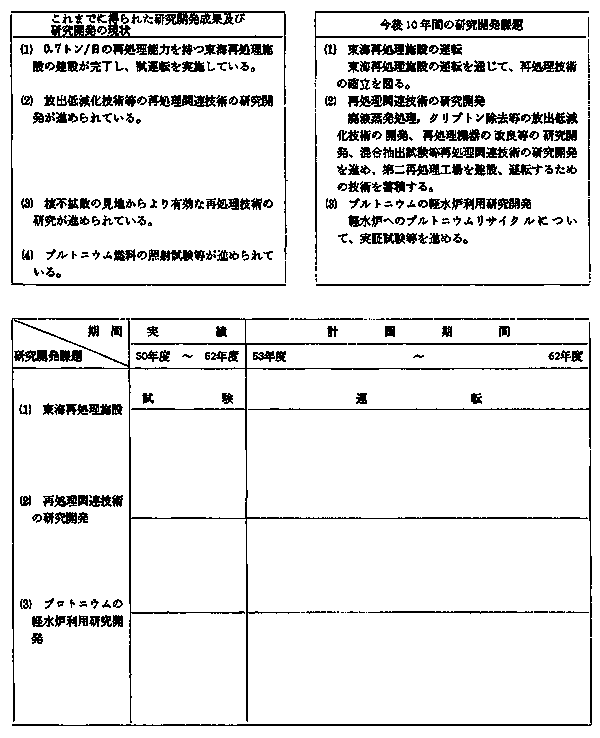 4 放射性廃棄物処理処分
原子力発電所等で発生する中・低レベルの放射性廃棄物及び再処理施設で発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の研究開発を進め、放射性廃棄物の処理処分システムの確立を図る。 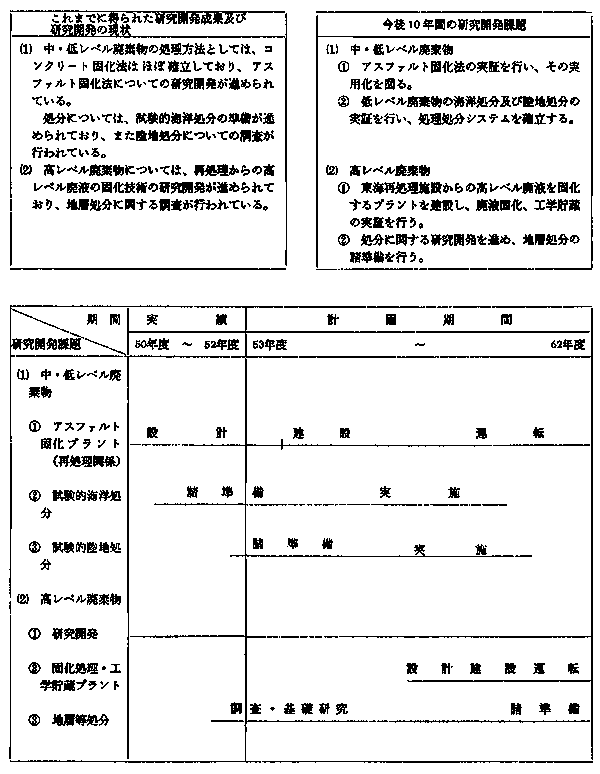 5 高速増殖炉
高速増殖炉(FBR)は、消費した以上の核燃料を生成する画期的な原子炉であり、昭和70年代に実用化することを目標に、その開発を進める。 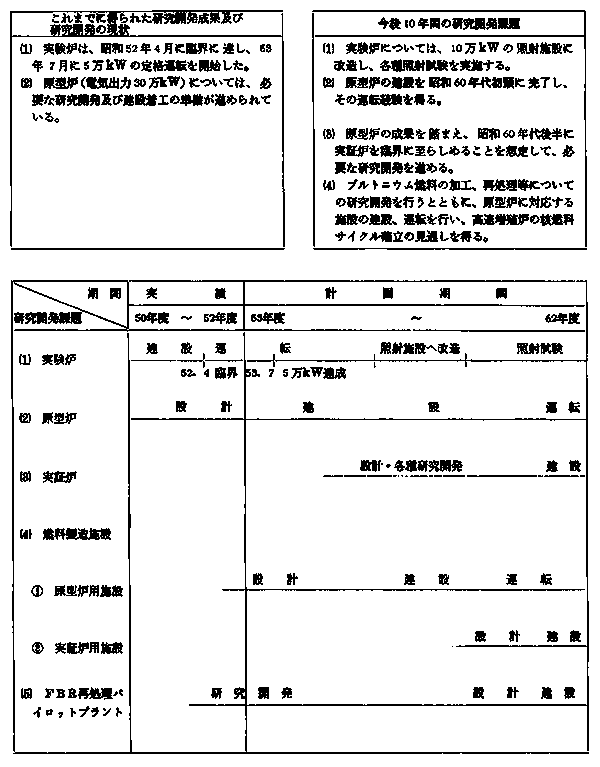 6 新型転換炉
新型転換炉(ATR)は、軽水炉の使用済燃料を再処理して回収されるプロトニウム、減損ウランを有効に利用し、ウラン資源、ウラン濃縮作業量の節減に大きく寄与するものであり、その開発を進める。 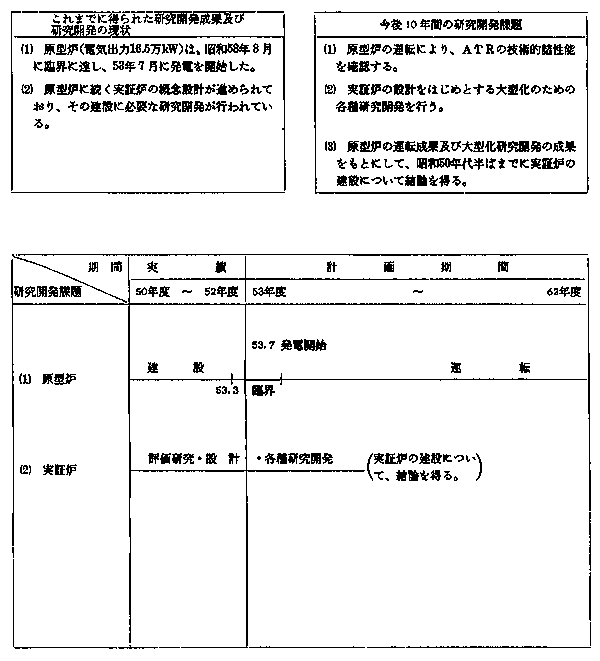 7 多目的高温ガス炉
原子力利用の非電料部門への拡大を図るため、核熱エネルギーを製鉄、水素製造等に多目的利用する冷却材出口温度1,000℃程度の多目的高温ガス炉を開発する。 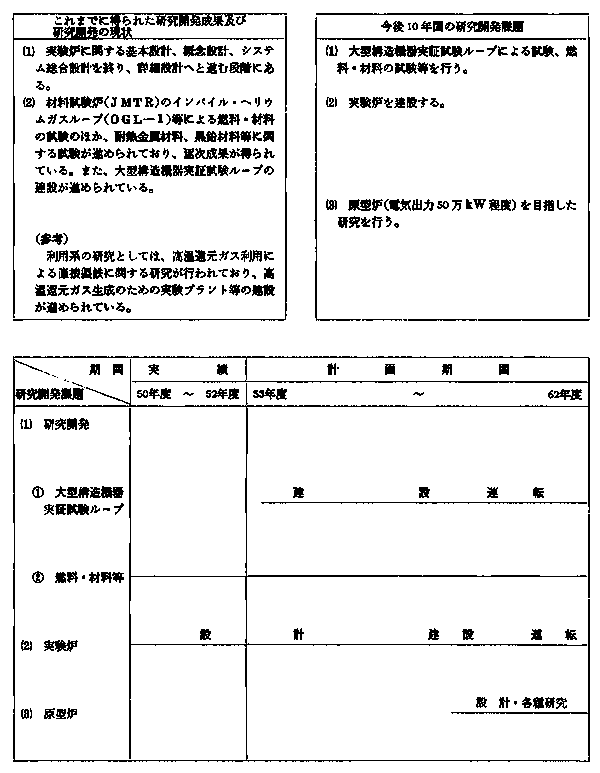 8 核融合
人類究極のエネルギー源として実現が期待される核融合について、21世紀早期の実用化を目指し、長期的な研究開発を行う。 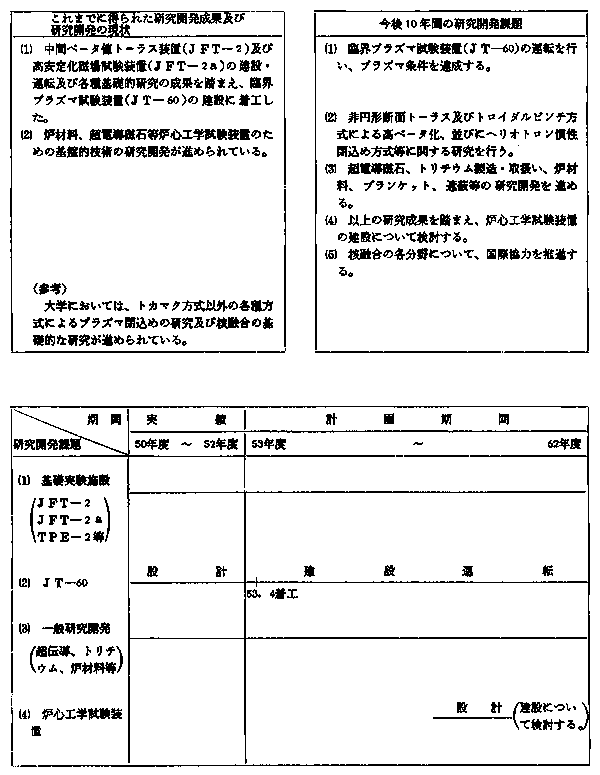 9 原子力船
原子力第1船「むつ」を開発するとともに、舶用炉プラントを中心とそる広範な研究開発等を行う。 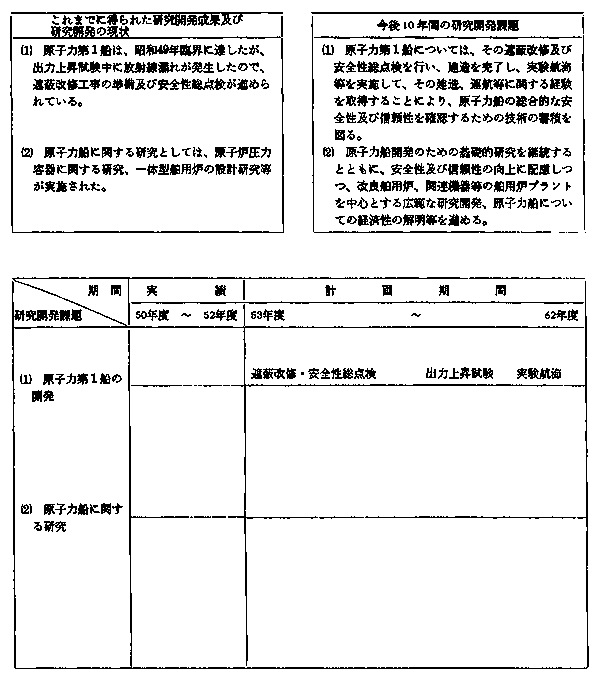 10 工学的安全研究 軽水炉の安全審査に必要な実証的知見の一層の増加を図るとともに、安全審査の基準、指針等の定量化、精密化に資するための安全研究を行う。 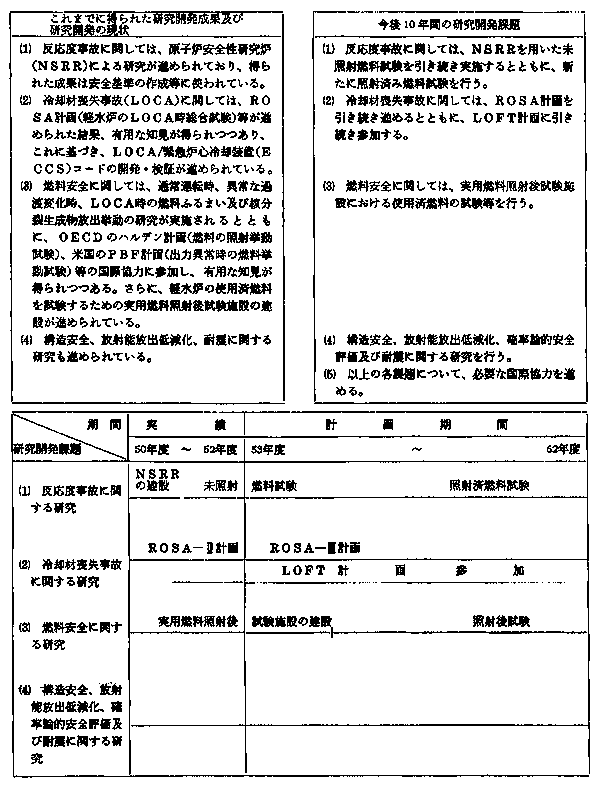 11 環境放射能安全研究
原子力施設から環境中へ放出される放射性物質の環境から人体への移行、ヒトに対する研究を行い、安全審査の基準、指針等の定量化、精密化及び影響の評価に資する。 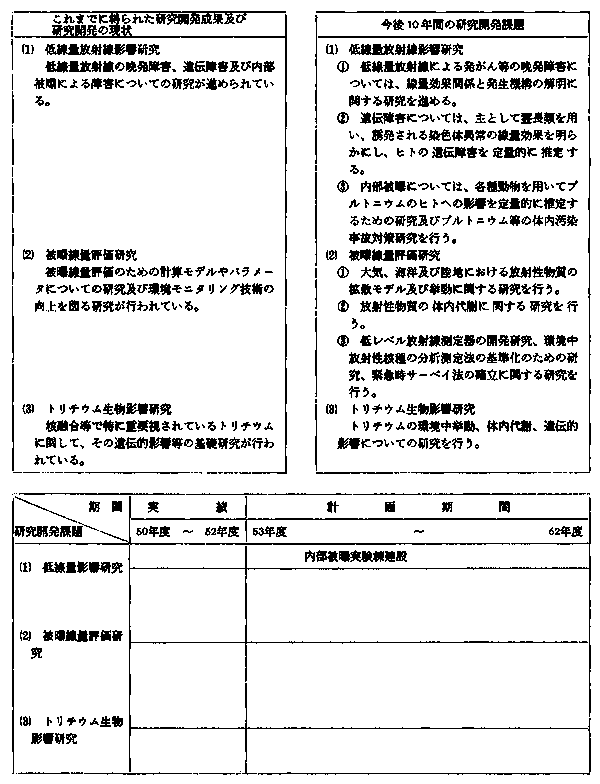 | ||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |