| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
昭和54年度原子力関係経費の見積りについて 昭和53年9月19日
原子力委員会
Ⅰ 昭和54年度施策の概要 エネルギーの確保は、国民の生活水準の維持向上及び社会経済の発展にとって必要不可欠の課題である。国内エネルギー資源に乏しく、一次エネルギーの大宗を輸入石油に依存している我が国は、エネルギー消費の節約を図りつつ、石油代替エネルギーの開発を進める必要があり、石油代替エネルギーとして最も重要な原子力の研究、開発及び利用をエネルギー政策上の最重要課題として推進していく必要がある。 他方、我が国の原子力研究開発利用をとりまく内外情勢は、近年大きく変化しつつあり、これに対する適切な対応が求められてきている。 このため、原子力委員会は、先般、我が国の原子研究開発利用をとりまく内外諸情勢の変化を十分に踏まえつつ、今後約10年間における原子力研究開発利用に関する施策の重点と、その推進計画を示す新たな長期計画を策定したところである。 昭和54年度は、新しい原子力研究開発利用長期計画の実質的な初年度であり、この長期計画に基づき、概要以下のような施策を講じ、原子力研究開発利用の総合的かつ積極的な推進を図るものとする。 なお、近く原子力安全委員会が発足することとなっており、昭和54年度の施策の進め方については、同委員会の考え方を十分に踏まえていく必要があることはいうまでもない。 1 安全対策の総合的強化
(1) 原子力安全行政の強化
原子力安全委員会においては、総合的安全規制政策の確立、行政庁の行った安全審査のダブルチェック、審査基準の策定、公開ヒアリングの開催等積極的な安全施策を展開することとし、これを補佐する事務局体制を整備する。 また、行政庁における安全行政の充実強化を図る。 (2) 工学的安全研究の推進及び安全基準の整備
軽水炉及びこれに付随する核燃料サイクル関連施設に関する工学的安全研究は、日本原子力研究所、国立試験研究機関等において、総合的、計画的に推進する。 日本原子力研究所においては、緊急炉心冷却実験装置による沸騰水型軽水炉の冷却材喪失事故実験(ROSA-Ⅲ計画)及び原子炉安全性研究炉(NSRR)による反応度事故の試験研究を引き続き行う。また、照射後の実用原子炉燃料を試験・検査するための実験燃料照射後試験施設(大型ホット・ラボ)の運転を開始し、照射後試験を実施するとともに、燃料・材料の安全研究、構造安全研究等を実施する。さらに、国際協力による安全研究として、引き続きハルデン計画、LOFT計画、オーバーランプ計画及びPBF計画に参加するほか、新たにデモランプ計画、PNS計画、PHEBUS計画に参加するとともに、ハルデン炉における出力急昇試験を実施する。 国立試験研究機構においては、材料、構造等の基礎的研究を実施する。 これらの安全研究の成果をも踏まえ、軽水炉、核燃料サイクル関連施設、放射性物質の輸送等について、各種安全基準の整備を進めるとともに、国際原子力機関を中心として進められている原子力発電所に関する国際的な安全基準作成事業に参加する。 さらに、新型動力炉の安全研究及び安全基準確立のための関連調査、原子力発電所の地下立地方式の安全性に関する調査等を実施する。 (3) 環境安全の確保
原子力利用に係る環境保全の一層の充実のため、原子力発電所等の環境審査を強化拡充する。 また、原子力施設周辺はもとより、一般環境の放射能水準調査、原子力軍艦の寄港及び外国の核実験に関連する放射能調査等を行い、環境放射能監視り万全を期する。なお、これらの放射能調査のための分析専門機関である(財)日本分析センターの移転計画を推進する。 また、再処理施設等から環境に放出される放射性物質の低減化のための研究開発を動力炉・核燃料開発事業団を中心に推進するとともに、原子力施設周辺及び全国レベルでの線量評価のための各種パラメータに関する調査研究等、環境放射能に関する研究を放射線医学総合研究所等において実施する。 さらに、低レベル放射線の人体に対す影響研究として、放射線による晩発障害、遺伝障害、内部被曝等に関する研究を放射線医学総合研究所を中心に推進する。特にプルトニウムの内部被曝研究を強化するため、内部被曝実験棟の建設の着手する。 この他、低レベル放射性廃棄物の安全な処理処分システムを確立するため、廃棄物パッケージの基準化を進めるとともに、試験的海洋処分については、船舶の改造等の諸準備を進め、試験的海洋処分を開始する。また、陸地処分についても調査を進める。 (4) 原子力事業従業員の安全対策の強化
原子力事業従業員の受ける線量の記録を一元的に管理する線量登録管理事業を引き続き整備するなどにより、原子力事業従業員の安全対策を強化する。 (5) 放射性物質輸送の安全確保
放射性物質輸送関係規則の新基準徹底のため、輸送事業者に対し講習会等による安全指導を強化する。また、使用済燃料の国内輸送の本格化等、放射性物質の輸送量の増大に対応して安全輸送基準の整備強化を図るため、輸送時の各種基準に係る調査・検討を行うとともに、関係機関の協力を得て輸送中の放射線事故等のトラブル処理のための緊急時体制の整備を進める。 さらに、核燃料物質の陸上輸送中の安全性評価のための調査検討を進める。 (6) 放射性同位元素等の安全確保
放射性同位元素等の量的、質的な拡大に対応して、放射線障害防止の強化、充実を図る。 (7) 原子力発電設備の改良・標準化
現在建設、運転が進められている軽水炉について、信頼性の向上、保守点検作業の的確化、作業員の被曝低減化等の観点から、自主技術による改良・標準化推進のための調査及び原子力発電機器の品質保証対策のための調査を行う。 また、原子力発電検査機器を開発するための調査を行う。 2 核燃料サイクル確立のための施策の推進
(1) ウラン資源の確保
動力炉・核燃料開発事業団による海外ウランの調査探鉱活動を強化するとともに、民間企業による海外ウラン探鉱開発活動に対する融資の円滑化等積極的な助成、協力を行い、ウラン資源の確保に努める。 また、ウラン資源開発のための研究開発を動力炉・核燃料開発事業団を中心に推進するとともに、低品位ウラン鉱の処理技術の企業化を目指し、新技術開発事業団による委託開発を進める。 (2) 濃縮ウランの確保
遠心分離法によるウラン濃縮技術の早期確立のため、動力炉・核燃料開発事業団においてパイロットプラントの建設を進めるとともに、新たに実証プラントの概念設計を行う。また、より高性能の遠心分離機の開発、遠心分離機量産化技術の開発等を引き続き進める。 さらに、濃縮ウランの備蓄を推進するとともに、ウラン資源国との協力等の観点から、国際共同事業についての調査を進める。 (3) 使用済燃料の再処理及びプルトニウム利用
動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設については、所要の施設整備を行うとともに、操業を行い、再処理技術の実証と確立を図る。 また、民間による第2再処理工場の建設に備えて、動力炉・核燃料開発事業団において、再処理の改良技術、放射性物質の放出低減化技術等の研究開発を進める。さらに、再処理関連施設を同一サイトに立地するいわゆるコ・ロケーション方式の採用の検討を進める。 プルトニウムの利用については、新型動力炉及び軽水炉への利用に関する研究開発を進めることとし、軽水炉へのプルトニウム利用の実証に関する調査、動力炉・核燃料開発事業団によるプルトニウム加工技術の開発、プルトニウム燃料の照射試験等を行う。 (4) 放射性廃棄物処理処分
再処理施設で発生する中・高レベル放射性廃棄物については、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を中心に、固化処理等の技術開発を推進するとともに、固化体の長期保管、地層処分等に関する調査研究及び処理処分に関する安全評価試験を実施する。 また、放射性廃棄物処理処分の事業化に関しては、そのフィージビリティ調査を行う。 (5) 「国際核燃料サイクル評価(INFCE)」への参加
昭和52年10月から開始された「国際核燃料サイクル評価(INFCE)」については、原子力の平和利用と核拡散の防止とは両立可能であるという我が国の立場に立脚しつつ、これに積極的に参加する。 3 新型動力炉、核融合等の研究評研プロジェクトの推進
(1) 高速増殖炉及び新型転換炉の開発
長期的観点に立った核燃料の有効利用を目指す次代の新型動力炉である高速増殖炉及び新型転換炉の開発を、動力炉・核燃料開発事業団が中心となって、日本原子力研究所等の協力のもとに進める。 高速増殖炉実験炉については、7.5万kWの定格運転を進めるとともに、照射用炉心への移行のための諸準備を行う。 同原型炉については、設計研究、炉物理、炉体構造、燃料・材料、安全性、蒸気発生器等の研究開発を進めるとともに、地元の受入れ体制が整い次第、仮設工事等の建設の諸準備を進め、昭和60年度臨界を目途に、本体製作に着手する。 新型転換炉の原型炉については。定格運転を開始し、運転経験を蓄積するとともに、大型炉の調整設計等を実施する。 また、高速増殖炉及び新型転換炉に使用するプルトニウム燃料の開発・製造を行うとともに、高速増殖炉の使用済燃料を再処理する技術を確立するため、所要の研究を進める。 (2) 核融合の研究開発
究極のエネルギー源である核融合動力炉の実現を目指し、その前提となる臨界プラズマ条件を達成するための研究を推進する。 日本原子力研究所においては、既定のスケジュールに沿って、臨界プラズマ条件達成を目指した臨界プラズマ試験装置(JT-60)の建設を進める。また、トーラスプラズマの研究、プラズマ加熱の研究開発、核融合炉心工学、炉工業技術の研究開発部を推進するとともに、臨界プラズマ試験装置等の核融合研究施設の建設用地の確保等、サイトの整備を進める。 電子技術総合研究所においては、高ベータ・ブラズマの研究のため、昭和56年度完成を目標に圧縮加熱型核融合装置(TPE-2)の建設を進めるとともに、理化学研究所においては、プラズマの診断・真空技術の基礎的研究、金属材料技術研究所及び名古屋工業試験所においては、材料の基礎的研究を行う。 また、臨界プラズマ条件達成後に必須となる超電導磁石技術及びトリチウムの製造・取扱い技術について、日本原子力研究所、電子技術総合研究所、金属材料技術研究所等において研究開発を拡充強化する。特に、超電導磁石技術に関しては、OECD-IEAの大型超電導磁石国際協力(LCT計画)に基づき、日本原子力研究所において、LCTコイルの製作を開始する。 この他、日米第二国間及びIAEA等多数国間の国際協力を推進し、我が国の核融合研究開発の効率的実施に資することとする。 (3) 多目的高温ガス炉の研究開発
製鉄、水素製造等非電力部門への核熱エネルギーの利用を目的とした多目的高温ガス炉の開発については、日本原子力研究所において、60年代前半の完成を目指して、実験炉の詳細設計を開始する。さらに、プラント機器の安全性を実証するための大型構造機器実証試験ループ(HENDEL)の製作を引き続き行うとともに、その建家の建設に着手する。また、炉心耐震試験、高温構造試験等各種実証試験を実施するとともに、被覆粒子燃料、黒鉛材料、耐熱金属材料等の研究及び伝熱流動試験等の研究開発を推進する。 (4) 原子力船の開発
原子力船の開発については、日本原子力船開発事業図において、原子力第1船「むつ」の遮蔽改修工事及び安全性総点検を実施するとともに、新定係港について、諸準備を進める、
また、船舶技術研究所においては、原子力船についての基礎的研究を実施する。 4 保障措置及び核物質防護対策の強化
核兵器の不拡散に関する条約に基づく国内保障措置体制の整備のため、収去試料分析用機器、査察用機器等を整備するとともに、核物質に関する情報処理、収去試料の分析等の業務を外部専門機関に委託する。 また、国内核物質防護体制の整備のため、法制面の検討等所要の施策を実施する。 5 基礎研究の充実及び原子力研究開発利用基盤の整備
(1) 基礎研究の充実
我が国独自の原子力技術の研究開発を進めるため、その基盤となる基礎研究を、日本原子力研究所、理化学研究所及び国立試験研究機関において、大学との緊密な連携のもとに推進する。また、所要の研究を民間に委託して行う。 日本原子力研究所においては、材料試験炉等による各種燃料・材料の照射試験を引き続き実施する。 また、タンデム型重イオン加速器の運転を行い、材料の照射損傷、核データ等の研究及び核融合等の開発に資する。さらに、食品照射の実用化の見通しを得ることを目標に、国立試験研究機関、理化学研究所等と協力して、毒性試験及び遺伝的安全性試験等の研究開発を進めるほか、放射線化学関係の研究、ラジオアイソトープの生産及び利用を推進する。 理化学研究所においては、重イオン科学用加速器の建設を完了し、重イオンに関する各種研究を開始する。また、リングサイクロトロンの建設に関して予備的研究を行う。 放射線医学総合研究所においては、サイクロトロンを用いて、速中性線によるガンの治療研究を引き続き進めるとともに、新たに陽子線による研究に着手し、さらに短寿命アイソトープの生産、利用の技術開発を推進する。 この他の国立試験研究機関においても、電子技術総合研究所において放射線標準に必要となる加速器整備を行うなど放射線利用に関する研究を強化する。 また、ラジオアイソトープの廃棄物対策のための施策を講ずる。 (2) 人材養成
原子力関係科学技術者の養成訓練については、大学に期待するほか、海外に留学生として派遣し、その資質向上に努める。また、日本原子力研究所のラジオアイソトープ・原子炉研修所及び放射線医学総合研究所養成訓練を実施する。 (3) 国際協力の推進
原子力における国際協力の質的、量的拡大に対処するため、国際協力関係業務の強化拡充をはかり、日豪協定改訂交渉をはじめとする協定関連交渉に適切に対処するなどにより、我が国原子力研究開発利用の円滑な推進に資する。 また、二国間原子力協力協定に基づく協力を推進するほか、国際原子力機関及びOECD原子力機関等を通しての多国間協力を推進し、科学技術者の交流、情報の交流、国際的共同事業等を進める。さらに、これら国際協力の推進に対応した国内体制の整備を図る。 6 国民の理解と協力を得るための施策の推進
原子力研究開発利用の円滑な推進のためには、原子力研究開発利用について広く国民の理解と協力を得ることが極めて重要である。このため、安全対策の強化、核燃料サイクルの確立、温排水有効利用のための研究等を推進するほか、以下の施策を進める。 (1) 電源三法の活用
電源立地促進対策交付金については、建設費及び財政状況のよる頭打ち制度を撤廃する。 放射線監視交付金及び温排水影響調査交付金については、交付期間を原子力発電施設等の運転の終了までの期間として、立地の円滑化を図る。同じく電源三法に基づく交付金等により、広報活動の充実、強化を図る。 さらに、安全性実証試験として、大型再冠水効果実証試験、蒸気発生器信頼性実証試験、放射性廃棄物安全性実証試験、使用済燃料輸送容器信頼性実証試験等を日本原子力研究所、(財)原子力工学試験センター、(財)原子力環境整備センター、(財)電力中央研究所等に委託して実施する。 また、原子力施設の耐震信頼性実証試験に対する補助金の交付を行う。 (2) 広報活動の強化等
原子力研究開発利用に対する国民の理解を求め、原子力研究開発利用を一層円滑に推進するため、テレビ、出版物等による広報、公開ヒヤリング、講演会、各種セミナー等の開催、オピニオンリーダーに対する資料送付、婦人層に対する広報、原子力映画の作成などの広報活動を積極的に推進する。 また、原子力モニターの卒直な意見、提案等を積極的に聴取する。 さらに、原子力施設等の立地を円滑に進めるために原子力施設の立地予定地域の有識者を対象とした原子力研修会等の開催、民間における広報事業の補助を図るとともに、電源立地企画官の機動的活動による原子力発電所の立地に係る地元調整を推進する。 また、運転に入った原子力発電所の立地県には、原子力連絡調整官を配し、地元と国との連絡を進める。 このほか、原子力船「むつ」の佐世保港における修理に当たっては、現地連絡事務所を設置し、担当官を常駐させて地元との連絡調整等を行うものとする。 Ⅱ 見積りの概要 1 見積りにあたっての基本的考え方
(1) 原子力研究開発は、その大規模性、投資の懐妊期間の長さ、関連分野の広範性等から、長期的観点に立って計画的かつ継続的に進める必要がある。 特に、今後、石油代替エネルギー源としての原子力の重要性の高まりと核不拡散を中心とする厳しい国際情勢の中で、高速増殖炉、核融合、ウラン濃縮等大規模化した研究開発プロジェクトを同時並行的に推進していくことが急務となっており、このうちいずれを欠いても、原子力政策の計画的推進が阻害されるという事態になってきている。 このような状況の中で原子力委員会は、今回、原子力研究開発利用長期計画を新たに決定したところであるが、この計画において、今後10年間(昭和53年度~62年度)の原子力研究開発所要資金は、約4兆円(昭和52年度価格)と急増し、しかも安全研究、新型動力炉開発、ウラン濃縮開発、核融合研究等広範多岐にわたる分野において大型施設の建設が集中する前期5ケ年は、所要資金の伸び率も高いものと見込まれている。従って、今後の原子力政策の計画的推進を確保していくためには、この原子力研究開発資金を円滑かつ安定的に確保していくことが喫緊の課題となっている。 (2) 以上の中・長期の見通しの上に立って昭和54年度についてみれば、同年度は、新しい原子力研究開発利用長期計画の実質初年度であって、今後の原子力政策の展開を方向付ける極めて重要な年である。昭和54年度においては、ウラン濃縮技術開発、放射性廃棄物処理処分技術開発、環境放射能安全研究など、今後の原子力政策の展開を図る上でいずれもゆるがせにできない重要プロジェクトの所要資金が増大する。他面、すでに着工した核融合臨界プラズマ試験装置(JT-60)の建設の本格化及び高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の建設着工による所要資金の伸びが著しい。 上記の「JT-60」及び「もんじゅ」の建設は、新しい長期計画の中で中核となるべき重要プロジェクトであるとともに、我が国の基本姿勢を問われるキープロジェクトとして、長期計画で定めたスケジュールからの遅延が許されないものである。 既に「JT-60」については、日本原子力研究所が54年度予算として、国庫債務負担行為限度額(以下 しかし、当委員会としては、これらプロジェクトの我が国エネルギー政策における緊要性よりみて、今後さらに、政府部内において各種の財源措置をも検討の上、これらの原要求の本旨を生かした所要資金確保がなされるべきものと考える。 2 原子力関係機関別の概算要求の概要
(1) 日本原子力研究所
東海研究所、高崎研究所及び大洗研究所の研究部門の充実、研究支援部門の整備等を含め、必要な経費は約665億円(うち政府出資金約623億円、電源開発促進対策特別会計より約26億円)、国庫債務負担行為限度額は約834億円であり、定員増は総計212名である。 うち、原子力施設の工学的安全研究、放射性廃棄物の処理処分の研究等の安全研究に必要な経費は約79億円で、研究の推進体制の整備を図るため、47名の増員を行う。また、核融合研究に必要な経費は約246億円で、核融合研究開発プロジェクト推進体制の整備をはかるため、116名の増員を行う。多目的高温ガス炉の研究開発に必要な経費は約32億円で、20名の増員を行う。 (2) 動力炉・核燃料開発事業団
高速増殖炉及び新型転換炉の開発プロジェクトを推進するために必要な経費は約543億円(うち政府支出金約469億円)、国庫債務負担行為限度額は約1,428億円である。また、動力炉開発プロジェクト推進体制の整備を図るため111名の増員を行う。 ウラン濃縮技術の研究開発プロジェクトを推進するために必要な経費は約198億円、国庫債務負担行為限度額は約252億円である。また同プロジェクト推進体制の整備を図るため、38名の増員を行う。 再処理施設の運転等に必要な経費は約210億円(うち政府支出金約102億円、政府保証借入金46億円)、国庫債務負担行為限度額は約50億円である。また、再処理施設の試運転等のため48名の増員を行う。 その他核燃料物質の探鉱及び製錬をはじめとする核燃料開発に必要な経費は約148億円である。 なお、政府支出金の総額は約913億円、国庫債務負担行為限度額は約1,753億円であり、定員増は総計252名である。 (3) 日本原子力船開発事業団
原子力第1船「むつ」の遮敝改修、安全性総点検、新定係港についての諸準備等に必要な経費は約44億円、国庫債務負担行為限度額は約55億円である。また、このために必要な7名の増員を行う。 (4) 放射線医学総合研究所
内部被曝実験棟の建設及び粒子加速器の医学利用、低レベル放射線の影響並びに環境放射線の被曝に関する特別研究の強化拡充等に必要な経費は約44億円、国庫債務負担行為限度額は約59億円である。また、このために必要な8名の増員を行う。 (5) 国立試験研究機関
原子力施設の安全研究、核融合、食品照射、放射線の医学利用に関する試験研究及び施設等の維持運営等原子力研究に必要な経費は約16億円、国庫債務負担行為限度額は約8億円である。 (6) 理化学研究所
核融合、食品照射、環境放射線、重イオン科学、サイクロトロン等の研究及び重イオン科学用加速器の建設等原子力研究に必要な経費は約11億円である。 (7) 新技術開発事業団
低品位ウラン鉱の連続浸出処理技術の企業化のための委託開発に必要な経費は、約2億円(事業費ペース)である。 Ⅲ 概算要求総表 1 科学技術庁一般会計概算要求総表 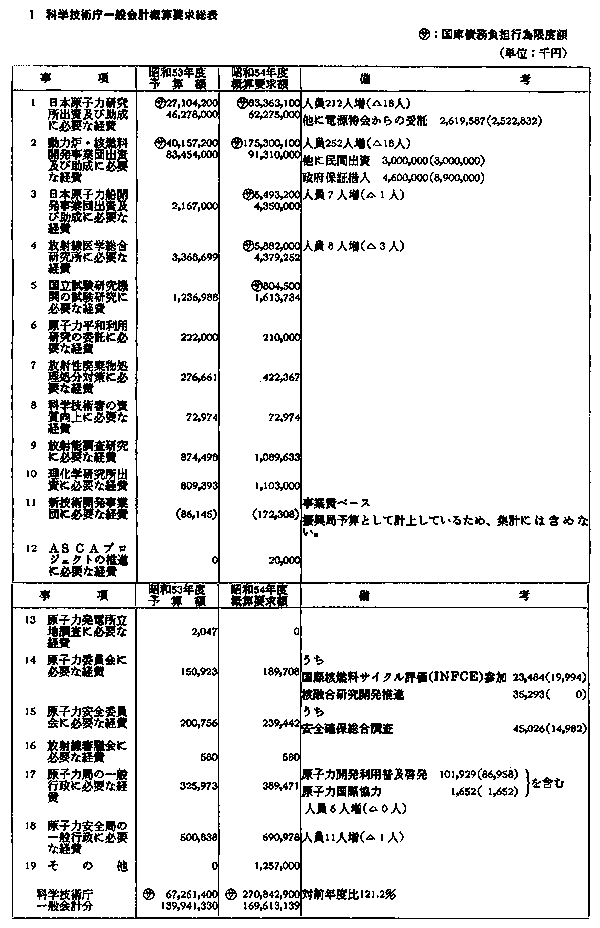 2 同 重要事項別総表 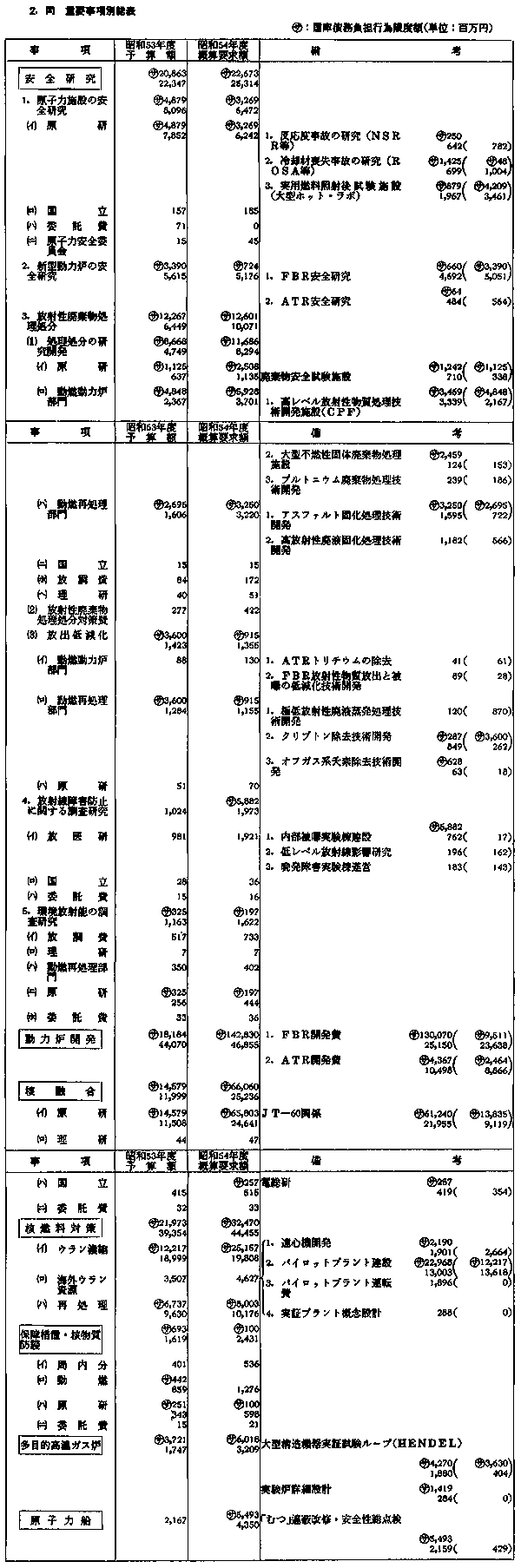 3 各省庁(科学技術庁を除く。)一般会計概算要求総表 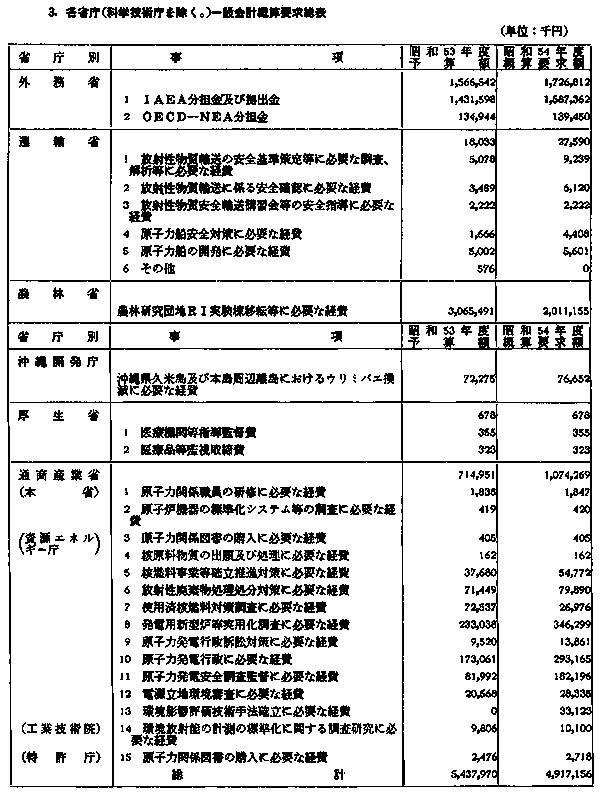 4 電源開発促進対策特別会計概算要求総表 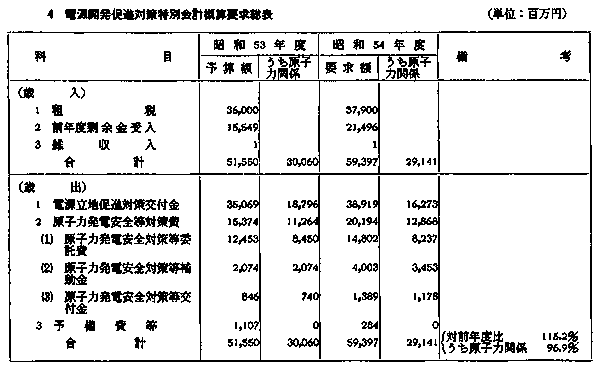 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |
 という。)912億円、現金408億円を要求し、また「もんじゅ」については動力炉・核燃料開発事業団が
という。)912億円、現金408億円を要求し、また「もんじゅ」については動力炉・核燃料開発事業団が