| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
核物質防護専門部会第一次報告について 昭和52年9月6日
原子力委員会委員長
宇野宗佑殿
核物質防護専門部会部会長
川島 芳郎
当専門部会は、昭和51年4月23日付け51原委第378号「核物質防護専門部会の設置について」に従って調査審議を行ってきたが、別添のとおり第一次報告書をとりまとめたので報告する。 (別添)
核物質防護専門部会第一次報告書
第1節 核物質防護をめぐる動向
原子力の開発利用の進展に伴い、核物質、とりわけ高濃縮ウラン、プルトニウム等の特殊核分裂性物質の取扱い量は、世界的に急速に増大してきているとともに、その輸送機会も著しく増大してきている。 一方、近年、組織化された暴力集団等による不法行為に対する不安が増大してきていると同時に、初歩的な核爆発装置の製造に対する知識あるいはプルトニウム等の不法な散布による有害性に関する知識が広まりつつある。 このような状況を背景に、核物質の盗取あるいは原子力施設に対する妨害、破壊等の事件の発生が危惧されるところとなっており、これに伴い、世界的に核物質を不法行為者の手から防護することの重要性が強く認識されてきた。 国際原子力機関(IAEA)は、1975年9月、各加盟国が自国の核物質防護制度を検討する上でのガイドラインとして「The Physical Protection of Nuclear Material」(以下「INFCIRC/225」という。)を発表し、各加盟国に対し、核物質防護制度を強化するよう呼びかけを行った。 また、これらのIAEAの活動と並行して、米国、英国、西独等各国においては、それぞれの国内措置を講じてきている。とりわけ、米国は、1969年に原子力規制委員会(NRC)規則10 CFR Part 73「Physical Protection of Plants and Materials」を制定し、その後数次にわたり改正を行う等核物質防護措置の強化を精力的に進めてきた。 さらに、とくに近時に至り、核の拡散に対する極めて厳しい世界的な潮流の中において、核物質の盗取等に起因する核の拡散が大きな問題として取り上げられてきており、このような見地から核物質防護の重要性はとみに高まり、核物質防護をめぐる動きは急速に活発化してきている。 例えば、本年2月には、IAEAにより、INFCIRC/225の見直しのための専門家会合が開催された。また、同文書は世界各国において一つのガイドラインとして好意的に受けとめられ、二国間原子力協力協定に引用される事例も生ずるに至っている。 また、米国は、本年3月に、前記10 CFR Part 73に原子力発電所に対する妨害、破壊行為に対する防護の要件を追加したほか、本年7月には、本Partを大幅に強化すべく改正案の提示を行った。 さらに、とくに注目すべき動きとして、原子力資材の輸出入にあたっての条件の一つとして核物質防護の問題が取り上げられてきたことがあげられる。 一昨年来、原子力資材の輸出国間で進められてきている輸出の際のガイドラインに関する検討においても、核物質防護の問題が取り上げられている。また、カナダは、1974年12月及び1976年12月にそれぞれ原子力輸出政策を発表し、その後、それを受け、我が国をはじめ各国との間に締結している原子力協力協定の改訂交渉に入っているが、その交渉において、原子力資材の輸出のための条件の一つとして、輸入国が適切な核物質防護上の措置を講じることを要求している。さらに、豪州は、本年5月発表した保障措置に関する新しい政策の中において、同様の趣旨を明らかにしている。 以上にみられるように、適切な核物質防護措置を講ずることについて、国際的に一定の約束を行うことが、原子力資材の移転に当たっての不可欠の要件となりつつある。 また、核物質防護に関する多国間の協約づくりの動きもみられるに至っている。 第2節 我が国における核物質防護の現状及びその充実強化の必要性
我が国では、核物質に対しては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」等関係法令の実施運用により、核物質防護に対する重要性の高まりを反映して既に種々の防護措置が講じられてきており、我が国の主要な原子力施設の防護状況を、例えば、INFCIRC/225に示されている核物質防護の要件に照してみると概ね満たし得る状態にあるといえる。 しかしながら、第1節で述べたような動向を踏まえると、核燃料の殆んどを海外に依存せざるを得ない我が国として、石油代替エネルギーのうち最も有望なものとして期待されている原子力の開発利用を推進するためには、核燃料の安定的な供給確保が極めて重要であり、このような見地から我が国の核物質防護制度に対する国際的信頼性を確保すべく、法制面の整備を進め、実施すべき核物質防護措置の内容を明確にするとともに、対応体制を確立する等今一層の努力を払う必要がある。 また、特に、特殊核分裂性物質は、在来の危険物質(例えば火薬)又は有害物質(例えば毒物劇物)に比べ、その持つ特別の性質から、万一、盗難等の事件が発生した場合には、その社会的影響は極めて重大なものとなる。したがって、これら特殊核分裂性物質の防護に関しては、在来の危険物質又は有害物質に比し、より一層慎重な考慮を払い、万全を期する必要がある。 第3節 核物質防護制度の目的及び構成要素
核物質防護のあり方については、INFCIRC/225の発表を契機に、その内容がかなり明確化されてきているものの、未だ流動的な要素を多く含んでいる。 したがって、本問題に関しては、今後の我が国の社会情勢、原子力開発利用の進展の状況、国際的動向等を見極めつつ、引き続き、検討を進めていく必要がある。 現段階においては、とりあえず、対応の第一歩として国際的に共通のガイドラインとして受け入れられつつあるINFCIRC/225を参考として、我が国としての核物質防護制度を検討することが現実的かつ適切であると考えられる。 我が国としての核物質防護制度の目的については、前記の観点から今後もさらに検討を加える必要があるが、当面、次の2点を中心に考えていくものとする。 ① 特殊核分裂性物質の窃取、強取等による不法な移転及び特殊核分裂性物質の取扱施設(以下「原子力施設」という。)又は特殊核分裂性物質の輸送(以下単に「輸送」という。)に対する妨害、破壊行為の発生を未然に防止する条件を確立すること。 ② 不法な移転又は妨害、破壊行為が発生するおそれがある場合又は発生した場合(以下「緊急時」という。)における迅速かつ総合的な対応措置を可能とするために必要な情報及び技術的援助が適確に提供されること。 以上のような目的を実現するための核物質防護制度の基本的な枠組みとしては、次のような構成が考えられる。 i)(規制の体系)国は、個々の原子力施設、又は輸送において実施すべき核物質防護措置の内容を明確にし、その義務付けを行うとともに、その遵守、履行を定常的に確認する。 ii)(実施の体系)事業者等は、上記義務付けの遵守、履行という形で規制の体系を具現化する。これは、基本的には、特殊核分裂性物質という社会的危険物を取扱う者としての各事業者等の責任においてなされるものであるが、核物質防護の特殊性にかんがみ、国としても、その盗難等の事件が発生することのないよう事業者等と一体となり、万全を期することが必要である。 iii)(支援の体系)規制-実施の体系を円滑に機能させるため、関連研究開発の推進等を図る必要がある。 一方、核物質防護制度の目的は、前記のとおり、妨害、破壊行為等の発生の未然防止と対応措置の迅速な発動にあるところから、治安当局の原子力施設周辺又は輸送における警戒活動、緊急時における出動等の迅速かつ総合的な対応措置を可能とするための体制が整備されることは、核物質防護制度にとっては、不可欠の前提であり、この対応体制の整備が必要である。 第4節 核物質防護の要件
第3節において述べた核物質防護制度の目的を実現するため、事業者等が原子力施設及び輸送において実施すべき核物質防護措置の要件としては、別表1に掲げる各区分に応じ、別表2の各項目が満たされる必要がある。 この要件は、原子力施設又は輸送に対し、不法な攻撃があった場合、その攻撃を速やかに把握し、その旨を適確に治安当局に通報するとともに、治安当局が当該攻撃に対応し得るまでの間、防護設備等の物的な防護手段をもって、当該攻撃の達成を遅滞させることを基本に一般的、共通的指針として作成したものである。また、この要件は、防護用設備、機器等のハードウェアと枢要な区域の設定、当該区域の人の出入の管理、監視、防護関係組織等のソフトウェアを一体として、いわばトータルシステムとして前記の基本的考え方を満足すべきものである。 したがって、この要件は、原子力施設が置かれている地理的条件等の原子力施設の特性、各種輸送形態の特性その他特殊な事情を考慮し、代替的な方途を含め、弾力的に適用されるべきものであるとともに、今後の技術的進歩、社会的環境の変化等に応じて今後、引き続き、見直されるべきものである。 なお、区分の設定については、INFCIRC/225に示されている区分が国際的に一応のガイドラインとして受け入れられてきていること、核物質防護は国際的共通性を強く求められていること等にかんがみ、INFCIRC/225の区分を採用することとした。 第5節 核物質防護制度の充実強化のための方策
核物質防護制度の充実強化を図るため、政府においては、当面、次の方策を講ずる必要がある。 1 法制面の整備
我が国においては、特殊核分裂性物質の管理に関し、既に原子炉等規制法等の関係法令に基づき所要の規制が行われている。したがって、事業者等が実施すべき核物質防護措置に係る規制は、これらの既存の関係法令の枠組みを活用して行うことが、適切かつ現実的である。 このため、既存の関係法令につき、前節の核物質防護の要件の目的とするところが、それぞれの関係法令に基づき、実現し得るか否かの検討を進め、必要に応じ、逐次、それらに必要な要件を付加し、法制面の整備を進めていくことが必要である。 なお、特殊核分裂性物質の窃取者等不法行為者に対する特別な罰則体系等については、国際的動向を見極めつつ、検討を進める必要がある。 2 対応体制の整備等
(1)緊急時における対応体制の整備
緊急時における対応措置、すなわち緊急時における治安当局の出動、不法移転された特殊核分裂性物質の回収、不法な攻撃に伴い何らかの災害が生じた場合の対策等につき、迅速かつ総合的な対応をとり得る体制が整備されることは、核物質防護体制の確立を図る上で不可欠の前提である。これらの対応措置の多くは、政府が中心となってあたるべきものであり、政府が関係機関の協力を得つつその実施体制を整備する必要がある。 このため、次の諸点について早急に検討を進める必要がある。 i)緊急時のそれぞれの程度に応じた対応措置に関する行動プログラムを作成すること及び当該対応プログラムに即して、事業者等、政府関係機関間において、それぞれの役割、とるべき具体的措置、手順等について事前の調整を行うこと。 ii)緊急時における事業者等からの通報受理体制の整備を図ること及び受理した通報の内容を適確に把握し、状況に応じ必要な関係機関へ連絡し、あるいは臨機にとるべき措置について判断等を行うための組織体制を確立すること。 iii)緊急事態の発生現場において、治安当局の活動と並行して、不法移転された特殊核分裂性物質の回収に際しての技術的助力等の対応活動にあたるチームを、既存の関係機関の機能及び能力を踏まえて、あらかじめ整備しておくこと。 (2)治安当局の対応体制の整備
事業者等が実施すべき核物質防護の要件については、第4節で述べたとおり、治安当局が不法な攻撃に対応し得るまでの間、物的な防護手段をもって、当該攻撃の達成を遅滞させることを基本に作成しており、不法な攻撃を制止し、鎮圧することは、治安当局に依存するとの考え方に立脚している。 したがって、事業者等が実施する核物質防護措置の実効を期するためには、それと密接な連携が図られるべき治安当局の体制の整備が不可欠である。 このため、治安当局による原子力施設周辺又は輸送における警戒活動、緊急時における出動等の対応能力の一層の拡充強化を図る必要がある。 (3)関係行政機関の連絡調整体制の整備
核物質防護は、警察庁、科学技術庁、外務省、通商産業省、運輸省等の多くの行政庁の所掌に係るものであり、また、核物質防護の内容はその時々の社会的環境に応じて整備される必要があることから、昭和50年9月に設置された核物質防護に関する関係省庁連絡会議の場を活用して、関係行政庁の緊密な連絡調整を図ることが重要である。 3 関連研究開発の推進
核物質防護措置を実施するうえで、侵入警報装置等の防護用の設備、機器等は、非常に有用であるが、これらに関する研究開発は、世界的にも比較的歴史が浅く、近年になって急速に努力が払われつつある状況にある。 また、各原子力施設レベルにおける、さらには国レベルにおけるトータルシステムとしての核物質防護に関するシステム設計及びその評価に関する研究等は未だ緒についたばかりの段階である。このような状況において、今後、我が国として効果的な核物質防護体制を整備していくためには、関係研究開発を強力に推進していく必要がある。 このため、まず、我が国として真に必要とされる研究開発課題の体系的整理を行い、その結果に沿って、この分野の研究開発が比較的に進んでいる米国をはじめ、関係国との国際協力に配慮しつつ、その推進を図る必要がある。 なお、この分野の研究開発が全般的に未だ初期的な段階に止まっていること、市場性に乏しいこと、機微な情報を必要とする特殊な分野を包含すること等にかんがみ、政府として、積極的にその推進を図る必要がある。 4 国際協力の推進
核物質防護の問題は、それぞれの社会の実態に対応して検討されるべきものであるという面において、すぐれて地域的な問題であると同時に、特殊核分裂性物質の国際間移転の機会が著しく増大してきていること、特殊核分裂性物質に関連する不法行為によってもたらされる影響が国際的な広がりを持つ可能性があること等から、国際的な共通性を強く求められるものでもある。とりわけ、近時、核物質等の輸出国が輸入国に対し、当該核物質等に係る核物質防護を強く要求してきているという状況のもとでは、国際的にも信頼性を確保し得る核物質防護上の措置を講ずることが肝要となってきている。したがって、核物質防護に関し、共通的事項の調査、研究開発、国際的ガイドラインの整備等の面で国際協力を積極的に進めていく必要がある。 一方、国際間の輸送における核物質防護については、輸送計画書の作成、荷送人、運送人、荷受人間の連絡調整等国内輸送と共通する部分も多いが、国の管轄権の問題、核物質防護責任の移転の問題、相手国の核物質防護制度との調整の問題等、これに特有な問題もある。このような点に着目して、IAEAを中心に国際的な検討が進められようとの動きがある。我が国としても、濃縮ウランの輸入あるいは使用済燃料の海外再処理のための移転等に何らかの支障が生ずることのないよう、このような検討に積極的に参加し、対処していく必要がある。 なお、このような検討において結論を得るには、相当な時日を要するものと考えられるが、それまでの間は、それらの検討の経緯を見極めつつ、ケース・バイ・ケースで相手国との話し合いに従って処理していくことが肝要である。 別表1 核物質防護の区分 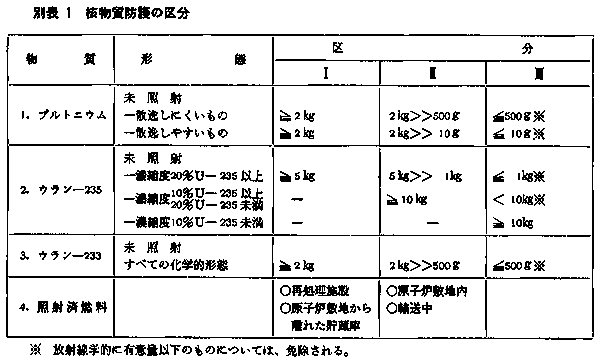 別表2 核物質防護の要件
区分Ⅰ
1 使用中及び貯蔵中の核物質防護の要件
(核物質防護のための区域の設定)
1.1 核物質防護のための区域(以下「区域」という。)を設定すること。 1.2 区域の設定は、二重以上のものとすること。 1.3 設定した区域のうち、外部のもの(以下「外部区域」という。)は、フェンス等の障壁によって囲うこと。 1.4 外部区域の境界周辺には、適切な照明装置を設けること。 1.5 設定した区域のうち、内部のもの(以下「内部区域」という。)は、堅固な構造の障壁によって囲うこと。 (区域の監視)
2.1 区域は、警備を担当する者(以下「警備人」という。)により、所定の頻度及び方法で巡視すること。 この場合、侵入警報装置等の機械的監視により補完してもよい。 2.2 特殊核分裂性物質を取扱う者は、職務交替時に、特殊核分裂性物質の不法な移転又は原子力施設に対する妨害、破壊行為が認められなかったことを確認し、その旨を、又は異常があると認められるときには、その旨を速やかに上級者に報告すること。 (区域の出入管理)
3.1 職務上常時区域の出入を行う者は、事前に許可を与えた者に制限すること。 3.2 上記3.1の者の区域の出入は許可を受けている旨を証明し得るものをもって管理すること。 3.3 臨時に区域の出入を行う者は、事前に当該者の信頼性確認のうえ許可を与えた者に制限すること。 3.4 上記3.3の者の区域の出入は、許可を受けている旨を証明し得るものをもって管理すること。 3.5 上記3.3の者が内部区域に立ち入る場合には、上記3.1により許可を受けた者の常時付添いにより管理すること。 この場合、上記3.3の者と付き添う者との比率を制限すること。 3.6 区域への私用自動車の立入りは原則として禁止すること。 3.7 区域の出入口で、荷物及び車両につき、所定の検査を行うこと。 ただし、3.1により許可を受けている者の荷物及び車両にあっては適時行うことで足りる。 3.8 必要に応じ、内部区域の入口には、金属探知器を、また、出口には、核物質検知器を設けること。 3.9 警備員のいない出入口には、錠及び必要に応じ侵入警報装置等を設けること。 3.10 錠は、複製の可能性を最小とするとともに、必要に応じ、適当な間隔により取換え又は構造の変更を行うこと。 また、これらに不信な点が認められた場合には、速やかに取換え又は構造の変更を行うこと。 3.11 鍵に接近できる者は極めて少人数に制限すること。 (特殊核分裂性物質の管理)
4.1 特殊核分裂性物質の使用は、内部区域内においてのみ行うこと。 4.2 使用中の特殊核分裂性物質は、3.1により許可を受けている者又は警備人による連続的な監視のもとに置くこと。ただし、4.3から4.6の要件を満たしている場合はこの限りでない。 4.3 特殊核分裂性物質の貯蔵は、内部区域内に設置する貯蔵施設内においてのみ行うこと。 4.4 貯蔵施設は、堅固な構造なものとし、錠及び必要に応じ、侵入警報装置を設けること。 4.5 貯蔵施設の出入を行う者は、事前に許可を与えた者に制限すること。 4.6 貯蔵施設は、警備人により、所定の頻度及び方法で巡視すること。 この場合、侵入警報装置等の機械的監視により補完してもよい。 (侵入警報系統の確立維持)
5.1 設置した侵入警報装置等(人の不法な侵入の感知装置、伝達装置及び表示装置により構成される。)は、信頼性のあるものとする。 5.2 主要な侵入警報装置等は、一次電源喪失の場合には、独立電源から作動できる状態に保つこと。 5.3 表示装置は、区域内又はこれに接近した場所に設けること。 5.4 表示装置は、警備人による連続的な監視のもとにおくこと。 (連絡通報体制の整備)
6.1 勤務中にある警備人と、警備人の詰所(警備室)との間に通報手段を確保すること。 6.2 区域内の主要な箇所と警備室との間に通報手段を確保すること。 6.3 警備室から治安当局への通報手段を確保すること。 6.4 法安当局への通報手段は、無線等を組み合わせた二重のものとすること。 (情報管理)
7.1 核物質防護措置の詳細に係る情報は不必要に分散されないこと。 (緊急時における対応体制の確立)
8.1 治安当局等とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと。 (設備、機器等の点険保守)
9.1 核物質防護に関する設備、機器等は、点検、保守し、その信頼性の維持を図ること。 (組織体制の整備)
10.1 核物質防護のための組織体制の整備を図ること。 (従業員の教育訓練)
11.1 従業員に対し、その職務に応じ、核物質防護に関する教育訓練を行うこと。 2 輸送中の核物質防護の要件
Ⅰ 輸送手段に共通の要件 (輸送計画の策定等)
1.1 荷送人は、輸送(積替、通関等を含む。以下同じ。)の核物質防護措置に関する計画書(以下「輸送計画書」という。)を策定すること。 1.2 輸送計画書は、あらかじめ荷送人及び荷受人の間で、又は荷送人、荷受人及び運送人の間で協議し、調整を行ったうえで策定すること。 1.3 輸送計画書には、次のものを記載すること。 1.3.1 輸送方式(輸送手段、積付け方法等)に関すること。 1.3.2 輸送経路に関すること。 1.3.3 輸送関係者(荷送人、荷受人、運送人等)の氏名。 1.3.4 輸送中の警備に関すること。 1.3.5 厳密な受渡し地点及びその予定時刻。 1.3.6 輸送中の連絡通報に関すること。 1.4 輸送方式の選定にあたっては、特別の事由がある場合を除き、輸送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよう配慮すること。 1.5 輸送経路の選定にあたっては、特別な事由がある場合を除き、自然災害等による突発的に事態が生ずる可能性が少ない地区を経過するよう配慮すること。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 荷送人は、輸送中の核物質防護の実施に係る責任者(以下「輸送責任者」という。)を準備し、輸送に付添わせること。 2.2 輸送責任者は、核物質防護上の措置について知識と経験を有する者であること。 2.3 荷送人は、輸送責任者に輸送計画書の要旨を携帯させること。 2.4 荷送人は、輸送中における警備人を準備し、輸送に付添わせること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 荷送人は、出荷後、直ちに、荷受人にその旨通知すること。 3.2 荷送人又は運送人は、輸送中、電話等により、あらかじめ指定した連絡場所(以下「指定連絡所」という。)へ連絡を行い得るよう連絡通報体制を整備すること。 3.3 荷送人は、指定連絡所との連絡の時間間隔又は連絡位置をあらかじめ定めておくこと。 3.4 輸送責任者は、上記3.3により定められたとおり、指定連絡所へ連絡を行うこと。 3.5 荷受人は、積荷が輸送計画書に記載された受渡し地点に到着したとき、又は予定時刻までに到着しないときは、速やかにその旨を荷送人に通知すること。 (施錠・封印等)
4.1 荷送人は、輸送容器又はコンテナーの開口部に、必要に応じ、錠及び封印(以下「錠等」という。)を付けること。 4.2 荷送人は、積荷が人手により容易に移動することが出来る場合は、コンテナー等へ収納する等の措置により、容易に移動することができないようにすること。 (輸送中の監視、点検等)
5.1 荷送人は、出荷に先立ち、又、荷受人は積荷受取り後直ちに、梱包及び付けられた錠等の健全性を検査すること。 5.2 輸送責任者及び警備人は、出荷に先立ち、妨害行為が着手されていないことを確認するため、輸送手段を検査すること。 5.3 警備人は、他の輸送手段への積替、他の積荷の積替及び通関時には、当該積荷を連続的に監視するか又は錠等を頻繁に点検すること。 5.4 警備人は、輸送中、当該積荷又は付けられた錠等を頻繁に点検すること。 ただし、航空輸送の場合においては必要ない。 5.5 運送人は、当該輸送に従事する者以外の者が通常立ち入ることができる場所で積卸し等の取扱いを行わないこと。又、当該場所に積荷を置かないこと。 (情報管理)
6.1 輸送計画の詳細に係る情報は、不必要に分散されないようにすること。 6.2 定期的に反復継続する輸送は、出来る限り避ける。 (緊急時における対応体制の確立)
7.1 荷送人は、治安当局等とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと。 Ⅱ 道路輸送中の核物質防護の要件 道路輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送計画の策定等)
1.1 Ⅰ.1.5の要件に加えて、緊急時における代替経路を考慮しておくこと。 1.2 荷送人は、輸送の途中において積替を予定しないこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 Ⅰ.2.1の要件に加えて、輸送に、輸送責任者を乗せた伴走車を付けること。 2.2 Ⅰ.2.4の要件に加えて、輸送に警備人を乗せた警備車を付けること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 Ⅰ.3.2の要件に加えて、荷送人は、積載車両、伴走車及び警備車との間に相互無線による通報手段を確保すること。 (輸送中の監視、点検等)
4.1 Ⅰ.5.4の要件に代えて、警備人は、輸送中、積載車両を連続的に監視すること。 4.2 警備人は、休憩等による停車時において、当該積荷を連続的に監視すること。 ただし、積載車両が有蓋車両である場合にあっては、当該有蓋車両の監視で足りる。 Ⅲ 鉄道輸送中の核物質防護の要件 鉄道輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送計画の策定等)
1.1 荷送人は、貨車で輸送を行うこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 Ⅰ.2.1及びⅠ.2.4の要件に加えて、荷送人は、当該貨車内又はその直前若しくは直後の車両に輸送責任者及び警備人を添乗させること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 Ⅰ.3.2及びⅠ.3.3の要件に代えて、荷送人は、あらかじめ指定した各予定連絡停車駅において、指定連絡所へ連絡を行うよう措置し、輸送責任者に指示すること。 (輸送中の監視、点検等)
4.1 Ⅰ.5.4の要件に代えて、警備人は、各停車地点ごとに、当該積荷又は有蓋貨車の錠等を点検すること。 Ⅳ 船舶輸送中の核物質防護の要件 船舶輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
1.1 Ⅰ.2.1及びⅠ.2.4の要件に代えて、航海中荷送人は、警備人を付けるか、又は警備のための係を選任すること。荷送人は沖合停泊中、出入港時、荷役時及び通関時に輸送責任者及び警備人を付けること。 (積卸し時等の監視、点検等)
2.1 Ⅰ.5.5の要件に代えて、輸送責任者は積卸し等及び通関のための保管及び運搬時において、関係者以外の者が立ち入らないよう措置すること。 Ⅴ 航空輸送中の核物質防護の要件 航空輸送中においては、Ⅰの要件(適用除外及び特記要件を除く。)を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送計画の策定等)
1.1 荷送人は、貨物機を用いること。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 Ⅰ.2.1及びⅠ.2.4の要件に代えて、荷送人は出発空港及び各着陸空港において輸送責任者及び警備人を付けること。 区分 Ⅱ
1 使用中及び貯蔵中の核物質防護の要件
(核物質防護のための区域の設定)
1.1 区域を設定すること。 1.2 設定した区域は、堅固な構造の障壁によって囲うこと。 (区域の監視)
2.1 区域は、警備人により、所定の頻度及び方法で巡視すること。 この場合、侵入警報装置等の機械的監視により補完してもよい。 2.2 特殊核分裂性物質を取扱う者は、職務交替時に、特殊核分裂性物質の不法な移転又は原子力施設に対する妨害、破壊行為が認められなかったことを確認し、その旨を、又は異常があると認められるときには、その旨を速やかに上級者に報告すること。 (区域の出入管理)
3.1 職務上常時区域の出入を行う者は、事前に許可を与えた者に制限すること。 3.2 上記3.1の者の区域の出入は許可を受けている旨を証明し得るものをもって管理すること。 3.3 臨時に区域の出入を行う者は、事前に当該者の信頼性確認のうえ許可を与えた者に制限すること。 3.4 上記3.3の者の区域の出入は、許可を受けている旨を証明し得るものをもって管理すること。 3.5 上記3.3の者が区域に立た入る場合には、上記3.1により許可を受けた者の常時付添いにより管理すること。 この場合、上記3.3の者と付き添う者との比率を制限すること。 3.6 区域への私用自動車の立入りは原則として禁止すること。 3.7 区域の出入口で、荷物及び車両につき、所定の検査を行うこと。 ただし、3.1により許可を受けている者の荷物及び車両にあっては適時行うことで足りる。 3.8 警備員のいない出入口には、錠及び必要に応じ、侵入警報装置等を設けること。 3.9 錠は、複製の可能性を最小とするとともに、必要に応じ、適当な間隔により取換え又は構造の変更を行うこと。 また、これらに不信な点が認められた場合には、速やかに取換え又は構造の変更を行うこと。 3.10 鍵に接近できる者は極めて少人数に制限すること。 (特殊核分裂性物質の管理)
4.1 特殊核分裂性物質の使用は、区域内においてのみ行うこと。 4.2 使用中の特殊核分裂性物質は3.1により許可を受けている者又は警備人による連続的な監視のもとに置くこと。ただし、4.3から4.6の要件を満たしている場合はこの限りでない。 4.3 特殊核分裂性物質の貯蔵は、区域内に設置する貯蔵施設内においてのみ行うこと。 4.4 貯蔵施設は、堅固な構造のものとし、錠及び必要に応じ、侵入警報装置を設けること。 4.5 貯蔵施設の出入を行う者は、事前に許可を与えた者に制限すること。 4.6 貯蔵施設は、警備人により、所定の頻度及び方法で巡視すること。 この場合、侵入警報装置等の機械的監視により補完してもよい。 (侵入警報系統の確立維持)
5.1 設置した侵入警報装置等(人の不法な侵入の感知装置、伝達装置及び表示装置により構成される。)は、信頼性のあるものとする。 5.2 主要な侵入警報装置等は、一次電源喪失の場合には、独立電源から作動できる状態に保つこと。 5.3 表示装置は、区域内又はこれに接近した場所に設けること。 5.4 表示装置は、警備人による連続的な監視のもとにおくこと。 (連絡通報体制の整備)
6.1 勤務中にある警備人と、警備人の詰所(警備室)との間に通報手段を確保すること。 6.2 区域内の主要な箇所と警備室との間に通報手段を確保すること。 6.3 警備室から治安当局への通報手段を確保すること。 (情報管理)
7.1 核物質防護措置の詳細に係る情報は不必要に分散されないこと。 (緊急時における対応体制の確立)
8.1 治安当局等とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと。 (設備、機器等の点検保守)
9.1 核物質防護に関する設備、機器等は、点検、保守し、その信頼性の維持を図ること。 (組織体制の整備)
10.1 核物質防護のための組織体制の整備を図ること。 (従業員の教育訓練)
11.1 従業員に対し、その職務に応じ、核物質防護に関する教育訓練を行うこと。 2 輸送中の核物質防護の要件
Ⅰ 輸送手段に共通の要件 (輸送計画の策定等)
1.1 荷送人は、輸送計画書を策定すること。 1.2 輸送計画書は、あらかじめ荷送人及び荷受人の間で、又は荷送人、荷受人及び運送人の間で協議し、調整を行ったうえで策定すること。 1.3 輸送計画書には、次のものを記載すること。 1.3.1 輸送方式(輸送手段、積付け方法等)に関すること。 1.3.2 輸送経路に関すること。 1.3.3 輸送関係者(荷送人、荷受人、運送人等)の氏名。 1.3.4 輸送中の警備に関すること。 1.3.5 厳密な受渡し地点及びその予定時刻。 1.3.6 輸送中の連絡通報に関すること。 1.4 輸送方式の選定にあたっては、特別の事由がある場合を除き、輸送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよう配慮すること。 1.5 輸送経路の選定にあたっては、特別な事由がある場合を除き、自然災害等による突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区を経過するよう配慮すること。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 荷送人は、輸送責任者を準備し、輸送に付添わせること。 2.2 輸送責任者は、核物質防護上の措置について知識と経験を有する者であること。 2.3 荷送人は、輸送責任者に輸送計画書の要旨を携帯させること。 2.4 荷送人は、輸送中における警備人を準備し、輸送に付添わせること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 荷送人は、出荷後、直ちに、荷受人にその旨通知すること。 3.2 荷送人又は運送人は、輸送中、電話等により、あらかじめ、指定連絡所へ連絡を行い得るよう連絡通報体制を整備すること。 3.3 荷送人は、指定連絡所との連絡の時間間隔又は連絡位置をあらかじめ定めておくこと。 3.4 輸送責任者は、上記3.3により定められたとおり、指定連絡所へ連絡を行うこと。 3.5 荷受人は、積荷が輸送計画書に記載された受渡し地点に到着したとき、又は予定時刻までに到着しないときは、速やかにその旨を荷送人に通知すること。 (施錠・封印等)
4.1 荷送人は、輸送容器又はコンテナーの開口部に、必要に応じ、錠等を付けること。 4.2 荷送人は、積荷が人手により容易に移動することが出来る場合は、コンテナー等へ収納する等の措置により、容易に移動することができないようにすること。 (輸送中の監視、点検等)
5.1 荷送人は、出荷に先立ち、又荷受人は積荷受取り後直ちに、梱包及び付けられた錠等の健全性を検査すること。 5.2 輸送責任者及び警備人は、出荷に先立ち、妨害行為が着手されていないことを確認するため、輸送手段を検査すること。 5.3 警備人は、他の輸送手段への積替、他の積荷の積替及び通関時には、当該積荷を連続的に監視するか又は錠等を頻繁に点検すること。 5.4 警備人は、輸送中、当該積荷又は付けられた錠等を頻繁に点検すること。 5.5 運送人は、当該輸送に従事する者以外の者が通常立ち入ることができる場所で積卸し等の取扱いを行わないこと。又、当該場所に積荷を置かないこと。 (情報管理)
6.1 輸送計画の詳細に係る情報は、不必要に分散されないようにすること。 6.2 定期的に反復継続する輸送は、出来る限り避けること。 (緊急時における対応体制の確立)
7.1 荷送人は、治安当局等とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと。 Ⅱ 道路輸送中の核物質防護の要件 道路輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送計画の策定等)
1.1 Ⅰ.1.5の要件に加えて、緊急時における代替経路を考慮しておくこと。 1.2 荷送人は、輸送の途中において積替を予定しないこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 Ⅰ.2.1の要件に加えて、輸送に、輸送責任者を乗せた伴走車を付けること。 2.2 Ⅰ.2.4の要件に加えて、輸送に警備人を乗せた警備車を付けること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 Ⅰ.3.2の要件に加えて、荷送人は、積載車両、伴走車及び警備車との間に相互無線による通報手段を確保すること。 (輸送中の監視、点検等)
4.1 Ⅰ.5.4の要件に代えて、警備人は、輸送中、積載車両を連続的に監視すること。 4.2 警備人は、休憩等による停車時において、当該積荷を連続的に監視すること。 ただし、積載車両が有蓋車両である場合にあっては、当該有蓋車両の監視で足りる。 Ⅲ 鉄道輸送中の核物質防護の要件 鉄道輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送計画の策定等)
1.1 荷送人は、貨物で輸送を行うこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
2.1 Ⅰ.2.1及びⅠ.2.4の要件に加えて、荷送人は当該貨車内又はその直前若しくは直後の車両に輸送責任者及び警備人を添乗させること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 Ⅰ.3.2及びⅠ.3.3の要件に代えて、荷送人は、あらかじめ指定した各予定連絡停車駅において、指定連絡所へ連絡を行うよう措置し、輸送責任者に指示すること。 (輸送中の監視、点検等)
4.1 Ⅰ.5.4の要件に代えて、警備人は、各停車地点ごとに、当該積荷又は有蓋貨車の錠等を点検すること。 Ⅳ 船舶輸送中の核物質防護の要件 船舶輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
1.1 Ⅰ.2.1及びⅠ.2.4の要件に代えて、航海中、荷送人は、警備人を付けるか、又は警備のための係を選任すること。荷送人は沖合停泊中、出入港時、荷役時及び通関時に輸送責任者及び警備人を付けること。 (積卸し時等の監視、点検等)
2.1 Ⅰ.5.5の要件に代えて、輸送責任者は積卸し等及び通関のための保管及び運搬時において、関係者以外の者が立ち入らないよう措置すること。 Ⅴ 航空輸送中の核物質防護の要件 航空輸送中においては、Ⅰの要件(適用除外及び特記要件を除く。)を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送責任者及び警備人の準備等)
1.1 Ⅰ.2.1及びⅠ.2.4の要件に代えて、荷送人は出発空港及び各着陸空港において輸送責任者及び警備人を付けること。 区分 Ⅲ
1 使用中及び貯蔵中の核物質防護の要件
(核物質防護のための区域の設定)
1.1 区域を設定すること。 (区域の監視)
2.1 区域は、警備人により、所定の頻度及び方法で巡視すること。この場合、侵入警報装置等の機械的監視により補完してもよい。 2.2 特殊核分裂性物質を取扱う者は、職務交替時に、特殊核分裂性物質の不法な移転又は原子力施設に対する妨害、破壊行為が認められなかったことを確認し、その旨を、又は異常があると認められるときには、その旨を速やかに上級者に報告すること。 (区域の出入管理)
3.1 職務上常時区域の出入を行う者は、事前に許可を与えた者に制限すること。 3.2 上記3.1の者の区域の出入は許可を受けている旨を証明し得るものをもって管理すること。 3.3 臨時の区域の出入を行う者は、事前に当該者の信頼性確認のうえ許可を与えた者に制限すること。 3.4 上記3.3の者の区域の出入は、許可を受けている旨を証明し得るものをもって管理すること。 3.5 区域への私用自動者の立入りは原則として禁止すること。 3.6 警備員のいない出入口には、錠及び必要に応じ、侵入警報装置等を設けること。 (特殊核分裂性物質の管理)
4.1 特殊核分裂性物質の使用は、区域内においてのみ行うこと。 4.2 特殊核分裂性物質の貯蔵は、区域内に設置する貯蔵施設内においてのみ行うこと。 4.3 貯蔵施設の出入を行う者は、事前に許可を与えた者に制限すること。 4.4 貯蔵施設は、警備人により、所定の頻度及び方法で巡視すること。この場合、侵入警報装置等の機械的監視により補完してもよい。 (侵入警報系統の確立維持)
5.1 設置した侵入警報装置等(人の不法な侵入の感知装置、伝達装置及び表示装置により構成される。)は、信頼性のあるものとする。 (連絡通報体制の整備)
6.1 警備室から治安当局への通報手段を確保すること。 (情報管理)
7.1 核物質防護措置の詳細に係る情報は不必要に分散されないこと。 (緊急時における対応体制の確立)
8.1 治安当局等とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応体制を確立しておくこと。 (設備、機器等の点検保守)
9.1 核物質防護に関する設備、機器等は、点検、保守し、その信頼性の維持を図ること。 (組織体制の整備)
10.1 核物質防護のための組織体制の整備を図ること。 (従業員の教育訓練)
11.1 従業員に対し、その職務に応じ、核物質防護に関する教育訓練を行うこと。 2 輸送中の核物質防護の要件
Ⅰ 輸送手段に共通の要件 (輸送計画の策定等)
1.1 荷送人は、輸送計画書を策定すること。 1.2 輸送計画書は、あらかじめ荷送人及び荷受人の間で、又は荷送人、荷受人及び運送人の間で協議し、調整を行ったうえで策定すること。 1.3 輸送計画書には、次のものを記載すること。 1.3.1 輸送方式(輸送手段、積付け方法等)に関すること。 1.3.2 輸送経路に関すること。 1.3.3 輸送関係者(荷送人、荷受人、運送人等)の氏名。 1.3.4 輸送中の警備に関すること。 1.3.5 厳密な受渡し地点及びその予定時刻 1.3.6 輸送中の連絡通報に関すること。 1.4 輸送方式の選定にあたっては、特別の事由がある場合を除き、輸送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよう配慮すること。 1.5 輸送経路の選定にあたっては、特別な事由がある場合を除き、自然災害等による突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区を経過するよう配慮すること。 (輸送責任者の準備等)
2.1 荷送人は、輸送責任者を準備し、輸送に付添わせること。 2.2 輸送責任者は、核物質防護上の措置について知識と経験を有する者であること。 2.3 荷送人は、輸送責任者に輸送計画書の要旨を携帯させること。 (連絡通報体制の整備)
3.1 荷送人は、出荷後、直ちに、荷受人にその旨通知すること。 3.2 荷受人は、積荷が輸送計画書に記載された受渡し地点に到着したとき、又は予定時刻までに到着しないときは、速やかにその旨を荷送人等に通知すること。 (施錠・封印等)
4.1 荷送人は、積荷が人手により容易に移動することが出来る場合は、コンテナー等へ収納する等の措置により、容易に移動することができないようにすること。 (輸送中の監視、点検等)
5.1 荷送人は、出荷に先立ち、又、荷受人は積荷受取り後直ちに、梱包及び付けられた錠等の健全性を検査すること。 5.2 輸送責任者は、出荷に先立ち、妨害行為が着手されていないことを確認するため、輸送手段を検査すること。 (情報管理)
6.1 輸送計画の詳細に係る情報は、不必要に分散されないようにすること。 6.2 定期的に反復継続する輸送は、出来る限り避けること。 (緊急時における対応体制の確立)
7.1 荷送人は、治安当局等とあらかじめ打合せを行っておくこと。 Ⅱ 道路輸送中の核物質防護の要件 道路輸送中においては、Ⅰの要件を満たす外、以下の要件を満たすこと。 (輸送計画の策定等)
1.1 Ⅰ.1.5の要件に加えて、緊急時における代替経路を考慮しておくこと。 1.2 荷送人は、輸送の途中において積替を予定しないこと。 (輸送責任者の準備等)
2.1 Ⅰ.2.1の要件に加えて、輸送に、輸送責任者を乗せた伴走車を付けること。 核物質防護専門部会構成員
(昭和52年9月6日現在)
核物質防護専門部会ワーキンググループ構成員
(昭和52年9月6日現在)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |