| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||
|
三菱原子燃料株式会社東海製作所における加工事業の変更について(答申) 52原委第413号
昭和52年7月5日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和52年4月18日付け52安(核規)第1474号をもって諮問のあった標記の件については、下記のとおり答申する。 記 (1)標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第16条第3項において準用する第14条第1項各号に掲げる許可の基準のうち第1号及び第2号については適合しているものと認める。 (2)上記許可の基準のうち第3号については、別添の核燃料安全専門審査会による安全性に関する審査結果報告のとおり適合しているものと認める。 (別添)
昭和52年6月27日
原子力委員会
委員長 宇野 宗佑 殿
核燃料安全専門審査会
会長 山本 寛
三菱原子燃料株式会社東海製作所における加工事業の変更に係る安全性について
当審査会は、昭和52年4月22日付け52原委第234号(昭和52年6月21日付け52原委第403号で一部補正)をもって審査を求められた標記の件について、結論を得たので報告します。 Ⅰ 審査の結果 三菱原子燃料株式会社東海製作所の加工事業の変更に関し、同社が提出した「核燃料物質の加工の事業の変更許可申請書」(昭和52年3月29日付け申請、昭和52年6月3日付け一部補正)について、「加工施設の安全審査指針」に基づき審査した結果、「Ⅲ審査の内容」に示すとおり、本加工事業の変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。 Ⅱ 変更の内容 1 建物の変更
(1)輸送物置場の設置
燃料集合体を輸送容器に収納した状態で一時的に保管するため、工場棟に付属して輸送物置場を設置する。 (2)放射線管理棟の増設
従業員の増加に伴い、第1種管理区域への出入のための更衣室、シャワー室を拡張するため、放射線管理棟を増設する。なお、増設に伴い更衣室の一部及びシャワー室を第1種管理区域とする。 また、シャワー室の排水用設備を設置する。 (3)付属建物の新設及び増設
材料試験室を設置するとともに、危険物貯蔵所及び事務棟を増設する。 2 内部施設の変更
(4)化学処理施設の改造
転換加工工程の作業を合理化するため、ウラン粉末の貯蔵、運搬等のため使用する容器として大型粉末容器(台車付、内容積750l)を新たに使用する。このため既設の混合充填装置(転換加工された二酸化ウラン粉末を、40本のポリエチレン製容器にその品質が均一になるように少量ずつ繰り返し充填するための設備)を撤去し、充填装置「転換加工された二酸化ウラン粉末を、1つの大型粉末容器(台車付)に、充填するための設備」2基及び大型混合装置1基を設置する。 (5)成型施設の改造
大型粉末容器(台車付)を使用することに伴い、ペレット加工室に大型混合装置を2基設置する。また、既設の粉末混合機と同じ仕様のもの1基及び粉末輸送装置1基を増設する。 (6)乾燥機の追加設置
燃料棒溶接室に、ウランペレットを乾燥するための乾燥機を、4基増設する。 (7)燃料集合体組立装置の追加設置
燃料集合体組立室に、17×17型用の燃料集合体組立装置を、1基増設する。燃料集合体組立装置は、組立てられる燃料集合体と同じ配列となるように燃料棒を配置したマガジンから燃料支持構造体に、燃料棒を挿入することにより、燃料集合体を組立てる。 マガジンは、燃料棒を配置した状態で移動することができる。 (8)貯蔵施設の増設及び改造
(イ)転換加工室の既設粉末貯蔵棚を撤去し、大型粉末容器(台車付)の置場とする。また、転換加工室の運搬台車の一部及びペレット加工室の粉末一時貯蔵棚の一部を、撤去する。 (ロ)ペレット加工室に、スクラップ貯蔵棚8基を、増設する。 (ハ)ペレット貯蔵室に仕上りペレット貯蔵棚9基を増設するとともに、既設の仕上りペレット貯蔵棚の一部及び仕上りペレット一時貯蔵棚について、その貯蔵能力を増加するため増設する貯蔵棚と同じ構造に改造する。 (ニ)燃料棒検査室に、燃料棒貯蔵棚(燃料棒25本を収納する容器56個を収納できる。)を、6基増設する。 (ホ)燃料集合体貯蔵室及び燃料集合体組立室に、それぞれ燃料集合体貯蔵架台2基、燃料集合体一時貯蔵架台2基を、増設する。いずれの架台も同じ構造であり、燃料集合体4体を収納できる。 (9)その他の変更
ペレット加工室にペレット外観検査装置を、燃料集合体組立室に燃料棒間隔測定装置を、転換加工室、ペレット貯蔵室及び核燃料倉庫に秤を、設置する。 なお、今回の変更により加工能力は変わらない。 Ⅲ 審査の内容 本変更にあたっては、以下のとおり適切な配慮がなされているので、変更にともなう安全性は確保されているものと判断する。 1 放射線管理
(1)輸送物置場
輸送物置場は、燃料集合体を輸送容器に収納した状態で一時的に保管するものであるため、ウランによる空気汚染の恐れはない。また、放射線管理は、第2種管理区域(密封状態のウランのみを取り扱う区域)として行い作業者に個人被ばく測定用具を着用させ、定期的に室内の空間線量率の測定を行うこととしている。 (2)放射線管理棟
放射線管理棟の増設に伴い第1種管理区域(非密封のウランを取り扱う区域)を拡張したが、放射線管理上とくに問題はない。 (3)付属建物の新設及び増設
材料試験室、危険物貯蔵所及び事務棟においては、核燃料物質を取り扱わないので、放射線管理を必要としない。 (4)化学処理施設の改造
本施設における変更は、六フッ化ウランから転換した二酸化ウラン粉末を充填し、ウラン粉末の均質化のために混合し、もしくは貯蔵するために用いる容器をポリエチレン製容器からステンレス鋼製大型粉末容器(台車付)に変更し、変更に伴い、転換加工室の充填装置を改造し、大型混合装置を設置することである。大型粉末容器(台車付)への粉末充填は、負圧維持がなされたフード内で行われ、かつ、大型粉末容器(台車付)は、十分な密封性を有しているので、室内の空気汚染の恐れは少ない。転換加工室は、従来どおり第1種管理区域として、エアースニッファー等によって空気中のウラン濃度を監視することとしている。 (5)成型施設の改造
本施設における変更は、転換加工室における大型粉末容器(台車付)の採用に伴う変更であり、大型粉末容器(台車付)は、転換加工室に設置するものと同じものであり、ペレット加工室に増設する粉末混合機及び粉末輸送装置は、いずれも粉末の飛散する恐れのある部分には、負圧維持がなされたフードを設置することにしており、室内の空気を汚染する恐れは少ない。 なお、ペレット加工室は、従来どおり第1種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (6)乾燥機の追加設置
燃料棒溶接室に増設する乾燥機は、燃料棒に充填する前のウランペレットをトレイに収納した状態で乾燥を行うものであり、乾燥時に室内の空気を汚染する恐れは少ない。また、乾燥機への出し入れの作業時間は短く、かつ、乾燥中は全ての工程操作は、自動的に行われるので、従業員の外部被ばくは少ない。なお、燃料棒溶接室は、従来どおり第1種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (7)燃料集合体組立装置の追加設置
燃料集合体組立装置を用いての組立作業においては、ウランは、燃料棒の状態で取り扱われるので室内の空気を汚染する恐れは少ない。 なお、燃料集合体組立室については、従来どおり第2種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (8)貯蔵施設の増設及び改造
(イ)転換加工室の大型粉末容器(台車付)置場には最大で54台の容器を置くが、大型粉末容器(台車付)は、密封しているので、室内の空気を汚染する恐れはない。 なお、転換加工室は、既述のとおり第1種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (ロ)ペレット加工室に増設するスクラップ貯蔵棚は、ペレット加工室で生じた不合格ペレットを酸化(焙焼)し、粉末としてポリエチレン製容器に密封し貯蔵するものであり、貯蔵棚を増設することにより室内の空気を汚染する恐れは少ない。 なお、ペレット加工室は、第1種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (ハ)仕上りペレット貯蔵棚(仕上りペレット一時貯蔵棚も同じ仕様である。)に貯蔵するウランペレットは、焼結、研削工程を経た後洗浄したものであり、空気汚染の恐れは少ない。 なお、ペレット貯蔵室及び一時貯蔵棚の設置されるペレット加工室は、いずれも第1種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (ニ)燃料棒貯蔵棚に貯蔵する燃料棒は、ペレット充填後汚染を除去し、かつ、ヘリウムリーク検査でその密封性を確認したものであり、室内の空気を汚染することはない。 なお、燃料棒検査室は、第2種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (ホ)燃料集合体貯蔵室に増設する燃料集合体貯蔵架台(燃料集合体組立室に増設する燃料集合体一時貯蔵架台も同じ仕様である。)は、組立完了後の集合体4体を収納するものである。燃料集合体は、燃料棒自体で密封性を有しており、室内の空気を汚染することはない。 なお、貯蔵室及び組立室は、いずれも第2種管理区域として放射線管理を行うこととしている。 (9)その他の変更
ペレット外観検査装置は、負圧維持のされたフード内でペレットを取り扱い、燃料棒間隔測定装置は、密封された燃料棒を取り扱い、秤はペレットもしくは粉末を密封した状態で取り扱うので、いずれも室内の空気を汚染する恐れは少く、また設置する各室は、いずれも管理区域として放射線管理を行うこととしている。 2 臨界管理
(1)輸送物置場の臨界管理
輸送容器1基には、燃料集合体2体を収納するが、その臨界管理は、中性子実効増倍係数を水没条件下を仮想しても0.93以下とし、かつ他の輸送容器内の燃料集合体との表面間距離を30.5㎝以上として水没条件下で各集合体が互いに核的に隔離されるように配置することにより、行うこととしている。 (2)化学処理施設の変更に伴う臨界管理
大型粉末容器(台車付)は、ほぼ円筒形であるが球状のモデルに置き換え、ウランの濃縮度、含水率、容器充填量等を安全側に仮定し、核計算コードを用いて無限個数の水没条件下の中性子実効増倍係数を求め、その値が十分小さなものであることを確認している。 大型粉末容器(台車付)の臨界管理については、前記評価に基づきウラン粉末の水分及び質量を、水分計及び秤を用いて管理することとしている。また、大型粉末容器(台車付)の停止位置と転換加工室の既設設備との間隔は、立体角法により核的安全性の確認されたものとなるように制限することとしている。 (3)成型施設の変更に伴う臨界管理
大型粉末容器(台車付)は化学処理の場合と同様に行うこととしている。 粉末混合機及び粉末輸送装置については、既設のものと同様それぞれ質量制限及び輸送装置の直径を制限することにより管理することとしている。 また、これら設備及び大型粉末容器(台車付)とペレット加工室に設置された既設設備との間隔は、立体角法により核的安全性の確認されたものとなるよう制限することとしている。 (4)乾燥機の追加設置に伴う臨界管理
乾燥機の臨界管理は、ウランペレットを収納する段の収納部分の厚さを制限するとともに、各段の間隔を30.5㎝以上とすることにより行うこととしている。 (5)燃料集合体組立装置の臨界管理
燃料集合体組立装置においては一体分の燃料棒しか扱わず、燃料棒がマガジン内にあっても、また燃料支持構造体に挿入された後であっても水没条件下でその実効増倍係数が十分小さなものであることを核計算コードで確認しており、かつ、マガジンの移動時及び燃料集合体組立時にも、燃料集合体組立室内の既設の設備及び他の燃料集合体との間を30.5㎝以上隔離することにより臨界管理を行うこととしている。 (6)貯蔵施設の増設等に伴う臨界管理
(イ)大型粉末容器(台車付)は、化学処理施設の場合と同様に行うこととしている。容器間の間隔は、30.5㎝以上とすることにより行うこととしている。 (ロ)スクラップ貯蔵棚における臨界管理は、既設のものと同様に、ポリエチレン製容器に収納するウラン量を制限するとともに各列の表面間隔を30.5㎝以上とすることにより行うこととしている。 (ハ)仕上りペレット貯蔵棚(仕上りペレット一時貯蔵棚も同じ仕様である。)については収納するウランペレット量を増加させるため、段相互間に中性子吸収板(銅板5㎜厚さ)を設けることとしているが、これらの貯蔵棚の臨界管理は、収納するウランペレットの収納厚さ(収納トレイ3枚分)を制限する。この場合の核的安全性については、核計算コードによる解析により確認している。 なお、この方法は、濃縮度を3.8%以下のものに適用することとしている。 (ニ)燃料棒貯蔵棚における臨界管理は、既設のものと同様に、燃料棒を収納する容器の厚さを制限するとともに、各段の間隔を30.5㎝以上とすることにより行うこととしている。 (ホ)燃料集合体貯蔵架台(燃料集合体一時貯蔵架台も同じ仕様である。)における臨界管理は、燃料集合体1体の水没条件下での中性子実効増倍係数が十分小さなものであることを核計算コードにより確認しており、燃料集合体相互の間隔を30.5㎝以上離すこととしている。 (7)その他の変更に伴う臨界管理
(イ)ペレット外観検査装置については、ペレット貯蔵設備と同様に二酸化ウランペレットの収納厚さを制限することにより、また、ペレット加工室に設置された既設設備との中性子相互干渉作用については、立体角法により解析し、核的に安全に配置することとしている。 (ロ)燃料棒間隔測定装置については、水没条件下で臨界の恐れのないものであることを核計算コードにより確認している燃料集合体1体のみを取り扱うこととし、燃料集合体間の表面間距離を30.5㎝以上としている。 (ハ)転換加工室の秤は、二酸化ウランを大型粉末容器(台車付)に収納した状態で、秤量するものであり、室内の既設設備との中性子相互干渉作用については、立体角法により解析し、核的に安全に配置することとしている。 ペレット貯蔵室の秤は、仕上りペレット貯蔵棚を秤量するものであり、室内の既設設備との中性子相互干渉作用については、立体角法により解析し、核的に安全に配置することとしている。 核燃料倉庫の秤は、質量制限されたポリエチレン製容器を1個ずつ、かつ、他の容器とは中性子相互干渉作用による臨界を防止するに必要な間隔をとって秤量することとしている。 3 耐震・耐火性
(1)輸送物置場
水平震度0.2に耐える耐震構造であり、かつ、不燃材料で作られた簡易耐火建築物とすることとしている。 (2)放射線管理棟の増設
水平震度0.2に耐える耐震構造であり、かつ、不燃材料で作られた耐火建築物とすることとしている。 (3)付属建物の新設及び増設
材料試験室並びに増設する危険物貯蔵所及び事務棟は、いずれも水平震度0.2に耐える耐震構造とし、かつ、不燃材料で作られた簡易耐火建築物とすることとしている。 なお、危険物貯蔵所は、消防法に基づいた建築物とすることとしている。 (4)化学処理施設の改造
(イ)大型粉末容器(台車付)は、粉末の貯蔵のためのみでなく、運搬、混合にも使用するので、それらの使用状態において破損することのないよう
① 容器本体は、二酸化ウラン粉末の重量と動的荷重(混合時)が同時に作用しても耐えうる。 ② 容器に付設される台車は、容器と粉末の重量に地震力(水平震度0.3)が同時に作用しても耐えうる。③ 容器の安定性については、水平震度0.3に耐えうるものとすることとしている。 (ロ)大型混合装置は、大型粉末容器(台車付)を円形バンドで固定し回転させ混合するものであり、回転時の応力に回転軸、円形バンド、ピン等が耐えうるものとすることとしている。また、大型混合装置は床にボルトで固定され、回転時においても水平震度0.3に耐えるものとすることとしている。 (ハ)充填装置は、転換加工設備の架台(建家とは独立した基礎の上に設けられており、鋼材で構成されている。)にボルトで固定する等により水平震度0.3に耐える構造としている。 (ニ)大型粉末容器(台車付)、大型混合装置及び充填装置は不燃材を主体とすることとしている。 (5)成型施設の改造
(イ)ペレット加工室において使用する大型粉末容器(台車付)は、化学処理施設において使用する容器と同じである。 (ロ)粉末混合機は、テストサンプル用粉末などの混合に用いるための容量約30lのものであり、既設と同じ仕様のものである。粉末輸送装置は、ウラン粉末を、粗成型用プレスのホッパーに供給するためのものである。 これらの設備は、床にボルトで固定する等により水平震度0.3に耐える構造とし、材質は不燃材を主体とすることとしている。 (6)乾燥機の増設
乾燥機は、水平震度0.3に耐える構造とし、材質は不燃材を主体とすることとしている。 (7)燃料集合体組立装置の追加設置
燃料集合体組立装置は、ボルトで床に固定することにより水平震度0.3に耐える構造とし、材質は不燃材を主体とすることとしている。 (8)貯蔵施設の増設及び改造
(イ)大型粉末容器(台車付)置場の床面の強度は、容器の全数に、所定のウラン粉末量が収められたものが所定の間隔をもって配置されているとして評価し、十分に余裕のあることを確認している。 (ロ)スクラップ貯蔵棚は、ボルトで床に固定することにより水平震度0.3に耐えるものとし、収容するポリエチレン製容器が滑落することのないよう金具を用いて固定することとしている。また、構造材は不燃材を主体とする。 (ハ)仕上りペレット貯蔵棚(仕上りペレット一時貯蔵棚も同じ仕様である。)はボルトで床に固定したベース(約20㎝の厚さで上面に貯蔵棚を移動させるためのローラが組込まれているもの)上に据置く構造であり、水平震度0.3に耐えるものとし、材質は不燃材とすることとしている。 (ニ)燃料棒貯蔵棚は、ボルトで床に固定することにより水平震度0.3に耐えるものとし、材質は不燃材とすることとしている。 (ホ)燃料集合体貯蔵架台(燃料集合体一時貯蔵架台も同じ仕様である。)は、床にボルトで固定することにより水平震度0.3に耐えるものとし、材質は不燃材とすることとしている。 (9)その他の変更
ペレット外観検査装置、燃料棒間隔測定装置及び秤は、使用の方法から判断して転倒もしくは移動することによって臨界事故等核的安全性を損うものではなく、とくに耐震性を要しない。材質は、いずれも不燃材を主体とすることとしている。 Ⅳ 審査の経過 本審査会は、次表のとおり、昭和52年4月25日第5回審査会において審査を行い、引き続き加工・使用部会において昭和52年5月25日及び6月21日に審査を行い、本報告書を決定した。 なお、同部会の委員は次のとおりである。 部会委員
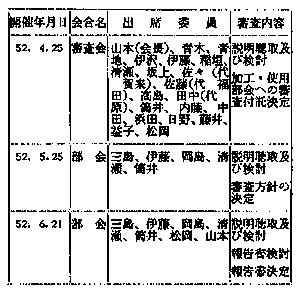 | ||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |