| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||
|
被ばく線量登録管理制度のシステム構成及び運用について(中間報告) 昭和52年4月5日
科学技術庁原子力安全局
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会
原子力安全局長
伊原 義徳 殿
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会
座長 中戸 弘之
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会は、昭和51年11月以来、被ばく線量登録管理制度のシステム構成及びその運用の具体策について検討を行った結果、別紙のとおりその大綱のとりまとめを見たので、ここに中間的に報告いたします。 なお、本検討会は、今後この中間報告に沿い、より詳細なシステム構成及びその運用の具体策について検討を進める予定であります。 1.用語の定義
本報告書の用語は、次のように定義する。 (1) 登録管理機関−核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)に基づく規則に定める科学技術庁長官等が指定する被ばく記録の引き渡しを受ける機関
(2) 原子力事業者(所)−規制法下の事業を行う者(所)
(3) 使用者−放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「障防法」という。)のRI等の使用者、販売業者、廃棄業者
(4) 従事者−規制法及び障防法下の従事者
(5) 随時立入者−従事者以外の者であって管理区域に業務上立入る者
(6) 従事者等−従事者及び随時立入者
(7) 登録−登録管理機関において電算機に投入すること
(8) 保管−登録管理機関において、引き渡された被ばく記録を保管すること
(9) 原子力事業者等−原子力事業者及びグループセンター
(注) グループセンター−放射線管理手帳に効力を付与し、かつ、同手帳の管理等を指導する者
2.被ばく線量登録管理制度の基本的考え方
(1) 登録管理機関を設置し、同機関において従事者等に係る被ばく記録を一元的に保管するとともに、原子力事業者等が従事者等に対して行う被ばく管理に必要なデータを提供する。 (2) なお、本制度においては、原子力事業者等が従事者等の被ばく歴を的確に把握し、被ばく管理に万全を期しうるよう、既に原子力事業者等が実施している「放射線管理手帳制度」と密接に関連した有効な機能を有することが望まれる。 3. 登録管理機関の行う業務
(1) 規制法により、原子力事業者から引き渡される記録の保管及びその一部の登録
(2) 原子力事業者から報告された随時立入者の被ばく線量記録の保管及びその一部の登録
(3) 使用者等から引き渡される記録の保管及びその一部の登録、ただし当分の間は、特定の非破壊検査事業者を対象とする。
(4) 規制法上と障防法上の被ばく線量の区別が甚だしく困難な原子力事業者については、事業所単位で引き渡される記録を保管・登録する。
(5) 原子力事業者等からの従事者等の事前登録の受理及びこれに基づく登録番号の付与とその原子力事業者等への通知
(6) 原子力事業者からの従事者等指定登録の受理
(7) 原子力事業者等からの個人の被ばく歴の照会に対する回答
(8) 登録番号を重複して有する者等のチェックとその結果の原子力事業者等への通知
(9) その他関連する業務
4. 登録管理機関の体制
(1) 適当数の人員を配置する。 (2) 被ばく線量記録の一元管理及び被ばく歴照会への対応のため、機関内において、電算機処理業務を実施する。 (3) 原子力事業者等との通信に必要な機器を設置する。 (4) 引き渡される記録を保管するための施設を置く。 5. 被ばく線量登録管理制度における業務の手順
(1) 原則的には次のように運用するものとする。 (イ)従事者等の事前登録−原子力事業者等から登録管理機関に従事者等の事前登録を要請する。 (ロ)登録番号の付番−登録管理機関は事前登録される従事者等に登録番号を付与し、その番号を事前登録要請者に通知する。 (ハ)従事者等指定登録−原子力事業者は(ロ)により通知された登録番号を付して登録管理機関に従事者等の指定登録を要請する。 (ニ)記録の保管とその一部の登録−原子力事業者は、当該従事者等の指定解除後、被ばく線量値の評価を待って、登録管理機関に、従事者については法定被ばく記録を、随時立入者については必要な被ばく記録を引き渡す。登録管理機関は、これらを保管するとともに、必要なデータを登録する。 (なお、同一原子力事業者(所)内にあって、従事者から随時立入者への区分の変更のあった者は、随時立入者を解除された後に記録を引き渡すものとする。)
(2) 従事者等の事前登録と指定登録との間に時間的余裕のない場合は、原子力事業者は事前登録兼指定登録を要請することができる。この場合、登録番号は追って登録管理機関より登録要請者に通知する。 (3) 被ばく歴の照会を行ったところ、未登録者である旨回答を得た場合には事前登録を行う。 (4) 登録管理機関は、二重登録者の有無などについて、随時チェックし、該当者がある場合には原子力事業者等に通知する。 6. 被ばく線量登録管理制度における文書の種類とその内容
3つの業務運用に必要な文書の種類とその内容は次の通りとする。 (注)文書名は仮称、原票とは電算機入力に用いる票をいう。 (1) 事前登録原票
下記項目を含むものとし、原子力事業者等において記入する。 (注)本原票の投入により電算機内で登録番号が付与されるものとする。 原子力事業者(所)等名、従事者等の氏名、生年月日、性別、*本籍、登録年月日
(*本籍については、県名程度とし、可能な範囲のものとする。以下、この項目については同じ。)
なお、本原票には登録番号通知先を記載する。 (2) 指定登録原票
下記事項を含むものとし、原子力事業者において記入する。 原子力事業者(所)名、従事者等の氏名、生年月日、登録番号、指定年月日
(3) 事前登録兼指定登録原票
下記項目を含むものとし、原子力事業者において記入する。 原子力事業者(所)名、従事者等の氏名、生年月日、性別、本籍、登録年月日、指定年月日、なお、本原票には登録番号通知先を記載する。 (4) 解除登録原票
下記項目を含むものとし、一連番号を除いて原子力事業者において作成、記入する。 原子力事業者(所)名、従業者等の氏名、生年月日、登録番号、指定年月日、解除年月日、被ばく歴及び被ばく放射線量、引き渡し書一連番号
なお線量を登録するかどうか、また登録するとすればどの項目か、更に検討の必要がある。また、従事者等に指定された後、当該原子力事業所から退所するまでに従事者等として、従事しなかった場合には、上記「解除年月日」に代えて「指定取消」とする。 (5) 登録番号通知書
下記項目を含むものとし、登録管理機関において作成し、事前登録要請者に送付する。 事前登録要請者、従事者等の氏名、生年月日、登録番号
(6) 被ばく歴照会原票
下記項目を含むものとし、原子力事業者等において作成する。 従事者等の氏名、生年月日、性別、照会者名(及び連絡先)、照会年月日
(7) 被ばく歴回答書
下記項目を含むものとし、登録管理機関において作成し、照会元に送付する。 (イ) 従事者等が既登録者である場合には、
その者の登録番号、登録年月日、事前登録に係る原子力事業者等の名及びその者が(原則として)直近2年間に従事者等の指定を解除された原子力事業者(所)名とその従事期間並びに(または)その者が現在従事者等として指定されている原子力事業者(所)名と指定年月日
なお、照会者の要請があるときは、保管されている法定記録の写しを、通常過去2ケ年間分までを送付する。 (ロ) 対象者が未登録者である場合には、その旨
(8) その他
身分関係の変更等の登録項目の修正、取消しのための原票類を原子力事業者等において作成する。 7. 文書の引き渡し等の手段
文書の送付等の手段は次のとおりとする。 (1) 事前登録原票、指定登録原票及び事前登録兼指定登録原票の送付は郵便またはテレ(ファ)ックスによる。 (2) 解除登録原票の送付は郵便による。 (3) 登録番号通知書の送付は郵便またはテレ(ファ)ックスによる。 (4) 被ばく歴の照会、回答は電話、郵便、またはテレ(ファ)ックスによる。 8. 機密保持及びプライバシーの確保
(1) 登録管理機関の従業員の雇用契約等に機密保持及びプライバシーの確保について規定する。 (2) 照会の目的を放射線被ばく管理のための被ばく歴の照会に限定するとともに、照会しうる者(原子力事業者等)の資格、担当部門、責任者等責任体制を明確にする。 (3) 原子力施設において作業に従事する際原子力事業者等に提出される被ばく歴の本人申告書に「被ばく記録等について問合せすることもある」旨明記し、これにより本人の承諾を受けることとする。 9. 記録保管の期間
法令による引渡し記録については無期限。それ以外の記録については被ばく管理上必要とする期間とする。 10. 過去の記録の引渡し
本制度発足以前に従事者指定を解除されたものについては、個人識別に必要な項目を登録し、登録番号を付与したのちに法定被ばく記録を引き渡すものとする。 11. 被ばく線量登録管理制度のタイムスケジュール
(1) 本制度の実施は昭和52年10月を目途とする。 (2) 昭和52年の時点で従事者等として指定中の者の事前登録兼指定登録を実施し、また、この時点以降恒常的に新規の事前登録兼指定登録及び解除者の記録の保管、登録を実施する。 登録管理機関は、当該者の登録番号を原子力事業者等に通知する。 (3) 昭和52年以前の解除者の記録の引き渡しは昭和53年度中に完了するよう努めるものとする。 (4) (3)の引き渡しにより事前登録を実施する。 (5) 被ばく歴照会に対する回答は昭和53年度より実施する。登録番号等については、一部昭和52年度より実施する。 12. その他
本検討会は、当初、その検討事項を規制法下の従事者を対象としていたが、検討の過程において、規制法下の随時立入者及び障防法下の従事者等も含めて検討することが適当であると考え、本中間報告をとりまとめたものである。本制度の趣旨にかんがみ、これらの者についても速やかに本制度の対象とすることが望まれる。 別表 原票記載項目 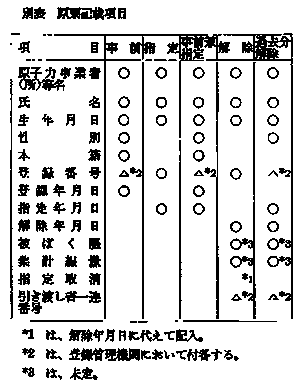
(付記1)
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会の開催について
51.10.18
原子力安全局
1. 開催の目的
原子力事業従業員の障害防止上、放射線被ばく線量の正確なは握は基幹的要件であり、これを確保するものとして従来から被ばく線量の中央登録管理制度の整備が強く望まれてきたところであるが、近時における従業員の急激な増加に伴ってその速やかな確立が急務となっている。 既に昭和40年の原子力委員会原子力事業従業員災害補償専門部会報告及び昭和48年の原子力局個人被ばく登録管理調査検討会報告において被ばく線量中央登録管理制度の確立が提言されているが、更に昭和50年には原子力委員会原子力事業従業員災害補償専門部会はこうしたシステムにつき速やかに結論を出すよう提言している。 当庁においては、この報告を受け、まず「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)適用下の原子力事業者から被ばく線量中央登録管理事業に着手するものとした。 こうしたことから、当面確立すべき従業員被ばく線量中央登録管理制度の具体的内容について検討する必要があるので、原子力安全局において標記検討会を開催する。 2. 調査検討事項
原子炉等規制法適用下の原子力事業を対象として確立する従業員被ばく線量登録管理制度のシステム構成及び運用に関する具体策について
3. 開催期間等
(1) 検討会は、月1〜2回開催する。 (2) 検討会の検討期間は昭和52年6月までを目途とする。 (3) 検討会の庶務は、原子力安全局原子力安全課において処理する。 4. 構成
| ||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |