| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
放射線医学総合研究所昭和52年度業務計画 昭和52年3月
第Ⅰ章 基本方針
本研究所は、昭和52年度において創立20周年をむかえるが、この間、放射線による人体の障害及び放射線の医学利用に関する調査研究ならびにこれらに従事する技術者の養成訓練について多くの成果をあげてきた。近来原子力平和利用の進展にともない環境放射能安全研究に関する社会の関心は一層高まってきている。従って昭和52年度において本研究所としては、これまでの実績の上にたって本所への各界の期待に応えるとともに長期的観点のもとに本来の使命が達成できるよう調査研究活動を推進して行くこととする。このため引き続いて昭和48年度に定めた本研究所の「長期業務計画」ならびに原子力委員会の定めた各般の計画等を基として本年度の業務計画を策定した。 第1節 計画の概要と重点
1. 研究部門
(1) 特別研究としては関係各部が総合的に協力して実施する研究として次の3課題について行う。 ①:環境放射線による被曝線量の推定に関する調査研究(継続、昭和48年度開始)
②:低レベル放射線の人体に対する危険度の推定に関する調査研究(継続、昭和48年度開始)
③:サイクロトロンの医学利用に関する調査研究(継続、昭和51年度開始)
(2) 指定研究としては、経常研究のうちすでに実績を有し将来の発展が予想される課題、又は緊急に着手、推進すべき課題を選定し、本所における調査研究の充実に資するため3課題を実施する。 (3) 経常研究は、本所の果たすべき使命の達成を期する上での研究活動の源泉であり基盤をなすものであるので、高度の学問的水準を維持し得るようその充実をはかることとし、73課題を実施する。 2. 技術部門
研究業務を円滑に推進するため、施設設備の適切な運営をはかるとともに放射線安全管理施設の更新ならびに環境保全対策を計画的に実施する。実験動植物については調査研究の進展に応じ生産、飼育に一層の努力をするとともに検疫ならびに開発業務を促進する。医用サイクロトロンに関しては、より有効な利用をはかるため、安全管理に十分留意しつつ円滑な運転体制をとるとともに関連設備の整備を推進する。 3. 養成訓練部門
関連各部の協力のもとに放射線防護、RIの医学利用等に関する技術者の養成訓練を実施する。 4. 病院部門
前年度までに得られた実績をもとに医用サイクロトロンの効率的運用を促進し速中性子線治療等の効果をあげるため、診療体制の充実をはかるとともに関連各部の密接な協力により診療内容の一層の向上を期する。 5. 施 設整備
(1) 「晩発障害実験棟」(5カ年計画)を完成させる。 (2) 「廃棄物処理施設」(更新、3カ年計画)および (3) 「サイクロトロン棟冷却水循環施設」(2カ年計画)の工事に着工する。 第2節 機構、定員、予算
1. 機構、定員
機構については、本年度は前年通りで次頁の如く16部54課室である。定員は、内部被曝障害研究ならびに速中性子線治療研究の強化のために4名の増員を行い(定員削減4名)52年度末で419名である。 2. 予算
以上の業務を遂行するための本年度の予算は、総額2,912,396千円で前年度の当初予算2,660,986千円に比し251,410千円の増となった。主要な予算の事項は、特別研究214,510千円、サイクロトロン設備整備311,978万円、晩発障害実験棟119,090千円、廃棄物処理施設 1.機構 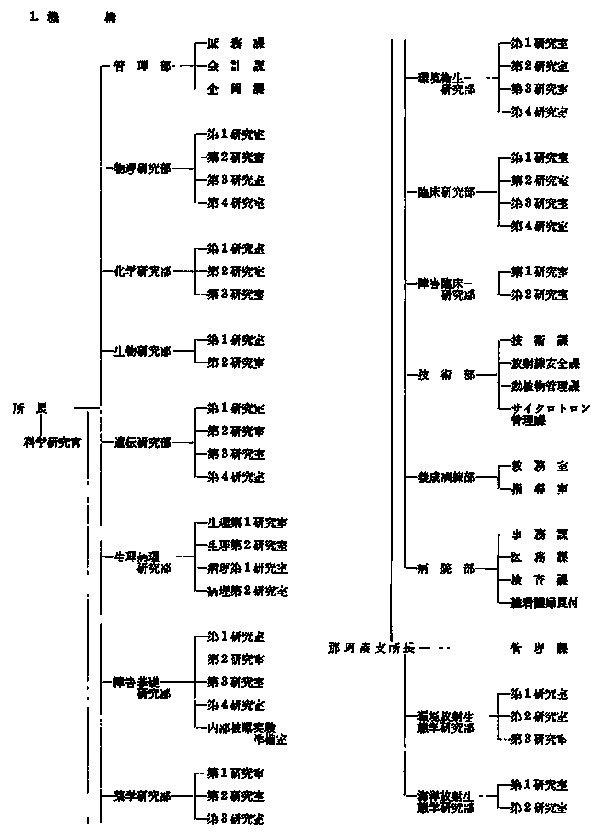
2.定員 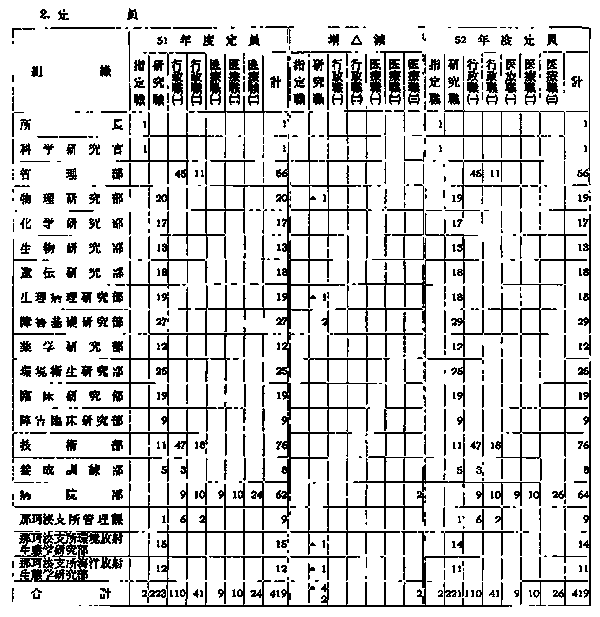
3.予算 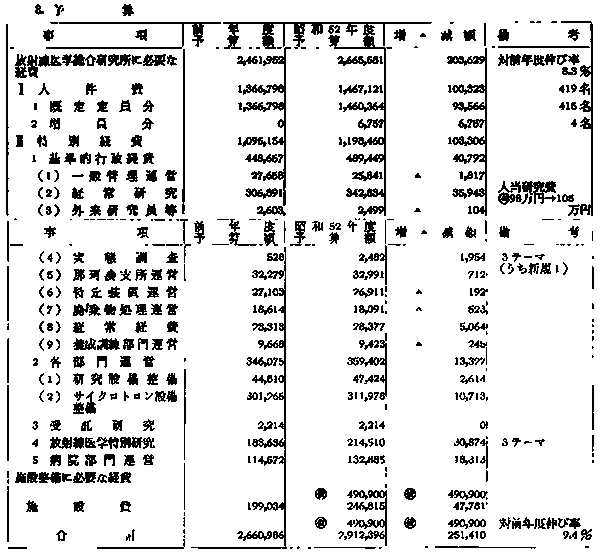
第Ⅱ章 研究
第1節 特別研究
本年度は、特別研究の実施に必要な経費として、214,510千円を計上する。 各課題の概要は次のとおりである。 1-1 環境放射線による被曝線量の推定に関する調査研究
本調査研究は、昭和48年度を初年度とする5カ年計画により着手したもので、原子力施設から環境に排出される放射性物質等に関し、排出されてから人体に至るまでの環境中における放射性物質の一連の挙動を総合的に把握し、個人及び集団の被曝線量を的確に推定する。これにより、一般公衆に対する放射線の防護と被曝の軽減に資することを目的とする。 本調査研究の実施に必要な施設設備の整備が諸般の事情により遅延し、当初の研究計画に遅れをきたしたが、52年度においては、前年度に引き続き、沿岸海域に放出された放射性物質の挙動等を究明する海グループ、大気・土壌・陸水など陸圏における放射性物質の挙動を究明する陸グループ、線量推定に必要な人体のデータを得るための調査研究を行う人グループ、体外線量推定等のための体外被曝グループ、トリチウムの食物連鎖中の挙動等を追求するトリチウムグループの各々のグループにより進捗度に応じ重点的に調査研究を進め最終年度としての一応の成果を得ることとする。このため引き続き次の5グループを設けて本研究を推進する。 1 低レベル放射性廃液の沿岸放出による人体被曝の予測に関する調査研究グループ
2 大気、土壌、水圏における放射性物質の移行に関する調査研究グループ
3 標準日本人の各元素摂取量と体組織濃度の決定に関する調査研究グループ
4 体外被曝線量の推定および放射性気体のモニタリング法の開発に関する調査研究グループ
5 トリチウムの食物連鎖における動向と生物への影響に関する調査研究グループ
1-2 低レベル放射線の人体に対する危険度の推定に関する調査研究
本調査研究は、昭和48年度を初年度として、ほぼ10カ年に及ぶ長期計画のもとに着手したもので、環境放射能による低線量及び低線量率被曝の人体に対する身体的、遺伝的危険度を推定し、一般公衆の放射性防護のための総合的影響評価に資することを目的とする。 本調査研究については、当面、低線量及び低線量率被曝の人に対する放射線障害の危険度を推定するうえに重要な晩発性の身体的影響及び遺伝的影響、並びに被曝様式の特異性からみて、特に内部被曝の障害評価の三つの研究分野に分けて、これを実施する。 1 放射線による晩発障害の危険度の推定に関する調査研究
現在までに得られた人の放射線被曝例の調査結果と、本研究所においてこれまで蓄積された造血器障害の研究成果の基盤に立って、生体の調節機構と発癌との関係及び実験動物系と人との相互関係の二点からこれを実施する。 本調査研究を遂行するうえで必要な晩発障害実験棟は、本年度に完成するが、次年度以降の本格的研究に備えて、前年度に引き続いて次の調査研究グループにより予備的実験と実験方法の開発を継続し、併せて研究体制の整備、国内外の情報収集等に努める。 (1) 放射線発癌の発症機構の研究グループ
(2) 血液幹細胞動態よりみた放射線誘発白血病発症機序の研究グループ
(3) 細網内皮系体液性因子等の造血統御機構が放射線白血病の発生機序に演ずる役割の研究グループ
(4) 免疫機能に対する放射線の晩発効果に関する基礎的研究グループ
(5) 放射線による異数性クローンの生成とその特性に関する研究グループ
(6) 放射線による細胞のトランスフォーメーションの研究グループ
(7) SPFマウスの加令性変化に関する病理学的研究グループ
2 放射線による遺伝障害の危険度の推定に関する調査研究
低レベル放射線の遺伝障害を明らかにするため、特に染色体異常に着目し、人に近縁な霊長類を用い、体細胞と生殖細胞について、低線量域における線量効果関係を明らかにする。これと人類体細胞の結果とを比較することによって、人についての遺伝障害の危険度の推定を行う。 このため、本年度は前年度に引き続いて行う4課題の他に生殖細胞の形質異常の研究及び放射線突然変異の線量効果の研究の2課題を新たに設定して、それぞれグループを編成し研究の推進を図る。 (1) 霊長類における放射線誘発染色体異常の比較遺伝学的研究グループ
(2) 低線量放射線による染色体異常の線量効果の研究グループ
(3) 霊長類における放射線の長期微量照射の遺伝学的効果に関する研究クループ
(4) 放射線による生殖細胞系の形質異常に関する研究グループ
(5) 霊長類の実験システムの開発に関する研究グループ
(6) 培養細胞における放射線突然変異の線量効果関係の研究グループ
3 内部被曝の障害評価に関する調査研究
内部被曝による障害評価においては、放射性核種の代謝の量的把握がその基盤をなしているが、この代謝は人並びに動物種間に少なからぬ相異のあることが知られている。 本研究では、超ウラン元素の吸入実験を行うための実験施設の概念設計を行うとともに、内部被曝の障害評価を人に外挿するための多種の動物の比較生物学的研究を実施する。このため、本年度は、内部被曝実験施設の設計研究について特殊実験室等の概念設計を進めることとし、前年度に引き続き次の2課題に関し、それぞれグループを編成して研究を推進する。 (1) 内部被曝実験施設の設計に関する研究グループ
(2) 放射性核種の代謝に関する比較動物学的調査研究グループ
1-3 サイクロトロンの医学利用に関する調査研究
本調査研究は、医用サイクロトロンを利用し総合的な研究体制のもとに、疾病の診断及び治療の研究を推進することを目的として昭和51年度より3カ年計画で着手したものである。速中性子線によるがんの治療は順調に実施され予期したとおりの効果を挙げているほか、短寿命ラジオアイソトープを生産し臨床に使用することが可能な段階に達した。昭和52年度においては、今までの経験に基づいてよりがん治療成績の客観的な評価のためのクリニカルトライアルをさらに推進する。 また「速中性子線治療研究委員会」及び「短寿命及び陽電子RIの医学利用の開発に関する研究委員会」を引き続き運営するとともに国際研究協力に留意し、治療基準の相互比較等を実施する。 陽子等の荷電重粒子線は診断及び治療の両面において優れた特性を有し、今後その実用化が期待されているので、陽子線の医学利用に関する基礎的研究を前年度に引き続き実施する。これらの研究を推進するため、以下の研究課題を設定し、それぞれグループを編成し目的達成に努める。 1 短寿命及び陽電子RI等の医学利用の開発に関する研究グループ
2 粒子線治療に関する基礎的研究グループ
第2節 指定研究
指定研究としては、本年度は次の課題を設定し、これを積極的に推進する。 1 γ線によるマウス脳細胞DNA損傷とその修復-加令との関係 (生物研究部)
2 放射性核種(金属)排泄促進剤としてのDTPA-金属キレートに関する化学的研究 (薬学研究部)
3 無菌マウスに関する研究-里親・飼料・長期飼育- (技術部)
第3節 経常研究
本年度は、経常研究に必要な経費として、研究員当積算庁費233,625千円及び試験研究用備品47,424千円をそれぞれ計上する。 経常研究に関する各研究部の本年度における方針及び計画の大要は、以下のとおりである。 3-1 物理研究部
本研究部は各種放射線の医学利用と障害の予防に必要な線量の測定と防護方法に関する研究をおこなうことを目的としている。 人体内放射能の測定に関してはガンマ線イメージ検出器の高速化及びポジトロン・イメージングの研究をおこなう。 放射線の吸収線量の評価に関しては、電離箱のイオン再結合損失、電子と物質との相互作用におけるエネルギー損失、LET分布および治療線量のトレイサビリティの確立に関する調査研究をおこなう。 放射線防護に関しては、加速器の遮蔽、各種被曝における決定臓器の線量評価、作業者の被曝低減に関する研究の所、ベータ線イメージングの基礎研究もおこなう。 重粒子線の医学利用に関しては、プロトンの医学利用のための準備をすすめるとともにKEKブースターの医学利用の研究を進める外、サイクロトロンにより生産されるRIの絶対測定および放射化分析の基礎的研究をおこなう。 3-2 化学研究部
本研究部では、生体の放射線障害の発現に関する基本問題を生物化学的に解明する一方、無機化学および物理化学の立場から、放射性同位元素の分析法の開発や無機元素に対する種々の有機化合物の作用について研究を継続する。 (1) 生物化学的研究
染色体の基本構造としてのDNA-蛋白質複合体の構造化学的研究、酵素活性の調節機構の研究、遺伝子DNAに起った損傷の修復機構の生化学的研究、免疫抗体産生機構における食細胞機能の生化学的研究、DNA複製と細胞分裂の制御機構の研究などを行い、多岐にわたる生命現象の本質の解明につとめる。 (2) 無機および分析化学的研究
放射性同位体に対する正確かつ簡便な分析法と選択的な無機化合物の捕集法の開発に関する基本的な研究を行う。キレート化合物や新しいクラウン化合物などと無機元素の結合状態に関する物理化学的な研究をも推進する。 3-3 生物研究部
本研究部は、生体における放射線障害発現の機構を究明する。 照射や発癌剤処理等による動物細胞DNAの傷害およびその修復を検討し、修復不能なDNA傷害の質・量を把握する。 一方、障害発現における細胞質の役割を明らかにするため、生体膜の構造的・機能的変化、細胞質の代謝調節に与る酵素の変化などについて検討する。 また、組織・個体レベルでの研究を推進する。まず、皮膚組織の増殖調節機構の照射による変化を調べ、発癌機作ならびに癌の放射線治療の基礎的知見の入手につとめる。 一方、魚類について内部被曝をふくめ、低線量率照射による生殖細胞の増殖と分化の変化、また化学発癌剤と放射線の併用による肝腫瘍の発生等について検討する。さらに種々の環境条件にあるアルテミアの生殖能力と老化の様相を把握する。 3-4 遺伝研究部
本研究部は放射線による遺伝障害の機構を解明し、危険度推定のためのシステムの樹立を図り、これに基づく各種データを得て、放射線による遺伝的危険度の推定を行うことを目的としている。このため、これに必要なヒトを含む高等生物遺伝学の研究を推進する。 分子レベルの研究については、酵母を用い放射線障害の回復過程の遺伝的支配の機構の解明を図るとともに培養哺乳類細胞を用いて各種突然変異体を分離し、高等生物の突然変異の特質を明らかにする。 細胞レベルの研究については、特別研究に主力を注ぎ、特にヒトを含む霊長類を用いて染色体異常についての低線量、低線量率の線量効果を明らかにする。 集団レベルの研究については、三島地区の調査を行い日本人集団の統計的性質の解明を図るとともにショウジョウバエの人工集団を用い放射線の遺伝効果の一層の解明を図る。 3-5 生理病理研究部
本研究部は、人体の放射線症の機構を研究し、その病理像を樹立することを目指している。それゆえ、生体を構成する細胞、組織、器官のレベルでの放射線効果を研究する。また、二次的には腫瘍に対する放射線治療の細胞生理学的、病理学的基礎にも貢献する。 生理研究部門では放射線症における免疫機能の重要性にかんがみ、キメラ個体を用いて免疫反応の遺伝学的基礎を追究する。また哺乳類、培養細胞を用いて障害論の基本的単位である細胞致死損傷と回復の研究を行う。DNAの分子損傷、複製障害を調べる。 病理研究部門は放射線治療に抵抗する悪性黒色腫を細胞感受性、転移性の面より調べ、他の人癌と比較研究を進めて抵抗性の本態を解明する。他方、造血器障害の病理発生を明らかにするため、幹細胞の分化、増殖の制御機構を網内系、体液性諸因子との関連において研究する。 3-6 障害基礎研究部
本研究部は人体における放射線の急性、晩発性障害ならびにその予防などに関する基礎的資料をうるために、哺乳動物を用いて以下の調査研究を行う。 放射線の急性効果での細胞障害について、細胞膜への効果に関して、また栓球系への影響ならびにその修飾に関しての実験検討を行う。障害評価のために照射様式を変えた動物での急性晩発障害についての実験を行い、その成果の検討ならびに解析を行う。造血系あるいは腫瘍系をモデルとして晩発障害発現の機構を検索する。また中枢神経系の晩発障害についてその発現ならびに発現機序を解明するために電気生理学的ならびに組織学的に検討する。内部被ばくによる障害の特異性に関する要因の追求によって、内部被ばくによる障害評価に資する基礎資料をうる。また超ウラン元素としてプルトニウムの内部被ばくの特殊性および重要性に注目し、粒子状プルトニウムの体内分布、ならびに生物学的効果を検討する。 3-7 薬学研究部
放射線障害の解析と回復に関して、有機化学、生化学的立場から、関連する生理活性物資の合成、抽出、精製、構造解析、作用機構等について実験を行う。 種々の物質に対する放射線作用の初期過程を、迅速測定技術を利用して化学的に解析すると共に、スーパーオキサイド・イオンを電気化学的に生成し、その物理化学的研究を行う。 放射線増感、防護物質や発癌制癌物質等の作用物質の構造を考慮しつつ、生理活性物質の化学的修飾および、それに関連する合成化学、構造化学的研究を行う。生殖腺の放射線障害に関する生理化学的研究において、精巣に存在するテストステロン合成酵素の酵素化学的分析と反応機構の解明を行い、新しく卵巣に対する放射線影響の基本的研究を開始する。放射線障害の回復を目標として造血機能に関連する細胞の増殖因子を抽出し、生化学的研究を行うと共に、増殖促進の作用機構を明らかにするため研究を行う。 3-8 環境衛生研究部
本研究部は環境放射線と放射性物質による人体の体外および体内被曝の経路とその機構の研究を実施し個人および集団の被曝線量の推定とその防護に資することとしている。 これらの調査研究のうち、経常研究として行っているのは次の通りである。大気中放射性核種の挙動、空間線量測定に関してのスペクトル解析手法の検討を行う。食物連鎖に関して水生生物の放射性核種代謝、哺乳動物での核種代謝とくに胎児、幼若令期での特殊性の研究を行う。137Csについてはフオールアウトを利用して人体測定を実施する。また、Puなど超ウラン元素については環境と人体での実測値を利用してその挙動の研究を行う。非放射性の微量元素濃度を各種人体組織について定量しその挙動の情報を得る研究を行う。一方放射性エアロゾルの存在する職場での吸入被曝の解析評価法を検討する。 3-9 臨床研究部
本研究部は病院、および関連研究部との協力のもとに、放射線の医学利用に関する研究を行い、定量的評価に基づき、放射線診断、並に放射線治療に関する基礎的・臨床的研究を推進する。 X線診断に関しては、より少ない線量をもってしても十分な情報を得るためのシステム開発と、画像情報より最終診断に至る工学系、ならびに診断の定量化に関する研究を行う。 核医学の分野では、短寿命RI生産が軌道に乗った今年度は、RI代謝とその解析、RI動態画像の情報処理に関する基礎的、臨床的研究は、さらに重要な課題となる。 放射線治療の分野では、腫瘍の放射線感受性と、その修飾に関する研究をすすめ、放射線による腫瘍治癒機転の解明を目指すとともに、正常組織、臓器に対する放射線効果の定量評価に関する研究を行う。 さらに、放射線治療入力情報を解析し、放射線治療成績の改善に役立てる。 3-10 障害臨床研究部
本研究部は人体に対する放射線障害の診断および治療に関する調査研究に従事している。 ビキニ被災者に関する追跡調査と健康管理は既に20年以上に亘っているが、これを続行すると共に、192Ir事故被曝者、トロトラスト被投与者について医学的検査を行う。特に血液学的、細胞遺伝学的ならびに免疫学的検査を重点的に実施する。また、骨髄造血能に関する定量的測定法の確立を目標として、正常人および被曝者について、造血幹細胞の定量法、特に末梢血を用いた幹細胞定量法を開発するよう努力する。 この他、放射線誘発白血病の発生機構解明の一助として、ヒト慢性骨髄性白血病について細胞遺伝学的研究を発展させる。また、加令による免疫能の変化も研究する。さらに、リンパ球の放射線照射による代謝障害について、主として実験的に研究を行う。 3-11 環境放射生態学研究部
本研究部は、環境中(海洋環境を除く)に存在しあるいは放出された放射性物質の、環境における大気、土壌、動植物などの間の蓄積、移行その他の挙動を研究することによって、これらに起因する個人あるいは集団の被曝の推定、予測、軽減方法を知ることをめざしている。 本年度は特別研究「環境放射線による被曝線量の推定に関する調査研究」の最終年度であるため、研究の主力はこれに向けられ、経常研究としては従来行ってきた3課題にかぎられる。 すなわち、①環境試料に含まれる核種分析を簡単かつ正確に行うため、スペクトル解析を主とした方法の開発を進める。②土壌中の核種の植物(いね)への移行に影響する諸因子、とくに共存元素の影響につき研究を行う。③人骨のストロンチウム代謝につき、とくに年令の影響と骨内の不均一分布に注目して研究を進め、放射性ストロンチウムによる線量預託推計に資する。 3-12 海洋放射生態学研究部
本研究部は、海洋環境中に存在し、あるいは放出された放射性核種の海洋中での動向、並びに海洋生物への移行等放射生態学的研究を行う。 本年度は、特別研究に重点をおくが、経常研究としては次の2課題を取り上げ実施する。①深海投棄された放射性物質に及ぼす共存物質の影響に関する研究では、放射性物質の深海処分後の環境安全に関する基礎的知見を求めることを目的としている。②安定元素分析及びRIトレーサー実験による無機物の環境中移動追跡法に関する研究では、特別研究で実施している海産生物の濃縮係数に関する研究を解析的に取り上げ、生物濃縮の機構を解明する知見を得ることを目的としている。 第4節 放射能調査
本研究所では、これまで放射能調査として、核爆発実験に伴う放射性降下物による環境放射能レベルの調査および原子力施設等の稼動に伴い放出される放射能レベルの調査について、解析研究を環境衛生、環境放射生態および海洋放射生態の各研究部において、また、国内外の放射能に関する資料の収集、整理、保存等のデータセンター業務を管理部企画課において、それぞれ実施してきた。 本年度は44,815千円を計上し、上記調査等に加えて新たに「放射能調査結果の評価に関する基礎調査」として①国民線量の推定に関する調査、②日本人に適用するための被ばく線量の推定および評価に関するデータの調査、を民間機関に委託し、これを実施する。 本研究所で行う放射能調査の課題は次のとおりである。 (1) 環境、食品、人体の放射能レベルおよび線量調査
① 大気浮遊じん中の放射性核種の調査
② 炭素-14の分析調査
③ 外洋の解析調査
④ 人体の放射性核種濃度の解析調査
⑤ 環境中のガンマ線々量調査
⑥ 屋内における放射線々量調査
(2) 原子力施設周辺のレベル調査
① 陸上試料の調査
② 沿岸海域試料の解析調査
③ 環境中のトリチウム測定調査
④ 環境、人体臓器中のプルトニウム等濃度測定
⑤ 原子力施設周辺住民の食品流通調査
⑥ 原子力施設周辺のモニタリングの基準化に関する調査
(3) データセンター業務
(4) 放射能調査結果の評価に関する基礎調査
① 国民線量の推定に関する調査
② 日本人に適用するための被ばく線量の推定および評価に関するデータの調査
第5節 実態調査
本研究所において、研究に関連する問題のうち必要な事項について実態調査を行い、その結果を活用して研究の促進を図ってきた。 昭和52年度においては、前年度に引き続きビキニ被災者調査及び医療被曝による国民線量の推定調査を実施するとともに、新たにトロトラスト被投与者の被曝線量の推定に関する調査を実施することとし、これに必要な経費として2,482千円を計上する。 (1) ビキニ被災者調査(障害臨床研究部)
(2) 非密封放射性同位元素による国民線量の推定のための調査(物理研究部)
(3) トロトラスト被投与者の被曝線量の推定のための調査(物理研究部)
第6節 外来研究員
本研究所における調査研究に関し、広く所外における関連分野の専門研究者を招き、その協力を得て相互知見の交流と研究成果の一層の向上を図ることを目的とする。 本年度はこれに必要な経費2,499千円を計上し、以下の研究課題について、それぞれ担当する研究部に配属させ、研究を実施する。 (1) 細胞死における膜系損傷の役割に関する研究
(2) 各種照射様式による哺乳動物の身体的障害の評価に関する基礎的調査研究
(3) 子宮頚癌の病理分類と放射線感受性に関する研究
(4) 魚類の汚染機構の生化学的研究
(5) トリチウムの生物に及ぼす影響研究における実験手法の確立
(6) 胸線機能のエイジングと放射線感受性の研究
(7) 霊長類生殖細胞の形態学的生理学的基礎研究
(8) 短寿命医用アイソトープの開発研究
第7節 受託研究
本研究所の所掌事務の範囲内において、所外の機関から調査研究を委託された場合、本研究所の調査研究に寄与するとともに研究業務に支障をきたさない範囲において受託実施することとし、このための経費2,214千円を計上する。 第Ⅲ章 技術支援
技術部では、経常運営費47,981千円、廃棄物処理費18,091千円、特定装置運営費26,911千円、サイクロトロン設備整備費311,978千円をもって、技術支援業務の計画的かつ効率的な運用に努める。 (1) 技術業務では、変電、ボイラ、空調等基本施設の運用にあたり、各部の要望に応えるよう保守管理体制を確保し、老朽化施設・設備の補強・改善を重点的に行う。また、最終年度を迎えた晩発障害実験棟建設工事(予算119,090千円、5年計画)を促進するとともに、新たに井水規制に対処するため、サイクロトロン棟冷却水循環施設設置工事(予算39,170千円、2年計画)に着手する。共同実験施設および共同実験用測定・分析機器、放射線発生装置関係では、研究部門からの高度化かつ多様化する要望をふまえて、施設の改善および効率的運用ならびに機器・装置の運用調整、更新、修繕等を計画的に行う。 データ処理業務では、電算機の円滑な利用体制を維持し、研究面については、病歴管理および医用画像処理ソフトウェア・システムの開発・改良を推進する。また前年度に引続き、新型電算機システムの導入調査も行う。 (2) 放射線安全管理業務では、経常的業務の推進に努めるほか、①放射線安全の立場から所内施設の再整備等必要な措置を講ずる。②職員の放医研入所前の被曝歴の再評価の実施 ③放射性同位元素の管理等を一層合理化するため、管理区域立入り管理システムの導入を図る。 廃棄物処理業務では、老朽化の進んでいる廃水処理施設の更新を行うため、本年度より3年計画で、 (3) 動植物管理業務では、研究計画に呼応して、必要な種、系統の実験動植物の生産・供給に努めるが、所要の一部特殊系統マウスについても、SPF化を図るべく業務を進める。また、動物衛生および検疫業務を一層促進しうるよう体制を整備し、実験動物の微生物学的、病理学的検索の強化を図る。一方、動植物関連施設の円滑な管理、運用を期するため、老朽化・安全対策等、施設・設備の整備に努力するとともに、晩発障害実験棟の本格的稼動に備え、実験動物管理に関する問題点の検討を行う。実験動物に関する研究としては、特別研究の課題を分担するほか、無菌マウスに関する研究、その他を実施する。 (4) サイクロトロン管理業務では、研究面においては、運転性能向上に関し、位相測定装置の開発を継続し、位相の変化を電磁石にフィードバックする位相安定化の研究へと進展させる。重イオン源の研究では、前年度で設計試作を終了したので、その性能特性について研究を進める。このほか、加速粒子エネルギーおよびエネルギー幅の測定などを行う。サイクロトロン運転技術関係では、効率的運転保守に努めるとともに、陽子線の利用に備え、ビームボート系の整備を行う。 短寿命放射性同位元素の生産では、従来と同様、関連特別研究班との協力のもとに、ルーチン生産、ならびに試験生産を行う。また、有機RI標識合成装置の整備を行う。 第Ⅳ章 養成訓練
養成訓練部は、昭和34年度から前年度までに、下表のとおり研修課程を実施し、課程修了者の累計は、2,041名に達した。 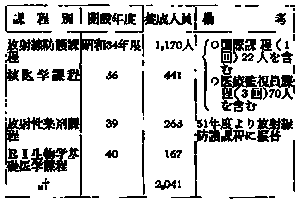 本年度は、運営経費として、9,423千円を計上して研究所の長期業務計画の方針に従がい教科内容の充実をはかり、関係各部との緊密な協力のもとに効率的且つ合理的な運営により研修効果の向上をはかる。 実施する課程は、次の6回で150名の科学技術者を養成する予定である。 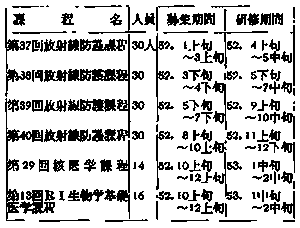 なお、内外の養成訓練制度について調査をすすめるとともに、研修成果の向上をはかるために必要な研究を行なう。 第Ⅴ章 診療
病院部は、運営費161,262千円を計上し、設置目的に即した患者の受入れ態勢を整備する。特に医用サイクロトロンによる速中性子線治療適応患者については、最優先とし、前年度の2倍の200人の受入れを目標に所内外の関連各研究者、施設との連けいを密にするよう努める。このため予算定床を8床増を図るとともに看護婦2名の増員を行う。 放射線障害患者の診療については、従来からのビキニ、イリジウム、トロトラスト等に係る患者の追跡調査を継続するとともに、新たな患者及び放射線治療患者を含めた造血能、免疫能の障害について、その診断法について関係研究部に協力する。 悪性腫瘍の放射線治療については、精度と再現性に富む安全有効な治療技術の確立を期するため、速中性子線、X線、r線、電子線等を用い、外部、腔内、組織内、あるいは開創術中等の照射法を駆使して、患者の病状に即した適正治療法手技について関連研究部と協力のうえ開発研究を進める。このために必要な医療機器等の整備を行い診療精度の向上を期する。 RIの医学利用については、悪性腫瘍患者治療の適応判定に資するため、サイクロトロン生産核種等の利用を関係研究部や特別研究班と協力し、病巣の局在や各種臓器の機能診断法の開発研究を行う。 患者の追跡調査は、臨床的研究の評価に不可欠であり、本年度より特別診療研究として新たに放射線診療のシステム化に関する研究を設定し、速中性子線治療患者を始め、全患者の追跡調査を進めるとともに、診療の実際における精度の向上、安全有効な新たな診療技術の開発、利用の推進に努める。 第Ⅵ章 研究施設整備計画
1.晩発障害実験棟 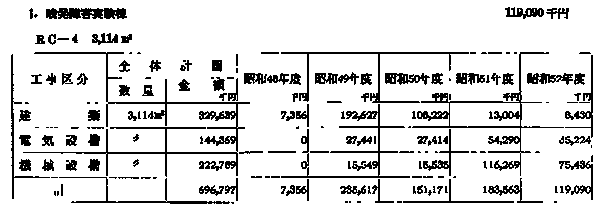
2.サイクロトロン棟冷却水循環施設 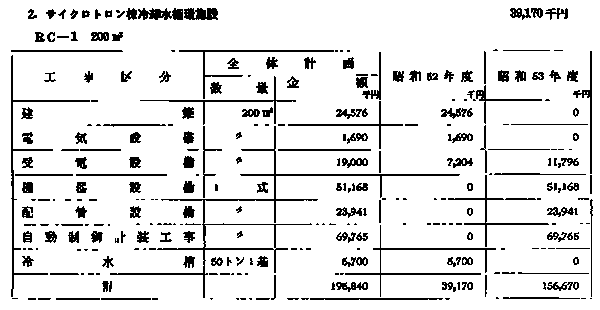
3.土留工事 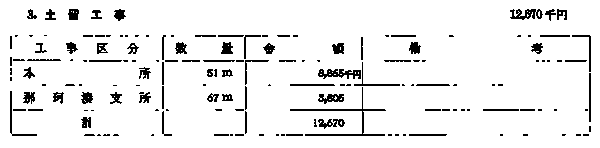
4.廃棄物処理施設 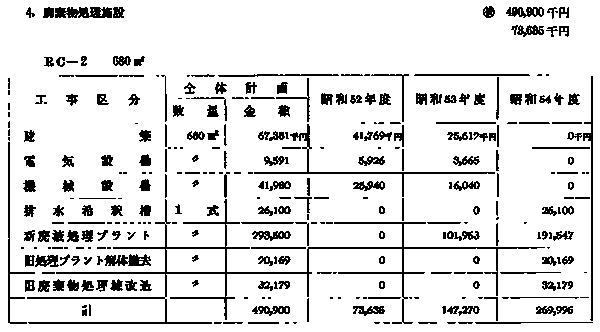
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |
 490,900千円等である。他に放射能調査研究費として44,815千円が計上されている。
490,900千円等である。他に放射能調査研究費として44,815千円が計上されている。