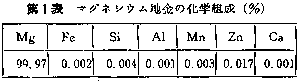原子力平和利用研究の紹介
古河電気工業の33年度研究
昭和33年度原子力平和利用研究費補助金による原子力平和利用研究のうち、原子炉用マグネシウム合金の製造に関する研究(古河電工)を以下に紹介する。
1.緒 言
コールダーホール発電炉の燃料被覆にマグネシウム合金が採用されて以来、原子炉用材料としてマグネシウムが注目されるようになった。核燃料被覆材としてはマグネシウム合金、不銹鋼等も使用されているが、天然ウラン炭酸ガス冷却型発電炉に使用されており、今後も同型炉に使用を予定されているのはマグノックスなる名称のベリリウム・アルミニウム・マグネシウム合金である。
本社においては、この種のマグノックス系合金の鋳塊ならびに鋳塊検査に関して研究を行なったが、その概要を以下に記す。
2.研究方法
(1)造塊法に関する検討
a 溶解法
マグネシウムを空気中で溶解すると音容湯が着火燃焼を起こすのでフラックスで溶湯を十分包みながら溶解しなければならず、注湯中へフラックスを巻き込まないで鋳込むためには高度の熟練を要する。そこでこの研究では次の二つの溶解法を取り上げて比較検討した。
(a)フラックスを使用する溶解鋳造法 (普通溶解法)
(b)フラックスを用いない溶解鋳造法 (アルゴン溶解法)
b 造塊条件
上記の溶解法のそれぞれについて次の4項目を組み合わせた条件で実験を進めた。
(a)溶解条件 680〜750℃の温度区間を適当に区切った鋳込温度
(b)鋳塊条件 680〜750℃の温度区間を適当に区切った鋳込温度
(C)鋳型条件 100〜300℃の温度区間を適当に区切った鋳込温度
(d)静置時間 0〜60分間を適当に区切った静置時間
c 検討した項目
以上の条件を組み合わせて得られた鋳塊について主として次の項目を調べた。
(a)鋳造組織、鋳肌
(b)巣、ピンホールの発生およびフラックス、酸化物の巻込状態
(c)偏析状態
(d)鋳塊組織と顕微鏡組織との関係
d 研究した合金の組成
Al:0.5〜1.5% Be:0.005〜0.1%
Mg:残部
e 溶解量
1回の溶解量10kg
f 鋳塊寸法
150mmφ×300mm(押出用素材の寸法)
(2)鋳塊検査法に関する検討
検査法としては、X線法および超音波を取り上げ比較検討した。
3.合金の配合および試料
普通溶解の場合にはまずマグネシウムをフラックスで被覆しながら溶解し、マグネシウムが溶け始めたら少量のAl-Be中間合金(4.9%Be)を加え、湯の温度が所定温度に到達したならば残りのAl-Beと不足分のAl(99.99)とを加えて所定量の合金配合を終る。Beを添加するとマグネシウム溶湯の着火燃焼を抑制するのでフラックスの使用量は一般マグネシウム合金に比較して少量でよい。しかし湯をかくはんする際には着火するので注意を要する。また注湯に際して湯の上へイオウ粉末をふりかける必要もない。
アルゴン溶解の場合には試作した溶解装置を使用するので、マグネシウム地金、Al-Be中間合金、Al等をるつぼへ同時に装入して溶解槽内の雰囲気をアルゴンとした後溶解鋳造した。第1表に使用したマグネシウム地金の組成を示す。
第1表 マグネシウム地金の化学組成(%)
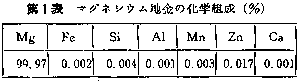
4.実験結果
(1)鋳塊の諸性質に及ぼす造塊条件の影響
a 鋳肌
普通解溶法で得られた鋳塊では鋳肌がたいてい黒灰色かまたは黒灰色の縞模様を現出するが、アルゴン溶解では金属光沢を有し、鋳放しのままで鋳塊面のマクロ組織を判別できる。しかし鋳肌と造塊条件との相関関係は認められなかった。
b 鋳造組織
溶解温度を高くし鋳込温度を低くすることにより良好な鋳造組織が得られた。また溶解温度を高くすることにより鋳塊の結晶粒度を微細化することができることも判明した。
純マグネシウムについても同様の実験を行ない鋳塊組織と造塊条件との関係を検討したところ、マグノックスの場合に準じた結果を得たが微細化効果はきわめて僅少であった。すなわち溶解温度を高くすることによる結晶粒度の微細化効果はAlおよびBeの添化によって顕著になることがわかった。
c 巣、ピンホールの発生について
普通溶解法で得られるマグノックス鋳塊では一般に鋳塊表層部の厚さ5〜10mmの部分にピンホールが発生しやすく、また鋳引部分の下方に巣ができやすい。この傾向は溶解雰囲気中に水分の多いとき、または吸湿Lたフラックスを使用したときより強くなる。鋳塊内部へのフラックスの巻込みが少なくかつ上述の内部欠陥の少ないインゴットを製造するには作業員の高度の熟練が要求される。
しかし、今回試作したアルゴン溶解鋳造装置を使用すればフラックスを用いることなく、したがって鋳塊中への混入物が少なくかつ上述の巣、ピンホールの比較的少ない実用寸法の鋳塊(150mmφ×300mm)を容易に得ることができる。しかし、造塊工程に溶解槽内へのアルゴンの導入その他の操作が入るので普通溶解法に比較して作業が多少複雑になる。しかしながら、アルゴン溶解を行なう場合においても使用するマグネシウム地金および配合する材料の表面を清浄にして配合することが望ましい。
d 配合組成と鋳塊組成
マグノックス中のBeは合金に耐酸化性を付与するために配合されているから溶解操業中にBeが酸化消耗し、配合組成の変動することが考えられる。そこで配合組成の変動状態と造塊条件との関係を詳細に検討した結果、標準組成のマグノックスA-12相当の鋳塊を得るにはBe配合量を多くした別の配合を行なわねばならぬことが明らかとなった。この場合のBeの割増量は溶解温度、鋳造温度および湯の静置時間等に左右される。すなわち、溶解温度が高いほど、静置時間が長いほどBeの割増量を多くしなければならない。AlとBeは逆に標準配合率よりやや少なめに配合するはうが良い。またアルゴン溶解の場合は普通配合の場合より Beの割増量を少なくしてもよい。こうして割増しされたBeはフラックスを使用する普通溶解ならば酸化による消耗と考えられるが、アルゴン溶解の場合は雰囲気中における酸素の分圧が空気の場合の数万分の1であって、Beの消耗の理由を前者と同様には考えられないことがわかった。そこでこの点を検討した結果、マグノックスの溶解中に溶解槽壁、鋳型壁等に蒸着するマグネシウム粉末中に濃縮して含まれていることが明らかとなった。濃縮の割合は造塊条件によって異なるが、たとえば800℃でアルゴン溶解を行ない、680℃で鋳込んだ場合には原料に配合したBe量の2〜3倍ぐらいであった。
e 鋳塊内の偏析
鋳塊内におけるAlおよびBeの偏析は造塊条件によって異なるが、偏析状態から分類すると次の二つになる。
(a)鋳塊表層部の中心部に対する偏析
(b)鋳塊上層部と下層部との間の合金成分の相違
(a)の偏析は適当な造塊条件を選ぶことにより軽減することができ、しかも実際に鋳塊を押し出す場合には5〜6mmの厚さを面削するので実用上のさしつかえは起こらない。
(b)の偏析類似現象は特にBeについて認められる現象であるが、適正な条件でアルゴン溶解を行なうことにより防止することができる。
f 顕微鏡組織
コールダーホールで使用されているマグノックスC合金ではBeの含有量が0.04%であるのに最近建設されたハンターストンその他の炉に使用されるマグノックスA-12のBe量は0.01%であってBe量がかなり減少している。そこでこの理由について顕微鏡的な検討を行なった。すなわち0.005〜0.09%Be、0.8〜0.9Al、残部Mgのマグノックス系合金の鋳造組織、加工組織、再結晶組織を顕微鏡的に観察した。その結果Beが0.01%をこえると結晶粒内または粒界に球状の物質が認められるようになり、Be%が増加するに従って球状物質も増加し、Be%が0.02%以上になると球状物質が粒界付近に集積する傾向を持つこと等が明らかとなった。この球状物質がジュネーブ会議で報告されたMgBe13 またはこれと類似の金属間化合物であるならば一般に硬くかつ脆いはずで、このような球状物の点在しているマグノックス(六方晶)を加工した場合には球状物の周辺に小さな亀裂の発生が懸念される。またジュネーブ報告によれば300〜400℃でクリープ試験を行なった試験片の断面を顕微鏡で調べたところ、結晶粒界に多数のキャビティの生成を認めたと報じている。粒界付近に以上のキャビティが発生したり、球状物質が存在したりすることは材料の面から好ましいことではない。したがって所要の耐酸化性を保持しうる最低限度までマグノックス中のBe量を減少しようとする理由も納得できる。
(2)鋳塊の欠陥検査について
マグノックス鋳塊を大量に検査する方法としてまずX線法と超音波法とを取り上げ、検査条件を検討した。マグネシウム合金の非破壊検査法については、わが国のみならず外国文献にもないので、マグノックス素材を使用して種々の形状の試験片を作成し、これに人工的欠陥を付与して適正検査条件を検討した。たとえばX線法により150mmφ×270mmの鋳塊を検査するにはS型フイルム2枚を鉛箔増感紙と組み合わせてカセッテに納め、カセッテの上に鋳塊を横に置いてX線を投射する。この場合の撮影距離は120cm、電圧は130kV、露出時間は3分間で良好な結果が得られた。欠陥検出分解能は被検物の厚さ1.4%ぐらいである。 次に超音波を使用すれば、被検物の厚さが30cmのときに3〜5MCの周波数において大きさが0.5mm以下の欠陥をも明確に検出することができる。また被検物を水中に入れて検査する場合には5〜10MCで良好な結果が得られた。しかし鋳塊の結晶粒度は一般の金属材料に比較して大きくかつ粒度が不ぞろいであるから検査のつど被検鋳物に適合するように探傷装置を調節するほうがよい。
5.結 言
以上マグノックス系合金の造塊法ならびに鋳塊検査法について実施した研究結果の概要を記述した。すなわち適正な条件で造塊すれば材質の均一した鋳塊を製造することができる。また鋳塊を検査する際のX線法および超音波法にはそれぞれ長短があるので一概にはいえないが、大量の造塊を処理する場合には両者を併用するのもー方法であろう。