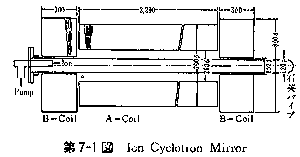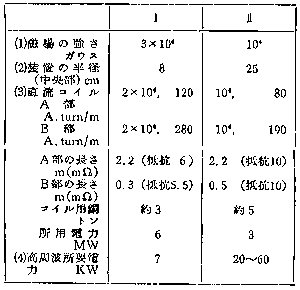|
核融合研究委員会報告書B計画報告書 本核融合研究委員会は1959年3月30日原子力委員会核融合専門部会(部会長湯川秀樹)が原子力委員長あてに答申した「核融合反応の研究の進め方について」(第4巻第4号37ページ参照)に基づき組織されたもので、答申中にある「B計画」を立案する研究委員会であり、予算、運営の便宜上日本原子力研究所内におかれた。 答申にあるB計画とは、外国である程度成功(注1)をみた型を参照して1,000万度(注2)程度のプラズマを発生し、ある時間保持する中型装置(注3)をすみやかに建設し、プラズマ科学の研究に資し、合わせてわが国核融合研究の強固な足場とすることである。 当初からこの委員会は研究体制やB計画そのものの批判に閑せず、わが国が近い将来持つことを望まれる中型超高温プラズマ発生装置の物理的、技術的検討、立案に重点をおいた。その主旨に沿い委員長が代表的な人々と相談の上委員を組織した。 メンバーは後記のように、実質的作業に参加できそうな人のほかに、わが国の主要な核融合研究グループの代表的研究者が参加するように配慮された。それは当初は特に大切な大局的判断をくだす段階にあり、また全国的な研究連絡、意見の疎通を容易にするためである。(注5)メンバーは、型式の種現、検討、設計の進行段階に応じて適宜追加または臨時参加をみた。 このように本委員会は研究体制諭におけるB計画の立場について統一的見解のもとに構成されていない。したがって委員会はこの点には触れぬ立場として運営された。触れた場合も単に参考的に意見分布を知る程度にとどめ結論を導くこととしなかった。 B計画としておよそ了解されている主旨、意義は、中型実験装置をすみやかに建設することにある。「すみやか」の度合、すなわちタイムスケジュールは核融合研究の進め方をきめる場合きわめて重要なポイントである。この点に関しては各委員の見解は必ずしも一致しなかった。しかし多くの実験研究者の要望があったので、最も早く実地に移す場合を考慮し、次年度の予算編成の可能性を保ち、まず59年7月までにいわゆる「1次設計」を行なう方針をたてた。そしてほぼ予定どおりにそれを終った。 しかしこの方針は'59年8月以降生じた研究体制の新しい事情のためにただちに実施される見通しを失ったので、1次作業に続く作業を保留し、残余の検討を若干補って今日に至っている。 あらゆる意味で現在は一つの屈曲点にあるので、この機会に本委員会はこれまでの成果をひとまず取りまとめることとした。もし今後新しい方針のもとに再出発されるならば、その成果は年度末に補追報告が加えられることになろう。 当研究委員会は発足にあたり、菊池原子力委員(現日本原子力研究所理事長)から格別の御配慮と御指導をいただき、また委員会運営については、科学技術庁原子力局佐々木局長、法貴次長ほか担当の方々、日本原子力研究所駒形前理事長、嵯峨根前副理事長、研究協力課および文書課の方々のお世話になった。 また研究委員会に参加された人はいずれも本務のかたわら格別の仕事を負担され、限られた期間に可能な最善をつくされた。また東京芝浦電気、日立製作所、三菱電機の各社およびその関係の方々は、この研究委員会にきわめて協力的に参加され、特に予算見積りには多大の御援助をおしまれなかった。ここに記して厚く謝意を表したい。 本報告書は現在の日本における一断面である。日本の核融合研究の一礎石として役だてばと願ってやまない。
1959年11月11日 委員長 山本 資三
(注1) この成功という語は一部に誤解をまねいた。もちろんその意味するところは、数千〜数万度に止っていたこれまでの段階から新しい原理工夫を加えて、一桁高い温度のプラズマを観測しうる程度の時間発生させることに成功したということである。 核融合研究委員会メンバー
(注1)在 外 第1章 内外の研究の現状 核融合反応の制御を目的とした研究は将来のエネルギー資源の問題としてきわめて重要であり、世界各国ともすでに約10年以前から、考えられる方式原理に基づいて多種類の型の装置を試作し熱心に研究を進めてきた。その間にさまざまな物理的、技術的間置が生じその解決をはかるとともに、さらに新しい方式の可能性の検討も続けなければならない。 高温プラズマを磁場で保持する方式は現在までのところ最も可能性のあるものとして広くかつ詳細に検討され、大きな組織と規模によって発展的に継続研究されてきた。この方式は磁場の保持方式、プラズマの加熱方式(高エネルギー粒子への入射を含む)によって十数種類の型にわけられる。そして温度と保持時間の大きいものを必要とするため、これらの中の数種は次第に大きい実験規模に発展しつつある。 しかしながら、これらの装置をもってただちに制御熱核融合反応に必要な温度、密度、保持時間の条件を満たしうる見通しは得られていない。現状では超高温プラズマのふるまいに関する理解の不足を認めざるを得ない。すなわち、核融合の研究は現在基礎研究の段階にあるといえる。 ひるがえってわが国の事情をみると、ようやく1955年ごろから研究の緒につき、現在十数ヵ所で小規模な基礎研究が行なわれている。研究の歴史も浅く、質、量ともにきわめて不十分な状態にある。その関係する分野がきわめて広いので、超高温プラズマの発生、制御の原理に関する基礎研究、装置に対する工学的、技術的研究、プラズマの性質を理解するための多様な精密計測装置の研究などを総合的に強力に推進すべきであろう。 一方研究者のグループとして核融合懇談会がつくられ(1958年2月)、大学、研究所、会社も含めきわめて広範囲の専門分野からの研究者による全国的協同研究の組織が確立された。また原子力委員会核融合専門部会(1958年4月発足)および学術会議核融合特別委員会(1959年4月発足)がもうけられ、核融合研究の進め方、体制、その他の検討が行なわれた。1959年4月には、専門部会が原子力委員会委員長に答申した「核融合反応の研究の進め方について」に基づき、B計画を立案する核融合研究委員会が発足した。その後8月まで核融合研究の体制につき専門部会、特別委員会は慎重に度々討議し、核融合は硯在基礎研究を行なうべき段階にあるので、大学の研究を強化すべきであり、その線に沿って文部省管下にプラズマに関する研究所を設けることを適当と認めた。そこにおいて、各大学、研究所、会社単独では持ち得ない規模の実験装置を設置し、これを中心にして超高温プラズマの発生、制御、計測に関し基礎学理と技術の研究を強力に推進することになった。この提案は1959年10月の日本学術会議の総会にて承認された。 第2章 B計画の主旨と目的 核融合専門部会は“核融合反応の研究の進め方について”と題する原子力委員会への答申において、研究の現状を分析したのち、当面の研究方針として、次の二つの組織された研究計画を提案している。
A)基礎研究に重点をおき、プラズマ物理の基礎的研究および装置に対する新しい着想の育成と具体化をはかるとともに、新しい分野にはたらく研究者を養成する。(A計画)
核融合研究委員会は後者の研究計画を具体化することを目的とする。
それゆえ、このB計画では核融合を目標としつつ、超高温プラズマの加熱保持の方式を研究し、またある程度の大きい装置でないと得られない超高温プラズマについて精密な諸計測の行なえるようにする。
このための装置としては、 装置の設計、製作、計測、実験の容易さから装置の大きさの最小の規模におのずから限界があるので、これから「中型」の実質的大きさや必要な予算がおのずから決ることになろう。規模、金額やタイムスケジュールは答申にこだわらず、研究者として弾力性をもたせて考える。これらは具体案について自然に決ってくるであろう。また当然Bは複数の型および台数になっていくものと考えられる。 このような中型装置および計測装置の設計、製作にあたっては、個々に解決すべき特殊な、また高精度を要する技術的諸問題がある。たとえば高電圧大電流開閉器、精密な強磁場発生装置、超高真空技術、ミリ波プラズマ診断装置などで、いずれも現在の技術ではこの目的には不十分であり、その開発は核融合研究を行なう上にきわめて望まれるところである。 またこの実験装置は広範囲の技術の総合的所産としてつくられるものであって、このような大規模な装置の設計、製作の経験を持つことはわが国の産業、技術の向上にも資し、核融合研究をすみやかに進めるのに必要な措置であると考えられる。
(注1) プラズマの基礎諸量のうち、電離度、電気伝導度、熱伝導度、緩和時間、拡散などは温度の函数である。温度が数万度(ほぼ電離電圧)以上になると電離度は100%に近づき、高温プラズマとしての性質が顕著になる。したがって高温プラズマの研究にはこの程度の温度が一つの目安になる。しかし核融合の研究にはさらに高い温度におけるプラズマが問題になり、上述の諸量の値は著しく変ってくる。参考のために温度に対するこれら諸量の依存性を示す。 プラズマの固有抵抗ηはT3/2(Tは温度)に逆比例し、106゜Kで約6×10-5Ωcmである。温度の上昇とともに抵抗は低下し、磁場の捕捉時間は長くなる。たとえば磁場分布の崩れる時間はT3/2に比例する。106゜Kで特性的長さ10cmのプラズマでは捕捉時間は約1msである。 純粋な熱核反応で発生する中性子量は温度の上昇とともに指数函数的に増加する。この発生量を正確に検知することにより、温度およびエネルギー分布に関する情報が得られる。106゜K以下では検出がきわめて困難であり、2〜3×106゜K以上であることが望ましい。 第3章 装置の型の選定について 核融合研究のための装置の型を選定する場合、その規準としてはいろいろ考えられるが、本委員会ではB計画の目的を考慮して検討した結果、主として次の事項を取りあげた。
(1)将来の核融合炉という点からみて見込みのあるもの。 加熱は保持と不可分であるが、加熱法(特に高温における加熱法)およびそれに伴う現象の研究を重点的にすすめる。 以上のほかこの研究を実施する研究者の意向も十分尊重されるべきであると考えられた。
(1)自己場による保持
(注2)
(3)高周波磁場による保持(注4)
(注1)高密度、超高温の発生という点では有用であるが、非定常なので現状では取り上げなかった。しかし定常化するための研究が行なわれているようである。 第4章 選定した型に関する検討 前章で選定した三つの型について、特長、問題点および本委員会で検討した事項について述べる。 §1 Stellarator型
(注1)Stellarator B-1のジュール加熱でKruskal制限電流が理論値とよく一致することが示されたのであるが、それに付随して測られた現象には理論的に説明できない点もある。
1.2 Stellaratorの加熱としては、高周波予備放電、ジュール加熱およびMagnetic Pumping(ion cyclotronresonanceを含む)の順序が考えられている。ジュール加熱は、プラズマの温度上昇とともに抵抗が減少するので到達温度には制限があるが、比較的簡単に高温プラズマ(〜106゜K)が得られる。またジュール加熱電場による逃走現象(runaway)について注意しなければならない。Magnetic
Pumpingは加熱の高周波、イオンサイクロトロン、イオンーイオン衝突およびtransitの各周波数との大小関係をたくみに利用するものである。しかし Magnetic
Pumping により与えられたエネルギーが、randomize されて、maxwell分布になる過程については理論的にも問題がある。(注1) Stellaratorにおける加熱の研究の現状は次のようである。高周波予備放電により2〜3%電離し、その後、ジュール加熱を行なったところ、kink型不安定性、交換型不安定性等を防ぎ、理論的には不安定性が予測されなかったので、ジュール加熱の途中から電子密度の急激な減少が起こった。(いわゆるpumpout(注2))この現象の理解のために、理論と実験の両面から精力的な研究が行なわれている。本委員会でも、このpumpoutは、ジュール加熱のため一方向に電場がかけられるので、一方向電流あるいは逃走電子(runaway
electron)によりプラズマが乱されるという認識からジュール加熱の周波数を上げるいわゆる高周波ジュール加熱が提唱された。(注3)しかし、高周波予備放電中にもPumpoutの起こることが、観測されており、(注4)高周波ジュール加熱をすれば、必ずPumpoutが避けられるとはいえない。Pumpoutは現状ではStellaratorの研究の重要課題であるが、一般にPumpoutを避けるためにはプラズマを静かに加熱することが必要であるならば、Stellaratorのみならず核融合研究の上でも、重大な問題となる。しかしPumpoutについては、現在どちらかといえば、実験的な探求を特に必要とする段階であり、高周波ジュール加熱等のいろいろな加熱方法を使い、実験条件を純粋にして集中的に実験することが大切であると考えられる。 なお、これにみられるように保持と加熱とは密接な関係があり、総合的に考えなければならない。 Stellaratorは、上述のような状態であるので、まだ本格的なMagnetic Pumpingは行なわれていないが、微少出力のion
cyclotron 加熱をした結果ではプラズマへのエネルギ一往入は予期のように有効であった。プラズマ加熱の研究では、エネルギー注入から加熱に至る過程とそれに伴う諸現象を調べることも重要である。
(注1)I.B.Bernstein;Phys.Rev,109(1959)10Appendix参照
(1)水素と重水素とではあまり変らないが、ヘリウムではこの現象は少ない。 Pumpoutの原因については逃走電子がプラズマ振動を励起し、その電場が電子を散乱するであろうという憶測がある程度で定説はない。
(注3) しかし、周波数をあげたため表皮効果による加熱能率が低下するなやみもある。また加熱するに従ってプラズマ状態が変化して、負荷の特性が変化するので、発振器の設計には相当の予備実験が必要である。
1.3 技術的意義
1.4 プラズマとしての性質をよく調べうること
1.5 下記のごとき項目について討論が行なわれた。 §2 DCX型 DCXは前節の Stellarator とは根本的にその原:壁を異にしている。すなわち保持は mirror型の直流磁場を用い、加熱は非常に高エネルギー(300KeV程度)の粒子の入射、蓄積による。 また Stellarator では初めに非常に強い放電をおこさせるから、容器内のガスはほとんどイオン化していると考えてよいが、DCX では有限の圧力の容器内に外からイオンを入射する。高エネルギーイオンは残留ガスの中の中性原子と電荷を交換して、高エネルギr中性原子となって側壁に行き、エネルギー損失の大きな部分を占めることになる。この中性ガスとしては初めに存在したガスあるいは出ガスだけでなく、定常的に高エネルギーイオンを入射しているときはそれと同じ割合で生じている中性ガスも含めて考える。(1mAは1.8×10-4mmHgl/secに相当する)(注1) DCX 装置の可能性の議論は大きく二つに分けられる。すなわち、保持、安定性、蓄積の方式、burnout熱損失および熱運動化等に関する基礎的なことと、技術的な加速器(加速管を含む)、排気系統およびコイル系統等に関することとである。また測定に関する問題がある。 本委員会の会合の初期にC.F.Barnett etal GenevaII31(1958)298(注2)を検討したが、burnoutに必要な入射電流が600keV、数100mAということから、日本の技術では製作が不可能視され、選定外になっていたが、後、各電機メーカーに問いあわせたところ、できないことはないというのが一致した意見だったので、DCX 小委員会をつくり、Thermonuclear
Project Semiannual Report for Period Ending January31,1959ORNL−2693をおもに参考としてその検討を行なった。(注3)おもに実験的な面で検討されたが、理論的面の重要さが再認識された。 DCX について討論したおもな事項は次のとおりである
(注1)A.Simon;Phys.of Fluids1(1958)495 §3 lon Cyclotron Resonance Mirror型 3.1 この方法は比較的低エネルギーのイオンをMir-ror型の直流磁場の磁力線に平行に入射し、サイクロトロン連動に共鳴する高周波電場を加え、磁力線に垂直方向のエネルギーを増加させることにより、加速と同時にとじこめを行なう。 その特長はおもに次のようなものである。
3.2 いくつか問題となった点をまとめておく
(注1) プラズマの反作用に関連して、UCRL5286の紹介があった。
3.3 本委員会で討論したおもな事項は次のとおりである。 第5章 Stellarator装置の演習設計 §1 Stellaratorの大きさをきある因子について Stellaratorのように外場による保持をしている場合は、βを大きくすると、プラズマからの反作用が大きくなり、現象としても複雑になり、:理論的解釈も非常に困難となる。したがってβの小さい(10-3〜10-4)場合でも、相当の密度および温度のプラズマを保持できるようにしておいて、この段階での保持、プラズマのふるまいなどの研究をへたのち、磁場を下げるなどの方法によりβを大きくした場合の研究に進むのがよい。したがって、強い磁場を出せる装置にしておけば(だいたい磁場の強さの自乗に比例して)広い範囲のβについての研究ができることになる。 下に、温度、粒子密度、磁場について常識的な数倍をとった場合の例を示す。
S−I、S−IIは演習設計した二つのStellarator型についての例である(§3参照) 第5−1図はプラズマの断面図で、tはプラズマ表面の厚さ、r0はプラズマ実体の半径である。tとしてはLarmor 半径をとるのが≡適当であると考えられる。
である。第5.2表からいえば、r0を大きく磁場を強く
するほど良いことになる。しかし、建設コストはr02〜3に比例することを注意したい。
この二つの保持時間のいずれになるかは、プラズマの状態により変る。また上の保持時間の式そのものも、現在、理論的、実験的に研究中である。
直線部分の長さは、真空の引き口、測定用枝管の太さ、数、枝管をつけたところの補正コイル、加熱部などから決まってくる。 測定としては、マイクロ波、分光、写真、質量分析などが必要である。しかも、プラズマは必ずしも軸方向に一様ではないので、たとえば分光測定などは、2、3ヵ所で行なうことができるのが望ましい。 ドーナツの太さと同じ太さの枝管をつけると、磁場の乱れの補正のため、ドーナツの太さ程度以上の長さの補正部を必要とする。
(5)ジュール加熱を行なう場合は、その電流値が、保持を行なうために制限される。(Kruskalの制限)これはジュール加熱を行なうのに十分な値にならなければならない。 ここに
これらはいずれも必要なジュール加熱を行なうに十分すぎるくらいの倍である。 (6)helical winding による磁場の極数は、安定性、β、磁場の有効さ、コイルの製作技術などから決められるが、l=3にするのが適当であろう。(注1)なお二つの半円部に helical windingをまくわけであるが、そのlの倍を異なったものにして、プラズマ保持の能率を上げるという試みもある。(本章3.2注1参照) (注1) dz/dr(r:軸からの距離)l=2のとき0、l=3のとき最大となり交換型不安定性に対して良い。l>3ではzは急速に減少し、またコイルの製作も困難になる。 (注1)10-10mmHg以下の真空度にすれば、不純物は10-3以下になり、不純物による損失がへり、温度は上げやすくなる。しかし、Stellarator程度の金属真空容器を10-7mmHg以下という超高真空度にすることは、技術的に相当困難な問題であるが、現在の最高の実空技術を使えば不可能ではない。なお、基礎真空度が下がれば、それに応じて当然、充填ガスの純度も上げなければならない。10-10程度の純度の水素あるいはへリウムを得ることは可能であるが、細心の注意を必要とするし、ヘリウムの場合は液体ヘリウムから精製する必要があり、相当大がかりなものになる。10-10mmHg以下に基礎真空度を下げる場合はさらにガスを純化することも考えなければならない。(注2) 現在、実際に10-10mmHg程度の超高真空をうるには、真空函を高真空度、450℃程度で10〜60時間加熱排気するいわゆるbackingを用いる。これによって、出ガスを10-10mm Hgl/secに下げられる。backingおよび出ガスなどのために超高真空用材料は制限をうけるとともに、高圧コイルの内側にある真空函を至るところ4500℃の高温にしなければならず(3.2注1参照)電気機器としては、非常に特殊なむずかしいものとなる。また真空函にフランジをつけて分解可能にすることは望ましいことであるが、S-IIのようにパルス磁場を使う場合は、磁場の時間的変化により誘起される電圧(約10V)のため、主コイル電流の数十%に及ぶ電流がフランジに流れるので、フランジをつけることは望ましくない。 したがって容器の枝管以外の部分はすべてHeliarc(注3)により溶接しなければならない。ジュール加熱用の誘導電圧を短絡しないために、容器は高密度のアルミナ・セラミックを入れなければならない(セラミック部)。Heliarc技術とセラミック金属接合の技術については、すでに国内で実用化しており、設計の当初危惧されたほどの製作上の困難はないようである。 予備加熱としては、高周波放電が一般に用いられている。その周波数は、充填ガス圧との関係があるので、多段切換にしておくことが望ましい。高真空(〜10-5mmHg)になると、高周波放電が困難となるのでLinhart(注4)の提唱している電子を入射して、その電子のdriftにより電離させることを考えなければならない。 保持磁場としては、定常磁場を使うか、パルス磁場を使うかは、もちろん実験計画から決まることであるけれども、費用の点も無視できない要素である。定常磁場にしておくと、できるプラズマも定常に近いものが期待できるので、非常によい。しかしながら、そのために装置としては膨大なものとなり、たとえばコイルに必要な銅は莫大な量になる。核融合反応のように“若い”研究分野にあっては、装置の有用さという意味での寿命は比較的短いので、電源のような流用できる装置はともかく、装置本体は研究上の支障のないかぎり手軽にしておくことが望ましいと考えられる。パルス磁場では、電流を数サイクル流して後、コイルの冷却時間をおくので、コイルの断面積は小さくなり、製作は容易になる。 しかし、この場合は、たとえば1分に1回しか測定ができないという不便はある。それ以上に重要なことは、磁場が時間とともに変化することである。その場合、頂上部分では磁場の変化はわずかであるので、その間に測定ができれば、研究上は定常の場合に比べて、あまり遜色のない装置とすることができる。もちろん定常的な装置は研究上すぐれている。研究の段階が進めば定常なものに進んで行くようになる。(sine波形にした場合の頂上部分の具体的な時間については注5参照。) パルス磁場の電源としては、はずみ車発電機、蓄電池、インダクタンス・コンデンサーが考えられる。これらの電源のどれを使うかは、電源エネルギー、使用相当周波数、くりかえしなどが決まると、経済的な問題として決定できる。S−IIのように 2×106ジュール、20サイクル、くりかえし1分間に1回程度の場合には、コンデンサーが経済的である。
(注1)J.M.Berger et al;Phys of Fluids1(1958)297 §3 S-II本体の設計および見積り 以上の考察を経て、S-I、S-IIの二つの設計を行なった。第5−3〜6図。§1に大きさをきめる因子について述べたがStellarator設計のとき、各パラメーターは物理的要請だけからは決まらない。製作の技術、建設コスト等と総合的に考えなければならない。研究費は一方的に決められるものではないが、おのずから限界がある。研究費を一定とした場合の各部のパラメーターは§1(3)のような不確実な要素があるにしても、一応いく組かを決定できる。Stellarator研究のどの点に重点をおくかにより、どのパラメーターの組を選ぶかが決まる。このS-Iでは測定の信頼度の点と保持の解析の簡易さに主眼をおき、§1(2)と(4)を重くみた。また加熱の研究も重点の一つであるので加熱部には相当大きなスペースを取った。
安定性の点から8字型でなく、racetrack型を選んだ。磁場の強さ、管の太さ、長さ等はLarmor半径β、Kruskalの制限、プラズマの表面と実質、保持時間、測定の便宜等を考慮して決定した。詳しい数倍は§1の各表にある。S-I、S-IIのおもな諸元は第5.6表のとおりである。 S-IIについては、さらに詳細な検討を行ない、次のような仕様にまとめた。 (2)コイル強度はもちろん 3×104ガウスの磁場による電磁力に耐えられなければならない。bakeのときも耐えられるように注意、磁場の検査のため“rabbit”(注1)を使うことを考えているので、コイル枠とコイルの中心は±2mm以内で一致していること。bakeのときの熱絶縁のための熱絶縁板はone−turn shortにならぬようにする。冷却水あるいは冷却風の量は制御する。 各コイルの図面指定の位置と実際のコイルのずれの2乗偏差は次のとおりである。(注2)
(3)ジュール加熱 Hypersil(ストン)、電源5kJ、3kV、投入およびクローバー・スイッチ付(イダニトロン)48turn。
(4)架台 真空函の中心が床上1.2m。架台のコイルに近い部分はNon−magnetic (5)真空系 Bayard−Alpert typeの球20本を用意する。真空計3台。ポンプは、液体窒素トラップ2段付4インチ油拡散ポンプ(液体窒素自動補給式。排気速度はトラップ2段付で5〜10l/sec、10-8mmHg)拡散ポンプ油は輸入。回転ポンプにも冷却トラップをつける。
(7)予備テスト用電源。磁場測定(rabbit等)などに使用する。300A、(これで300ガウスできる)20kWの発電機、簡単な安定器をつける。
(注1) S-IIで考えている rabbitは電子銃および螢光面からなり電子の飛行中にうける偏向をはかり、それによりそこの磁場をはかるものである。 コイルの仕様書を、磁場で決めるか、上述のように幾何学的位置で決めるかは問題である。前者にするとメーカーの技術向上にもなり一方研究者側の設計の負担が軽減するので、これが理想的であるが、現状では前例もなく諸種の事情で困難である。
3.2 S-IIの見積りおよびメーカーとの交渉
3.1の仕様によって、東芝、日立、三菱の3社に、製作上の検討および見積りをしてもらった。
(1)3社から製作上の問題についてこもごも注意されたが、そのおもなものは次のとおりである。 コイルの中心の位置で0.5mmと指定してあるが、中心は非常に測りにくい。 コイルについて、磁場で指定された場合は、3社でも、それくらいのことはやれると思われる。しかし、それをやれるような体制になるには時間がかかる。 bake電源について、bake されない所が1cm2あってもいけない(注1)と指定されると、案外設計がむずかしい。実際につくって、各部の温度をはかり手直しをすることになろう。しかし手直しをすればできる。 直接、真空函に電流を流すのは電流のリードなどでうまくないので、フレキシブル・ヒーティング・テープをまいたほうが良い。セラミック部分がbakeをくり返したとき、こわれる恐れがある。 (注1)stainless steelの出ガス量
(2)S-II本体の見積り 区分の仕方は社内事情により各社で異なっている。次表は主として、A社の区分を用いた。このためにB、C社の区分は、ふぞろいなものになったが、もちろんB、C社ともに上述の仕様にある S-II本体の見積りである。
§4 S-IIの全容、研究計画 測定器、付属施設を全部数え上げ評価すると第5.8表のとおりである。
4.1 S-II研究計画(タイムスケジュール) 第5.9表がその研究計画である。この研究計画は概算要求等の国家予算の時間割も考慮してつくってある。スタッフとしては、密接な連絡があり、区別しにくい面もあるが、専門に応じて装置関係、測定関係、理論関係の3グループに分けられる。S-II本体の設計は計画の各部にわたり関係があるので、本体の設計、特にその初期の段階では、全グループが参加しなければならない。 測定グループは、本体設計の途中から、本体納入までの約2ヵ年間、測定器の整備、調整を行ない、さらに簡単なプラズマによりプラズマ測定を行ない、測定結果の信用度を上げるような予備研究を行なう。 装置グループは主として本体設計後、本体納入までの1年3ヵ月加熱装置の設計、予備実験、試運転を行なう。理論グループは、本体設計に参加し、次いで加熱の検討、簡単なプラズマの測定結果の解析等を行なう。 図の下方にある本運転についての検討は全グループが、それまでの結果をもちより、本運転による研究についての検討を集中的に行なう期間を示す。また、同じく下方にある“New idea についての模索、将来計画”は、そのころから S-II建設のための仕事量が減ってくるので、S-IIについて直接研究する人々以外に、もっと自由な立場にたって研究するグループを持つことができる。このグループへは、もちろん、3グループから参加し、3〜5人が中心となる。 各グループの各年度別の構成は第5.10表のとおりである。ただし、この構成は、現実に、そのような人が得られるかどうかについては考慮してない。
しかし、日本の現状では、これらの人すべてに既成の人を予想することはできない。相当の部分は S-II研究グループ自身で養成しなければならない。 この表で、A+Bとあるが、Aは研究者、Bは研究補助者の意味である。 第6章 DCX装置の具体的検討 §1 基礎的問題
1.1 保 持
1.2 安 定 性
1.3 イオン蓄積の方法
1.4 熱 損 失
(注6)T.K.Fowler and A.Simon ORNL−2552
1.5 Burnout A.Simonにより計算されているが、側壁へのイオンの損失が無視されており、No(プラズマ外空間の中性原子密度、1cm3)、n0(プラズマ内中性原子密度、1cm3)およびn+(イオン密度、1cm3)等の取り方にも相当問題がある。 そして1critの約10倍の電流で中性原子による損失が無視できるようになる。プラズマ形成のためにはburnout以上の電流が必要であり、これは加速器の出力に直接関係するから、もっと詳細な検討が望ましい。この臨界電流値の大きさは§21に示す。(注1,2,3,7,8,9)
1.6 熱運動化 表からD+より H+を用いたほうがburnoutは容易で磁場の全エネルギーは小さいことがわかる。したがってburnout前後のプラズマの様子を調べるにはH+を用いるほうが有利である。次に加速器に対するメーカー(東芝、日立、三菱)の意見を述べる。いずれも予備実験を重ねれば製作できる見通しで、具体的内容は次のとおりである。
(1)Cockcroft(1kc/sec)4段、1台、数百mA、脈動率0.1% イオン源は各種の型(低電圧アーク、高周波型、Von Ardenne型およびP.I.G.型等)につき検討する必要
があり、また加速管は相当問題である。 (注10)C.F.Barnett and H.K.Reynnlds;Phys. Rev.109(1958)355 n2+σcv+PV=1crit、ここでV=3/4πρc3でプラズマの体積、Pはあるイオンが損失円錐に散乱させる確率、V+はイオンの平均速度である。 (注15)重水素ガス内の重水素イオンのとき1crit=2×10-8P0、同様にして水素のとき1crit=2.5×10-7P0、P0はmmHg、1critはmAo、ただし、イオンエネルギーは300keV、磁場の強さは104ガウスとした。
2.5 コイル系統
(注17)TID−7558
3.2 捕捉されたビーム
(注18)C.B.Wharton et al;Geneva II 32(1958)388 DCXをProject として取り上げる場合は、次の3段階をへるのが適当であろう。 第1段階:加速器の開発、アークの予備実験および理論的検討をする。またアークおよび捕捉イオンによるポンプ作用を有効に利用する方法の予備実験も重要である。 第2段階:burnoutの手掛りをつかめるようなDCXをつくり burnout前後の状態を研究する。 第3段階:十分burnoutできる装置をつくり、DCX全体として研究をする。 ただし以上の3段階は今後の研究成果を取り入れ、修正されるかもしれない。 第7章 Ion Cyclotron Resonance Mirror装置の具体的検討 ここで考える装置はburnoutはねらわず入射イオンの捕捉を研究の対象とする。 §1 設計の原理的考え方 装置設計の原理的考えは次のとおりである。
(1)最終エネルギーの重水素イオンを閉じこめるために必要なB.ρc(ρcはLarmor半径)から磁場の強さと半径の関係が得られる。 §2 Scaling Law 設計の見通しをつけるために、次のようなscalinglawが検討された。結論を先に述べると、E0が低く、(H.ρが一定でも)Hを大、ρを小にとるほうがイオン密度が上り、必要な高周波出力が減り、有利である。(注1) 装置のパラメーターおよび単位、〔 〕内は従属変数と考えられる量。
(注1)高周波出力が減るのは高周波発振器のコストが下るだけでなく、高周波コイルの絶縁が容易になる点からも有利である。高周波コイルは磁場コイルの内側にあるので絶縁が簡単になることは重大である。
重水素の場合σiは200keV で最大になるので、イオンの最終エネルギーとして 200keV をとった。また、加速されすぎて外壁にあたるとする場合、イオンのエネルギー分布の山は最終エネルギーの約1/5のところにあるので最終エネルギーが 200keV であれば分布の山は約40keV となり測定の点からもよい。 入射エネルギーは上述により物理的に低いほうがよいが、イオン源の技術的制限から 400e Vとした。イオン源は低電圧アーク式で第1、第2電極を持ついわゆる Caltron型である。イオン電流は100mA。 装置の加熱部分(A部)の長さを2.2mとする。端の部分にはA部と別のコイルを巻き(B部)、入射イオンのエネルギーは400eV とする。最終の重水素イオンのエネルギーは200keVである。
IIのはうは装置の製作、技術、経費の点からみて有利であるが、burnout、粒子密度の点からはIのほうが有利である。 Iではイオンの平均寿命時間から粒子密度はだいたい1.5×1011/cm3 ぐらいである。なお、プラズマの反作用については今後とも検討すべきである。 burnoutするとしても数秒でプラズマは定常になるし、加速されすぎて側壁にあたるとすると10-2秒程度で定常になるのでこの程度の磁場の持続時間があればよい。磁場コイルの設計には本質的な困難はないが、冷却、コイル間引力に対する機械的強度などには注意がいる。上述のI、IIの例は既存の電源を使うことを前提にして設計したので、大電流、低電圧式になっている。自由に考える場合は、もちろん電源電圧、電流、コイルの作り方などを総合的に考えるべきである。 イオンが加速されすぎて、壁にあたるのを防ぐために、磁場の強さを空間的にわずか波うたせてoff-resonance にする方式も考えられている。このような磁場を作るためのコイルの巻き方は相当技術的にむずかしく、また磁場電源は波うたさない場合に比べて大きなものが必要になる。 (注1) ここに示されたものは本委員合で行なわれた演習設計である。日立製作所は粒子損失、エネルギー分布などを検討して新しく具体的設計を行ない、原子力平和利用研究委託費によりその研究に着手した。 第8章 測定に関する検討 超高温プラズマの測定に関して本委員会で行なった プラズマ内を流れる電流はたとえばRogowskiコイルで直読するか下に述べる磁気探針による磁場分布の測定から間接に測定する。これからたとえばピンチの形体、波形の変動および不安定性も推定されるし、またプラズマの電気抵抗のだいたいの値も見当がつく。 電子密度、イオン密度、電子温度、イオン温度、空間電位などは通常の低温プラズマではLangmuirの探針の電流電圧特性から求められる。しかし高温プラズマではこの方法は完全に確立しているとはいえない。 プラズマ中の磁場を測定するためには磁気探針が利用される。これはたんに磁場のみでなくプラズマ諸量の理論的関係によってプラズマ中を流れる電流、プラズマの圧力などを時間空間の函数として与えることが可能であり、有用な手段である。 電磁波による測定にはプラズマから輻射される電磁波のスペクトル、偏光等を測定する方法と、外部から電磁波を入射して反射率、透過率などを測定する方法がある。これらの測定結果からプラズマ諸量を求めることができる。以下に電磁波の波長の順に述べる。
3.1 マイクロ波 次に雑音の測定では、それに利用する周波数がプラズマ周波数より小さいことが必要で透過の場合と逆である。雑音をヘテロダイン受信器で受け、その強さを標準の雑音源からの値と比較して電子温度が得られる。また磁場のある場合サイクロトロン輻射の幅からも電子温度が推定できる。 以下にいくつかの問題点をまとめておく。 3.2 可視光、紫外線
(2)カメラによる測定 3.3 X−ray ものであるか否かをたしかめるためには、中性子発生の絶対強度、エネルギー分布および角度分布については慎重な配慮が必要である。 1回の放電で発生する中性子の総数は activation counter,BF3 counter,scintillation counter等によって測られる。activation counterは115In,106Agをパラフィンで減速した中性子で活性化し、発生するベータ線をGM計数管あるいはscintillation counterで測定する。ガンマ線のback groundは問題にならない。BF3 counter では中性子減速のため、速い中性子に対する感度がよくないので、パラフィンで中性子を減速する。 装置はガンマ線および外部の電磁場から遮蔽する。BF3では減速のためtime resolutionはよくない。scintillatorおよび光電増倍管のtimeresolutionはきわめてよい(〜10-8秒)。scintillatorは、鉛遮蔽でガンマ線およびX線をさけ、光電増倍管にも電磁遮蔽が必要である。 中性子のエネルギー分布は、核乾板、霧箱、scintillation counterによる。前2者は、time resolution がない。霧箱は、エネルギー分解能がいいので役だつ。 4.2 荷電粒子 4.3 中性粒子 第9章 結 論 核融合研究用超高温プラズマ発生装置としてどの型がすぐれているかを決定することは、現段階ではできない。しかしながらわが国が核融合研究を促進するためなるべくすみやかに中型装置を建設し研究するとして、望ましい条件を設定することができる。本研究委員会は各種の点から検討し、第3章に述べた選定基準をまず立て、これにしたがって一応三つの型をえらんで検討した。その結論は次のごとくである。
(1)保持磁場としてはStellarator型磁場およびMirror型磁場を適当とする。
(注1)その後米国にても同種の案が検討されたことが知られた。 |
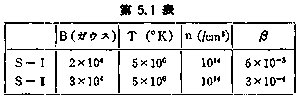
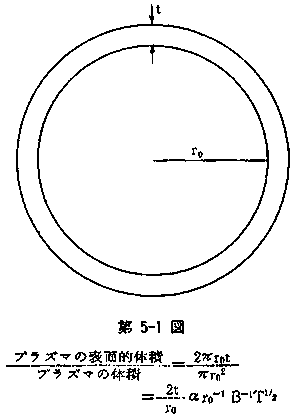
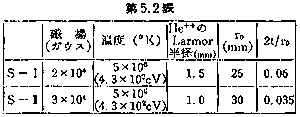
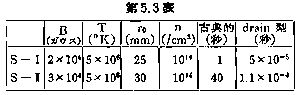
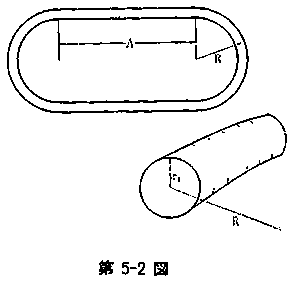
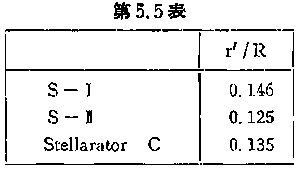
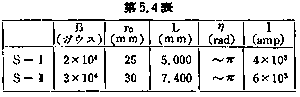
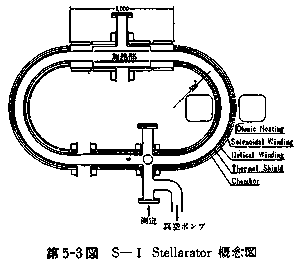
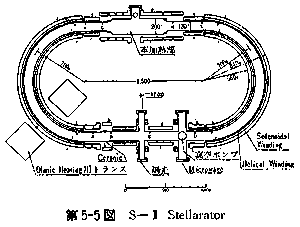
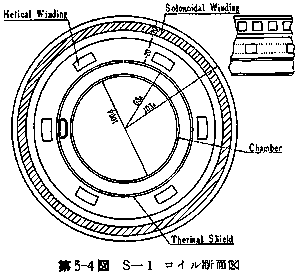
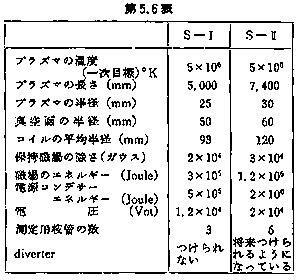
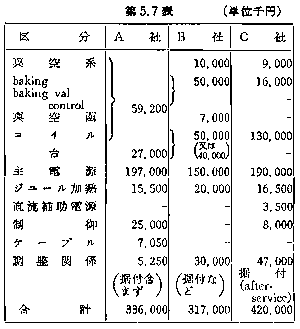
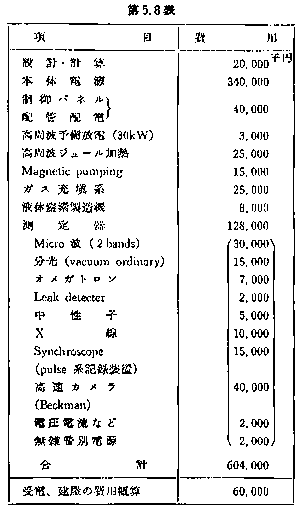
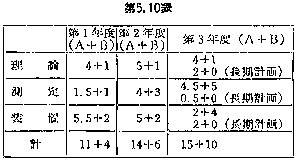
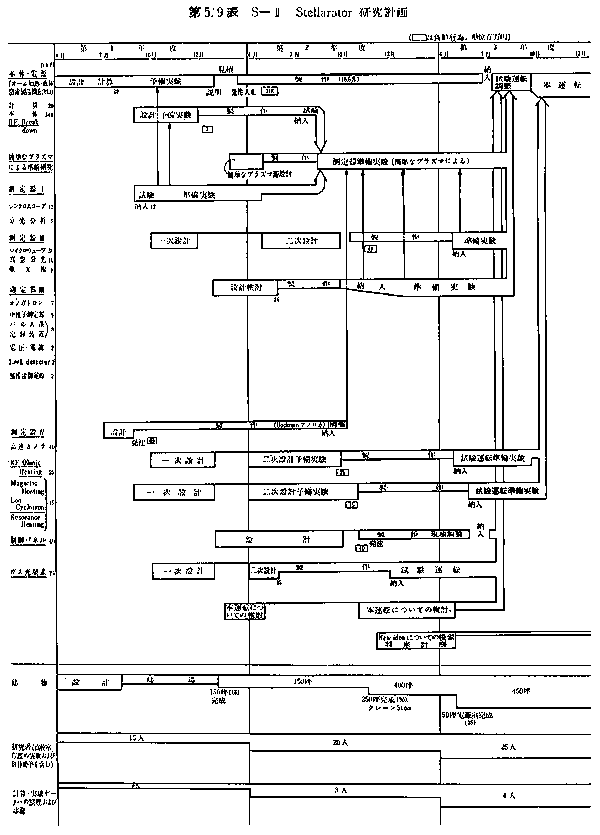
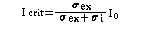 から加速器の仕様がだいたい決まる。σexはイオン速度Vとともにだいたい指数函数的に減り(注10)、σiはV-2で(注11)、σdis(アークにより解離する断面積)はV-1でともに減る。(注4)。これらの数値を第6.1表に示す。
から加速器の仕様がだいたい決まる。σexはイオン速度Vとともにだいたい指数函数的に減り(注10)、σiはV-2で(注11)、σdis(アークにより解離する断面積)はV-1でともに減る。(注4)。これらの数値を第6.1表に示す。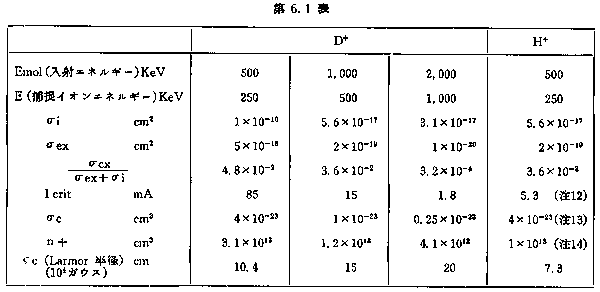
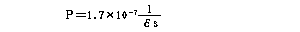
 ≦2×10-81critから εs≧8.5、水素イオンのとき εs≧0.68でなければならない。カーボンアークのSは実験によれば重水素で7.5、水素で10.4。
≦2×10-81critから εs≧8.5、水素イオンのとき εs≧0.68でなければならない。カーボンアークのSは実験によれば重水素で7.5、水素で10.4。