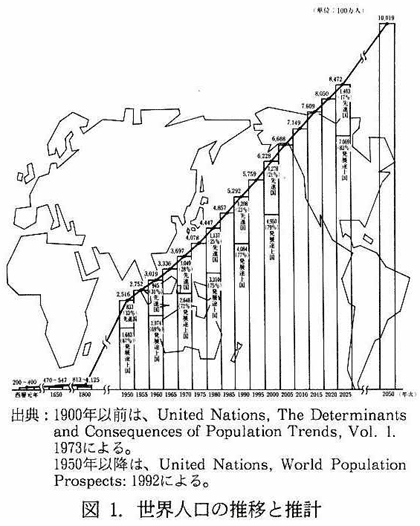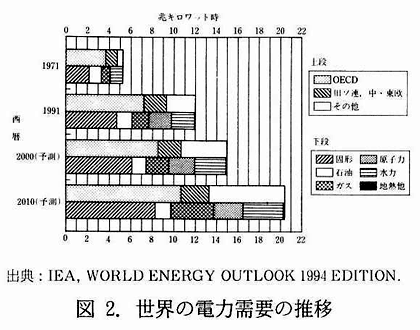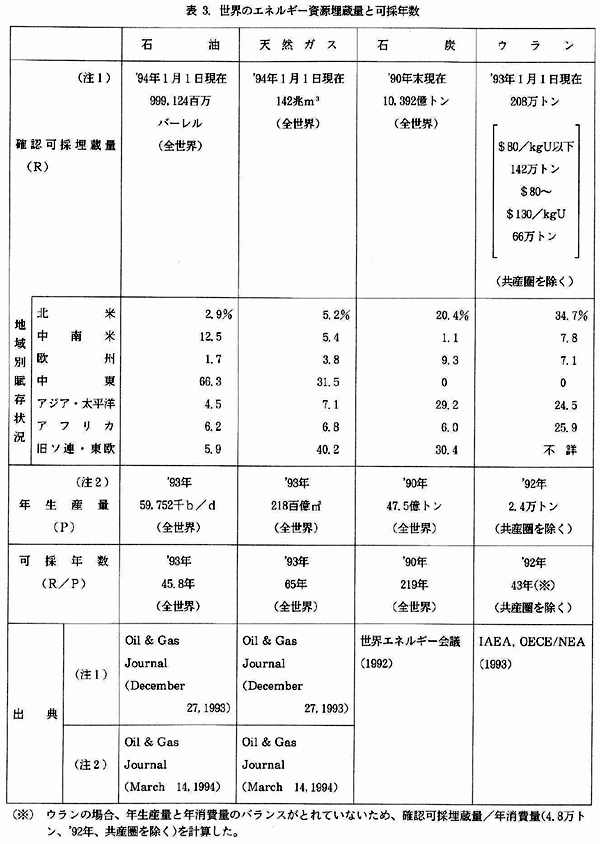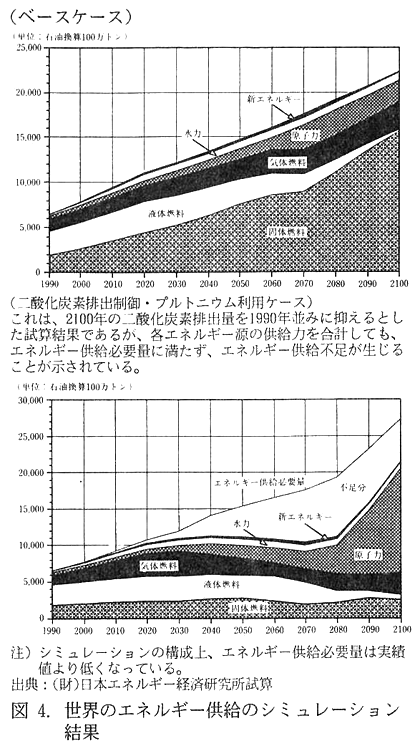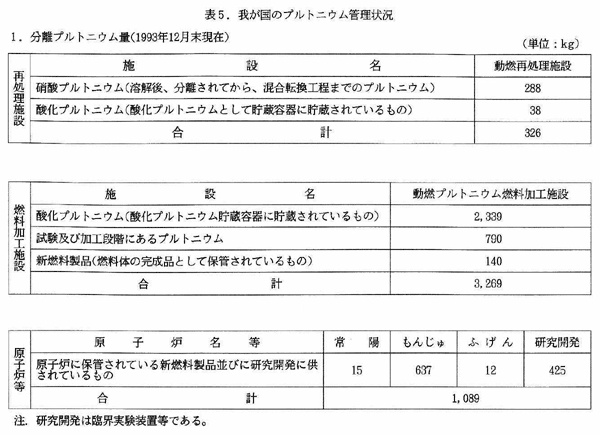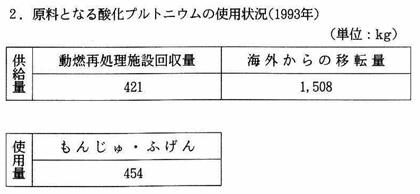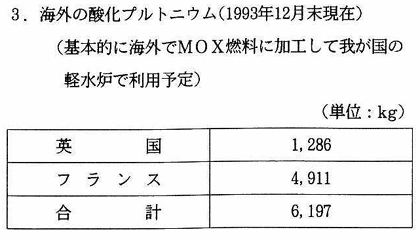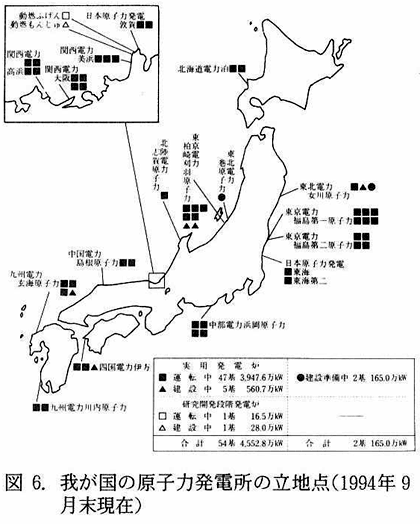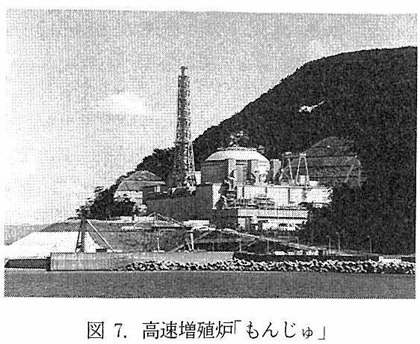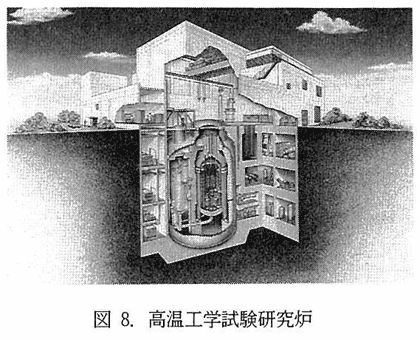| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
委員会の決定等 (決定1)平成6年版原子力白書について(要約) 平成6年11月
原子力委員会
(本資料は平成6年11月24日に行われた事務次官等会議に提出された要約版である。平成6年版原子力白書の全文については、大蔵省印刷局発行「平成6年版原子力白書」を参照のこと。) 第1章 新しい長期計画の策定 原子力委員会は、我が国の原子力の平和利用を計画的かっ効果的に進めていくため、原子力開発利用に関する長期計画を1956年以来、おおむね5年ごとに数次にわたり策定している。本年6月24日新しい長期計画「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(以下「新長期計画」という)を1987年以来7年振りに策定した。 新長期計画は、まず21世紀の地球社会を展望し、直面する諸問題とそれに対し原子力の平和利用が果たし得る役割を示し、その上に立って、我が国が原子力開発利用を行う目的と我が国の原子力開発利用を進める上での政策の柱となる基本方針を明らかにし、さらにその基本方針の下で進められる将来計画を具体的に提示したものである。 本章では、新長期計画に示された基本的考え方とその背景及び2年近くにわたった新長期計画策定の経緯、さらにはこの新長期計画に基づく当面の取組に対する原子力委員会としての考え方などについて示した。 1.新長期計画の基本的考え方 新長期計画の策定に当たっては、我が国の原子力開発利用が、内外の理解の下に進められることが特に重要であるとの認識に立って、これまでの長期計画と同様に我が国の原子力開発利用に携わる人々の活動の指針となることはもとより、国民に対して原子力開発利用に関する明確な理念と計画を提示するよう努めるとともに、諸外国の人々にも我が国の基本的立場を的確に伝えるものとなるよう努めた。このため、新長期計画においては、まず我が国の原子力開発利用をめぐる直接的な情勢に対する認識のみならず、これら情勢をさらに取り巻く背景や全地球的観点からの将来情勢を幅広く踏まえながら原子力の意義、役割を改めてとらえ直した。 (1)新長期計画の時代的、国際的環境 今回の長期計画は過去7回のものに比べ、原子力開発利用の背景となる内外の情勢がいわば質的に大きな変化を遂げつつあり、原子力開発利用が進むべき方向をその理念とともに示すことが特に重要となっている状況の中で策定されたものということができる。 このような内外情勢の変化とはおおむね次のような点である。 (冷戦構造の崩壊) 冷戦の終了により現実化した核兵器の大幅な削減は、これに伴う核兵器解体の結果取り出されるプルトニウム等の核物質の取扱いが大きな課題となっている。また旧ソ連、中・東欧諸国における原子力発電所の安全性に対する懸念が以前にも増して高まるとともに旧ソ連・ロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄に対する不安も生じている。このような問題への対処は当事国の責任が一義的ではあるが、長期的な解決のためには国際社会が協力して対処していくことが重要になってきている。 また、北朝鮮、イラクの核兵器開発疑惑等を背景に新たな核兵器の拡散への懸念が高まっている。 (地球環境問題への意識と国際的取組の高まり) 地球環境問題は、1980年代末からは温室効果による地球温暖化やオゾン層破壊などの全地球規模での環境問題に国際社会が協力して取り組み、具体的な方途を国際政治の場において論じ、行動を起こしていく方向がでてきている。 今後、原子力開発利用も地球環境問題への対応の観点を十分考慮することが必要になっている。 (我が国の原子力開発利用の進展と海外からの視点) 我が国は原子力開発利用に着手した当初より核燃料サイクルの確立を政策の基本としており、ウラン濃縮などの民間事業化が実現し、また、民間再処理工場の建設に着工するなど施設の整備が実証的な規模から、商業規模へと段階が進んだ。また、現行の日米原子力協定下での初のプルトニウムの国際輸送の実施、高速増殖原型炉「もんじゅ」の臨界達成など原子力開発利用はおおむね着実に進展している。 他方、国際的には、冷戦構造の崩壊に伴いプルトニウムの存在やその取扱いが核兵器の拡散につながるとの懸念から大きな関心を呼ぶとともに、これまで原子力開発利用において先進的な地位にあった多くの欧米諸国において種々の事情から原子力開発利用が停滞する傾向が見られ、我が国の政策や行動が、内外から大きく注目されている。 また、我が国において原子力発電が30年の実績を重ね、国民生活に不可欠なものとなったが、今後の電力需要の増加等が予想される中での原子力施設の新規立地の促進や原子力利用の多様化等を目指した新しい展開の方向が求められている。 (2)人口、エネルギー、資源、環境と原子力 (世界人口の増加とエネルギーの消費) 世界の人口は、21世紀に入るころには60億人を超えると言われており、2010年に71億人、2025年には85億人、21世紀半ばには地球人口100億人の時代が到来すると予想されている。地域別に見ると、先進地域の人口が定常状態になる一方で、1990年に既に世界人口の4分の3を若干上回っている開発途上地域の人口は、2025年には世界人口の83%に達する見込みである。
特に開発途上国においては、上記のような急激な人口増加等により、2010年には、1991年の約2.2倍もの需要が見込まれる。これに対し先進国では約1.3倍となっている。 IEAによると、世界の電力需要は、1991年から2010年までに12兆300億キロワット時から20兆4,500億キロワット時にまで1.7倍に増加すると見込まれている。このうち開発途上国では2.6倍、これに対し先進国では1.5倍となっている。
(化石エネルギー資源への依存とエネルギー資源の制約) このようなエネルギー需要を賄うに当たり、2010年ごろまでの予測では、天然ガスヘの移行が進むものの、化石燃料への依存度はほとんど変わらず、電力供給についても、石油火力発電は減少するものの、天然ガス火力、石炭火力が増加する。特に発電電力量に占める石炭火力の割合については、開発途上国において1991年の39%に対し、2010年には44%になると予測されている。 一方、エネルギー資源の埋蔵分布状況を比較すると、天然ガスは旧ソ連、中・東欧と中東に、石炭はアジア・太平洋と旧ソ連、中・東欧に、ウランは北米に遍在している。確認可採埋蔵量を年生産量で割った可採年数は、石油、天然ガス、ウラン(核燃料リサイクルをしない場合)で数十年、石炭は200年程度とされている。 表3.世界のエネルギー資源埋蔵量と可採年数 (地球環境への調和) 地球温暖化問題は、主要原因物質とされている二酸化炭素が人類の活動から不可避的に発生するものであり、その影響は国連環境計画と世界気象機関が共同で設置した「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の試算によると、二酸化炭素等の排出などについて特段の方策を採らなければ21世紀末までには約3℃平均気温が上昇すると予測されている。 現在の世界のエネルギーの約9割は化石燃料から得ているが、今後のエネルギー需要の増大に対応していく上においては、二酸化炭素の放出抑制と人類社会の持続的な発展のためのエネルギー源の確保という課題を併せて解決していく取組が必要になっている。 (資源、環境制約と原子力の役割) このような長期的な人口増加に伴うエネルギー需要の増大に対して、地球環境との調和を保つとともに貴重な資源を温存しつつ、人類が地球と共生し持続的な発展を遂げていくためには、現在エネルギー消費の約9割を依存している化石エネルギー資源から、非化石エネルギーに大きな役割を持たせていくことが必要である。 非化石エネルギーの中で太陽光、風力などの新エネルギーは分散型エネルギーとして将来のエネルギー供給に一定の役割を果たすものの、近い将来において現実的な大規模エネルギー源としての役割をこれに期待することは困難である。他方原子力は、経済面、技術面での課題が克服され、既に現実の安定したエネルギー源となっており、将来的にも大規模なエネルギー源として一層大きな役割を果たしていくことが期待できる。 地球環境への影響の観点からも、原子力は、その発電過程においては二酸化炭素、窒素酸化物等を排出せず、施設の建設等の過程を含めても、他の化石燃料による発電方式に比べて二酸化炭素の排出量が少なく、さらに単位エネルギー当たり発生する廃棄物の量も少ない。 (ベースケース) また、二酸化炭素の放出抑制を図ろうとする場合、ウラン資源について、確認可採埋蔵量を使い尽くした後に、本格的な核燃料リサイクルを実施するというケースでは、21世紀半ば以降シミュレーション上は、大幅なエネルギーの供給不足に立ち至る結果が示されている。従って、早期に核燃料リサイクルを確立していくことが不可欠であることが示されている。 (3)新長期計画に示した我が国の原子力開発利用の在り方 以上に述べたような認識にたって、新長期計画では地球規模で見た原子力の平和利用の役割が、 i)エネルギーの安定供給等により豊かで潤いのある生活の実現を図ること、 ii)資源制約を緩和し、また二酸化炭素の排出を抑制して地球環境と調和した人類社会の持続的な発展を図ること、 iii)エネルギー資源をめぐる国際状況の不安定要因を取り除くなど21世紀地球社会の条件整備へ寄与すること、 の3点にあるとしている。 (我が国の原子力開発利用の目標) このような地球規模での原子力平和利用の役割を踏まえ、新長期計画では我が国が原子力開発利用を進めていく上での目標として、「エネルギーの安定的確保と国民生活の質の向上」と「人類社会の福祉の向上」を掲げた。 我が国のエネルギー供給構造は極めて脆弱であり、エネルギーの輸入依存度は8割を超え、エネルギーの石油依存度は約6割に達し、その石油のほぼ全量を輸入に依存している。これは、米国、ドイツ、フランス、英国などの主要先進国に比べて極端に不安定なエネルギー供給構造と言える。 原子力は、技術集約型エネルギーとしての特長などに注目すると準国産エネルギーと考えることができ、我が国のエネルギー供給構造の脆弱性の克服に貢献する基軸エネルギーとして位置付け、これを推進することが必要である。 さらに、原子力の利用については、エネルギーの利用のみならず、「国民生活の質の向上」との観点から、放射線の利用も重要であり、既に基礎研究、工業、農業、医療、環境保全など広範な分野で普及している。今後は重粒子線によるがん治療法などが実用化され、身の回りの生活を豊かなものとする上で一層その役割が大きくなると考えられる。 また、我が国が原子力開発利用を進めるに当たっては、それにより、独り我が国の短期的繁栄のみを目指すのではなく、常に人類社会への貢献という視点を持ちつつ、これに取り組むことが必要である。 我が国が原子力発電を導入することは、化石エネルギーの安定供給の観点や地球環境保全の観点から、それ自体が国際貢献になっているとも言えるが、さらに、エネルギー資源を大量に消費する一方、豊かな経済力と高度の科学技術を併せ持つ我が国は、常に人類社会への貢献という視点を持ちつつ、原子力開発利用に取り組んでいく。 また、我が国が原子力開発利用に取り組むに当たっては、人類にとってのエネルギー供給の多様化を図るという姿勢が重要であり、この観点からは、まず現在原子力発電を行っている国が原子力発電システムの信頼性を一層向上させていくこと、さらにそれを世界的に普及させていくことが重要である。核燃料リサイクルについては、技術的・経済的な能力や核不拡散の確保を考慮すれば、短中期的にはこれに取り組むことのできる国は限られており、我が国としても直ちにこれを世界に普及させていくことには十分慎重でなければならない。しかしながら、核燃料リサイクルは有限なウラン資源を飛躍的に有効利用でき、長期的には人類社会にとって重要な役割を担うことが期待できるものである。したがって、これを必要として、そのための能力を有する我が国としては、将来の人類のエネルギー供給源の選択肢を拡げるという認識でこれに取り組む。さらに核融合は、必要な燃料資源等が世界中に広く豊富に存在し、人類の恒久的なエネルギー源の1つになることが期待されるものであり、我が国は主体的な国際協力の推進を図りつつ、これに積極的に取り組んでいく。このように我が国は科学技術先進国として、核燃料リサイクルを推進するとともに、太陽光などの新エネルギーや核融合などの研究開発を推進し、多様なエネルギー技術がお互いに補完し合いながら使われていく人類社会の実現を目指すことが重要である。 (原子力開発利用の大前提) 新長期計画においては、我が国の原子力開発利用は、厳に平和の目的に限り、安全の確保に万全を期することを改めて大前提として示した。 特に平和利用の堅持という点では、一部の海外の論調に見られた、我が国が将来核兵器を開発するのではないか、との疑惑に対し「我が国が核兵器を持つことは決してない」旨を特に表明し、日本は、自由貿易体制の中で、国際協調を基調として繁栄を享受していく道を選択しており、核兵器を持つことは何ら益がないことを強調した。 今後とも、我が国は原子力基本法の精神にのっとり、我が国の原子力開発利用を厳に平和利用に限り推進するとともに、核兵器の不拡散に関する条約(NPT)を厳守し、世界の核不拡散体制の維持・強化にも引き続き貢献していくものであり、また、原子力開発利用に関する国際協力に当たっても、この精神を尊重しつつ具体的な国際協力に取り組んでいくとの従来からの立場を一層明確に示した。 安全の確保については、今後とも厳重な安全規制、管理、防災対策の実施により安全の確保に万全を期すとともに、原子力発電所の高経年化対策などの安全対策や安全研究を一層充実させることにより、安全優先の高い意識を持った人間、技術基盤、組織体制などに支えられたより高度な「原子力安全文化」の構築を続けることが重要である。安全水準の向上が必ずしも国民の安心感につながらないという実態も踏まえなければならないが、しかしながらこれらを払拭して安心感を醸成していくには、地道に安全運転の実績を積み重ねることが何よりも基本である。 さらに、諸外国の安全確保の状況は我が国の原子力開発利用にも影響を与えかねないとの観点も踏まえ、我が国としても国際的な原子力安全確保に積極的に貢献することが必要である。 (原子力開発利用の基本方針) 前述のような目標と大前提の下に、新長期計画では我が国の採るべき基本方針として、
①原子力平和利用国家としての原子力政策の展開 我が国は核不拡散についての国際的信頼を確保するため、NPTとこれに基づいたIAEA保障措置体制を維持・強化するとともに自発的な努力をしていく。 NPTは原子力平和利用と核不拡散を両立させる枢要な国際的枠組みであり、原子力の平和利用の円滑な推進のためには核不拡散体制の維持・強化が不可欠であることにかんがみ、NPTの無期限延長の支持は妥当と考える。このことは現在の核兵器国による核兵器の保有の恒久化を意味するものであってはならず、我が国としては未加入国に対し、早期加入を促すことによりNPTの普遍性を高めるように努めるとともに、核兵器国に対しては一層の核軍縮努力を促すことが重要である。また、NPTに基づく保障措置を厳格に受けている我が国は、NPT締約非核兵器国として、NPT体制の中で原子力平和利用の利益を最大限享受出来ることを自ら示す必要がある。さらにNPT体制から要求される義務に加えて、余剰のプルトニウムを持たないとの原則を堅持し、核燃料リサイクル計画の透明性をより高めるための国際的な枠組みの具体化に向けて努力するなどの自発的な政策を採る。 さらに、平和利用を指向した技術開発として、保障措置や核物質防護の技術開発を進めるほか、アクチニドのリサイクル技術の研究開発にも取り組んでいく。また、平和目的に限った原子力利用の普遍化を図ること、各国の原子力開発利用の安全性の向上に貢献することを基本としつつ、近隣アジア地域の原子力発電への展開も含む原子力利用に対する国情に応じた長期的継続的な協力や基盤整備等への協力、旧ソ連共和国の核兵器解体等への支援、旧ソ連、中・東欧諸国における原子力の安全確保への貢献、あるいは核融合における国際熱核融合実験炉(ITER)計画への主体的参加、先端的研究開発施設の国際的な開放など平和利用先進国にふさわしい国際対応に取り組んでいく。 また、原子力の平和利用と情報の公開は密接不可分であり、原子力が国民生活に密接に関連していることを踏まえ、「国民とともにある原子力」であるよう、国民参加型の意見交換の場等を通じた行政運営にも配慮しつつ、国民が原子力について判断する基礎となる情報の公開、提供の施策の一層の充実を図っていく。 ②整合性ある軽水炉原子力発電体系の確立 軽水炉による原子力発電は今日、我が国の総発電電力量の約3割を賄うまでになっており、軽水炉は高い信頼性を持つ炉型として定着している。今後とも相当長期にわたり軽水炉が原子力発電の主流になることが予想される。 原子力発電規模については2000年において約4,560万キロワット、2010年において約7,050万キロワットの設備容量を達成することを目標とし、このための立地円滑化の観点から、地元と施設が共生できるよう、関係省庁も一体となってこれを支援していく。 軽水炉主流時代の長期化をにらんで、軽水炉発電については、安全性、信頼性を確保しつつ、経済性の向上に対しても不断の努力を続けることが望まれる。具体的には、原子炉の高経年化対策など総合的な予防保全対策の一層の充実に努めつつ、ヒューマンファクターに係る対策、作業員の被ばく低減等を図るための自動化技術の高度化、さらには長期的視点を踏まえた燃料・炉心の高度化に取り組む。 軽水炉原子力発電を安定的に継続していくためには、ウラン資源を安定的に確保していくとともに、ウラン濃縮、ウラン燃料加工などをその規模や時期などの観点で、適切かつ合理的に進めていくことが重要である。ウラン濃縮については濃縮ウランの安定供給や核燃料サイクルの自主性確保の観点から、経済性を考慮しつつ国内における事業化を進めることとし、その目標として、当面2000年過ぎころ1,500トンSWU/年規模の安定操業の実現に取り組む。 整合性のある原子力発電体系の観点から残された最も重要な課題は、放射性廃棄物の処理処分と原子力施設の廃止措置を適切に実施するための方策を確立することである。 特に高レベル放射性廃棄物の処分は重要な課題であり、国は処分が適切かつ確実に行われることに対して責任を負いつつ、高レベル放射性廃棄物は地層処分することを基本的な方針とし、国の重要プロジェクトとして地層処分の研究開発を進める。また、処分事業の実施主体は2000年を目途に設立することとし、実施主体は地元の了承を得て処分予定地の選定、同地における処分技術の実証を行い、さらに所要の許認可を経て、2030年代から遅くとも2040年代半ばまでの処分場の操業開始を目途とする。 ③将来を展望した核燃料リサイクルの着実な展開 化石エネルギー資源と同様にウラン資源も有限であり、ウラン資源の確認可採埋蔵量を現在の年需要量で除して得られる値で43年程度であるが、今後長期的に見たときにはこの数字はより厳しい方向に推移することが予想される。 我が国にはウラン資源がほとんど存在しないことを踏まえると、ウラン資源を最大限有効に利用する考え方が重要であり、我が国は将来を展望しながらエネルギーセキュリティーの確保を図っていくために、リサイクルの実用化を目指して着実に研究開発を進めることとしている。核燃料リサイクルは資源や環境を大切にし、また、放射性廃棄物の処理処分を適切なものにする観点からも有意義である。 高速増殖炉は、発電しながら消費した以上の核燃料を生成することができ、ウラン資源の利用効率を飛躍的に高めることができることから、将来的に核燃料リサイクル体系の中核として位置付けられるものである。このため高速増殖炉を、相当期間にわたる軽水炉との併用期間を経て将来の原子力発電の主流にしていくべきものとして、その開発を官民協力して継続的に着実に行う。具体的には1994年4月に初臨界を達成した原型炉「もんじゅ」は1995年末の本格運転を目指し、「もんじゅ」までの開発成果に基づいて、電気事業者がこれに続く実証炉を建設していく階段に入りつつある。実証炉は1号炉を2000年代初頭に着工することを目標に計画を進める。さらにこれに続いて2号炉の建設を行い、再処理、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料加工等の燃料サイクル技術の開発と整合性をとりつつ、2030年ごろまでには実用化が可能になるよう技術体系の確立を目指す。 また、将来の高速増殖炉時代に必要なプルトニウム利用に係る広範な技術体系の確立、長期的な核燃料リサイクルの総合的な経済性向上を図っていく観点から、一定規模の核燃料リサイクルを実現することが重要である。このため現在建設中の六ケ所再処理工場(年間処理能力800トン)については2000年過ぎの操業開始を目指すこととし、その建設、運転を通じて商業規模での再処理技術の着実な定着を図る。軽水炉によるMOX燃料の利用を、エネルギー供給面で一定の役割を果たすことにも留意して、再処理施設の規模等を勘案しつつ、計画的に進めていく。さらに新型転換炉実証炉の建設、運転等によるMOX燃料利用を進める。 これらの核燃料リサイクルを進めるに当たっては、我が国において計画遂行に必要な量以上のプルトニウム、すなわち余剰のプルトニウムを持たないとの原則を堅持しつつ、合理的かっ整合性のある計画の下でその透明性の確保に努める。 ④原子力科学技術の多様な展開と基礎的な研究の強化 原子力技術の応用範囲は極めて広範であり、今後とも多様な展開を図る。 多様化、高度化する原子力のニーズに適切に対応し、国民の福祉の一層の向上を図る観点や国際公共財ともいうべき知的ストックの蓄積に我が国が貢献する観点から、既存の原子力技術の高度化のみならず、新しい原子力技術の高度化が必要である。このため、原理・現象に立ち返った研究開発を積極的に進めていくこととし、原子核・原子科学に関する研究、TRUや未知の超重元素に関する研究、各種ビームの発生と利用に関する研究等に取り組む。さらに既存の原子力技術にブレークスルーを引き起こす可能性のあるフロンティア領域や将来の新たな技術開発の進展を生み出す基盤を形成する可能性のある技術領域として、放射線生物影響分野、ビーム利用分野、原子力用材料技術分野、ソフト系科学技術分野及び、計算科学分野について当面の対象として研究を重点的に進める。 また、原子力によるエネルギーの生産と原子力利用分野の拡大を図るため、受動的安全性を高めた原子炉等新しい概念の原子力システムに関する研究開発、高温工学試験研究等に取り組む。 放射線利用は医療分野における高度診断、がん治療、あるいは農業分野における害虫防除、食品照射等、さらには工業分野における計測・検査など広範な分野への展開を通じて国民生活や福祉の向上に大きく貢献するものであり、エネルギー利用と並ぶ原子力開発利用の重要な柱として推進していく。医療や電子線による排煙処理といった環境保全など生活者を重視した利用技術の普及促進を図るとともに、加速器を用いたビーム発生・利用技術及び研究用原子炉を用いた中性子照射・利用技術に関する研究開発を進めていく。特に次世代の大型放射光施設の整備を引き続き進め、その利用を図るとともに、イオンビームを用いたがんの照射治療等に関する研究開発等に取り組んでいく。 核融合については、今後は自己点火条件の達成、長時間燃焼の実現、原型炉の開発に必要な炉工学技術の基礎を形成することを主要な目標に研究開発を進めていく。このための実験炉の開発が我が国にとって不可欠なものとなっており、JT-60に続いてトカマク型の実験炉の開発を進める。現在そのような実験炉の開発を目指してITER計画の工学設計活動が行われており、これに主体的に参加する。 さらに、原子力開発利用の安全の確保の一層の充実や関連する先端的技術開発の着実な進展を図っていくためには、その担い手となる優秀な人材の養成と確保にたゆまず努力することが不可欠である。特に青少年期における正しい原子力知識の普及活動を充実・強化する。 2.新長期計画策定の経緯 (長期計画改定への取組と具体的な審議)今回の長期計画策定については、原子力委員会は、1987年策定の長期計画の見直しを行うことを1992年7月に決定し、原子力委員会の下に長期計画専門部会を設置した。 同専門部会の下には、基本分科会、第一~第四分科会の5つの分科会を設置し、具体的な検討を行った。 (長期計画懇談会の設置) 長期計画の策定過程においては、原子力分野以外の学識経験者等から原子力開発利用について意見を求めるため、原子力の専門家以外の有識者から構成される長期計画懇談会を設置した。 (国民からの意見募集の実施と「ご意見をきく会」の開催) 今回の長期計画の改定については、原子力関係者はもちろんのこと、国民各界各層の関心が極めて高く、このため長期計画専門部会においては、広く国民各界各層から長期計画改定に関する御意見を頂くこととし、広く一般の方々から御意見の募集を行うことと、あわせて「ご意見をきく会」を開催することとした。募集期間中に寄せられた御意見は3,301通に達した。「ご意見をきく会」は、御意見をお寄せ頂いた一般の方々の中から抽選で選ばれた14名と、同専門部会側でお願いした各界の13名の方々にお集まりいただき、御意見を述べて頂いた。 (意見募集と「ご意見をきく会」で頂いた御意見への対応) 御意見の募集と「ご意見をきく会」で寄せられた多様な御意見は、長期計画の専門部会及び各分科会の審議において貴重な参考となり、それら御意見を十分吟味した上で長期計画が策定された。 長期計画の策定の過程で、寄せられた御意見をどのように参考としたかを明らかにするため、新長期計画と、それとあわせて公表した各分科会の報告書それぞれに対応する形で、「長期計画改定に関するご意見への対応について」資料を作成した。 (長期計画策定過程の透明性向上) 今次長期計画改定においては、長期計画策定過程自体の透明性を向上するため、長期計画懇談会に関しては、会議で使用した資料の公開、会合の内容のプレス関係者等への報告を行った。さらに、新長期計画の決定とあわせて、従来は公表されていなかった各分科会の報告書を公表し、より詳細な審議内容について参照できるようにした。 3.新長期計画に基づく当面の原子力政策の展開 本節においては、新長期計画に基づく当面の原子力政策の展開における諸課題とその取組への基本的な考え方を示すこととする。(我が国の原子力開発利用の大前提に対する認識) 我が国の原子力開発利用は、平和利用の堅持と安全の確保を大前提に進めるものであり、新長期計画においてもこの点を改めて示した。 平和利用の堅持の観点からは、今後とも我が国が核兵器を決して保有することはなく、制度上もこのことが確保されているとともに、そもそも核兵器の保有は我が国の平和と繁栄に何の利益もないということをあらゆる機会を通じて示していくことが重要であるが、原子力平和利用の透明性に対する国際的信頼の増進には、さらに不断の努力を傾注していくべきことを認識しなければならない。また安全の確保という観点からは、原子力施設の安全確保対策の充実、原子力防災対策の充実、安全研究の推進を図るとともに、高度な原子力安全文化の構築に努める。また、民生用原子力発電所の国際的な安全確保を目的に策定された「原子力の安全に関する条約」に1994年9月に署名したことを受けてその早期批准と発効に努めていく必要がある。 (核不拡散への取組) 我が国が原子力をめぐる国際情勢に的確に対応しつつ、平和目的の原子力開発利用を着実に進めるに当たっては、核不拡散体制の維持・強化は特に重要である。我が国として今後ともこれに最大限の努力を払い、NPTの下での我が国としての義務を厳格に履行するとともに、国際社会における核拡散の懸念を生じさせかねない動きについては毅然たる態度をとっていくことが肝要である。 とりわけ、北朝鮮の核兵器開発疑惑は、我が国の原子力平和利用推進にとっても重要な問題であり、米国と北朝鮮の間で署名された合意が誠実に履行されることにより、北朝鮮がNPTにとどまるとともにIAEAとの保障措置協定が完全に履行されることが重要である。 核不拡散体制の維持・強化の観点から当面重要な課題として、1995年4月に開かれるNPTの延長会議への取組がある。原子力委員会はNPTの無期限延長の支持は妥当であり、延長会議に向けてNPTの普遍性をより高めていくことが重要であるとの考え方を表明している。さらに核兵器の究極的な廃絶を望む我が国としては、NPTの無期限延長が核兵器国による核兵器保有の恒久化を意味するものであってはならず1955年のNPTの延長会議に向けてすべての核兵器国がより一層の核軍縮の進展への努力を払う重大な責務を負っているとの強い認識の下に、核兵器国に対しその責務の全うを働きかけていくことが重要である。 (国民の理解の増進と情報の公開、提供) 新長期計画の策定過程においては国民各界各層からの意見の募集や「ご意見をきく会」の開催という新しい試みが行われたが、このような「国民参加型」ともいうべき意見交換の場は、重要な機会となることが認識された。 今回の新長期計画の策定過程で設けたこれらの機会を通じて、情報の公開、情報の提供への一層の取組を望む強い声が聞かれた。情報の公開については核物質防護、核不拡散、財産権の保護に関する情報など非公開にすべきものはあるが、原子力の安全性に関する情報などについて公開がなされてきており、さらにはプルトニウムの管理状況に関する情報を今回公表しており、今後とも一層の配慮が必要である。 また、情報の提供の面では、国民が判断する際の基礎となる情報が適時的確に提供されていくことが重要であり、提供窓口の充実やその周知に一層努力するとともに、今後は情報ネットワーク等の新しい媒体の活用にも留意する必要がある。さらに、情報の送り手から受け手への単なる提供から進めて、「参加型」の意見交換の場を通じた情報提供という観点も重視していく必要がある。 さらに、エネルギーや原子力に関する青少年に対する学習機会の確保・充実も、情報の提供の重要な課題と考えられる。 (核燃料リサイクルの展開) 核燃料リサイクルを展開していく上で当面する重要課題は、青森県六ケ所村の再処理工場建設の円滑な推進、軽水炉でのMOX燃料利用計画や新型転換炉実証炉計画の進展、高速増殖炉開発においては1994年4月に臨界を達成した高速増殖原型炉「もんじゅ」の本格運転開始への取組、実証炉1号炉の2000年代初頭の着工に向けての所要の研究開発や準備、さらに核不拡散や放射性廃棄物による環境への負荷の軽減の観点から重要な意義を有するアクチニド・リサイクルの研究開発の具体化などである。 これらの中でも、軽水炉でのMOX燃料利用計画は、今後の核燃料リサイクルの具体的な展開のうえでの端緒となる緊要なものである。MOX燃料利用計画は技術的には特段の問題はないものと考えられ、政府、事業者ともそれぞれの役割に応じて、これが新長期計画に示された方向に沿って確実に展開されるよう最大限の努力を払っていかなければならない。 さらにこれらの核燃料リサイクル計画を進める上では、透明性の向上の観点が特に重要であり、余剰のプルトニウムを持たないという原則の厳守を内外に示すとともに、現在関係国間において精力的に進められているプルトニウム利用の透明性の向上のための国際枠組みの構築に積極的に取り組んでいくことが重要である。 (高レベル放射性廃棄物対策) 1995年春にはフランスヘの再処理委託によって生じた高レベル放射性廃棄物のガラス固化体の我が国への最初の輸送が予定されているが、この輸送と輸送されたガラス固化体の一時貯蔵の開始は今後の高レベル放射性廃棄物対策の展開を図る上で重要な意味を持つものであり、これが内外の理解を得て円滑に実施される必要がある。 さらに、高レベル放射性廃棄物の地層処分については、その推進に当たっては処分方策全般についての透明性の向上に留意し、高レベル放射性廃棄物処分に関する調査・研究の成果を明らかにすること等を通じて国民の理解を得ていくことが必要である。特に研究開発の進展は地層処分実施の基礎となるとともに国民の理解を得る上でも極めて重要であり、研究開発の進捗状況を的確に把握し、その公な評価を通じて研究開発の到達度を適時に国民に明らかにしていく必要がある。 (放射線に関する研究開発の取組) 放射線の利用はエネルギーと並ぶ原子力開発利用の重要な柱であり、最近では、重粒子線によるがんの治療技術の開発などの医療、農業など生活に密着した領域や環境の保全等の面で成果が上がりつつあり今後その普及、拡大の促進に一層の努力を払っていくことが重要である。さらに大型放射光施設の整備による放射光の利用など加速器によるビームの発生とその利用技術に関する研究開発に取り組む必要がある。 (国際協力への取組) 近隣アジア地域は、今後、経済発展とともに原子力開発利用が、大きく進展することが予想される地域である。 これら諸国においては、我が国に対する期待感も表明されている。我が国としてはこのような進展を踏まえ、安全確保・安全規制面での協力等に着手しつつあるが、今後は、さらに我が国からの原子力資機材等の供給の活発化等が予想され、我が国としてはこれに的確に対応できるよう国内関係機関の間の連携強化を図らなければならない。 旧ソ連・中・東欧諸国の原子力安全の支援に関しては二国間、多国間の枠組みにより、諸外国の実施する支援と調整を図りつつ、短期的な技術改善に係わる措置、長期的視点からの安全確保体制の充実等への支援を進めていく。特にチェルノブイル原子力発電所の早期閉鎖とその代替措置に関する支援についてはその具体化を注視していく必要がある。また、旧ソ連・ロシアによる日本海での放射性廃棄物の海洋投棄についてはこれが再び行われることがないよう廃棄物処理施設の建設等の支援を進める。 ITER計画については今後、実際の炉の建設計画を検討していくこととなるが、我が国としては研究開発の効率化と主体的な国際貢献の観点から、この問題への取組について検討を深める必要がある。 新長期計画においては、21世紀に向けて人類が地球を慈しみ、地球と人類がともに末永く生きていくという新しい価値観に基づいた文明―リサイクル文明―を創り上げていくとの理念に立って原子力開発利用を位置付けている。原子力委員会としては、この位置付けにのっとり、新長期計画の中の言葉の「国民とともにある原子力」を常に念頭に、国民の理解の下に、さらには国際社会の理解の下に原子力政策の展開に努める考えである。 第2章 新長期計画策定の背景としての内外の原子力開発利用の現状 1.核兵器の不拡散をめぐる内外情勢 (1)NPT体制の維持・強化に向けた動向①NPT体制の概要 「核兵器の不拡散に関する条約(NPT)」は、1944年9月末現在、米国、ロシア、英国、フランス及び中国の核兵器国5か国を含む165か国が締約国となっている。我が国は1976年に加盟している。NPTは、その発効以後、締約国の中で新たな核兵器保有国はなく、また、近年、未加入の核兵器国であったフランス、中国が加入するなど核不拡散を図る上で極めて普遍性の高い国際的枠組みとなっている。 その一方、締約国である北朝鮮、イラクの核兵器開発疑惑、南アフリカ共和国のNPT締約前における核兵器保有や旧ソ連の核兵器等の管理の不安定化などの問題が生ずるとともに、インド、パキスタン、イスラエルなどのNPTの未締約の国が依然として存在している。我が国としてもNPTの維持・強化に向けた一層の努力が必要である。また、今後ともNPT体制上の義務を厳格に履行するとともに、原子力平和利用の意図を改めて明確にし、我が国は核兵器に関する技術を有しておらず、また将来にわたっても制度的に核兵器への転用の可能性は排されていることを国内外に示していくことが必要である。 ②NPT延長会議に向けた動き NPTは、1995年4月に開催が予定されているNPT再検討・延長会議において、無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかが決定されることとなっている。 我が国は、既に政府がNPTの無期限延長支持を表明しており、原子力委員会も、無期限延長の支持は妥当との考え方を表明している。国際的にも、1994年7月のナポリサミットの議長声明において、「すべての未締約国に対し、非核兵器国としてNPTに加入するよう呼びかける。1995年における条約の無期限延長に対する明確な支持を宣言する。」としている。もちろん、NPTの無期限延長が核兵器国による核兵器の保有の恒久化を意味するものではなく、すべての核兵器国に対してより一層の核軍縮を働きかけ、核兵器の廃絶に向けて努めていくことが重要である。 (2)新たな核不拡散努力 ①世界的な核軍縮 冷戦構造の終結後、第一次戦略兵器削減条約(STARTI)の調印、第二次戦略兵器削減条約の調印など米国及び旧ソ連において大規模な核軍縮の動きが進展しつつある。また、米国、ロシア、英国及びフランスは核実験停止を継続しており、米国は軍事目的の核物質の生産を中止している。さらに、ジュネーブにおいて、1994年1月にはCTBTに関する交渉が開始された。 一方、旧ソ連の崩壊に伴い、ロシア以外に三つの旧ソ連共和国(ベラルーシ、カザフスタン及びウクライナ)にも戦略核兵器が存在することとなったが、これら三国はSTARTIを批准するとともに戦略核兵器をロシアに移転したうえで非核兵器国としてNPTに加入することとなり、べラルーシ及びカザフスタンはNPTに加入した。ウクライナについても、米国、ロシアがウクライナの安全保障を約束するとともに、ウクライナがNPTに非核兵器国として加入することを再確認した。 核軍縮の進展は、今後の国際社会の平和と安定にとって重要かつ喫緊の課題であることから、核不拡散を担保としつつ核軍縮を早期に進展させることが重要である。 ②旧ソ連における核拡散懸念 (i)非核化支援 冷戦の終了後、旧ソ連等における核兵器の廃棄等を進め、核軍縮を中心とする軍縮の大幅な進展を図ることが、今後の国際社会の平和と安定によって重要かつ喫緊の課題である。このため、第一義的には当事国が責任を持って対処すべきではあるものの、我が国が、これまで培ってきた原子力平和利用の技術と経験をいかし、旧ソ連の核兵器の廃棄等平和に向けた国際的努力に積極的に協力することは、核軍縮と核兵器の拡散防止に貢献する上で重要である。 そのため、核兵器廃棄の支援に係る我が国とロシアとの二国間取極が署名され、核分裂性物質貯蔵や放射性廃棄物等に関する専門家による4つのワーキング・グループが設置され、現在検討が進められている。同様の協定は、ベラルーシ、ウクライナ及びカザフスタンとの間でも署名が行われた。 冷戦終結に伴う核軍縮を安全かつ確実に進めるためには、特に核兵器の解体により生じるプルトニウム等の核物質が再び核兵器に利用されないための国際的な管理計量体制を早急に確立する必要がある。 (ii)国際科学技術センター 旧ソ連の大量破壊兵器関連の科学者、技術者等の能力を平和的活動に向ける機会を提供することを主目的として、1994年3月に本センターが設立された。我が国は、この目的のため、2,000万ドルの支援を行うこととしており、また、本センターに事務局次長等の人材の派遣を行っている。 ③核物質の密輸問題 1994年夏以降、ドイツ等において核不拡散上機微な核物質の不法取引が数次にわたり摘発されている。本件については1994年9月に開催されたIAEA総会においても取り上げられ、核物質の不法取引の最近の増加を憂慮するとともに、各国が核物質の密輸防止のため連絡協議の場を設置することが合意され、今後各国が密輸を防止するため連絡を密にし適切に対応していくことを内容とする決議が採択された。 ④プルトニウムの使用等に関する国際枠組みの検討 冷戦終結後の核軍縮の進展による核兵器解体に伴いプルトニウム及び高濃縮ウランが大量に発生することが予想されており、その動向については、国際的にも関心が高まっているそのため、IAEAでは1992年12月に関係国(核兵器5か国及び日独)によるプルトニウム等の蓄積・利用に関する非公式会合を開催し、国際的な枠組みに関して検討が進められてきたが、1994年2月以降は、関係国イニシアティブ会合の場で国際枠組みの具体化に向けて検討が行われている。 ⑤米国による核爆発目的の又は国際的保障措置の枠外の高濃縮ウラン及びプルトニウムの生産を禁止する多国間条約の提案 1993年9月に米国は「核爆発目的の又は国際的保障措置の枠外の高濃縮ウラン及びプルトニウムの生産を禁止する多国間条約」を提案した。これは、核爆発装置の研究・製造・使用のための高濃縮ウラン生産・プルトニウム分離の禁止、他国による核爆発装置の研究・製造・使用のための高濃縮ウラン生産・プルトニウム分離に対する援助の禁止等の内容が想定されている。本条約は、核兵器国及びNPT非締約国の核能力を凍結することにより核不拡散、核軍縮に貢献しうるものであり、交渉の早期開始が望まれる。 (3)北朝鮮の核兵器開発疑惑 北朝鮮は、1985年にNPTに加入後、1992年4月にIAEAとの間の保障措置協定を締結したものの、追加情報の提供と追加施設への査察の実施を求めてIAEAが要求した特別査察を拒否し、1993年3月にはNPTから脱退を決定するに至ったが、米朝会談を通じて、脱退が発効する直前の1993年6月に脱退の一時中断を宣言した。その後、更なる米朝会談及びIAEAによる査察の継続により核兵器開発疑惑の解明の努力が続けられてきたが、1994年には、放射化学研究所に対する査察、5メガワット実験炉の燃料棒交換に対する査察等に関して、IAEAの要求する査察を十分に受け入れない等の問題が発生した。これを受けて1994年6月、IAEA理事会はすべての保障措置に関連する情報及び場所へのアクセス要求等を内容とする決議を採択したところ、北朝鮮は、IAEAからの即時脱退、今後のIAEAの査察拒否等を表明した。 その後、カーター元米国大統領の訪朝等により第3回米朝協議が開始され、10月には、①北朝鮮の黒鉛減速炉の軽水炉への転換(約2,000メガワット規模の軽水炉プロジェクトの提供とそのための国際的コンソーシアムの組織、代替エネルギーの提供、黒鉛炉及び関連施設の凍結・解体等)、②両国の政治的・経済的関係の完全な正常化(貿易・投資の障壁緩和、連絡事務所の開設等)、③核なき朝鮮半島の平和と安全保障への努力(米国による核兵器の不使用、南北非核化共同宣言の実施のための措置等)、④国際的な核不拡散体制の強化への努力(NPTに留まる、IAEA保障措置協定の履行等)、の4点を柱とする合意文書に署名がなされた。 本問題については、IAEA保障措置が適切に適用され、国際社会における北朝鮮への核拡散懸念が払拭されるよう努めることが重要であるが、今回の合意内容は、基本的にこれに沿うものであると認識される。今後は、北朝鮮が今回の合意内容に従って誠実に行動することが重要であり、その際には、北朝鮮における原子力活動が平和利用に限られることと安全の確保が十分に行われることが不可欠であると考えており、引き続き注視していくことが必要である。 (4)我が国の核不拡散への取組 ①保障措置 我が国は、1976年にNPTを批准し、これに基づき1977年にIAEAとの間に保障措置協定を締結し、国内の保障措置制度を前提とした国内すべての原子力施設に対するIAEAの保障措置を受け入れているとともに、IAEAにおいて行われている保障措置関連のプロジェクトに積極的に参加するなどIAEAの保障措置体制の整備・強化に積極的に貢献している。 また、我が国が締結している二国間原子力協定上の義務を履行するため、供給当事国別の核物質等の管理を実施している。 ②核物質防護 核物質の不法な移転の防止及び原子力施設等への妨害破壊行為に対する防護については、我が国は核物質の防護に関する条約等を遵守し、原子炉等規制法等に基づき関係行政機関により所要の施策を実施してきている。 ③我が国の分離プルトニウムの管理状況 我が国は核燃料リサイクルを推進するに当たって、計画遂行に必要な量以上のプルトニウムを持たない、すなわち余剰のプルトニウムを持たないとの原則の下、プルトニウム利用計画の透明性をより向上させるために、我が国のプルトニウム利用の計画とその現状を具体的に国内外に明らかにしていくよう努めているところである。 新長期計画によると、国内再処理によって回収されるプルトニウムは、六ケ所再処理工場の操業前は、単年毎には国内的に需要が供給を上回る状態が続き、2000年代後半の再処理工場の本格操業以降は需給はバランスする。一方、海外再処理によって回収されるプルトニウムは、基本的には海外で軽水炉MOX燃料に加工された後、我が国に返還され軽水炉で利用される。 我が国の分離プルトニウムは、再処理工場で分離された硝酸プルトニウム、これを転換した酸化プルトニウム、燃料加工工程中のプルトニウム及び原子炉に装荷される前の新燃料中のプルトニウム並びに研究開発の目的に供されているプルトニウムで構成される。現状としては、1993年12月末において、再処理施設(プルトニウム転換施設を含む。)に約326キログラム、燃料加工施設に約3,269キログラム、原子炉施設内の新燃料等として約1,089キログラムの分離プルトニウムが管理されている。 また、燃料加工に当たって直接の原料となる酸化プルトニウム(主として粉末の形状)については、1993年1年間における供給量として、国内の東海再処理施設から回収された約421キログラムのほか、高速増殖原型炉「もんじゅ」の取替燃料用に海外から移転された約1,508キログラムがある。一方、同期間中の酸化プルトニウムの使用量は、「もんじゅ」等の燃料を製造するために燃料加工工程に移転された約454キログラムである。 なお、1993年12月末における酸化プルトニウムの量は再処理施設に約38キログラム、燃料加工施設に約2,377キログラムである。これらは貯蔵容器に封入され専用の貯蔵庫において厳重に保管されており、順次「もんじゅ」の取替燃料等に加工され利用されることになっている。 また、核軍縮の進展や、核燃料リサイクルによる、将来のプルトニウムの備蓄傾向に関して国際的な関心が高まってきており、関係国において平和利用等の透明性を高めるための国際的枠組みの在り方に関する非公式の検討が進められている。我が国としては、プルトニウム利用計画の透明性を一層向上させる等の観点から、このようなプルトニウムの国際的枠組みの在り方についての国際的検討において、関係国及びIAEAとも緊密に協議しながら、その策定に向けて積極的に関与していくこととしている。 表5.我が国のプルトニウム管理状況 2.原料となる酸化プルトニウムの使用状況(1993年) 3.海外の酸化プルトニウム(1993年12月末現在) 2.原子力安全確保 (1)原子炉施設等の安全確保従来から国は厳格な安全規制等を行うことにより原子炉施設等の安全確保に万全を期してきている。 安全規制の概要としては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」の定めるところにより、厳重な安全のための規制が行われている。そして、原子力委員会及び原子力安全委員会が、所管大臣の諮問に基づき、各所管行政庁の行った審査の結果について審査指針等に照らし独自の立場から調査審議(いわゆるダブルチェック)を行っている。 放射性同位元素(RI)等の取扱いに係る安全性の確保については、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)」等に基づき許認可等の厳正な審査、立入検査、監督指導等所要の規制が行われている。 (2)原子力の安全研究等 原子力施設の安全性を今後とも高い水準に維持していくため、原子力開発利用の拡大と多様化に対応して、安全審査等に資するため安全研究年次計画に基づく原子力安全研究や原子力施設等の安全性実証試験等が積極的に推進されている。 (3)環境放射能調査 国民の被ばく線量に最も大きく寄与する自然放射線による被ばく線量を推定するため、自然放射線の調査、原子力施設周辺の放射能調査、核爆発実験等に伴う放射性降下物の放射能調査、米国原子力軍艦の寄港に伴う放射能調査、米国原子力軍艦の寄港に伴う放射能調査が行われている。 (4)原子力安全確保に係る国際協力 ①旧ソ連、中・東欧諸国の原子力安全対策に対する協力 ナポリサミットの経済宣言において、旧ソ連、中・東欧諸国に対する原子力安全支援のうち、特にウクライナの原子力安全が重点的に取り上げられた。我が国においても、多国間協力としては、IAEAのソ連型原子力発電所の安全性評価プロジェクト等に人的及び資金的な面で積極的に貢献し、二国間協力については、旧ソ連、中・東欧及びアジア諸国より原子力技術者等を受け入れ、原子力安全向上のための研修を実施している。 ②原子力の安全に関する条約 旧ソ連、中・東欧諸国の原子力発電所の安全問題を契機として、各国の原子力施設の安全性確保を目的とした原子力の安全に関する条約が1994年6月に開催された外交会議において採択され、9月のIAEA総会の機会に同条約の署名解放がなされた。1994年10月中旬までに49か国が署名しており、今後、原子力発電所保有国の17か国以上を含む22か国の批准が終了した日の後90日で発効することとなっている。 本条約は、民生用原子力発電所を対象として、各国が遵守すべき安全上の基本的措置に係る義務的条項や、条約の遵守状況を確認するための締約国会合の開催等について盛り込んである。 3.情報公開と国民の理解の増進 (1)原子力開発利用に対する最近の世論の状況1990年に行われた総理府の世論調査、1993年に行われた、(社)エネルギー・情報工学研究会議の全国での世論調査によると、原子力の必要性については多くの人が感じているものの、安全性に対する不安・心配は残っており、原子力の安全性に対する理解を促進していくことが必要であることがわかる。 (2)国民の理解の増進と情報の公開の基本的考え方 新長期計画においては、上記のような世論の状況をも踏まえて原子力開発利用を円滑に進めていくためには、「国民とともにある原子力」との認識の下、まず国、原子力事業者に対する国民の信頼感、安心感を得ることが重要であるとし、国民参加型の行政運営の重要性、情報公開、情報の提供への一層の配慮と方策の充実さらに青少年に対する正確な知識の普及について強調している。 (3)原子力に対する国民の理解の増進のための活動の状況 従来からの講師の派遣等対話型の活動、簡易型放射線測定器「はかるくん」の貸出しといった体験型の活動、パンフレット等の配布が行われるとともに、テレビ・雑誌・新聞等のマスメディアを活用した広報も行われている。本年度は、新たに通商産業省資源エネルギー庁が、7月より「原子力発電ライブラリ」及び「原子力発電目安箱」を設置し、原子力発電の安全性に関する情報の公開と国民からの質問・意見の聴取を開始した。また、科学技術庁と通商産業省資源エネルギー庁が共同し、公募により「原子力の日」のポスターを選定した。 4.原子力発電の現状と見通し (1)我が国の原子力発電の状況1994年3月に九州電力(株)玄海原子力発電所3号炉(電気出力118万キロワット)、8月に東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所4号炉(電気出力110万キロワット)がそれぞれ新たに運転を開始したことにより、1994年9月末現在、運転中の商業用発電炉は47基、発電設備容量は3,947万6千キロワット、新型転換炉原型炉「ふげん」を含めると、48基、3,964万1千キロワットとなっている。これは、米国、フランスに次ぐ世界第3位の設備容量である。原子力発電は、1993年度末現在総発電設備容量(電気事業用)の20.2%、1993年度実績で総発電電力量(電気事業用)の31.2%を占め、主力電源として着実に定着してきている。 (2)原子力発電の将来見通しと原子力施設の立地の促進 ①原子力発電規模の見通し 今後の原子力発電の開発規模については、2000年において約4,560万キロワット、2010年において約7,050万キロワットの設備容量を達成することを目標とし、さらに長期的展望として、2030年の原子力発電の設備容量は約1億キロワットに達することが期待される。 ②原子力施設の立地促進 今後、上記の原子力発電設備容量を確保するには、既存サイトでの増設に加えて新規サイトの確保が必要であるが、原子力発電所の立地には計画から運転開始までのリードタイムが長期に及ぶことを考慮すると、早急に新規サイトの確保に向けて対策を充実していくことが必要である。 (3)世界の原子力発電の状況 世界の原子力発電設備容量は、1994年6月末現在、運転中のものは、423基、3億5,419万キロワットに達している。また原子力発電は現在、30か国(地域)で行われており、原子力発電所を建設若しくは計画している国を合わせると37か国(地域)に上っている。
5.軽水炉体系による原子力発電 (1)軽水炉技術の向上我が国では、政府、電気事業者、原子力機器メーカー等が協力して、自主技術による軽水炉の信頼性、稼働率の向上及び従業員の被ばく低減を目指し、軽水炉の改良標準化計画を第1次から第3次まで実施してきた。今後の軽水炉技術の開発に当たっては、一層の安全の確保に積極的に取り組むとともに、設計、運用の両面から技術の高度化を図ることが必要である。 (2)ウラン資源の確保と利用 我が国の原子力発電に必要な天然ウランについては、電気事業者により、カナダ、英国、オーストラリア等から主として長期契約等により、2000年過ぎごろまでの所要量を確保しているが、我が国の原子力開発利用の自主性・安定性の確保の観点から、引き続き、長期購入契約、自主的な探鉱活動、鉱山開発への経営参加等供給源の多様化に配慮し、天然ウラン資源の確保に努めることとしている。 (3)ウラン濃縮の核燃料成形加工・再転換 ①ウラン濃縮 ウラン濃縮役務については、現在世界的に、供給能力が需要に対して過剰な状況であり、この状況は2010年過ぎにおいてもある程度の期間続くものと推定されているが、我が国としては、濃縮ウランの安定供給の確保の観点ばかりではなく、我が国における核燃料サイクル全体の自主性の確保の観点から、経済性を考慮しつつ、ウラン濃縮の事業化を推進することとしている。 六ケ所ウラン濃縮工場(事業主体:日本原燃(株))については、1988年10月に建設工事が開始され、1992年3月に150トンSWU/年の規模により操業を開始し、現在は600トンSWU/年の規模で操業中である。本プラントは2000年過ぎごろに、最終的には1,500トンSWU/年の規模とする計画となっている。それ以降の国産化の展開に関しては、国際動向、経済性、技術の継承等を考慮しつつ具体的な事業規模と時期を検討することとしている。 さらに、今後のウラン濃縮の経済性の向上のために、遠心分離技術の高性能化等を進める一方、次世代の技術と考えられるレーザー法の新濃縮技術の研究開発を着実に進めていくこととしている。 ②核燃料成形加工・再転換 再転換のうち、加圧水型軽水炉(PWR)燃料用のウランの再転換については、ほぼすべてが国内で行われている。また、沸騰水型軽水炉(BWR)燃料用のものについては、一部を海外に委託している。 成形加工については、PWR用、BWR用ともに全量が国内で加工されている。 ③回収ウラン利用に関する技術開発 国内再処理により回収されたウランについては、動力炉・核燃料開発事業団がウラン濃縮原型プラント等を利用して実用規模による再濃縮計画を進めて行く等、将来の本格利用に備えて民間関係者と同事業団が共同して研究を行っていくこととしている。 6.核燃料サイクルの技術開発 (1)使用済燃料の再処理の動向我が国は、使用済燃料の再処理について、現在、動力炉・核燃料開発事業団東海再処理工場並びに英国核燃料公社及びCOGEMAで再処理委託契約により実施している。国内では、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理工場の使用済燃料の累計再処理量は、試験運転期間を含め1977年9月から1994年3月で、約720トンとなっている。また、日本原燃(株)は、1993年4月、青森県六ケ所村に年間再処理能力800トンの民間再処理工場の建設に着手し、2000年過ぎの操業開始を目指し建設工事を進めている。 使用済燃料は、再処理されるまで適切に貯蔵・管理することとしており、各原子力発電所の貯蔵プールには、1994年3月現在、合計約3,900トンの使用済燃料が安全に保管されている。 (2)軽水炉によるMOX燃料利用と新型転換炉の開発 ①軽水炉によるMOX燃料利用 軽水炉におけるMOX燃料の利用は、将来の高速増殖炉の実用化に向けた実用規模の燃料リサイクルに必要な技術の確立、体制の整備等の観点から重要であり、また、プルトニウムをMOX燃料としてリサイクルしていくことが、核不拡散上に意義あることを考慮しつつ、軽水炉でのMOX燃料利用を弾力的に運用していくことが重要である。 現在の軽水炉において、MOX燃料を利用することについては特段の技術的問題はなく、着実に計画を進めていく段階にある。 具体的には、1990年代後半からPWR及びBWRそれぞれ少数基において利用を開始し、2000年頃に10基程度、その後は、再処理の状況等を勘案し、2010年までには十数基程度の規模にまで計画的かつ弾力的に拡大することとしている。 ②新型転換炉の開発 新型転換炉(ATR)は、プルトニウム、回収ウラン等を柔軟かつ効率的に利用できると言う特長を持つ原子炉として自主開発を進めてきている。これまで、原型炉「ふげん」(16万5千キロワット)の設計・建設・運転の成果に基づき実用化に向けての技術的見通しが得られている。 新長期計画では電源開発(株)が実証炉(電気出力約60キロワット)を青森県大間町に2000年代初頭の運転開始を目標に建設計画を進めることとしており、その後の計画については、実証炉の建設の状況、実用化に向けての経済性の見通し、核燃料リサイクル体系全体の開発状況等を踏まえつつ対処していくとしている。 ③MOX燃料加工 我が国のMOX燃料加工の研究開発は、動力炉・核燃料開発事業団を中心として実施されてきており、その加工実績も1994年3月末までの累積で約130トンMOXに達しており、我が国は世界的にみてトップレベルにある。 また、軽水炉によるMOX燃料利用計画及び2000年過ぎに予定されている六ケ所村の再処理工場の操業開始を踏まえ、年間100トン弱程度の国内MOX燃料加工の事業化を図る必要があり、現在、電気事業者を中心とした民間関係者により、加工事業主体の設立に向け、検討が進められている。 また、海外再処理により回収されるプルトニウムについては、基本的には海外においてMOX燃料加工し、海上輸送を行い、軽水炉で利用する予定である。 (3)高速増殖炉の開発 ①実験炉の運転 実験炉「常陽」は、1977年4月の初臨界以来順調な運転を続け、高速増殖炉の開発に必要な技術データや運転経験を着実に蓄積してきた。 初臨界以来、1994年7月末現在で、累積運転時間が約50,400時間、累積熱出力が約410万メガワット時間に達しており、照射中のものを含め445体の燃料集合体等の照射試験を実施してきており、今後引き続き高速増殖炉の実用化のための燃料・材料開発用照射炉として活用していくこととされている。 ②原型炉の建設 原型炉「もんじゅ」は、1994年4月5日の初臨界達成も含め、順次段階的に性能試験が着実かつ慎重に進められている。今後、1995年末の運転開始を目指し、引き続き高速増殖炉技術を確立するための試験データを取得するとともに、その後は原型炉としての運転実績を積み重ね、その安全性、信頼性等を実証し、さらに炉心性能等の向上を図り、得られる成果を実証炉以降の高速増殖炉開発に反映していく計画である。 ③実証炉の開発 原型炉に続く実証炉の開発は、設計・建設・運転について、電気事業者が動力炉・核燃料開発事業団との密接な連携の下に主体的役割を果たし、関連する研究開発については、電気事業者、動力炉・核燃料開発事業団、そのほか関連する研究機関等がそれぞれの役割に即し、整合性を持って進められている。
海外から我が国へ輸送される核燃料物質は、発電用低濃縮ウラン燃料の場合は、低濃縮ウランの原料となる天然六フッ化ウラン、海外で濃縮された六フッ化ウラン又は更に転換加工された二酸化ウラン粉末の形態で輸送されている。 (5)核燃料リサイクルをめぐる国際動向 原子力平和利用を進める上で核燃料リサイクルを行うこととしている国は、フランス、英国、ドイツ、スイス、ベルギー及び日本等である。他方、核燃料リサイクルを行っていない国としては、米国、カナダ、スウェーデン等がある。核燃料リサイクルの選択は、それぞれの国ごとの事情によってなされるものであるが、核不拡散の動向やエネルギー資源の状況によるところが大きく、また、経済性の比較、環境への負荷度も大きな要素であると考えられる。 7.バックエンド対策 (1)放射性廃棄物の処理処分対策新長期計画においては、整合性のある原子力発電体系という観点から残された最も重要な課題は、バックエンド対策を適切に実施するための方策を確立することであり、これは原子力による便益を享受している我々世代の責務であるとしている。 また、バックエンド対策の基本方針として、多種多様な放射性廃棄物の特性を踏まえて合理的に実施することとし、安全確保を大前提に、国民の理解と協力の下、責任関係を明確化して計画的に推進していくこととしている。特に、高レベル放射性廃棄物の処分については重要な課題として取り上げ、処分の手順、スケジュール、関係各機関の責任と役割等を明確にしつつ、円滑に実施していくことが必要であるとしている。以上の基本方針の下、今後、必要な研究開発等の諸施策を進めていくこととしている。 動力炉・核燃料開発事業団が北海道幌延町で計画している貯蔵工学センターは、高レベル放射性廃棄物等の貯蔵と併せて、地層処分のための研究開発等を行う総合研究センターを目指したものであり、本計画は処分場の計画と明確に区別し、地元及び北海道の理解を得てその着実な推進を図っていくこととしている。 (2)原子力施設廃止措置対策 我が国における商業用原子力施設の廃止措置は1990年代後半に現実のものになると予想される。新長期計画においては、原子力施設の廃止措置は、原子力施設設置者の責任の下に行うこととし、その基本的考え方として、安全確保及び地域社会との協調を挙げ、さらに商業用発電炉の廃止措置については、原子炉の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤去することを原則とし、解体撤去後の敷地の利用については地域との協調を図りつつ原子力発電所用地として有効利用することとしている。 8.原子力科学技術の多様な展開と基礎的な研究の強化 (1)基礎研究・基盤技術開発①基礎研究の動向 原子力技術はなお多くの可能性を秘めており、原理・現象の解明のための基礎に立ち返った研究は、現在の技術の改良をもたらすだけでなく、未知の新技術を生み出し、現在の原子力技術を大きく変えていくものと期待されることから、基礎研究の充実に努めている。 ②基盤技術開発 原子力技術に対するニーズの一層の多様化や高度化に弾力的に対応するとともに、技術シーズの探索、体系的な研究開発の積み重ねなどにより、将来の新しい原子力技術体系を意識的に構築していくことが必要であることから、既存の原子力技術にブレークスルーを引き起こし、基礎研究とプロジェクト研究とを結びつける基盤技術開発を推進している。 (2)原子力利用分野の拡大に関する研究開発等の状況 ①新しい型の原子炉の研究 受動的安全性を具備した中小型炉、モジュール型液体金属炉等の新しい型の原子炉については、幅広く基礎的・基盤的研究を推進し、将来の原子炉技術の飛躍的発展の可能性の検討を行っている。
高温ガス炉の基盤の確立、高度化及び高温工学に関する先端的基礎研究を積極的に進めるための中核的研究施設として高温工学試験研究炉の建設が日本原子力研究所において1998年ごろの臨界を目指して進められている。 ③原子力船研究開発 我が国最初の原子力船である「むつ」は、1991年から1年間の実験航海により、原子力船の設計、建造、運航に必要な基礎的技術基盤が確立され、また得られたデータ、経験等は今後の原子力船の研究開発に最大限に活用される。 (3)放射線利用の現状と研究開発 ①放射線利用に関する研究開発 日本原子力研究所及び理化学研究所は、兵庫県播磨科学公園都市において、1997年の一部供用開始を目指し、世界最大(8ギガエレクトロンボルト)の大型放射光施設(SPring-8)の建設を推進している。本施設の高指向性・高輝度の放射光によって、物質・材料系科学技術、情報・電子系科学技術、ライフサイエンス等の広範な分野の研究・技術開発に飛躍的な発展をもたらすことが期待される。 放射線医学総合研究所では、重粒子線によるがん治療法の研究開発を進めており、1987年度より重粒子加速器を用いた重粒子線がん治療装置の建設を進め、1994年に完成に至り、1994年6月より、患者への照射治療が開始され、現在頭けい部、肺、中枢神経のがんを対象として、臨床試行が進められている。 ②放射性同位元素及び放射線発生装置の利用状況 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)に基づく放射性同位元素(RI)又は放射線発生装置の使用事業所は着実に増加しており、1993年3月末現在、4,958事業所に達している。これを機関別に見ると、民間企業1,865、研究機関908、医療機関808、教育機関408、そのほかの機関969である。 ③放射線利用技術の実用化等の状況 医療分野において、放射線は診断、治療等で、農業分野では、品種改良、害虫防除、食品照射といった分野において放射線が利用されている。また、排煙、廃水、汚泥の処理など環境保全分野においても放射線が利用されている。 (4)核融合研究開発 核融合は、重水素やトリチウム(三重水素)などの軽い元素の原子核同士が融合してヘリウムなどのより重い原子核に変換する反応である。必要な燃料資源等が地球上に豊富に存在すること、原理的に高い安全性を有すること、地球環境問題の原因となる物質を排出しないことなどエネルギー源として優れた特徴を有している。これが実用化された場合には、世界のエネルギー問題の解決に大きく貢献するものと期待されていることから、国内外において積極的な取組が行われている。 我が国の核融合の研究開発は、1992年に原子力委員会が策定した第三段階核融合研究開発基本計画により進められている。同基本計画の主要な目標は、核融合の自己点火条件の達成及び長時間燃焼の実現並びに原型炉の開発に必要な炉工学技術の基礎を形成することである。現在、日本、米国、EU及びロシアの4極により工学設計活動が進められている国際熱核融合実験炉(ITER)は、そうした目標を達成するための研究開発の中核を担い得る装置である。新長期計画においては、我が国としてITER計画に主体的に参加することが明記されている。ITER計画については、現在、工学設計活動が行われている。また、これに加え、日本原子力研究所、大学、国立試験研究機関等が連携・協力して核融合の研究開発を行っている。 9.原子力分野の国際協力 原子力分野においては、各国に共通する技術課題の解決が必要な分野や、多額の資金、研究者、技術者の結集が必要な分野が存在するため、国際協力で研究開発を進めることにより、国際的なコンセンサスを形成するとともに、経済面等において効率化を図ることが重要である。また、核燃料リサイクルについては、先進諸国の開発成果の有効利用の観点、社会的な理解促進の観点等から、この分野において長年にわたり研究開発を進め相当な技術蓄積を有する先進諸国と協調して進めることが重要である。10.原子力開発利用の推進基盤 (1)人材の養成と確保近時の学生の理工系離れや理工系学生の製造業離れ、さらには生産年齢人口の減少といった傾向の中で、科学技術系人材の不足が懸念されており、特に原子力への関心の低下が目立つことから、安全確保の一層の向上、原子力に関連する先端的技術の開発など今後とも拡大する原子力開発利用に対応するためには、着実な人材の養成・確保が重要な課題である。 (2)資金 資金の確保については、1994年度の政府原子力関係予算は前年度比99.1%の約4,470億円、うち科学技術庁分が、前年度比約100.1%の約3,240億円、通商産業省分が前年度比96.4%の約1,180億円、その他が前年度比95.2%の約52億円であり、一方、産業界における原子力関係支出高(1992年度実績)は、電気事業で約1兆8,349億円(うち研究開発費は約480億円)、鉱工業で約2兆967億円(うち研究開発費は約770億円)などとなっている。研究開発関連資金の確保に当たっては多様な手段を用いるとともに、資金の重点的、効率的、効果的な活用を図っていくこととしている。 (3)研究開発推進体制と研究基盤の高度化 研究開発推進体制については、現在、主な政府関係研究開発機関として、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、理化学研究所の3つの特殊法人、放射線医学総合研究所、金属材料技術研究所、船舶技術研究所等の国立試験研究機関、(財)原子力発電技術機構、(財)電力中央研究所、(財)核物質管理センター及び(財)原子力環境整備センター等の公益法人があり、これらを始めとした各研究開発機関がそれぞれの適切な役割分担の下に能力や特長を十分に活用しつつ、基礎から応用段階まで計画的、総合的に研究開発を推進している。また、原子力の先端的研究開発分野を中心に、政府関係研究開発機関、民間、大学等の研究者の交流、共同研究の実施、研究用原子炉等の先端的かつ高度な研究を行うための設備・機器の共同利用等を通じた研究開発機関間の緊密な連携を図ることによって、その研究基盤を強化している。 11.我が国の原子力産業 原子力産業は、原子力機器、役務等を供給する原子力供給産業と電気事業者に分けられる。原子力供給産業には原子炉、機器等を供給する原子力機器供給産業、ウラン濃縮、燃料加工、再処理等を行う核燃料サイクル産業、保守等を行う原子力ソフト・サービス産業等があり、多種多様な企業群により構成されている。原子力産業は、総合的な装置産業という性格も有しており、原子力開発利用の進展はこれら広範な企業群を維持、活性化させることとなり、ひいては国民経済等にも好影響を及ぼすことが期待される。そうした中で、原子力供給産業は調和の取れた複合産業として、これまでの技術力・開発力を維持向上させるとともに、産業として成熟・自立していくことが望まれる。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |