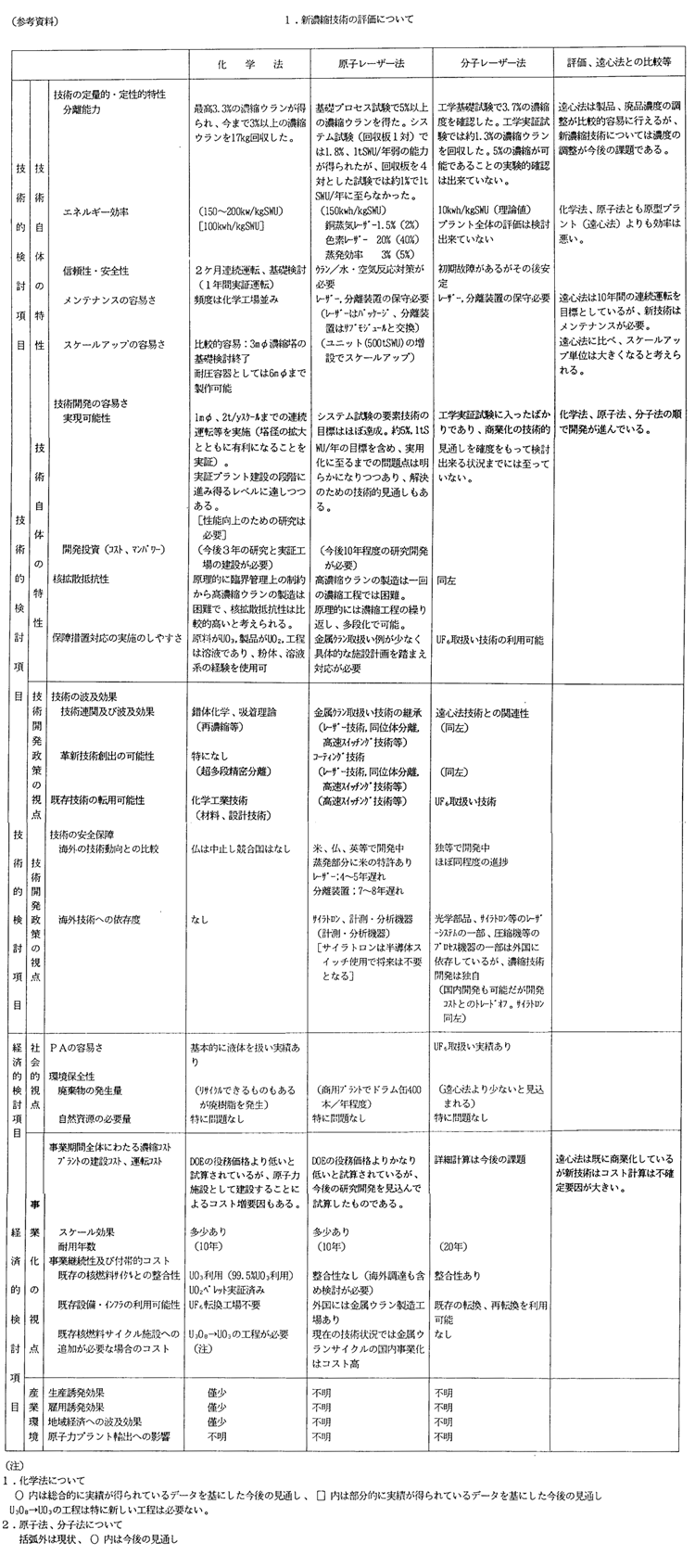| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
委員会の決定等 ウラン濃縮懇談会報告書 1992年8月11日
原子力委員会ウラン濃縮懇談会
まえがき 我が国では、濃縮ウランの安定供給を図るという見地ばかりでなく、プルトニウム利用等を含め核燃料サイクル全体の自主性を確保する観点から、経済性を考慮しつつ、国内のウラン濃縮の事業化を進めてきており、これまでの動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)を中心とする技術開発の結果、本年3月には青森県六ケ所村で日本原燃産業(株)(本年7月1日をもって日本原燃(株)に変更。以下「日本原燃」という。)の六ケ所ウラン濃縮工場(以下「六ケ所濃縮工場」という。)の操業が一部開始された。
さらに、ウラン濃縮の経済性向上を図るために、新素材高性能遠心機、原子レーザー法ウラン濃縮技術、分子レーザー法ウラン濃縮技術及び化学法ウラン濃縮技術について開発を進め、それらは一定の成果を上げつつある。
このような状況の中で、「今後のウラン濃縮技術開発に関する評価検討の進め方について」(平成3年7月30日原子力委員会決定)に基づき、当懇談会は、新技術評価検討ワーキンググループ及び遠心法検討ワーキンググループを設置し、ウラン濃縮を巡る内外の諸情勢を踏まえ、新技術の評価検討、遠心分離法技術の検討を行い、これらを踏まえた今後の濃縮技術開発のあり方及びその体制等について調査審議を行い、以下のとおりとりまとめた。
1. 国内外のウラン濃縮事業を巡る現状と将来動向 (1) 国際情勢
ア. 需給動向
経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)の統計によると、1990年におけるOECD諸国のウラン濃縮設備容量は、米国エネルギー省(DOE)が19,200tSWU/年(ガス拡散法の2工場)、ユーロディフ(フランス)が10,800tSWU/年(ガス拡散法の1工場)、ウレンコ(ドイツ、オランダ、英国)が2,600tSWU/年(遠心分離法の3工場)、日本が200tSWU/年(動燃の原型プラント)であり、合計32,800tSWU/年である。同年のOECD諸国の需要実績は23,784tSWU/年であり、世界の供給能力は需要をかなり上回っている状況にある。
また、同統計によると、ウレンコ(ウレンコと米国の電力会社等との共同出資による米国工場を含む。)及び日本の供給能力の増加に伴い、2010年においては供給能力が37,700tSWU/年に達するのに対し、需要は30,984tSWU/年にとどまり、約20年後においても依然として供給能力過剰の状況にあると予測している。
このような世界の濃縮需給の将来動向には、米国の濃縮事業公社化の将来動向が必ずしも明確ではないこと等により、少なからぬ不確定要因が残されている。しかし、欧米の濃縮事業者は既存工場について今後2010年以降まで競争力のある運転が可能と判断していると伝えられていること、さらに、近時、米・旧ソ連間で進められつつある劇的な核兵器の削減の動きに伴い、10,000tSWU/年ともいわれる旧ソ連の濃縮ウラン供給能力のかなりの部分が西側市場に提供される可能性があること等を勘案すると、今後20年間程度の世界の濃縮需給は供給能力過剰の状態で推移するものと考えられる。
イ. 技術開発の動向
欧米においては、将来のウラン濃縮事業の国際競争力の一層の向上を図ることを目標として、以下のとおり新濃縮技術の開発を進めている。
(ア) 米国
米国の濃縮事業主体でもあるエネルギー省(DOE)は、ローレンスリバモア研究所で1973年に原子レーザー法ウラン濃縮技術の研究を開始した。DOEは1985年に原子レーザー法をガス拡散法の後継技術として選定したことにより研究開発を加速させ、これまで約12億ドルを投資したといわれている。現在は、100tSWU/年規模の実証試験を実施するとともに商業化への移行のための検討が行われている。
当初、この実証試験の結果を基にした商業化移行についての決定が1992年11月に行われる予定とされていたが、この決定は1993年以降に延期されている。DOEは原子レーザー法の商業化は十分可能との判断をしているが、商業化の前提となる経済性、既存ガス拡散工場の解体・除染費負担の問題等については議会を含め、米国内に種々の議論があり、原子レーザー法の濃縮事業主体になるとされる政府公社設立については未だ計画が明確になっていない。
このようなことから米国における原子レーザー法による濃縮事業の商業化についてはその時期等が不確定な状況にある。
(イ) フランス
フランスでは1980年代前半からいくつかの新濃縮技術の開発を行ってきたが、1985年からはそれらの中から原子レーザー法を選定し、原子力庁(CEA)で研究開発を行っており、現在、基礎試験及びパイロット機による研究開発が実施されている。今後は1990年代半ばにその後の開発の進め方を評価し、商業プラントに向けての研究開発投資の是非が決定されるとしている。実際の商業プラントの建設は市場動向等の要因に左右される見込みであるが、順調に計画が進展すれば、最初の商業プラントの導入時期は2005年頃、競争力のある商業プラントの運転は2010年以降とも伝えられている。
(ウ) 英国、ドイツ(ウレンコ関係国)
英国では1974年から原子レーザー法及び分子レーザー法ウラン濃縮技術について英国原子力公社(UKAEA)で研究が開始されたが、1983年に分子レーザー法の研究が中止され、現在、UKAEA及び英国原子燃料公社(BNFL)が協力し、原子レーザー法の研究開発を実施している。これらの研究開発の成果は未だ基礎的段階にあるといわれている。また、ドイツではウレンコの構成員であるウラニット社が中心となり、約20年間にわたり分子レーザー法の研究開発を実施してきている。
遠心分離法(以下「遠心法」という。)技術は、既にウレンコの濃縮工場に採用されているが、1989年の同社の発表等によると同社は1972年のパイロットプラント機、1976年の実証プラント機を始め、遠心法技術の改良、性能向上のための研究開発を進めており、稼働中のプラントには商業プラント導入機(第一世代)から数えて第二世代、第三世代及び新鋭の第四世代の遠心機が導入されている。現在、第五世代の遠心機を開発しており、その開発が成功すれば、分離能力は1976年に開発された実証プラントの約12倍、コストも約1/5になるといわれている。
ウレンコは、遠心法による濃縮事業が今後2010年以降も国際競争力を持ち得ると判断しているといわれているが、1992年末に、以上の濃縮技術開発の成果について評価し、将来取り組むべき技術開発の方向を見極めることとしている。
(2) 国内情勢
ア. 需給動向
原子力開発利用長期計画(昭和62年6月決定)では、2000年における原子力発電設備容量を少なくとも5,300万kw程度と見込み、これを前提とする我が国のウラン濃縮の年間所要量は少なくとも7,000tSWU程度と見込み、併せて我が国における濃縮事業確立の目標を2000年過ぎに年間3,000tSWU程度の規模としている。
しかしながら、現時点で2000年及び2010年の原子力発電設備容量の目標は5,050万kw及び7,250万kw(石油代替エネルギーの供給目標について、平成2年10月閣議決定)であり、これを前提とすると、ウラン価格の変動による濃縮時の劣化ウラン濃度の仕様の変更、プルサーマルの導入による濃縮ウランの節減等により、2000年での濃縮役務所要量は6,000tSWU/年程度、2010年では8,000tSWU/年弱と見積もられる。
このような我が国の需要量はOECD諸国の需要量の約1/4を占めているにもかかわらず、現在のところ国内供給力はほとんどないという状況にあるが、2000年には六ケ所濃縮工場による1,500tSWU/年の国内供給力を有することになる。
この国内供給力と電気事業者による海外との契約により2000年頃までの供給は確保されることとなる。
イ. 六ケ所濃縮工場の進捗状況及び遠心法技術開発の動向
動燃がパイロットプラント及び原型プラントの建設、運転等を通じ開発してきた遠心法技術が日本原燃に移転され、同社は、昭和63年10月に六ケ所濃縮工場の建設を開始し、本年3月末、150tSWU/年の規模で同工場の操業を開始したところである。六ケ所濃縮工場は、今後、毎年150t/SWU/年の規模で増設され、2000年には1,500tSWU/年の規模に拡大される予定である。
六ケ所濃縮工場に導入されつつある遠心機は金属胴遠心機であるが、現在、同遠心機に比べ大幅な性能向上が期待される新素材高性能遠心機について、動燃、日本原燃及び電気事業者が協力し、研究開発を進めており、また、これらの機関及びメーカにより製造技術の開発が国の補助も得て進められてきている。
この新素材高性能遠心機については、動燃のパイロットプラントを活用し、平成4年度末から約3年間、遠心機1,000台程度からなる実用規模カスケード試験が実施されることが計画されており、その成果を踏まえ、新素材高性能遠心機が六ケ所濃縮工場に導入されることとなっている。従って、この研究開発が順調に進展すれば、六ケ所濃縮工場の当初の1,050tSWU/年分は金属胴遠心機となるのに対し、残りの450tSWU/年分、さらには当初導入の金属胴遠心機の取替機分は新素材高性能遠心機が導入されることとなる。
ウ. 新技術開発の動向
(ア) 原子レーザー法
原子レーザー法ウラン濃縮技術については、日本原子力研究所(以下「原研」という。)が昭和51年から原理実証試験を開始し、昭和59年からは基礎工学試験として小型分離機器の試作を行ってきた。昭和62年からは原研では長期的・基盤的な基礎プロセス試験を、レーザー濃縮技術研究組合では国の補助を受けて、1tSWU/年規模のシステム試験を、相互に補完させつつ実施してきている。
これまでの研究開発では、基礎プロセス試験の過程で5%以上の濃縮ウランが回収されるなどの成果が得られ、また、システム試験での要素技術の開発についても概ね順調に進展しているが、システム試験装置全体での濃縮試験の結果は昭和61年に本懇談会が設定した技術水準目標(年間tSWU相当の約5%の濃縮)に到達していない。技術開発状況は、フランスとはさほど遜色のない開発状況にあるが、米国に比べれば約5年程度の遅れがあるとみられる。
(イ) 分子レーザー法
分子レーザー法ウラン濃縮技術については、理化学研究所(以下「理研」という。)が昭和51年にレーザー科学研究グループを設置し、レーザー技術について学際的な研究をスタートし、この中で分子法に関連した研究成果を得た。理研では昭和60年からは分子法原理実証試験を開始し、その成果を踏まえ、昭和63年度からは、動燃で機器開発及びその後の濃縮試験を目的とした工学実証試験を、理研では動燃の工学実証試験を支援するための工学基礎試験を実施している。
これまでの研究開発では、工学基礎試験の過程で約3.7%の濃縮ウランが分離されるなどの成果が得られたが、昭和61年に本懇談会が設定した技術水準目標(原理的に5%の濃縮が可能であることの確認)には到達しておらず、また、工学実証試験では機器開発は概ね順調に進展しているが、濃縮試験は濃縮度等の面で十分な成果が得られていない。
(ウ) 化学法
化学法ウラン濃縮技術については、昭和47年から旭化成工業(株)において研究が開始され、昭和55年度からは国の補助を受け、試験研究、モデルプラントの開発が行われた。同社では昨年7月、モデルプラントでの開発は全て終了したとし、現在は研究開発活動を休止しており、今後の国内需給動向等を踏まえ、将来の活動を検討するとしている。
これまでの研究開発では3%以上の濃縮ウランを回収するなどの成果が得られている。
2. 今後の国内ウラン濃縮事業化推進に当たっての基本的考え方 ウラン濃縮を巡る国内外の状況は1.に述べたところであり、全体としては当面、供給能力過剰の状況が続き、我が国が海外から濃縮役務調達を行うことは比較的容易な環境にあると見られるが、このような状況の中で今後の国内ウラン濃縮事業化推進に当たっての基本的考え方を改めて整理し、将来の方向付けをしておくことが重要であると考えられる。
我が国が自主的核燃料サイクルの確立の一環として、国内でのウラン濃縮事業化を推進してきたのは、濃縮役務を全て海外に依存することに伴い、プルトニウムを含む核燃料リサイクル計画の推進に役務提供国から予期せぬ制約がかかることを出来るだけ避け、併せて自らの技術により、濃縮ウランの一層の安定供給を実現することを目的としたからである。換言すれば、国内濃縮事業化推進の意義は、核燃料サイクル全体の自主性の確保を図り、それによって原子力を長期的に安定なエネルギー源とし、エネルギーセキュリティを高めるということに要約される。さらに、ウラン濃縮の事業化は、関連する技術開発及びその実用化が他の科学技術、産業技術の発展に貢献するという波及効果も期待されてきたところである。
かかる観点からは、一定の国内供給力及び技術力を保育するという我が国の濃縮路線の意義には基本的にはいささかの変化もないと考えられる。
しかしながら、今後、世界の濃縮事業者間の需要獲得競争の激化が予想され、各事業者は濃縮役務の経済性の向上に一段と努力を傾注していくものと見られる中で、国内濃縮事業化を的確に進めていくためには、我が国の国内濃縮事業も国際的に遜色のないレベルの役務価格の提供を目指して、不断の努力を重ねていく必要がある。
このため、我が国初の商業工場となった六ケ所濃縮工場については、第一により安定した操業を図ることが重要であるが、事業化を進めてきた間の大幅な為替変動等により、当初期待した海外の濃縮役務価格に対する相対的経済性が達成されたとは言えない状況にあるため、中長期的観点からも同工場の経済性の向上に従来以上に積極的に取り組むことが不可欠である。また、高い経済性実現の潜在的可能性をもつ新濃縮技術の開発は我が国のエネルギーセキュリティをより確かなものとするためにも重要である。一方、濃縮技術は原子核科学技術にとっても、同位体元素の特性研究、同位体の利用技術の研究等を行うための中心となる技術であり、ウランのみに限らず、各種の同位体分離にも利用される可能性を考慮することが重要であり、これらの観点にも配慮しつつ研究開発がなされることが期待され、さらに、新濃縮技術の開発による波及効果が他の科学技術分野のブレークスルーや産業の高度化をもたらす可能性が大きいことに留意する必要がある。
また、六ケ所濃縮工場以降の我が国の国内濃縮規模の拡大及びその時期については、海外の供給源の多角化による供給安定性の確保の状況、六ケ所濃縮工場による経済性の達成度、新濃縮技術の実用化見通し等を総合的に勘案し、また、国際情勢の変化に柔軟に対応できるよう、判断していくことが適当である。
3. 遠心法技術の研究開発のあり方 (1) 研究開発目標
六ケ所濃縮工場については、2.に述べたとおり、中長期的にもその経済性を一層高めることが極めて重要な課題であり、遠心機の単機性能の飛躍的向上及びその製造コストの低減化が必要である。
このためには、先ず、現在進められている新素材高性能遠心機の開発を円滑に推進し、同遠心機の六ケ所濃縮工場への導入を図っていくことが必要である。また、この開発を行うことはその後の遠心機の性能向上を実現する上でも不可欠である。
他方、事業化を進めてきた間の大幅な為替変動等により、この開発だけではそれ以前に期待していたほどの経済性の達成が困難になったこと、既に世界市場に進出している同じ遠心法技術を採用したウレンコが現在も新しい遠心機の研究、開発及び導入に精力的に取り組んでいること等に照らし、我が国においても新素材高性能遠心機をさらに高度化した遠心機の開発、導入を図ることが必要である。
新素材高性能遠心機の次世代機となる高度化機が実現出来れば、単位分離性能当たりの一層のコスト低減を図ることが可能と考えられる。具体的には、現在開発中の新素材高性能遠心機胴の構造を単純化、長胴化し、同時に回転胴の周速を上げ、性能向上を図ることにより、新素材高性能遠心機の約1.5〜2倍の分離能力を有する高度化機の開発を含め検討していくことが適当である。
既に動燃及び民間による基礎的な試験において、このような単純構造の回転胴の回転性能は一応安定していることは確認されており、実現の可能性がある。また、これまでの開発によって得られた知見及び新素材高性能遠心機の今後の研究開発成果を効果的に利用することにより、従来のような多数の遠心機によるカスケード試験が不要と考えられるなど、開発コストの低減化も期待出来る。
さらに、構造の単純化により回転胴の製造コストの大幅な低減が期待されるなどにより、六ケ所濃縮工場の遠心機の取替機として相当の役務価格低減を実現することが期待出来る。
ただし、このような高度化機は、新素材の特長を十分に生かした、回転特性上画期的な構造を持つものであり、回転胴の周速が上昇することに伴う材料特性の確認、安定した製品抜き出し機構の開発等新たに克服すべき技術開発課題が少なからずあり、効率的、効果的な研究開発を進めていくことが必要である。
(2) 高度化機開発の進め方
ア. 開発計画及びスケジュール
六ケ所濃縮工場の経済性の向上を着実に、かつ、出来るだけ速やかに実現していくためには、新素材高性能遠心機の開発計画をも考慮しつつ、高度化機は遅くとも平成15年度の同工場への導入に向けての計画を検討する必要がある。
高度化機の開発に当たっては、可能な限り従来の経験と知見を活用し、研究開発の効率化を図ることが望ましいが、その場合であっても、高度化機の設計解析、各要素技術の開発、単機の開発、信頼性の確認等最小限の開発工程は必要と考えられる。
単機開発は、高度化機数機によって安定性能を実現するとともに、高度化機10台程度の小規模カスケードによる回転特性や流動分離特性のばらつきの確認までを行う必要がある。なお、この単機開発の当初においては、複数のモデルを試作、試験し、技術的、経済的により見通しのある目標仕様を決定するという方法が有意義であると考えられる。
信頼性試験は、新素材高性能遠心機開発の場合は遠心機約1,000台からなる規模のカスケードによる試験であるが、高度化機の場合は、新素材高性能遠心機の成果を効果的に活用すれば、大幅に少ない遠心機台数でのカスケードによる試験でも十分な成果が得られる可能性があり、この点について今後更に検討する必要がある。
イ. 研究開発体制
現在の新素材高性能遠心機の開発過程全体は、動燃、日本原燃及び電気事業者の共同研究という形で進められている。高度化機に求められる諸性能の厳しさ、それを支える新たな研究開発要素等を勘案すると、高度化機の開発の効率性、確実性を確保するためには、動燃に蓄積されてきた遠心機技術開発の能力を活用することが不可欠と考えられる。
従って、高度化機の単機開発の終了までは新素材高性能遠心機開発の場合と同様に、動燃が日本原燃を支援する研究開発体制をとることが適当である。この際、日本原燃は国内濃縮事業者として、今後、自らの研究開発能力を高めていく必要があることからも、主体的な取り組みを行うことが適当である。単機開発後の信頼性確認試験、寿命試験その他関連する試験研究については、六ケ所濃縮工場への導入を図るための最終的な試験でもあり、日本原燃が所要の試験研究設備等を整備し、自ら実施することが重要である。さらに、これらの開発過程全体にわたり、電気事業者、メーカも今までと同様に協力することが期待される。
(3) 基礎的・基盤的な研究開発等の進め方
これまで動燃においては、将来の遠心機技術の
開発に必要な基礎的データ、情報の蓄積のため、基礎的・基盤的な研究開発、先導的な研究開発、国として必要な安全性の研究等を進めてきた。これらの研究開発については、引き続き動燃において、軸受け材料等の物性研究、流体工学研究、遠心胴に関する構造力学研究等を着実に進めていくことが重要である。
この際、高度化機開発をより効果的にするためには、これらの研究開発の成果が、逐次高度化機開発に反映されることが重要である。なお、将来の高度化機以降の更に超高性能の遠心機の開発導入の是非に係る判断に当たっては、この動燃での研究開発の成果が考慮されることが重要である。
(4) 関連技術開発
再処理により回収されるウランについては、再濃縮によるリサイクル利用が最も適当と考えられるため、民間関係者と動燃の協力により原型プラントを利用して実用規模による再濃縮計画を進めていくなど、将来の本格利用に備えることが適当である。
また、遠心機の取替え等に伴い、機微技術の拡散につながる恐れがなく遠心機を処理出来る技術の開発を動燃において行っているが、これを着実に進めていくことが重要である。
4. 新濃縮技術の評価検討 (1) 原子レーザー法
ア. 技術面
原研による基礎プロセス試験及びレーザー濃縮技術研究組合によるシステム試験は相互補完的に良好な関係を保ちつつ、概ね順調に研究が進められてきている。基礎プロセス試験においては、5%以上の濃縮ウランが得られており、システム試験では、色素レーザー、分離セル等の要素技術の開発目標は概ね達成され、また、銅蒸気レーザーの高出力化等、商業機目標への手がかりが得られたものもある。ただし、商業機の開発のためには、レーザー出力、レーザー効率、電子ビーム出力等の要素技術の目標性能が長期間安定的に維持される必要があるが、これらの性能達成の面では不十分である。
年間tSWU相当の約5%の濃縮という技術水準目標については、現在レーザー濃縮技術研究組合が設置しているレーザー装置で得られる繰り返し数では困難であることなどから達成されておらず、1tSWU/年の能力を得るためには電源容量を増やさなければならないこと、5%を達成するためにはレーザー装置を多重化しなければならないことが判明した。
また、金属ウランの蒸発効率の向上、電離効率を含めた光利用率の向上等の濃縮コスト低減への影響が大であると考えられる技術の開発、製品及び劣化ウランの連続回収技術の開発も残されており、原料の転換、製品の再転換技術についての検討も更に必要である。
我が国の原子レーザー法技術開発の進捗状況は、フランスに比べ同程度、米国に比べレーザーで約4〜5年、分離装置で約7〜8年の遅れがあると推定される。
イ. 経済性
開発当事者の試算では、金属ウランの転換、再転換に係るコストを除けば、現在期待している商業機の技術目標が達成された場合には、現在のDOEによる濃縮役務価格に比べかなり低コストになるとしている。
なお、原子レーザー法の事業化には金属ウランの転換、再転換の事業化も併せて行う必要がある。現在の技術状況において国内事業化を行えば六フッ化ウランの転換及び再転換よりコストが高くなると推定される。
ウ. 評価
個々の要素技術についての技術目標への達成状況は概ね良好であり、また、濃縮役務価格の大幅低減化への潜在的可能性は高いものと考えられる。
しかし、開発当事者による原子レーザー法の経済性の試算については、今後の技術開発目標の達成を加味した場合のものであり、その前提となる技術開発の状況は、要素技術の面で商業機目標への手がかりが得られたものもあるが、実現への確度ある見通しが得られていない要素技術が残されており、また、システム性能の開発目標は達成されていない。
従って、実用化に至るまでの工学的問題点は明らかにされたものの、商業化判断を行うには、時期尚早であり、将来、安定化した生産プロセス実現の技術的実証が行われ、期待される役務価格の低減化の確たる経済的評価がなされるとともに、内外のウラン濃縮事業化に係る諸情勢等も考慮した評価検討が必要と考えられる。
当面の課題としては、生産プロセス実現の技術実証を行う前に、現在のシステム試験の施設を活用し(改造を含む。)、所要の機器の整備を進め、銅蒸気レーザー及び色素レーザーの高出力化・長寿命化、製品・廃品回収プロセスの確立等、更に確たる見通しを得るべき要素技術を開発していくとともに、プラント設計技術を確立することが必要である。
また、光電離率、光利用率、蒸発効率等を上昇させれば、経済性が大幅に改善され、プラント構成機器の仕様、コスト等の負担が軽減できるため、今後とも基礎的な試験を行い、その成果をシステム試験に活用していくことが不可欠である。
さらに、金属ウランの転換及び再転換技術、原子レーザー法による回収ウランの再濃縮の有利性について検討を進めることも重要である。
(2) 分子レーザー法
ア. 技術面
理研による工学基礎試験及び動燃による工学実証試験においては相互の能力が効果的に発揮され、概ね順調に研究が進められている。理研においては、約3.7%の濃縮ウランが分離され、また、他の技術よりもエネルギー効率が高いことが推定されている。動燃において実施された工学実証試験では、比較的短期間で分離能力の向上が図られている。
原理的に5%の濃縮が可能であることの確認という技術水準目標については、実験的確認はなされていないが、分離を2段以上とすることで可能と推定される。また、動燃での試験では、分離係数及び製品生産量が目標値より小さいため、今後分離プロセスの最適化、ノズルの改良等が必要なこと等から、商業プラント機の技術的見通しを確度をもって検討出来る状況までには至っていない。
イ. 経済性
現在技術的に商業化の見通しを得られる状況にないため、経済性について論じられる段階にない。
なお、分子レーザー法は、工学実証試験においては六フッ化ウラン取扱い技術を始め、遠心法技術の応用が図られ、また、六フッ化ウランを取り扱うため既存の転換、再転換の工程を利用出来るとの技術的特長を有しており、付帯的なコストは低いものと推定される。
ウ. 評価
現在までの研究開発は工学実証試験に入ったばかりの段階であり、濃縮ウランの回収も期待された成果が得られておらず、商業プラントの具体的設計が出来るだけの技術的蓄積はない。
しかし、分離エネルギー、既存核燃料サイクル施設との整合性等の面で潜在的には優れた可能性があるため、今後も基礎的な研究成果、工学実証試験の施設等を活用し、所要の機器の整備を進め、スペクトルの精密測定、分離プロセスの最適化、炭酸ガスレーザーシステムの長寿命化、ラマンレーザーの高繰り返し化・高効率化、ノズル型反応装置の最適化、製品等の捕集技術、光学素子や光結合技術の改良等の研究開発を行うことが必要である。
また、ラマンレーザー及び炭酸ガスレーザーシステムの抜本的改良、反応機構の解明及び制御等、性能の画期的進展が期待されるブレークスルーを目指した研究開発を行うことも分子レーザー法の可能性を見極める上で極めて有意義である。
さらに、原子レーザー法と同様に、回収ウランの再濃縮の有利性について検討を行うことが重要である。
(3) 化学法
ア. 技術面
システムの簡素化等を図ったスーパー法プロセスの開発、高耐久性・高吸着性吸着体の開発等を踏まえ、モデルプラントにより、3%濃縮ウランのkgオーダーでの取得、長期安定運転の可能性等を実証し、モデルプラントでの研究開発事項はほぼ終了している。なお、濃縮プロセスで得られたウランによる燃料ペレットの品質が良好であることも確認されている。
今後、商業化を図るためには工業化実証のための実証プラントの建設を行い、長期連続運転の実証、工業化機器の開発を進めることが必要となる。さらに、この実証プラントに濃縮塔、還元塔等の追加を行えば商業プラントとして使用可能となる。
イ. 経済性
技術的には成熟しているため、今後の研究開発により大幅なコストダウンは見込めないものの、プラント規模によりコスト低減を図ることが出来る。開発当事者の試算では現在のDOEのウラン濃縮役務価格に比べて低コスト化が可能としているが、プラントとしては原子力施設としての事例がないため、開発当事者の試算値に追加的なコスト上昇要因があると考えられる。
ウ. 評価
化学法による濃縮は、以前は3%程度の濃縮に数年かかるといわれていたが、旭化成(株)はこれを数カ月で達成するなど十分な成果を得ており、技術自体については、今後の事業化に向けてブレークスルーを要するような技術開発課題は認められない。また、実証プラントを建設した場合は、濃縮塔等を追加することにより1,500tSWU/年程度の商業プラント規模までは比較的容易に拡充出来るものと判断される。
(4) 新技術開発の波及効果
原子レーザー法は、分離セル技術を中心とする電子ビーム技術、高温材料技術等について、高融点金属の単結晶化、金属部材の薄膜コーティング化、真空機器への技術波及が考えられる。
また、分子レーザー法は、ノズル設計技術、高速流体取扱い技術等について、粉体捕集、高速機械の設計等への技術波及が考えられる。
さらに、原子レーザー法及び分子レーザー法いずれのレーザー法も同位体分離、元素分離、分析・計測、加工等への技術波及が考えられる。
化学法は耐放射線樹脂、精密多段分離等の技術で原子力分野への応用が考えられる。
5. まとめ…長期的なウラン濃縮の進め方 遠心法技術については、六ケ所濃縮工場の安全確保に万全を期し、安定した操業を図るとともに、経済性の向上を図るための着実な努力を重ねることが不可欠であり、財政事情を考慮しつつ、3.で示した研究開発の計画的な推進が図られるべきである。
原子レーザー法及び分子レーザー法については、欧米でも研究開発が進められてきているが、濃縮ウラン需給の供給能力過剰傾向、既存工場の今後の供給能力等に鑑み、これらの研究開発は一時に比べれば時間をかけて着実に進めていくとの傾向が見られる。我が国においてもこれら新技術によるウラン濃縮の経済性向上の潜在的可能性は遠心法技術よりも高いものの、その有利性は遠心法技術の経済性の向上の進展状況、国内需給の動向等の周辺事情に影響を受ける側面がある。このため、これまでの研究開発の状況も含めて判断すると、今後の研究開発は段階的に進めていくことが現実的であり、その都度、これらの周辺事情を踏まえ開発成果の評価検討を行い、開発継続の是非を判断することが適当である。
原子レーザー法については、これまでの研究開発の成果で実用化に至るまでの技術的問題点が明らかとなりつつあり、また、海外での開発状況も勘案すると、これらの問題点を解決するための技術的見通しもある。このため、原研は光電離率の向上等のための基礎的研究開発を行い、この成果も利用しつつレーザー濃縮技術研究組合は、現在保有するシステム試験施設を活用し、システムの最適化を目指した要素技術等の開発を官民の協力体制のもと、着実に進めることが必要である。これによって、平成10年頃には生産プロセス実現の技術実証、すなわち、試験機による開発成果の実証の段階に進むべきか否かの判断が可能となると期待される。従って、この実証段階に進むべきか否かの評価検討をこの時期に実施することが適当である。
分子レーザー法については、未だ工学実証試験に入ったばかりであり、動燃及び理研の研究協力関係を維持しつつ、技術の可能性を見極めるために、理研はブレークスルー研究を、動燃は工学実証試験施設等を活用し、工学試験を継続し、原子レーザー法に係る評価検討の時期にそれまでの成果を評価検討することが適当である。なお、原子レーザー法、分子レーザー法については相互に関連する事項もあるため、関係機関の情報交換に努めることが望ましい。
化学法については、既に技術的観点からは商業化を目指した実証プラントの建設の段階に進み得るレベルに達しつつあるが、一方、現時点で実証プラントを建設するとの決定を行うことは、事業化判断を行うに等しい意味を持つものと考えられ、そのような決定は、今後の国内外のウラン濃縮需給の動向、国内外のウラン濃縮事業の経済的見通し、今後更に必要となる技術開発投資・期間等を総合的に判断して行われることが適当と考えられる。
六ケ所濃縮工場以降の国内濃縮事業規模の拡大及びその時期についての基本的考え方は既に2.において示したとおりであり、2000年以降の国内需要に応える方策の一環として、今後、この点についての検討を進めていくことが必要である。
|
|
1. 新濃縮技術の評価について |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |