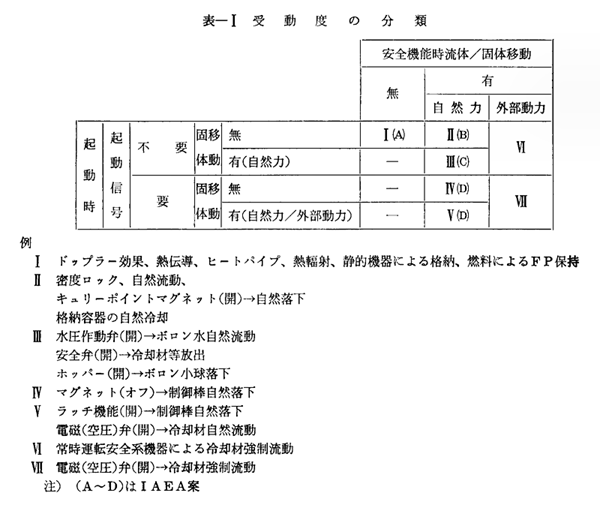| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
受動的安全システムに関する調査報告(概要) 本研究調査は、将来の新しい原子炉の設計思想の中で重要な役割を果たすものと考えられる受動的安全システムについて、その特性や、炉への導入に関する課題等について検討したものである。
本報告書は、第一部「受動的安全システムに関する整理」と、第二部「炉型別受動的安全システム」より構成されている。
第一部においては、受動的安全システムに関する整理を行うため、「受動度」という概念の導入が行われた。受動的安全性の定義には種々の考え方があるが、典型的な定義としては、「システムの安全機能が、外部からのエネルギーあるいは信号、操作なしにそれ自体の有するメカニズムによって確保されること」ということができよう。この場合のメカニズムとは、そのシステムに含有される物質およびその物理化学的性質や内部に含まれるエネルギーの他、そのシステムに作用する自然法則(重力、熱伝導、熱輻射)等も含むものとする。また、内部エネルギーに化学ポテンシャルも含むものとすれば、蓄電池による動力源も含まれることとなる。
受動的安全性について以上のように定義するのは一応妥当であるにしても、個々の安全機能を具体的に見てゆくと、上記の定義だけでは、その安全機能が受動的か能動的かを区別できたい場合が多い。従って、本調査では受動性を分類して、「受動度」という概念の導入を行った。
また、一般に異常発生とそれに伴う安全保護動作を考えると、まず正常な運転状態があり、何らかの異常の発生に伴って工学的安全施設等が起動され、その後異常状態の継続中、その安全機能が維持されねばならない。このように、工学的安全施設等においては、一般的に一連の安全動作が、起動と安全機能に分割される。起動については、とくに起動信号を要しないほうが受動的であり、また、何ら固体要素の移動がなく起動が行われる方が受動度が高いと考えられる。信号を要しない弁の開閉(安全弁、水圧作動弁)がそれに続くであろう。安全機能の継続状態については、何ら物資の移動を要しないドップラー効果や、熱輻射等が最も受動度が高いといえよう。次に重力や密度差による流体の流動、固体の落下という順になろう。
以上を取りまとめたものが表Ⅰである。表Ⅰでは、受動度が最も「受動的」と考えられるⅠから「能動的」と考えられるⅦに分類されている。勿論、これらは一義的分類ではないが、個々の受動的学全システムが、如何なる受動性の設計思想に基づいているか、どの程度受動的であるかを整理するうえで有効であろう。
なお、「受動度」が高いということは、必ずしも信頼性が高くかつ安全性に優れているということを意味するものではない。しかし、受動的安全性の中に、システムの簡素化並びに高信頼性を暗黙のうちに期待しているといえよう。
更に、第一部では、受動的安全システムに関連する以下の諸項目、すなわち「受動的安全システム」と固有の安全性、Walk away time(Grace period)、シリーズシステムの受動度、構造健全性、設計における受動性と能動性の採用、についての検討結果が述べられている。
第二部においては、炉型別に受動的安全システムについての研究調査が行われた。
対象となった炉型は以下のとおりである。
高速増殖炉、SPWR(System Integrated PWR)、改良型船舶用炉(MRX/DRX)、HTGR(モジュラー型)、超小型高速炉、PIUS、ISER、HSBWR、MSPWR、AP-600、SBWR
これらの炉型別に、1.受動的安全システムの機能別分類、2.信頼性に関する検討、3.炉への適用の可能性、4.その他の検討課題、についての研究調査結果が記述されている。以下、横断的にそれらの概要を記述する。
1. 機能別分類としては、原子炉停止、崩壊熱除去、放射性物質の放散防止の機能に分類して、研究調査が行われた。
2. 信頼性に関する検討としては、信頼性についての実証、信頼性の阻害要因、信頼性確保のための対策が研究調査された。
3. 炉への適用の可能性については、炉出力、炉のサイズ等との関連について検討が行われた。
4. その他の検討課題としては、受動的安全システムの導入に伴う諸問題、能動的システムとの組合せ等について、研究調査が行われた。
上述の諸事項に関する調査・研究の結果の概要を、今後の課題をも含めて、以下に記述する。
1. 機能別に分類した場合の代表例 原子炉停止
負の反応度フィードバックを大きくするような設計
SASS(Self Actuated Shutdown System)
GEM(Gas Expansion Module)
密度差ロックや水圧作動弁とボロン水自然流動
崩壊熱除去
炉心の冷却材による冠水
冷却材の自然循環の効果的利用
自然通風による熱除去
ヒートパイプを用いる冷却系
重力落下式非常用炉心冷却系
放射性物質の放散防止
燃料、被覆、冷却材、冷却材バウンダリー、格納容器バウンダリー(受動的格納容器冷却系付き)
2. 信頼性に関する検討 信頼性に関しては、すでに実験的に実証されているものもある。しかし、解析的な検証にとどまっているものが多い。従って、今後、更に実証試験を行っていく必要があろう。また、受動的安全システムを構成する諸要素(弁など)の性能の信頼性、構造健全性がシステム全体の信頼性にとって重要である。
3. 炉への適用の可能性 受動的安全システムの原子炉への適用は、中小型炉の場合の方が、大型炉の場合より、一般的に、より容易であると考えられるが、一方、炉出力の大きさに関係なく、炉に適用できるものもある。更に、今後の研究開発(例えば、新しい材料の使用や新しい発想)により、出力やサイズの大きな炉への適用の可能性を追求することが望まれる。
4. その他の検討課題 受動的安全システムは、基本的には自然現象に依存する点で、多くの利点を有する。しかし、現象によっては、その作動力は弱く、また、緩慢なものもある。なお、運転員が制御できないことが、受動的安全システムの欠点となる可能性もある。このようなことを考えると、能動的システムと受動的システムとの最適な組合せを検討することが必要と思われる。
なお、受動的安全システムの導入による設計の簡素化の経済性向上への効果、その導入に伴う具体的な安全設計や安全評価についての新しい考え方、その導入の立地上の諸問題の解決への貢献等についての検討も重要な課題と考えられる。
以上
表-Ⅰ 受動度の分類 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |