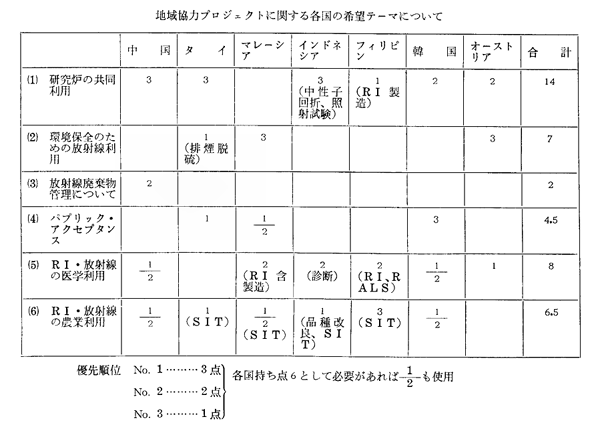| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
平成2年度地域協力構想調査(概要) Ⅰ.近隣アジア諸国からの提案を中心に(調査の概要) 1. 調査の方法 日本原子力産業会議国際協力センターは、平成2年度においては、昨年度までの「地域協力構想調査」の結果を踏まえて、以下の方法により調査・検討を実施した。
イ) 「地域協力構想調査委員会」委員会を設置して、地域協力プロジェクトについて協力関係国の現状を調査するとともに、協力実現性を検討する。
ロ) 上記に基づき、関係機関、および専門家の協力を得て、地域協力関係国の研究開発の現状調査、および地域協力プロジェクト選定等のため現地調査を実施する。
ハ) 第2回アジア地域原子力協力国際会議に参加する各国の政府高官、研究者、専門家等との意見交換を通じ、地域協力プロジェクト実現の可能性について調査する。
ニ) その他、地域協力構想の具体化のため、幅広い調査・検討を行う。
2. 調査結果の要約 地域協力構想調査委員会における調査検討の結果、平成2年度における地域協力構想調査で取り上げる協力テーマは、①研究炉の共同利用、②RI・放射線の医学利用、③RI・放射線の農業利用、④パブリック・アクセプタンス、⑤放射性廃棄物管理、⑥環境保全のための放射線利用技術の6つが選定された。
選定された主な理由は、平成2年3月に開催された第1回アジア地域原子力協力国際会議において日本からケース・スタディとして提案した①研究炉の共同利用、②不妊虫放飼法による害虫駆除計画、③子宮癌の放射線治療センターの設置の3つのテーマについては多くの国からこれを支持する旨の意志表示がなされたため、引き続き、関係各国の専門家等による意見交換、ならびに協力具体化の検討を行うことになった。
また、パブリック・アクセプタンスの問題と放射性廃棄物管理の問題については、本年度の調査を実施している段階で、いくつかの関係国から地域協力の共通課題として取り上げるよう提案があったものである。調査の段階で関係各国が表明した地域協力のテーマに関する、優先順位は別表の通りである。
環境保全のための放射線利用技術については、世界的に地球環境問題が取りざたされているおり、日本からも原子力分野において、貢献できる技術を広く関係各国に紹介して、互いに技術レベルの向上をはかろうということで提案したところ、関係各国からもこれを支持する旨の意志表示があったため、選定した。
調査の進め方については、関係資料、文献等による調査、および現地調査の他、主として平成3年3月に開催された第2回アジア地域原子力協力国際会議に参加のため来日した各国関係者、専門家等との意見交換を通じて、各国原子力事情の把握、地域協力実現の可能性について調査を実施した。
地域協力構想を進める上で、基本的な考え方として以下の項目が確認された。
・地域協力対象国は前年度調査時の国に新たにオーストラリアを加え、中国、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、インドネシア、オーストラリアの7か国とする。
・本地域協力構想は日本が既に実施している2国間協力、もしくは国際原子力機関において実施されているRCAの協力活動のような多国間協力を阻害するものではなく、これらを相互に補完するものとなること。
・第2回アジア地域原子力協力国際会議における各国関係者、専門家等との意見交換を通じ、前年度に日本から提案した3つのケース・スタディに加え、各国から様々な提案がなされ、近隣アジア諸国における地域協力にふさわしい共通の関心事および課題がより明確となり、①研究炉の共同利用、②放射線の医学利用、③放射線の農業利用、④パブリック・アクセプタンス(放射性廃棄物管理、環境保全のための放射線利用技術を含む)の4つのテーマについて、次回のアジア地域原子力協力国際会議までに各国の専門家が集まり、より具体的な協力計画を策定する。
・今後の地域協力構想の進め方については、平成3年度に予定される上記の各専門家会合の場において、関係国の主体性に基づく地域協力計画を策定し、関係国の代表者が一堂に会する次回の第3回アジア地域原子力協力国際会議に報告し、地域協力計画の方針を決める。
・これら一連の活動を通じ、地域内に協力分野別に地域協力のための、ネットワークを構築するとともに、将来、協力活動を通じ地域全体の原子力技術のレベルアップをはかる事を最終的な目標とする。
以上の基本的な考え方のもとに専門家グループによる,地域協力構想調査を実施した結果の要約について以下に述べる。
(1) 研究炉の共同利用
アジア地域各国では原子力平和利用のために研究用原子炉を導入し、原子力に関する研究開発を進めている。しかし、東南アジア諸国においては、1~3MW級の研究炉が利用されてきているにすぎず、大出力の研究炉の利用については、唯一インドネシアが試験運転中の多目的原子炉、MPR-30がそのような可能性を有する研究炉である。
今回の現地調査、各国専門家との意見交換を通じ、このMPR-30を中心に地域協力を進めていく事が合意されたため、MPR-30の各種施設を利用しての訓練、研究の可能性について、調査・検討を行った結果、適当なテーマと考えられるものは以下の通りである。
・中性子放射化分析による地域環境調査……元素分析、汚染物質測定、動植物生態調査等
・中性子回折による材料物質の組織、残留応力、破壊現象等の研究
・中性子ラジオグラフィによる非破壊検査、材料照射効果研究等
・ラジオアイソトープの生産と利用・配布の方法と機構
・原子炉運転・維持管理・利用技術の経験の交流、統一した技術基準の訓練と技術認定
なお、以上のテーマについて地域協力を進めるには、プロジェクトの実施にあたり中心となる機関、専門家を設定する事が望ましく、わが国の専門家が長期に現地に赴任し、指導に当たるとともに、各国専門家がワークショップ等に参加する費用等を確保する事も計画を遂行するために必要な事である。
(2) RI・放射線の農業利用
RI・放射線の農業利用については、この分野に強い関心を持っているフィリピン、インドネシア、タイの3カ国について現地調査を実施し、各国の研究開発の現状、および地域協力のテーマに関する意向を調査した。
それによると、フィリピン、タイについては不妊虫放飼法による害虫駆除(SIT)の研究を既に進めており、地域協力のテーマでSITを取り上げることに強い支持を表明した。インドネシアについては、米穀類の品種改良、家畜類の品質管理、食品照射等が中心であり、SITについては、隔離できる地域がないため、実用化の可能性がほとんどないと考えられており、インドネシアの地域協力に対する希望はイネ等のバイオテクノロジー応用であった。
その他の国については、第2回アジア地域原子力協力国際会議で報告された論文の内容をもとに調査した結果、マレーシアがSITを支持、韓国、オーストラリアは植物、穀物、土壌の改良等を支持、中国からは特定のテーマについての支持表明はなかった。
近隣アジア諸国のRI・放射線の農業利用は各国とも放射線の照射利用とRIのトレーサー利用とに大別されるが、農業はそれぞれの地域の自然環境、社会環境条件に立脚して行われるために、RI・放射線の農業利用の対象は各国の農業政策の力点の置き方によって違っている。そのため、共通の地域協力計画のテーマを見いだす事はかなり困難である。
しかし、本年度の調査を通じマレーシア、フィリピン、タイ、マレーシアがSITに対し興味を示したということは、これらの国が将来の農業形態を穀物生産よりも付加価値の高い野菜や果実の栽培に重点が移る事を予測しているからであろう。
結論としては、RI・放射線の農業利用において地域協力のテーマとしてSITを取り上げていく事になると思われるが、地域協力の最終目標を根絶をめざした不妊虫放飼法による害虫駆除事業とするか、あるいはこの技術の情報交換、もしくは研修、訓練あたりにとどめるのかよく検討する必要があろう。
なお、高付加価値の野菜や果実を生産するための基本は優良品種の育成にあり、いずれは地域協力計画のテーマとしてバイオ技術を取り入れた品種改良が上がってくると思われる。
(3) RI・放射線の医学利用
近隣アジア諸国におけるRI・放射線の医学利用の研究開発の現状については、医療分野において広範に利用が拡大されつつある状況であり、最新技術の導入に当たっては、その技術経験を有する国との協力が強く望まれている。
このため、第2回アジア地域原子力協力国際会議においては、各国から積極的、かつ具体的な地域協力計画に関する提案があり、その内容は以下の通りにまとめられる。
インドネシアは肝炎と初期段階の肝臓癌の診断に関する研究に重点をおいているため、地域協力ではこの分野の共同研究プロジェクトを提案したいとの意向を表明した。
オーストラリアからは、1)医療用サイクロンの利用、2)ほう素中性子捕獲セラピーの技術開発、3)体内蛋白モニター、4)Tc-99mイメージングへのコンピュータの利用に関する研究協力を取り上げてはどうかとの提案があった。さらに、これらを実施するための地域的なセミナーまたはトレーニングコースを組織する意向のあることも表明された。
マレーシア、韓国、中国、タイからも同様にアジア地域のRI・放射線の医学利用を促進するためのトレーニング・センターを設置して、セミナー、トレーニング等を実施していくのが効果的であるとの提案を支持する旨の意見表明がなされた。
一方、フィリピンからは、昨年、日本が提案した子宮癌の放射線治療に関する共同研究のテーマについて、ラルストロンを導入して治療技術の修得をはかる計画のあることが報告され、地域協力において取り上げるよう提案があった。
近隣アジア諸国におけるRI・放射線の医学利用分野における、地域協力については診断、治療の両側面において、強い協力のニーズのあることが調査を通じて確認された。
地域協力の具体化にあたっては、アジア各国が共通に関心を持つテーマの選定とそれに基づく地域協力計画の策定が必要であるが、平成3年度においてはオーストラリアの主催により専門家会合の開催が予定されており、その場において日本の考え方をよく説明するとともに、相互の意見交換を通じ適切な地域協力プログラムを作成していくことが重要である。
(4) パブリック・アクセプタンス
各国のパブリック・アクセプタンスの現状については、主として第2回アジア地域原子力協力国際会議において提出された論文の内容を中心に分析、調査してまとめた。
それによると、各国の原子力開発に対する国民の受けとめかた、あるいは原子力反対運動の状況等については、国情の違いにより、まったく異なった状況ではあるものの、いくつかの共通点がある事がわかった。
1つはチェルノブイリ原子力発電所事故の影響によるものである。特に、アセアン諸国においては輸入食品中に含まれる放射能に対する不安が引き金となり原子力開発全般に広がるという反対運動の動きが目だつようになっている。もう1つは、政治的な反体制運動と連動して発生している点がある。
一方、日本のパブリック・アクセプタンス活動は一般国民を対象としているのに対し、近隣アジア諸国の多くは当面は、政治家、マスコミ、オピニオン・リーダーなど一般公衆に影響力を持つ人たちが対象となっているのが特徴であろう。
日本で起きている原子力の事故についても、アジア各国にとっては現地の新聞しかニュース・ソースがないため、事実と異なって、かなり誇張された表現で伝えられ、様々な影響を及ぼしているようである。
どの国もパブリック・アクセプタンスに関する決定的な手法を確立している国はなく、このテーマこそ地域共通の課題として取り組んでいく価値があるというのが各国の大方の意向である。具体的にどのような協力を進めていくかということについては、情報の交換、セミナー、トレーニング、PA専門家の交換等が提案された。
このテーマについては、地域共通の関心事項であり課題ではあるものの、他の研究分野の協力と異なり、技術レベルの向上というよりも、適切な戦術、戦略の策定をいかに進めるかということが重要である。パブリック・アクセプタンスに関する協力の最終目標をどこに置き、どのような手法で、どこから始めていくべきかなど、各国異なった状況の中で、関係者と相互によく意見交換した上で、コンセンサスを得てから進めるべきであろう。
当面の目標としては「各国間の情報交換体制の確立」を目指すことにより世界各国の原子力施設で生じたトラブル等の情報交換が考えられるが、その前に各国のパブリック・アクセプタンスの担当者間の連携が前提となろう。
平成3年度にはパブリック・アクセプタンスの専門家が一堂に会し、地域協力計画について検討する機会がもたれる予定であるが、協力の目標、手法等についてよく意見交換し、相互理解を深めることが重要である。
なお、中国に関しては、原子力開発36年の歴史と地域住民への十分な説明により、現在のところ原子力反対運動は起きていない。しかし、将来そのような問題が起こらないとは言えず、パブリック・アクセプタンス問題におおいに関係する放射性廃棄物管理の問題を取り上げるよう提案があった。本年度の地域協力構想調査の中で提案された放射性廃棄物管理問題と環境保全のための放射線利用技術については、パブリック・アクセプタンス問題との関連もあるため、地域協力構想のパブリック・アクセプタンスに関する協力に関係づけて検討していくことも必要であろう。
地域協力プロジェクトに関する各国の希望テーマについて Ⅱ.「近隣アジア諸国における原子力発電導入に関する調査」(調査の概要) わが国近隣のアジア諸国に原子力発電導入の波が押し寄せつつある。
韓国では90年末時点で9基・762万kWの原子力発電所が運転中であり、全電力の50.2%を供給しており(89年実績)、更に2基・200万kWが建設中、3基・268万kWが計画中である。また、中国でも現在、3基・210万kWが建設中であり、今年中にも送電を開始する予定である。また、近隣地域としては台湾が6基・514万kWを運転、35.2%を原子力で供給している(同実績)。
更に特筆すべきことは、1989年夏、インドネシアが大統領命令によって、原子力発電導入へと公式に動き始めたことである。同国は東南アジア諸国では最大の原子力研究開発陣容を誇り、長らく原子力発電導入へ向け、国際原子力機関や先進国の援助を受けて調査等を行ってきた。今回の原子力発電導入計画が公式になったことで、今後、フィジビリティ・スタディの実施や発注メーカーの選択等、建設へ向けて現実的なステップをとることが必要となり、日本にとっても、これから協力の重要性が増してくるものと考えられる。
また、インドネシアの決定が刺激となり、その周辺諸国でも原子力発電導入の動きが速まることも考えられる。
こうした状況を踏まえ、平成2年度の調査では、主にインドネシアについてケーススタディを行うこととし、その参考事例として近隣諸国の中で最も身近な中国の原子力計画を選び、更にわが国の原子力導入当時の状況と比較することとした。これは、日本の導入当時と現在の開発途上国がおかれている状況には様々な違いがあるものの、開発途上国における原子力発電導入準備への取り組みへの何らかの示唆となり得るのではないかと考えたからである。調査は、中国、インドネシア、及び日本の、原子力発電導入に関する経緯を対象とし、できるだけ調査項目を合わせ、各国間での相互比較が可能となるよう留意した。
主な調査項目は、中国、インドネシア、及び日本について、原子力発電導入の背景と政治、経済、エネルギー事情、原子力発電導入時の原子力研究開発状況、導入にあたっての国際協力体制、の3点とした。
本委員会としては来年度以降も、調査対象途上国での原子力発電導入に関わる経済、政治、社会、技術、産業面等の分析、建設資金等の調達方法、原子力発電導入への具体的ステップとこれへの協力方策等の調査を行い、その上で、開発途上国での原子力発電導入に関わる総合評価と、わが国が今後、近隣アジア諸国と原子力発電協力を進めていく上での政策提言を行いたいと考えている。
近隣アジア諸国地域において、原子力が安全かつ開発の牽引力として有効に利用されるように、日本として原子力発電分野における本格的な協力を検討する契機に本調査がなるよう、関係機関のご尽力をお願いしたい。
第1章 中国の原子力発電導入に関する経緯
1. 中国の政治、経済、エネルギー事情と原子力発電の導入 中国は1970年代の「文化大革命」による一大混乱期を終え、その後は「現代化」または開放経済への改革期に入った。しかし中国は依然社会主義国であり、その経済体制はいまだ計画経済の枠を出ないものである。中国の1978年から今日に到る十数年間の「改革」を子細に観ると、そこにはいくつかの波があり、開放と調整が繰り返されており、それは中国の国内政治の動静とも一致している。1970年代末から開始された開放政策は、数年後にはその「過熱」を避けて調整政策を採ることになったが、同様のことが80年代に再び繰り返されて、現在は第二の調整期にある。その中で中国経済は幾多の問題をかかえながら、徐々に改革と発展を進めている。
その問題の一つであるエネルギー供給政策は、経済政策の中で重要な位置を占める。経済改革の中でエネルギー関連産業への投資の重点性は配慮されたが、価格関連ではほとんど手がつけられていない。経済成長と軌を一にするエネルギーの需要に対し、その供給、特に電力の供給は、工業、農業、運輸などの経済の主要部門にて、その死活を制するものである。それが充分になされていない今日、改革はまだ途上にあることは明らかである。
中国の逼迫する電力供給の中で、原子力発電に関する各省、各地の設置要望は強い。すでに、江蘇、広東、福建、山東、吉林等の各省からそれが求められているとのことである。これに対し核工業総公司の立場は慎重であり、かつ資金配分と技術力もその全てを満たすには充分ではない。しかし中国は原子力発電に関しては着実なぺースで急がずに進めるようであり、あくまでも、石炭中心の火力発電と水力発電への補助的立場に変わらないであろう。原子力発電設備の導入と技術の吸収、向上は行うが、基本は国産で自主技術を目指している。それは中国が開放経済政策を採り始めた1980年代の初期から同じであった。原子力発電関連の基本建設投資額は過去着実に増加している。この投資額は今後とも増加するだろう。
中国での原子力発電への期待は大きい。西暦2015年までに発電電力量3000億kWh、設備容量を5000万kWにしたいというエネルギー需給の予測もある。それは、原子力発電を大規模に導入することによって、中国が直面しているエネルギー問題の解決の糸口にしようというものである。原子力発電所の建設によって、中国はエネルギーの不均等な分布を緩和でき、またエネルギー資源の輸送面での逼迫をも軽減できる。さらにエネルギー構造の改善によって、石炭への偏重を避け、これによって環境汚染も軽減される。しかし、原子力発電所の経済的な立場に関しては、議論が多岐にわたる。一応その重点地域は、華東、華南地区とされ、エネルギー需要が供給を大きく上回る地域が優先されているが、各省、各地区による原子力発電設置の要望は大きく、これをどこに優先させるかは決定が難しい状況にある。
2. 発電利用を中心とする中国の原子力研究開発の現状 2-1. 原子力研究開発の経緯
中国における実質的な原子力開発は1955年にソ連の協力でスタートし、最初の研究炉もソ連の援助によって建設された。しかし、1950年代末からのソ連との関係の悪化により、以後は独力で核兵器の製造を目的に進められ、1964年には最初の核実験に成功した。中国が本格的に原子力の平和利用に取り組み始めたのは文化大革命終了後で、1980年の第一回中国核学会が実質的契機となって、原子力発電開発に積極的な取り組みを開始した。
2-2. 原子力研究開発体制
中国の原子力開発は従来、国務院の下、核工業部(原子力工業省)により進められてきたが、1988年3月に全体的な行政改革で、政府のエネルギー関係機構が大幅に改編された。これにより、従来の核工業部、水利電力部の電力部門、石炭工業部、石油工業部などが統合されて能源(エネルギー)部となった。そして、発電に関わる建設、運転などの現業部門は核工業総公司等の企業体に再編された。
中国核工業総公司は、原子力開発の現業部門を統括し、傘下に200以上の企業体、30万人以上の職員・労働者、7万人以上の専門技術者を擁している。そして、現在建設中の秦山・大亜湾原子力発電所を所管するほか、関係の所属研究所において設計・研究活動にも責任を有している。また、ウラン鉱山や精練工場を所轄している。
2-3. 原子力発電開発計画
第12回中国共産党全国大会における2000年までに工農業総生産を1980年の4倍増にするとの国家経済開発計画に基づき、中国では1980年代の前半に、2000年までに1,000万kWの原子力発電所を建設する計画が打ち出された。しかし、その後の経済政策上の行き詰まりから、引き締め方向に政策が軌道修正され、原子力発電所建設計画も下方修正され、現在では今世紀中に600万kWの原子力発電所を建設することとなっている。
2-4. 燃料サイクル開発
燃料サイクル開発の状況については、軍事利用とのからみもあり、対外的に明らかにされていないことも多く、なかなか全貌がつかみににくいが、その概況は大体以下のようである。
ウラン探査では、中国国内で、1955年から全国的規模で開始され、これまでに約35年間の探査経験があり、日本とほぼ同様の探査史を持つが、日本と比べて国外での経験はない。
ウランの粗製練では、多くのウラン鉱山と湿式粗製練工場が稼働中である。中国の生産能力は年間の鉱石処理量は200万トン程度である。
転換では、内蒙古自治区の包頭核材料工場が1963年から生産を開始しており、UF2からUF4、UF4からUF6への反応の双方に流動床法を採用している。中国は、現有能力で今後の原子力発電での必要量を確保できるとされている。
ウラン濃縮については、1962年11月に、甘粛省にガス拡散法による蘭州ウラン濃縮工場が完成しており、現在まで長期運転されていて、1981年には濃縮ウラン世界市場に参加し、低濃縮ウランの一部が輸出された。中国は現在遠心分離法や原子レーザーウラン濃縮法の研究も実施している。
燃料製造では動力炉用燃料要素製造の研究開発が、原子力潜水艦用燃料製造の研究とともに開始された。四川省宣賓にPWR用燃料製造プラントが建設され、1984年末に試験用燃料集合体の製造を開始した。宣賓核燃料工場では、1989年3月より秦山原子力発電所用の燃料集合体も製造しており、1990年11月までに総計121体の燃料集合体が秦山に到着した。今後、外国企業との協力で60万kWと90万kW級PWR用燃料集合体の生産能力を確立するとしている。
再処理は、1970年4月に、甘粛省酒泉に軍事用再処理工場を建設した。1980年代に原子力研究が軍事用から民生用へ移行後、原子力発電所からの使用済燃料の再処理パイロットプラントに向けての検討が行われており、核工業総公司では蘭州に建設する計画が既に国務院等の承認を得ており、処理能力は100kg/日で、1998年に運転開始の予定という。
放射性廃棄物の処理・処分については、すでに中・低レベル放射性廃棄物のアスファルト固化およびセメント固化技術を取得し、中レベル放射性廃棄物の地層処分に対する技術試験を完了している。高レベル放射性廃棄物については、ガラス固化の研究が行われており、地層処分に関しては、5か年にわたる処分計画に関する研究を行ってきており、今後、地層処分の研究開発を進めて行く予定である。
2-5. 新型炉開発
中国の原子力開発戦略は3段階になっており、第一段階で熱中性子炉を開発し、第2段階で高速増殖炉を、第3段階で核融合―核分裂炉(fusion-fission reactor)あるいは核融合炉を開発するとしている。熱中性子炉開発については、まず最初に加圧水型原子力発電所に取り組むこととし、あわせ将来に備え、高温ガス炉及び低温プロセス加熱用原子炉の研究も行うとしている。
2-6. 原子力安全規制
原子力発電建設についての安全規制は、国家核安全局が総括している。国家核安全局は、1984年10月に国務院が批准・発効した「中華人民共和国核施設安全監督管理条例」に基づいた機関であり、中国における原子力施設の安全性を統一的に監督する権限を有する独立機関で、直接、国務院に対して報告を行う。その主要な任務は、原子力安全に関する法律や規定の作成と公布、商業用原子力関連施設の検査・運転許可証の発行、核物質安全利用の管理、原子力事故緊急管理の技術的支援などである。このため、設立以来、原子力発電先進国や国際原子力機関の原子力安全基準を参考にして、安全規定、基準及び指針などを制定してきている。原子力関係の許認可については、5段階(立地選定、建設、初期燃料装荷、運転、デコミショニング)の原子力安全運転許可システムが採用され、次第に民間施設においても実施されている。
3. 中国の国際協力体制 3-1. 中国が原子力技術導入に至る経緯
中国の原子力開発が本格化したのは「中ソ原子力協定(1955年~1959年)」の締結後であり、1960年代の半ばには既に原子炉、核燃料サイクルの一連の技術的基盤を築き上げている。しかし、四半世紀に亘る原子力開発も1966年から始まった「文化大革命」の影響を受けたこともあり、ほとんど軍事利用に終始していた。文革後の1977年から78年において、中国は大型の原子力発電所を導入することで、米国、西独、仏、カナダ、イタリア等と交渉を進め、一時は仏フラマトム社から出力90万kWの加圧水型炉2基の購入することに合意したが、その後の経済調整の中でこの購入は一次棚上げとなった。このような大型原子力発電所導入計画の財政面からの行き詰りにより、一挙に、国産原子力発電所原型炉として秦山原子力発電所の開発が進められることとなった。一方、大型輸入原子力発電については、仏より原子炉、英国よりタービン発電機その他関連設備を導入することで、1983年に英中、仏中政府間の覚書が調印された。
3-2. 国際協力体制の整備
多国間協力としては、中国は1984年、IAEAに正式加盟し、同年9月に指定理事国に選出された。また、IAEAのアジア・太平洋地域における協力協定(RCA)プロジェクトへも積極的に参加している。しかし、核不拡散条約(NPT)には加盟していない。
二国間原子力協力協定としては、日本、ソ連、米国、仏、英国、ドイツ、パキスタン、イタリア、ユーゴスラビア、ルーマニア、ブラジル、アルゼンチン、ベルギー等と、それぞれ締結している。
第2章 インドネシアの原子力発電導入計画
1. インドネシアにおける原子力発電所導入決定の背景 1-1. 1989年、スハルト大統領の原子力発電所建設に関する指示
1989年8月、スハルト大統領は、原子力発電所の建設の準備を実施するように指示した。建設計画予定地は中部ジャワのムリア地区で、最終的には入札で選ばれた海外のコンサルタントに委託する調査に基づき、決定される。計画発電能力は600MWで、完成は西暦2000年の予定である。
この原子力発電導入決定に対する国内では、主に原子力発電所の経済性と国内技術開発に対する波及効果に関する議論がある。これは、これまでのインドネシアにおける経済開発の実施過程において、技術開発重視の掛声の下に経済採算性を軽視する大型プロジェクト投資を実施し、その結果、外貨の浪費を通じたマクロ的経済の非効率を引き起こしたことがたびたびあったためである。かかる批判は政府内のテクノクラートやエコノミストの中で主流である。一方、現業部門における政府高官や企業経営者では、長期的な観点から技術力の向上が必要であり、そのための先導的役割を最新のハイテク技術を利用する大型投資に与えるべきであるとの意見が支配的である。
1-2. 1980年代末の経済急成長
原子力発電所建設決定は、1980年代末のインドネシア経済の急成長と深く関わっている。それは1986年を底とするオイルグラット(油価低迷)や、1985年9月のプラザ協定以降の円高ドル安に伴う累積債務問題に対する積極的な経済自由化政策(構造調製政策)と無関係ではない。インドネシアは、1980年代のオイルグラットと経済成長の低迷、累積債務問題(国際収支危機と財政赤字の深刻化)などの問題を経験しながらも、これに対して経済構造調整の促進と規制緩和政策である程度の成功をおさめつつある。
これらは完全でないにせよ、金融、資本市場の活性化を導き、また活発な投資活動を通じて輸出の拡大に貢献した。しかし、これまでの自由化政策は生産部門における諸規制の緩和までにはいたっておらず、新たな規制緩和が待たれている。また、包括的な制度改革による構造調整が必要な時期にきている。21世紀初頭に期待されている本格的な工業化は、安定的な経済構造の構築を必要とする。そのためには、不必要な政府の介入による経済構造の歪みを着実に排除することが必要である。
1-3. 経済開発計画の特徴と今後の方向
インドネシアは、1969/70年度に第一次5か年計画を開始して以来、第3次5か年計画終了までは、順調に経済成長を達成してきた。第4次5か年計画ではオイルグラットのため成長率は低下し、年平均成長率は目標の5%を下回る4%程度の実績であった。第5次5か年計画(1989/90~1993/94)成長目標率は第4次計画と同じ5%とし、初年度は7.4%と好調な滑り出しである。インドネシア政府は第5次5か年計画期を「離陸準備期」と位置づけ、第6次5か年計画を「離陸」のための基盤造りの期間としている。
第5次5か年計画目標達成の目標を達成するための条件としては、以下のものがあげられる。第一に、インドネシアが計画期間5か年間を通じて年平均5%の経済成長を達成するかどうかは、ガス・石油依存構造の達成ができるかどうかである。第二に、1990年末で430億ドルある公的累積債務問題をいかに解決するかの問題である。第三に、対外債務返済と石油収入停滞によって引起こされた財政の硬直化を改善しなければならず、そのためには国内税収増大策として、税制改革が必要である。第四に、年平均5%の経済成長率達成のために、民間部門の主導性が欠かせない。最後に、第五次5か年計画で民間主導の発展が重視されていることと併せて、国営企業の役割は依然として大きい。
1-4. 経済成長の制約条件
インドネシアの開発戦略の中心が輸出工業化であることから、工業化への問題点としては、インフラストラクチャーの未整備、低水準な技術開発力、財政資金投下のシステムが不透明で、公共投資予算や内容について、民間に対する情報公開度がきわめて低いこと、それに関連してプロジェクト工事の実施過程における一元的管理体制が取りにくいことなどがあげられる。
1-5. エネルギー問題と電力供給
インドネシアに豊富なエネルギー資源としては、石油、天然ガス、石炭、水力、地熱等があり、またウラン資源も探鉱は仏、独の技術協力を得てカリマンタンおよびスマトラで実施され、既知ウラン資源は西カリマンタンのkalanにあり、回収可能確認資源は1,000トンとされている。
インドネシアの電気事業は、基本的にはPLN一社のみであるが、各企業が自家発電所をもっており、この数の非常に多いのが特徴である。インドネシア全体の電力消費量は、1968/69年度の約32億kWhから20年後の1989/90年度には415億kWhに増大し、年平均14%で伸びている。しかし、PLNが企業の必要とする電力供給を行えず、また、頻繁な停電、電圧、周波数の変動等を起こすなどPLNの電力の信頼性が低いことが問題点で、自家発電への依存を増やしている原因となっている。
1988/89年度のPLNの総発電設備容量は852.9万kWであり、その内訳は、水力197.3万kW、汽力394.7万kW、ディーゼル179.5万kW、ガスタービン123.4万kW、地熱14.0万kWである。PLNの長期需給計画では、2003/04年度までに2,555.7万kWの電源開発が必要となっている。
1-6. 原子力発電所建設に関わる問題点
インドネシアの原子力発電所導入に関係する問題点は以下の5点に集約される。
第1にマクロ経済の観点からの問題点である。計画されている60万kWの原子力発電所の建設費用は一基当たり最低10億ドルかかり、数基の設置や周辺機器投資を考えると、全体の投資額はインドネシアの経済規模においては巨額である。資機材の大半は輸入され、しかも、建設期間が長期にわたるため、慎重な国際収支政策が必要である。また、財政資金の面でも負担が大きく、発電所建設の費用負担が他の公共事業予算を圧迫し、バランスのある開発に障害となる。
第2に、現在のエネルギーおよび電力事情からすると、主要な外貨獲得源である石油以外のエネルギー源の活用も可能であり、これらを利用した場合の費用対効果を分析することが肝要である。また、インドネシアは1万3000の島々からなり、132万平方kmの広大な国土に1億8000万人が住んでおり、ジャワ島における電力需要だけを優先できない社会的、政治的問題があり、この点も熟慮する必要がある。
第3に、インドネシア政府は原子力発電の建設、運転、メインテナンス等を通じて、技術水準の向上を図ろうとしている。しかし、原子力発電たどの場合、その技術が高度すぎること、ブラックボックス部分が多いことなどから、全体的に技術水準の低いインドネシアがタイアップすることは容易でない。また、補修用パーツ等の国産化も、生産コストの問題もあって、困難であろう。技術力向上の核として原子力発電導入を利用するという論理の展開には、無理が残ろう。
第4に、安全管理と環境問題がある。原子力発電所の故障等の場合に対処できるシステム造りは、インドネシアの風土方化に馴染むものでなければならない。実際に建設した場合のアフターケアは、こうしたシステム造りをも重視するべきであり、ハード部門のみのアフターケアだけでは大きな欠陥となる。また、発電所立地候補地はジャワ島の人口過密地域であり、建設にあたっては環境問題、特に住環境問題に配慮しなければならない。
最後に、原子力発電所建設は政治問題と不可分である。国内的には、スハルト現政権の安定性、民主主義の浸透度、国軍の政治的支配力等のカントリーリスクには注目しておくことが重要である。スハルト大統領の引退問題も、具体的な政治スケジュールに折り込みが始まっている。また国際的には、インドネシアが原子力平和利用を確約し、それを確実に実行するという信頼を醸造しなければならない。
2. インドネシアの原子力研究開発水準 2-1. 開発の歴史
スカルノ前インドネシア大統領は、インドのネール首相と同様に、封来のエネルギー源として原子力の利用を重要視して、原子力関連の研究開発を積極的に進めた。インドネシア原子力庁(BATAN)は、1958年は設置された原子力委員会がその後改組して、1964年に設立された組織である。BATANは、大統領令により原子力関連の技術開発を行う機関として、原子力関連の研究開発施設の設置から許認可までの権限を持っている。1964年には米国ゼネラルアトミック社からトリガー型のスイミングプール研究炉を導入した。インドネシアで設計・製作した100kWの教育用原子炉が1978年には運開した。
1982年に西独のインターアトム社と大型の多目的研究炉MPR-30建設の契約を結び、1988年10月には10.7MWで72時間の連続運転を行い、インドネシア側に引き渡された。MPR-30はJRR-3と並んで、世界でも一級の研究炉となっている。この研究炉に付帯する研究施設として、核燃料の製造施設、照射後試験施設、中性子ビーム利用施設、放射性アイソトープ製造施設等が完成または建設中である。これらの研究に必要な人材は、世界銀行や日本の経済協力基金(OECF)からの借款によるインドネシア政府留学制度や、各主契約者と結んだ研修資金により、若手の研究員を多数海外に送って、現在研修を続けている。
2-2、2-3. 研究用原子炉、付属研究所の概要
BATAN所属の研究所としては、バンドン原子力研究所、ジョクジャカルタ原子力研究センター、スルポン原子力研究所群、パサールジュマット放射線利用研究センターがある。
バンドン原子力研究所には、1MWトリガ型研究炉、核燃料加工施設、中性子ビーム利用施設、熱ループ試験装置、RI製造、化学研究室、放射性廃棄物処理施設等がある。
ジョクジャカルタ原子力研究センターには、カルティーニ教育用原子炉、未臨界核燃料集合体、原子力技術教育センター等がある。スルポン原子力研究所群には、多目的研究炉MPR-30、研究炉燃料製造施設、放射線冶金研究所、工学的安全性研究所、実験用燃料製造施設、原子核メカノエレクトロ研究所、放射性廃棄物処理施設、放射性アイソトープ製造施設、中性子ビーム利用施設がある。また、パサールジュマット放射線利用研究センターでは、IAEAのRCAプロジェクトにより、ガンマ線照射施設と低エネルギー電子線照射施設が完成している。
2-4. 原子力安全規制の現状
現在、原子力の利用に関する安全規制ほすべてBATANの安全規制部が担当している。ここでは、MPR-30の運転手順の見直しから、放射線を利用した非破壊検査の審査まで、許認可を行っている。今後の課題として、十分な知識力を持った行政官を育成し、技術開発の現場以外に安全規制当局にも、有能な人材がそろう事が望まれる。
2-5. インドネシアにおける原子力発電立地安全評価の現状
BATANでは、イタリアのNIRA社と協力して中部ジャワのムリア地区の原子力発電候補地の立地安全に関する調査研究を行っており、ムリア地区に3つの立地候補地が選定され、現在フィージビリティスタディーの対象となっている。
3. インドネシアの国際協力体制 3-1. 二国間原子力協力協定、協力取決め等の現状
主な原子力及び科学技術協定および協力取決めとしては、米・インドネシア原子力協力協定(1960年)、ソ連・インドネシア原子力協力協定(1961年)、仏・インドネシア原子力協力協定、独・インドネシア科学技術協力協定(1971年)、イタリア・インドネシア科学技術協力協定(1972年)、カナダ・インドネシア原子力協力協定(1982年)、日本・インドネシア科学技術協力協定(1981年)等がある。この他にインドネシアは、オーストラリア(1988年)、ユーゴスラビア(1970年)、ルーマニア(1978年)、パキスタン(1980年)と、インド(1981年)と、原子力平和利用に関する協力協定を締結している。
3-2. 国際機関との協力
インドネシアは、1957年8月にIAEAに加盟した。1967年12月にIAEA・米国・インドネシア三者間の保障措置協定が発効した。また1970年にはIAEAのRCA協定に加盟した。MPT条約については、1979年7月に批准し、翌1980年にIAEA保障措置協定が発効した。
3-3. 主要実績と今後の計画
インドネシアは、ジャカルタ郊外のスルポンに国立研究科学技術センターを建設し、BATANは、ここに30MWの多目的研究炉MPR-30を中心とした研究施設の整備を、先進諸国との共同研究を取り入れながら進めている。
3-4. 原子力発電分野における協力
1991年11月には、本導入計画に関するフィージビリティ・スタディと立地調査に関して、仏ソフラトム社、加カナトム社、米ベクテル社、及び新日本技術コンサルタントの4社が入札した。現在インドネシア側は、採用会社を選考中である。また、原子力発電導入に向けて技術者や専門家の養成を、先進国との協力のもとに進めたい意向である。
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |