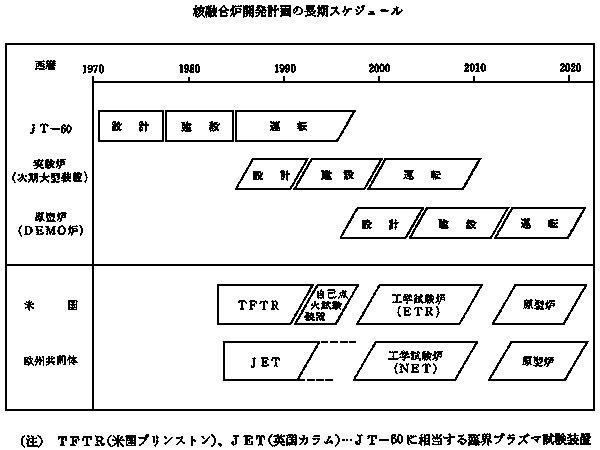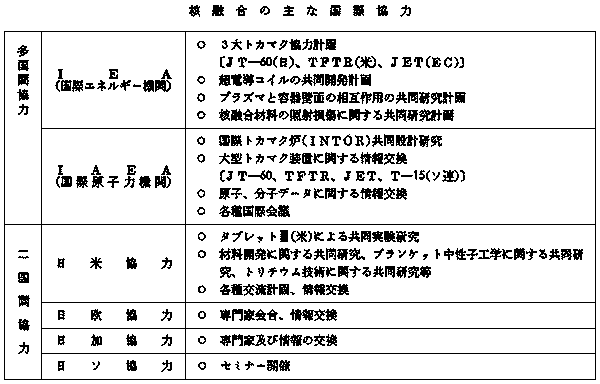| 前頁 |目次 |次頁 | |||
|
時の話題 国際熱核融合実験炉(ITER)の国際協力 昭和63年2月 我が国における核融合の研究開発は、JT-60(日本原子力研究所の臨界プラズマ試験装置)による臨界プラズマ条件の目標領域の達成(昭和62年9月)により、いよいよ新しい飛躍の時を迎えようとしています。 JT-60に続く次期大型装置によって、人類の歴史上初めて人工の太陽の火を地上に灯そうとするものです。その装置は、「核融合実験炉」といいます。JT-60は、核融合炉を模擬した、いわば、燃えない燃料(水素)を使った装置ですが、「核融合実験炉」では重水素と三重水素(トリチウム)を燃料として実際に核融合反応を超そうとするものです。 この「実験炉」によって核融合の科学的実証から工学的実証へ進み、引き続き原型炉、実証炉などによる核融合炉の安全性、経済性の確認を行うことになります。その上で核融合発電炉を実現し、21世紀中頃には日常生活において核融合エネルギーの恩恵に浴することができるものと期待されています。 1.核融合実験炉の開発について (1)我が国では、昭和62年6月、原子力委員会が「原子力開発利用長期計画」の改訂を行いましたが、この新しい長期計画によれば、核融合の研究開発の次の主要目標として「実験炉」の建設を進め、2000年頃の核融合の「工学的実証」の達成を掲げています。 その具体的な建設計画については、「1990年代前半に国内建設を開始することを念頭に置きながら、国内外における核融合の研究開発状況や国際動向を踏まえて定める」と述べています。 一方、世界の核融合先進国である米国、EC、ソ連では、我が国とほぼ同様の長期的展望のもとに次期計画として、「実験炉」計画の準備が進められています。 (2)世界的に核融合の研究開発が、臨界プラズマ試験後の「実験炉」建設に向けてその方向が一致しているのは、将来の核融合発電炉の実現に至る道程の重要な段階として、「実験炉」の開発が必要不可欠であると認識しているからです。 「実験炉」の実現のためには、核融合プラズマに耐える材料の開発、燃料となるトリチウム取扱い技術の確立、超電導磁石の開発など広い範囲にわたる工学技術の研究開発、そして、これらを総合した「実験炉の設計」研究を推進する必要があります。
核融合炉開発計画の長期スケジュール 2.核融合の国際協力について (1)核融合の研究開発は、初期の実験室規模の研究から段階的に拡大し、臨界プラズマ試験を迎えて、その規模も実験室のレベルを大きく越えて大型プロジェクトとなってきました。この傾向は、「実験炉」の建設をひかえ、開発すべき技術が人類未踏の分野に及ぶことから、今後ますます拡大することとなります。 これに伴って開発に要する資金、人員が増大することとなります。したがって、開発資金の低減、テーマの重複回避、研究開発の効率化につながる国際協力は極めて重要であると考えられています。 (2)我が国は、自主開発を基本として研究開発を進めていますが、世界の核融合分野におけるリーダ国の一員として、国際社会での責任を果すとともに、研究開発の効率的な推進をはかるという見地から、これまで、国際機関を通じての多国間協力や米国、ECなどとの二国間協力を活発に行ってきました。 今後、国際社会での我が国の地位向上と相まって、核融合分野の国際協力の面で我が国に対する期待はますます高まるものと予想されます。 核融合の主な国際協力 3.国際熱核融合実験炉(ITER)について (1)これまでの国際協力は、情報交換、人材交流などが主流でしたが、さらに踏み込んだ協力を実施しようとする動きがでてきました。それは「実験炉」の概念設計を国際原子力機関(IAEA)のもとで、日本、米国、EC(ユーラトム)及びソ連が共同して実施しようとするものです。 (2)昭和60年と61年のレーガン・ゴルバチョフ米ソ首脳会談の際に両首脳間で核融合の国際協力についての話し合いが行われ、その結果、米国から日本とECに対し、共同設計への協力提案がなされました。 以来、四者はその協力の可能性について話し合いを進めてきましたが、昭和62年10月、実施の枠組、方法などについて基本的合意に達しました。そして、共同設計をする実験炉を「ITER:イーター」と命名しました。 4.ITER共同設計活動の概要について ITERの共同設計活動は、国際原子力機関(IAEA)の下で実施されます。その活動の概要は次のとおりです。 (1)参加国、目的、期間 ① 参加国は、日本、米国、ソ連、EC(ユーラトム)(2)協力の態様 ① 各参加国は、分担して自国内で設計作業及び必要な研究開発を実施します。
(3)設計活動の組織 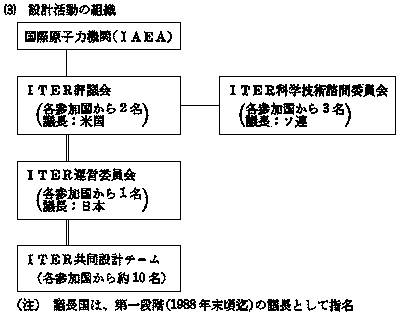 5.我が国の対応について (1)JT-60に続く我が国の「実験炉」建設計画は、先に述べたとおり、国際動向を踏まえて決定するものとしております。また、国際協力についても、原子力開発利用長期計画では、研究開発の拡充、効率化、開発リスクの低減等の観点から、新しい国際プロジェクトによる共同建設の可能性の検討を含め、国際協力に積極的に取り組むものとしております。 (2)ITER共同設計の国際協力に我が国が参加することは、上記の方針に合致するもので、ITER設計活動によって得られる成果は、今後の我が国の核融合計画に反映し、有益に活用することができます。 (3)ITER共同設計活動の我が国の対応については、「原子力委員会核融合会議」において総合的な調整を図ることとしております。 (4)ITERは、日本原子力研究所を中心として、大学、国立試験研究機関及び民間企業の協力のもと、国内の知見を結集して実施することとしております。 |
|||
前頁 |目次 |次頁 |