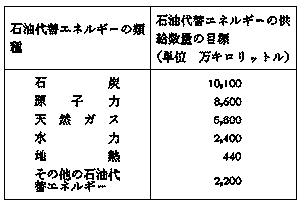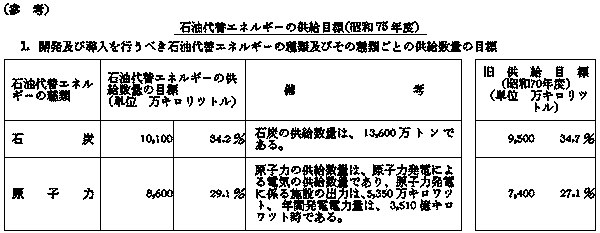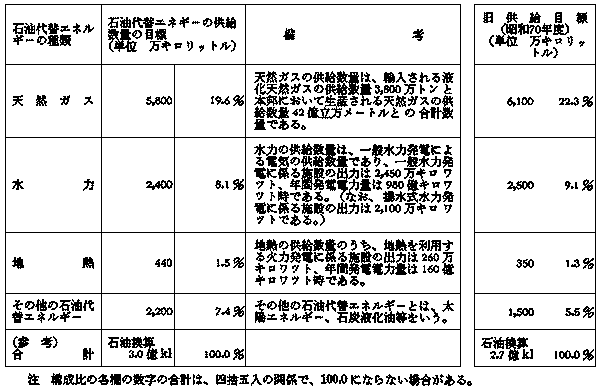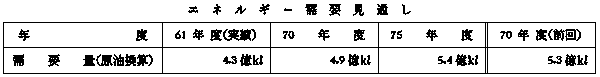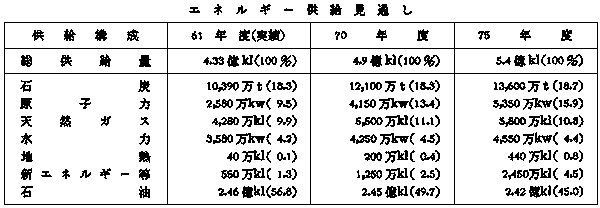| 前頁 |目次 |次頁 |
|
石油代替エネルギーの供給目標 昭和62年10日16日 昭和75年度までに開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、昭和75年度におけるその種類ごとの供給数量の目標は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
① 石油代替エネルギーの供給数量の目標の欄に掲げる数量は、石油代替エネルギーの供給数量をそれぞれ原油の数量に換算したものである。2.その他石油代替エネルギーの供給に関する事項 (1)この目標は、民間の最大限の理解と努力、政府の重点的かつ計画的な政策の遂行及び官民の協力の一層の強化を前提としたものであり、環境の保全に留意しつつこれを達成するものとする。 (2)この目標は、エネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発の状況その他の事情の変動のため必要があるときは、これを改定するものとする。 注 石油代替エネルギーの供給目標(昭和58年11月18日閣議決定)は、廃止する。 (参 考) 石油代替エネルギーの供給目標(昭和75年度) 1.開発及び導入を行うべき石油代替エネルギーの種類及びその種類ごとの供給数量の目標
(1)この目標は、民間の最大限の理解と努力、政府の重点的かつ計画的な政策の遂行及び官民の協力の一層の強化を前提としたものであり、環境の保全に留意しつつこれを達成するものとする。 (2)この目標は、エネルギーの需要及び石油の供給の長期見通し、石油代替エネルギーの開発の状況その他の事情の変動のため必要があるときは、これを改定するものとする。 (解 説) 長期エネルギー需給見通し及び石油代替 前回の長期エネルギー需給見通しは昭和58年11月に策定したものであるが、その後原油価格動向の変動、経済構造調整に向けての我が国エネルギー需要の構造的変化等内外のエネルギー情勢は大きな変化を遂げており、現実との乖離が顕著になってきた。このため、総合エネルギー調査会は、昭和62年10月14日長期エネルギー需給見通しの改定を行い、通商産業大臣に対し報告を行った。 この改定見通しに則り、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に基づく「石油代替エネルギーの供給目標」についても改定が行われた。 新たな長期エネルギー需給見通し及び石油代替エネルギーの供給目標の概要は、以下のとおりである。 (長期エネルギー需給見通しの概要) 1.基本的考え方 (1)国際的な石油需給は、現在緩和基調で推移しているものの、1990年代には石油供給の不安定化と石油需給の逼迫化が進展し、石油価格も上昇していくものと考えられ、こうした見方を前提に今後のエ去ルギー需給を見通していく必要がある。 (2)我が国のエネルギー需要は、経済構造調整の中で、民生部門のエネルギー需要の着実な増大は見込まれるものの、産業部門のエネルギー寡消費化等により、緩やかな増加を示すと考えられる。 (3)石油依存度の長期的低減を図る等により、脆弱な我が国エネルギー需給構造の強靭化、柔軟化を進めていくことは、国際エネルギー需給の安定に寄与することとなり、今後の経済構造調整期にあっては、国際社会へ積極的貢献の見地からも一層望まれるところである。また、経済社会の高度化の進展に伴い、国民生活のエネルギーへの依存は、ますます高まっていくものと考えられ、国民生活の質的向上等の面から、エネルギーの安定的かつ低廉な供給がより強く要請されるとともに、ニーズの多様化・高度化に応じてエネルギー供給形態等について適確な対応を行う必要性、すなわちニーズ適合性への要請も高まっていくものと考えられる。 2.目標年度 今回の長期エネルギー需給見通しにおいては、昭和70年度については可能な限り現実的な見通しの対象年度とし、新たに昭和75年度を政策的な目標年度として設定した。 3.エネルギー需要 エネルギー需要については、今後の経済構造調整による構造的変化の方向性を踏まえて見通しを行った。 エネルギー需要見通し ① 産業構造のエネルギー寡消費化、一層の省エネルギー努力等による産業部門のエネルギー需要のシェアの低下 ② 国民生活の質的な充実、サービス経済化の進展等による民生部門のエネルギー需要のシェアの拡大 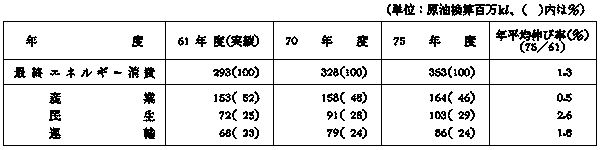 4.エネルギー供給 エネルギー供給について、各エネルギー源が有する諸特性や国際的な需給状況等に記慮しつつ見通しを行っ た。 エネルギー供給見通し 主要点 ① 石油の供給量は概ね横這いで推移し、今後のエネルギー需要量の増加分については石油代替エネルギーの供給増加によってほぼ対応。 ② 石油依存度の低下 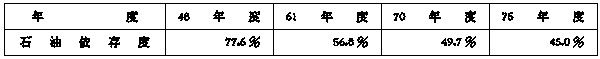 |
前頁 |目次 |次頁 |