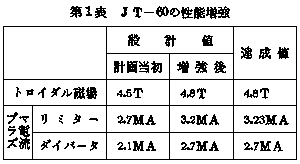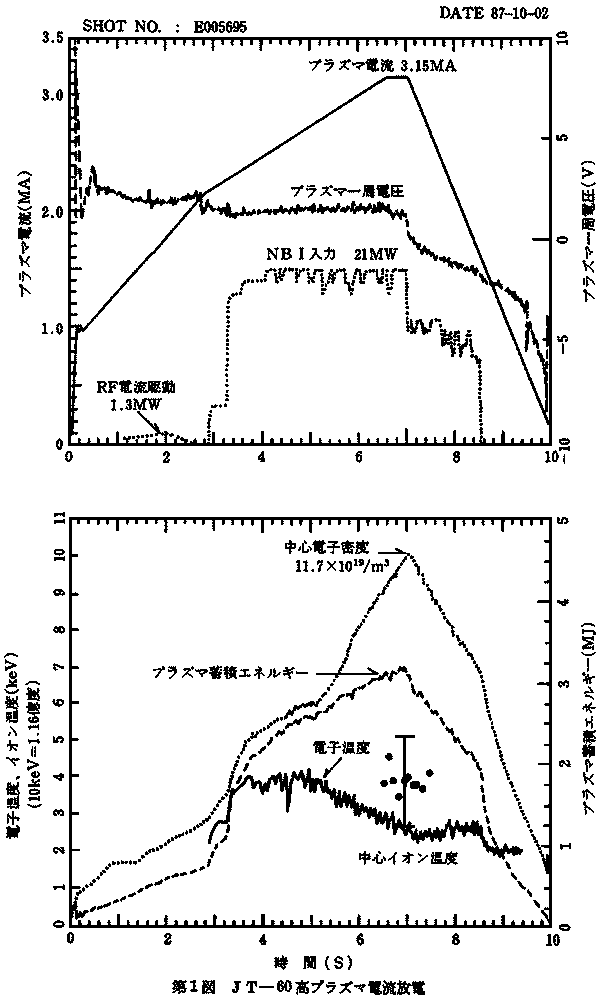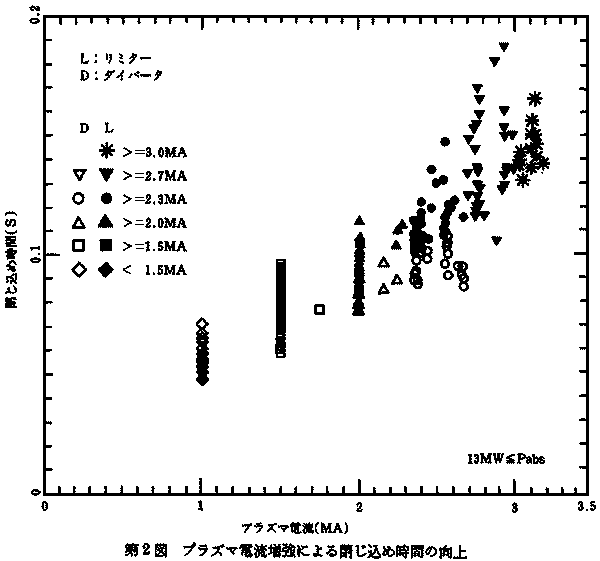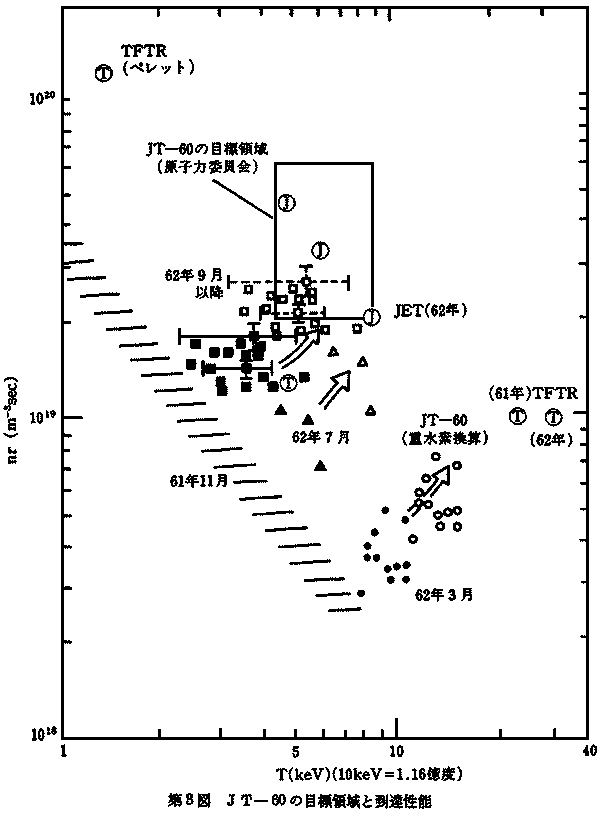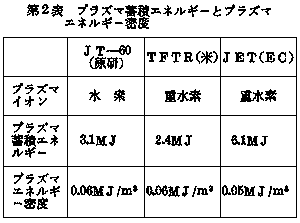JT−60では、62年4、5月に第一壁の一部グラファイト化、電源増強、加熱装置運転領域の拡大等を実施して、JT−60装置性能の向上を図った後、62年6月より10月までの4カ月余にわたって実験を行った。この結果、プラズマ電流の増加による閉じ込め性能の向上を実現し、重水素プラズマへの換算値において、原子力委員会の定めたJT−60の目標領域(温度数千万度から1億度程度、プラズマ密度と閉じ込め時間の積2〜6×1019m-3・秒程度)に到達したことを確認した。
1.JT−60は、電源の増強、コイル渡線の補強、及び制御機能の強化等の装置性能の向上を図るとともに、中性粒子入射による安定化、及び次期大型装置の基本運転シナリオである高周波を用いた非誘導電流駆動の導入によって、JT−60計画当初の設計値を大巾に越える320万アンペアのプラズマ電流の放電を実現した。この電流値において、電磁流体力学的な安全係数(qψ)は、2.2に至った(第1表、第1図)。
第1表 JT−60の性能増強
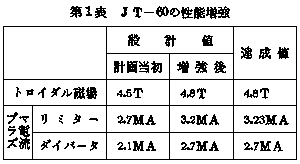
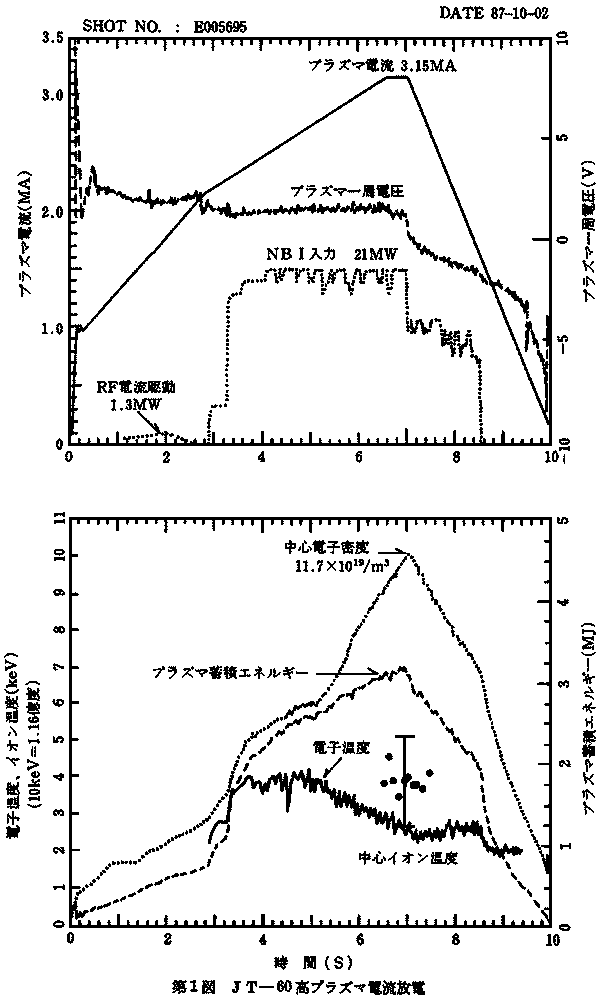
第1図 JT−60高プラズマ電流放電
2.プラズマ電流の増強に伴ってプラズマの閉じ込め性能は順次向上し、13MWを越える高い加熱入力のもとで、本年3月までのプラズマ電流200万アンペアにおける閉じ込め時間0.12秒を大巾に上回る0.18秒に達した(第2図)。
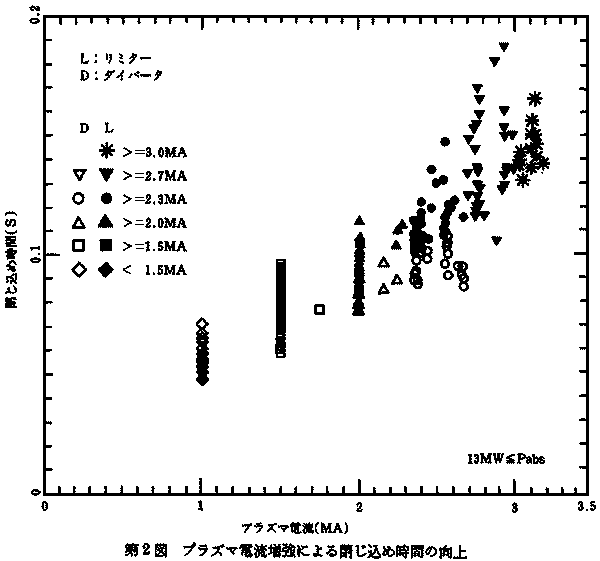
第2図 プラズマ電流増強による閉じ込め時間の向上
3.プラズマ電流の増強による閉じ込め性能の向上とともに、密度、温度等も向上し、第3図に示すデータを得た。最高の性能値は、プラズマ電流320万アンペアにおいて、中心密度1立方メートル当り、1.3×1020個、中心イオン温度4300万度、プラズマ密度と閉じ込め時間の積1.8×1019m-3・秒を得た。この性能値は、水素プラズマで得られた最高記録値であるとともに、JT−60の目標領域にきわめて近接している。(第3図の黒い四角点)。
4.閉じ込め時間及び同じ加熱入力における温度が、水素や重水素イオンの質量数の平方根程度に比例して向上するという実験則に基づいて水素プラズマから重水素プラズマに換算したJT−60のプラズマ性能値は、目標領域に到達したことを確認した(第3図の白い四角点)。
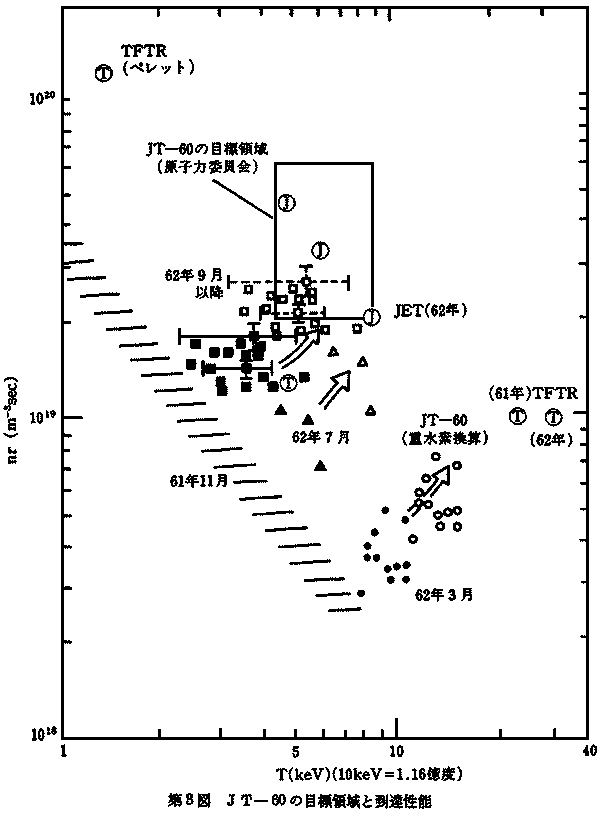
第3図 JT−60の目標領域と到達性能
5.温度と密度をかけ合わせた量のプラズマ全体での総量を示すプラズマ蓄積エネルギーもプラズマ電流の増大とともに向上し、最大3.1メガジュールに達した。このプラズマ蓄積エネルギーは、重水素を用いたTFTRを大幅にこえてJETに次ぐものであるとともに、単位体積当りのプラズマ蓄積エネルギーについては、水素プラズマであるにもかかわらず、重水素を用いたTFTR、JETに並ぶものである(第2表)。
第2表 プラズマ蓄積エネルギーとプラズマエネルギー密度
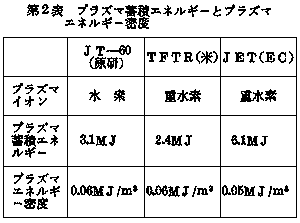
6.JT−60は、プラズマ電流の増強による閉じ込め性能の向上とは別に、固定リミタ配位及びダイバータ配位のいずれについても、高効率閉じ込め(Hモード)に固有の現象のいくつかを観測した。
JT−60は以上の成果を得て、62年10月16日、これまでの一連の実験運転を終了した。その後、63年2月までの期間をかけて、下ダイバータコイルの設置、プラズマ電流増強(350万アンペアまで)のための電源の改良、ペレット入射装置新設等の工事を実施する。63年3月には実験運転を再開し、下ダイバータ配位による高効率閉じ込め(Hモード)の実現、プラズマ電流増強による閉じ込め特性の一層の向上、ペレット入射による密度上昇と密度分布制御による閉じ込め特性の改善等を目指して実験を進める。
63年度からは上記の高性能化実験と並行して、大電流化改造による第2段階の高性能化計画に着手する予定である。64年度から65年度にかけて、約1年間運転を停止して現地工事を実施する。実験運転再開後は、ダイバータ配位で600万アンペアを目指す大電流化実験に進み、JT−60目標領域の上限近くのプラズマ性能を目指す予定である。
|