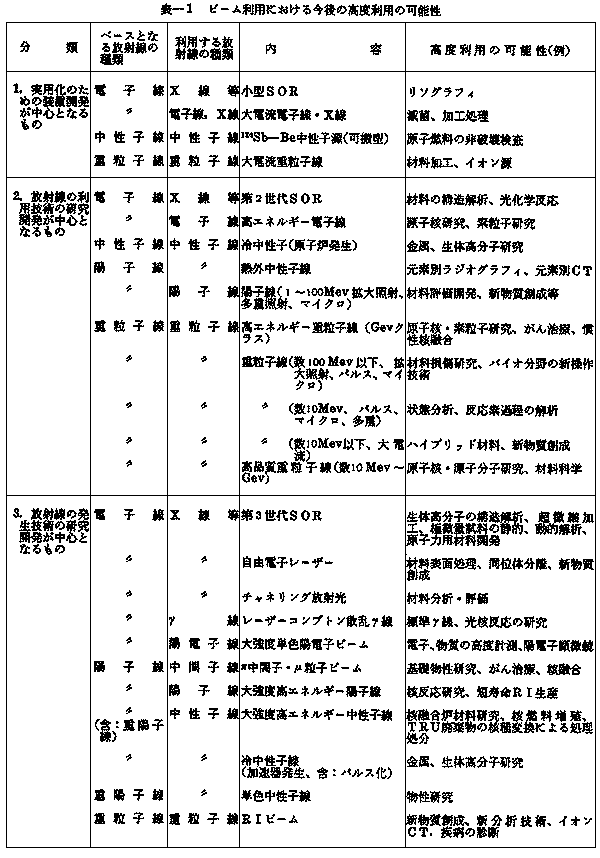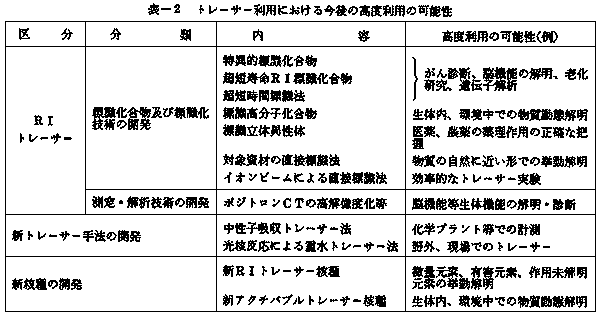| 前頁 |目次 |次頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
放射線利用の推進について 昭和62年2月26日 放射線利用については、原子力発電と並ぶ原子力平和利用の重要な柱として、これまで様々な研究開発が進められ、現在、工業、農業、医療等様々な分野で放射線が幅広く利用され、国民生活の向上に大きく貢献している。 このような状況に加え、近年、放射線の新たな利用について期待が集まっている。即ち、物質・材料、情報・電子、ライフサイエンス等の先端科学技術の急速な進展及び放射線利用分野における加速器技術の進歩等が相まって、先端科学技術の放射線利用への応用と放射線の先端科学技術分野への応用とが相互に進みつつあり、今後の一層の進展が期待されている。このような従来とは異なる放射線利用の新しい局面は、科学技術の発展に大きく貢献する可能性を秘めている一方、この研究開発には、多額の資金、優れた人材及び長期の期間を必要とするため、今後の研究開発の効率的な推進方策につき検討する必要がある。 また、これまで研究開発が行われてきた分野で、実用化が円滑に進んでいない分野や今後実用化が期待される分野について、実用化の促進に必要な事項を検討することも必要な状況となっている。 さらに、放射線利用に係る国際協力は、原子力平和利用における国際協力の重要な柱として、開発途上国協力を中心に様々な分野について進められてきたが、今後とも、我が国が原子力先進国として国際的責務を果たす等の観点から、今後の国際協力のあり方について検討していく必要がある。 当専門部会は、このような放射線利用に係る最近の状況を踏まえ、今後の放射線利用推進のための研究開発等のあり方について鋭意審議を進めてきたが、今般以下のとおり取りまとめたので報告する。 なお、加速器を応用した二次ビームの利用のなかには、従来の原子力の研究開発利用における放射線利用の範囲を越えるものもあると考えられるが、加速器技術の今後の全体的なあり方を考える上で検討対象に含めることが望ましいとの判断からこれらを含めて検討を行い、本報告を取りまとめた。 当専門部会は、本報告に沿って逐次具体的施策が展開され、放射線利用がさらに進展することを期待する。 2 放射線利用の現状 (1)実用化の現状 これまで進められてきた放射線利用の研究開発の成果として、放射線は、現在、工業、農業、医療等の分野、さらに広範な研究分野で幅広く利用されている。 工業分野においては、各種の高分子材料等の製造・加工、検査、計測等に放射線が幅広く用いられている。電子線は、耐熱性電線被覆材料、発泡ポリエチレン、熱収縮チューブ、電池用隔膜等の製造、タイヤ用ゴムの前処理、塗装塗膜の硬化等に幅広く利用されており、現在、これらに用いられる電子加速器は国内で90台以上が使用されているといわれている。また、Ⅹ線装置や60Co、192Ir等の密封RIが非破壊検査に用いられているほか、密封RIを利用した厚さ計、レベル計、密度計、水分計、硫黄分析計、ガスクロマトグラフ装置等が工程管理等に広範に利用されている。このほか、医療用具等の滅菌が60Coのγ線を用いて国内数カ所の施設で実施されている。 農業分野においては、食品照射、害虫防除、品種改良等に放射線が利用されている。食品照射は、放射線の生物効果を利用して食品の保蔵性を高める方法であり、近年世界的に実用化等の動きが活発化しているが、国内では、60Coのγ線により馬鈴薯の発芽防止を行う実用照射施設が1カ所稼動している。また、害虫防除については、60Coのγ線により不妊化した害虫を野外に放飼して害虫を根絶させる不妊虫放飼法が実用化されており、南西諸島及び小笠原諸島の3カ所で害虫根絶に成功している。このほか、60Coのγ線等を利用した農作物、園芸植物等の品種改良が行われており、優れた形質を持った品種が育成されている。 医療分野においては、診断及び治療に放射線が広く用いられている。診断については、RIを結合させた放射性医薬品が特定臓器やがん病巣などの診断、血液や尿中の微量物質の検査等に広範に用いられており、また、Ⅹ線透視装置、Ⅹ線装置とコンピュータとを結びつけた断層画像情報を得ることができるⅩ線CT等が広く診断に用いられている。 治療については、がんが主な治療対象となっており、現在、60Co遠隔照射治療装置及び60Co、192Ir等の密封小線源によるγ線、電子加速器等によるⅩ線、電子線を用いたがん治療が広く行われている。 研究分野においては、特にライフサイエンス関連分野において、RIがトレーサーとして生合成機構や代謝機構、ホルモンや薬物等の作用機構の解明等に広く用いられるとともに、最近の遺伝子工学分野においてもRIは不可欠なものとして幅広く利用されている。また、分析手段として、蛍光Ⅹ線分析装置やRIを装備したガスクロマトグラフ装置等が広く用いられるとともに、放射化分析法も微量元素の分析に広く利川されている。さらに、様々なタイプの加速器が広範な研究に利用されている。 このように、これまで進められてきた放射線利用の研究開発の成果のかなりのものが様々な分野での実用化に結びついており、これらの開発された技術は、民間主体の技術分野として、かなり成熟化、定着化してきていると考えられる。 このような実用化の一方で、後に述べるように、研究開発の成果が実用化に結びつかなかったものもあるなど、いくつかの問題もある。 (2)研究開発の現状 放射線利用の研究開発は、目指す利用目的において多岐にわたり、また研究開発のレベルにおいても様々なものがあるが、当専門部会における今回の検討においては、今後の研究開発のあり方を考える上で、これを大きく次のように分類して検討を進めた。 ①60Coのγ線、電子加速器からの電子線等の照射利用技術や一般的なトレーサー利用技術のように既に基本的に確立されている利用技術を、新たな用途に応用することを目指した、いわば応用的な研究開発(i)応用的な研究開発 応用的な研究開発は、古くから特殊法人や国公立試験研究機関を中心に行われ、数多くの実用化の成果を生み出してきたが、現在も引き続きこれらの機関を中心に、照射利用及びトレーサー利用について研究開発が実施されている。 照射利用についてみると、工業分野については、日本原子力研究所や国公立試験研究機関を中心に、機能性高分子材料、耐放射線性材料等の開発、生物活性体の固定化、中性子ラジオグラフィによる非破壊検査、工程管理用オンライン分析計測技術等に係る研究開発が行われており、環境保全分野についても、同じくこれらの試験研究機関を中心に、排煙処理技術、上水原水や下水汚泥の処理技術等の研究開発が行われている。農林水産分野については、農林水産省の試験研究機関を中心に、品種改良、食品照射等の研究開発が、また、医療分野については、放射線医学総合研究所や大学を中心に、速中性子線や陽子線等によるがん治療の研究開発が行われている。このほか、これらの分野での放射線利用の基礎となる放射線標準の研究が電子技術総合研究所を中心に進められている。 トレーサー利用に係る応用的な研究開発は、現在、農林水産分野や医療分野におけるものが大宗を占めている。農林水産分野については、農林水産省の試験研究機関を中心に、動植物体内や環境中での物質の動態解明等へのRIトレーサーやアクチバブルトレーサーの利用のための研究開発が行われている。医療分野については、厚生省の試験研究機関を中心に、疾患の機構解明、検査、診断等へのRIトレーサーの利用のための研究開発が進められている。 (ii)高度利用のための研究開発 応用的な研究開発の一方で、加速器技術、ビーム制御技術、新しい放射線の発生技術等の開発が近年急速に進み、放射線の高度利用を目指して、現在のような取組みが進められている。 近年の放射線の照射利用分野における高度利用は、いわゆるビーム利用として、大学、日本原子力研究所、理化学研究所、国立試験研究機関(電子技術総合研究所、放射線医学総合研究所等)を中心に様々な研究開発が進行中である。大学関係では、新しい放射線の基礎的研究が進められているが、特に、高エネルギー物理学研究所においては、大規模加速器施設による高エネルギーの陽子線、電子線、陽電子線等を用いた原子核・素粒子研究等への取組みを進めているほか、高エネルギー電子線を用いた放射光(SOR)実験施設(第2世代SOR施設)で各種の利用研究が行われている。 日本原子力研究所では、冷中性子を利用した研究等のためJRR-3の改造が行われているほか、高度に制御された重粒子線等の広範な利用を目指した放射線高度利用研究や、高品質重粒子線及び自由電子レーザーの研究開発に取組むこととしている。理化学研究所では、重イオン科学分野を中心に研究開発を進めてきており、現在、高エネルギー重イオンの原子核物理研究等への利用及び材料、生物学研究等への応用を目指したリングサイクロトロン施設の整備を進めている。 電子技術総合研究所では、高エネルギー電子線をベースとするSOR、自由電子レーザー、チャネリング放射光、レーザーコンプトン散乱γ線等の基礎的な発生技術の開発等を進めている。放射線医学総合研究所では、高エネルギー重粒子線によるがん治療を目指して、重粒子線がん治療装置の建設に着手することとしている。このほか、民間企業が中心となって小型SORの開発に着手している。 トレーサーの高度利用のための取組みとしては、医療分野において、ポジトロンCTの高解像度化等に係わる研究が放射線医学総合研究所を中心に民間も参加して進められているほか、短寿命RI標識化合物の開発が放射線医学総合研究所や大学、厚生省の機関等で進行中である。 (3)国際協力の現状 放射線利用分野の国際協力は、現在、開発途上国協力を中心として、国際機関(IAEA等)を通じた協力、二国間協力、原子力研究交流制度による協力、国際協力事業団(JICA)を通じた協力等各種の枠組みの下で、理工学、医学、農林水産等様々な分野で積極的に進められている。 (i)開発途上国協力 放射線利用分野の開発途上国協力は、IAEA/RCA協定(原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定)に基づく多国間協力を中心に進められてきているが、最近、関係国の要請を背景に二国間協力等も活発になってきている。 IAEA/RCA協定に基づく協力計画としては、現在、工業利用プロジェクト、医学・生物学利用プロジェクト等が進められている。我が国は、工業利用プロジェクトについては、日本原子力研究所、民間団体等が中心となり、天然ゴムラテックスの放射線架橋、電子線による木材の表面塗装、非破壊検査、放射線計測機器の維持管理等の分野で、専門家派遣、研修生受入れ等を行うとともに、医学・生物学利用プロジェクトについては、放射線医学総合研究所、国立がんセンター等が中心となり、核医学、放射線治療、環境放射能等の分野で共同研究、専門家派遣等を進めている。また、IAEAの下で、放射線利用による生物活性体の固定化とバイオマス変換に関する個別研究協力、食品照射等放射線の農業利用関係の専門家派遣、研究者受入れ等を、日本原子力研究所や農林水産省の試験研究機関で実施中である。 二国間協力としては、インドネシアとの天然ゴムラテックスの放射線改質の研究協力、マレーシアとの60Co照射施設の設計等の協力、中国との重イオン核物理・加速器技術に関する情報交換や共同実験、γ線照射線量評価に関する情報交換等を、日本原子力研究所、理化学研究所、名古屋工業技術試験所等が進められている。 このほか、原子力研究交流制度による研究者交流、JICA協力、WHO等の枠組みの下での研修生受入れ等が関係機関により行われている。 (ii)先進国協力 放射線利用分野の先進国協力は、二国間協力のほか、IAEA等国際機関の下での多国間協力等も進められている。 二国間協力としては、理化学研究所が、重イオン科学関係で米国の大学との研究協力及びフランスの国立研究機関との共同研究を、また、日本原子力研究所が、中性子散乱、核物理・加速器技術関係で米国国立研究所等と情報交挨、共同実験等をそれぞれ進めている。また、OECD/IEA(国際エネルギー機関)や米国との核融合炉材料中性子照射共同研究等を日本頂子力研究所等が進めているほか、IAEAの下では、IAEA/CRP(協力研究計画)として進められている放射線利用における各種研究に関する情報交換活動、IAEAや国際度量衡局(BIPM)の下での放射線単位・標準の情報交換活動等に、日本原子力研究所、放射線医学総合研究所、電子技術総合研究所等が参加して協力を進めている。また、FAO、IAEA等の下で、農林水産省の試験研究機関が、農業分野での放射線利用に関して専門家派遣等を行っている。 3 放射線利用の今後の課題 以上述べた放射線利用の現状をみると、これまでの研究開発の成果のかなりのものが実用化に結びついているが、実用化に至らなかったものもあるなど、いくつかの問題も抱えている一方、加速器技術及びビーム利用に関し新しい動きが起こっており、そのいくつかは、原子力平和利用の重要な柱の1つとして進められてきたγ線、電子線の利用等の伝統的な放射線利用から大きく発展しており、原子力という範囲を越えて一般的な科学技術と密接な関連を有し、その発展に大きく貢献しつつある。そのため、長い間行われてきた応用的な研究開発と実用化の推進に係わる考え方の整理、また新しいビーム利用等への対応、さらに国際的研究協力についての新たな展開が今後の重要な課題である。 このような背景から、今後の放射線利用に係る次のような課題が検討されるべきである。第1に挙げられるものは、これまでのように、放射線利用の実用化の推進を図っていくことである。既に述べたように、放射線利用の研究開発の成果のかなりのものが様々な分野での実用化に結びついているが、研究開発の結果、実用に供することができる程度の技術レベルに達しながら、実用化に至らなかったもの、あるいは、不十分であるものも少なくない。その例としては、照射利用分野における高分子合成・改質のいくつかの例や食品照射、トレーサー利用分野におけるRIの野外トレーサー利用等が挙げられる。このうち、食品照射については、原子力委員会の原子力特定総合研究として、馬鈴薯、玉ねぎ、米、小麦等7品目について研究開発が実施されたが、現在実用化されているものは馬鈴薯にとどまっている。これらの実用化への阻害要因を整理すると、研究開発に係る問題を越える次のような要因が挙げられる。 ① 経済的要因:放射線の照射利用の場合、一般に照射施設は線源、遮へい等の関係から高価なものとなることが多いため、高分子合成・改質の一部のものにみられるように、個々の事業者において、一定量以上の安定的な需要が見込めない場合は、放射線処理法はコスト面で不利となり、実用化には結びつき難い。今後、放射線利用の実用化の推進を図っていくためには、利用の拡大を阻害する上記の要因による問題について、各々の実情に即してその解決を図っていくことが重要である。 また、実用化の推進を図るための研究開発については、先に述べた応用的な研究開発が重要となるが、この分野については、これまでかなり広範な分野にわたって研究開発が進められ、現在も、国の機関を中心として様々な研究開発が実施されている。しかし、一方で大学や国の機関を中心に様々な新しい利用の可能性を秘める高度利用のための取組みが進められており、一定の限度のある国の資金、人材を考慮すると、応用的な研究開発分野については、国が推進すべき分野を明確にして、重点分野を絞っていく必要がある。 この場合、実用化の可能性について、技術的、経済的、その他の観点からの検討、評価を十分に行う必要がある。 第2の課題は、多くの新しい利用の可能性を秘める放射線の高度利用のための研究開発を積極的に推進していくことである。この研究開発には、多くの異なる分野の研究者の協力が不可欠であるとともに、特にビーム利用について大型加速器等への多額の資金と優れた人材の確保が前提となるが、これらの研究開発資源には一定の制約があり、研究開発の効率的な推進に十分配慮する必要がある。 第3の課題は、我が国が、放射線利用分野における開発途上国からの協力要請に応え、また、放射線の高度利用への取組みを通じて放射線の新しい利用分野を創出することなどにより、従来にも増して国際社会に貢献していくことである。開発途上国協力については、協力をより効果的なものにするためには、従来のIAEA等を通じた協力に加え、二国間協力の積極的な推進が必要である。また、国内における放射線の高度利用への取組みの推進に併せ、研究開発資金の重複投資の回避、各国の得意分野の成果の持寄りによる研究開発の加速化等の観点から、今後放射線の高度利用分野における先進国協力が重要となる。 表-1 ビーム利用における今後の高度利用の可能性 (1)放射線利用の実用化の推進 γ線、電子線等を中心とした放射線利用は、既に述べたように、長い年月にわたる研究開発や市場開拓の努力もあり、多くの分野で実用化されている。今後さらに民間部門で実用化を促進するためには、経済的あるいは社会的な阻害要因を除去していく必要があり、そのため次のような諸点が重要であると思われる。 まず第1に、放射線法の特徴が十分生かせる分野に重点を絞って応用対象の拡大を目指すことである。従来の実用化例について、放射線法の特徴をみると、放射線の優れた物質透過性、低温での反応が可能などの特性を利用した結果、競合する技術に比べ、製品の高品質化が図れるとともに、プロセスの簡素化、省資源化、省エネルギー化、低公害化等が促進されるなどの点を挙げることができる。 例えば高分子の架橋についてみると、放射線の優れた物質透過性から、固体内部に均一な反応を起こさせることが可能であるため、反応を促進させる条件として反応開始剤を添加し、これを加熱するなどの手間のかかるプロセスを必要としないといったことが良い例であろう。このように、高分子の架橋、塗装塗膜の硬化、医療用具の滅菌等、放射線の特徴が十分生かせる分野では放射線が不可欠な技術として使用されており、今後も放射線法の特徴を十分認識し、重点を絞って応用対象の拡大を目指すことが重要である。 第2に経済性になじむような加速器の開発等効率的な照射技術を開発することである。これまでの加速器等の照射装置は多目的に使用できるような設計になっている場合が多いこと、さらに放射線の遮へい等が高価であることから、設備投資に多くの資金が必要となる。 これに対して、現実には、照射品目が少なく、また、各製品の需要も少ない場合が多く、経済性になじまないことが原因となって放射線法の普及が進まない状況がしばしばみられる。このため、今後は、加速器等のメーカー及びユーザーが協力して、各々の照射対象に適合した効率的な加速器の開発等、必要な性能を維持しつつ装置の簡素化・小型化等を進め、ひいては経済性が発揮できるような、効率的な照射技術を開発することが望まれる。 節3は、先に述べた2つの点とも深い係りを有するものであるが、民間企業等において施設の共同利用化を図ることである。グラフト改質による機能性膜の製造、食品包装材、半導体等の加工等に加速器が、また、材料の耐放射線性評価等に60Co・γ線照射施設が共同利用されている例が一部あるが、研究を支援する手段としてのみ必要であったり、市場規模が小さいこと等により、独自で照射施設を設置することは投資効率が非常に悪い場合がかなりある。 この場合、民間企業等において、既存の施設の共同利用を推進したり、新たな共同利用施設を建設する等の取組みが期待される。 また、消費者の適切な理解を得られないとか、施設の立地に係わる住民の反対など社会的要因等により実用化が阻害されることに対しては、国及び民間により積極的な啓発及び広報活動を行うとか、特に食品照射の分野などについては、国民の理解の促進を図りつつ、関係行政機関において制度面の整備や合理的な運用を行うなどの措置が緊要である。 さらに、放射線利用の実用化の推進に必要な応用的な研究開発については、次のようなものについて国等の公的機関が主導して研究開発を進めることが適当であると考えられる。 ①例えば、環境、資源、医療、農業分野などにおける放射線利用研究のように、社会的要請がありながら民間がその主体になろうとする強いインセンティブが働かない研究今後の放射線利用の研究開発については、成熟しつつある技術領域での上記の努力のほかに、次に述べるような新しいビーム利用、新しいトレーサー利用といった放射線の利用を高度化の方向へ導く分野に研究開発資源を重点的に投入する必要がある。 (2)放射線の高度利用のための研究開発の推進 (i)ビーム利用 イ高度利用の可能性(ii)トレーサー利用 イ高度利用の可能性 表-2トレーサー利用における今後の高度利用の可能性 ロ 具体的な取組み(iii)研究開発体制の整備 高度利用に係わる研究開発の重点分野をみると、研究領域が科学技術の最先端の進歩と深い係わり合いを持っていること、また、研究開発資金、研究者といった研究開発資源の本分野への投入について調和のとれた効率的な配分が必要であることから、特に研究開発体制については従来の考え方にとらわれない斬新なものが要求される。 放射線利用分野における研究開発体制については、昭和56年の放射線利用専門部会報告において、放射線化学分野の研究開発体制のあり方の基本が次のように示されている。 即ち、新分野を開拓し、シーズを提供する純基礎研究は大学、シーズとニーズの結合による実用化への芽を提供する目的基礎研究は国公立試験研究機関及び特殊法人、ニーズに対応した実用化研究開発は民間が中心となって研究開発を推進するという体制が示されている。 今後の放射線利用に係る研究開発についても、基本的にはこれらの考え方に沿って研究を推進していく必要がある。 しかし、新しいビーム利用やトレーサー利用のような放射線の高度利用のための研究開発については、次のような特質があり、資金負担等の面から全体的な推進役として、国の役割が特に重要である。 ①これらの先端的技術分野は、様々な分野の高度な技術の結集が必要である。このため、従来の役割分担では必ずしも効率的な研究開発は困難であり、中心的機関を明確にして、各々の分野で十分な研究開発ポテンシャルを有する大学、特殊法人、国立試験研究機関、民間等の力を結集してこれに当たることが不可欠である。そのため、産・学・官によるプロジェクト体制の整備など産・学・官の連携の拡大・強化を図り、総合的・計画的・効率的な研究開発を推進する必要がある。なお、放射線利用に係るデータはこれまで各分野ごとに偏在しがちであったが、各分野の研究開発の効率的推進、資金の効率的運用等を図るため、データベースの整備が必要である。 (3)国際協力の推進 放射線利用分野の国際協力の今後の取組みとしては、開発途上国協力、先進国協力とも、協力対象国及び協力内容の拡充、受入れ体制の整備・強化等を積極的に進める必要がある。国内の関係諸機関においては、従来の取組みを一層推進することに加え、新たな国際協力にも積極的・計画的に取り組んでいくことが望まれる。 (i)開発途上国協力 放射線利用分野の研究は、長期的観点に立てば、開発途上国の科学技術の振興のみならず、当該国の経済・社会の発展に大きく貢献するものであることから、従来の多国間協力に加えて二国間協力を積極的に推進し、相手国のニーズ・実情を踏まえ、開発段階に応じたきめ細かい協力を積極的に推進していく必要がある。 また、本分野の研究は、研究基盤や技術基盤の整備・充実が必要不可欠であるため、従来からIAEA/RCA協力等を通じ、人材養成に重点を置いた技術協力、研究協力等が進められてきたが、今後ともIAEA/RCA協力、二国間協力、原子力研究交流制度等を発展させ、当該国の基盤整備に資することが重要である。この場合、我が国との信頼関係の基礎となる人的つながりの形成にも配慮して取り組んでいく必要がある。 さらに、このような開発途上国協力を一層効果的なものとし、我が国が原子力先進国としての国際的責務を積極的に果たしていくという観点から、日本原子力研究所に、先進国協力も含め、宿泊施設、人材の訓練施設等の整備を始めとする人材の交流を総合的に行う中核的組織を整備することについても検討していく必要がある。 (ii)先進国協力 放射線利用分野においては、特に今後の放射線の高度利用のための取組みにおいて、研究設備が大型化、複雑化し、多方面の高度な知見が不可欠であるなど、多額の資金と優れた人材の確保が重要な要素となる。しかし、これには相当の制約も予想され、このような財政上及び人材確保上の制約を克服し、また我が国に期待されている原子力先進国としての国際的責務を十分果たしていくという観点からも、放射線利用分野における先進国協力として、共同研究、研究者交流等を今後さらに積極的に推進していく必要がある。 この場合、従来の研究組織体制を越えて国内外の多分野の研究者を結集し、最大限の流動性を付与して新たな発想に基づく独創的研究を推進することにより、科学的知見の効率的発掘を目指すなど、開かれた体制の整備についても検討していく必要がある。 (参考) 放射線利用専門部会構成員
放射線利用推進分科会構成員
放射線利用専門部会開催状況 (放射線利用専門部会)
(放射線利用推進分科会)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前頁 |目次 |次頁 |