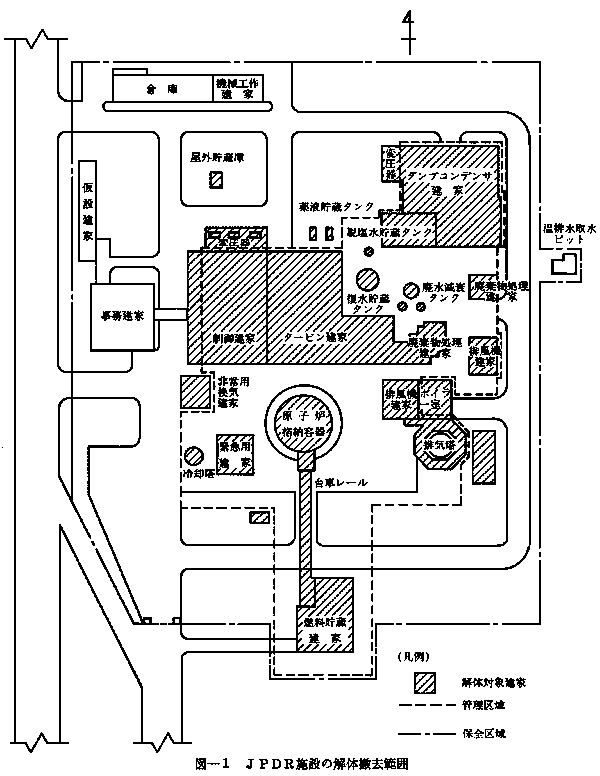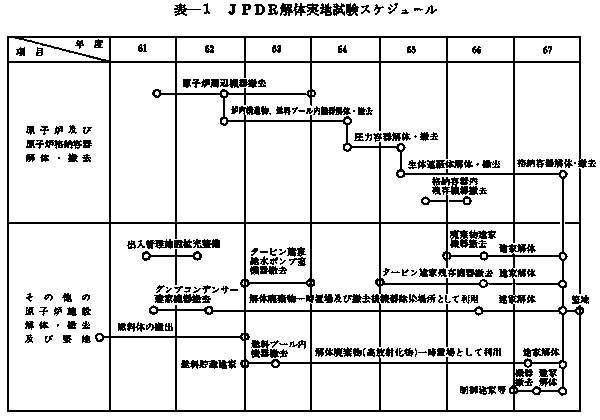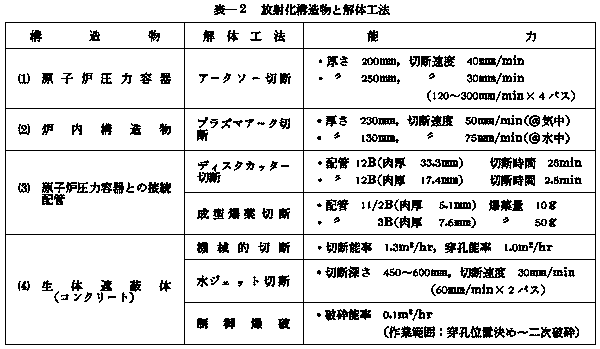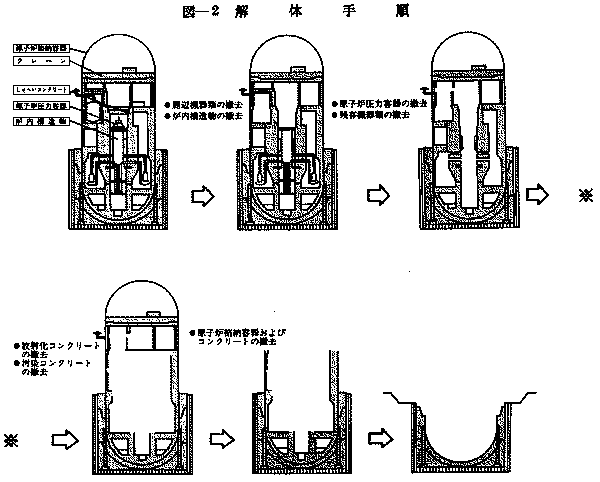| 前頁 |目次 |次頁 |
|
時の話題 日本原子力研究所動力試験炉 原子力局技術振興課 将来の商業用原子力発電所の廃止措置技術の確立を目指し、日本原子力研究所の動力試験炉(JPDR)の解体撤去を行うJPDR解体実地試験を昨年12月4日から開始した。 JPDRの解体撤去は、原子炉解体技術開発の一環として日本原子力研究所が実施するものである。 原子炉解体技術開発は、大きく2段階に分けられており、まず第1段階で解体撤去に必要な要素技術を開発し、続く第2段階で開発した技術をJPDRの解体撤去に適用して将来の商業用原子力発電所の廃止措置に資するデータ、知見等を得ることを目的としている。 2 要素技術開発 第1段階の要素技術開発は、56年度から開始し、61年度までに概ね終了している。開発した要素技術の内容は、以下のとおりである。 (1)解体システムエンジニアリング3 JPDR解体実地試験 実地試験の対象となるJPDRの解体撤去の範囲は、図−1に、スケジュールは表−1に示すとおりである。
表−2に放射化構造物解体に適用する解体技術と対象構造物を示す。 表−2 放射化構造物と解体工法 (1)原子炉内構造物、原子炉圧力容器等の解体に先立ち、原子炉周辺機器の一部を撤去して作業スペースを確保し、作業効率を高める。以上の考え方を踏まえた解体手順として原子炉格納容器及びその内部構造物の解体手順を図−2に示す。 図−2 解体手順 先に表−1に示したとおり、62年度後半から圧力容器内構造物の解体撤去を開始する。引き続き圧力容器、生体遮蔽体、格納容器等の解体撤去を行い、昭和67年度には一部建屋を除くすべての原子炉施設の解体撤去を終え跡地は整地し更地とする予定である。 |
前頁 |目次 |次頁 |