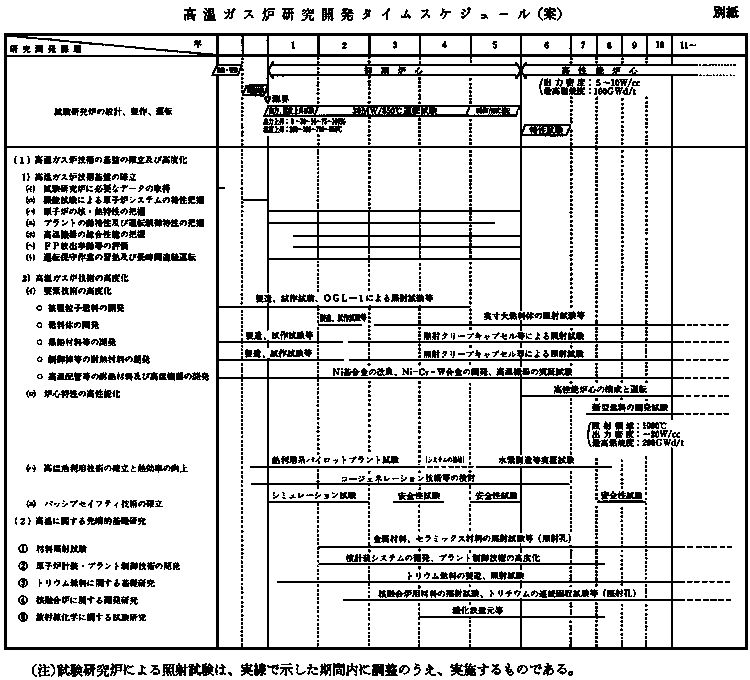
| 前頁 |目次 |次頁 |
|
高温ガス炉研究開発計画専門部会報告書 昭和61年12月23日 本年3月に設置された本専門部会は、多目的高温ガス実験炉計画を定めた現行の原子力開発利用長期計画(昭和57年6月30日、原子力委員会)策定後、近年の日本原子力研究所(原研)等における高温ガス炉技術に関する技術的知見の蓄積及び核熱プロセス利用の需要の動向等高温ガス炉を取りまく社会情勢の変化に鑑み、高温ガス炉研究開発の意義、高温ガス炉研究開発の現状及びそれを取りまく状況並びに今後の研究開発の進め方についてこれまで鋭意審議、検討を行ってきた。 去る8月には、 ① 高温核熱の産業界での利用については、その技術的見通しはあるものの近い将来に経済性が成り立つ情勢にないため、現行の長期計画に示された実験炉を建設する計画は見直すことが適当である。ことをその主な内容とする中間報告(別添)を取りまとめ、高温ガス炉研究開発の意義、高温ガス炉研究開発の現状及びそれを取りまく状況並びに高温ガス試験研究炉を軸とする我が国における高温ガス炉研究開発の今後の進め方について、原子力委員会に報告したところである。 その後、本専門部会は、この中間報告を取りまとめた際に今後の検討課題とされた、高温ガス炉技術の基盤の確立と高度化及び高温に関する先端的基礎研究についての具体的な研究開発課題及びその進め方、国内における研究開発推進体制並びに国際協力の展望について検討を行い、今般以下のとおり取りまとめた。 この報告書に示した研究開発は、長期間に亘るものであるため、必要に応じ適宜見直しを行いつつ、長期的視点に立って着実かつ積極的に推進することが重要である。 1 研究開発課題及びその進め方 (1)高温ガス炉技術の基盤の確立及び高度化 これまでに蓄積されている研究開発の成果を基に試験研究炉を建設し、高温ガス炉技術の基盤の確立及び高度化を図るための研究開発を進めるものとする。試験研究炉は次の機能を満足するものとするので、炉出力は30MWt程度が必要である。 ・燃料体に関する実寸大照射試験、燃料破損限界試験、計装付き照射試験等が行えることなお、必要に応じ、大型構造機器実証試験ループ(HENDEL)、大洗ガスループ(OGL-1)等の既存の試験装置を活用した実験等をもって補完しながら研究開発を進めていくこととする。 以下に研究開発課題ごとの研究開発の進め方を示す。 1)高温ガス炉技術基盤の確立 2 研究開発体制 高温ガス炉技術の基盤の確立及び高度化並びに高温に関する先端的基礎研究を総合的かつ効率的に進めるためには、原研がその中心となり、大学及び国立試験研究機開からの参加はもとより広く産業界との協力の下に遂行されるべきである。 このため、節目節目において各機関の高温ガス炉に関する研究開発成果の評価とそれによる計画の見直し等について審議を行い、もって我が国全体の高温ガス炉研究開発の円滑な推進を図ることが重要であり、そのための機関として、原子力委員会の下に「高温ガス炉懇談会」(仮称)を設置することも考えられる。 原研は、高温ガス炉研究開発の中核機関として、試験研究炉を建設、運転し、高温ガス炉技術の基盤の確立及び高度化を総合的に推進するとともに、セラミックス材料、核融合炉材料の照射試験等各種の高温に関する先端的基礎研究を実施することとする。その際、産・学・官から専門家、有識者の参加を得て、研究開発の具体的な進め方、研究施設利用計画等を検討する委員会を設けることが適当である。さらに、産・学・官及び海外の研究者の受入れ、交流等を積極的に行うための組織整備を図ることが必要であり、研究開発課題によっては外部研究者と原研の研究者から構成される研究組織を設ける等、研究開発を弾力的に進めることが望ましい。 大学は、高温ガス炉技術に関する基礎的研究及び高温に関する先端的基礎研究を積極的に行うことが望まれる。例えば、試験研究炉を利用した高温ガス炉に関する炉物理、炉工学試験、高温耐熱核計装システムの開発、トリウム高転換技術の研究、耐熱金属材料、黒鉛材料、セラミックス材料の大型試料による高温照射試験、高温雰囲気下での計装付きの照射試験、放射線化学、水の熱化学分解法に関する研究等の基礎研究を行うことが期待される。 国立試験研究機関は、主として、高温ガス炉用耐熱材料の開発及び評価に係る研究を行うとともに、セラミックス材料及び耐熱金属材料の高温照射挙動に関する研究等材料系科学技術分野を中心とした先端的基礎研究を推進することが期待される。 産業界は、将来の高温ガス炉技術の進展に備え、高温ガス炉の需要の動向や経済性について評価、検討を進めるとともに、高温ガス炉要素技術の高度化等を進め、さらに試験研究炉を利用する研究開発に参加し成果の活用等に努めていくことが望まれる。 3 国際協力の展望 西独、米国における高温ガス炉研究開発の特徴は、中・小型モジュラー型の発電用高温ガス炉の機能と安全性の実証、経済性の向上等を主たる目的としており、また西独においては核熱直接利用た関する高温機器、プロセス利用技術等の要素技術の開発も進めている。中国においても高温ガス炉への関心が高い。 他方、我が国における研究開発の特徴は、試験研究炉によって核熱プロセス利用炉を目指した高温ガス炉技術基盤の確立と高度化を図ることを主たる目的としており、試験研究炉を用いた各種照射試験、核熱プロセス利用技術の実証試験等を計画している。 高温ガス炉研究開発においては、海外で蓄積されている経験、技術を取り入れつつ、より高度の研究開発を効果的かつ効率的に推進するとともに、我が国の研究開発の成果を提供しながら国際協力を進めていくことが重要である。国際協力の将来展望としては、以下に示す内容が考えられる。 ① 国内におけるこれまでの優れた技術開発の成果を基に、試験研究炉の建設、運転を行い、自主技術基盤を確立することとするが、この際、西独、米国等の先進国との国際協力により、海外の成果を必要に応じ活用することとする。 以上 高温ガス炉研究開発タイムスケジュール(案) |
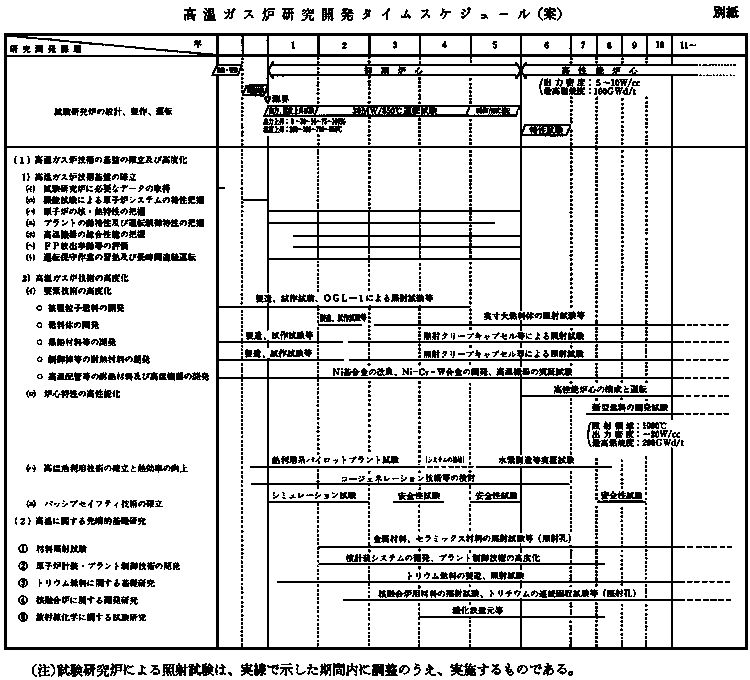
| 別添 高温ガス炉研究開発計画専門部会中間報告
昭和61年8月12日 序論 我が国の高温ガス炉研究開発については、現在、原子力開発利用長期計画(昭和57年6月30日原子力委員会決定)に沿い、日本原子力研究所(原研)において実験炉の設計及び関連研究を進めており、炉物理、炉工学、燃料・材料、高温機器等の分野で実験炉建設に必要な技術的知見が蓄積されてきている。 他方、上記長期計画策定後のエネルギー事情、核熱プロセス利用の需要の動向、国の財政事情等高温ガス炉を取りまく社会情勢の変化も著しく、今後の高温ガス炉研究開発計画について改めて検討、評価を行う必要が生じた。 このため、本専門部会において、本年4月より核熱利用の需要の動向、高温ガス炉研究開発の意義、今後の高温ガス炉研究開発の進め方等について検討を行ってきたところである。 本報告は、現在までの検討状況を整理し、中間的に取りまとめを行ったものである。 1 高温ガス炉研究開発の意義 我が国においては近年軽水炉による発電が定着し、ウラン資源の有効利用等を目指して高速増殖炉等新型動力炉の研究開発も進められているが、もとより原子力開発においては自主技術により安全性の確保を基本としつつ、経済性を追求し利用分野の拡大を図ることが本質的に重要な課題である。 原子炉システムは多量のエネルギーを発生する熱機関であり、その安全性を確保しつつより高温の熱を取り出すことにより熱効率の向上を図ることができれば、経済性の向上及び利用分野の拡大がもたらされることが期待され、ひいては地球環境の保全にも一層寄与するものと考えられる。 高温ガス炉は、1000℃程度の高温の熱を供給できるのみならず、その特性に基づく固有の安全性が高く、また燃料の高い熱焼度を達成し得るので、安全性を確保しながら経済性の向上、利用分野の拡大などの課題の解決に寄与できる炉型であり、現時点では核熱利用の導入時期の見通しは明確ではないものの、その研究開発の推進は非電力分野への原子力利用等原子力の未踏領域への展開を図る上で十分に意義があるものと認められる。 さらに、現在我が国は技術革新を図るための創造的研究を育成すべき時期にあり、国の研究機関を中心に広く大学、産業界の協力を得て、長期的展望の下に新技術の萌芽を創生し得る研究開発を推進することが必要である。高温ガス炉技術は他分野における耐熱材料、黒鉛材料、高温機器等の技術に種々の波及効果を及ぼすことが期待されるので、この観点からも、将来の技術革新の契機となる各種の新技術の萌芽の創生に貢献し得る高温ガス炉の開発は我が国にとって重要な意義を有すると考えられる。 2 高温ガス炉研究開発の現状及びそれを取りまく状況 (1)我が国における研究開発 我が国においては、原研を中心に高温ガス炉の研究開発が昭和44年以降進められてきている。 原研においては、大型構造機器実証試験ループ(HENDEL)による燃料体、炉内構造物等の高温高圧のヘリウムガス中における伝熱・流動等の実証試験、高温ガス炉臨界実験装置(VHTRC)による被覆粒子燃料を用いた臨界実験、大洗ガスループ(OGL-1)による被覆粒子燃料の照射試験等により、高温機器、炉物理、炉工学、燃料・材料等高温ガス炉要素技術について技術的知見が蓄積されてきている。 特に、高温機器についてはHENDELにおいて最高1000℃、延べ6000時間の運転に成効しており、炉計測については約800℃の高温に耐える中性子検出器が開発され、燃料については量産規模により生産された被覆粒子燃料について1300℃、5万MWD/tonの照射試験により健全性が確認され、耐熱金属材料については原研で開発したハステロイXRの15000時間のクリープ試験データが取得され、黒鉛材料については機械的強度の優れた国産黒鉛IG-110が開発されるなど多くの優れた研究開発成果が得られている。 また、昭和55年以降、実験炉の詳細設計を進めるとともに、炉システムの合理化をも検討してきた。 さらに、被覆粒子燃料、炉心用黒鉛、耐熱合金材料等については、国産技術として国内メーカーにも技術的蓄積がなされている。 以上のように、現在我が国においては、炉の建設、運転により初めて取得が可能となる技術的知見を除いて、炉出力数+MWt程度でかつ運転初期における炉出口温度約850℃の炉の建設に着手できる技術的基礎は整っているものと考えられる。 (2)海外における研究開発及び国際協力 高温ガス炉の研究開発は、西独及び米国が積極的に進めており、既に発電用原型炉を運転している。両国における開発の進め方の特徴は、まず発電を主目的とする原子炉を建設して、高温ガス炉の機能と安全性の実証を行い、さらに経済性の向上を目指している点にある。 核熱直接利用技術開発については、西独において石炭ガス化への利用を主目標に高温機器、プロセス利用技術等の要素技術の開発が進められている。また、中国においては、重質油の改質、回収用の熱源とするため高温ガス炉の研究開発が進められており、さらにソ連においても、アンモニア製造等を目的として炉設計等の研究開発が進められている。このように、核熱直接利用については、各国においてその国特有の事情に基づく用途を想定して要素技術の開発が進められている段階にあり、西独において発電用実験炉を核熱プロセス利用実験炉に改造するなどの計画が検討されてはいるが、炉システムとしての技術の確立は今後の課題である。 我が国の高温ガス炉研究開発は核熱直接利用のための炉システムの構成を目指していることが大きな特徴であるが、高温ガス炉システム中西独及び米国の計画と共通する要素技術について、研究開発を効率的に推進するため、両国との協力を実施しており、今後も積極的に協力を進めることとしている。また、中国との間でも、研究協力を開始する方向で協議を行っている。 (3)産業界における高温核熱利用の見通し 現在、我が国における高温ガス炉による高温核熱の産業への利用の見通しは概ね次のとおりである。 即ち、化学工業においては、高温ガス炉によって供給される熱が将来化石燃料によるものと経済的に競合し得るようになれば、核熱利用の可能なプロセスがいくつかあり、また、製鉄業においては、高温ガス炉によって生産される還元ガスが価格競争力を持つようになれば、その利用の可能性がある。 核熱による水素製造については、水の熱化学分解法の研究開発が進められており、将来の化石燃料に比べて安価な核熱が供給できるようになれば、これを水の熱化学分解法による水素製造の熱源として利用する可能性がある。 一方、高温ガス炉による高温核熱が早期に化石燃料に代替する見通しは少ないが、そのコストが21世紀前半に化石燃料価格と競争し得る可能性があるとの試算もある。 発電利用については、当面高温ガス炉が発電体系に組み込まれる見通しはないが、将来コージェネレーションという形態等で導入できる技術的可能性はある。 (4)大学等の高温ガス炉施設利用の見通し 大学には高温ガス炉に関連する基礎研究への志向があり、原研に高温ガス炉施設が建設された場合には、この高温ガス炉を活用して、炉物理、炉工学試験、高温耐熱核計装システムの開発、トリウム高転換技術の研究、耐熱材料、セラミック材料等の大型試料による高温照射試験、高温雰囲気下での計装付の各種照射試験等の先端的基礎研究を行いたいという意向を有している。 さらに、核融合研究分野からも、この高温ガス炉を利用して高温ヘリウムガス技術の開発、核融合炉用ブランケット材料等の材料照射試験、トリチウム生産に関する研究等を行いたいという要望がある。 また、高温ガス炉施設を利用する種々の材料研究については、国立試験研究機関の利用も相当程度見込まれる。 3 高温ガス炉研究開発の今後の進め方 高温ガス炉の研究開発は、これまで、製鉄業等での利用を早期に実現すべく進められてきており、2(1)に示すように高温機器、炉物理、炉工学、燃料・材料等の分野で優れた研究開発成果が得られ、炉の建設に着手できる技術的基礎は整っているが、2(3)で見たように、現状では、高温核熱の産業界での利用については、その技術的見通しはあるものの近い将来に経済性が成り立つ情勢にない。従って、現行の原子力開発利用長期計画に示された、高温ガス炉の早期の実用化への一ステップとして位置付けられている実験炉を建設する計画は、この際、見直すことが適当であると考えられる。 本専門部会においては、研究開発の中断等も含め今後採り得る高温ガス炉研究開発の進め方について、それらの意義及び問題点を検討した結果、以下の結論に達した。 高温熱供給、高い固有の安全性、燃料の高燃焼度等の優れた特性を有する高温ガス炉の研究開発は、安全性の確保の下に経済性の向上、利用分野の拡大などの課題の解決に寄与し得るという点で、我が国の原子力開発上大きな意義を有しており、近年の社会情勢の変化に拘わらずこの認識に変わりはない。エネルギー資源の乏しい我が国においては、特に高温熱供給による原子力利用分野の拡大により将来のエネルギー供給の多様化に資する可能性を高めておくことが重要であり、これまでに蓄積された技術及び人材を分散させることなく、引き続き高温ガス炉技術の基盤の確立と高度化を展開していくべきである。 現在の高温ガス炉技術の高度化を図るための主要な課題を集約すると、 ① 熱効率の向上と高温熱利用システムの確立となる。 また、2(4)に挙げられたような各種の高温に関する先端的基礎研究は、主に材料系科学技術分野において、将来の技術革新の契機となる各種の新技術の萌芽の創生に大きな貢献をなし得るものと期待される。 長期的観点の下に、高温ガス炉技術の基盤を確立し、加えて上記の高度化のための課題を体系的に解決していくため、また高温に関する先端的基礎研究を行うためには、高温ガス炉の基盤技術及び高度化技術に関する各種試験並びに高温領域における各種基礎的照射試験等を、所要の機能を有する炉システムにおいて実施することが必要不可欠であり、そのための研究施設として高温ガス試験研究炉を建設することが適当である。 この高温ガス試験研究炉の建設に当たっては、我が国において蓄積されてきている高温ガス炉に関する基礎技術及び原子炉設計技術を用いて、自らの手で炉を設計、製作、運転し、データを取得しつつ自主技術を確立していくことが何よりも重要である。さらに、将来の高温ガス炉技術の進展に柔軟に対応できる施設にすること、また、経費の節約を含めて効率的な研究開発に努めることが重要である。 高温ガス試験研究炉の持つべき機能については、高温ガス炉技術の基盤の確立及び一層の高度化を目指した要素技術の試験並びに高温領域における各種基礎的照射試験を行うことができるよう炉内に照射領域を設けるとともに、燃料破損限界を明らかにするための試験、計装付の照射試験等を行うことができるような構造にすべきであり、その炉出口温度については現在の技術レベルで達成可能な約850℃から段階的に上昇させていくことが適当である。また、このための炉心構造としてはブロック型が適切である。さらに、各種試験を行うために十分な大きさの実験孔を持つ照射領域を設けかつ所要の高温を達成するために必要な最小限の炉出力は30MWt程度と考えられる。 また高温ガス試験研究炉建設の時期については、建設期間及び試験研究実施期間を合わせて少なくとも十数年の年月が必要なこと並びに技術レベル及び研究開発体制の現状を考慮すれば、今後の研究開発の効率的な進展を図るため、早急に建設に着手することが適当であると考えられる。 なお、この高温ガス試験研究炉の建設費は、900億円程度と見込まれている。 長期的にみると、将来の高温ガス炉では炉出口温度約1000℃以上の高温を要求されることが予測されるので、それを目指して高温ガス炉要素技術の高度化を図ることは重要であり、そのためには、高性能化のための照射試験等を行う主要施設としてこの高温ガス試験研究炉を活用するとともに、HENDEL、VHTRC等の既存の諸施設も有効利用することが必要である。 また、このような高温ガス炉研究開発計画の実施については、長期的展望の下に原子力に関する先駆的研究を展開していく役割を担っている原研がその中心となり、大学及び国立試験研究機関からの参加はもとより広く産業界との協力の下に遂行されるべきである。 さらに、この高温ガス試験研究炉は高温照射試験機能を有し、かつ中間熱交換器から900℃近い高温の熱を取り出すことができる、世界でもユニークな研究施設であることから、国際協力の場において重要な意義を有する施設となるので、海外諸国との国際協力を積極的に行い、研究の効果的促進を図っていくべきである。 一方、核熱プロセス利用技術の開発については、我が国における今後の核熱プロセス利用に関する動向、経済性などを十分に考慮しつつ、必要に応じHENDELの利用等を含めて計画的に進めるものとする。 また、今後の高温ガス炉研究開発を進めるに当たっては、非効率的な開発とならないよう周到な計画管理に十分留意するとともに、節目節目において柔軟な立場から研究成果の評価とそれによる計画の見直しを行いつつ進めていくことが重要である。 以上 |