| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原子力モニターの声(昭和60年度)(アンケート調査結果) 昭和60年8月
振興局 原子力局 原子力安全局
原子力モニター制度は、原子力開発利用に関して、広く一般国民から率直な意見等を聴取し、これらを原子力行政に反映させることを目的とするものである。 昭和60年度の原子力モニターは、各都道府県知事より推薦を受けた候補者のうち、本人の同意を得た536名に委嘱を行った。昭和60年6月に実施したアンケート調査結果は以下のとおりである。 Ⅰ アンケート調査 1. 調査の概要
(1) 調査目的
原子力の開発についての認識及び原子力行政、原子力安全行政に対する要望等を調査し、今後の施策の参考とする。
(2) アンケート項目
1) エネルギーの将来について
2) 原子力の開発について
3) 新型炉の開発について
4) 核燃料サイクルについて
5) 原子力安全行政について
6) 原子力防災について
7) 原子力広報について
(3) 実施時期 昭和60年5月27日~昭和60年6月15日 (4) 調査方法 郵送による選択回答方式 (5) 調査対象 昭和60年度原子力モニター(全国536名) (6) 回答者数 474名(回答率88.4%) (参考) 男女別、職業別、年代別モニター数及び回答者数
(注) この報告で使われる記号の説明
1. Nは比率算出の基数であり、100%が何人の回答に相当するかを示す。特に示していない場合はN=474人(回答者)である。
2. SQ(追加質問):前問で特定の回答をした一部の回答者に対して行った質問。
3. MA(多数回答):1回答者が2以上の回答をすることができる質問。このときのMT(回答合計)は回答者数(100%)を越える。
2. 調査結果の概要 (1) エネルギーの将来について
石油に代わる大量のエネルギー供給源として、今世紀内では原子力が多く利用されると考える者が71.9%、21世紀では原子力が利用されると考える者が、69.4%あり、石油代替エネルギーとしての原子力の期待が大きいことを示している。 (2) 原子力の開発について ① 原子力発電所の建設について
原子力発電所の建設については、62.2%の者が「安全性を十分確認しながら慎重に建設すべきである」と考えており、次いで28.9%の者が「安全性を確認しながら積極的に建設すべきである」と考えている。 これらに「安全性は確立しているので積極的に建設すべきである」とする者3.2%を合わせると原子力発電所の建設の必要性を認める者は94.3%となっている。 ② 原子力発電所の建設計画について
自分の居住地近くに建設することについては、73.4%の者が「安全性に十分納得できれば賛成する」としている。これに「積極的に賛成する」とする者7.6%を合わせると81.0%の者が理解を示している。 ③ 原子力発電施設等の立地推進について
原子力発電施設等の立地が難航している理由として、61.2%の者が「原子力発電所の安全性に不安があるから」としており、次いで19.6%の者が「放射性廃棄物の処理処分に不安があるから」としている。また、この立地問題の有効な解決策としては、48.7%の者が「現在の原子力発電所の安全性及び安全対策、防災対策等について地元で一層ていねいに説明する」こととし、31.2%の者が「原子力発電所の安全運転の実績をさらに積み上げる」と考えている。 (3) 新型炉の開発について
ウラン資源の有効利用を図るために新型炉(新型転換炉、高速増殖炉)の開発を進めていることを59.3%の者が「知っている」としている。このうち、67.6%の者がこの政府の施策について「もっと強化すべきである」と考えている。 (4) 核燃料サイクルについて
① 安定したエネルギー供給源としての原子力発電の推進を図っていくためにウラン濃縮、使用済燃料の再処理等の核燃料サイクルの確立を目指していることを81.2%の者が「知っている」としている。このうち、71.7%の者がこの政府の施策について「もっと強化すべきである」と考えている。 ② 低レベル放射性廃棄物の処理処分について 低レベル放射性廃棄物の最終的処分はどうあるべきかについて39.0%の者が「当面の間、施設内での貯蔵を行う」と考えている。また、18.1%の者が「海洋処分及び陸地処分を同時に推進すべきである」、15.6%の者が「陸地処分を推進すべきである」、さらに「海洋処分を推進すべきである」とする者は10.6%となっている。
(5) 原子力安全行政について ① 原子力利用の安全確保について
原子力利用の安全確保について政府の施策のうち今後最も重要であると考えられるものについては、33.1%の者が「安全性、信頼性等に関する研究開発の推進」と考えており、次いで32.7%の者が「国民に正しい知識を与え、国民の理解を得ていくための施策」と考えている。 ② 原子力安全委員会について
原子力安全委員会の機能のうち最も期待していることとしては、27.9%の者が「行政部局の行った安全審査を、より高度な立場から再審査(ダブル・チェック)すること」としており、次いで27.2%の者が「安全審査に当たり、公開ヒアリング等により、地元住民等の意見を十分に安全行政に反映させること」としている。 ③ 原子力安全委員会の公開ヒアリングについて
原子力安全委員会の公開ヒアリングについては、原子力発電所の安全性に関する再審査(ダブル・チェック)に当たって、これまで10回の公開ヒアリング等を実施していることを65.0%の者が「知っている」としている。このうち52.3%の者がこのような体制について「改善すべき点がある」と考えており、次いで34.4%の者が「機能している」又は、「非常によく機能している」と考えている。 (6) 原子力防災について
災害対策基本法に基づき原子力発電所等が立地する各自治体が原子力防災計画を定め、緊急時モニタリング、医療、避難などの対策をとれることになっており、更に国も原子力の専門家による助言、要員、資機材の派遣、動員等により、自治体の防災活動を支援することになっている。このような原子力防災体制について43.7%の者が「概要は聞いたことがある」としており、「知っている」とした29.3%の者を合せると73.0%の者が知っていることを示している。また「知っている」とした者のうち76.3%の者が現在の原子力防災対策について「もっと強化すべきである」としている。 (7) 原子力広報について
① 「原子力の日」に関する広報や記事について (ⅰ) 「原子力の日」の前後に、政府などによる広報を見た者は64.6%となっている。また、その中で60.5%の者が「政府による広報」に接し、次いで50.7%の者が「電力会社による広報」に接している。(MA) これらの広報媒体としては、74.5%の者が「新聞」、次いで50.0%の者が「テレビ」、46.4%の者が「パンフレット」を通じて接している。(MA) ② 原子力について、特に詳しく知りたいこととしては、58.2%の者が「放射性廃棄物の処理処分対策」を、次いで53.2%の者が「原子力の長期的な展望」を、36.5%の者が「原子力発電所等の安全対策」をあげている。(MA) ③ 原子力広報について望んでいる手段媒体としては、58.0%の者が「テレビ」を、次いで55.5%の者が「原子力発電所等の施設見学会」を、44.9%の者が「新聞」をあげている。(MA) ④ 新聞、テレビ、ラジオ等の媒体で広報をする頻度としては、52.7%の者が「月に1、2回程度」、次いで20.9%の者が「週に1、2回程度」、13.5%の者が「3ケ月に1回程度」をあげている。 ⑤ 自分の居住地の近くに、原子力発電所等の立地が計画された場合の、広報活動について望んでいる手段媒体としては、74.9%の者が「原子力に関する各種の講習会や説明会」を、次いで59.5%の者が「原子力発電所等の施設見学会」を、30.6%の者が「新聞」をあげている。 3. 集計結果 問1. エネルギーの将来について
1. あなたは、石油に代わる大量のエネルギー供給源として、今世紀内はどのようなエネルギーが多く利用されると思いますか。1つだけあげて下さい。
2. 長期的観点から、石油に代わるエネルギー源として21世紀にはどのようなエネルギーが利用されると思いますか。1つだけあげて下さい。
問2. 原子力の開発について
1. わが国の原子力発電の規模については、現在(59年度実績)の約2,056万kw(全発電設備の約14%、全発電量の約22%)から、さらに拡大する目標が立てられています。あなたは、原子力発電所の建設についてどのようにお考えですか。1つだけあげて下さい。
2. もし仮に、あなたの居住地の近くに原子力発電所の建設計画が発表されたとしたら、あなたはどうしますか。1つだけあげて下さい。
3. 原子力発電施設等の立地推進について (1) 原子力発電施設等の立地に際しては、必ずしも十分な地元住民の協力が得られず立地が難航する面があります。その理由は、次のうちどれが最も大きく影響していると思いますか。1つだけあげて下さい。
(2) これらの立地問題を解決するには、どのような方策が最も有効であるとお考えですか。1つだけあげて下さい。
問3. 新型炉の開発について
1. ウラン資源の有効利用を図るため、政府としては、新型炉(新型転換炉、高速増殖炉)の開発を進めています。あなたは、このことをご存知ですか。
SQ〔対象者281名〕
2. 前記の問いで「知っている」と答えた方にお尋ねします。現在の政府の施策について、どのようにお考えですか。
問4. 核燃料サイクルについて
1. 安定したエネルギー供給源としての原子力発電の推進を図っていくため、政府としては、ウラン濃縮、使用済燃料の再処理等の核燃料サイクルの確立を目指しています。あなたは、このことをご存知ですか。
SQ〔対象者385名〕
2. 前記の問いで、「知っている」と答えた方にお尋ねします。現在の政府の施策について、どのようにお考えですか。
3. 低レベル放射性廃棄物の処理処分について
原子力発電所等で発生する低レベル放射性廃棄物は、現在適切な処理を施した後、敷地内の貯蔵庫内に安全に貯蔵されていますが、最終的には処分されることになります。その方法としては陸地への処分及び海洋への処分が考えられます。 あなたはこのことについてどうあるべきだとお考えですか。1つだけあげて下さい。
問5. 原子力安全行政について
1. 原子力利用の安全確保については、国民の理解と信頼を得ることが大切であり、政府としては、現在、次のようないろいろな施策を講じています。あなたは、このうち、どれが今後最も重要であるとお考えになりますか。1つだけあげて下さい。
2. 原子力安全委員会は、原子力の安全確保に関する事項についての国の施策を企画、立案決定して、原子力行政の民主的な運営をはかることを目的に設置されています。このため、原子力安全委員会は下記の①~⑤の機能を有していますが、あなたはこの中のどれに最も期待していますか。1つだけあげて下さい。
3. 原子力安全委員会は、原子力発電所の安全性に関する再審査(ダブル・チェック)に当たって、これまで10回の公開ヒアリング等を実施しましたが、この公開ヒアリング等についてお尋ねします。 (1) あなたは、公開ヒアリングをご存知ですか。
SQ〔対象者308名〕
(2) 前記の問いで「知っている」と答えた方にお尋ねします。あなたは、このような体制について、どのようにお考えですか。
問6. 原子力防災について
原子力発電所等については、厳重な安全対策が講じられていますが、更に万一の事故に備えた原子力防災対策が講じられています。災害対策基本法に基づき、原子力発電所等が立地する各自治体が原子力防災計画を定め、緊急時モニタリング、医療、避難などの対策をとれるようになっており、更に国も原子力の専門家による助言、要員、資機材の派遣、動員等により、自治体の防災活動を支援することになっています。 1. あなたは、上記のような、原子力防災体制についてご存知ですか。
SQ〔対象者139名〕
2. 前記の問いで「知っている」と答えた方にお尋ねします。あなたは、現在の原子力防災対策について、どのようにお考えですか。
問7. 原子力広報について
科学技術庁では、昨年度(昭和59年度)も10月26日の「原子力の日」を中心として、記念講演会の開催、テレビスポットの放映、パンフレットやポスターの作成など原子力の広報を実施しました。また、政府広報として新聞やテレビなどによる広報を行ったほか、関係機関等によっても種々の広報が行われました。 この他に、そういった広報とは別に、「原子力の日」に関する記事などを掲載している新聞等もありました。 あなたは、こうした広報や記事を、御覧になったり、気がついたりされたでしょうか。 1. 「原子力の日」に関する広報や記事についてお尋ねします。 (1) 昨年度「原子力の日」の前後に政府などによる広報を御覧になりましたか。
SQ.御覧になられた方に〔対象者306名〕 (ⅰ) どこの広報を御覧になりましたか(MA)
御覧になったものすべてに○印を御記入下さい。
(ⅱ) また、その広報は何で御覧になりましたか。(MA)
御覧になったものすべてに○印を御記入下さい。
2. あなたは、原子力について、特にどのようなことを詳しくお知りになりたいですか。(MA)お知りになりたい項目に○印を御記入下さい。
3. あなたは、原子力広報について、どのような手段媒体をお望みになりますか。(MA)希望する項目に○印を御記入下さい。
4. あなたは、原子力について、新聞、テレビ、ラジオ等の媒体で、どのくらいの頻度で広報をした方がよいと思いますか。1つだけあげて下さい。
5. もし仮に、あなたの居住地の近くに、原子力発電所等の立地が計画されたとしたら、あなたはどのような手段媒体による広報活動をお望みになりますか。(MA)希望する項目に○印を御記入下さい。
Ⅱ 昭和60年度原子力モニター構成 1. 職業別 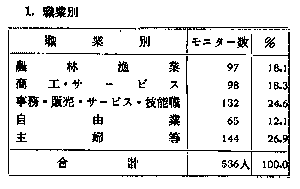 2. 年代別 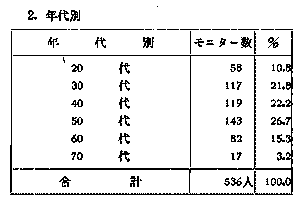 3. 男女別 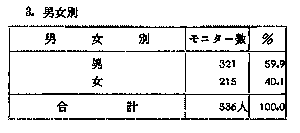 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |
 原子力(核融合を含む)
原子力(核融合を含む) 石炭(液化、ガス化を含む)
石炭(液化、ガス化を含む) 太陽
太陽 天然ガス
天然ガス 水力
水力 わからない
わからない 生物エネルギー、波力、風力
生物エネルギー、波力、風力 地熱
地熱  その他
その他 (無回答)
(無回答) 原子力発電のしくみ
原子力発電のしくみ 環境放射線モニタリングについて
環境放射線モニタリングについて わからない。
わからない。