| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
国立機関における原子力試験研究の現況 サイクロトロンで産生される超短半減期核種の臨床応用に関する研究
厚生省国立療養所中野病院
まえがき
われわれの身体を構成している元素の90%以上は、O、C、H、N、の4元素であり、摂取する栄養源の大部分もまたこの4元素より成っている。この中でHを除いた3元素は短寿命のポジトロンを放射する同位体をもっている。即ち11C(半減期-20分)、13N(半減期-10分)、15O(半減期-2分)である。これらの核種で標識した化合物を人体に投与し、その体内動態を追求することが出来れば、生体内の生化学的機構の解明に役立つし、また多くの疾病は形態的変化を起こす前に、生化学的な乱れや、物質代謝の異常が起ることが予想されるので、疾病の早期診断に役立つことも十分に期待される。 しかしこれらの核種が短寿命であるために、この検査を行うには次の条件が必要である。 これらの核種を産生するサイクロトロンを病院内に設置し、産生された核種を速かにホット・ラボに導き、標識化合物を合成しなければならない。この際合成法も出来るだけ短時間に行える方法を開発し、また従事者の被曝を避けるために自動合成装置を作る必要がある。出来た標識化合物は直ちに被検者に投与され、ポジトロンCTによる測定が行われる。これら一連の装置は、Cyclotron Imaging Complexとも呼ばれ、隣接した場所に設置されて、全ての行動が速かに行える体制が必要である。 現在中野病院で行っている方法を項目別に紹介する。 図1. Baby Cyclotronの鳥瞰図 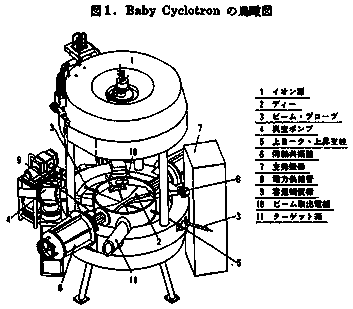 Ⅰ サイクロトロン C、N、Oのような軽い元素の同位体をサイクロトロンで作る場合には、ビーム・エネルギーは低くて十分である。 表1 サイクロトロンの性能と特長 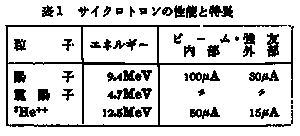 この点に着目して、理化学研究所の唐沢は、11C、13N、15Oと18Fのみを作り得る必要最少限の性能をもつ、超小型サイクロトロンを設計し、日本製鋼所において試作器を完成した。当院にあるのはこの試作器であり、昭和54年3月に設置された。その性能は表1に示す通りであり、鳥瞰図を図1に示す。 普通サイクロトロンで核種を作る場合は、ターゲットが固体である場合が多いが、小型サイクロトロンの場合は、産生する核種が短寿命のため、速かに使用場所に運ぶために、ターゲット物質として気体や液体のような流体を用いる。当院で用いている核種生産の核反応、ターゲット物質を表2に示す。現在最も頻繁に使用されている核種は11Cであるが、その場合ターゲットにN2ガスを、加速粒子にプロトンを用い、14N(Pα)11C、の核反応を利用している。 表2 RI生産 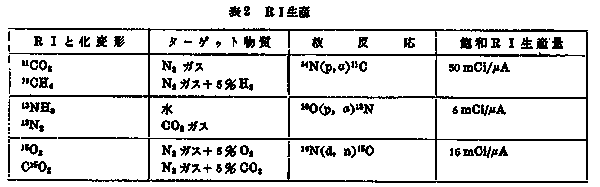 Ⅱ 標識化合物の合成 11C、13N、15Oはいづれも有機化合物の構成元素の同位体であるから、これらの核種を用いて標識化を行うことは、ほとんど全ての有機物について理論的には可能である。しかしこれらの核種は短寿命であるから、きびしい時間的制約をうけるので、合成法の開発は必ずしも容易ではない。 当院で日常臨床に使用されているトレーサーは、11CO2、と11C-グルコースであるが、11CO2はガス体で一次的に生産されるので問題はないが、11C-グルコースは、ガラス容器に11CO2とホーレン草の葉片を封入し、約10分間光照射を行い、11C-グルコースと11C-フルクトースの混合液を作製し使用している。 また現在合成法の開発中のものに、有機合成法による11C-グルコースと11C-マンノースの混合液を作る方法と、沃化メチルからメチオニンを作る方法があり、両者共自動合成装置はほぼ完成しているが、未だ臨床には使用されていない。 Ⅲ ポジトロンCT サイクロトロンで製造されたポジトロン放出核種を用いて生体内放射能分布を測定しようとする場合、ポジトロンCT検出器が直接検出するのはポジトロンではなく、ポジトロンが生体物質を通過して運動エネルギーを消失したのち陰電子と結合して放出される二次放射線(消滅光子)であって、この二次放射線がポジトロン消滅部位から同時に正反2方向に放出されるから、互に180度離れた2個の検出器を1組として同時計測を行うことによってポジトロン消滅部位を正確に測定出来るのである。 表3 ポジトロンCT施行 中枢神経疾患の内訳 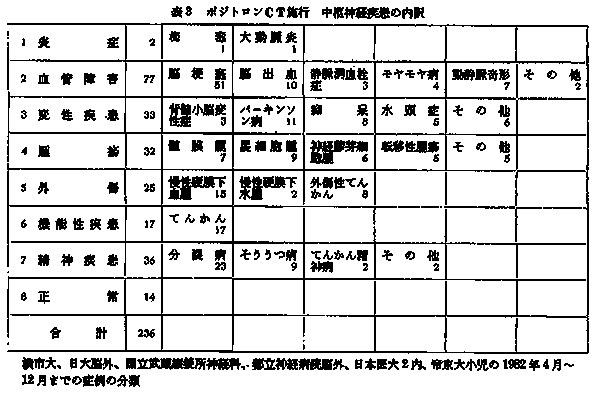 当院に設置されているポジトロンCTは、秋田脳研と島津製作所が開発したもので、頭部専用の検出器で、内径420mmのリング状に64個のNaIを配列したものを1リングとし、2リング配置されていて、3層が同時に撮影出来るようになっている。主コンピューターには、NOVA4/Xが用いられ、プログラム開発にも便利なように128Wの大きさメモリーが用意されている。 Ⅳ 臨床応用 臨床に使用されたトレーサーは主に11CO2と11C-グルコースである。11CO2ガスは1回吸入法により被検者に吸入させ、そのまま約30秒間呼吸停止を行わせた。吸入された11CO2は速かに肺動脈中に移行し、肺毛細管上及び細胞にある酵素Carbonic anhydraseの作用をうけ大部分は血液中の重炭酸塩に入り、一部分はCO2の状態で溶解するものと考えられる。 この状態で脳に到達するので、呼吸停止後30秒~60秒でポジトロンCTの測定を開始すると、脳内の炭酸ガスの分布を測定することが可能である。通常は1回吸入量10mCi、100秒間の測定で2スライスの映像をつくっている。 11C-グルコースは前述の如く、光合成法により作製した11C-グルコースと11C-フルクトースの混合液を、空腹時に被検者に経口的に投与し、その後15~20分を経過してからポジトロンCTによる測定を行った。 この混合液を経口投与後に、ガンマ・カメラおよびウェル型シンチレーションカウンターを用いて、被検者の肝、脳、血液の放射能を測定してみると、肝の放射能は時間の経過と共に低下するが、脳・血液中の放射能は10~15分以降、約1時間に亘って定常状態を保っていた。この状態にある時の脳の11C放射能は主としてプールを形成するアミノ酸に標識されているものと見てよい。11C-フルクトースは脳関門を通過せず、肝でグルコースになるものと考えられる。また頭部軟部組織の放射能は一般には脳内放射能が高いため映像化の防害にならなかった。 この定常状態の時点でポジトロンCTによる測定を行った。 現在迄に実施した中枢神経疾患患者236例の疾患別一覧表が表3である。これらの症例のポジトロン画像は、夫々疾病に応じて特異の所見を呈しているが、その意義の解明は容易ではない。元来ポジトロンCTの特徴は病的状態における体内情報の定量化という点にあるが、現状では未だ成功しておらず、生体内情報をトレーサーの分布のイメージとして表現しているに過ぎないが、このような画像でも正常のパターンと比較しつつ多数の症例を定性的に検討することも意義のあることと思う。X線CTで診断の困難な症例を供覧する。 図2は正常例のパターンである。 症例1(図3)は、24歳女性で側頭葉てんかんの例である。数年前から自動症、不安感などの発作がある。脳波で右側頭葉にスパークがあり、X線CTでは異常がない。ポジトロン像は11C-グルコースで右側頭葉に広汎な集積の低下を認める。 症例2(図4)は、47歳男子、精神分裂症の例である。11C-グルコースで頭部軟部組織に異常に高い集積が認められる。 図2 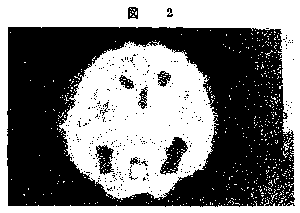 図3 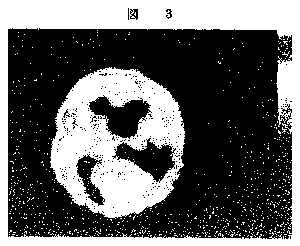 国立武蔵療養所の豊田は、分裂病における特有の所見として、11C-グルコースを投与した場合、11C-グルコースが血液中に出現しているにも拘らず、頭部軟部組織に比して脳内の放射能集積が著しく低いことを指摘している。 症例3(図5)、57歳男子で痴呆(脳血管性)の例である。53歳時脳硬塞により右不全麻痺となる。以後痴呆が進行し、長谷川式スコアーで18点である。X線CTでは、左視床、尾状核頭部、半卵円中心に多発性の硬塞巣が認められた。ポジトロン像では皮質基底核ともびまん性に放射能の集積が低下している。日本医大氏家らは、痴呆の中にも豊田が指適した症候群の存在することを明らかにし、今後の研究課題の1つに取上げている。 以上中野病院で実施している11C-グルコース、11CO2の臨床応用を紹介した。今後測定に関しては定量性を充分に加味し、病態の数量化の試みと、脳の生理的刺激反応に関する研究を進める予定である。 図4 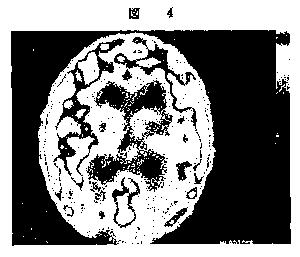 図5 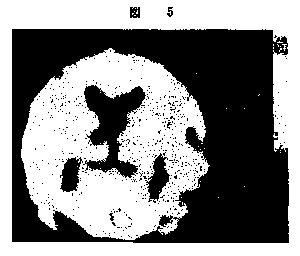 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |