| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
金属材料技術研究所の原子力研究の現況 科学技術庁金属材料技術研究所
1. はじめに
現在、金材技研が実施している原子力研究は、次の5研究テーマであり、各研究テーマの現況において、以下に述べる。 (1) 核融合炉用高抗張力超電導磁石材料に関する研究
(2) 核融合炉第一壁の低Z物質被覆に関する研究
(3) 金属材料の中性子照射損傷のシミュレーション試験研究
(4) 軽水炉用金属材料の腐食疲労及び応力腐食に関する研究
(5) 軽水炉施設の超音波探傷技術に関する研究
2. 核融合炉用高抗張力超電導磁石材料に関する研究
核融合炉用超電導線材は、高磁界下、強応力下及び中性子照射下で大きい臨界電流密度(Jc)を有することが要求されるが、現在、実用化されている超電導線材の中で、Nb-Ti合金系線材では高磁界特性に、Nb3Sn及びV3Ga線材では、耐応力及び耐中性子照射特性に問題があるため、新超電導線材の開発が望まれている。 本研究では、核融合炉用新超電導線材の開発及び応力下での超電導特性の劣化機構の解明を行ってきた。 核融合炉用新超電導線材の開発では、耐中性子照射特性がNb3Snに比べ10倍以上優れ、臨界磁界Hc2(4.2K)が20~26T(テスラ)と極めて高いV2Hf基化合物超電導材料を発見し、線材化法を確立し、実用規模に近い芯数を有するV2(Hf,Zr)基ラーベス型極細多芯線の試作に成功した。この線材は、4.2Kで実用Nb3Sn線材と同等のJcを有するとともに、超流動ヘリウム温度(~2K)でJc及びHc2が著しく増加し、12~18Tの磁界発生用線材として有望であると思われる。また、超流動ヘリウム温度でHc2が著しく向上するHfを添加したNb-Ti合金及びTaを添加したV-Ti合金を開発し、現在、最適線材化条件の検討を行っている。 一方、各種超電導線材の応力特性の研究では、応力下での超電導特性測定法を確立するとともに、Ti等の添加により高磁界特性を改良したNb3Sn線材は、引張応力による歪を加えても、臨界温度(Tc)、臨界磁界(Hc2)、臨界電流密度(Jc)等の臨界特性の劣化が少ないことを見出した。また、V2(Hf,Zr)基ラーベス型極細多芯線では、臨界特性は全く劣化しなかった。(図1)
図1. Nb3Sn、(Nb、Ti)3Sn及びV2(Hf、Zr)線材の歪量によるHc2の変化の比較 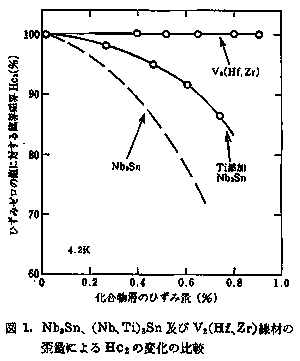 3. 核融合炉第一壁の低Z物質被覆に関する研究
核融合炉におけるプラズマ-壁相互作用によるプラズマ温度低下を軽減させるに必要な第一壁金属材料の低Z物質(Z:原子番号)被覆技術を確立し、優れた被覆材料を開発することを目的として、被覆法(化学蒸着、イオンプレーティング、マグネトロンスパッタリング)及び基質材料(モリブデン、黒鉛)の相違が材料の耐熱特性等に与える影響を系統的に調べた。 被覆法の違いでは、化学蒸着法によるTiC膜が結晶性、TiとCの結合性及び高温高真空中での耐蒸発特性に優れている。しかし、化学蒸着法によるモリブデン基材上のTiC膜は、1,800℃以上の高温試験で蒸発による重量減少を呈するとともに、被覆処理温度が1,100℃と高いため、モリブデンの再結晶による脆化の傾向が確認された。一方、化学蒸着法による黒鉛基材上のTiC膜では、高温試験による蒸発が全く観測されない。これは、TiC膜とモリブデンまたは黒鉛基材との相互作用の違いによることを明らかにした。(図2)また、マグネトロンスパッタ法によるモリブデン及び黒鉛基材上のTiC膜について、D+イオン照射(5×1018D+/cm2)を行った結果、D2ブリスタ発生が見られた。この現象は、化学蒸着法、イオンプレーティング法で被覆した材料では見られない。マグネトロンスパッタ法によるTiC膜は、膜の成長時の残留応力、加熱時のArブリスタ発生などのAr含有に起因する特性が現われるため、この特性の制御技術の研究を行っている。 図2. 各被覆法によるTiC膜と基材との相互作用による蒸発特性 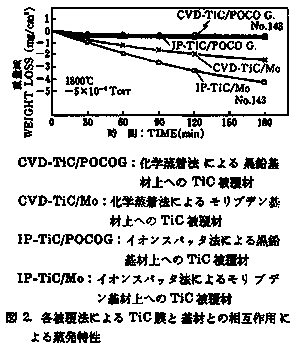 一方、日本原子力研究所との共同研究により、TiC膜の1.4keVH+スパッタによる表面形態及び化学組成の変化等を調べるとともに、トカマク装置実機によるTiC被履材の評価のため、スイス、チューリッヒ大学と協力して、TEXTOR計画用試料を送付して、実験準備を進めている。 今後は、耐エロージョン特性、水素リサイクリング特性、再蒸着及び耐中性子照射損傷特性等について研究を行う計画である。 4. 金属材料の中性子照射損傷シミュレーション試験研究
本研究では、核融合炉及び高速増殖炉の炉心構造材料の中性子照射損傷を各種のシミュレーション試験法によって評価する技術を確立することを目的とし、それらシミュレーション試験により、照射下のクリープ特性の測定、ボイドスエリングの把握及びヘリウム脆化の解明等を行い、新材料開発に反映させる。 照射下クリープ特性の研究では、ステンレス鋼(316鋼)及びFe-25Ni-15Cr-Ti系合金について、照射クリープ試験装置ターゲット部試作機を用いた試験を行った結果、高Ni化とTi添加によって照射クリープ速度が低下することを確認した。なお、今後は、軽イオン照射下クリープ試験装置を完成させ、系統的な研究を実施する予定である。 ボイドスエリングの研究では、プロトン照射後のFe-25Ni-15Cr-Ti系合金について調査した結果、結晶粒界に沿って無析出帯が形成され、この無析出帯にボイドが形成され易いことが判明した。この領域でTi濃度が低下しており、照射がTi濃度の低下を促進させること及びTi濃度が0.6%以下になるとボイドが形成されることを見出した。現在、この領域におけるTi濃度の確保等の方策について、研究を実施している。 ヘリウム脆化の研究では、Fe-16Ni-15Cr系合金等について、理研のサイクロトロンによるヘリウム注入を行い、ヘリウム脆化機構の解明及びヘリウム脆化に対する材料面からの検討を行った結果、耐ヘリウム脆化に対しては、合金中にTiCを微細分散させることが必要であり、その方策として、高温での溶体化処理が有効であることを見出した。 5. 軽水炉用金属材料の腐食疲労及び応力腐食に関する研究
原子炉の圧力容器及び配管等の機器の供用中検査基準として、ASME Code Sec.XIがあるが、我が国の安全審査における判断基準のデータベースとして、国産材料に関する材料データの蓄積が必要である。 本研究では、ビーチマーク法及びコンプライアンス法等の亀裂長さ測定法の検討を行った上で、BWR型軽水炉を模擬した288℃、80気圧(溶存酸素濃度0.1ppm)の高温高圧水中下における圧力容器鋼の疲労亀裂伝播試験を実施し、上記条件下における国産材料の亀裂伝播速度は、ASME Code Sec XIに示される参照曲線に比較して低く、安全側にあることが判明した。また、亀裂伝播速度は温度、溶存酸素濃度の環境条件及び応力比応力波形等の力学的条件に支配されるため、これら影響因子の検討を行うとともに、設計基準としてのASME Code Sec Ⅲの疲労寿命曲線に関して、国産材料の疲労寿命特性に及ぼす環境効果の検討とデータベースの確立を目指した圧力容器鋼等の環境中疲労寿命試験を実施していく。 一方、BWR配管溶接熱影響部のステンレス鋼の応力腐食割れ挙動については、軽水炉の起動・停止等の高温水の温度(T)、溶存酸素(DO)及び付荷応力(σz′)を組合せた8時間周期の繰返し変化を与えた場合には、図3(b)に示す昇温降温が繰り返されると粒界割れが発生し易く、図3(f)に示す昇温降温の繰返しと溶存酸素の変化があると、図3(b)の溶存酸素が8ppmで一定のときよりも粒界割れが発生し易いことを確認した。このことは、実際の軽水炉の起動時には、溶存酸素を少なくする脱気運転が必要であること及び熱膨張による付加応力の増加程度では配管の応力腐食割れを加速しないことを示していると思われる。 更に、ステンレス鋼以外のニッケル鋼のPWR型軽水炉一次冷却系における応力腐食割れについても調査し、粒界炭化物の析出状況と応力腐食割れの関係を明確にした。 図3. 温度、溶存酸素及び応力の繰返し条件と応力腐食割れの関係 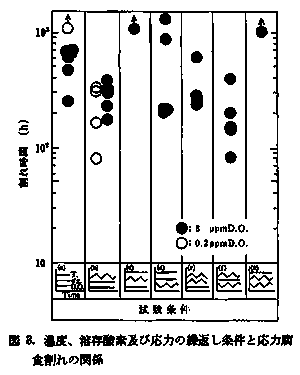 6. 軽水炉施設の超音波探傷技術に関する研究
軽水炉圧力容器の使用中に内面から発生または成長した亀裂の位置及び寸法を、圧力容器の外面から高精度で定量的に測定する超音波探傷技術を確立することを目的として、研究を実施している。 圧力容器内面は、ステンレス鋼がオーバレイされているため、その粗大組織に起因する減衰及び雑音信号が亀裂の定量的測定の支障となる。このため、オーバレイ中における超音波の伝播速度及び減衰の方位依存性を明らかにした。また、圧力容器内面の小さい亀裂を感度良く検出することを目的として、大形点集束斜角探触子を試作し、能率良く超音波を送受信することに成功するとともに、縦波及び横波の利害得失を実験的に検討し、パルス幅の狭い縦波超音波の使用が、オーバレイ中の埋れた亀裂モデルの検出に有効であることを明確にした。 更に、信号処理によって、亀裂の検出性及び識別性を改良する方法を検討し、マッピング法が亀裂の位慣及び寸法の定量的評価に有効であることが判明した。 今後は、更に、探触子の改良及び信号処理方法について研究を行う予定である。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |