| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
原子炉解体技術開発 日本原子力研究所
Ⅰ 原子炉解体技術開発の必要性 原子力発電の進展につれ、原子力発電所の立地問題にも関連して、近年原子炉の廃止措置の問題が国内外において論議されるようになり、原子炉の設置及び運転の場合と同様に運転終了後の措置についても適切な対策を講じておくことが、原子力開発利用の推進の観点から重要になってきた。 原子力委員会では、昭和55年11月廃炉対策専門部会を設置して、原子炉の廃止措置に係る重要事項について審議を進め、昭和57年3月その結果を得た。昭和57年6月に決定された「原子力開発利用長期計画」では、原子炉の廃止措置については、「安全の確保を前提に地域社会との協調を図りつつ進めるべきであり、さらに敷地を原子力発電所用地として引き続き有効に利用することが重要である。」とされている。また、「措置の方式については、原子炉の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤去することを原則とし、個別には必要に応じ適当な密閉管理又は遮蔽隔離の期間を経るなど諸状況を総合的に判断して決めるものとする。」としている。 さらに、原子炉の廃止作業は、現時点でも既存技術又はその改良により対応できると考えられるが、作業者の受ける放射線量の低減等安全性の一層の向上を図るとともに費用の軽減を図る観点から、解体技術、除染技術、遠隔操作技術等を中心に、既存技術の実証・改良及び新技術の開発を進めることが望まれる。」とされている。 日本原子力研究所では、このような国の考え方に沿って原子炉解体技術の開発を進めている。 Ⅱ 原子炉解体技術開発の概要と現状 原研では、将来商業用発電炉の解体撤去に際して必要と想定される技術開発を行って、その成果をJPDRに適用して解体撤去する構想の下に、科学技術庁からの受託事業として開発を進めている。以下にその概要と現状について述べる。 1. 解体システムエンジニアリングの開発
開発概要:原子炉解体に必要な要素技術の開発作業る分解して作業単位を明らかにし、原子炉解体技術開発システムモデルを作成する。また、原子炉解体についても全ての作業単位を明らかにするとともに、この作業単位の相互関連、所要日程、費用、リスクに関する検討を行って原子炉解体システムモデルを作成する。さらにJPDRの解体実地試験による検証によってシステムモデルの修正、改良を行う。 開発現状:ワークブレークダウンストラクチャー技法を用いて、原子炉解体作業の分解、開発を要する要素技術の抽出を行い、ネットワーク図を作成することによって、開発行程及びクリティカルパスを検討している。また、原子炉解体システムモデルの作成に必要なコスト算定手法、コスト因子に係る調査並びに原子炉施設関連データの収集整備をすすめている。 2. 内蔵放射能評価技術の開発
開発概要:原子炉解体における除染、解体、廃棄物処理処分計画の立案に資するため計算による放射能評価技術と測定による放射能評価技術を開発し、両者を組み合せて、原子炉施設内の内蔵放射能量を効率的に評価できる技術の開発を行う。 開発現状:計算による放射能評価技術の開発では、原子炉からの中性子による放射化放射能を評価するため、Sn及びGRAYコードの改良、群定数ライブラリーの作成並びにこれらのシステム化を行っており、測定値に基づいて検証・改良することとしている。また、原子炉一次系のクラッドによる放射能汚染量の計算コード作成を進めている。 なお、既存のコードを用いてJPDRの内蔵放射能の概略計算を行った結果、昭和57年12月時点の値として約8,000Ciが得られた。 測定による放射能評価技術の開発では、炉内構造物、圧力容器及びコンクリート遮蔽体などについて試料を採取し、放射能測定及び組成分析などを行っている。コンクリート遮蔽体から約3m長さの棒状試料を6本採取し放射能分布を測定した結果、炉心中央高さの試料で内壁側から約1mの附近まで放射化していることが認められた。 3. 配管系内部放射能非破壊測定技術の開発
開発概要:原子炉一次系配管内部の放射能の核種、量及び状態を配管の外側から非破壊で定量的に測定するための技術を開発する。 開発現状:γ線検出部、スキャンニング装置、超小型信号増幅系、双方向多重テレメーター装置及びデータ解析装置等からなる現場測定実験装置を製作し、構成機器の機能試験を行っている。γ線検出部の設計に当っては、Geガンマ線検出器の冷却に高圧ガスの断熱膨張を利用した冷却素子を使用し、従来の液体窒素冷却方式に比較し大幅な小型化と軽量化を図った。 また、本装置を用いて模擬実験を行うため配管の内部にRIを封入した原子炉一次系模擬配管の製作を進めている。 4. 解体工法・解体機器の開発
開発概要:原子炉圧力容器の解体技術としてはアークソー、炉内構造物にはプラズマアーク切断機、圧力容器接続配管にはディスクカッター及び成型爆薬の各技術について、またコンクリート遮蔽体の解体技術として制御爆破法、機械的工法及び熱的工法について、試験片の切断試験及び模擬構造物の解体試験を行って解体性能の向上及び解体工法の確立を図る。さらに解体時に発生するヒューム、粉じんなどへの対策を明らかにする。 開発現状:鋼構造物及びコンクリート構造物に対する各種解体工法・解体機器について調査し技術現状、解体への適用性及び技術課題を明らかにした。装置の調査結果を反映させ、鋼構造物については、200mm厚さの鋼板の切断を目標とするアークソー切断試験装置、80mm厚さのステンレス鋼を切断可能なプラズマアーク切断試験装置及び直径300mm、厚さ7mm~33mmの配管を切断可能なディスクカッター試験装置の製作を進めている。またコンクリート構造物については、コンクリートの切断深さ400mmのカッター及び水平方向500mm、垂直方向900mmの穿孔が可能なコアボーリング機を塔載するコンクリート構造物機械的切断試験装置の製作も進めている。制御爆破法については取扱う爆薬の種類、量に関する目安を得るための基礎実験を了え、コンクリート遮蔽体を模擬した構造物を用いての解体試験の準備を進めている。 5. 解体関連除染技術の開発
開発概要:解体作業被曝の低減化と作業の容易化のために行う解体前化学除染では、各種の除染試験を段階的に行い、希薄液法及び濃厚液法の対比評価試験を通して各化学除染の特性を把握し、除染作業性及び廃液処理の容易性をも考慮した除染技術を開発する。また、熱交換器タンク、プール等の除染並びにコンクリート汚染表面の研削・破砕除去に適用する除染装置等を試作し、実用化技術を開発する。さらに解体後除染に関しては、浸漬化学除染法、電気化学的除染法などの除染技術を開発する。 開発現状:化学除染基礎試験として、JPDR一次系配管から採取した試料を用いてクラッドの性状分析などを行ったほか、JPDR一次系の解体前化学除染に希薄液除染法及び濃厚液除染法を適用する場合の除染システムの概念設計を行っている。また流動除染試験が可能な基礎試験装置や化学除染廃液前処理試験装置等も完成し、それぞれ試験を開始した。さらに、JPDR一次手配管の一部を用いて系統別化学除染試験を行うため、JPDR強制循環系統と原子炉冷却水浄化系統に試験装置を設置して試験運転を行っている。 6. 解体廃棄物の処理、保管及び処分技術の開発
開発概要:原子炉の解体における廃棄物の管理システムを検討評価するとともに、保管・処分用コンテナ・パッケージの開発、配管等の切断・高圧縮による減容処理技術及びコンクリート解体物等の固化処理技術の開発を行う。 開発現状:解体廃棄物管理システムについては廃棄物の発生から保管・処分に至る廃棄物管理システムを作成し発生量、輸送回数及び保管・処分量等を試算し、本システムの予備的な検討評価を行っている。保管処分用コンテナ・パッケージ技術については、高放射化した構造物を対象とした高レベル廃棄物用コンテナの基本設計を行った。またこの基本設計に基づきコンテナの安全評価試験のための鋳鉄製及びコンクリート製の1/3縮尺モデルコンテナの試作を進めている。 賦容処理技術については、配管・機器等を対象に、切断装置(800トン・ギロチンプレス)及び高圧縮装置(850トンプレス)を用いて切断力及び圧縮減容比等に関する基礎試験を行った。固化処理技術についてはコンクリート解体物の固化方式を選定するために、模擬コンクリート破砕物を用いてプレバクト固化法等によるモルタルの強度及びコンクリートの粒径の大きさ等に関する基礎試験を進めている。 7. 解体に係る放射線管理技術の開発
開発概要:解体作業環境のもとで、作業者の安全を確保し、被曝の低減化を図るとともに、作業を効率よく実施するための放射線管理用機器の開発を行う。また、解体作業に伴い大量に発生する放射能レベルが極めて低い廃棄物の環境影響の評価解析法を確立する。 開発現状:電離箱型検出器を用い、0.1~1000R/hの範囲の線量率の遠隔操作による測定が可能な空中高放射線量率測定装置を製作した。また、炉内構造物等の線量率測定のため、水深10mまで使用可能な防水型電離箱を用い、測定範囲10~105R/hの水中高放射線量率測定装置の製作も進めている。 管理区域から大量かつ頻繁に搬出される作業用機器、工具類の表面汚染密度を効率的に測定するため、表面汚染密度検出下限値1×10-5μCi/cm2及び放射能量の検出下限値1×10-3μCiを目標とした大面積ガスフローカウンターを有する搬出物品自動表面汚染検査装置を製作した。また、この装置にプラスチックシンチレータまたはNaI(Tl)シンチレータを組み込み、一体化して搬出物の表面及び内面の汚染を同時に検査できる搬出物内面汚染検査装置の製作を進めている。 8. 解体遠隔操作技術の開発
開発概要:原子炉解体作業における高放射線環境下での作業を遠隔操作で行い、作業員の放射線被曝の低減化をはかるたるため耐放射線性、耐水性、耐雑音性などを備えた軽作業及び重作業用の半自動式作業装置(作業ロボット)を含む遠隔操作システムの開発を行う。 開発現状:無限軌道走行式台車に7自由度の電動式マニプレータ、テレビカメラ等を積載した誘導制御装置と、それらの遠隔制御用通信制御装置を1つのシステムとしてまとめた遠隔操作実験装置を製作した。また、原子炉圧力容器のような円箇形構造物内においてマニプレータを用いた遠隔操作作業を行う際、マニプレータの足場を支持固定する方法を実験するため定場固定実験装置の製作を進めている。本装置の設計に当っては半径方向に独立に伸縮可能な3本の脚部を有し、それらの脚で円筒形構造物の内側から壁面を3方向に押して支持する方法と円筒壁の端を掴んで支持する方法について水中試験ができるように考慮した。 Ⅲ 原子炉解体技術開発スケジュール 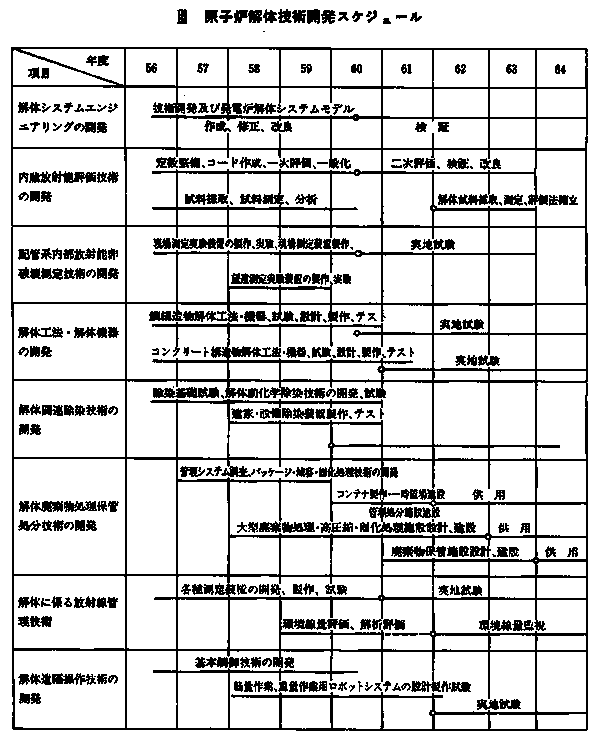 Ⅳ JPDRの解体について 1. 経緯
昭和57年12月9日付けをもって日本原子力研究所は、原子炉等規制法第38条第1項の規定に基づき、科学技術庁長官あて東海研究所原子炉施設(JPDR)の解体届を提出した。 JPDRの解体は、昭和57年6月30日原子力委員会が定めた「原子力開発利用長期計画」において「将来の商業用発電炉の廃止措置において活用し得る解体技術等の開発と実地試験を行うこととする」ものとして位置付けられているものであるが日本原子力研究所は、JPDRを当該技術開発等に供するに当たり、その実施が原子炉等規制法に定める原子炉の解体に該当するものであるため、着手に先立ち解体の届出を行ったものである。 2. 解体届の構成及び解体スケジュール
(1) 解体の基本方針
JPDRの解体は、全工程を、2段階に分けられ、第1段階においては、原子炉の解体に必要な技術開発を行い、第2段階においては、その成果を反映させて本格的な解体を実施することとしている。 本格的な解体を行う第2段階をさらに3期に区分する。 第1期においては、狭隘な原子炉格納容器内での撤去作業を容易にするため、原子炉周辺機器及び炉内構造物の一部を撤去する。また、タービン建家及びダンプコンデンサ建家の設備機器等を撤去する。 第2期においては、原子炉圧力容器及びこれと一体になった炉内構造物を撤去し、その後に原子炉格納容器及びその他の建家を撤去する。 第3期においては、汚染のないことを確認した跡地を整地する。 なお、第2段階の本格的解体については、解体着手に先立ち今回提出した解体届の記載事項を見直して変更届を提出することとしている。 (2) 解体届の構成
① 名称及び住所並びに代表者の氏名
② 解体に係る事業所の名称及び所在地
③ 解体の方法及び工事工程表
④ 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の処分の方法
(以下、添付書類)
⑤ 解体の方法に関する説明書
⑥ 工事工程に関する説明書
⑦ 放射能量及び解体廃棄物の推定並びに放射性廃棄物の処理処分の概要に関する説明書
⑧ 安全性に関する説明書
(3) 解体のスケジュール
解体は、昭和58年1月に着手され、昭和60年度末頃までを第1段階として原子炉の解体技術の開発を行い、その後第2段階に移行して本格的解体を行い、昭和64年度末頃に整地が完了する予定となっている。 3. 解体届の取扱いと今後の対応
本解体については、解体工事の詳細及び進捗状況の把握に資するため、一定期間ごとに工事方法等明細書及び工事工程明細表を提出するほか、東海研究所原子炉施設保安規定に所要の変更を行い、解体中必要に応じ原子炉等規制法第68条に基づく立入検査が実施されるなど、解体着手後解体完了まで原子炉等規制法に規定する原子炉施設として所要の規制が行なわれることとなっている。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |