| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
総合エネルギー調査会原子力部会報告書(Ⅲ) -プルトニウム利用の今後のあり方について-
昭和57年9月27日
総合エネルギー調査会原子力部会
1. まえがき
① 石油を中心とする国際エネルギー情勢は依然として厳しいため、エネルギーの海外依存度及び石油依存度が高く、脆弱なエネルギー供給構造を持つ我が国にとって石油代替エネルギー開発導入促進は急務であり、その中で原子力の果たすべき役割は極めて大きい。 ② 当部会は、昨年6月に、原子力をめぐる内外の諸情勢を踏まえ、原子力開発の基本的方向、核燃料サイクルの自立化のための諸方策等について、原子力部会報告(Ⅰ)として取りまとめた。また更に、同年8月には、原子力発電の立地の推進のための諸方策について、原子力部会報告(Ⅱ)として報告を行ったものである。 ③ 以上の報告の中にも示されているように、我が国の原子力発電は、今後も当分の間は軽水炉に主体が置かれることとなるが、長期的にウラン資源の制約から開放され、原子力発電規模を長期にわたって拡大していくためには、使用済燃料を再処理し、それにより再生産されるウラン及びプルトニウムを有効に利用していくことが必要である。 ④ このため、プルトニウムを燃料とし、かつ消費した以上のプルトニウムを生成する高速増殖炉を開発し利用していくことが、我が国にとってエネルギー資源の自立化を図る上からも最善の方策である。しかしながら、高速増殖炉が実用化するまでの間及びそれ以降においてもその導入量によっては相当量のプルトニウムの蓄積が予想されることとなるため、プルトニウムを熱中性子炉(軽水炉及び新型転換炉)にリサイクルしていくことが重要な課題である。更に高速増殖炉及び熱中性子炉へのプルトニウム利用を進めていく上で必要となる混合酸化物(MOX)燃料(注)の製造、MOX燃料の再処理等の燃料サイクルについても、その確立を図っていくことが重要である。 ⑤ このような点から、当部会は再処理による回収されるプルトニウム等の利用のあり方、具体的方策等について昨年12月から検討を行ってきた。検討に当っては、当部会の基本政策小委員会、同専門委員会に加え、プルトニウム・リサイクル小委員会を設け、特に今後の重要なプルトニウム利用方策のひとつであり、これまで比較的検討がなされていなかった軽水炉によるプルトニウム利用に重点をおいて、プルトニウムのリサイクルのあり方について精力的に審議した。 ⑥ その結果、プルトニウム利用の今後のあり方、具体的方策等について、以下のような取りまとめを行ったのでここに原子力部会報告(Ⅲ)として報告する。 (注)
混合酸化物(MOX)燃料:酸化ウラン及び酸化プルトニウムを混合した燃料
2. 再処理・プルトニウム利用をめぐる環境
(1) INFCE(国際核燃料サイクル評価)とポストINFCEの動向
① カーター前米大統領の提唱に基づき、1977年10月から1980年2月までの間行われたINFCEにおいては、原子力の平和利用と核不拡散の両立という課題について詳細な検討がなされ、その結果「核不拡散を確保しつつ原子力の平和利用を推進することが可能であり、また、そうすべきである。」との我が国の基本的立場に概ね沿った方向で結論がまとめられた。 ② 核不拡散を担保しつつ再処理・プルトニウム利用を推進するという我が国はじめ、仏、英、西独等の立場と、これらを核不拡散の観点からできる限り延期させたいという米国の立場との対比を中心に議論が展開されたが、その結論のうち、再処理・プルトニウム利用に関する重要な記述は以下の通りである。 (イ) ウラン資源は、必要な探査と投資が行われれば2000年までの需要を満たすことは困難ではない。また、原子力発電規模がINFCEの低ケースで成長すれば、2025年までの需要を満たすことができようが、新型炉技術の実用化は、これをさらに確実なものとする。 (ロ) 大規模な原子力発電計画を有する国が濃縮、再処理等核燃料サイクル施設について一国単位の大規模施設を建設することは意義がある。 (ハ) 技術改良により、軽水炉では10~15%、重水炉では30%のウラン節約の可能性がある。既存の技術による軽水炉のプルトニウム・リサイクルは、既存のワンス・スルーに比べ35~40%のウラン節約となりうる。重水炉ではより以上の節約となろう。 (ニ) 再処理によるウラン及びプルトニウムが軽水炉にリサイクルされるならば、経済的な利点はそれ程大きくないが、ある国々では、それをエネルギー自立と供給保証に役立つものと考えている。他方、高速増殖炉の経済上、供給保証上の利点は大きい。 (ホ) 再処理・プルトニウム取扱技術に関する基本的な技術は確立している。 (ヘ) 核燃料の再移転及び再処理の事前同意権については、燃料の供給保証の観点からその行使の基準を確立すべきであり、また事前同意権は予見しうる形でかつ消費国の政策と個別の事情を考慮する形で、さらには両当事者間で持たれていた理解に合致する形で行使されるべきである。 (ト) 国際プルトニウム貯蔵(IPS)は、もし、広く適用可能でかつ無差別的な条件についての国際間の合意が成立するものであれば、核不拡散及び供給保証の面で重要な貢献を行いうる。 ③ 以上のようなINFCEでの成果は、今後はいわゆるポストINFCEとしての国際プルトニウム貯蔵(IPS)、供給保証委員会(CAS)及び国際使用済燃料管理(ISFM)等の多国間の場での制度的検討や、二国間関係の場で実現されていくこととなろう。我が国としても、核不拡散を担保しつつ、再処理・プルトニウム利用を進めるための制度的検討に積極的かつ主体的に取り組んでいくことが必要である。 (2) 多国間及び二国間協議の動向
(i) 国際プルトニウム貯蔵(IPS)
ポストINFCEにおける多国間の制度的検討のなかでもIPSは、今後プルトニウム利用を本格的に進めようとしている我が国にとって極めて重要な関係を有する国際制度であり、その概要及び検討状況は次のとおりである。 (イ) IPSは、IAEA憲章に基づき、再処理により分離されたプルトニウムのうち、余剰なプルトニウムをIAEAに預託し、国際的な管理の下で貯蔵することにより、核拡散を防止しつつ、プルトニウム利用の円滑化を図ろうとする構想である。 (ロ) これまでの議論においては、プルトニウムの登録・預託、プルトニウムの払出手続、使用の検証等について、現行の保障措置制度との整合性を図りつつ検討が進められているところである。 (ハ) 我が国としては、IPSが再処理・プルトニウム利用に際して、核不拡散上十分に機能するようにすべきであり、また同時にその内容が過度に複雑となり、再処理・プルトニウム利用の円滑な実施が妨げられることとならないような合理的な制度作りに貢献していく必要がある。 (ⅱ) 二国間協議の動向
① 米国のレーガン政権は、核不拡散政策を基本としつつ、進んだ原子力計画を有し、核拡散の危険のない国に対しては再処理等に関する事前同意権の行使を予見可能性のあるものにするために、包括的な扱いとする方針を明らかにしてきている。二国間協定によるケース・バイ・ケースの諸規定を予見可能性ある形で行使することが供給保証の観点からも必要であるという方向は前述のINFCEの結論のひとつでもあり、我が国としてもそのような方向を踏まえて、原子力協定を締結しているウラン資源供給国等との間の二国間協議を進めてきた。 ② 本年8月17日発効した日豪原子力改正協定においては、再処理、再処理のための第三国移転等について包括的同意を与えるために、いわゆる「プログラム・アプローチ」が採用され、我が国が関係各国と再処理協議を進める上での先例となった。また、カナダとも現行日加協定を前提に独自の包括的同意方式について実質合意に達したところである。更に、米国との間でも、日米再処理問題の恒久的解決を図るための協議が進められているところであり、我が国としては、この協議にあたっては、核不拡散を担保しつつ、我が国におけるプルトニウム利用が円滑に進められるよう対処していく必要がある。 (3) 再処理・プルトニウム利用をめぐる主要国の政策
(i)米国
① カーター前政権においては商業再処理工場の凍結、高速増殖炉開発計画に係る予算支出の削減等の政策を打ち出すとともに、対外原子力政策においても、核不拡散政策を画一的に適用した。 ② これに対し、レーガン政権は、米国内での商業用再処理の禁止を解いて民営により再処理を進めていく方針を打ち出すとともに高速増殖炉についてもその開発促進を明確にした。 また、対外的にも進んだ原子力計画を有し、核拡散の危険のない国での再処理や高速増殖炉の開発は妨げないとして、カーター前政権より弾力的姿勢を示した。しかし、議会の一部には依然として核不拡散政策強化の意見も少なくない。 (ⅱ) 西独
① 西独では、再処理・プルトニウム利用を原子力開発の基本方針とし、従来から高速増殖炉の開発及び軽水炉によるプルトニウム利用技術の開発を進めてきている。 ② しかしながら、近年になり軽水炉から高速増殖炉の時代へ移行する期間が、従来考えられていたものより相当延びることが予想されており、この結果、この期間において軽水炉によるプルトニウム利用の重要性が増しつつある。 ③ したがって、西独のプルトニウム利用政策は、引き続き高速増殖炉の開発を進めるとともに、当面余剰となるプルトニウムは積極的に軽水炉に利用していくことを方針としており、このため現在、電力会社が共同して実用化試験を計画しているところである。 (ⅲ) 仏国及び英国
① 仏国は、従来から高速増殖炉開発計画を進めてきており、プルトニウムは全て高速増殖炉に利用する計画である。現在、高速増殖炉実証炉スーパーフェニックス(電気出力120万kW)を建設中であるが、ミッテラン政権はスーパーフェニックス以降の政策決定は同炉の完成後に行うこととしている。また、高速増殖炉の核燃料サイクルについては、再処理パイロットプラント(TOR)を建設中である。 ② 英国では、仏国と同様、プルトニウム利用の開発研究の主目標を高速増殖炉開発に向けている。現在、電気出力130万kWの実証炉CDFRの設計を行っているが、電力需要、ウラン需給等からみて、高速増殖炉を早急に開発するインセンティブは大きくないと考えられている。 (4) ウラン需給展望
① 世界のウラン需要量とウラン資源量の関係は、OECD/NEA及びIAEAの最近の報告によれば、30ドル/ポンドU3O8以下のコストで開発が可能なものは、確認されている埋蔵量だけでも2000年過ぎまでの需要がまかなえることが想定されており、また推定される埋蔵量を加えると2010年頃までの需要をまかなうことが可能とされている。 ② 上記のようにウラン資源量にはかなりの余裕があると考えられるが、現在のウラン鉱山の開発状況から推察すれば、現在稼動中の鉱山の産出量では1980年代末頃までの需要しか満たすことができない。更に建設中及び開発中の鉱山を含めても、原子力開発がいわゆる低ケースの場合でさえ、1990年代半ばまでに需給バランスがくずれるものと考えられる。 したがって、1990年代以降のウラン供給は、今後探鉱開発される新規鉱山に大きく依存せざるを得ないこととなるが、現在、ウラン市況の低迷を反映して世界的に探鉱開発意欲が低下している現実とウラン鉱山開発のリードタイムが長いことを考慮すると、1990年以降には、ウラン需給バランスがくずれウラン価格が上昇し始めることも想定される。 このような状況に対処するため、我が国を始めとして各国ともウラン資源の探鉱開発等を積極的に推進して行く必要があるが、なお、1990年代以降のウラン供給及びウラン価格については、不安定な側面が大きいと言わざるを得ない。 3 我が国における再処理・プルトニウム利用の基本方針
(1) 再処理の目的及び基本方針
① ウラン資源に乏しい我が国にとっては、原子力発電所から生ずる使用済燃料を再処理し、それにより再生産されるウラン及びプルトニウムを利用することによってウラン資源の有効利用等を図ることが必要不可欠である。 ② すなわち我が国はウラン資源を全面的に海外に依存しているため、エネルギー・セキュリティ確保の観点からできる限り早期に我が国自身の自立した核燃料サイクルを確立することが是非とも必要であり、また、再処理によって回収されるウラン及びプルトニウムの利用により、天然ウラン及び濃縮役務の所要量を低減させることも極めて重要な課題である。 ③ 更に、再処理は、使用済燃料中に含まれる高レベル放射性廃棄物をより安全かつコンパクトな形で管理するという観点からも極めて重要である。 ④ このため、我が国の原子力発電所から生ずる使用済燃料は、全て再処理することを基本方針とし、1990年度頃の運転開始を目途に大型商業再処理工場の建設推進を図っているところである。 それまでの当面の間は、国内の動力炉・核燃料開発事業団東海再処理工場の運転及び英仏への海外委託により対応していくこととしている。 (2) プルトニウム利用の意義
① プルトニウム利用を進めることは、それが単にウラン資源の節約となるだけでなく、再処理により回収されるプルトニウム等をいわば国産エネルギー資源として利用することができるため、海外依存度の低減及び燃料源の多様化につながり、エネルギー・セキュリティ確保の観点から重要といえる。 ② 我が国は、原子力発電所から生ずる使用済燃料は全て再処理することを基本方針としているため、生成したプルトニウムを適切な管理のもとに利用していくことが、核不拡散上からも最善の方策である。 (3) プルトニウム早期利用の必要性
① プルトニウムを高速増殖炉にリサイクルすれば、同一量のウラン資源を熱中性子炉に利用する場合に比べて数十倍のエネルギーを取り出すことが可能であり、エネルギー資源の自立化を図る上からも、プルトニウムの高速増殖炉へのリサイクルが最善の方策である。しかしながら、高速増殖炉は、現在原型炉着工前の段階にあり、本格的実用化は2010年以降となるものと考えられている。 プルトニウムを高速増殖炉に利用するまでの間、長期貯蔵せずにMOX燃料に加工し、熱中性子炉に利用していくことは、それ自体、核不拡散努力の一環である。同時に、このことは、我が国が原子力先進国として、来たるべき本格的プルトニウム利用時代に備えて、核不拡散を担保しつつ円滑なプルトニウム利用を行う前例を用意するという意味から望ましい。 ② また、高速増殖炉の本格的実用化時期には、プルトニウム大量加工等のプルトニウム取扱技術が不可欠となるが、この技術の定着までには段階的開発を経ねばならず、高速増殖炉の本格的導入前に大量プルトニウム取扱技術を確立しておく必要がある。 ③ さらに、プルトニウムをそのまま高速増殖炉本格的実用化時期までの間、長期貯蔵しておくことは、経済的にも大きな負担となるだけでなく、プルトニウム中のプルトニウム241が崩壊して非分裂性のアメリシウム241に変わり品質が低下するとともに、その取扱いも複雑になるという問題がある。 (4) プルトニウム利用の方針
① このため、プルトニウムの高速増殖炉へのリサイクルが長期的な原子力開発の基本路線であるが、高速増殖炉が実用化するまでの間は、これを熱中性子炉にリサイクルすることによりプルトニウムの早期利用を進めることとする。 ② 熱中性子炉への利用方法としては、軽水炉によるプルトニウム利用及び新型転換炉が考えられる。 軽水炉によるプルトニウム利用については、1990年代における我が国のプルトニウム利用の有力な手段として位置付けることができ、今後実証計画等を進めることにより、軽水炉によるプルトニウム利用の本格化が時宜を失せず可能となるよう開発を進めていく必要がある。 一方、新型転換炉は、我が国独自で開発を行っているプルトニウム利用のための新型炉であり、軽水炉によるプルトニウム利用とともにプルトニウム利用の有力な手段である。今後1990年代初め頃の運開を目途に実証炉の建設を行い、その実用化を目指した開発を進めていく必要がある。 4. 軽水炉によるプルトニウム利用(プルサーマル)
軽水炉は、低濃縮ウランを燃料として、ウラン235の核分裂によるエネルギーで発電するものであるが、プルサーマルは、プルトニウムを軽水炉の燃料の一部として活用する方法である。 我が国は、これまでに軽水炉においてプルトニウムを燃料として照射した経験は有してないが、海外においては、プルサーマルについて種々の照射実績を有し、技術的にはほぼ問題のないことが報告されている。 (1) プルサーマルの特性
① プルサーマルは、既設の軽水炉の設備及び運転方法をほとんど変更することなくそのまま使用できる。この場合、全体の燃料のうち30~40%にMOX燃料を使用することとなろう。 ② また、MOX燃料集合体とウラン燃料集合体との互換性により、プルトニウム需給バランス等に応じて柔軟な対応が可能である。 ③ 軽水炉は、その運転・補修の実績が多く、機器設備の信頼性も高い。また、海外においては、MOX燃料の照射実績が豊富であり、これまで、西独、アメリカ、イタリア、ベルギー、オランダ等での実例が報告されている。 (2) プルサーマルの経済性
① プルサーマルの経済性評価については、評価の手法、ウラン価格の動向及び再処理コスト、MOX燃料加工コスト等の燃料サイクルコストの算定方法並びにプルトニウム価値の評価などにより、その結論が一様でなく、これまでの経済性評価の結果が今後のプルサーマルに対する十分な指針となっているとは考えにくく、また、経済性評価を左右する諸要因の不確実性は、今後とも継続するものと考えられる。 ② 過去の経済性評価をみると、例えばINFCEにおけるワンス・スルー方式(再処理せずに使用済燃料のまま貯蔵・処分する方式)との比較による経済性は、ウラン価格並びにプルトニウム及び回収ウランの利用方法に依存し、ウラン及びプルトニウムが軽水炉にリサイクルされても、経済的な利点はそれ程大きくないとしている。 しかし、西独におけるプルサーマルの経済性は、再処理を前提にした場合、プルトニウム価値の評価に依存するが、MOX燃料加工施設の製造規模がある程度の規模に至れば、経済的に有利になり得るとの評価もなされている。 ③ 今後のプルサーマルの経済性の見通しとしては、プルトニウム価値の評価、燃料サイクルコスト等の諸因子に大きく左右されることになるが、我が国においては軽水炉の使用済燃料を全て再処理する方針であるので、今後のウラン需給動向によるウラン価格の変動、MOX燃料加工コスト等の低減化努力等を考慮すれば、プルサーマルの経済性が将来成り立ちうるものと考えられる。 (3) プルサーマル本格利用への具体的計画
プルサーマルは、技術的には開発要素が少ないが、本格利用までには、少数体規模及び実用規模での実証計画において燃料特性、炉心特性等を確認しつつ進めていくことが適当であり、その具体的な進め方については以下のとおりとする。(付表参照)
(i) 少数体MOX燃料照射計画
MOX燃料単体の特性等の確認を目的として、PWR、BWRそれぞれ一基に少数体のMOX燃料を装荷し、照射及び照射後試験を実施する。照射炉については、PWRは関西電力美浜発電所1号炉、BWRは日本原子力発電敦賀発電所1号炉を予定し、1980年代後半には、試験を終了するものとする。 (ⅱ) 実用規模利用実証計画
実用規模でのプルサーマルの実証を目的とし、炉心特性、運転特性等の把握を行う。 実証計画としては、PWR、BWR大容量商業炉各1基ずつに1/6~1/3炉心程度MOX燃料を装荷し照射を行うこととし、1990年代半ば頃までにこれを終了するものとする。このため、1985年頃には対象プラント、装荷規模を具体的に決め、詳細設計を開始する必要がある。また、実証試験用の燃料加工についても1988年~89年頃に開始できるようにする必要がある。 (ⅲ) 本格利用
プルサーマルの本格利用の時期及び規模については、今後のプルトニウム供給、高速増殖炉実用化の見通し、新型転換炉の導入状況、ウラン資源の動向、プルトニウム利用に対する国際情勢、プルサーマルの経済性等を見きわめた上で総合的に判断する必要があるが、1990年代半ば頃には本格利用が可能となるよう努力する必要がある。 また、この場合、規模については未だ不確定要素が多いが、一応の見通しを得るため、現在までに確定しつつあるプルトニウム利用計画をベースに、2000年でのプルサーマル導入規模を試算すると、1/3炉心利用で約20基程度(約2,000万kW)になるものと考えられる。また、本格利用におけるプルサーマル立ち上がりの規模としてはPWR、BWR各5基ずつ程度(約1,000万kW)が想定される。 5. 新型転換炉(ATR)
(1) 新型転換炉開発の意義及びプルトニウム利用上の特性
① 新型転換炉は、我が国が独自に開発を進めてきた炉型であり、プルサーマルと同様に高速増殖炉が実用化するまでの間、プルトニウムを利用する有力な手段である。 ② また、プルトニウム利用は、特に国際的動向に影響を受けやすい側面があり、原子力発電の安定性確保の観点からプルトニウム利用についての手段の多様化を図ることが重要である。 ③ 新型転換炉のプルトニウム利用上の特性としては、以下の点が挙げられる。 (イ) プルトニウム専焼炉を前提として設計されており、全炉心にMOX燃料を使用出来るため、プルトニウム利用効率が高く、集中してプルトニウムの利用が可能である。 (ロ) 新型転換炉に使用するMOX燃料集合体は、2種類であり、それぞれ2種類のプルトニウム富化度の燃料棒から構成されているので燃料製造工程やプルトニウム管理の単純化が図れる。 (ハ) 多重リサイクルにより、高次プルトニウムを利用する場合でも非核分裂プルトニウムによる中性子吸収の悪影響を受けにくい。 (2) 新型転換炉の開発計画
① 新型転換炉は、高速増殖炉とともに、その自主開発がエネルギー政策における重要課題として、1967年以来ナショナル・プロジェクトとの位置づけのもとに動力炉・核燃料開発事業団が中心となってその開発が進められてきている。 ② 原型炉「ふげん」(電気出力16万5,000kW)については、1969年のチェック・アンド・レビューを経て1970年12月に着工、1979年3月に本格運転を開始し、現在順調に運転を続けており、設計手段及び設計コードの検証改良のための貴重な運転データを提供している。 ③ 原型炉に続く実証炉(電気出力60万kW程度)については、電源開発(株)が建設主体となり、原型炉の経験を踏まえ、大容量化に伴う技術の実証及び経済性の見通しの確立を図るため、1990年代初め頃の運開を目標に実証炉の建設を行うこととする。 6. MOX燃料加工
(1) MOX燃料加工の現状
① 我が国におけるMOX燃料の加工については、既に動力炉・核燃料開発事業団が年間製造規模約10トンの施設を有しており、MOX燃料取扱技術については、世界で有数のものといえる。 ② この施設においては、新型転換炉「ふげん」、高速増殖炉「常陽」の取替燃料の製造が行われておりこれまでに約50トンの燃料加工の実績を有している。 ③ 更に、動力炉・核燃料開発事業団においては、高速増殖炉「もんじゅ」の燃料加工用として製造機器の自動化や遠隔操作技術を取り入れた年間製造規模約5トンの施設を建設しているところであり、また、新型転換炉実証炉の燃料加工のために年間製造規模約40トンの施設の建設を現在計画しているところである。 (2) 技術課題
① MOX燃料加工技術については、これまでの動力炉・核燃料開発事業団の製造実績により新型転換炉用及び高速増殖炉用燃料のプルトニウム加工技術等が蓄積されている。また、民間においてもウラン燃料加工における集合体組立等に関する十分な実績が積まれている。 ② プルサーマル用のMOX燃料加工に関しては、燃料ピン製造以降の工程において、その工程、使用機器、製品仕様等ウラン燃料加工と基本的に変りなく、ウラン燃料加工を通して民間に蓄積された技術とこれまでに動力炉・核燃料開発事業団が蓄積した技術を総合すれば、MOX燃料の大量加工技術への対応も基本的には可能なものといえる。 ③ 今後の課題としては、多量のプルトニウムを取り扱うことから作業被曝の低減についてより一層の配慮が必要と考えられ、そのために製造機器の自動化、遠隔操作化を図ることが必要である。 (3) 実施体制
MOX燃料加工の事業化を図っていくに当たっては、プルトニウム利用計画の各段階に対応した実施体制を確立していくことが重要である。また、ウラン燃料加工に関して充分な経験と実績のある民間が、動力炉・核燃料開発事業団における経験を活かしその協力を得て、技術の確立を円滑に進めていくことが必要である。 (i) 技術移転
① 現在、動力炉・核燃料開発事業団のMOX燃料加工施設においては、一部民間からの技術員の派遣協力により運営されているが、プルトニウム利用が本格化し民間が主体となって施設を運転していくためには、プルトニウムの取扱い・製造経験、プルトニウムに関する特有な管理方法、種々のリスクヘの対応、工程の合理化等将来の事業化に必要な評価経験を積むことが不可欠となってくるものと考えられる。 ② このため、民間においては、動力炉・核燃料開発事業団のMOX燃料加工技術の開発計画に積極的に参画していくことが望ましい。 この様な民間の参画については、ウラン燃料の加工実績を有する燃料加工事業者等が中心となるのが適当であろう。 ③ また、技術移転を円滑に進めていくためには、動力炉・核燃料開発事業団の施設の設計及び建設の段階から民間が協力することが望ましく、その運転についても民間が委託を受けて行っていくことも有効な方策と考えられる。 (ⅱ) プルサーマルのMOX燃料供給体制について
① 上記のプルサーマル利用計画におけるMOX燃料供給については、次のように対応していくこととする。 ② 少数体照射計画用のMOX燃料のうち、PWRに装荷する燃料については既に海外委託により製造を終了しているが、BWRに装荷する燃料については動力炉・核燃料開発事業団MOX燃料加工施設により製造することが適当である。 ③ 実用規模実証計画用のMOX燃料加工については、プルトニウムの本格利用時における加工技術を蓄積するという観点から、動力炉・核燃料開発事業団の新型転換炉用MOX燃料加工施設を活用し、同施設に年間製造規模約20トンの設備をプルサーマル用として確保されることが望ましい。 そのため、実用規模実証計画の開始に間に合せるよう、計画の具体化を早急に進める必要がある。 ④ なお、実用規模実証計画において海外再処理委託により回収されたプルトニウムを利用する場合には、必要に応じ、その燃料加工の一部を海外に委託して行う方途も過渡的対応策として併せて検討していくものとする。 ⑤ 本格利用時におけるMOX燃料加工については、1990年代半ば頃までに、民間による体制整備を図るものとする。 施設としては、プルサーマルの本格利用時における導入規模から想定すると年間製造規模約100トン~200トン程度のものになると考えられ、また、立地場所の選定については、プルトニウム輸送時における核拡散リスク軽減等を配慮することが望ましい。 (ⅲ) 新型転換炉及び高速増殖炉のMOX燃料供給体制について
① 新型転換炉及び高速増殖炉の実証炉までのMOX燃料加工については、動力炉・核燃料開発事業団において対応していくことが可能である。 ② また、それ以降のMOX燃料加工については、より大規模なMOX燃料加工施設が必要となるが、これらについては、新型転換炉及び高速増殖炉の具体的な建設計画と対応させながら、プルサーマル用MOX燃料加工との関連も考慮しつつ、燃料供給体制の具体化を図っていくこととする。 (4) 国の役割り
① プルトニウム利用は、エネルギー供給の自立化を図る上で我が国として極めて重要であり、得られたプルトニウムを早期に利用することが核不拡散上有効な措置である。しかしながら、MOX燃料加工の事業化に当たっては、プルトニウムという非常に機微な物質を取り扱うため、政治的社会的要因に大きく左右されるとともに、プルトニウム需給の不安定性から民間事業として成立していくためには多くのリスクを有している。 ② このように、プルトニウムを早期に利用していくことは、国の方針でもあり、また、事業化を図っていく上で、単に民間の活力を活かすだけでは十分でないことから、国による積極的な支援が必要不可欠である。 ③ このため、国としても円滑なプルトニウム利用を進めるため,国内及び国外の環境を整備していくとともに、国自らMOX燃料加工の事業化のための具体的ビジョンを明らかにしていくことが重要である。 また、加工施設建設に際しては、建設資金等の確保のための長期低利融資等財政面における支援措置、MOX燃料加工技術の動力炉・核燃料開発事業団からの円滑な民間への移転方策の確立等技術面における支援措置、施設の立地推進を図るための措置等を講じていく必要があろう。 7. MOX燃料の再処理
(1) 技術課題
① プルサーマル及び新型転換炉の使用済燃料の再処理技術については、基本的にはウラン燃料の再処理技術によって対応が可能であるが、通常のウラン燃料とは、MOX燃料の溶解性、臨界安全上からの処理量の制約などの点が異っている。 しかしながら、これらのMOX燃料の再処理に特有な技術課題については、溶解性の高いMOX燃料製造法と適切な工程設計により対応可能と考えられる。 ② また、高速増殖炉燃料の再処理技術については、プルトニウム含有量が多いこと及び熱中性子炉の場合よりも燃焼度が高くなることから、基本的には、従来の再処理技術をベースとしつつ、その技術の確立を図っていくものとする。このため、動力炉・核燃料開発事業団が中心となって、東海再処理工場の経験も取り入れつつ、自主技術の確立を目指すことが重要である。 (2) 実施体制
(i) プルサーマルの使用済燃料の再処理
① プルサーマルの実証計画段階の使用済燃料については、1990年代半ば以降再処理することが必要となるが、再処理需要量としては大きくないこと及び実証計画の一環としての意義を考慮して、東海再処理工場において再処理することが考えられる。 ② プルサーマルが本格利用段階に至った場合には、再処理需要量も大きくなるため、本格利用の規模等に合わせて、民間事業による再処理によって対応していくことが必要である。 (ⅱ) 新型転換炉及び高速増殖炉の使用済燃料の再処理
① 新型転換炉「ふげん」及び実証炉の使用済燃料の再処理については、東海再処理工場により対応していくことが考えられる。 ② また、高速増殖炉「もんじゅ」の使用済燃料の再処理については、動力炉・核燃料開発事業団高速炉燃料再処理試験施設(パイロットプラント)により対応していくものとする。 ③ 更に、将来の再処理需要については、大型施設の建設・運転、研究開発の体制等について今後検討する必要がある。 8. プルトニウム利用の環境整備
① 英国及び仏国に委託している我が国の軽水炉使用済燃料の再処理は、ほとんどが現在建設中の再処理工場(BNFL-THORP工場、COGEMA-UP3A工場)で行われることとなっているので、工場運開後の操業立ち上がり時期等を考慮すれば、我が国へのプルトニウムの本格的返還は、1990年代前半頃始まることとなろう。 ② また、我が国において、現在計画中の商業再処理工場は、1990年度頃の運開を目途にしており、我が国におけるプルトニウムの本格的な生産は、やはり1990年代前半頃になるものと考えられる。 ③ このように1990年代前半以降、多量のプルトニウムが生産され、これに伴い国内での利用を円滑に進めていくためにも、次のような環境整備が早期に図られることが重要である。 (1) プルトニウム管理体制の確立
① 我が国におけるプルトニウム利用は、ウラン資源供給国等との二国間協定に基づく種々の制約のもとに行われてきており、今後、プルトニウムの確実かつ円滑な移転を期する我が国としては、国際的に信頼されるような国内のプルトニウム管理体制を充実することが重要となろう。 ② プルトニウム管理体制確立のためには、保障措置及び核物質防護措置の充実を図るとともに、プルトニウム管理の信頼性を高めるための措置についても検討する必要があろう。 ③ このような管理体制は、現在、国際原子力機関(IAEA)の場において検討されている国際プルトニウム貯蔵(IPS)構想に先行するものであるが、将来、IPSが設立された場合には、その移行も円滑に行われるものと考えられる。 (2) 輸送対策
① プルトニウムの海外輸送については、これまでに動力炉・核燃料開発事業団が少量のものについて行った経験があるが、今後、海外における再処理の本格化に伴い輸送量の増大が予想される。 ② 輸送時においては、核物質の盗取の危険性に対処するため、核物質防護措置の適用、輸送容器の開発、プルトニウムの輸送形態等について検討が必要である。特に、輸送時における核物質防護については、IAEAにおける核物質防護条約の採択を契機に国際的な要請も高まってきているところである。 (3) 保障措置及び核物質防護措置の適用
① 保障措置及び核物質防護措置の具体的な適用にあたっては、MOX燃料加工事業等の円滑な遂行を妨げることのないよう考慮される必要がある。 ② このため、国としては、プルトニウム取り扱いに係る有効かつ効率的な保障措置及び核物質防護措置を適用していく必要がある。 (4) パブリック・アクセプタンスの確保
① 今後のプルトニウム利用を進めていくためには、プルトニウム利用の必要性、計画等に対する国民の理解を得ることが重要である。一部には、プルトニウムそのものに対する不安感も存在していることは事実であり、国及び民間は積極的な広報活動を展開していくことが必要である。 ② 特に、プルサーマルについては、通常の軽水炉においても燃焼に従ってプルトニウムが生成蓄積・燃焼されるものであり、その点については両者の間に大きな差異はないことを理解してもらうことが重要である。 9. 回収ウランの利用
(1) 回収ウランの利用の必要性
使用済燃料の再処理により回収されるウランは、現在国内では、東海再処理工場から発生しており、同工場敷地内に貯蔵されている。 また、今後、英国及び仏国への海外再処理委託並びに商業再処理工場の運開に伴って1990年以降大量の蓄積が予想される。回収ウランは、天然ウランよりも一般にウラン235の含有率が高く、これを核燃料として再利用していくことがウラン資源の有効利用の観点から重要である。 (2) 利用分野
① 回収ウランの利用方法としては、
(イ) 回収ウラン(UO3)をUF6に転換し、再濃縮した上で軽水炉燃料として利用する方法
(ロ) 回収ウランをUO2に転換し、プルトニウムを混合してMOX燃料として利用する方法
(ハ) 将来の需要に備えて備蓄する方法
が考えられる。 ② 回収ウランの具体的利用については、今後の天然ウランの需給等との関係において見通されるものと考えられるが、いずれにせよ上記の利用方法の組み合せにより対応していくことになることから、それぞれの利用方法についてのシナリオを明確にするとともに、然るべき時期に回収ウランが利用可能となるよう準備をしておくことが重要である。 (3) 回収ウラン利用の課題及び方策
① 回収ウランの利用については、基本的には現在の天然ウラン燃料の取扱技術で対応が可能と考えられるが、天然ウランと異なりウラン236による中性子吸収、ウラン232等による放射線影響等配慮すべき課題がある。 ② 東海再処理工場から発生している回収ウランについては、発生量も限定されることから、当面プルサーマル及び新型転換炉のMOX燃料の母材として活用することが望ましい。 ③ しかし、上記母材としての利用だけでは発生する回収ウラン量の一部しか消化できないため、再濃縮して軽水炉燃料として利用することも必要となると考えられる。その場合、上記課題に対応するため動力炉・核燃料開発事業団が一部技術の開発を進めているが、回収ウランが大量に発生する1990年代の実用化を目指し必要な技術の確立を図るものとする。 ④ 回収ウランの備蓄については、今後実施体制等について検討していくことが必要である。 10. 国際的動向への対応
(1) 我が国の基本姿勢
① 原子力の平和利用を推進していく上で、核不拡散の確保は極めて重要である。我が国としては、再処理・プルトニウム利用を進める上で国際的な環境を十分に踏まえるとともに、核不拡散の目的に沿って国際協調を進めていくことを基本とし、同時に我が国の自主的核燃料サイクル確立及び円滑なプルトニウム利用を目指して今後とも努力していくことが重要である。 ② 今後の再処理・プルトニウム利用の円滑化を図り、我が国のエネルギー・セキュリティ向上に寄与するためには、国際的な合意に基づく長期的に安定した秩序を形成していくことが不可欠の条件であり、我が国としてもかかる国際的な合意形成のための検討に積極的に対応していくことが重要である。また、核拡散を防止しつつ再処理・プルトニウム利用の本格化を図っていくことは、原子力先進国としての我が国が負っている責務ともいえるものである。 ③ このような観点から、我が国としては、今後とも二国間及び多国間の国際的交渉に対し、主体的かつ積極的な対応を図っていくことが必要である。 (2) 国際協力の推進
① 我が国は、原子力先進国として再処理・プルトニウム利用の分野において種々の経験及び研究の蓄積を有しているが、未だ解決すべき課題も残されている。 再処理・プルトニウム利用の分野における課題は、我が国と同様に再処理・プルトニウム利用を進めようとしている欧米諸国が直面しているものと共通のものであり、これらについて情報交換、共同研究等関係国間の協力を推進していくことも有効であると考えられる。 ② また、国際協力を推進するに当たっては、我が国の核不拡散努力に対して、各国の理解を一層深めるように努めるとともに、我が国の再処理・プルトニウム利用の考え方が十分反映されるような国際環境づくりに努めていくことも重要である。 (付表) プルサーマル計画 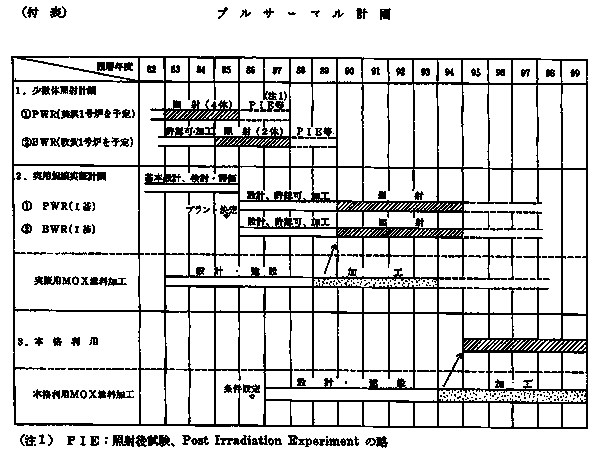 総合エネルギー調査会原子力部会委員名簿
総合エネルギー調査会原子力部会
基本政策小委員会委員名簿
総合エネルギー調査会原子力部会
基本政策小委員会専門委員会委員名簿
プルトニウム・リサイクル小委員会委員名簿
(昭和57年7月19日現在)
プルサーマル検討作業グループ委員名簿
(プルトニウム・リサイクル小委員会委員を除く)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |
