| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
世界における炉心プラズマ研究の現状 日本原子力研究所
昭和44年英国カラム研究所のチームは計測器を携えてモスコーに赴き、クルチャトフ研究所のトカマク型装置T-3の実験結果を確認した。これをうけて直ちにわが国をはじめ、米、仏、西独等で相ついでトカマク型装置が建設され、以来世界の核融合研究はトカマク型を中心に展開されて来た。 この間トカマク型の研究進展はとくに目覚しく、今日では、この方式による核融合の科学的実証が近い将来期待できる段階を迎えている。すなわち臨界プラズマ条件の達成を目標とする大型トカマク型装置、JT-60(原研)、TFTR(米)、JET(EC)、T-15(ソ連)が、今年末のTFTRに続いてここ2-3年のうちに稼動に入る予定である。トカマク以外の磁気閉込め方式の研究も一時期の低迷を脱し、ミラー型、ステラレータ型、高ベータ系において最近注目すべき成果が得られている。慣性閉込め方式に関しても、トカマク型に雁行しつつ大型レーザ核融合装置が建設中であり、またイオンビームを用いる方式の研究にも力が注がれている。 本年9月、米国バルチモア市においてIAEA主催第9回プラズマ物理学および制御核融合研究国際会議(以下バルチモア会議と記す)が開催され、2年前の第8回会議(ベルギー、ブラッセル市)以降の炉心プラズマに関する研究成果がまとめて発表された。なおわが国からは初めてソ連を抜き米国に次ぐ数の論文が採択された。最近とくに進展しているわが国の研究状況がここにも反映されている。 表1 バルモア会議発表論文(テーマ別) 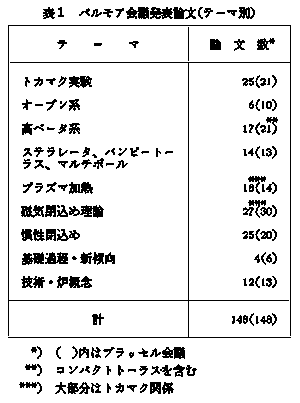 表2 バルチモア会議発表論文(国別) 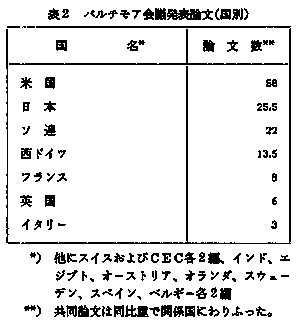 以下バルチモア会議での発表を参照しつつ、トカマク型を中心に炉心プラズマ研究の現状について述べる。 1. トカマク型
各国の多数の装置による実験、IAEAによるINTOR作業で代表される設計研究、この両者相まってトカマク型に関する研究課題は、他の方式に比べはるかに具体的、定量的に明らかにされ、それらを解決するための研究が進められている。バルチモア会議でも発表論文の半数近くがトカマク型に関するものであり、着実な進展が報告された。 1) 日米核融合研究協力に基づくDoublet-Ⅲの実験で4.6%のベータ値が達成された。ベータ値は閉込め効率の指標となるもので、トカマク型装置でこれがどこまで大きく出来るかが注目されて来た。2年前、JFT-2(原研)、ISX-B(米)、またT-15(ソ連)で2-3%という値がえられて以来の成果であり、しかも大型装置でそれを達成したことが特筆される。因みにINTORの設計では5.6%という値が採用されている。大型装置ASDEX(西独)、PDX(米)等での実験とともに、今後のDoublet-Ⅲの高ベータ実験が大いに期待される。 2) 現在のトカマク型装置では閉込めに不可欠なプラズマ電流を電磁誘導によって駆動している。この方式による限り運転は断続的とならざるを得ず、トカマク型の大きな欠点として指摘されてきた。2年ほど前JFT-2において、低域ハイブリッド波帯の高周波をプラズマ中に入射し、40ミリ秒の間15kAのプラズマ電流を駆動することに成功した。それ以来、京大、名大はじめ世界各所で実験が精力的に行われて来たが、大型装置PLTの最近の実験では、3.5秒間165kA、また0.3秒間、420kAのプラズマ電流を駆動することに成功した。ただこの高周波による電流駆動の効率は、プラズマ密度の増大とともに低下する。AlcatorC(米)はプラズマ密度5×1013/㎝3まで電流駆動を観測しているが、密度1014/㎝3以上の炉領域でこの方式が可能か否か、今後の研究が注目される。 3) 高温プラズマを生成するための第二段加熱法として、中性粒子入射(NBI)法につづいて高周波法の有効性が確認されてきた。とくに最近、イオンサイクロトロン周波数帯(ICRF)加熱の実験が、PLT、JFT-2、TFR(仏)で行われ成果を挙げている。PLTではこれによってイオン温度3keVを達成した。因みにNBI法を用いてPLTでは2年前に7keVのイオン温度を得ている。高周波加熱法はNBI加熱法にない特長をもっており、今後低域ハイブリッド波帯、またとくに電子サイクロトロン周波数帯の高周波の利用も含めて一層の研究がのぞまれる。 4) トカマク型装置の欠点の一つとしてプラズマ電流が急激にしゃ断されるディスラプションと呼ばれる現象がある。これに伴って高い電圧が誘起されるため装置の保全上も問題である。この現象を抑制する手段としてJFT-2a(原研)に始まる極低安全係数放電があるが、最近TORIUT-4(東大)において、閉込め磁場を人為的に乱すことによってディスラプションが回避できることが示された。これも注目される成果である。 5) トカマク型装置でのプラズマ閉込め時間はこの数年間改善されていない。現在稼動している装置を寸法的に上廻る建設中のJT-60等の成果が期待される。実験ではNBI加熱で閉込め時間の劣化が報告されているが、これはプラズマ電流の分布等に左右されるところが大きい。大型化とともにプラズマパラメータの制御による閉込め時間の改善が期待される。 2. ミラー型
この型には磁力線に沿うプラズマ損失(端損失)がある。トーラス系に比べたときこれがミラー型の最大の欠点であるが、数年前、静電場を併用して端損失を抑制するタンデムミラー型が米、ソ連で提案され、γ-6(筑波大)、TMX(米)でその配位が実現された。その後さらに熱バリアを生成して閉込めを改善する方法が考案された。これらを取入れたTMX-upgrade(米)、γ-10(筑波大)が最近完成したばかりであり、今後の実験面での進歩が期待される。なお大型装置MFTF-B(米)が建設中であるが、米国ではこれとトカマク型のTFTRの結果によって、次のステップを選択するという考えが出て来ているようである。ミラー型は直線形状であることが利点として挙げられているが、端損失や不安定性を回避するため改良が加えられた結果、その構造はかなり複雑なものとなっている。 3. ステラレータ型
2年前、WⅦ(西独)において、NBI加熱を行いつつプラズマ電流の作る磁場を徐々に外部コイルによって肩代りさせ、プラズマ電流のないステラレータ型本来の閉込めが実現された。最近では同規模のトカマク型装置に比べ遜色のない温度、密度、閉込め時間を達成したことが注目される。またHeliotron E(京大)では多彩なプラズマ生成、加熱手段を駆使して実験が進められている。 ステラレータ型の改良について、技術面ではヘリカル巻線のモジュール化等、物理面ではベータ値の増大等の検討が行われている。 4. バンピートーラス型
ミラー型をトーラス状に連結したもので、大電力のミリ波帯マイクロ波をプラズマ中に入射して高速電子ビームリングを生成し、これによって閉込めを行う。EBT-S(米)、NBT(名大プラズマ研)により基礎過程の解明、ICRFによるイオンの加熱等が行われた。NBTの改造は最近完了したが、EBT-P(米)の建設は難航しており、このところ実験上の成果は少い。 5. 高ベータ系
逆磁場ピンチ型の研究は一時期中断されていたが,数年前のETA-BETA(伊)による安定な配位の実現、とくにそれにつづくTPE-1R(M)(電総研)の実験を契機として新しい段階を迎えた。電子温度600eV(TPE-1R(M))、放電継続時間20ミリ秒(ZT-40(米))などが達成された。 同じく古くから研究されてきた逆磁場テータピンチ型では、回転不安定の抑制(阪大)などの成果があるが、継続時間は0.1ミリ秒程度である。 トカマク型装置のトロイダル磁場コイルを不用とするものとして提案されたコンパクトトーラス型(スフエロマク型)の基礎的実験も阪大や米国で行われている。またプラズマフォーカスの研究が群馬大、阪大のほかイタリヤ、ソ連等で続けられている。 6. 慣性閉込め方式
レーザ核融合では、米国の大型装置が建設中あるいは改造中であり、爆縮実験を行っているのは現在GEKKO MⅡ他(阪大)のみである。注目すべきものとして、昨年阪大から提案されたキャノンボールターゲットがある。爆縮用ターゲットの周囲に孔のあいたタンパーを配置し、その孔からレーザ光を入射、X線に転換して、それによって爆縮を行わせるものである。このターゲットではレーザビーム数が少くても一様な爆縮が可能であり、またとくに必要なレーザエネルギーを大幅に減少できることが大きな利点である。臨界プラズマ条件達成用のターゲットとして極めて有望との評価がなされている。なお類似のものは米国でも考えられているようであるが公開されていない。一方レーザ光をそのままターゲットに吸収させる方式では、ブラッセル会議につづいて短波長化が進められている。この面では最近ガラスレーザの4倍高周波で100%近い吸収効率が達成された(電総研)。電子ビームあるいはイオンビームに関する研究も阪大、長岡技術大のほか米国、ソ連で進められている。 以上炉心プラズマ研究の現状について記したが、ブラッセル会議以降ここ2年間の進展を概括すると次のように言えるであろう。トカマク型はベータ値や高周波による電流駆動などで着実な歩みをみせた。 世界の臨界プラズマ装置(4大トカマク装置) 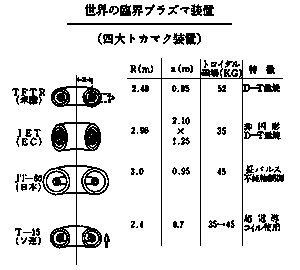 JT-60 完成予想図 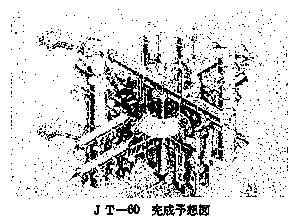 TFTR 完成予想図 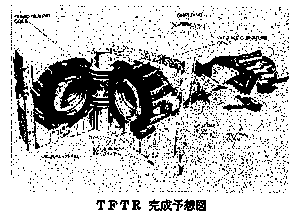 JET 完成予想図 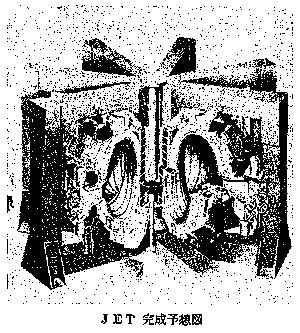 一方閉込め時間は改善されていない。ステラレータ型ではトカマク型に近い高温プラズマ閉込めが実現された。高ベータ系は一時期の低迷を脱しつつあるが、閉込め時間等の改善が今後の課題である。ミラー型やバンピートーラス型はこの間実験面でやや淋しかった。慣性核融合も大型装置が建設中で爆縮実験の面での発表は少かった。 なお、バルチモア会議で、原子核のスピンの向きがそろっている核偏極プラズマを利用する提案があった。反応率の増加等の利点がある。また核融合研究の初期に提案されたミュー中間子を利用する低温核融合でも、数年前基礎的な面で新しい進展があった。何れもその実現可能性に関してはさらに検討を要するものであるが、今後とも新しい提案が期待される。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |