| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
エネルギー研究開発基本計画〔抄〕 昭和53年8月11日決定
昭和54年4月19日改定
昭和55年7月15日改定
昭和56年8月7日改定
昭和57年7月26日改定
内閣総理大臣
序
人類の文明はエネルギー利用の拡大とともに発展を続けてきており、今日の社会・経済活動の源泉はエネルギーにあると言っても過言ではない。 周知のとおり、エネルギー利用の中心は石炭から石油へと移ってきたが、今後は、石油依存度を低減させつつ、原子力を中心として、従来からのものに加え新しい利用形態での石炭・天然ガスなどの化石エネルギー、太陽エネルギー・地熱・風力・バイオマス等の自然エネルギーなど多様なエネルギー源を利用することが必要となり、また、これと並んでエネルギーの一層有効な利用を図ることが必要となろう。これには、利便性・経済性の問題が伴うが、エネルギー問題の解決のかぎとなるのは科学技術そのものの進歩であることは言うまでもない。エネルギー科学技術の開発は長いリードタイムを要するものが多く、今日、既に世界各国で研究開発の努力が払われているが、特に、先進工業国がグローバルな見地からエネルギー研究開発になお一層の努力を払うことが要請されている。国際石油情勢は1973年の石油危機以降不安定のうちに推移しており、今後、石油需給は一時的な緩急のうちにも、中長期的にひっ迫化に向かうものと考えられる。このため、各般にわたるエネルギー研究開発を積極的に推進する必要が生じてきている。我が国としても、このため最大限の努力を払うことが必要であり、この面での努力の成果が資源に乏しい我が国の経済的安全保障の確立に大きく寄与するものであることは言うまでもない。このような認識の上に立って国のエネルギー研究開発政策を継続的に展開していく必要がある。 エネルギー研究開発の推進に当たっては、原子力、化石エネルギー、自然エネルギーといったエネルギー源の開発及びエネルギーの有効利用技術を強力に、かつ、相互に調和のとれた形で進展させることが重要である。また、開発された技術が社会で受け入れられ、有効に機能するためには、これらと並行して環境保全・安全確保のための技術の向上が不可欠であり、目的指向的なエネルギー研究開発を円滑に遂行するためには、基礎科学・基盤科学技術・支援技術の一層の推進が重要である。 このように、エネルギー研究開発は、広範な分野を対象とし、長期にわたり膨大な研究開発資源(資金・人材)を必要とする。したがって、限られた資源を最大限に生かし、確実に成果を挙げるためには、研究開発全般を計画的に推進することが重要である。このため、政府が中心となって推進するエネルギー研究開発については、研究開発全般の現状等を十分に踏まえつつ、統一的考え方の下に作成された基本計画にのっとり、その着実な推進を図る必要がある。 Ⅰ 計画の目的 本基本計画においては、エネルギーに関する内外の動向に対する長期的展望の下に、政府が中心となって推進するエネルギー研究開発の基本を定めることを目的とする。 Ⅱ 計画の期間 本基本計画においては、エネルギー研究開発の長期性にかんがみ、21世紀までを展望し、おおむね向こう10年間に行う研究開発を対象とする。 Ⅲ エネルギー研究開発推進に当たっての留意事項 1 環境保全及び安全確保への配慮
エネルギー研究開発の目標設定及び実施に当たっては、環境保全及び安全確保に十分配慮する。 2 国民の理解と協力
エネルギー研究開発の推進に当たっては、研究開発の目的、必要性、成果の社会への貢献度を実用化までの各段階において常に国民に明らかにすることにより、広く国民の理解と協力を得るように努める。 3 国際協力
エネルギー研究開発は、膨大な研究開発資源及び長期間を要し、また、各国共通の重要課題でもあり、国としてこれを効率的に推進するには、国際協力に配慮する必要がある。さらに、外国との研究開発協力等によって国際協調に資することも重要である。 4 エネルギー研究開発の特性への留意
エネルギー研究開発には、その実用化時期が比較的早いものから非常に遅いものまで、種々のものが含まれており、研究開発目標の設定及び実施に当たっては、次の点に留意する必要がある。 (1) 実用化時期が比較的早い研究開発課題については、国のエネルギー需給見通しとの関連に留意して推進する。 (2) 実用化時期が非常に遅いものについては、国のエネルギー需給見通しとの関連については弾力的に考え、研究開発の進ちょくに応じて評価を加えながら段階的に着実に推進するものとする。 その際、最適方式を決定するに十分な知見がまだ得られていないなどの理由によりやむを得ない場合には、同一目的のために異なる方法によって同時並行的に研究開発を進める方式の採用に配慮するものとする。 (3) (1)と(2)の中間のものについては、それぞれ実用化時期に応じて、(1)と(2)の中間的考え方の下に推進する。 5 社会科学的研究への留意
エネルギー研究開発の推進に当たっては、各種研究開発を総合的に考察し、研究開発の最適化を図るとともに、その成果を社会に定着させるために必要な社会科学的研究(技術予測、テクノロジー・アセスメント等)の推進にも留意する必要がある。 6 研究開発における官・学・民の有機的連携
エネルギー研究開発の推進については、基礎から応用・開発にわたって、大学、国立試験研究機関、特殊法人研究機関、民間研究機関等の研究者、研究機関の有機的連携の下に進めることが重要である。 特に、基礎科学の振興と人材の育成に大きな役割を持つ大学が、その特質を発揮しつつ、各研究機関等との有機的連携協力の下にその研究を進めることが望まれる。 Ⅳ 研究開発基本計画 1 我が国において期待されるエネルギー研究開発分野
経済の安定成長と国民福祉の向上に不可欠なエネルギーを安定的に確保するために、エネルギー科学技術の果たす役割が極めて大きいことにかんがみ、その研究開発を着実に推進する必要がある。その際、重点を絞って努力することが効率的であることはもちろんであるが、新しいエネルギー科学技術の中には基礎的段階にあるため将来の見通しが明確でないものが多く、現在の時点で特定の課題に限定することは不適当である。また、エネルギー資源に乏しい我が国は、国内資源の利用可能性を追求するという姿勢で対処するとともに、外国との技術協力によってエネルギー供給の増加に努めることも重要である。 このような観点から、政府・民間を含めた国全体における研究開発の推進対策としては、次に示すように原子力・非原子力を通じて幅広い分野を考え、研究開発の進展段階に応じて、重要なものについて重点的に配慮することが期待されている。 (1) 原子力開発
原子力は、供給量が大きく、石油に代替するエネルギーとしても最も有望である。このため、既に実用段階にある軽水炉による原子力発電の着実な推進を図ることとし、そのため、安全性の確保に万全を期するとともに、核燃料サイクルの確立を図る。その際、核拡散防止を巡る国際動向に十分留意することが大切である。 さらに、中期的目標として、ウラン資源の効率的利用を図るため新型炉の研究開発を進める。また、人類究極のエネルギーとして期待されている核融合については、技術的に解決すべき問題が多く、21世紀の実用化を目指して研究を進める必要がある。 <分野と目標> ① 軽水炉
軽水炉の安全性・信頼性の向上を図る。また、我が国に適した軽水炉技術の確立のため、改良、標準化、原子炉の廃止措置に関する技術開発等を進める。さらに、立地方式の多様化につき調査検討を進める。 ② 核燃料サイクル
ウランの製錬・転換技術、遠心分離法によるウラン濃縮技術の実用化及びそれを補完するものとしての化学法ウラン濃縮技術、使用済燃料の再処理技術、プルトニウムの加工・取扱い技術、放射性廃棄物の処理処分等の一層の進展を図る。 ③ 新型炉
新型転換炉については、原型炉の運転経験を蓄積し、実証炉に開する研究開発を行うとともに、実用化の検討を進める。高速増殖炉については、実験炉の運転を通じて技術的経験を蓄積するとともに、原型炉の建設を進める。また、多目的高温ガス炉については、実験炉に関する研究開発を推進する。 ④ 核融合
第2段階核融合研究開発の主計画であるトカマク型の臨界プラズマ試験装置(JT-60)及びその関連技術の開発を行う。さらに、核融合反応プラズマに関する準備研究を実施するとともに、従来に引き続きヘリオトロン、ピンチ等各種プラズマ閉じ込め方式についての基礎的研究及び関連分野の研究を進める。 ⑤ 原子力船
原子力第1船「むつ」の開発を通じて、原子力船に関するデータ及び経験を取得するとともに、その成果を十分に活用しつつ、経済性・信頼性の優れた船舶用原子炉を中心として原子力船の開発に必要な研究を進める。 (2) 化石エネルギーの開発(略) (3) 自然エネルギーの開発(略) (4) エネルギー有効利用技術の開発(略) (5) エネルギーの供給・利用に伴う環境保全のための研究開発
エネルギーの供給・利用は環境保全に十分配慮して推進すべきものであり、研究開発に当たっては環境に対する汚染負荷量を増大させる技術とならないよう配慮し、次の研究開発を推進する。 ① 既に普及しているエネルギーの供給・利用技術による環境負荷を極力低減するための研究開発 ② 上記(1)~(4)に掲げる研究開発に関連する環境保全対策上の調査研究(新たに開発される技術が環境に与える影響の解明、実際に技術を適用する場合に行うべき環境影響の予測評価手法の開発等) (6) エネルギーの供給・利用における安全確保のための研究開発
エネルギーの供給・利用に当たっては、安全確保に万全を期す必要があり、この観点に立って次の研究開発を推進する。 ① 既に普及しているエネルギーの供給利用技術に係る安全確保対策のための研究開発 ② 上記(1)~(4)に掲げる研究開発の実用化に当たっての安全上の問題点の予測及びこれらに係る対策のための研究開発 (7) エネルギーの供給・利用に関するソフトサイエンスの研究開発
エネルギーと社会・経済のかかわりがますます深まる中で、エネルギー研究開発を推進するに当たって、社会・経済事象の解明、国民の生活観、価値観の把握・分析等総合的なソフトサイエンスの研究開発を行う。 (8) 基礎科学、基盤科学技術及び支援技術の振興
基礎科学、基盤科学技術の研究開発は、全く新しいエネルギー利用の方式、極限及び高性能新材料の開発等エネルギー研究開発の方向を見極めるための基礎的情報を提供する役割を果たすものであり、支援技術の研究開発は、共通的技術の向上をもたらし、目的指向的研究開発の基盤の強化・加速化に貢献するものである。いずれも、上記(1)~(7)の領域の研究開発の成功のかぎともなるべきもので、可能な限り広く、かつ、着実な推進を図る。 2 研究開発基本計画 (1) プロジェクト
上記1の研究開発分野に属する研究開発課題のうち、次の研究開発課題についてはプロジェクト(注)として管理し、推進すべきものとして、それぞれ別表により適切な官民協力の下に計画的に推進する。その際、プロジェクトの間で共通的な技術の研究開発がある場合には、相互に有機的連携を図るよう努めるものとする。 (原子力開発)
1 ウランの製錬及び転換
2 遠心分離法によるウラン濃縮
3 使用済燃料再処理
4 放射性廃棄物の処理処分
5 プルトニウムの加工及び取扱い
6 新型転換炉
7 高速増殖炉
8 多目的高温ガス炉
9 核融合
10 原子力船
11 工学的安全研究
12 環境放射能安全研究
(注) プロジェクトとは、科学技術会議第5号答申で、「社会・経済などのニーズにこたえて解決しなければならない研究開発課題のうち、多くの科学技術分野にまたがり、しかも多くの機関が関与しなければならない大規模なものを効果的に進めるためには、行政部局がその目標を設定し、管理し、推進するプロジェクト方式によることが有効である。」と記述されたプロジェクトをいう。 (化石エネルギーの開発)(略) (自然エネルギーの開発)(略) (エネルギー有効利用技術の開発)(略) (2) プロジェクト以外の研究開発
(1)以外の研究開発課題についてもその着実な推進に努める。なお、これらの課題のうちプロジェクト方式に適するものがその段階に達した時はプロジェクト方式により計画的に推進する。 (3) 国際協力
(1)及び(2)に示された研究開発課題の推進の一環として、次のような国際協力を行う。 ① 国際エネルギー機関(IEA)エネルギー研究開発実施協定に基づく各種協力事業、原子力機関(NEA)ハルデン計画のハードウェア研究開発事業等への参加を通ずる多国間協力の推進 ② 米国とのエネルギー等研究開発協力協定の下での核融合、石炭液化、地熱、太陽エネルギー、光合成及び高エネルギー分野における協力を始めとする科学技術協力協定、原子力協定、交換公文等に基づく二国間協力(開発途上国での協力を含む)の推進 ③ 国際エネルギー機関(IEA)、原子力機関(NEA)、国際原子力機関(IAEA)等の国際機関への参加 (別表)
本表においては、プロジェクトとして掲げた研究開発課題ごとに下記の事項が示されている。 1 研究開発の内容:研究開発課題の必要性及び内容についての簡潔な説明 2 当面の主な研究開発事項:研究開発課題に関し、政府が中心となって当面推進する主な研究開発事項 3 担当行政部局:当面の主な研究開発事項について目標の設定、予算の確保等によりこれを推進している行政部局名 4 研究開発の将来展望:各研究開発課題(民間が推進するものも含む。)について、将来の発展が展望及び各研究開発課題の実用化についてのおおよその見通し(ただし、政府の推進する研究開発が所期の成果を挙げ、更に必要な民間の努力が得られ、経済条件、社会条件、国際環境等が当該技術の実用化に有利に展開することを前提とする。)
原子力開発
1 ウランの製錬及び転換 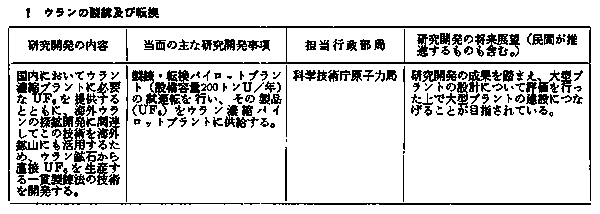 2 遠心分離法によるウラン濃縮 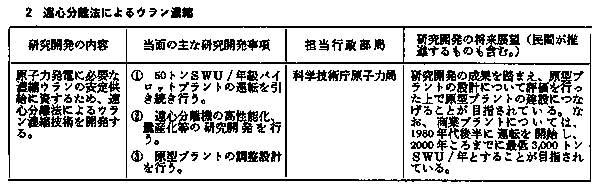 3 使用済燃料再処理 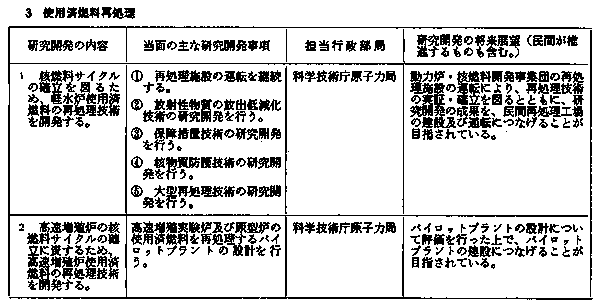 4 放射性廃棄物の処理処分 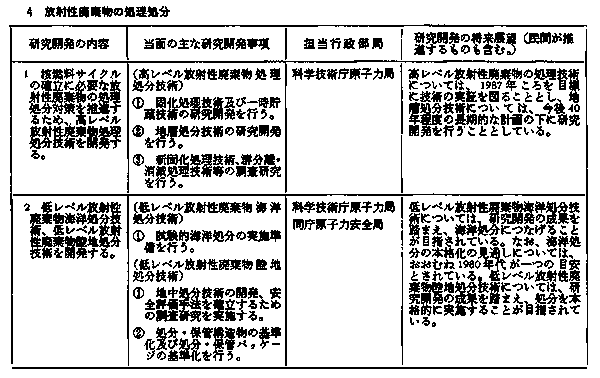 5 プルトニウムの加工及び取扱い 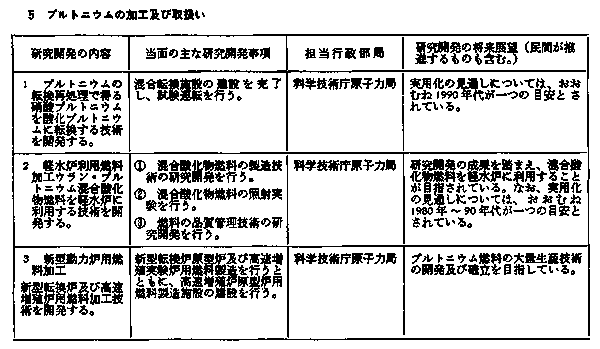 6 新型転換炉 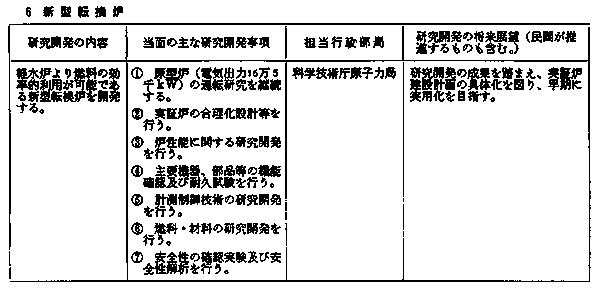 7 高速増殖炉 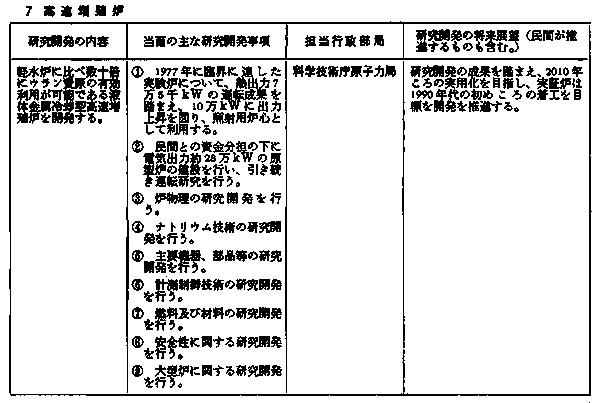 8 多目的高温ガス炉 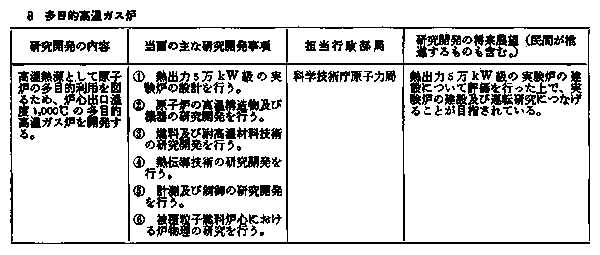 9 核融合 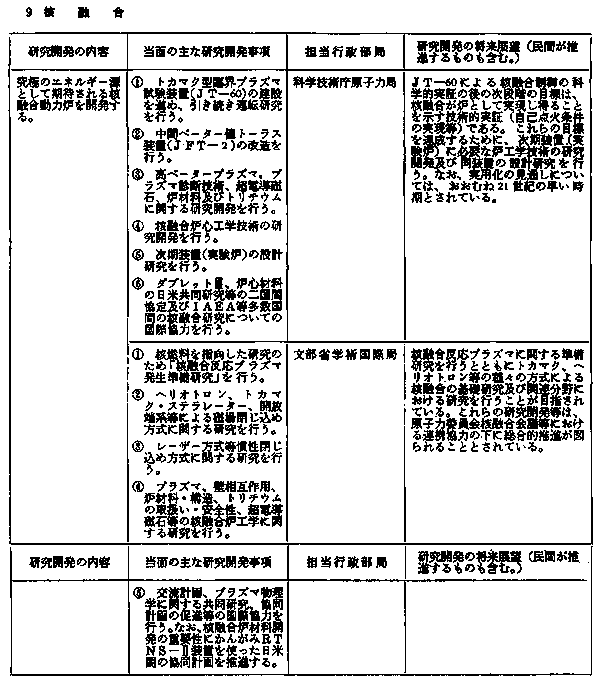 10 原子力船 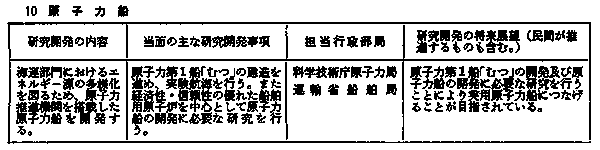 11 工学的安全研究 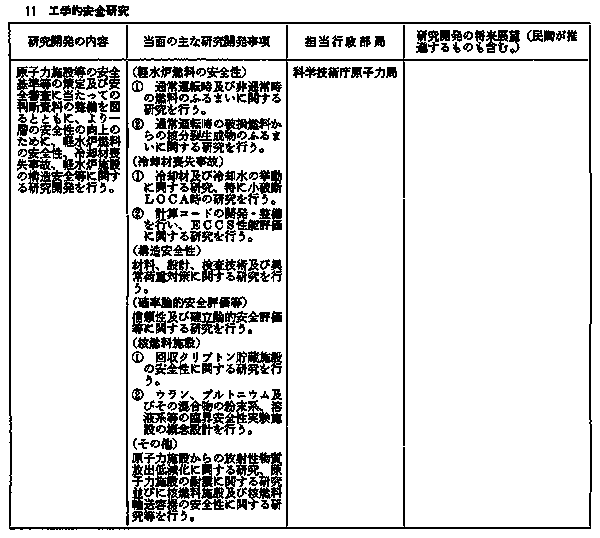 12 環境放射能安全研究 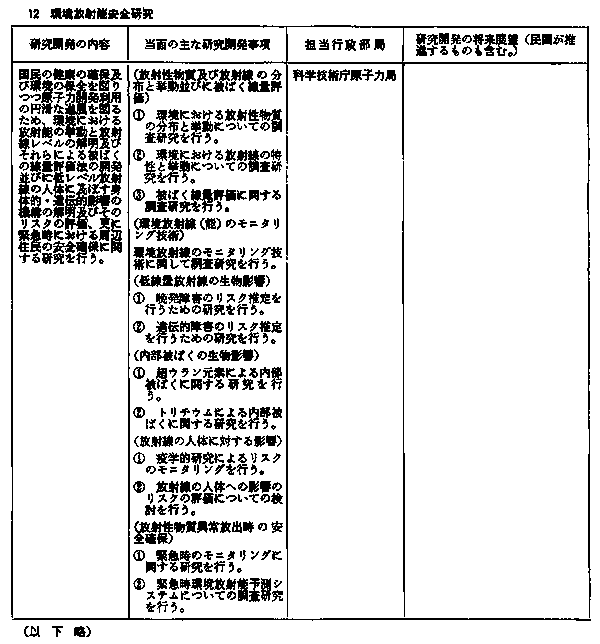 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |