| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
LCT計画の現状 日本原子力研究所
1. はじめに
日本原子力研究所は、本年6月核融合研究施設(茨城県那珂町)において、超電導トロイダル・コイル開発の一環として進めている国際エネルギー機関(IEA)による大型コイル事業(LCT)のためのコイルの国内試験を行った。その結果は、当初の設計条件を満足し、わが国の超電導磁石開発の記録を大幅に更新したばかりでなくLCTの他の参加国のコイルに先駆けて成功したという二つの大きな意義があった。本稿では核融合のための超電導コイル開発の技術的課題、LCT計画の概要及びこのたび行った国内試験の成果を紹介する。 JT-60を始め、現在世界で建設が進められている大型トカマク装置のコイルには銅が用いられている。この銅コイルによって、プラズマの発生・閉込め・制御のための磁界を発生するには多量の電力が必要である。将来の核融合炉において銅コイルを用いると更に多くの電力を要し、かなりの規模の炉でないと正味の電力が得られないことが試算されている。 そこで電力消費の軽減のために、極低温で電気抵抗が零となる超電導現象を用いて核融合用の各種のコイルを作ることが不可欠となる。超電導コイルは液体ヘリウム温度での冷却を必要とし、ジュール発熱が全く無くとも冷却のためにエネルギーを消費する。しかし、銅で作ったコイルによるジュール発熱損失と超電導コイルに要する冷却のための電力とを比較すると、同一の寸法のコイルにおいて後者の方が桁違いに少い。大型かつ強磁界のコイルになればなるほどこの差は大きくなる。 超電導コイルの技術開発は、核融合以外の目的のためにも進められているが、核融合のための超電導コイルの開発は、強磁界、大型、形状の複雑さ等によりその性質を異にする。その技術的課題としては、強大な電磁力に対する対策、パルス磁界に原因する電気磁気的及び機械的問題の対策、ヘリウム液化・冷凍機の大型化と十分な信頼性の確立等が挙げられる。このため、世界各国でその技術開発が強力に進められつつある。 2. LCT計画
核融合装置には、いくつかの方式があるが、その中で最も良い成果を示しているのはトカマク方式である。従って、超電導コイルの技術開発は、トカマク方式のコイル中最も大型なトロイダル・コイルから始めるのが適切であろう。このトロイダル・コイル自身についても多くの方式及び構造が考えられている。しかし、これらの多くの方式等の評価を机上計算のみに頼ることはできない。すなわち、工業的技術開発を進めながら実験的に各種の方式を評価してゆくことが必要である。この開発手法はトカマク方式のトロイダル・コイルに限った事でなく、ポロイダル・コイルあるいはトカマク以外の方式の核融合用超電導コイルについても言えることである。 さて、コイルの寸法及び物理量という観点から、超電導トロイダル・コイル開発の一つの手法として、実験炉の約二分の一の寸法のコイルを作り、磁界や応力を実験炉と同程度の値にして、工学的評価研究を行ってゆこうという作業が米国で計画された。この作業の中では、上に述べたようないくつかの方式について同時に評価研究を行うことが考えられ、大型コイル事業(Large Coil Task-LCT)という国際協力として取上げられた。実験炉のトロイダル・コイルに要求されている条件とこれを模擬するためのLCTコイルの設計条件を第1表に対応させて示した。我が国も独自の核融合用超電導コイルの開発計画にこのLCTの作業を織り込み、原研(JAERI)を調印者として参加することが決められ、昭和53年4月に協定に調印した。本計画では、米国のオークリッジ国立研究所(ORNL)が3個のコイルを作り、原研、スイスの原子核研究所(SIN)及び、ユーラトムを代表して西ドイツのカールスルーエ原子力研究所(KfK)がそれぞれ1個のコイルを作ることになっている。各コイルは幾何学的取合面等を共通にして或る条件内での独自の設計と方式により作られる。第1図はこのLCTコイルの基本的構造を示すものである。6個のコイルは第2図に示す配置でオークリッジ国立研究所の実験装置に取りつけられ、それぞれのコイルの技術的評価を行う計画である。 3. 各国のLCTコイル
LCTコイルの設計は、参加国それぞれの独自性を発揮して進めることが基本的考え方である。設計パラメータの自主的決定の結果6個のコイルの特徴は次のようなものとなった。すなわち、浸漬冷凍方式によるものは米国のコイル2個、日本のコイル1個であり、残りの3個のコイルが導体の断面内にヘリウムを圧送する強制冷凍方式によるものである。この二つの方式が丁度半分ずつになった。超電導材料としては、米国の1個がNb3Sn材を用いるのに対し、他の5個のコイルはNb-Ti材を用いるという選択となった。巻枠の構造材料も、ステンレス鋼304系、同316系とアルミニウム合金の3種類のものがそれぞれ独自に用いられるという結果になった。更に巻枠の閉じ方もボルト方式、溶接方式の2方式が独自に選ばれた。導体構造、巻線方式等々数多くの設計項目が選定され、これらの一部をまとめてみると第2表のようになる。代表的な2個の導体の断面構造を第3図に示す。 このようにしてみると、6個のコイルは正に各国の技術レベル、LCTの技術的仕様の達成度、各方式の将来の発展性についての展望等多くの背景によってそれぞれの設計がまとめられていることが解る。そして、その製作結果を実験的に相互に比較評価することがLCTの作業の特徴である。超電導コイルは開発性の非常に強いものであり、また、LCTコイルが大型のものであること、さらに、米国までの距離があることから、ユーラトムと日本とはそれぞれ国内試験を行うことを自主的に決めた。 小型の超電導コイル製作の実績は十分あったとはいえ、いずれの国においてもLCTのような大電流、大型、高磁界、高応力のものの製作は初めての経験である。従って、基本的設計を決めた後も、詳細に進むに従って、それぞれの国で異った基本的データの充足、小型模型による理論的解析の実証、遭遇する加工技術上の難題の克服等、技術的諸課題の解決に主力を注ぎつつ作業が進められてきた。 4. 日本のコイルの製作と国内試験
日本のコイルの製作に当っては前節でのべた技術的課題を幾多克服してきたが、ここでは二つの例を挙げる。この作業の開始当初、国内のNb-Ti線については7T以上のデータはなく、原研で評価したところ、国外のものよりその特性がかなり劣っていることが判明した。このため、加工度、熱処理条件等を変え幾たびも試作改良を重ねた。その結果、最終的に8Tで105A/cm2の電流密度を得ることができ、国外そのものと同等かそれ以上になり、LCTの仕様を満足することができた。第二の例として、工業規模で作られるステンレス銅の4.2Kにおける機械的性質の解明が挙げられる。このデータも作業開始当時は全く無く、窒素の添加量により、その性質が極低温でどのように変るかを解明し、これにより、日本のLCT構造材である304L材に窒素を0.14%添加するということが決定された。 このようにして日本のコイルは昭和56年末に製作を終え、原研に搬入された。第4図は、そのコイルを国内試験装置に取りつける状況を示すものである。 LCTコイルの作業と並行してLCT国内試験装置の設計・建設を進めた。超電導コイルの実現はコイル本体のみでなく、ヘリウム液化・冷凍機を中心とする他の周辺機器が整備されて初めて首尾よく行われるものであり、これら周辺機器の信頼性が低いためにコイルの実験目的が達せられない例もよく見られた。国内試験装置は、ヘリウム液化、冷凍システム、コイルを収納する真空容器、コンピュータによるデータ取得・制御システム、直流電源及び遮断システム等から構成されている。いずれも未踏のものであるため、コイルの作業に勝るとも劣らぬ努力を払う必要があった。国内試験装置は昭和56年6月に完成した。第5図はLCTコイルを収納した高さ8m、直径5mの真空容器を示す。ヘリウム液化、冷凍機は原研がこれまでに蓄積した低温技術を結集して作られたもので、液化能力350l/h4.5Kの冷凍能力1200Wという国内外をとおして最大級の規模のものである。この機械にはタービン回路と液化回路とを分離する方式を採用した。第6図に、コイルを含むこの系統図を示す。このヘリウムのシステムはコンピュータにより制御されるという手法を取っており、これも先端技術の一つといえる。 このように周到に準備した国内試験装置を用いて行ったLCTコイルの実験により次のような成果が得られた。 ① 約50トンのコイルを、120時間(ORNLの仕様)で予定のヘリウム流量で極低温に冷すことができた。これにより熱設計が正しいことが実証された。 ② コイルへ定格電流値(10,220A)まで常電導転移することなく通電でき、かつ、この値を長時間保持できた。 ③ コイルの応力分布を測定し、計算値とほぼ一致した傾向が得られた。 ④ 定格電流値において人為的に1/2ターンの常電導部を作っても、自然に超電導状態に戻ることが実証された。第7図は、常電導部の伝播速度の測定結果を電流の関数としてグラフに示したものである。速度が負であることは、常電導が自然に超電導に戻ることを示している。これによりコイルの超電導性は十分安定であることが示された。 ⑤ コイル外部にある抵抗に人為的に磁気エネルギーを放出させ、そのエネルギー吸収率を測定した結果約95%という高い割合であることが解った。 ⑥ ヘリウム液化、冷凍機及びコンピュータ・システムは1ヵ月以上に亘る連続運転により高い信頼性が実証された。 このようにして日本のLCTコイルは、単体コイルとしての評価試験でオークリッジ国立研究所から与えられた仕様を十分に満足していることを示した。 5. まとめ
日本のLCTコイルは、米国オークリッジ国立研究所のLCT試験装置を据付け、先ず米国のコイルの一つとともに、二つのコイルを組合せての実験を昭和58年早々に実施する予定である。その後に完成するコイルを加え、昭和59年の初めには、六つのコイルによる実験が開始される計画である。この時、パルス、コイルが加えられ、パルス磁界による大型コイルヘの諸々の効果が初めて実験的に評価される。大型トロイダル・コイルの研究は、このように展開してゆくことになろう。 一方、実験炉においては、ポロイダル、コイルの超電導化も必要不可欠である。そのための開発は諸々の条件から、トロイダル、コイルの開発より立遅れてきた。今後この跛行性を取り除くよう、超電導ポロイダル、コイルの開発に一層力を入れることが、求められている。 原研における超電導トロイダル、コイルの研究開発が急速な進展をみせ、後発であったにも拘らずこのたび他国に先駆けてLCTの国内実験に成功したことは、核融合炉実現に向けての大きな成果と言えよう。これらの研究の遂行にあたり、官界、学界、産業界から多くの激励、御指導、御協力を受けた。感謝の意を表したい。 第1表 実験炉に要求されている条件とこれを模擬するためのLCTコイルの設計条件 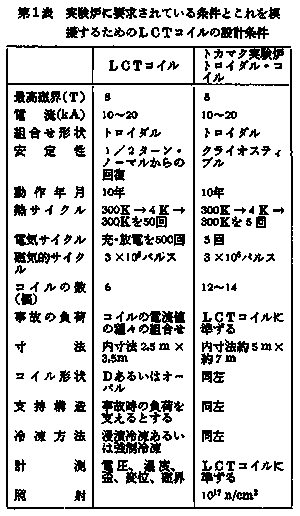 第2表 LCTの各コイルの基本設計パラメータ 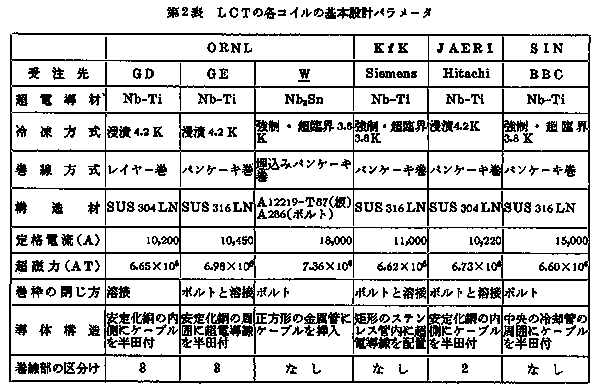 第1図 LCTコイルの基本的構造 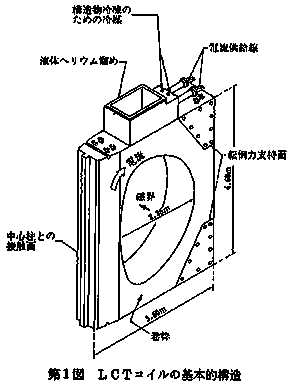 第2図 LCTコイルの配置と参加国 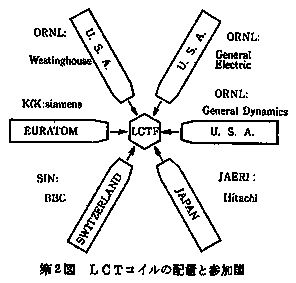 第3図 LCTコイルの代表的な導体構造 (a) KfK-Siemensの導体 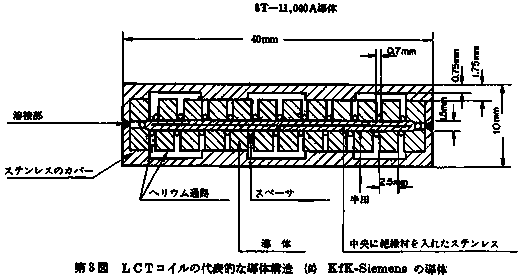 (b) JAERI-Hitachiの導体 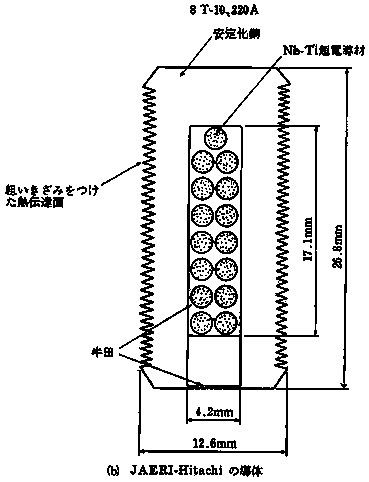 第4図 原研のLCT国内試験装置に設置される日本のLCTコイル 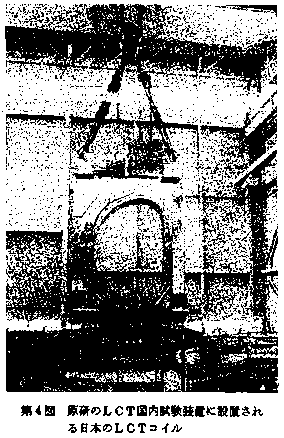 第5図 日本のLCTコイルを収納した真空容器(右側) 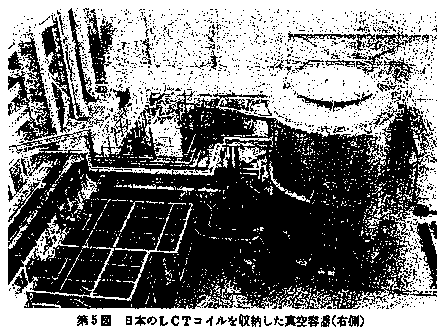 第6図 LCT国内試験装置のヘリウム系統図 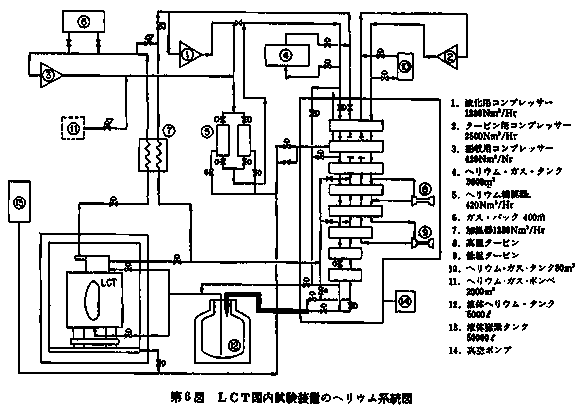 第7図 LCT国内試験結果の一つ:電流値による常電導部の伝播速度の変化。速度が負であることは自然に超電導に戻ることを意味している。 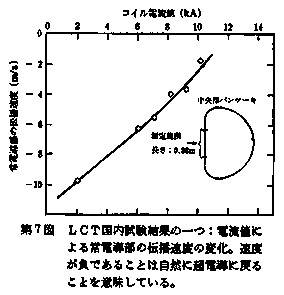 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |