| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
日本原子力研究所昭和57事業年度事業計画 内閣総理大臣が定めた昭和57年度原子力開発利用基本計画に基づく、昭和57事業年度における日本原子力研究所の事業計画を次のとおり定める。 Ⅰ 基本方針 昭和57年度においては、安全性の研究、多目的高温ガス炉の研究開発及び核融合の研究開発を重点として推進するとともに、放射線利用研究、関連研究及び基礎研究等について一層の充実をはかり、原子力の研究開発及び利用の促進に寄与するものとする。すなわち、
(1) 安全性の研究のうち工学的安全性研究については、軽水炉の冷却材喪失事故時の模擬実験、反応度事故実験を進めるとともに、燃料、材料及び構造等に関する安全性研究を進めるほか、燃料試験施設において使用済燃料体の試験を実施する。また、核燃料施設の臨界安全等に関する研究を進める。さらに、国から受託する安全性実証試験を進めるとともに、安全性研究に関する国際協力を行う。 環境安全性研究については、放射性廃棄物の処理処分の安全評価に関する研究及び実証試験、環境放射能・放射線の測定と評価に関する研究等を進める。 これらの試験研究の成果にもとづいて、各種の安全性解析コードの開発を進めるとともに、国の原子炉施設等の安全審査に協力する。 (2) 多目的高温ガス炉の研究開発については、大型構造機器実証試験ループの本体部の運転を行うほか、試験部の製作を進める。また、実験炉詳細設計を引き続き進めるとともに、高温構造試験研究及び炉物理、炉工学に関する研究、燃料及び材料の研究開発等を行うとともに、西独及び米国との国際協力を進める。 (3) 核融合の研究開発については、箏二段階核融合研究開発基本計画の主装置である臨界プラズマ試験装置の製作を進める。これと並行して、核融合研究用地の取得整備及び施設の建設を行う。また、プラズマの閉込め、加熱、計測等に関する実験等を進めるとともに、炉物理、炉工学、材料、超電導コイル、トリチウム技術等の研究並びに核融合炉システムの研究を進める。さらに日米科学技術協力をはじめ国際協力を進める。 (4) 放射線利用研究については、放射線化学の研究並びにラジオアイソトープの製造及び利用の研究を進めるとともに、原子力特定総合研究として進めてきた食品照射研究の成果のとりまとめを行う。 (5) 関連研究及び基礎研究については、炉物理、炉工学、燃料・材料、基礎的物理、原子炉化学、保障措置技術、原子炉解体技術等の研究開発を進めるとともに、高速増殖炉等の研究開発に関する動力炉・核燃料開発事業団の計画に協力する。 (6) 研究支援及び対外協力については、研究炉、材料試験炉、ホットラボ、照射施設、加速器等の施設の安全運転確保及び有効利用につとめ、JRR-3改造炉詳細設計を進める。また、安全管理及び放射線管理、並びに核物質保障措置及び防護対策の充実をはかる。アイソトープ事業として、特殊線源及び短寿命精製ラジオアイソトープ等の生産・頒布を進める。技術情報活動、成果の普及、並びに人材の養成につとめるとともに、国内及び海外原子力関係諸機関との協力を進める。 Ⅱ 事業の内容 1. 安全性の研究
(1) 工学的安全性研究
冷却材喪失事故に関しては、緊急炉心冷却系実験装置(ROSA-Ⅲ)によるBWRの緊急炉心冷却系(ECCS)作動模擬試験を終了させるとともに試験結果の解析を行う。また、PWRの小口径破断模擬試験のためのROSA-Ⅳ計画では、定常二相流試験装置による個別効果実験を開始するとともに、大型非定常試験装置の設計、製作を進める。 反応度事故に関しては、原子炉安全性研究炉(NSRR)による軽水炉燃料の破損実験を引き続き進めるとともに、高燃焼度燃料の実験に関する検討を行う。燃料安全性に関しては、燃料の照射挙動について材料試験炉(JMTR)等において沸騰水キャプセル(BOCA)等を用いた試験研究を実施するほか、燃料被覆材の事故時挙動に関する試験研究を進めるとともに、燃料試験施設による実用燃料の照射後試験を実施する。また、原子炉用電線ケーブルの健全性試験法の研究を進める。 国の安全性実証試験計画の一環として、格納容器圧力抑制系信頼性実証試験を完了させ、配管信頼性、大型再冠水効果及び再処理施設排気フイルタ事故時安全性に関する実証試験を引き続き進める。さらに、高性能燃料出力急昇試験設備整備等を引き続き行う。 このほか、LOFT、PBF、PNS、PHEBUS、ハルデン、デモランプ、スーパーランプ、HBEP(バッテル計画)等の海外における安全性研究計画に参加するとともに、大型再冠水効果試験に関する米国及び西独との研究協力を推進し、国際協力により安全性研究の一層の強化を図る。 (2) 環境安全性の研究
低・中レベル廃棄物固化体の安全評価試験、廃棄物固化体の海洋投棄時の健全性試験、陸地処分に関する安全評価等の研究を進めるとともに、高レベル放射性廃棄物固化体の安全評価試験及び新固化技術の開発、高レベル廃液の群分離技術の開発、地層処分に関する安全評価等、放射性廃棄物の処理処分の安全評価に関する研究を進める。また、国の安全性実証試験計画の一環として、低レベル放射性廃棄物封入容器の腐食安全性実証試験及び固化体長期浸出実証試験を進める。 また、緊急時の環境放射能予測システムの確立に関する研究など環境における放射能・放射線の測定と評価に関する研究を行うほか、気体状放射性物質の放出低減化に関する研究を進める。 (3) 原子炉安全性解析コードの開発及び安全審査解析
(1)、(2)の試験研究の成果にもとづき、原子炉及び核燃料取扱施設の安全性評価に関する解析コード及び環境放射能解析コード等の整備開発、導入コードの適用性評価を進めるとともに、確率論的安全評価手法の開発研究を行う。また、国からの受託による臨界安全解析データ・プログラム整備を開始する。さらに、国の原子力施設安全審査に協力するため、関連事項の調査及び必要な計算解析を行うほか、原子力工学試験センターの安全解析業務に協力する。 2. 多目的高温ガス炉の研究開発
大型構造機器実証試験ループ(HENDEL)の本体部の運転を開始するとともに燃料体スタック実証試験部(T1)の製作を完了し、炉内構造物実証試験部(T2)の製作に着手する。炉心部、配管等に関する高温構造試験研究及び伝熱流動試験、高温計測器開発などの炉工学的研究を行うほか、実験炉の設計、安全審査等に資する炉物理実験のために半均質臨界実験装置(SHE)の改造を進める。また、材料試験炉の大洗1号ガスループ(OGL-1)及び研究炉による被覆粒子燃料、黒鉛及び耐高温金属材料の照射試験及び核分裂生成物挙動試験等を行う。さらに、核熱利用による熱化学的水素製造に関する基礎的研究を進める。また、実験炉の詳細設計を引き続き実施する。さらに、研究開発の効果的促進を図るため、西独及び米国との国際協力を進める。 3. 核融合の研究開発
(1) 核融合炉心プラズマ技術の研究開発
臨界プラズマ試験装置(JT-60)並びに計測装置の製作を進めるとともに、加熱装置実機の製作を開始する。 中間ベータ値トーラス磁場装置(JFT-2)により、引き続きプラズマ閉込め実験、中性粒子入射及び高周波を用いたプラズマの高加熱密度試験を行い、プラズマ計測、プラズマ閉込めの理論等について研究を進める。また、JFT-2の改造を進める。 (2) 炉心工学技術及び炉工学技術の研究開発
真空壁の表面現象等炉心工学に関する研究を進めるとともに、超電導コイルの研究、核融合炉物理実験用中性子源(FNS)を用いた炉物理の研究、核融合炉材料の物性研究及び照射研究等、炉工学の研究を進める。また、トリチウム取扱・プロセス技術及び製造技術の研究をより強化するためトリチウム・プロセス研究棟の建設を開始する。さらに、核融合炉システムの研究を継続して進める。 国際協力では、新エネルギー研究開発に関する日米科学技術協力に基づくダブレットⅢ計画を進めるとともに、核融合炉材料に関する共同照射計画を開始する。また、国際原子力機関(IAEA)の次期装置共同検討計画(INTOR計画)、国際エネルギー機関(IEA)の超電導コイル共同開発計画(LCT計画)、核融合炉材料の照射損傷に関する研究開発計画等に引き続き参加する。 4. 放射線利用研究
(1) 放射線化学の研究
放射線法による電池隔膜、固定化酵素、徐放性制癌剤及び難燃性電線材料等の高分子材料の開発、並びに放射線による汚泥の速成堆肥化及び排煙・廃水処理技術の開発等を進めるとともに、高線量率加速器等による放射線化学の研究を進める。 また、開発途上国への技術移転を目的としたRCA計画を中心として国際協力を進める。 (2) 食品照射研究
原子力特定総合研究として進めてきた指定品目の照射技術の開発について、成果のとりまとめを行う。 (3) ラジオアイソトープ製造及び利用研究
各種有用ラジオアイソトープの製造研究等を進めるとともにカリホルニウム-252等のアイソトープの利用に関する研究を進める。また、外部のアイソトープ利用業務に協力する。 5. 関連研究及び基礎研究
炉物理、炉工学の研究では、高速炉、熱中性子炉等の炉物理及び計測制御等に関する研究を進めるとともに、高速臨界実験装置(FCA)、軽水臨界実験装置(TCA)等を用いた炉物理実験等を行う。 燃料・材料及び核燃料サイクルに関する研究では、ウラン・プルトニウム混合炭化物燃料、原子炉材料等の物性研究及び照射研究、同位体分離技術の研究、保障措置技術の開発研究、研究炉の新燃料要素の開発等を進める。 基礎的物理の研究では、タンデム加速器等を用いて重イオン・中性子等による核物理、燃料・材料の基礎物性の研究を行うとともに、核データ及び原子分子データの整備を引き続き進める。さらに中性子散乱及び核物理の研究について、米国との協力を進める。 原子炉化学の研究では、放射性核種の原子炉化学的研究、水素同位体分離の研究、核燃料・炉材料等の分析化学的研究等を進める。 国からの受託により、原子炉解体技術開発を引き続き進めるとともに、大型再処理施設保障措置に関する試験研究を開始する。 さらに、エネルギー戦略分析、原子力システム解析、及び熱中性子体系標準コードシステムの開発等のソフトウェア活動を進める。 6. 研究支援及び対外協力
(1) 施設の運転管理
(a) 原子炉
本年度は次の運転を行い、その効率的利用をはかるとともにJRR-3故造炉の詳細設計を進める。 (b) ホットラボラトリ及び加速器等の共同利用施設
(ⅰ) ホットラボラトリ(東海地区及び大洗地区)
研究炉、材料試験炉(JMTR)による照射試料等各種燃料材料の照射後試験を進める。 (ⅱ) 加速器
線型加速器(東海地区)を核物理実験等に、コックロフト・ワルトン型加速器(高崎地区1号)及びカスケード型加速器(高崎地区2号)を放射線化学の研究開発試験等に使用するとともに、共同利用を行う。 (ⅲ) コバルト-60照射施設
東海地区では、1万キュリー線源により、共同利用を進める。 高崎地区では、60万キュリー線源により、放射線化学の研究開発を行うとともに、共同利用を進める。 (2) 計算センター
安全性の研究、原子炉の設計、原子力コード及び核データの整備、核融合の研究等のために必要な計算業務を進める。 原子炉運転予定表 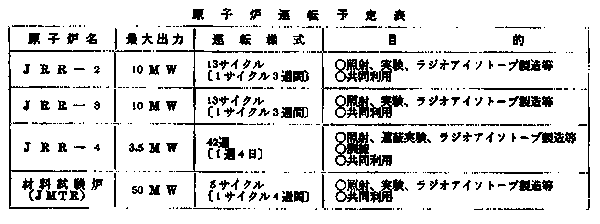 (3) 安全管理、保障措置及び放射性廃棄物処理
原子炉、ホットラボラトリ、各種照射施設等を中心とした放射線管理、個人被曝管理、環境放射能管理をはじめとする各種安全管理業務を進めるとともに、これらに必要な管理技術の開発及び緊急時対策の整備を進める。核燃料物質等の管理については、保障措置及び防護のシステムの維持に努める。また、放射性廃棄物の処理業務を行う。 (4) 施設の保守管理・整備及び技術サービス
諸施設の保守、管理及び整備、工作・エレクトロニクスに関する技術サービスの業務を進める。 (5) アイソトープ事業
モリブデン-99等の精製ラジオアイソトープ、イリジウム-192等の線源ラジオアイソトープの製造及び頒布を進めるとともに、日本アイソトープ協会経由等の他機関の放射性廃棄物の処理事業を行う。 (6) 技術情報及び成果の普及
国内外の技術情報資料の効果的な収集及び提供並びに所内研究成果等の公刊普及に努めるとともに、国際原子力情報システム(INIS)計画に関する業務の充実を図る。 (7) 技術者等の養成、訓練
ラジオアイソトープ研修部門については、基礎、高級、専門の各課程並びに第1種放射線取扱主任者講習及び作業環境測定士講習(合計21回)を実施する。原子炉研修部門については、一般、高級及び専門の各課程並びに入門講座、短期講座のほか、新規課程として放射線防護専門課程(合計20回)を実施する。 (8) 建設整備
(1) 東海地区
(a) 安全性研究のため、大型非定常ループ試験棟、廃棄物安全試験施設及び環境シミュレーション試験施設の建設整備を行う。 (b) 多目的高温ガス炉の研究のため、大型構造機器実証試験ループ試験部建家の建設を完了する。 (c) 基礎研究のため、第1研究棟の改修を行う。 (2) 那珂地区
核融合研究に必要な用地の取得及び整備並びにJT-60実験棟等の建設を進めるとともに、ユーティリティ施設、厚生施設等の建設を行う。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |