| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「長期エネルギー需給見通し」中間報告 昭和57年4月21日
総合エネルギー調査会需給部会
「長期エネルギー需給見通し」中間報告
総合エネルギー調査会需給部会は、別添の通り、需給部会企画専門委員会から、当部会に報告された「『長期エネルギー需給見通し』の改定について」を審議した結果、これを当部会の中間報告とする。 昭和57年4月21日
総合エネルギー調査会需給部会
部会長 円城寺 次郎
「長期エネルギー需給見通し」の改定について
昭和57年4月21日
総合エネルギー調査会需給部会
企画専門委員会
-はじめに-
当専門委員会は、昭和56年6月3日以降11回にわたり、長期的なエネルギー需給の見通しについて、様々な角度から検討を進めてきたが、4月21日、以下のとおりとりまとめを行ったので報告する。 なお、この見通しは、日本経済が1980年代において年率5%程度の経済成長を遂げることを前提として官民を挙げて最大限の努力を行った場合のエネルギーの需給の見通しを示したものである。 第1章 需給見通し策定の背景と基本的な考え方
<背景>
1. 当専門委員会は、昭和54年8月、昭和60年度、昭和65年度及び昭和70年度のエネルギー需給暫定見通しを策定し、また昭和55年11月には、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に基づく昭和65年度石油代替エネルギーの供給目標策定のための基本的考え方を示した。 2. しかし、その後、内外のエネルギー情勢は大きく変動している。まず、国際エネルギー情勢については、昭和54年春以降、イランの政情不安、イラン・イラク紛争の本格化等による石油需給逼化の影響を受けて基準原油価格(アラビアンライト価格)は、石油輸出国機構(OPEC)諸国により数次にわたって引き上げられ、昭和54年8月の18ドル/バーレルから昭和55年11日にはアラビアンライト価格で32ドル/バーレル、見なし基準原油価格で36ドル/バーレルまで上昇した。 このような石油情勢に対応すべく、先進消費国は、国際エネルギー機関(IEA)、先進国首脳会議(サミット)等の場において国際協調の強化を図ってきた。昭和55年6月に開催されたベニス・サミットにおいては、経済成長と石油消費のリンクを断つこと、IEA加盟国の昭和60年の石油輸入目標が東京サミットにおいて設定された数値を大幅に下回ることなどを内容とする宣言が出され、またその後に開催されたIEA閣僚理事会やオタワ・サミットにおいても、エネルギー需給構造の変革のための諸施策の進展に努力を払う旨の合意がなされた。 先進消費国は、このような国際協調のもとに、省エネルギーの推進、石油代替エネルギーの開発・導入の促進等の施策を進め、エネルギー生産性の向上や石油消費の節減に努力を傾けてきた。 先進消費国におけるかかる諸施策の浸透に加えて、石油価格の上昇に伴うデフレ的影響を反映した世界経済の停滞等により最近に至り世界の石油消費は大幅な減少を示し、このため昭和56年初頭以降、国際的な石油需給は緩和基調で推移している。これを反映して、第一次石油危機時には67%であった自由世界に占めるOPEC諸国の石油供給のシェアは昭和56年には54%にまで低下し、また同年10月のOPECジュネーブ総会においては基準原油価格(アラビアンライト価格)が34ドル/バーレルに統一された。 このように国際石油情勢にはある程度構造的な変化が生じつつあるとみられるが、かかる傾向が持続するか否かは明確でなく、かつ、本年3月にはOPEC諸国が生産上限を設定するなど新たな動きがみられ、国際石油情勢は、当面緩和基調にあるものの多くの不安定要因を含みつつ推移している。 次に、国内面においては、基礎素材産業の伸び悩み、加工組立産業の著しい伸展にみられる産業構造の変化、エネルギー多消費型産業を中心とする省エネルギーの進展、石油代替エネルギーの開発・導入等により、昭和55年度には、3.7%の経済成長を達成しつつ、エネルギー総需要は前年度に比して減少を示した。また、エネルギー供給における石油依存度も11年ぶりに7割を下回るなど、近年の我が国のエネルギー需給には構造的な変化の徴候がみられるに至っている。 3. このように、我が国を取り巻く世界のエネルギー情勢は大きく変化しており、また我が国のエネルギー需給両面にも様々な変化がみられ始めていることから、改めて今後のエネルギー政策の指針となる長期エネルギー需給見通しを明らかにする必要がでてきている。 <基本的な考え方>
1. 今後のエネルギー情勢の基本認識
今後のエネルギー情勢を考えるに当たって、引き続きエネルギー供給の大宗を占めると考えられる石油については、その国際的な需給は、当面緩和基調で推移するとの見方もなされている。これは、二度にわたる石油危機を通じた石油価格の大幅な上昇等が、石油消費国における石油需要の大幅な減退をもたらし、従来の石油需給に係る消費国と産油国の基本的関係に変化の兆しが現われつつあることの反映とも考えられる。 しかしながら、中長期的にみれば、世界景気の回復等に伴い世界の石油需要は増加するものと予想されるが、それに見合って世界の石油供給が今後とも増大することは困難とみられることから、国際的な石油需給は、一時的に緩和することがあっても、基本的には、循環的かつ構造的に、逼迫するものと考えらる。また、石油の主要な供給源である中東地域の政情は依然として不安定であり、この地域からの一時的あるいは長期的な供給制約が強まる可能性も否定してない。 他方、原子力、石炭、天然ガス等の石油代替エネルギーについては、今後とも、基本的には、経済性、安定性等の面において石油に対する優位性を維持していくものと考えられる。なお、石炭及び天然ガスについては、国際的な需給動向や供給国の政策如何によっては、不透明な点も残されている。 このような状況を踏まえ、またエネルギーの持つ国民生活、経済活動全般にわたる影響力の大きさを勘案するならば、長期的かつ多面的な視点に立ったエネルギー問題への対応が要請されよう。 2. エネルギー政策の基本的な考え方
我が国は、エネルギー供給の石油依存度が高いことに加え、国内資源が乏しいことなどから、多くの先進国に比してエネルギー供給構造の脆弱性が際立っている。このため、今後の国民生活、経済活動の安定的発展を図る上で、エネルギー供給の不安定性及び国際的なエネルギー需給の変動によるエネルギー価格の大幅な上昇が制約要因となる可能性は依然として高いものと考えられる。特に、近年、エネルギー価格の上昇がエネルギー多消費型産業を中心として産業活動の面においても大きな影響を与えており、このような状況にかんがみてもエネルギー問題の解決は今後とも我が国にとって大きな課題の一つといえよう。 こうした問題に対処するためには、需要面において、引き続き各分野での省エネルギーに全力を挙げて取り組むとともに、供給面において、石油の安定供給の確保に加え、石油代替エネルギーの開発・導入の促進を図ることにより、安定的なエネルギー供給の基盤整備を基本とし、また今後とも予想されるエネルギー価格の実質的上昇を国民経済全体が吸収し、安定化しうるエネルギー需給構造の実現に努めることが必要である。更に、より長期的な視点に立って、国際的な需給の変動による影響の小さいエネルギーについて技術開発に努め、エネルギー供給力の向上を図ることも不可欠である。 3. 総合エネルギー政策の展開
(1) 我が国は、従来から、石油の安定供給の確保、石油代替エネルギーの開発・導入の促進及び省エネルギーの開発・導入の促進及び省エネルギーの推進を基本的な方向とする総合エネルギー政策を推進しているところであるが、以上に述べたエネルギー政策の基本的な考え方に基づき、新たな決意のもとに、昭和65年度の石油依存度を5割以下とすべく、次のとおり、今後とも総合エネルギー政策を強力かつ効率的に推進すべきものと考える。 ① 石油の安定供給の確保:我が国は、エネルギー・セキュリティの確保、国際的責務の遂行等の観点から、エネルギーの石油依存度の低減を図ってきているが、石油が依然エネルギー供給の相当の部分を占めるものであることから、その安定供給の確保を図ることは重要な課題である。今後とも、産油国との関係強化、自主開発の推進、備蓄の推進等の努力を続けるほか、石油安定供給の担い手である石油産業の体質強化を図る必要がある。 ② 石油代替エネルギーの開発・導入の促進:我が国は、昭和55年度においてエネルギーの石油依存度が7割を下回ったが、依然として他の先進国に比して石油依存度が高く、それが我が国エネルギー供給構造の脆弱性の大きな要因となっている。今後ともエネルギー需要の増大が予想される我が国にとって、石油代替エネルギーの開発・導入は、石油依存度の低減に加え、エネルギーの安定的確保及びエネルギーコスト上昇の抑制の観点からも極めて重要な課題であり、このため、原子力、石炭、天然ガスを中心に導入促進のための各種施策の円滑な推進を図るとともに、新たなエネルギーを中心に技術開発に努めることが不可欠である。 なお、石油代替エネルギーの開発・導入に当たっては、エネルギー需要動向や技術開発状況等を踏まえて、適切な供給構造の着実な実現に努める必要がある。 ③ 省エネルギーの推進:省エネルギーは、単にエネルギーの需要を縮小するのみならず、エネルギー効率の向上を通じてエネルギー価格の上昇を吸収し、経済全体の活性化に資するものであり、また、我が国独自の努力によって推進されうるものである。エネルギー供給構造の脆弱な我が国にとって、省エネルギーの推進は、エネルギー制約を緩和しうる極めて有効な手段であるといえよう。 省エネルギーの推進は、プライス・メカニズムの働く余地が大きく、民間の創意と活力に期待するところも少なくないが、政府としては、これを補完する観点から、普及啓蒙に努める一方、省エネルギー対策の導入に要する資金負担の増大等を勘案して適切な政策的誘導を図るとともに、将来の省エネルギー対策の基盤となる技術革新が円滑に進むよう技術開発を積極的に進める必要がある。 第2章 需給見通しの概要
<需要>
昭和65年度におけるエネルギー総需要については、経済成長率は昭和55年度以降年平均5%程度、産業構造は産業構造審議会報告「80年代の産業構造の展望と課題」(昭和55年11月)を基本に、その後における産業構造審議会各部会における検討結果等、最近の経済環境の変化を折り込んで展望を行い、これらを前提とすれば、省エネルギー推進の効果と相まって、全体として5億9,000万kl程度(原油換算)になるものと見込まれる。この場合、エネルギー需要の国民総生産原単位は、昭和55年度の226kl/億円から昭和65年度には191kl/億円となり、15.5%低減するものと見込まれるが、更に一層の省エネルギーに努めることが肝要である。 二次エネルギー需要については、電力のシェア(総エネルギー需要に占める電力需要の割合)は、昭和55年度の33%から昭和65年度の37%に増加するものと見込まれる。 また、産業、民生、運輸の各分野におけるエネルギー需要の動向は、まず、産業については、エネルギー多消費型産業を中心とした省エネルギー努力の一層の進展や基礎素材産業の伸び悩み、加工組立産業の著しい進展等の産業構造の変化の結果、生産額当たりの原単位は大幅に低下し、エネルギー需要全体に占めるシェアが低下する。また、民生については、家庭部門において省エネルギー意識の定着は図られるものの生活水準の向上により電力を中心としたエネルギー需要が増加し、一方業務部門においてもサービス産業の伸展等に伴いエネルギー需要は増加するなど、エネルギー需要全体の伸びをかなり上回って需要が拡大する。更に、運輸については、乗用車、トラック、航空機を中心に輸送量の伸びは続くが、燃費改善、乗車効率の向上等によりエネルギー需要に占めるシェアは若干低下する。 <供給>
昭和65年度におけるエネルギー供給については、各エネルギー源の量的側面に加え、経済性・安定性等の質的側面に配意した、適切な供給構造の実現を見込み、全体として石油依存度の低減を図ることが肝要である。 ① 石炭
石炭は、世界的にみて化石燃料中最も豊富な資源であり、また世界各地に分散して賦存していることから我が国においても当面石油代替エネルギーの中でも最も量的に期待できるものとして、環境保全に留意しつつ、その導入を積極的に推進すべきものである。このため、貴重な国内資源である国内石炭については、昭和56年8月の石炭鉱業審議会の答申を踏まえ、現在程度の生産の維持を基調としつつ、今後の石炭企業の体質改善や石炭需給環境の好転を待って、将来における年産2,000万t程度の生産水準の達成を目指すことを基本的な考え方とし、保安の確保を第一として、現存炭鉱における合理化等所要の施策を講ずべきである。また、海外炭については、今後の需要動向を踏まえつつ供給源の多角化や石炭利用技術の開発による利用炭種の拡大に加え、炭鉱開発から積出し、受入れ施設に至るコールチェーンの総合的システム化等を推進し、長期安定的な供給確保を図っていくことが重要である。 ② 原子力
原子力は、自主的な核燃料サイクルの確立と相まって供給安定性のある準国産エネルギーとして位置付けられるとともに、経済性・大量供給性等多くの特長を有しており、今後とも石油依存度低減の中核的役割を担うものとして、その開発を最大限に推進すべきものである。そのため、安全性の確保、核燃料サイクルの確立等に努めることに加え、地元をはじめ国民の理解と協力を得るべく、パブリック・アクセプタンスの向上を図るなど立地の円滑化のための施策を強力に推進する必要がある。また、長期的な観点から、新型炉の開発・導入、新立地方式の導入、多目的利用等のための技術開発を推進することが重要である。 ③ 天然ガス
LNGは、クリーンなエネルギーであり、その供給にも比較的安定性が期待しうることから、今後とも都市及びその周辺地域を中心とした導入の拡大を推進する必要がある。また、国内天然ガスについては、国内石油と相まって貴重な国内資源として積極的にその開発を促進する必要がある。 ④ 水力
水力は、今後は中小規模の多地点開発が中心となるが、貴重な国内資源であり、かつクリーンな循環エネルギーであることから、積極的に開発を促進する必要がある。 ⑤ 地熱
地熱は、火山国である我が国に豊富に賦存する貴重なエネルギーであることから、環境保全に留意しつつ、積極的に開発を促進する必要がある。 ⑥ 新燃料油、新エネルギー、その他
新燃料油等の新たなエネルギー源については、その性状は様様であるが、石油の直接的な代替となって将来の石油価格上昇の抑止力となりうるもの、未利用資源の活用が可能となりエネルギー供給量を増大させるもの、再生可能なもの等が多く含まれるため、将来のエネルギー供給源としての期待が大きい。これらについては、一部実用化されているもの
もあるが、長期の技術開発期間を要するものも多いことから、短期的な市場の動向に左右されることなく、計画的な開発・導入を進める必要がある。 ⑦ 石油
石油については、今後需要の伸びを見込むことは困難であるが、昭和65年度においては、なお、エネルギー供給の大宗を占めることが予想され、産油国との協調、自主開発の推進、更には、安定供給の担い手たる石油産業の基盤強化等により、その安定的な供給に努めるべきである。一方、石油需要が民生用石油製品を主体とする中軽質留分にシフトするものと見込まれることから、重質油対策の実施が必要となる。LPGについては、供給源の多角化等の対策が重要となる。 また、緊急時に備えた石油備蓄については、石油供給の不安定性にかんがみ、引き続き計画的に所要の備蓄量の確保に努める必要がある。 <昭和75年度(西暦2000年)のエネルギー需給>
1. 石油代替エネルギーの開発、新しいエネルギー利用技術の研究あるいはエネルギー供給システムの確立には、多くの時間を必要とし、また省エネルギーの一層の実現には、産業社会の変化等を伴う長期間の努力を払う必要がある。このようなエネルギー政策の長期的性格にかんがみ、エネルギー需給の将来の方向を示すべく、今回新たに、昭和75年度(西暦2000年)のエネルギー需給を展望した。 2. しかしながら、こうした長期の展望については、不確定要因も多く、ここでは経済成長率が昭和65年度以降年率4%程度を推移するなどの仮定に基づき需給の推計等を行ったが、その考え方は、以下のとおりである。 (1) 国際的な石油需給については、産油国の資源温存政策、発展途上国の工業化等により、漸次逼迫化りの傾向をたどり、それに伴って国際石油価格も実質ベースで上昇を示すとともに、石油供給の不安安性も増大する。 (2) 我が国のエネルギー需要については、相当程度の省エネルギーが進展しつつ、産業、運輸、民生の各分野とも経済の発展に伴いかなり増大する。産業においては、多角的な知識集約化が一層進展し、エネルギー需要の伸びは相対的に小さくなる。また、民生では、生活水準の上昇や生活形態の変化等に伴い電力を中心として、運輸では、モータリゼーションの進展等に伴いそれぞれ需要は増加する。 (3) 以上のような内外の動向を踏まえて、エネルギー供給は、次のような方向で推移する。 ① 石油需給の逼迫化傾向のもと、石油代替エネルギーへの移行が着実に進展する。 ② 原子力利用がより一層増大し、電力供給構成において原子力の割合が4割を超え、化石燃料全体のそれを上回る。 ③ 技術開発の成果が遂次実用化されることに伴い石炭液化等新エネルギーの利用が本格化する。 ④ 石油については、民生用、運輸用を主体とした中軽質留分への需要が引き続き増大する。 第3章 結論
1. 我が国は、他の先進国に比して高い経済成長を達成しつつ、昭和55年度には、11年ぶりに石油依存度が7割を下回るなど、二度にわたる石油危機への対応は、適切なものであったといえる。このことは、エネルギー問題への我が国の対応が妥当なものであったことを示すとともに、この問題が官民一体となった努力により克服しうるものであることを意味している。 2. 他の先進国に比して極めて脆弱なエネルギー供給構造を有し、エネルギー問題が国民生活、経済活動に対する制約となる可能性が高い我が国にとっては、将来において大きな困難を招来することのないよう、今後とも常に長期的な視点に立ったエネルギー問題への取り組みが必要である。このため、安定的なエネルギー供給の基盤整備に加え、今後とも上昇が予想されるエネルギー価格を国民経済全体が吸収し、安定化しうるエネルギー需給構造の実現や各種技術開発等による将来におけるエネルギー供給力の向上を目指すことが肝要であると考える。 3. かかる基本的な考え方のもとに策定された本長期エネルギー需給見通しは、今後のエネルギー政策の指針となるべきものであり、また国民がエネルギー問題克服のために目標とすべきビジョンでもある。この長期エネルギー需給見通しを踏まえて、引き続き、官民あげて重点的かつ計画的に総合エネルギー政策を推進するよう期待する。 4. なお、具体的な施策等については、今後、必要に応じ、関係審議会等における審議を経るなど十分な検討を加え、早急にその実現を図っていく必要がある。また、「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」に基づく石油代替エネルギーの供給目標については、今回改定した「長期エネルギー需給見通し」に基づき、速やかに所要の改定を行うべきであると考える。 長期エネルギー需給見通し 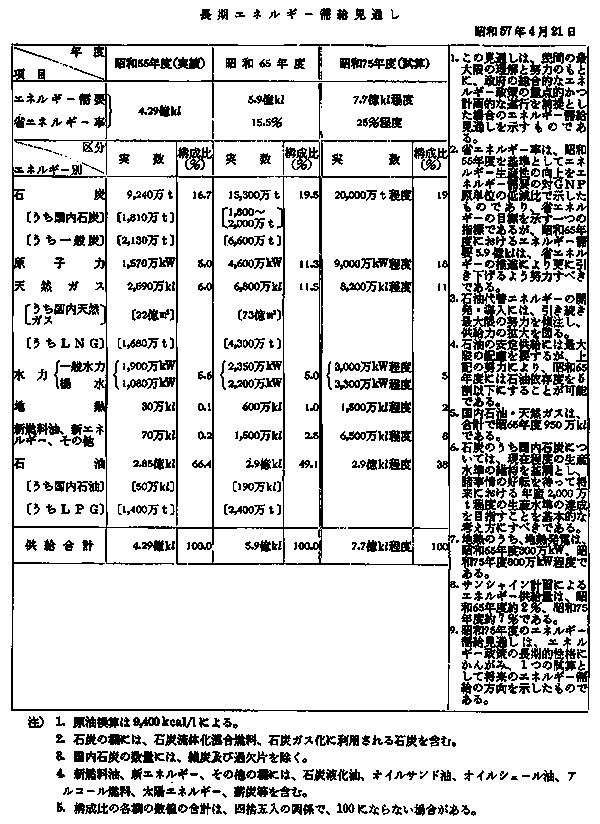 (参考資料1)
エネルギー需要見通し 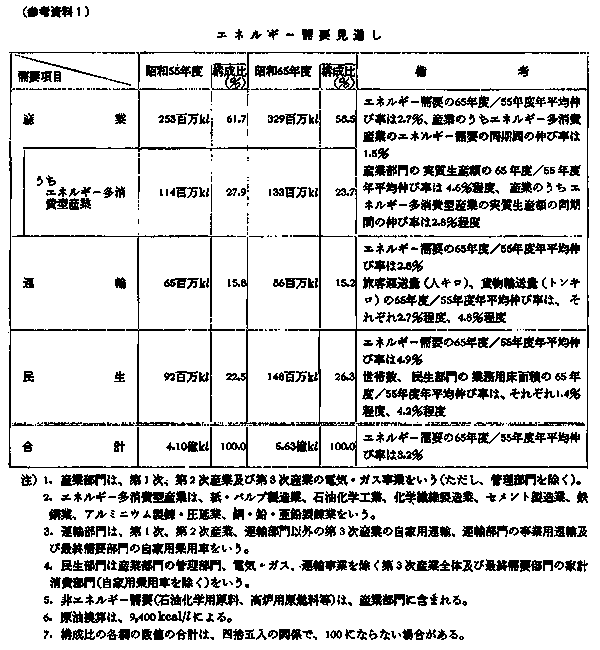 (参考資料2)
エネルギー供給見通し 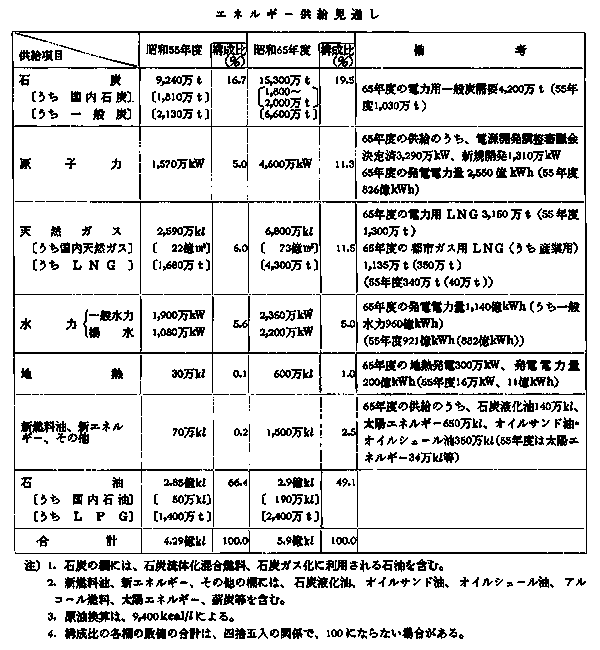 (参考資料3)
エネルギー需給バランス表 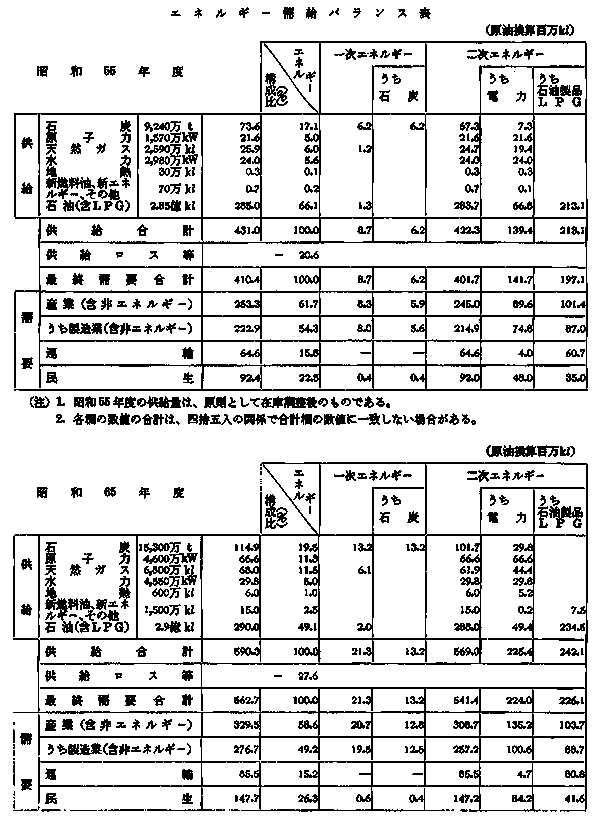 総合エネルギー調査会需給部会
(部会長)
総合エネルギー調査会需給部会企画専門委員会
(委員長)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |