| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廃炉対策専門部会報告書 原子炉の廃止措置について 昭和57年3月16日
原子力委員会
廃炉対策専門部会
昭和57年3月16日
原子力委員会
委員長 中川 一郎殿
廃炉対策専門部会
部会長 吉岡 俊男
本専門部会は、昭和55年11月28日付け原子力委員会決定に基づき、原子炉の廃止措置に係る重要事項について鋭意審議を行ってきましたが、このほどその結論を得たので、ここに報告いたします。 はじめに
原子力開発利用の進展に伴い、原子炉が稼働期間を経過した後における、原子炉の恒久的な運転終了に伴ってとられる廃止措置を円滑に実施するための対策を確立することが、近年重要な課題となっている。このため、本専門部会は昭和55年11月28日付け原子力委員会決定に基づき、これまでの内外の調査研究の成果を基礎資料としつつ、本措置のあり方及びそのための対策に関する基本的事項、総合的な技術開発計画等について鋭意審議を行い、ここにその結果をとりまとめた。 なお、本報告書では、実用発電用原子炉に主眼を置いて検討したが、試験研究用原子炉等についてもこれに準じた考え方で対応できると考えられる。 Ⅰ 原子炉の廃止措置に関する基本的な考え方 1. 対策の重要性
我が国初の実用発電用原子炉が運転開始されたのは、昭和41年(日本原子力発電(株)東海発電所)であり、以降順次新しい原子力発電所が建設、運転され、今後も、我が国のエネルギー供給の重要な方策として原子力発電所の建設は更に推進されることになる。こうした、原子力開発利用の進展に伴い、近年、原子炉が稼働期間を経過した後における、原子炉の恒久的な運転終了に伴ってとられる廃止措置(以下、「原子炉の廃止措置」という。)のあり方及びそのための対策を明確にすることが要請されている。 (1) 現状
欧米各国において、運転を終了した発電用原子炉は既に30基を超え、それぞれ、原子炉施設(原子炉及びその附属施設をいう。)は密閉管理、遮蔽隔離あるいは解体撤去と呼ばれる措置がとられている。また、小型の試験研究用原子炉や臨界実験装置についても数多く運転を終了しており、同様の措置がとられている。これらのうち、現在までに完全に解体された発電用原子炉施設の例としては、米国のエルク・リバー炉(BWR.電気出力2.2万キロワット)がある。 一方、我が国では発電用原子炉に関しての廃止措置をとった例は未だないが、日本原子力研究所の水均質臨界実験装置(AHCF)等は解体され、同研究所の試験研究用原子炉(JRR-1)等は燃料等を取り除き安全に保管管理されている。 このように内外の原子炉施設の解体等の実例は小規模の試験研究用原子炉が主であるが、今後、大型の実用発電用原子炉が恒久的に運転を終了することになると予想されることから、ここ数年来、各国とも原子炉の廃止措置のあり方について調査検討を行うとともに必要な技術開発を推進している。また、国際原子力機関(IAEA)、経済協力開発機構(OECD)等の国際機関においても同様の検討が行われつつある。特に、IAEAは、昭和50年に原子炉の廃止措置に関して3種類の分類を提案し、各国の対策確立上、参考にされている。 (2) 対策の視点
こうした状況の下で原子炉が恒久的に運転を終了した後の対応が、原子炉設置者にとって重要な課題となり、また原子炉が立地している地域社会にとっても大きな関心事となりつつある。即ち、原子炉の廃止措置が原子炉の設置、運転の場合と同様に適切に実施されることは、原子力開発利用の推進の観点から特に要請されることであり、原子力政策上の重要な課題である。 この原子炉の廃止措置は、従来内外で実施された調査研究又は原子炉施設の解体等の経験からみて、現在の技術等でも対応可能と考えられるが、安全性、経済性等に留意してこれをより円滑に進めるための十分な対策を、現時点から順次整備していく必要がある。 2. 原子炉の廃止措置のあり方
原子炉の稼働期間は、個々の原子炉によって多小の差があるものの、一般に30~40年と考えられており、対策を考える上での運転開始から恒久的な運転終了までの期間は、一応30年程度とみることが適当である。恒久的に運転を終了した原子炉は、燃料を取り出した後も放射化生成物等残存放射能を有しており、こうした原子炉施設について安全な管理、処分等の措置がとられなければならない。 (1) 原子炉の廃止措置に関する分類
原子炉の廃止措置に関しては、昭和50年にIAEAより3種類の分類が提案されており(「原子炉施設のデコミッショニングに関する技術委員会」報告書、IAEA-179)、米国(米国原子力規制委員会(NRC)規制指針 Regulatory Guide 1.86)、西独(原子力法)等においてそれと類似の廃止措置がそれぞれの制度の中で適宜、実施できるようになっている。これらは原子炉施設の物理的状態等から原子炉の廃止措置を次の3つに大別している。 (ⅰ) 原子炉施設を閉鎖し、これを適切な管理下におくもの。 (ⅱ) 原子炉に遮蔽等の工事を行って放射能を有する物質を強固に外部から隔離するもの。 (ⅲ) 原子炉施設内の放射能を有する構造物等を解体撤去するもの。 我が国において原子炉の廃止措置を検討する場合も、IAEA等の分類を踏まえ、別表のような分類を基本とするのが適当である。 (参考)IAEAとNRCの分類の比較 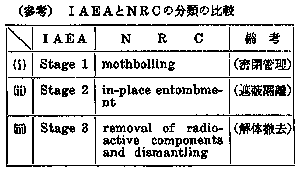 (別表) 原子炉の廃止措置の分類
1. 密閉管理
(措置) 燃料、制御棒、冷却材等は原則として除去する。更に一次系機器は洗浄、乾燥を行う場合もある。附属機器には、原則として手をつけずに原子炉施設を閉鎖する。 (管理) 上記の作業後、公衆の健康と安全を確保するために、常時、放射線モニタリング、環境の監視、出入管理等を行う。 (状態) 原子炉建屋の敷地内には再利用可能な余地は少ない。 2. 遮蔽隔離
(措置) 燃料、制御棒、冷却材等は全て除去する。上記1より広範囲の除染と構造物の部分的解体撤去を行うとともに、残存する放射化構造物(圧力容器、炉内構造物)等を生体遮蔽コンクリート等からなる強固な遮蔽隔離障壁の内部に封じ込め保管する。 (管理) 当初は放射線モニタリング等の管理を行うが、継続的な安定が確認されれば、定期的な点検に移行する。 (状態) 遮蔽隔離障壁内の封じ込め部以外は解体可能であり、これにより原子炉施設の敷地内には相当の再利用可能な余地が生ずる。 3. 解体撤去
(措置) 原子炉施設(再利用されるものは除く。)を解体し、撤去する。なお、解体の時期によって、原子炉の運転終了後早い時期に行う即時解体と、密閉管理又は遮蔽隔離の期間を経る遅延解体とに分かれる。 (管理) 解体撤去後、再利用上の安全性を確認する。それ以降は、特別な管理は必要としない。 (状態) 原子炉施設の敷地は再利用可能となる。 (2) 基本的方針
原子炉の廃止措置に関しては、次の事項を基本的な方針として進めていく必要がある。 ① 安全の確保に万全を期すため、原子炉の廃止措置に関する解体等の工事計画の作成、工事の実施及び工事前・後の管理においては、終始一貫して、一般の産業災害の事故対策はもちろん、対象となる原子炉施設の作業環境の放射線防護及び周辺公衆の被曝防止等の安全確保が図られる必要がある。 ② 国土が狭あいな我が国の特殊事情にかんがみ、対象となる原子炉の廃止措置後における当該施設の敷地の有効利用が図られるような措置が講ぜられることが適切である。 ③ 地域社会との協調を図りつつ原子力発電が推進されることにかんがみ、原子炉の廃止措置を進めるに当たっても、原子力発電所が立地している地域社会との協調に配慮する必要がある。 原子炉の廃止措置に関する方式は、前記Ⅰの2(1)において分類されたもの(密閉管理、遮蔽隔離及び解体撤去)を組合せることにより種々の方式が考えられる。その方式の選択については、原子炉設置者が原子力発電所に係る諸状況を総合的に判断して決めることになるが、基本的には、上述の方針を踏まえ、原子炉の運転終了後早い時期に解体撤去するか、又は、技術的、経済的条件等から必要に応じ適当な密閉管理又は遮蔽隔離の期間を経たうえ、最終的に解体撤去することによって、原子炉の廃止措置が終わるという構想が適当である。この場合、引続き使用できる施設等は再利用されることが望ましい。 原子炉施設の一部又は全部を撤去した後の敷地については、原子炉施設の建設用等原子力発電所の用地として継続して利用されることが望ましいと考えられる。 Ⅱ 原子炉の廃止措置に関する対策の推進 前章で原子炉の廃止措置に関する基本的な方針及び考え方を述べたが、今後、これらの方針及び考え方に沿って原子炉の廃止措置をより円滑に実施するため、技術の向上、諸制度の整備等以下のような対策が必要である。 1. 推進されるべき対策
(1) 解体及びその関連技術の向上
原子炉の廃止措置は、従来内外で実施された調査研究又は原子炉施設の解体等の経験からみて、既存技術又はその改良により対応できるとの見通しが得られているが、安全性と経済性を一層高めるため、今後更に技術の向上を図ることが重要である。 特に、前記の原子炉の廃止措置のうち、広範囲かつ高度の技術を要する即時解体を可能とする技術の確立が望まれる。 このため、高放射線レベルの環境下で行われる作業を円滑に進めるための解体作業用ロボットの開発等の遠隔操作技術、大型で堅固な構造物、機器等を対象にした解体技術、大量の廃棄物を安全かつ合理的に処理処分するための技術等を中心に、既存技術の実証と改良及び新技術の開発を推進することが重要である。 また、実際の原子炉の廃止措置による経験の積み重ねは技術を確立していく上からも極めて重要であるところから、既に役割を終えた試験研究用原子炉(動力試験炉等)の解体の経験を将来の実用発電用原子炉の廃止措置に関する技術に活かすことが必要である。 かかる観点から、今後一層推進されるべき主な技術開発の課題は、部分的に開発すればよいもの、技術の実証を要するもの等も含め、次のとおりである。 なお、これらの課題は、我が国の原子炉の設置状況、技術の汎用性、関連技術の現状等にかんがみ、100万キロワット級の大型の軽水型原子炉を解体撤去する際に適用される技術を中心としたが、ガス冷却型原子炉を解体撤去する際に適用される技術、密閉管理又は遮蔽隔離する際に適用される技術についても考慮した。 〔技術開発課題〕
① システムエンジニアリング
(各要素技術を組合わせて最適な解体作業手順を求めるための技術)
(イ) 解体作業手順及びその評価方法の確立
(ロ) 各要素技術の組合せによる技術のシステム化
(ハ) 解体作業用ロボットの作業形式の調査
② 残存放射能量評価技術
(原子炉の廃止措置に関する計画を検討する上での基本的なデータである原子炉施設内の残存放射能量を正確に把握するための技術)
(イ) 残存放射能量評価コードの開発
(ロ) 測定による評価技術の開発
③ 安全管理技術
(作業の安全を確保するための作業者の被曝評価、周辺への影響評価及び放射線管理に関する技術)
(イ) 解体時の作業者の被曝評価方法の確立
(ロ) 解体時の周辺への影響評価方法の確立
(ハ) 放射線管理技術(測定機器及び防護器具)の高度化
④ 除染技術
(作業を行いやすくし、特に作業者の被曝低減を図るための解体前除染及び解体した鋼構造物等の再利用等を図るための解体後除染に要する技術)
(イ) 解体前除染技術の開発
○化学的系統除染技術
○物理的・機械的系統除染技術
○建屋コンクリート表面汚染の除染技術
(ロ) 解体後除染技術の開発
(ハ) 密閉管理又は遮蔽隔離に適した除染技術の開発
⑤ 解体技術
(原子炉施設の鋼構造物及びコンクリート構造物を解体するための技術)
(イ) 鋼構造物解体技術の開発
(ロ) コンクリート構造物解体技術の開発
⑥ 遠隔操作技術
(高放射線等のため作業が困難な場所における作業を可能にするとともに作業者の被曝を大幅に低減させるための技術)
(イ) リモートコントロールシステムの開発
(ロ) 解体作業用ロボットの開発
(ハ) モジュール化(交換可能なように規格化)された作業機器の開発
⑦ 解体廃棄物対策技術
(原子炉施設の解体に伴って発生する放射性廃棄物(以下、解体廃棄物という。)を適切に処理、輸送、保管及び処分するための技術)
(イ) 解体廃棄物の減容処理技術の開発
(ロ) 解体廃棄物の固化処理技術の開発
(ハ) 解体廃棄物の輸送技術の開発
(ニ) 解体廃棄物の保管・処分用パッケージ、コンテナの開発
(ホ) 黒鉛の処理処分技術の開発
⑧ 廃棄物等再利用技術
(廃棄物の低減、資源の有効利用等の観点から解体により生ずる金属、コンクリート等を別途他の目的に材料として再利用するための再利用方法の調査と技術の整備)
⑨ 施設保管管理技術
(原子炉の廃止措置として密閉管理又は遮蔽隔離を採用した場合に、残存する原子炉施設を安全に保管管理するための技術)
(イ) 施設管理システムの確立
(ロ) 密閉・遮蔽措置構成物に関する耐久性確認方法の確立
また、将来建設される原子炉施設の設計に当たっては、あらかじめ原子炉の廃止措置を考慮しておくことが望ましい。このため、機器、配管の設計及び配置、建屋の構造等の設計、原子炉構成材料等について解体しやすさを指向した改良研究も有意義である。 (2) 安全性の確保
原子炉の廃止措置に関する安全性については、工事の実施及び工事の前・後を通じて、一般の産業災害の防止及び周辺公衆の被曝防止はもちろんであるが、特に作業者の放射線被曝の低減に努める必要がある。 被曝線量に関しては、100万キロワット級の軽水型原子炉を即時解体撤去した場合(工事中、輸送中及び工事後を含む。)についてなされた米国原子力産業会議(AIF)及び米国原子力規制委員会の試算があるが、これらは、化学除染の効果に対する考え方、解体撤去手順、作業活動に対する時間配分が異なること等の理由により差がみられる。 しかし、これらの報告にある解体工事期間中の作業者の推定総被曝線量は、その工事期間に対応する、我が国の運転中の実用発電用原子炉施設の従事者(定期検査、保守作業時等を含む。)の平均的な総被曝線量とほぼ同程度と考えられる。 また、周辺公衆の放射線被曝評価についても、上記の報告によると、原子炉施設を解体撤去した場合の個人被曝線量は自然放射線によるそれに較べて極めて低いものと考えられる。 これらの評価、昭和47年から昭和49年にかけて解体された米国エルクリバー炉の実例等から、原子炉の廃止措置は現在の技術によっても安全に実施されうると推定される。 今後、作業者の被曝低減等一層安全性を向上させるため、除染技術、遠隔操作技術等の技術開発を推進することが必要である。 また、これらの技術開発及びこれと合わせて進められる調査研究で得られた知見をもとに、安全基準が整備される必要がある。 (3) 資金面の対応策の確立
実用発電用原子炉の廃止措置の費用は、使用される技術、原子炉施設の再利用の程度等各種の前提条件によって相当異なるが、海外における報告をもとに即時解体撤去に要する推定費用と建設費とを対比すると、数%~20%程度と幅のある結果が得られる。 実用発電用原子炉の廃止措置は、多額の資金を比較的短期間に必要とするものであることにかんがみ、今後、合理的な費用の算定が図られるとともに、これを踏まえ、受益者の世代間の負担の公平化等を考慮し、料金制度、税制等に関する具体的な検討が行われ、資金面の対応策の確立が図られる必要がある。 (4) 廃棄物対策
原子炉施設の解体に伴い排出される物は、①炉内構造物等高度に放射化されたものから建物構築物等放射能汚染のないものまで多種多様であること、②通常運転時における廃棄物と異なり、大型鋼構造物、機器、配管、コンクリートなども含まれること、③また、量的にも大量であり、比較的短期間に発生すること等の特徴を有している。 これらの排出物のうち、再利用可能なものは極力これに供し、また廃棄物となるものについては次の事項が考慮されて取り扱われることが必要である。 ① 廃棄物のうち、そもそも放射能汚染のないものは、これを区別し、放射性廃棄物とは別途に取り扱われるべきである。また、放射能レベルが極めて低い廃棄物については、非放射性廃棄物と同等に合理的な処理処分ができるようにするための検討が必要である。 なお、放射能汚染がある廃棄物については、必要に応じ、適当な除染を行い、放射能汚染の程度を確認することにより、上記のような区分に応じて取り扱われることが適切である。 ② 放射性廃棄物の処分は、陸地処分と海洋処分との組合せとなると考えられるので、これらの処分対策を更に強力に推進する必要がある。 (5) 諸制度の整備
米国、西独等において、原子炉の廃止措置は法律上の一行為として位置づけられ、原子炉の設置、運転に関する許認可を終結させるものとしてその実施には法的規制が行われている。 我が国においては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に原子炉の解体の事前届出及び主務大臣の措置命令についての規定等がある。今後、それらの運用に関し、これまでの内外の原子炉の廃止措置の実施例を参考として、技術開発面での実態等を踏まえつつ、以下の項目について検討が行われる必要がある。 ① 原子炉の廃止措置として密閉管理又は遮蔽隔離を行う場合の規制のあり方
② 解体撤去工事の安全基準
③ 解体撤去工事の完了条件
④ 密閉管理又は遮蔽隔離期間中における原子炉施設の安全管理基準(遮蔽構造物等の健全性に関する基準、監視、巡視・点検に関する基準等)
このほか、次の項目についても、関連諸制度の整備を検討する必要がある。 ① 資金面の対応策
② 原子炉施設の解体に伴って発生する放射性廃棄物の処理処分基準
③ 原子力損害賠償制度上の取扱い
2. 対策の進め方
(1) スケジュール
前述のように、原子炉の稼働期間を30年程度と見積ると、我が国においては、昭和70年代に入って具体的な実用発電用原子炉の恒久的な運転終了があり得るとして、それまでの間に段階的に技術の開発、諸制度の整備等対策を推進することが必要である。 第Ⅰ期(昭和50年代後半)
① 原子炉の廃止措置に関する基本的考え方及び合理的な計画方法の定着化の促進
② 原子炉施設の解体等に関する総合的な技術開発(確証試験を含む。)
③ 原子炉の廃止措置を行う上での安全性及び経済性の面から整備されるべき関連制度の必要事項及び枠組みの検討、整理
④ 資金面の対応策の確立
第Ⅱ期(昭和60年代前半)
① 第Ⅰ期で開発された原子炉施設の解体等に関する技術のシステム化の推進及び試験用原子炉施設を活用した解体の実地試験の実施並びに確証試験の実施
② 原子炉の廃止措置に関する安全基準等関連する制度の整備
③ 原子炉の廃止措置を実施する上で必要な人材の養成等体制の整備
第Ⅲ期(昭和60年代後半)
① 原子炉施設の解体等に関する技術の改良
② 個別の実用発電用原子炉について必要に応じた具体的計画の策定
(2) 協力体制
前記のように、原子炉の廃止措置に関する対策は原子力開発利用推進上の重要な課題であり、地域社会へ及ぼす影響も考慮し、国、関係民間機関等が協力して、今後積極的に技術の向上、諸制度の整備等対策の確立に努めるべきである。 原子炉施設の解体等に関する技術開発については、原子炉の廃止措置が民間の原子炉設置者により実施されること、多くの技術が既存技術の改良により開発されるものであることなどから、民間が主体となって進められるべきである。また、安全規制に必要な技術的知見の集積、民間における解体等の技術開発の促進及び原子力発電のパブリック・アクセプタンスの増進等の観点から、国はリスクの大きい技術開発、安全性、信頼性の確保上特に重要と考えられる技術の開発(確証試験を含む。)及び試験用原子炉施設の解体の実地試験を行うことが適当である。 一方、安全規制、資金面の対応策等の関連制度については、関係行政機関において、相互に有機的な連携をとりつつ、具体的な検討作業が進められる必要がある。 上記のスケジュールに沿った対策の均衡のとれた推進を図るために、原子力委員会は適宜、進捗状況のチェックアンドレビューを行う必要がある。 (参考)
廃炉対策専門部会構成員
基本問題分科会構成員
(計16名)
注) ○印専門部会構成員
技術開発分科会構成員
(計16名)
注) ○印専門部会構成員
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |