| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第4回遠心分離法濃縮施設保障措置プロジェクト(Hexapartite Safeguards Project)全体会合の結果について 原子力安全局
保障措置課
1 設立の経緯
(1) 遠心分離法濃縮施設が世界的に運転段階に入っているにもかかわらず、(参考)国際原子力機関(IAEA)におけるこの施設に対する保障措置適用の検討が進捗していないとする米国が、保障措置適用のあり方を確立するための国際協力プロジェクトをすでに施設を運転中、あるいは建設中、計画中の各国及び査察当局側によって発足させることを昭和54年に各国に提案した。 (2) これを受け、昭和55年9月にウィーンに、日本、米国、トロイカ3国(英国、西独及び蘭)、豪州、IAEA及びユーラトム六者が非公式会合を持ち、Hexapartite Safeguards Projectとして発足させることが決定された。 2 本プロジェクトの目的
2年間における検討により遠心分離法濃縮施設における種々の保障措置技術について共同して検討を行い、もって運転中の施設及び計画中の施設に対し、IAEAの有効な保障措置を適用していくために必要な施設付属書を作成するための技術的ベースを作成する。 3 現在までの進捗状況
(1) 昭和55年10月の第1回全体会合(英国のスーロー)において、以下の4つのチームにより作業を進めていくことが決定された。 ① チーム1… 施設設計の特徴(リーダー国 日本)
② チーム2… 封印・監視(リーダー国 英国)
③ チーム3… 計量管理(リーダー国 豪州)
④ チーム4… 保障措置戦略(リーダー国 米国)
(2) その後の開催状況は以下の通りである。
4 第4回全体会合の結果
(1) 出席者
全体会合の議長は、英国のF.Brown(エネルギー省)が勤めた。 (2) 現在までの各チームの成果
(ⅰ) チーム1(施設設計の特徴)
検討の対象とする全ての施設の設計の特徴を横ならびの表にとりまとめ、その主な作業が終了した。 (ⅱ) チーム2(封印・監視)
情報の連続性の確認等の見地から、封印・監視システムについて要求される定量的な有効性評価について実証試験を中心として、今後検討を「評価サブグループ」で行うこととし、現在利用可能な封印・監視システムの機番等についてのカタログをとりまとめ了承された。 (ⅲ) チーム3(計算管理)
既存の計量管理及び封印・監視システムを前提とし、施設者における計量管理能力及び保障措置上の独立した計量検認の有効性について検討を行い、年間2,000トンSWUの生産規模のプラントについては、低濃縮ウランの保障措置目標を達成しうるとの考え方をとりまとめた。 (ⅳ) チーム4(保障措置戦略)
カスケード・ホールへのアクセス査察の5つのケースについて比較検討したレポートと保障措置戦略の有効評価手法を検討したレポートをとりまとめた。 (3) チームの再編成
4つのチームを全て廃し、新たに「アクセスモデルとノン・アクセスモデルを比較評価するグループ」が設置されることとなった。 このグループは、今までの4つのチームの成果を踏まえて、次のような検討の前提条件とタスクを持って、明年3月末を目途に作業をすることとなった。 1) 検討の前提条件
① ウランの重要な量の転用と申告した濃縮度以上の濃縮ウランの重要な量の生産をタイムリーに検知することを保障措置の目的とすること。 ② 保障措置により、全ての核物質が枢要地点を通り、かつプラントが申告された通りに運転されることを保証されること。 ③ 検討の対象となる濃縮施設は、INFCIRC153タイプの保障措置を受けるものであり、かつ濃縮度が、5%以下の濃縮ウランを生産するものであること。 2) タスク
① タスク1
限定された頻度の事前通告しないアクセスについての詳細な検討
② タスク2
ノン・アクセスモデルについての詳細な検討
③ タスク3
タスク1とタスク2の成果を評価方法モデルを活用し比較評価し、予備的な結論と勧告を出すこと。 なお、本チームの議長は、西ドイツのR.Gerstler(研究技術省)が勤めることとなった。 (4) 機器実証試験計画
英国がカーペンハーストにおける機器実証プログラムの進捗状況について報告するとともに、IAEAも濃縮施設における保障措置技術の研究開発の現況について報告した。又、日本も保障措置技術の研究開発において、IAEAと協力していく用意のあることを表明した。 このような状況を受けて、HSPとしては、独自に機器実証試験計画等のチームを作って進めていくことはせずに、各メンバー国が、IAEAとバイラテラルに協力計画を進め、その成果を適宜HSPに反映していくとの方針が確認された。 5 アクセス、ノン・アクセスの問題
カスケードホールへの査察官のアクセス、ノン・アクセス問題については、我が国はノン・アクセスの姿勢であり、トロイカ3国は、西ドイツが、ノン・アクセルよりの姿勢を見せてはいるものの、全体的にみてアクセスに対しても柔軟であり、米国は、国務省、軍縮庁を中心として、アクセス特に前述の限定された頻度の事前通告しないアクセスを強く推そうとしている。豪はほぼ米国と同様の態度である。 6 今後のスケジュール
(1) 全体会合
今後の全体会合及びサブ・グループ会合のスケジュールは以下の通りである。 ① 第5回 昭和57年3月29日~4月2日 オーストラリアにて
② 第6回 昭和57年7月 西ドイツにて
③ 第7回 昭和57年11月日 イギリス
(2) アクセス、ノン・アクセスの比較評価グループ
① 第1回 昭和57年2月1日~2月5日 西ドイツにて
② 第6回 昭和57年3月1日~3月5日 西ドイツにて
7 今後の我が国の対応
今次会合の結果に鑑み、今後、我が国としては以下の方針で本プロジェクトに対応していくことが適当と考えられる。 (1) アクセス、ノン・アクセス比較評価サブ・グループ
タスク1のアクセスの検討については、カスケード・ホール外での査察活動を含めた全体的な保障措置活動をとりまとめ、ノン・アクセスによる保障措置の有効性を引続き主張することとする。 タスク2のノン・アクセスについては、計量管理により、高濃縮ウランの検知も可能であることを証していくアプローチをとる。 (2) 人形濃縮施設の施設附属書の作成作業
人形濃縮施設については、現在、設計情報をIAEAに提出ずみの状況であるが、今後1年間のHSPの作業により、各国別施設の施設附属書の技術的情報のぺースが、作成せられることも考慮し、我が国としても、人形濃縮施設における施設附属書のドラフト作成の作業を進めること。 (3) 人形濃縮施設における保障措置機器の研究開発
現在、動燃事業団が開発している①ロードセル重量計、②ボータルモニター、③プラスチックシール等の機器の開発を、対IAEA保障措置技術支援協力計画(JASPAS)に組み入れていくとともに、IAEAが開発している非破壊測定機器の実証試験に協力していく。 (参考)
各国の遠心分離法濃縮施設の状況 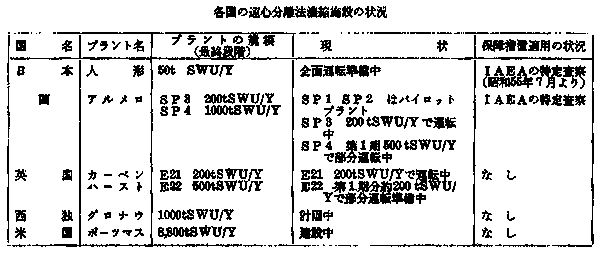 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |