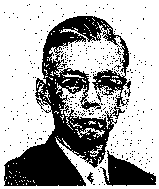| 目次 | 次頁 |
|
ヨーロッパ一見 原子力委員会委員
島村 武久
11月28日から12月10日までの12日間、英、仏、独三国を廻って主な原子力施設を視察する機会を得た。何分にもかなり無理な日程であったため、充分な調査が出来た訳でもなく、見間違いや聞き間違いもあったとは思うが、印象の薄れぬうちに気がついた二、三の点を書いて置きたい。 第一にフランスでは、予想以上に原子力開発が活溌に進められていること、又対照的にドイツがこれ又予想以上に低迷している感じがした。フランスについてはミッテラン政府になってトーン・ダウンが心配されていたが(フランス関係者も心配していたそうだ)、10月の国民議会で決定されたエネルギー開発計画によると微調整程度のものに過ぎず引続き原子力開発が推進されると承知していたが、実際に現地でスーパー・フェニックス、ユーロデュフの濃縮工場、マルクールの廃棄物ガラス固化施設、更にはラ・アーグの再処理施設の状況を見ると、単に原子力発電所の建設にとどまらず、一連の計画が着々と遂行されていること、又これに携わる人達の意気が高く自信にあふれていることに感銘を受けた。これに反しドイツに対してはこの一、二年環境保護論者の原発反対運動や政策、或いは中央と地方の摩擦等で開発テンポの遅れが伝えられていたが、行って見ると高速増殖炉や高温ガス炉の開発も資金的な面から見透しが暗く、再処理事業もサイト候補地も決まらず、カールスルーエやユーリッヒの研究所では今後5年間に7.5%の人員削減を申し渡されているという状況で思いの外に士気が消沈しているように感じた。その背後には何といってもドイツには豊富な石炭資源を有しているという事実があることも忘れてはなるまい。フランス以上にエネルギー資源に恵まれず、輸入依存率の高い日本として行き方は自ら明らかであると思う。 第二に仏、独両国における官民協力の見事さに思いを改めさせられた。フランスはイギリスと同様電力事業は国営であり、原子炉の研究開発も国営を基本としていること、又フランスではCEA(原子力庁)とEDF(電力庁)の傘下に業務毎に沢山の会社を設立し極力民間の技術、資本、経営力を動員していることは既に知られていたが、実際に眼に写る限りこれら各機関とCEAの各研究所の仕事の組合せが物凄く複雑であるにもかかわらず、実によく連繋され、周到な計画の下に組織の垣を感じさせない運営が図られている。事業化段階で会社組織に移すということに納まらず、例えばマルクールのAVM(高レベル廃棄物のガラス固化パイロットプラント)ですらCEAの手から離れてCOGEMAによって運転されている。一方濃縮事業やスーパー・フェニックスの様な巨大な事業では外国との合併も辞さない。この様な政策を採る最大の理由は資金問題にある。巨額の資金需要を国費のみで賄うことは如何にフランスが原子力に傾斜しても耐えるところではない。会社組織にすることによって民間資金を導入すると共に銀行借入による資金獲得の道を開いたということである。しかし私自身にとっては資金問題よりもむしろ研究開発された技術の実用化へのスムースな移転という点で極めて有効であると我が意を得た想いがした。事情は全くドイツにおいてと同じである。いやむしろドイツでは研究開発段階から民間の参画が活発である。カールスルーエ研究所内にあるWAK(再処理パイロットブラント−能力30〜40t/年)の運転は電力12社の出資会社であるDWK(再処理会社)によって運転されている。同じ敷地内にある大型再処理の工学試験設備も建屋はカールスルーエの研究所によって建てられたが装置類はDWKによって搬入運転されている。ユーリッヒ研究所内にあるHTGR試験炉のAVRは15の電力会社によって出資され運転会社が運転している。同じくHTGRの工学試験施設はHABというBBCグループとGAの子会社の合弁会社によって運営されている。しかもこれらの運営と研究所自体の研究活動は一体不可分となっていて何等の違和を感じさせない。大いに得る所があった。 最後にウラン濃縮について一言したい。今回の旅行では先ずカーペンハーストにあるウレンコの遠心分離工場と、トリカスタンにあるユーローディフのガス拡散法濃縮工場の二つを見ることが出来た。カーペンハーストでは、往来の200tから400tへの増設工事が殆んど完成に近づいていたし、トリカスタンの方は1万800tの工場がこれ又最後の仕上げ工事と云った所であった。従って両者は規模の点では全く比較にならない。日本はガス拡散方式を採ることはないので、ただ見物させて貰っただけだが高さ20m、直径5mという濃縮機が1グループ70分づつずうっと並んだ姿は壮観という外なく、しかもこのグループが20あり、全体で1,700台というのは驚嘆の外はない。トリカスタンの場合は勿論であるが、カーペンハーストの場合共通に言えることは、全く商業感覚で運営せられているということである。例えば、トリカスタンの場合、オペレーターは5グループ3交替で、1グループは30人、内中央制御室に入るのは4人ということであり、カーペンハーストの場合は4チーム3交替で1グループは9人とのことであった。私の見る所では規模は異にするとは云へ両者とも建設投資に莫大な費用を投入しており(ユーロデュフの場合建設費の三分の二以上が借入金)、需要も充分でない所から現在ではかなり経営的には苦しいのではないかと思われたが、両者ともコスト的には全くアメリカを問題とせず、自信満々であった。ウレンコの場合はカーペンハウストもアルメロも共に200t/年台という小規模工場の段階から商業的に運営され、1976年以来研究開発費を含めて政府から援助は何も受けていないと自慢していた。又現在建設中の工場の建設費は遠心機部品市販品に合わせて競争入札によって調達する等の努力によって、数割も削減し得たと云っていた。これを要するに、短期的には苦しくても、長期的視野に立って易く商業化に踏み切った決意は見上げたものであり、又そうすることによって、種々の改善とコスト・ダウンが実現したものと思われた。 今回の旅行ではスーパー・フェニックスも見せて貰ったし、高温ガス炉の開発状況、再処理や廃棄物処理の施設も見ることが出来た。技術の細部について語る資格はないが、それぞれの問題について所感がない訳ではない。しかし紙面の都合もあって省略したい。しかし上述のいくつかの問題について御意見ある方その御叱正を得たいと思う。 |
| 目次 | 次頁 |