| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原子力モニターの声 昭和56年9月
振興局
原子力局
原子力安全局
昭和55年度原子力モニターついて
原子力モニターは、原子力開発利用に関して、広く一般国民から卒直な意見等を聴取し、原子力行政に反映させることを目的とした制度であり、昭和52年度に開始された。昭和55年度の原子力モニターは、各都道府県知事より推薦を受けた候補者のうち、本人の同意を得た509名に委嘱を行った。 昭和56年3月に実施したアンケート調査及び昭和55年9月から昭和56年3月までの7ヶ月間に寄せられた随時報告の概要は以下のとおりである。 Ⅰ アンケート調査 1 調査の概要
(1) 調査目的 10月26日の「原子力の日」を中心とした原子力広報に関連して、原子力の開発利用についての認識及び原子力安全行政に対する要望等についての意識を調査し、今後の施策の参考とする。
(注)この報告で使われる記号の説明
1 Nは比率算出の基数であり、100%が何人の回答に相当するかを示す。特に示していない場合はN=363人(回答数)である。 2 SQ:前問で特定の回答をした一部の回答者に対して行った質問
3 MA:1回答者が2以上の回答をすることができる質問、このときの回答合計(M.T)は回答者数(100%)を越える。 2 調査結果の概要
(1) 「原子力の日」に関する記事等についての関心
原子力に関する広報については、91%の人が新聞、パンフレット、テレビ等を通じて何らかの広報に接しているが、「原子力の日」に関連した広報記事を見た人は76%となっている。 また、小冊子に関する意見としては、
◎エネルギー問題について、真剣に考える必要性を感じた。 ◎エネルギーとしての原子力の普及状況を認識した。 ◎事故防止に万全を期し、積極的な開発の促進を図るべきである。 ◎学校教育等の場に大いに活用すべきである。 などの意見が寄せられた。 (2) エネルギー問題についての認識
エネルギー問題については、97%の人が関心を持ち、99%に近い人がエネルギー不足に不安感を持っている。 また、石油代替エネルギー源としては、原子力(56%)、石炭(20%)に強い期待を抱いている。 (3) 原子力の開発推進についての認識と態度
原子力発電の建設については、「安全性を十分認識しながら建設すべきである」が66%、「積極的に建設すべきである」が28%、「今後は現在の割合程度に止めるべきである」が2%を占め、反対はわずか1%に過ぎない。 また、これらの立地推進に際して難航する面があるが、最も大きく影響している理由としては、「原子力発電所の安全性に不安がある」が62%を占めている。さらに立地難を解決する方策としては、「現在の原子力発電所の安全性及び安全対策、防災対策について地元で一層ていねいに説明する」(43%)及び「原子力発電所の安全運転の実績を積み上げる」(41%)が有効であると考えられている。 (4) 原子力安全行政についての意見
原子力安全行政については、①国民に正しい知識を与え、国民の理解を得て行くための施策(43%)、②安全性、信頼性等に関する研究開発の推進(28%)、③各種規制段階で、国民の意見を聞き、規制の実施に当ってこれを十分活用するための施策(14%)、④厳正な安全規制の実施(13%)を強く推進すべきである。 などである。 通産省と原子力安全委員会によるダブルチェック体制については、7割以上の人が一応知っているが、よく知っている人となると11%に過ぎない。 原子力安全委員会に期待している機能としては、公開ヒアリングを開催し、地元住民の意見を反映させる(41%)が大半を占め、そのほかより高度な立場からダブルチェックすること(21%)、専門家によるシンポジウムの開催(15%)、及び安全研究の推進(11%)を図ることと考えられている。 原子力安全委員会では、これまで4回の公開ヒアリングを開催したが、公開ヒアリングについては86%の人が知っており、93%の人が関心を寄せている。 また、公開ヒアリングに対する具体的な意見としては、
◎住民の不安に対し、十分な理解が得られるようさらに努力を重ねてほしい。 ◎説明が専門的すぎで内容が良く理解できない。 などの意見が多く寄せられた。 放射性廃棄物の陸地処分及び海洋処分に関する国の基本的な考え方等については、93%の人が一応認識している。原子力安全行政についての具体的な意見としては、
◎原子力発電所の見学を積極的に行って、現状を強く認識させるべきである。 ◎国、地方自治体、電力会社が一体となった安全管理体制を確立すべきである。 ◎安全性に対する基礎研究、実証研究体制の拡充強化を図るべきである。 など、安全性全般にわたってのきびしさを求める意見が多く見られた。 (5) 原子力広報に対する要望
原子力広報の重要点として、原子力発電所の安全対策については、①原子力発電所の安全管理の方法(32%)、②周辺住民の放射線防護(26%)、原子力の必要性については、①わが国のエネルギー需給の現状及び今後の見通し(32%)、②,エネルギー供給の中での原子力の位置づけ(30%)、③原子力の長期的な展望(23%)と答えており、放射性廃棄物の処理処分対策については、①処理処分の方法、安全性及び今後の計画(62%)、②処理処分に係る研究開発の現状(24%)。放射能(線)の人や環境への影響については、①環境における放射性物質の挙動とその人間環境への影響(53%)、②放射線による晩発障害の解明の現状(23%)、③放射線による遺伝的影響(22%)に関心が集まっている。 原子力広報の期待される方法としては、テレビ、新聞、各種セミナーが代表的な方法である。広報を行う機関として政府を期待している人が約半数(48%)を占め、他は地方自治体などである。新聞、テレビ等による広報の年間頻度については、①週に1、2回程度(43%)及び月に1、2回程度(42%)を希望している意見が最も多かった。 原子力広報に対する要望としては、
◎原子力がもっと身近なものとして受け入れられるようやさしくわかりやすい内容のものをできるだけ多くPRしてほしい。 ◎広報の対象として、婦人あるいは学生などそれぞれの対象にそったPRも行ってほしい。 などの意見が寄せられた。 3 集計結果
問1 10月26日の「原子力の日」を中心とした原子力の広報について
1 原子力に関する新聞広告(広報)や記事について
(1) 今年度「原子力の日」の前後に政府あるいは原子力関係機関(電力会社や原子力関係団体など)による広告(広報)をご覧になりましたか。
SQご覧になられた方に〔対象者329名〕
(i)どこの広告(広報)をご覧になりましたか。(M.A)
(ii)また、その広告(広報)は何でご覧になりましたか。(M.A)
(2)「原子力の日」に関連した記事はご覧になりましたか。
SQご覧になられた方に〔対象者295名〕
ご覧になった記事の内容は何でしたでしょうか。
2「原子力の日のポスター」についてご感想・ご意見等がありましたらお書き下さい。(回答数199件)
3 小冊子「エネルギーをたずねて-ニルスの旅-」はお読みいただけましたでしょうか。
問2 エネルギー問題について
1 あなたはエネルギー問題について関心をお持ちですか。
2 これからのわが国における石油の供給について、あなたはどうお考えですか。
3 あなたは、石油に代わる大量のエネルギー供給源として、今世紀内はどのようなエネルギーが一番多く利用されると思いますか。
4 長期的な観点から、石油に代わるエネルギー源として21世紀にはどのようなエネルギーが利用されると思いますか。
問3 原子力の開発について
1 あなたは、原子力発電所の建設についてどのようにお考えですか。
2 もし仮にあなたの居住地の近くに原子力発電所の建設計画が発表されたとしたら、あなたはどうしますか。
3 原子力発電の立地推進について
(1) 原子力発電施設等の立地に際しては、必ずしも十分な地元住民の協力が得られず立地が難航する面があります。その理由は次のうちどれが最も影響していると思いますか。
(2) これらの立地難を解決するには、どのような方策が有効であるとお考えですか。
問4 原子力安全行政について
1 近年、原子力をめぐって、特に立地問題、安全問題等については、国民の理解を得ることが不可欠の課題となっており、政府としては、現在次のようないろいろな施策を講じています。あなたは、このうち、どれが最も重要であるとお考えになりますか。
2 原子力発電所の安全規制については、通商産業省が設置許可から運転管理に至るまで、一貫して規制を行うこととなっており、通商産業省が行う設置許可等に関する安全審査について、原子力安全委員会が最新の科学技術的知見に基づいて客観的立場から再審査(ダブルチェック)する体制になっています。 あなたはこのような体制をご存知でしたか。
3 あなたが原子力安全委員会に最も期待している機能はどれでしょうか。
4 原子力安全委員会は再審査(ダブルチェック)に当たって、これまで4回の公開ヒアリングを開催しましたが、この公開ヒアリングについてお尋ねします。 (1) 公開ヒアリングをご存知ですか
(2) 公開ヒアリングについて関心をお持ちですか。
(3) 公開ヒアリングについて、何かご意見、ご提言がありましたらお書き下さい。(回答数204件)
5 原子力発電所等にかかわる防災対策については、災害対策基本法に基づき所要の措置が講ぜられることになっていますが、原子力安全委員会において、防災対策の重点的実施地域の範囲等原子力発電所等に係る防災対策特有の専門的技術的事項について、昨年6月30日、「原子力発電所等周辺の防災対策について」として報告書が取りまとめられました。あなたはこのことをご存知ですか。
6 放射性廃棄物について、国としては陸地処分及び海洋処分を併わせて行うこととしており、事前に安全性を評価し、試験的処分の結果を踏まえて慎重に進めることとしています。あなたは、このような状況及び国の基本的な考え方をご存知ですか。
7 同封のパンフレット「安全で確実な海洋処分をめざして」についてお尋ねします。 (1) パンフレットの内容は、放射性廃棄物処分に対する国の方針、試験的海洋処分計画のあらましについて述べたものですが、これは、わかりやすいですか。
(2) このパンフレットについて、ご意見、ご提言がありましたらお書き下さい。(回答数121件)
8 わが国の原子力安全行政について、何かご意見、ご提言がありましたらお書き下さい。(回答数180件)
問5 原子力広報についてお尋ねします。 1 あなたは原子力について、特にどのようなことを詳しくお知りになりたいですか。 (1) 原子力発電について
(2) 原子力発電所の安全対策について
(3) 原子力の必要性について
(4) 放射性廃棄物の処理処分対策について
(5) 放射能(線)の人や環境への影響について
2 原子力広報の方法についてお尋ねします。 (1) あなたは、原子力広報について、どのような手段媒体をお望みになりますか。
(2) これからの広報をどのような機関が行うことを期待されますか。
3 あなたは、新聞、テレビ、ラジオ等の媒体で、どのくらいの頻度で広報をした方がよいと思いますか。
4 原子力広報について政府に望まれることがありましたらお書き下さい。(回答数229件)
Ⅱ 随時報告 1 意見の内訳
全国509名の原子力モニターから、昭和55年9月から昭和56年3月までに寄せられた随時報告の件数は164件であり、これを事項別にみると、原子力広報についての意見が42件と最も多く、次いで開発利用についての意見が36件、原子力行政についての意見が24件などとなっている(表1参照)。 職業別にみると、主婦等が68件と最も多く、次いで商工、サービス業が32件となっている(表2参照)。 また、年代別では、60代が55件と最も多く、次いで50代が32件、30代が28件などとなっている。(表3参照)。男女別では、男性が106件、女性が58件となっている(表4参照)。 2 意見の概要
寄せられた意見の中で、開発利用についての意見では、「国と地方自治体が一体となった開発体制を充実させるとともに、安全の確保を大前提に開発の推進を図るべきである。」
「原子力開発の重要性などについては、理解も一段と深められている。今後は、安全性に対するよりきびしい姿勢をもって開発にあたるべきである。」など開発の推進とより一層の安全性を求めた意見が見られた。 原子力行政についての意見では、
「今後、原子力発電の開発をどこまで推進して行くのか、建設を急がなければならない理由は何か、また、安全性についてはどのようなシステムがとられているのか、などをもっと周知させるべきである。」などの意見のほか、「温排水を利用した研究開発の促進」などの地域に密着した施策を求める意見が見られた。 廃棄物処理についての意見では、
「累積する放射性廃棄物の貯蔵があとどの程度可能なのか、また、陸地処分、海洋処分を今後どのように進め、その安全性をいかに確保して行くのか。」など多様な意見が寄せられた。 安全性、事故についての意見では、
「国民にとって、一番関心の強いのは安全性の問題であり、また、それが原子力に対する不安の原因ともなっているので、国民の不安を解消するためにも、より詳細にかつ具体的な説明を積極的に行うべきである。」
「安全性を高めるためには、どんなに小さな事故であってもできる限りなくすよう努力するとともに、体制の整備を一層強化し、万全を期すことが重要である。」などの意見が多かった。 代替エネルギーについての意見では、
「他国で産出されるエネルギー源に依存することは、国際情勢に左右される不安があり、安定したエネルギーの確保を図るためにも自力によるエネルギー開発を急ぐべきである。」「当面は、原子力が最優先させるべきであるが、将来的には自然を利用したエネルギーの利用技術の開発も進めておくべきではないか。」などの代替エネルギーに対する積極的な研究開発を望む意見が多かった。 原子力広報についての意見では、
「現在のエネルギー事情から原子力の開発は、国民にとって非常に重要な問題である。一人でも多くの人が理解できるようにPRしてほしい。」「積極的な広報と意見の吸収に努めるほか、原子力発電所の見学を幅広く行って、安全の実態を周知させるべきである。」などの意見が最も多かった。 原子力教育についての意見としては、
「学校教育等の場を通じて、原子力に関する基礎教育を行う必要がある。」などの意見が最も多く、その中に、「学校教育において、正しい認識を与えることが、安全性に対する不安を解消する遠くて近い解決策と考える。」などの意見も見られた。 その他の意見としては、
「地域住民の理解と信頼を得るために、もっと積極的な姿勢をもって原子力の開発と、安全性との調和を十分図るべきである。」などの意見が寄せられた。 参考Ⅰ 報告(164件)の内訳
表1 事項別の内訳 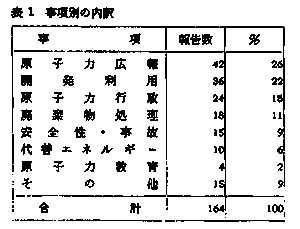 表2 職業別の内訳 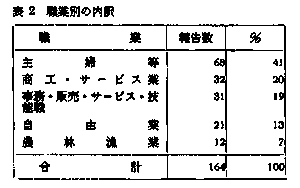 表3 年代別の内訳 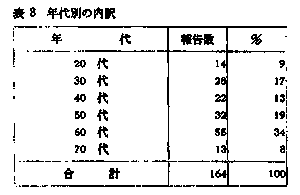 表4 男女別の内訳 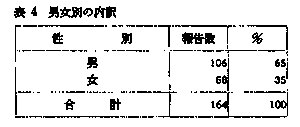 Ⅲ 参考 昭和55年度原子力モニター構成 1 職業別 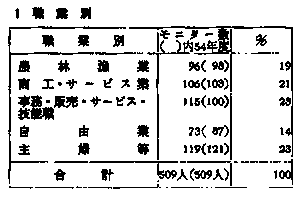 2 年代別 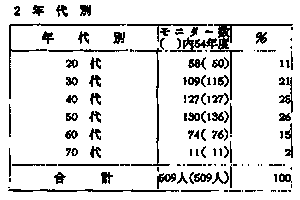 3 男女別 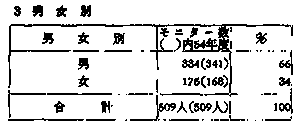 4 都道府県別 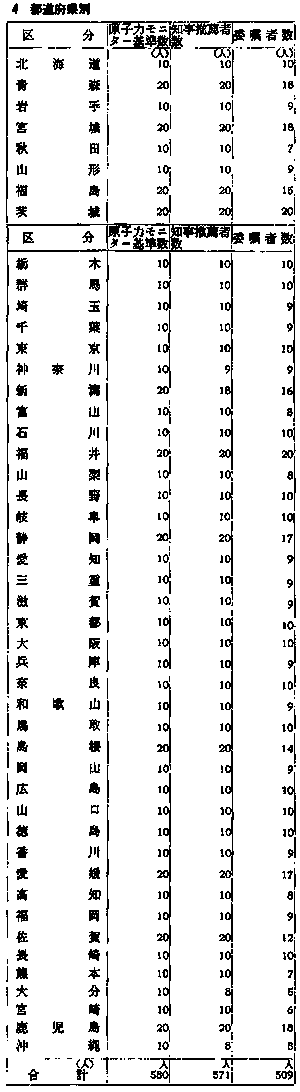 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |
 見た
見た 政府による広報
政府による広報 原子力関係機関による広告(広報)
原子力関係機関による広告(広報) その他の広告(広報)
その他の広告(広報) 雑誌
雑誌 週刊誌
週刊誌 生物エネルギー、波力、風力
生物エネルギー、波力、風力 地熱
地熱 ラジオ
ラジオ ポスター
ポスター