| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
55年度原子力委員会委託「トータルエネルギーの観点からみた原子力の長期的役割に関する調査」要旨 未来工学研究所
1 研究の目的
エネルギー資源が乏しく、主要先進七ケ国(サミット参加国)中エネルギー自給率が最低である我が国にとって、準国産エネルギーである原子力は石油代替エネルギーの中心的役割を担うことが期待される反面、安全牲に対する不安に根ざす反対運動等のため原子力発電所の立地が計画通り進まないなど、多くの問題をかゝえている。本プロジェクトの目標はこのような我が国のエネルギーの未来の姿を描くいくつかのシナリオを出来るだけ客観的なデータに基づいて想定し、これらのエネルギー需給シナリオによって原子力を削減した場合の経済、環境等社会への影響を定量的に分析することにより、原子力の長期的役割の議論に資することにある。 今年度は、前年度の成果を踏まえて、調査研究項目として(1)エネルギー需給シナリオ分析、(2)経済影響の解析方法の検討、(3)環境影響の検討と事故データの収集、の三つを採り上げ、これらを総合して原子力の必要性を示すためのシステム分析手法を確立することを研究の目的とした。 2 研究の概要
(1) エネルギー需給シナリオの分析
ⅰ) エネルギー需要の想定
54年度は総合エネルギー調査会の長期エネルギー需給暫定見通しの延長ケースを考えたが、1980年のエネルギー需要の実績は省石油を中心とする省エネルギーによって見通しより低めになっている。この点を考慮して今年度は暫定見通しより低い需要ケース2ケース(中需要ケース及び低需要ケース)について2020年迄の想定を行なった。 想定の方法は次の通りである。まず産業部門については11部門に分類し、将来の生産額の伸びと生産額当りのエネルギー原単位を想定して、エネルギー需要を積み上げている。民生部門、輸送部門については産業の生産額から算出されるGNP(国民総生産)等を指標として同様のエネルギー需要の積み上げを行なっている。 表1に中需要ケースのGNP、一次エネルギー需要の想定結果を示す。中需要ケースでは、2020年のGNP、一次エネルギー量は各々1980年の約3倍及び2倍に達すると想定している。 ⅱ) エネルギー供給シナリオ
次に前項で与えられた需要量及び前年度収集し、今年度見直し整備したエネルギー供給技術データ(技術特性、経済性等)を用いて、IEAのエネルギーシステム分析に使用されているMARKALコードによりエネルギー供給シナリオを計算した解析方法は線形計画法により、各種エネルギーの技術的社会的供給可能性の制約を与え、そのもとで全システムの2020年迄のトータル・コストを最小にするようなエネルギー種別供給量、エネルギー変換設備の導入量等を求める方法による。供給ケースとして、原子力を暫定見通しの傾向に沿って導入する基準ケース及び原子力の寄与を200年以降0とする原子力削減ケースを考え、原子力の削減分を石炭で代替する場合を原子力削減ケースⅠ、石炭及び再生可能エネルギーで代替する場合を原子力削減ケースⅡ、石油及びLNG
表1 GNP、一次エネルギーの想定(中需要ケース) 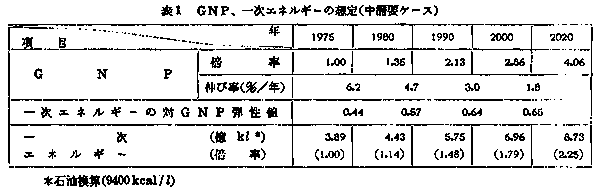 (液化天燃ガス)等で代替する場合を原子力削減ケースⅢとしている。 表2にこのシナリオ分析の中心的ケースである中需要シナリオ・基準ケースにおける、原子力による一次エネルギー供給と電源の構成を示す。原子力はこのケースで2020年において一次エネルギーの32%を供給することになるが、その殆どは電力利用である。 表3に中需要シナリオにおける、基準ケース及び原子力削減ケースの一次エネルギーの構成と国産比率を示す。表で明らかな通り、我が国のエネルギー自給率は1980年の値で14%であるが、中需要ケースの2020年の場合、原子力推進の基準ケースでは42%、原子力削減ケースⅠ、Ⅱ、Ⅲで各々14%、16%、15%となっており、原子力削減によって大幅にエネルギー自給率が低下する結果となっている。 表2 原子力による一次エネルギー供給と発電の構成(中需要・基準ケース) 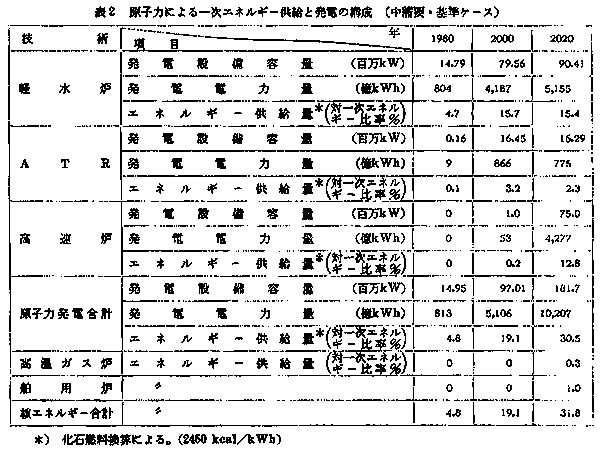 表3 中需要ケースの一次エネルギー構成比と国産比率 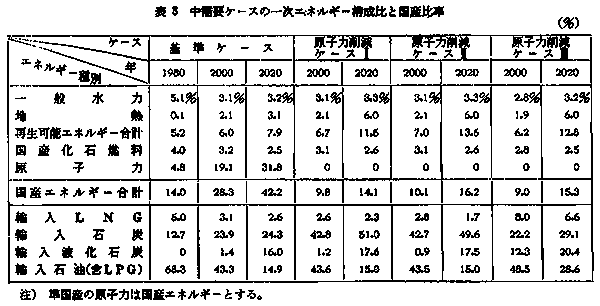 (2) 原子力削減による経済影響の解析方法
原子力を削減した場合マクロ経済に影響を与える最も重要な要因は輸入化石燃料の増加にあると考えられ、この影響を解析するため図1のようなマクロ・エネルギー経済モデルを試験的に構築した。このエネルギー経済モデルをエネルギー需給シナリオの基準ケースと原子力削減ケースに対して適用することによりシミュレーションを行ない、GNPと貿易収支(経常収支)への原子力削減の影響を検討した。今年度作成したモデルは過去の趨勢から見た関係式を中心に組立てられており、今後に残された課題もあるが参考までに試算結果を表4に示す。 図1 マクロ・エネルギー経済モデルの概要 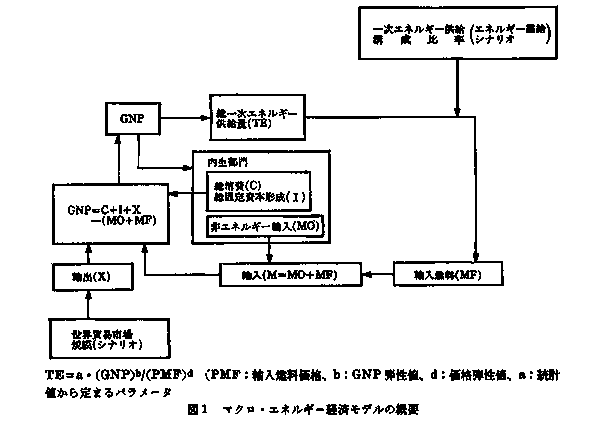 表4 原子力削減のGNP、貿易収支への影響の試算 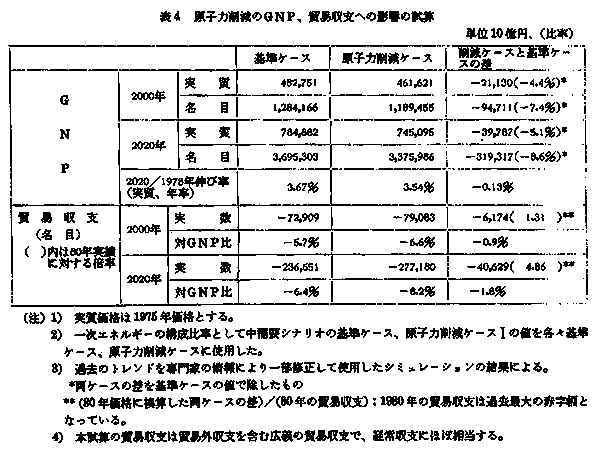 結果に示されているように、原子力の削減分は石油より価格の安い石炭で代替できる等の前提があるため、2020年における原子力削減の影響は経済成長率でみると年率0.1%程度の差であるものの、経常収支の差では対GNP比で石油危機直後の1974年の水準の2倍程度の赤字が余計に発生することに相当し、しかもこれが恒常的に累積されることを考えると為替レートの変化を通じてのインフレ促進等に少なからぬ影響を及ぼす結果と云えよう。 以上のようにマクロ・エネルギー経済モデルをエネルギー需給シナリオのもとに解析することを試みたが、更に輸出の扱い方、輸入燃料価格の想定等前提条件を改善し、貿易収支の名目のバランスを考慮することによって、経済影響の分析に有効な手法となることが期待される。 なお経済影響については他に産業連関表を用いた産業構造変化の解析方法の検討も行なっているが、ここでは説明を省略する。 (3) 環境影響の検討
大気汚染物質(SOX、NOX、ばいじん、CO2)について前年度収集した部門別、エネルギー種別汚染物質排出係数とエネルギー需給シナリオのエネルギー供給量の積から全国排出量を求め、原子力推進の基準ケースと原子力削減ケースとの差を分析した。また公害防止計画等に示された大都市圏、コンビナート地域の大気汚染物質別の排出量と環境質(大気汚染物質濃度)の関係をもとに、将来のエネルギー需要量の増大に伴なう環境質への影響をマクロ的に把握する方法の検討を行なった。 その結果全国排出量においては、中需要シナリオで現状の各汚染物質削減率を前提とした場合、原子力削減ケースⅠでは、基準ケースに対して、SOXでは11~16%、NOXでは12~27%、ばいじんでは8~11%、CO2では34~53%現状対策後の排出総量が多く放出されることが示され、石炭火力ヘの対応が主要課題であることが示された。また環境質へのマクロ影響分析に関しては、地域別排出量と大気濃度との間に相関関係があることが示された。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |