| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
放射線化学の研究開発について 日本原子力研究所
1. まえがき
アイソトープ・放射線利用は原子力平和利用の一翼をになう重要な分野であり、医学、工業などへの応用も着実に進展し、直接、間接に国民生活の向上に役立っている。さらに、環境保全や資源利用などの社会的要請に応えるための放射線照射利用技術の開発も着実に進められている。このように、アイソトープ・放射線利用は国民生活に密着した幅広い分野でその成果を挙げているが、一方では、原子力平和利用に対する社会一般の理解を深める上でも重要な役割を果たしている。最近、アジア・太平洋地域の開発途上国における原子力平和利用技術の促進をはかるため、原子力科学技術全体の中で技術移転に最も適した分野として、食品照射、アイソトープ・放射線の工業利用などが取り上げられ、先進国としての日本の援助と協力が期待されている。 日本原子力研究所におけるアイソトープ・放射線利用の研究開発は、アイソトープの製造ならびに利用開発と放射線化学の研究開発であり、それぞれアイソトープ事業部および高崎研究所がこれらを担当している。 高崎研究所は昭和38年の創立以来、放射線法による新しい高分子材料の研究開発と環境保全や資源合成に対する放射線利用技術の開発を推進することによって多くの成果を挙げ、放射線化学の分野において最高の水準を有する応用研究の研究機関として内外から注目されるようになった。最近では、原子力エネルギー開発の分野における有機材料の耐放射線性の研究や、原子炉その他における放射線化学の関与する問題に対する研究の要請が強まったため、この分野の研究開発をも進めている。 2. 放射線化学の研究開発
放射線化学の研究開発では、放射線法による高分子材料の開発と環境保全などのための放射線照射利用技術の開発研究を進めている。 (1) 高分子材料の開発
放射線法による高分子材料の開発では、触媒を用いることなく、常温以下の温度でも、また固体の内部においても放射線エネルギーによる諸反応が効率よく行われるという特長を活かして、放射線プロセスを工業化しようとするものである。高崎研究所は当初、高分子化学の工業化を目指して開発研究を進め、繊維のグラフト重合、エチレンの重合、トリオキサンの固相重合、ポリ塩化ビニルの改質など、いわゆる汎用樹脂の製造プロセスの工業化のための技術開発を進めてきた。この期間、民間産業からの外来研究員と一体となって中間規模試験を進めた結果、放射線法プロセスの技術移転や民間技術者の養成が行われ、日本の化学工業界における放射線化学の工業化の基礎を確立するという成果を挙げることができた。 昭和48年の第1次石油ショック以後、産業界の変化に対応して、付加価値の大きないわゆる“ファイン・ケミカル”材料の開発に目標を移し、機能性をもつ高分子材料などを放射線法によって開発することに研究を移行した。現在では、グラフト重合の特長を活かした一次電池用隔膜*、二次電池用隔膜ならびに水の電気分解に用いるイオン交換膜の製造、低温放射線重合による光学用有機ガラス材料(大口径レンズ、プリズム、フレネル・レンズ)の開発や生体活性体の固定化技術の開発と、それを応用したセルロース廃資源の糖化・発酵の研究、および有機溶剤を必要としない無公害、省資源のエマルション水性塗料の開発研究を進めている。このほか、基礎研究として高線量率の電子線照射による重合反応で生成する反応性オリゴマーなどの研究も進めている。 * 注) 一次電池用隔膜の製造技術は、新技術開発事業団の開発課題に選定され、湯浅電池(株)において55年度に実用化試験が開始された。 これらの開発研究の中で、現在重点的に進めているセルロース廃資源の利用技術の開発について、少し詳しく説明することにする。未利用のバイオマス資源(光合成によって生産される生物資源-主として植物)を工業用原科あるいは代替エネルギー原科に変換する、いわゆるバイオマス変換の利用技術の開発が急がれている。たとえば、昭和55年度には通産省主管の新燃料油開発技術研究組合が発足し、多くの民間会社がこれに参加してセルロースの糖化・発酵の開発研究が進められている。高崎研究所では、これに先立って、昭和49年頃から低温放射線重合法により薬剤や酵素を高分子で固定化する技術の開発を進めてきた。薬剤の固定化では、固定化された薬剤の効果を長時間持続させることができる。このような徐放化医薬品のうち、とくに固定化制癌剤について医学界の関係者と協力し、その実用化を目標に開発を進めている。昭和52年頃から固定化酵素などを用いて、モミ穀、ワラなどのセルロース廃資源を糖化・発酵させ、エタノールに変換する技術の開発研究を進めている。この一連の開発研究には、放射線照射によるセルロース廃資源の前処理法も含まれている。すなわち、セルロース廃資源に約10Mradの電子線照射を行ったのち、化学的添加物(分解促進剤)を加えて機械的粉砕を行い、スラリー化する方法がセルロースとリグニンの両成分を分離するための前処理法として有効である。酵素などの固定化では、低温過冷却状態で放射線重合を行うため高温で不安定なセルラーゼや、その生産菌を生態活性を失うことなく高分子材料に複合固定化することができるという利点がある(第1図)。 第1図 固定化セルラーゼ菌体
担体:ポリエチレングリコールジメタクリレート重合体
固定化条件:温度-78℃、線量1Mrad
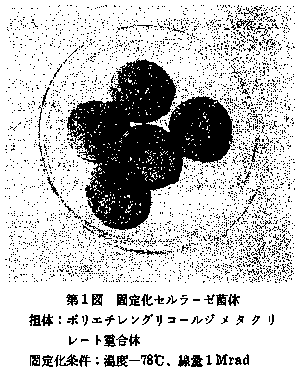 放射線法による固定化酵素の糖化・発酵プロセス全体への適用性を明らかにし、この手法についての中間評価をまって関係諸機関との協力関係をつくり、その実用化をはかることを目標として、一連の糖化・発酵プロセスの検討を始めようとしている(第2図)。昭和56年度には、原科の前処理条件や酵素・菌体などの固定化条件の検討を行うとともに、固定化物による糖化・発酵試験を進め、固定化物の性能評価を行う予定である。 今後、遺伝子工学などの技術によって開発が予測される高性能の酵素・菌体に対しても、このような固定化技術が利用できるので、将来の燃料油の開発技術に対してその期待は大きい。 第2図 プロセスフローシート 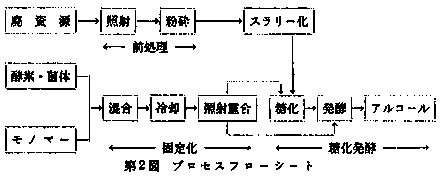 (2) 放射線照射利用技術の開発
放射線照射により環境汚染物質を無害化したり、汚泥を堆肥化して農業資源として再利用するような放射線利用技術の開発研究は国家的、社会的ニーズに応えるための技術開発として重要な課題である。近年、大容量のコバルト-60線源や大出力の工業用電子加速器の利用が可能となり、放射線の相対的コストも下ったため、大量の放射線照射を必要とする上述のプロセスの実用化に対して、明るい見通しが得られるようになった。 環境保全のための応用技術の開発研究では、鉄鉱焼結炉からの排煙に含まれる比較的低濃度のNOX、SO2を放射線照射によって除去する技術開発を行い、その成果を用いて、鉄鋼業窒素酸化物防除技術研究組合によりパイロット試験が実施された。現在は、石炭排煙に含まれる高濃度のNOX、SO2の処理技術の研究開発を進めている。また、オゾンと電子線の併用による産業廃水や難分解性物質の放射線分解などの開発研究を行っている。さらに、下水処理システムへの放射線法の応用の一環として、余剰汚泥の放射線処理によるコンポスト(堆肥)化技術の開発など、資源の有効利用に関連した研究も進めている。下水道の整備に伴い、下水処理プロセスで発生する汚泥の処理処分は重要な問題となっている。汚泥の緑農地還元をはかるため、0.3~0.5Mradのγ線を照射して汚泥を減菌化した後、発酵菌などを加えてコンポスト化するプロセスについて、高速コンポスト化実験装置(第3図)を用いて工学科検討を進めている。 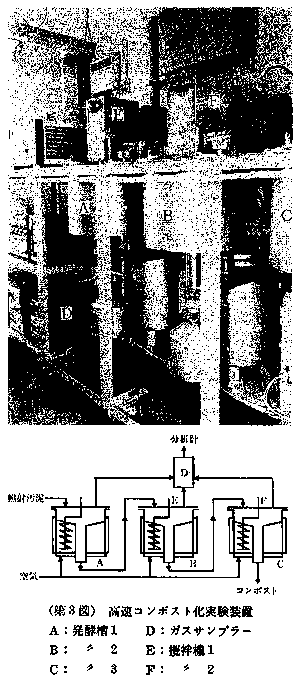 食品照射の分野では、高崎研究所は国の特定総合研究で指定されている7品目の食品について研究を分担しているほか、他の研究機関と協力して飼料の照射についての研究も進めている。 基礎的な研究の分野では、一酸化炭素、メタン、メタノールなどのいわゆるC1化合物から、電子線照射によってエチレンなどのC2以上の化合物を有機工業原料として合成する反応や、石炭の高温放射線分解などの研究を行っている。 大線量測定技術、照射施設・装置の設計などは上述の放射線照射利用の基盤技術として必要であり、また産業界における放射線利用を側面的に支援して、その普及を図るためにも重要である。高崎研究所では、このような照射技術を進める一方、ジャガイモの照射工場の設計やウリミバエの不妊化のための照射施設の設計・建設など、外部からの要請に応えて協力を行っている。 高崎研究所の照射施設は、コバルト照射1棟(50万キュリー)、コバルト照射2棟(50万キュリー)、食品コバルト棟(40万キュリー)のγ線照射施設、1号加速器(2MV、30mA)、2号加速器(3MV、25mA)の電子加速器、3号加速器(200kVp、1A)のX線発生装置などがある。このうち、1号加速器は共振変圧器型の旧加速器を更新し、建屋関係7.2億円、本体関係2.8億円を投じて建設し、昭和56年1月から試運転を、2月中旬から試験照射を開始したものである。この加速器は加速電圧0.5~3MeV(連続可変)、電子電流0.1~30mA(連続可変)のコッククロフト・ワルトン型加速器で、2本の加速管により水平方向と垂直方向に電子ビームを取り出せるようにした世界で始めてのデュアルビーム方式を採用している(第4図)。加速器建屋は3階建で、加速器本体は2階に設置され、加速器室の隣には水平照射室、真下の1階には垂直照射室が設置されている。今後、この加速器を利用することによりオゾンと電子線の併用による廃水処理技術、汚泥のコンポスト化のための殺菌処理技術、セルロース廃資源の糖化・発酵のための電子線前処理技術、イオン交換膜の製造などの研究開発が行われる予定である。 第4図 更新1号加速器本体 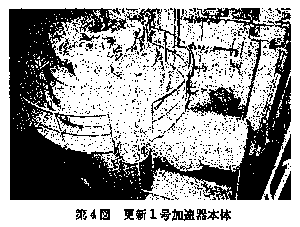 3. 原子力エネルギー開発に寄与する研究開発
原子力エネルギー開発に寄与する研究開発では、放射線化学の分野における経験や知識を活用できる諸問題を取りあげることとし、とくに原子力施設に用いられる有機材料の耐放射線性の試験研究を進めようとしている。 すでに数年来、軽水炉の工学的安全性研究の一環である、軽水炉用電線ケーブル等の健全性を確認するための試験方法の研究として、軽水炉の冷却材喪失事故(LOCA)を模擬した環境下における電線材料等の試験を進めている。この試験研究では、冷却喪失事故の模擬環境をつくるための原子炉用電線ケーブル試験装置(SEAMATE-Ⅱ)が用いられている(第5図)・また原子炉の40年間の平常運転時における絶縁材料の劣化の状況を短時間の試験で再現するための促進劣化試験法の研究も進めている。一方、軽水炉に用いるための耐放射線性電線絶縁材料の開発では、絶縁材料に臭素化アセナフチレン縮合体を添加して難燃性の向上をはかるとともに、耐放射線性を改善するための助剤の開発をも検討している。このほか、有機材料の放射線損傷の機構の解明のための研究も行っており、今後さらにウラン、リチウムの捕集のための有機系吸着剤の開発など、原子力エネルギー開発の分野に対する研究開発を拡充強化する予定である。また、多目的高温ガス炉の核熱利用系開発の一環として、熱化学法による閉サイクル水素製造プロセスの開発を進めるとともに、放射線化学反応による水素製造法についても基礎研究を進めている。 第5図 本体圧力容器の中に試験用ケーブルを入れるところ 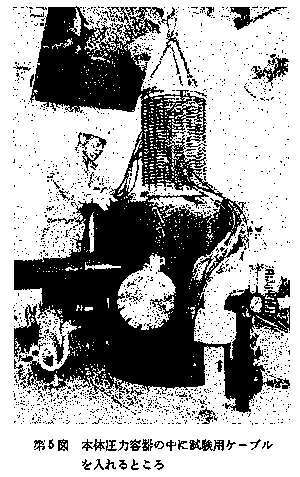 4. 対外協力
放射線利用の研究開発は利用の対象が広範囲で多岐にわたっており、研究開発を効率的に進める上にも、また研究成果を実用化に結びつけるためにも他の研究機関、大学、産業界などとの協力が必要である。外部機関との協力については従来からも努力してきたが、今後国家的、社会的ニーズに応えるための開発研究を重点的に取り上げてゆく上で、さらに一層対外協力を強化する必要がある。 国際協力については、昭和40年以来フランス原子力庁(CEA)と放射線化学の分野における協力協定を進め、共同研究と情報交換を行ってきた。この協力協定により、両国における放射線化学の工業化の問題について効果的な検討がなされたことは有意義であったが、その役割を終了したことによって昭和55年5月に協定を終結した。 昭和53年8月、日本政府は国際原子力機関(IAEA)のアジア-太平洋地域協力協定(RCA*)に加盟した。この協定は原子力平和利用科学技術を開発途上国に移転することを目的とするものであるが、開発途上国からの要請の強いアイソトープ・放射線利用技術の移転を中心に、計画がつくられている。日本政府は協力の対象分野として、食品照射およびアイソトープ・放射線の工業利用を優先課題として取り上げ、関係官庁、研究機関および民間企業の専門家で構成するIAEA/RCA活動推進会議を設けて具体的な対応策の審議を行っている。 日本原子力研究所は国の要請により本協定の実施に積極的に協力することになり、高崎研究所としては東南アジア諸国から食品照射技術、放射線プロセスの工業利用に関する研修生の受入れや専門家の派遣、ワークショップの分担実施などに協力している。これらの分野における東南アジア諸国の高崎研究所に対する期待はきわめて大きいものがある。 * 注)原子力委員会月報通巻289号(55年)、P.19藤井“RCA活動の意義と展望”で詳しく解説されている。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |