| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
昭和56年度原子力開発利用基本計画について(答申) 56原委第62号
昭和56年3月31日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
昭和56年3月30日付け56原第19号をもって付議された標記の件については、審議した結果、原案どおり議決したので日本原子力研究所法第24条の規定に基づき答申する。 昭和56年度原子力開発利用基本計画
Ⅰ 基本方針 エネルギーの安定的確保は、国民生活水準の維持向上及び社会経済の発展にとって必要不可欠である。最近の国際石油情勢は、イラン・イラク紛争の影響等により、依然として、量及び価格の両面で不安定であり、中長期的にも需給のひっ迫化傾向は避けられない。 このような情勢の下で、先進消費国の中でも特に輸入石油への依存度が高い我が国としては、石油消費節減の努力とともに、石油代替エネルギーの開発及び導入を促進し、石油依存度低減のための努力を積み重ねていかねばならない。 原子力発電は、大量のエネルギー供給が可能な石油代替エネルギーの中核となるものであり、かつ、在来の石油火力等に比べ低廉なため、物価の抑制及び石油輸入のための外貨流出の低減による国際収支の安定にも資することができる。 このように、原子力の開発利用は我が国のエネルギー政策上の重要課題となっている。 原子力の開発利用の推進に当たっては、安全性の確保が大前提であり、その上に立って、広い国民的支持を得るように努めていくべきであり、安全確保についての施策の一層の充実を図るものとする。 我が国の原子力発電は既に電力供給の重要な担い手となっているが、昨年11月政府が決定した石油代替エネルギーの供給目標における原子力発電の開発目標を達成するには、当面する立地難の打開を図らなければならない。このためには、原子力発電の必要性と安全性について国民の理解を得る方策の充実とともに、地元住民の福祉向上の方策を充実するなど、原子力発電所等の立地を促進するための施策を強化するものとする。 次に、原子力発電を拡大していくに当たっては、ウラン資源の確保、濃縮ウランの国産化、国内再処理事業の確立、放射性廃棄物処理処分対策の推進等、核燃料サイクルを早期に確立せねばならない。特に、ウラン濃縮については、これまでの自主技術開発の成果を踏まえて、国内事業化の方策を確立するとともに、放射性廃棄物の処理処分対策については研究開発等を一段と充実するものとする。 また、中長期的観点から、次代の発電炉として期待される高速増殖炉等の新型動力炉の開発、多目的高温ガス炉の研究開発、更には核融合の研究を引き続き精力的に推進する。新型動力炉については、国は特に民間産業界の積極的な協力を得て、実用化を促進するものとする。また、原子船の研究開発についても、これを着実に進めるものとする。 放射線利用については、医療、工業、農業等多くの分野で進められているが、その多様化及び高度化を一層促進するものとする。 更に、原子力開発利用の基盤を強化するため、基礎研究を充実するとともに、長期的観点から原子力関係科学技術者等の養成訓練を行い、人材の確保に努めるものとする。 一方、原子力を取り巻く国際情勢については、昨年2月に終了した国際核燃料サイクル評価(INFCE)の成果を踏まえ、現在、国際原子力機関(IAEA)を中心として、核不拡散を確保しつつ、原子力平和利用の促進を図るための新しい制度に関する多国間協議がなされており、また、二国間の原子力協力協定の改正交渉等が進められている。我が国としては、核拡散防止のための国際的努力に協力しつつ、自国の原子力平和利用の促進を図るとの基本的考え方に立って、これらの諸協議等に積極的に対処していくとともに、より効果的な保障措置体制の確立を図り、併せて、国内核物質防護体制の整備、充実を進めるものとする。 昭和56年度においては、以上の基本方針の下に、次の施策を講じ、原子力開発利用の総合的推進を図るものとする。 Ⅱ 昭和56年度施策の概要 1 安全確保対策の総合的強化
原子力の開発利用を進めるに当たっては、これまでも厳重な規制と管理を実施し、安全の確保に万全を期してきたところであるが、今後における原子力開発利用の進展に対応してゆくためには、スリー・マイル・アイランド(TMI)原子力発電所事故の教訓をも踏まえ、原子力の安全確保対策を、更に充実し、安全性の一層の向上を図っていく必要があり、次の施策を講ずる。 (1) 原子力安全規制行政の充実
原子力の安全確保のための規制については、行政庁において、法令に基づき、厳正な安全規制を行うため、安全審査、検査、運転管理監督体制等の強化を図る。 原子力安全委員会においては、行政庁の行う設置許可等に係る安全審査についてダブルチェックを行うほか、設置許可等の後の各段階における重要事項についても審議し、行政庁の行う安全規制の統一的評価を行い、原子力の安全確保に万全を期する。 原子力安全委員会の審査、審議に当たっては、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の調査、審議において、独自の安全解析を行うなど、審査機能等の充実を図り、客観性、合理性の確保に努めることとする。また、原子力発電所等主要原子力施設の安全審査について、ダブルチェックを行う際には、当該施設の安全性に関し、公開ヒアリングを開催する。 また、放射線利用の拡大普及に対処するため、昨年、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律の改正が行われた。この改正の趣旨にのっとり、放射線利用施設に対する検査体制の強化、放射線取扱主任者免状取得に当たっての講習の義務付けを図るとともに、これらの検査、講習等を国に代って行う指定代行機関を指定し、その実施体制の整備を図る。 安全規制に必要な各種安全基準及び指針の整備については、発電用軽水炉、核燃料施設等に関し、前年度に引き続き、更に拡充、整備を図るとともに、新型動力炉に関しても鋭意安全基準及び指針の整備を図っていく。 更に、IAEAにおける原子力発電所に関する安全基準作成計画及び放射性物質安全輸送規制の改訂事業並びに経済協力開発機構原子力機関(OECD-NEA)における原子力施設安全規制国際協力事業に参加するとともに、米国及びフランスとの間で安全規制の情報交換を進め、我が国の安全基準及び指針の整備等安全規制の充実に資する。 なお、原子力全般に共通する安全問題について専門家によるシンポジウムを開催することとする。 国際放射線防護委員会(ICRP)の新勧告の導入については、放射線審議会において審議中であるが、その答申を得て所要の措置を検討する。 (2) 安全研究の推進
安全規制の裏付けとなる科学技術的知見を蓄積し、各種安全審査基準、指針等の一層の整備・充実に資するため、軽水炉等原子力施設の工学的安全研究及び放射線障害防止に関する研究等環境安全研究を推進する。 ① 工学的安全研究
軽水炉に関する工学的安全研究については、日本原子力研究所を中心に国立試験研究機関等の協力の下に総合的、計画的に実施する。特に日本原子力研究所においては、緊急炉心冷却実験装置による沸騰水型軽水炉の冷却材喪失事故実験(ROSA-Ⅲ計画)、原子炉安全性研究炉(NSRR)による反応度事故時の試験研究、実用燃料照射後試験施設(大型ホット・ラボ)による実用原子炉燃料の試験等の安全研究を実施する。また、TMI事故に関連する研究として引き続き、加圧水型軽水炉の小破断冷却材喪失事故時の総合実験(ROSA-Ⅳ計画)、原子炉電線材料等の健全性に関する研究等を進める。 核燃料施設に関する工学的安全研究については、日本原子力研究所を中心に臨界安全性に関する研究、しゃへい安全性に関する研究、再処理施設の安全評価に関する研究等を実施する。 また、機械技術研究所、船舶技術研究所、建築研究所等の国立試験研究機関においては、核燃料輸送容器の構造強度、耐火性等に関する安全研究及び地震の実測データの収集分析等についての安全研究を実施する。 更に国際協力による安全研究として燃料の性能及び信頼性等に関する研究を行うハルデン計画、冷却材喪失事故の研究を行うLOFT計画、燃料照射研究を行うデモランプ計画、バッテル計画等に参加するほか、日本原子力研究所の原子炉安全性研究炉(NSRR)と、米国、西ドイツ及びフランスの安全性実験施設との間の研究員の相互派遣、情報の交換等を行う。 ② 環境安全研究
放射線障害防止に関する調査研究として放射線医学総合研究所を中心に低レベル放射線による晩発障害、遺伝障害、内部被ばくに関する研究等を推進する。 特に、プルトニウム等の内部被ばく研究を強化するため、内部被ばく実験棟の建設を昭和58年度の完成を目途に進める。 放射線医学総合研究所以外の国立試験研究機関等においては、低レベル放射線による哺乳動物系における突然変異の検出法に関する研究、植物における突然変異の誘発に関する研究等を実施する。 また、環境放射能に関する調査研究として、放射線医学総合研究所、その他の国立試験研究機関、日本原子力研究所、地方公共団体試験研究機関等において、環境放射線モニタリング及び公衆の被ばく線量評価に関する調査研究並びに一般環境、食品及び人体内の放射能の挙動と水準の調査を行うほか、防災対策関連の研究として、日本原子力研究所及び気象研究所において環境放射能予測システムに関する研究等を実施する。 (3) 防災対策の充実
原子力発電所等の万が一の緊急時には、災害対策基本法により、迅速かつ適切な対策がとられることとなっているが、防災対策を一層充実するため、一昨年7月中央防災会議において、「原子力発電所等に係る防災対策上当面とるべき措置」を決定するとともに、原子力安全委員会においても一昨年緊急技術助言組織を設置したほか、昨年6月に「原子力発電所等周辺の防災対策について」を決定した。これらの措置に基づき地方公共団体等関係各機関において防災業務計画及び地域防災計画の修正による防災対策の一層の充実整備が図られている。 本年度は引き続き国と県、国と発電所等を専用回線及びテレファックスで結ぶ緊急時連絡網、モニタリングポストの増設等による緊急時環境放射線監視体制及び県の病院等における緊急医療体制の整備を図るほか、日本原子力研究所等において地方自治体職員等のための防災研修コースを開催するなど教育訓練体制を整備し、また、関連研究の推進等防災対策の充実強化を図る。 (4) 原子力事業従業員の被ばく管理対策の充実
原子力事業従業員の被ばく管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、労働安全衛生法等に基づき、今後ともその徹底を図る。 更に、定期検査等における従業員の被ばく線量の低減化対策の充実を図る。 2 原子力発電の推進
近年、原子力発電の必要性及び安全性についての国民の認識は高まってはきているものの、立地地域における合意形成は必ずしも容易なことではなく、地域固有の事情を踏まえ、よりきめ細かい推進方策を総合的に展開し、合意形成の促進に努め、原子力発電を推進する必要がある。 また、現在の発電炉の主流を占める軽水炉の信頼性等の向上を図るため、軽水炉の改良、標準化等を推進する必要がある。以上の見地から次の施策を講ずる。 (1) 原子力発電所の立地の促進
① 広報活動等の強化
原子力研究開発利用に対する国民の理解を求め原子力発電を始めとする原子力の研究開発利用を一層円滑に推進するためテレビ、出版物等の活用、講演会、各種セミナーの開催、オピニオンリーダーに対する資料送付、原子力映画の作成、原子力モニター制度の活用などにより、広報活動を積極的に推進する。 更に、原子力発電所等の立地を円滑に進めるために立地予定地域の有識者を対象とした原子力講座等の開催を図るとともに、電力施設計画計上以前の原子力発電所立地の初期段階における地元住民の理解と協力を得るため、国自らが広報活動を展開するとともに、地方自治体の行う広報対策等への助成を行う。 また、電源立地調整官等の機能的活動により、原子力発電所の立地に係る地元調整を推進するとともに、運転に入った原子力発電所の立地県については、原子力連絡調整官による地元と国との連絡調整を進める。 ② 電源三法の活用
発電用施設周辺地域整備法等の電源三法を活用し、原子力発電施設等の周辺住民の福祉の向上等に必要な公共用施設の整備を進めるとともに、施設周辺の環境放射能の監視、温排水の影響調査、防災対策、原子力発電施設等の安全性実証試験等を推進し、原子力発電施設等の立地の円滑化を図る。 更に、昭和56年度から、新たに次のような施策を推進する。 イ 原子力発電施設等の周辺地域の住民、企業等に対する給付金の交付及び当該原子力発電施設等の周辺地域住民の雇用確保事業のための原子力発電施設等周辺地域交付金及び発電用施設の周辺地域住民の雇用確保事業のための電力移出県等交付金からなる電源立地特別交付金制度を創設し、原子力発電施設等の立地対策の抜本的強化を図る。 ロ 既存の制度についても、電源立地促進対策交付金について、同交付金により整備された公共用施設の維持等のために使えるよう、その使途を拡大するとともに、放射線監視交付金及び温排水影響調査交付金についても、設備の更新にも使用できるようその使途を拡大し、また、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金について、緊急時の周辺環境への影響調査を交付対象に追加する等内容の充実を図る。 (2) 軽水炉の改良・標準化等の推進
現在、建設、運転が進められている軽水炉について、信頼性の向上、保守点検作業の的確化、作業員の被ばく低減化等の観点から、自主技術による改良・標準化推進のための調査を行うとともに、原子力発電所に係る品質保証対策のための調査、原子力発電検査機器の開発のための調査及び民間における原子力発電検査機器の開発のための調査及び民間における原子力発電支援システムの開発の助成を行う。 また、軽水炉の安全性・信頼性を実証するため、大型再冠水効果実証試験、配管信頼性実証試験、耐震信頼性実証試験及びポンプ信頼性実証試験等を実施する。 更に、作業員の被ばく低減化のための確証試験及び技術開発を行うとともに、高性能燃料について確証試験に着手し、その実用化の促進を図る。 このほか、原子力発電所の廃炉の時期に備えて、日本原子力研究所の動力試験炉(JPDR)をモデルとして廃炉の技術開発を推進するとともに、発電用原子炉の廃炉に使用される設備について確証試験を実施する。 また、原子力発電所の新立地方式に関する調査を行う。 3 核燃料サイクルの確立
我が国の自主的核燃料サイクルを早期に確立するため、海外ウラン調査探鉱活動の強化、ウラン濃縮技術開発の推進、国内再処理事業の確立のための施策の推進、放射性廃棄物の処理処分対策の推進等を行う。 (1) ウラン資源の確保
動力炉・核燃料開発事業団によるアフリカ諸国オーストラリア、カナダ等における単独又は諸外国の機関との協力による共同の海外ウラン調査探鉱活動を強化するとともに、金属鉱業事業団の出融資制度等民間企業による海外ウラン探鉱開発活動に対する助成策の拡充強化を図り、ウラン資源の確保に努める。 国内探鉱については、動力炉・核燃料開発事業団で東濃地区の美佐野鉱床の精密試錐等を行う。更に、ウラン資源開発のための研究開発として動力炉・核燃料開発事業団において、ウラン鉱石から六弗化ウランまでの製錬転換試験等を行うとともに、製錬、転換パイロット・プランの運転を開始する。 また、低濃度ウランの回収技術に関する研究、海水ウランの回収システムの開発調査等を進める。 (2) ウラン濃縮
動力炉・核燃料開発事業団のウラン濃縮パイロット・プラントの建設を完了させ、遠心分離機7,000台による全面運転を開始する。また、より高性能の遠心分離機の開発、遠心分離機の量産化技術の開発等を引き続き行うとともに、原型プラントの詳細設計を進める。 また、国は民間産業界との密接な協力の下に遠心分離法によるウラン濃縮国内事業化のための推進方策を確立する。 更に民間企業による化学法ウラン濃縮技術の試験研究及びシステム開発調査に対して、助成を行うとともに、日本原子力研究所において、各種のウラン縮濃技術に関し、基礎的研究を進める。 また、オーストラリアにおけるウラン濃縮事業の確立に関するフィージビリティ調査に協力する。 (3) 使用済燃料の再処理並びにプルトニウム及び回収ウランの利用
① 再処理技術の実証と確立を図るため、動力炉・核燃料開発事業団において東海再処理施設の操業を行うとともに、プルトニウム転換施設の建設等所要の施設整備を行う。更に、再処理の改良技術放射性物質の放出低減化技術等の研究開発を進める。また、今後増大する再処理需要に対処するため、民間再処理会社による再処理工場の建設計画を推進することとし、国はこれに対し、支援する。 このため、動力炉・核燃料開発事業団における技術及び経験の円滑な移転を図るとともに大型再処理施設の環境安全の確保及び保障措置の適用のための技術開発並びに技術確証等を実施する。 なお、当分の間、国内再処理能力を上回る需要については、海外再処理委託により対処する。 ② プルトニウムについては、これを高速増殖炉等新型動力炉の燃料に使用するため、動力炉・核燃料開発事業団においてプルトニウム加工技術の開発、プルトニウム燃料の照射試験等を行う。また、軽水炉のプルトニウム利用に関しては、軽水炉へのプルトニウム実用規模利用の実証に関する調査等を行う。 ③ 回収ウランを再濃縮して利用する技術の確立を図るために、動力炉・核燃料開発事業団においてカスケード試験装置(BT-3)の改造に着手する。 ④ 放射性廃棄物の処理処分
低レベル放射性固体廃棄物については、原子力発電の進展に伴い、今後発生量増大が予想されていることから、その一層の減容化に努めるとともに、海洋処分については、本格的処分に先立ち、海洋処分の安全性を確認するため、内外関係者の理解を得て、試験的海洋処分の実施に努める。 陸地処分については、試験的陸地処分に備え、日本原子力研究所において、新たに環境シュミレーション研究に着手し、安全評価に関する試験研究を充実するとともに、引き続き処分技術に関する調査研究等を進める。 更に、高レベル放射性廃棄物の処理処分については、動力炉・核燃料開発事業団等において、ガラス固化処理の技術の開発、固化貯蔵パイロット・プラントの基本設計等を進めるとともに、地層処分に関し、地層に関する調査研究、工学バリアに関する研究等を進める。また、日本原子力研究所において、処分に関する安全評価試験を引き続き実施する。 海外再処理に伴う返還固体化に関しては、その技術仕様についての検討を行うとともに、我が国への受け入れが円滑に行えるよう受入れシステムに関する調査を行うほか、動力炉・核燃料開発事業団において冷却等の試験を行う。 4 新型炉の開発
(1) 新型動力炉の開発
① 高速増殖炉
プルトニウムを燃料とし、かつ、消費した以上のプルトニウムを生成し、将来の発電用原子炉の本命として位置付けられる高速増殖炉の開発については、実験炉「常陽」について7.5万kwの定常運転を行った後、10万kwの照射用炉心への移行のための作業を開始する。同原型炉「もんじゅ」については、設計研究、炉物理、炉体構造、燃料、安全性、蒸気発生器等の研究開発を進めるとともに、昭和62年度の臨界を目途に地元の受入れ体制等が整い次第、仮設工事の建設の諸準備及び本体製作を進める。 ② 新型転換炉
高速増殖炉が実用化するまでの中間段階において、核燃料サイクル上有効な役割を果たすものと期待される新型転換炉の開発については、原型炉について冷却系配管の取替工事を実施し、定常運転を再開し、運転経験を蓄積する。 また、実証炉については、合理化設計及び燃料材料部品機器、安全性等の研究開発を実施し、これらを基に、新型転換炉に関する技術的、経済的の評価等を行い、実証炉の開発に関する今後の施策の確立を図る。 ③ その他
高速増殖炉「常陽」及び新型転換炉「ふげん」に使用するプルトニウム燃料の開発のため、引き続きプルトニウム燃料製造施設の整備、運転を行うとともに、新たに高速増殖炉「もんじゅ」の燃料製造施設の建設に着手し、また、高速増殖炉の使用済燃料を再処理する技術を確立するため、所要の研究開発を進める。 (2) 多目的高温ガス炉の研究開発
製鉄、水素製造等非電力部門への核熱エネルギーの利用を目的とする多目的高温ガス炉の開発については、日本原子力研究所において、プラント機器の安全性を実証するための大型構造機器実証試験ループ(HENDEL)の建設を行うとともに、実験炉の詳細設計を進める。 また、炉物理実験、高温構造試験、伝熱流動試験等の実施及び被覆粒子燃料、黒鉛材料、耐熱金属材料等の研究開発を進める。 5 核融合の研究
実現された暁には半永久的なエネルギーの供給を可能にするものとして期待される核融合については、大学における各種研究の進展をも総合的に考慮し、国際協力の推進にも留意しつつ、日本原子力研究所におけるトカマク方式による大規模な研究開発等を計画的に推進する。 日本原子力研究所においては、臨界プラズマ条件達成を目指した臨界プラズマ試験装置(JT-60)の建設を進めるとともに、同装置等の核融合研究施設の建設用地の確保等、引き続きサイトの整備を行う。 また、中間ベータ値トーラス装置(JFT-2)によるトーラスプラズマの研究及び同装置の改造並びにプラズマ加熱の研究開発、核融合炉心工学、炉工学技術の研究開発等を進める。 電子技術総合研究所においては、高ベータ・プラズマの研究のため、圧縮加熱型核融合装置(TPE-2)の建設を進める。 理化学研究所においては、プラズマの診断、真空技術の基礎的研究を進める。金属材料技術研究所及び名古屋工業試験所においては、材料の基礎的研究を行う。 なお、超電導磁石技術については、日本原子力研究所、電子技術総合研究所、金属材料技術研究所等において研究開発を拡充強化し、特に大型超電導磁石の開発については、OECD-IEAの大型超電導磁石国際協力計画(LCT計画)に基づき、日本原子力研究所が分担するLCTコイルの製作及び国内試験を進め、米国への搬送を行う。 更に、米国のダブレット-Ⅲを使った日米間の共同研究等の二国間協力及びIAEA等多数国間の核融合研究についての国際協力を推進し、我が国の核融合研究開発の効率的実施に資することとする。 6 原子力船の研究開発
日本原子力船研究開発事業団において、原子力船「むつ」のしゃへい改修工事及び安全性総点検補修工事を進めるとともに、同船の新定係港を早急に決定し、所要の施設整備を行う。 更に、原子力船の開発に必要な研究については、船舶用原子炉等の開発に必要な研究を引き続き行う。 また、船舶技術研究所においては、原子力船についての基礎的、先導的研究及び安全規制研究を進める。 7 放射線利用の推進
放射線利用については、医療分野におけるサイクロトロンによるガン治療、各種疾病の診断に関する研究開発、工業分野における放射線化学の研究、農業分野における食品照射の研究等を推進する。 このため、放射線医学総合研究所においては、サイクロトロンを用いて速中性子線によるガンの治療研究及び陽子線による研究を引き続き進めるとともに、短寿命ラジオ・アイソトープの生産、利用の技術開発を推進する。 日本原子力研究所においては、放射線化学関係の研究、ラジオ・アイソトープの生産及び利用を推進する。 国立試験研究機関においても、電子技術総合研究所で放射線標準に関する研究に必要な加速器の整備を行うなど、放射線利用に関する研究を強化する。 また、食品照射研究については、実用化の見通しを得ることを目標に、日本原子力研究所、理化学研究所、国立試験研究機関等が協力して、照射技術、毒性及び遺伝的安全性の試験研究を進める。 8 原子力開発利用の基礎強化
(1) 基礎研究等の充実
我が国独自の原子力技術の研究開発を進めるため、その基盤となる基礎研究等を、日本原子力研究所、理化学研究所及び国立試験研究機関において大学との緊密な連携の下に推進する。 日本原子力研究所においては、材料試験炉等による各種燃料、材料の照射試験を引き続き実施するとともに、タンデム型重イオン加速器の運転を行い、材料の照射損傷、核データ等の研究及び核融合等の開発に資する。 また、理化学研究所においては、重イオン科学用加速器の前段加速器である線型加速器を用いて重イオンに関する各種研究を引き続き進めるとともに、重イオン科学用加速器の後段加速器であるリングサイクロトロンの建設を進める。 (2) 科学技術者等の養成訓練
原子力開発利用の進展に伴い原子力の様々な分野で、需要の増大している原子力関係科学技術者の養成訓練については、大学に期待するほか、海外に留学生として派遣し、その資質向上に努める。また、日本原子力研究所のラジオアイソトープ・原子炉研修所及び放射線医学総合研究所において養成訓練を引き続き実施する。 また、長期的観点から、原子力発電所等の運転員の養成資格制度の整備により運転員の資質向上を図る。 9 国際協力の推進
(1) 国際核燃料サイクル評価(INFCE)は昭和55年2月に終了し、各国の原子力事情に対する相互理解が増進したが、その後INFCEの成果を踏まえ、国際原子力機関を中心に、新たな枠組み作りとして国際プルトニウム貯蔵、国際使用済燃料管理及び核燃料等の供給保証の多国間協議が行われており、また日豪原子力協定の改正交渉等の二国間交渉太平洋ベースン使用済燃料暫定貯蔵構想に関する日米共同フィージビリティ調査等が進められている。 我が国としては、これらの多国間協議、二国間交渉等において、核拡散防止のための国際的努力にはできる限り積極的に協力しつつ、INFCEの結論が尊重され、我が国の原子力平和利用の円滑な推進に支障が生じることのないよう対処する。 (2) また、原子炉の安全研究協力、核融合に関する日米協力等を推進するほか、新型動力炉の開発、多目的高温ガス炉の研究開発、保障措置技術等の各分野において、米国、西ドイツ、フランス、ソ連等との二国間協力等を進める。また、米国、フランスとの二国間規制情報交換を進める。 更に、IAEAにおける原子力発電所に関する安全基準作成計画及び放射性物質安全輸送規則の改定事業並びにOECD-NEAにおける原子力施設安全規制国際協力事業に参画するなど国際機関の活動に積極的に参加する。 開発途上国に対する技術援助については、昭和53年8月加盟した、原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練に関する地域協力協定(RCA)に基づく協力を中心として、適切な協力に努める。 10 保障措置及び核物質防護対策の強化
(1) 保障措置
核兵器の不拡散に関する条約に基づく保障措置のより有効な実施を図るため核物質に関する情報処理、査察、試料の分析等の国内保障措置業務を一層充実するとともに、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団等において、保障措置技術の改良に関する研究開発を積極的に推進するほか、IAEA等との国際共同研究開発に積極的に参加することを通じ、より効果的な保障措置体制の確立を図る。 (2) 核物質防護
核物質防護については、原子力発電所、日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団の施設を始めとする各種原子力施設の防護措置の一層の拡充を図るとともに、関連調査研究等を行う。更に核物質防護強化に関する国際的な動向にも留意しつつ、国内核物質防護体制の整備・充実を進める。 11 昭和56年度原子力関係予算の概要
昭和56年度における原子力開発利用を推進するために必要な原子力関係予算及び人員は、次表のとおりである。 (1) 昭和56年度原子力関係予算総表 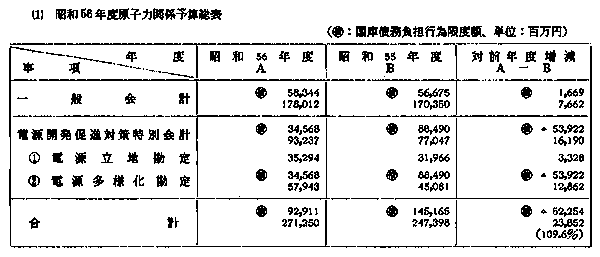 (2) 科学技術庁計上分及び各省庁行政費(一般会計) 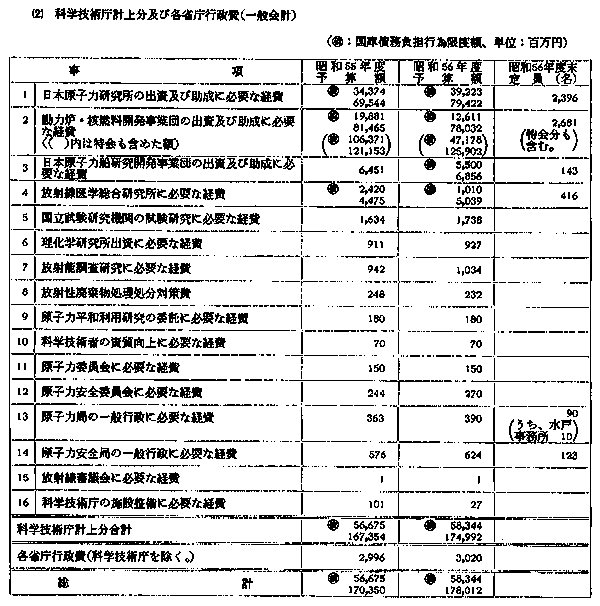 (3) 電源開発促進対策特別会計 (総理府、大蔵省及び通商産業省所管) 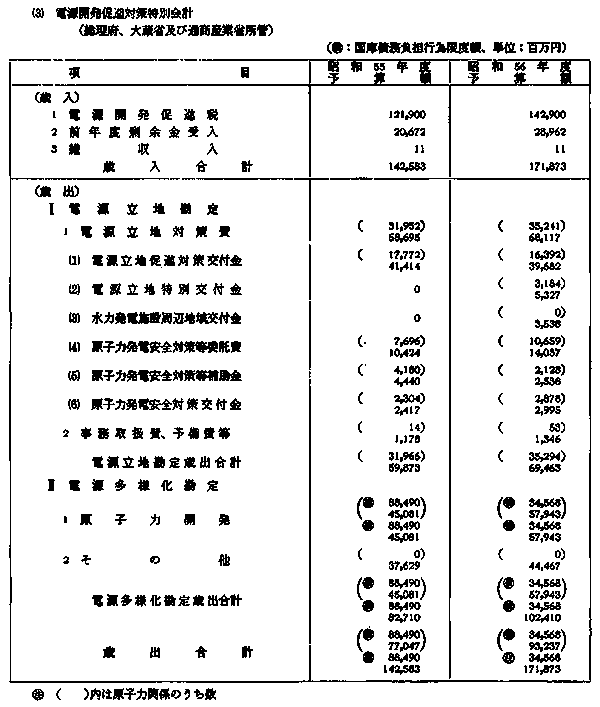 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |