| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||
|
原子力発電に対する意識構造に関する調査の概要 野村総合研究所 経営環境研究室
鈴木 正慶・吉田 隆
はじめに
本調査は昭和54年度科学技術調査資料作成委託調査費によるものであり、その目的は、原子力、とくに原子力発電に対する一般市民の意識構造および受容性を解明することにある。すなわち、本調査では一般市民の日常生活のなかで、原子力や原子力発電に対する不安や必要性の意識がどのようになっているのか、また、それらの意識がどのような背景から形成され、あるいは変化するのかを、電力の消費地と供給地において実施した市民アンケート調査の結果をベースに、明らかにした。(市民調査の実施要領参照)
市民アンケート調査の実施要領
1. 原子力発電に対する一般市民の基本意識
原子力発電に対する一般市民の基本意識を探るために、まず今後の原子力発電の開発に対する意見を尋ねると、電力消費地では約6割の人々が開発推進に肯定的であるが、原子力発電所既設地、さらには候補地へと行くにしたがって肯定的な人々は少なくなり、逆に否定的人々が多くなる。また、意見をはっきり表明しない不明層は電力消費地および候補地では20%を越していて、既設地を大きく上回っているが、原子力発電所といった具体的対象を身近に実感できるかどうかが、意見表明に影響を与えているといえよう。(表1参照)
表1 今後の原子力発電の開発に対する意識 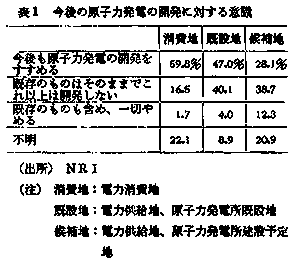 つぎに、電力消費地において近隣(自宅から5km以内)での原子力発電建設に対する賛否を尋ねると、賛成(強いていえば賛成も含む)が28%、反対(強いていえば反対を含む)が60%、不明が11%という結果がみられ、前述の開発推進への肯定的意見と一
変している。(表2参照)ここに電力消費地における原子力発電の推進に対する総論賛成・各論反対の構造がはっきりみられる。そして近隣での原子力発電所建設反対の理由として、原子力発電の技術上の安全が確認されていないことを挙げている者が多く、また、とくに理由はないが、なんとなく不安を感じて反対している者も15%いる。なお、賛成理由としては、エネルギー不足への対処や原子力以外の代替エネルギーの開発が期待できないことなどが挙げられている。(表3参照)
表2 近隣(自宅から5キロ以内)での原子力発電建設への賛否 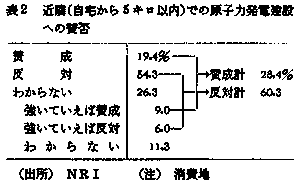 表3 近隣での原子力発電建設の賛否理由 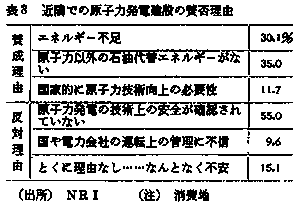 また、原子力発電に対する受容性について、一般市民の意見を総合すると次のような傾向がみられる。すなわち、「我国におけるエネルギー問題は重大であり、代替エネルギーの開発が必要であるが、原子力発電は技術的安全性が確認されていないため不安である。そして、どんな技術でも完全に安全なものはないのだから、ゆっくり時間をかけ地元の完全な了解をとりながら決めていくことが重要である」といった考え方が一般市民の意識の中に流れているといえよう。(表4参照)
表4 原子力発電に対する基本意識 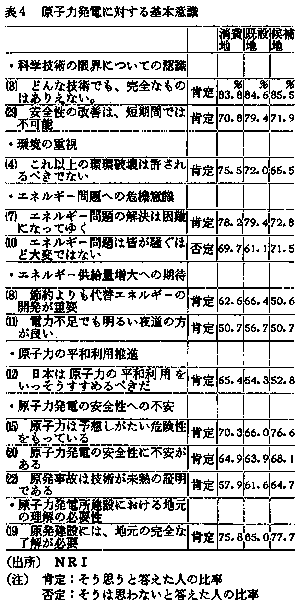 2. 原子力発電に対する一般市民の態度構造:好意者・非好意者の特徴
一般市民の原子力発電に対する意識、とくに受容性をより深く、構造的にとらえるために、市民アンケート調査におけるいくつかの意見質問を用いて原子力発電に対する態度(好意度)をはかる尺度を設定した。そこで最も好意度の強い人々と非好意度の強い人々をとらえ、それぞれ好意者、非好意者と名付け、それらの特徴を、社会経済属性、生活構造・行動、生活意識、原子力に関する知識量等の違いから構造的に分析した。これによって、原子力発電に対する一般市民の態度構造(好意度・非好意度)が何によって違ってくるのかを探る最初の手がかりとなる。 原子力発電に対する好意者像を社会経済属性面からみると、中高年の男性で、職業は商工サービス業や事務、管理職、学歴が高く、年収も比較的高いという人が多いといえる。非好意者は、このような特定の属性にまとまっているのではなく、年令の若い人、労務職、専業主婦などが混在している。 次に、好意者・非好意者の生活構造・行動面の特徴をみると、好意者は新聞閲読時間が長く、現在居住地での居住年数も長いということがいえる。また、エネルギー消費量も既設地を除くと好意者の方が多くなっている。 生活意識面では、好意者は、生活における態度が革新的で、新しい技術に対する受容性に富んでいて、エネルギーに関する危機意識をもっている一方、非好意者は、生活態度は保守的で、他人に追随的であり、エネルギー危機意識も薄い。 このような結果から判断すると、好意者においては原子力発電の推進に対して、自分なりの理由をもって積極的賛成という人が多いのに対して、非好意者においては、はっきりとした理由のないまま、なんとなく反対している人が多いのではないかと推測される。このことは、市民アンケート調査の意見質問に対して、非好意者において態度を保留する人の割合が大きかったということからも判断される。 以上が、原子力発電に対する好意者、非好意者の概観であるが、それは地域によって多少色合いが異なっている。東京、大阪といった電力消費地においては、今まで述べてきた両者の特徴が、最もよくあらわれている。そこでは、電力消費者としての意識が強いため、電力供給の安定という観点から原子力発電所建設問題を考える人が多く、非好意者の多くは、エネルギー問題にはあまりはっきりした意見をもっておらず、原子力発電に対してあまり具体的な理由をもたず、情緒的に反対する傾向がみられる。 原子力発電所既設地では、すでに原子力発電所が現実に稼動しており、殆んどの住民が、原子力発電所の見学などの経験をもつなどにより原子力発電所の問題を身近なものとして認識している。そして、現実には、原子力発電所の建設が地域に役立ったという感じをもった人が多くみられる。その結果、東京・大阪の好意者にみられた生活意識において革新的な人は少なく、「身近な人たちとなごやかな生活を送る」ことを望み、「地域社会は自分の生活のよりどころ」と考えるような、やや他人に追随的で、地域のなかでの争いを好まないような人々も好意的な態度をもつようになっているのではないかと考えられる。 原子力発電所建設候補地では、他の地域と比べて非好意者の特徴が明確にはあらわれてはいない。その理由としては、他の地域では原子力発電に対して消極的反対の人が非好意者において多かったのに対し、候補地では、原子力発電が生活の利害に直接かかわる問題であるため、積極反対の人も多く混在しているからである。非好意者を職業でとらえた場合、他の地域でも共通にみられた専業主婦のほかに、漁業権保障などの観点から反対運動を行っている農林漁業者が多くみられ、非好意者にも属性的に2つのグループがあることがわかる。また、好意者の職業としては、商工サービス業、労務職といった、発電所建設工事などから利益を受けやすいものがみられるなど、候補地においては、各人の利害関係によって原子力発電に対する態度が決定される傾向の強いことがうかがわれる。(以上表5参照)
表5 原子力発電に対する好意者・非行為者の特徴 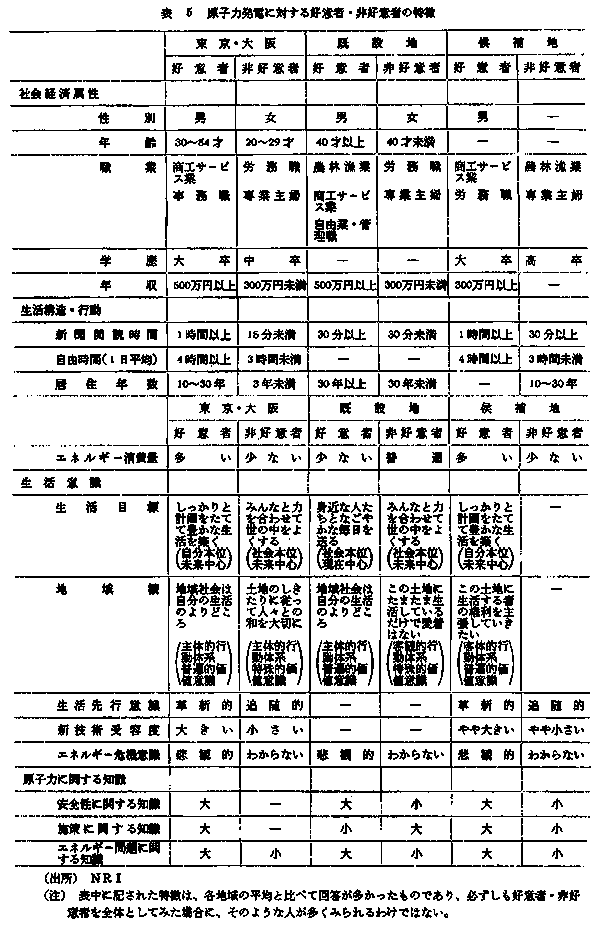 3. 原子力発電に対する態度形成要因と態度変容
原子力発電に対する態度形成要因としては、候補地でみられた原子力発電所建設に伴う各個人の利害をはじめとして、数多くの要因があり、それが複綜しているが、本質をさぐっていくと「代替エネルギー開発の必要意識」と「原子力発電の安全性に対する不安意識」の2つに絞ることができる。そして、好意者は前者を、非好意者は後者の方をより大きく意識している。「節約よりも代替エネルギー開発が必要」という意見に対し、好意者では東京・大阪で70.1%、既設地で70.6%、候補地で61.7%が肯定しているのに対し、非好意者においてはそれぞれ57.3%、62.9%、33.3%となっている。逆に、「原子力発電の安全性に不安がある」という人は、好意者においてはそれぞれ49.3%、50.7%、55.9%であるのに対し、非好意者では85.9%、77.4%、83.4%となっている。 好意者において代替エネルギー開発の必要性の方が強く意識されている理由としては、①社会問題に対する関心が強く、エネルギー問題に関しては強い危機意識をもっていること、②安全性に対する不安を多少感じていても、一般的に科学技術の進歩に楽観的な見通しをもっていること、③原子力発電の仕組みや、安全対策などに対する知識が豊富であることなどがあげられる。 非好意者において原子力発電の安全性に対する不安意識の方が大きい理由としては、①原子力発電の安全性に対する知識が比較的乏しいこと、②安全性に関する情報を主として提供している国や電力会社に対して不信感をもつ人が多く、原子力発電に関する情報を家族、友人や地元の人などからの話といったクチコミから得ている人が多いこと、③科学技術の進歩に対し否定的な考えをもっている人が多いことなどがあげられる。 好意者、非好意者の意識を比較してみると、好意者においては原子力発電の安全性を知識、情報によって判断する傾向がみられるのに対し、非好意者は多分に感情的にとらえていることがわかる。おそらく、非好意者においては、原子力発電の実体がはっきりつかめないまま、安全性への不安だけが先行していると考えられる。このことは、原子力発電所の見学会への参加などその実体が具体的につかみやすい既設地において、安全性に不安をもつ人の割合が候補地よりも少ないことにあらわれている(図1参照)。 以上のように、好意者においては安全性への不安よりエネルギー危機意識の方が強いため、代替エネルギー開発=原子力発電の推進という論理が展開されるが、非好意者の場合、原子力発電は安全性の面で代替エネルギーとしては不適格であり、エネルギー問題に関しては、原子力以外の代替エネルギーの開発をすすめるべきだという論理展開がみられる。しかし、非好意者においては、比較的多くの人が具体的な代替案をもっておらず、候補地のように、単に原子力発電に対し否定的態度をとるだけでは不充分で、具体的な代替案の提示が求められる状況にあるところでは、非好意者においても原子力が代替エネルギーとしてふさわしいと認める人の割合が消費地や既設地に比べて高くなっている。 図-1 原子力発電に対する意識構造(態度形成) 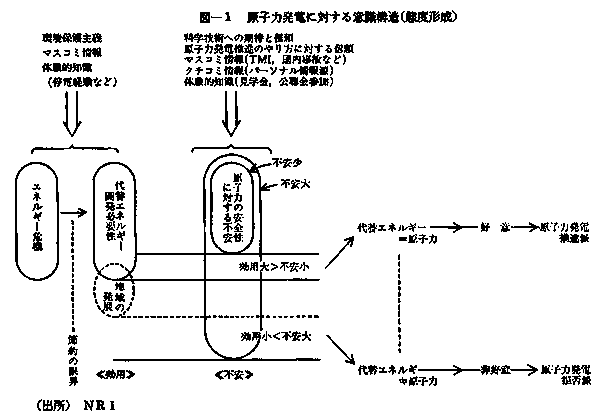 候補地にみられるように、エネルギー問題に対する具体的な対応策が強く求められる状況では、代替エネルギー=原子力という図式を認める人が多くなる。そして、候補地においては今までに述べてきたような理由から、それが原子力発電に対する態度に必ずしも結びついていないが、一般的には、代替エネルギー=原子力と考える人ほど原子力発電に対して好意的な態度をとっている。したがって、エネルギー危機意識が高まるにつれ、今まで原子力発電の推進に反対していた人が、賛成に態度を変えることがある。実際、最近5年ぐらいの間に原子力発電の推進に反対の立場から賛成の立場に変わった人にその理由を聞いてみると、約3分の2の人が、「いままでのような石油の輸入が困難になったから」と、エネルギー問題の深刻化を理由としてあげている。このような人々は、学歴が相対的に高く、年収も高い。つまり、生活水準は比較的高く、エネルギー・資源問題に広く関心をもっている人が多いといえよう。 これと対照的に、態度が反対から賛成に転化した理由として「原子力発電に関する安全性を理解する機会があったから」と答えた人はわずか1割程度であり、安全性に対する理解を深めるという面では、あまり効果のある施策がとられていなかったことを示している。ただし、注目すべきことは、これら態度が好意に転化した人々は、原子力発電の安全性を理解する機会はあまりなかったとしながらも、それに関する知識は比較的高いということである。つまり、単に安全性に関する知識を付与すること以上に、そのような知識が説得力をもつ形で人々に理解されるような情報提供がなされなかったということである。 従って好意者においては、安全性を充分に理解していない人でも、それに関する情報提供者に対する信頼をもつことにより、あまり大きな不安を感じないことが多いとの調査結果からみて、国や電力会社による原子力発電推進の方法に不満をもっている人が多く、安全性に関する情報提供がなされても、それが直接態度を変化(好意化)させるものにはなりにくいため、国や電力会社は、より具体的な安全性に関する情報提供を行う必要がある。 結 語
原子力発電に対する一般市民の受容性は、代替エネルギー開発の必要意識の強さと原子力発電の安全性に対する不安意識の強さによって決まってくる。これまでは、エネルギー危機を背景に原子力発電の受容性を高める代替エネルギー開発の必要意識が多くの人々に醸成されてきたといえよう。しかし、原子力発電の安全性に対する不安を軽減・解消するための、説得力のある施策や情報提供は少なかったといえよう。したがって、今後は国、地方自治体や電力会社は一般市民との信頼関係を築きながら、原子力発電の安全性に関する、一般市民の納得のいく具体的で、解りやすい、施策や情報提供を行うことに今迄以上に努力すべきである。勿論、エネルギー資源の無駄使いをなくす節約・省資源キャンペーンや代替エネルギー開発の必要性の醸成にも、同時に努力していくことは当然であろう。 なお、今回の調査はサンプル数や方法論上の制約があったため、より深く意識の深層に迫った分析を展開することが困難であった。したがって、今後はより制約の少ない大規模で、総合的調査が必要となろう。 | ||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |