| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
RCA(アジア地域原子力協力協定)活動の意義と展望 原子力局調査国際協力課
藤井 三樹夫
1 RCAの発足
RCAはThe Regional Cooperative Agreement for Research, Development and Training Related to Nuclear Science and Technologyを略したものである。 1972年国際原子力機関(International Atomic Energy Agency, IAEA)は、アジア・太平洋・極東地域の発展途上国における原子力平和利用の促進をはかるため、その地域の発展途上国自身の発意に基づいて、当初5カ年の予定で多国間地域協力協定であるRCAを発足させた。 しかし、その活動は必ずしも順調に進まず5カ年では十分に目的が達成されなかったので、IAEAは1977年に5年間の延長を決定した。 その後、アジア・太平洋地域の先進国の1つであるオーストラリアが協定に加盟し、さらに1978年には,本地域における最先進国である日本の加盟が実現し、さらに、RCA活動をコーディネートするIAEAの研究およびアイソトープ局のトップである事務局次長にわが国の垣花東工大教授(当時)が就任するに至って、本協定が実質的に動きだしたのである。延長された協定の締約国は現在オーストラリア、バングラディシュ、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、スリランカ、タイ及び日本の12カ国である。 2 RCA活動の目的
RCA活動の目的を要約するなら、アジア、太平洋地域における原子力技術の開発、移転を通じて、加盟国相互間の経済的福祉を増大することである。RCA活動は現在、アジア・太平洋地域のみを対象とした地域協力であるが、IAEAは今後この活動を中東、アフリカ、ラテンアメリカ等に拡大することを検討している。 表1 RCA活動の推移と我が国との関係 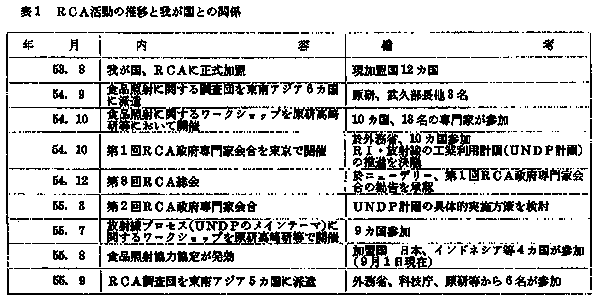 原子力の平和利用には大別すれば、エネルギー利用とラジオアイソトープ(RI)・放射線利用とがあり、エネルギー利用はもちろん石油に代るものとしてきわめて重要である。しかし、核拡散というデリケートな問題がからんでいる。一方、RI・放射線利用については、食糧、化学工業、医療、農業などの生活に密着した分野で利用されており、しかも核拡散の怖れが全くないものである。発展途上国が直面している重要な問題は食糧問題であり、そして工業化の促進による生活の近代化である。そこでRCAに基づく活動の当面の重点は、食糧、農業および工業を近代化するためのRI・放射線利用におかれることになったのである。 3 RCA活動の内容
RCA活動の枠組の中で現在進行中及び計画中のプロジェクトの概要を次に述べる。 1) 水牛の飼育改善へのアイソトープの利用
水牛は東南アジアにおいては重要な農業用の労働力であると同時に、ミルク、肉は重要な食料であるため、その効率的な飼育、改良が必要とされている。 2) 放射線照射による豆類の品種改良
東南アジアでは重要な蛋白源である豆類の品種改良によって、その収穫量を高めることは重要な課題とされている。 3) 医療に関連した環境科学への放射線利用
医療器具の放射線滅菌、放射線によるワクチンの弱毒化などがある。医療具器の滅菌については、これまですでにUNDP(国連開発計画)のデモンストレーション・プラントがインドおよび韓国に設置された。今後さらに、韓国のプラントをRCAの地域センターとして放射線滅菌の技術の普及に役立てることとしている。 4) 放射線計測器の保守
発展途上国にRI・放射線利用技術を定着させるためには、それに用いられる種々の計測器が正しく使用され、保守されることが必要であるが、現実には多くの機器が故障したままで放置されている。このような問題を解決するために研修コース、専門家の派遣等を通じて、改善して行くこととしている。 5) 水理学および堆積学へのRIの利用
港湾の建設等にはアイソトープを利用した水理学の技術が重要である。 6) 放射線利用による食品保存
開発途上国において、緊急に解決しなければならない問題の1つとして食糧事情の改善があげられる。 そのため、本RCA活動の中でも放射線を利用した魚類の保存計画が当初から優先的にとりあげられ、東南アジア諸国で研究開発が進められてきた。1昨年、我が国がRCAに正式加盟した直後、まず最初に協力依頼があったのも本プロジェクトであった。そのため、我が国は、現地の実情とニーズを把握するため、昨年9月に、東南アジア6カ国に調査団を派遣するとともに、さらにこれに引き続いて、10月から約1カ月にわたり、原研高崎研究所を中心にして、ワークショップを開催し、今後の協力のあり方を検討してきた。 これら一連の準備作業を経て、食品照射に関する一般的、基礎的技術の研究及び修得を内容とする食品照射協力協定が、本年8月末に正式に発足した。3年間、23万6千ドルの本プロジェクトに対して我が国は、資金の拠出、専門家の受入れ、派遣等を通じて、参加協力することとなった。 7) アイソトープ放射線の工業利用計画
RCA加盟の発展途上国にとっては、自国の工業を確立することが、強い願望である。IAEAはその要望を受けて、一昨年、これらの国に長期の調査団を派遣し、RI・放射線の工業利用の必要性を調べた。その結果に基づき、総額約800万ドルに達する技術移転計画を作成し、500万ドルをUNDPに、300万ドルを加盟国に対して拠出するよう要請している。 この計画の内容は表2に示す通りであり、6つのプロジェクトからなっている。いづれも発展途上国の工業化には、きわめて重要なものと考えられる。 昨年10月15日に東京で開催された第1回RCA政府専門家会合では、本プロジェクトに対するUNDPの優先的援助を要請する決議がなされるなど、加盟国の本計画に対する期待は非常に大きい。 UNDPは本計画に対し専門家によるレビュー等を行なった結果、80年度は主に調査費として386,000ドルを認可した。IAEAとしてはRCA加盟国の協力を得て、更に詳細な調査を行ない、それに基づいて、より具体約な技術移転計画を作成し、UNDPに提出し、今後5カ年間の資金の拠出の最終決定を得たい考えである。 本UNDP計画においては、日本は先進国として強く指導的役割を求められており、資金援助の他専門家派遣、研修生受入れ、技術供与等の指導が期待されている。 表2 アイソトープ・放射線の工業利用計画 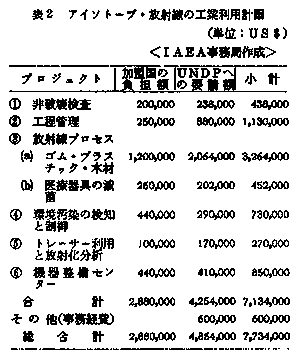 このようなことから、本年7月、わが国は東京においてUNDP計画を具体的に検討するため、放射性工業利用に関するワークショップを開催し、9カ国から専門家を集め、2週間にわたって討論を行ない計画をつめた。 さらに10月には、シンガポールにおける非破壊検査トレーニングコース、タイおよびインドでの製紙および製鉄工業における放射線厚み計の設置に関するワーキンググループ会合、さらに11月の日本における放射線利用の専門家会合など、本計画を推進するための会合やトレーニングコースが着々と計画されている。 8) RI・放射線の医学利用
本プロジェクトは現在、我が国が中心となって、計画を立案しているものである。本計画が実現されるとRI・放射線利用のテーマとして、農業、工業、医療の3分野がカバーされることになる。 4 今後の展望
上述のように、既にスタートし、また具体的計画が立案されているテーマの大部分は、RI・放射線の利用を中心としたものが中心となっているが、今後、RCAの活動分野を研究炉を利用した、研究者の養成訓練等の分野に拡大して行くことが検討されている。 一方、将来、本RCA活動が活発化してくるに伴い、各分野の協力を統轄する、「アジア地域協力センター」の必要性が検討されており、そのための「検討グループ」が昨年設立されたが、我が国は本年9月8日から約10日間にわたり本構想に関する各国のニーズと現状を把握するため、東南アジア各国に調査団を派遣した。 5 結び
以上、RCA活動の現状と展望を我が国との関係が深い部分を中心に述べてきた。東南アジアの各加盟国からは、原子力分野での最先進国である我が国に対して、有形、無形の協力を要請する声は非常に強い。 しかし、本活動が真に実効性のあるものとして、進展して行くためには、開発途上国における原子力技術導入の必要性に関する経済的、社会的評価検討は、受領国側に委ねるにしろ、我が国としては、先方の要望と技術的受入基盤を慎重に検討しつつ、本活動をstep by stepに進めて行く必要があると思われる。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |