| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
昭和53年原子力年報(総論) はしがき
「昭和53年原子力年報」は、昭和53年12月19日の原子力委員会において決定され、同12月22日の閣議に提出された。 本年報は、総論、各論、資料編から構成されている。 総論
第1章 原子力委員会の歩みと新体制の発足
我が国の原子力研究開発利用は、昭和31年1月1日に施行された原子力基本法に基づいて、平和の目的に限り、民主、自主、公開の原則の下で進められてきたところである。 原子力委員会は、この基本法の下で原子力の研究、開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的運営を図るために設置され、以来22年余の間、通算5回にわたる原子力研究開発利用に関する長期計画(以下、「長期計画」と略す。)の策定をはじめ、毎年度の予算の配分計画の調整や原子力施設の安全審査に至るまで、広般な任務を遂行し、名実ともに、我が国の原子力研究開発利用の中枢としての機能を果たしてきたところである。 このたび、従来の原子力委員会が全面的に改組され、新たに安全確保に係る事項を所掌する原子力安全委員会が設けられ、原子力委員会も平和利用の担保と原子力政策の総合的、計画的推進を中心とするものに、その面目を一新するに至った。 この時に当たり、従来の原子力委員会を中心とした22年余の活動を振り返ることは、今後の原子力の研究開発利用を進めるに当たって有意義であると考える。 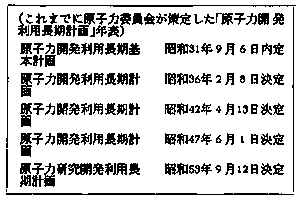 1 原子力基本法の成立と原子力委員会の設立
我が国における原子力研究開発経費は、原子力平和利用の推進に対する世界的な認識の拡大を受けて、昭和29年度予算に初めて計上された。 この予算化を契機として、我が国における原子力の研究開発利用は、平和利用に徹していくとの従来からの趣旨を明文化するとともに、これを監視し、かつ、巨額な経費を要する原子力研究開発利用を総合的、計画的に推進するための体制を整備する必要性が痛感された。原子力基本法及び原子力委員会設置法は、このような強い要請を受け、我が国の原子力研究開発利用を平和目的に限り民主、自主、公開の原則の下に推進することを基本理念として、昭和30年12月19日、議員立法により、超党派的な支持の下に成立し、原子力委員会が誕生した。 2 原子力委員会の歩み
原子力委員会が行った決定や推進してきた施策等は種々の紆余曲折を経てきており、今日からみれば、全てが万全であったとは限らず、反省すべき点もみられる。しかし当然のことながら、この22年余の間を通じて、周辺環境や周辺地域住民に影響を与えるような原子力施設の事故は発生しておらず、また、近年の発電分野における原子力利用の本格化、自主技術開発の進展など、総じてみれば、ほぼ、当初の国民の期待に応えうる役割を果たしてきたと考える。 これらの施策のうち、特に、①発電用原子炉の導入と原子力発電規模、②核燃料サイクル関連施策、③動力炉等自主技術開発及び④安全確保のための施策の今日なお重要な4つの大きな課題についての歩みは、次のとおりであった。 (1) 発電用原子炉の導入と原子力発電規模
原子力委員会は、その発足と同時に直ちに原子力の研究開発利用についての海外の状況の調査を行った。その結果、原子力発電は実用化の段階に入りつつあるとの判断に立って、我が国への発電用原子炉の導入に関する検討を進めた。この検討を踏まえ、昭和32年12月、「発電用原子炉開発のための長期計画」を策定し、発電用の第1号原子炉としては、英国からコールダー・ホール改良型炉を導入することを決定した。 しかし、その後の海外、特に米国における原子力開発状況の進展により、2号炉以降の発電用原子炉は、経済性、将来性の観点から、米国で開発された軽水炉が適当と考えられるようになった。このため、昭和36年2月の長期計画の決定に当たっては、このような情勢を踏まえ、なるべく早い機会に海外へ調査団を派遣し、その選定に慎重を期しつつ、建設の準備を進めることとした。これらの調査の結果、軽水炉を米国から導入し、これを発電用の原子炉の主流としていくこととした。また、軽水炉の導入に当たっては、昭和42年の改訂された長期計画の方針に沿って、国産化を推進し、原子力産業基盤の確立等を図ってきた。 今日、軽水炉は、世界で最も一般的に広く利用され、また、その設計、運転に至る諸技術データが蓄積完備し、かつ安全研究の進んだ信頼度の高い炉型とされるに至っており、その導入は適切であったと考える。しかし、高度な、かつ、新しい総合的な科学技術を基盤とする原子力の特殊な事情を考えれば、軽水炉導入の初期の段階から安全研究をより積極的に進めた方が良かったのではないかと認められる点もあり、また、まだ我が国では輸出産業となっていない現状を考えれば、国内における技術基盤の強化、あるいは我が国により一層適した炉型の自主的な研究開発に早くから取り組むなど、他の一般の技術導入とは異なる配慮をすることがより有効ではなかったかとも思われるが、今日では国内における安全研究や安全性実証試験が進み、改良・標準化など軽水炉定着化の努力も進むなど我が国として必要な自主的技術の確立が達成されつつある。 一方、これらの発電用原子炉による原子力発電の規模の見通しについては、その10~20年先を見通した発電規模を検討し、長期計画の改訂の毎に、これを見通し、必要な核燃料サイクル関連施策、及び研究開発計画との整合性をとってきている。 例えば、昭和50年度の原子力発電規模については、昭和36年の長期計画では昭和45年頃の100万キロワットの規模と昭和55年頃の600ないし850万キロワットの規模との中間になるであろうと見通したが、昭和42年の改訂では、これを600万キロワットと見込み、実際には、660万キロワットが達成された。 また、昭和60年度の原子力発電規模については、昭和42年に、3,000ないし4,000万キロワットと見通したものの、その後の高度経済成長に伴うエネルギー需要の急速な伸びに応えるため、昭和47年の長期計画では「6,000万キロワット程度を原子力発電で賄うことが要請されている」と、上向きの修正をすることとなった。しかし、この見通しについては、その後の立地の難航等の傾向も踏まえ、昭和53年9月、新長期計画の策定に当たっては、再度の修正を行った。今後は、この長期計画に基づき、3,300万キロワットの規模を大きな遅れなく実現させるよう、政府及び民間での最大限の努力と協力が望まれている。 (2) 核燃料サイクル関連施策
原子力委員会は、我が国における核燃料サイクル関連施策については、一貫して長期的に安定な核燃料の確保を図るとの観点から、その供給確保及び関連する研究開発等を推進してきた。このように施策の中で、昭和30年代における各分野の研究開発と体制整備の進展、特に濃縮技術の開発、使用済燃料再処理施設の建設準備の進展等の情勢を踏まえ、昭和42年の長期計画においては、我が国に適した総合的な核燃料サイクルの確立を図る方針を明らかにした。更に、昭和47年の長期計画改訂に当たっては、原子力発電規模の見通しの増大に伴ってより大量の核燃料の安定的供給が必要になったことを背景として、必要な核燃料を安定的に確保し、その有効利用を図っていくためには、経済的でかつ我が国としての自主性を確保できるような核燃料サイクルを確立していくことが必要なことを強調した。 これらの施策の積み重ねにより、今日では昭和65年頃までに必要とする天然ウラン量、濃縮役務量及び再処理役務量を確保できている。また、米国との再処理交渉や国際核燃料サイクル評価(INFCE)等の場でも、実績の積み重ねの上に立って我が国の自主性に基づいた積極的な主張を展開することができるようになっている。 これらの施策を、更に各分野別に振り返ってみると次のとおりである。 〔核燃料所有方式〕
核燃料サイクル全体を考える上で、核燃料物質の所有方式のあり方は核物質管理上重要な問題である。 原子力委員会は、諸外国のこれに関する事情等をも勘案し、昭和33年4月、「内外の諸条件が整うに従い、民間の所有を考慮するが、暫らくの間は原則として民間所有を認めない」との方針を決定した。 その後、国際原子力機関による保障措置が制定されるなど対外的諸条件も明確になり、国内的にも原子力損害賠償制度の確立、原子炉等規制法の改正による国内規制措置の整備等が進んだため、昭和36年9月、特殊核物質(濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン-233)以外の核燃料物質(天然ウラン等)の民間所有を認めることとし、更に、国内管理体系の一層の整備、濃縮ウランの提供国である米国の同意等を踏まえ、昭和43年7月、これらの特殊核物質についても民間所有を認めることとした。 このように我が国においては、核燃料物質は、民間所有を原則としつつ、原子炉等規制法等の法令に基づいて、国による厳しい監督の下に置いている。 〔天然ウラン確保〕
原子力委員会は、その発足の当初において核燃料は極力国内資源に依存し、やむを得ない場合の不足分のみを海外に依存するとの方針を打ち出し、昭和33年の「核燃料開発に関する考え方」においても、原子燃料公社を中心にまず国内探鉱を推進することとした。しかし、国内探鉱が進むにつれ、国内資源では拡大する核燃料需要を賄えないことが明らかとなり、昭和42年の長期計画の改訂に当たり、供給の大部分は海外に依存せざるを得ないこと、そのため、海外ウラン資源の低廉かつ安定な供給を確保するなどの観点から、必要の都度の購入、長期契約による購入、開発輸入等を適宜組み合わせる必要があるとの考えを示した。 また、昭和47年の長期計画では、将来の年間所要量の1/3を開発輸入とすることを目途に、海外ウラン探鉱を促進するとの方針を示した。これらの方針を踏まえつつ調査探鉱・長期購入契約、開発輸入が進められており、既に昭和60年代後半までの必要量は手当済みとなっている。 〔製錬・加工〕
ウランの製錬及び核燃料への加工については、当初よりその企業化は民間で行うとの考え方の下に進めることとし、この間、軽水炉の導入に伴い、当初の天然ウラン燃料から濃縮ウラン燃料への変更はあったものの、今日では既に核燃料加工分野は、発業として成立するまでに成長している。また、昭和33年の「核燃料開発に対する考え方」の中で、原子燃料公社で技術開発を進めることとした一貫製錬技術は、今日では動力炉・核燃料開発事業団の一貫製錬転換法として世界的にも高い評価を受けるまでになった。 〔ウラン濃縮〕
我が国における濃縮ウランの確保は、昭和43年の長期計画により、自主技術開発が進展するまでの間は、海外からの輸入に頼るとの方針の下で、米国との原子力協力協定の改訂を進めることとした。この結果、昭和43年及び昭和48年の2回にわたる協定改訂を通じ、現在では約5,100万キロワットの原子力発電所のために必要な濃縮役務を米国政府から受ける長期契約が結ばれている。更に、供給の多様化を図るとの観点から、昭和49年には、フランスを中心とした合弁会社であるユーロディフ社とも、毎年1千トンSWU(約900万キロワット相当)の濃縮役務を10年間受ける契約が、電気事業者によって結ばれた。 我が国におけるウラン濃縮技術については、基礎研究段階から広汎な方法について研究開発を進めた。昭和36年の長期計画の策定に際しては、軽水炉の導入が見込まれるようになったことを背景に、ウラン濃縮技術の開発を推進することとし、それまで理化学研究において進めてきた遠心分離法が最も有利とする見方を踏まえつつ、その研究開発を原子燃料公社に移管することとした。この研究開発は、昭和43年に設立された動力炉・核燃料開発事業団に引き継がれ推進された。また、昭和47年には、ガス拡散法との最終的な比較検討を行った結果、遠心分離法が、国産工場に適しているとの結論が得られ、昭和47年の長期計画では、昭和65年頃までの必要量の一部を国産化するとの目標をたてた。今日では遠心分離機の性能も世界的にもそん色のない水準に達し、自主技術による国産工場によって新規需要の相当部分を賄うという目標の達成にも明るい見通しが得られている。 〔再処理〕
使用済燃料の再処理については、昭和31年の長期計画により、極力国内技術によることとするとの方針を出していたが、その具体的な開発計画を検討した結果、昭和33年の「核燃料開発に対する考え方」の中で、当面は海外において再処理を行うとの考え方を明らかにした。 この考え方に基づき、最初の商業用発電所である日本原子力発電株式会社東海原子力発電所からの天然ウラン使用済燃料をはじめ、その後の軽水型原子力発電所から発生する濃縮ウラン使用済燃料についても、英国及びフランスと再処理の委託契約を行ってきた。 一方、国内における研究開発は、日本原子力研究所の協力を受けて原子燃料公社が行うこととし、昭和36年の長期計画では、昭和45年頃までにパイロットプラントを建設することとして開発を進めるとの方針を示した。その開発は若干遅延したが、同公社の業務を引き継いだ動力炉・核燃料開発事業団によって積極的に推進された結果、昭和52年には、試験運転を開始することとなった。 なお、将来の再処理事業の実施主体については、核燃料物質の民間所有を認めないとの考え方等に沿って、原子燃料公社が行うとの方針を当初とってきたが、その後の再処理技術の進展、民間所有を認めるとの決定等に伴い、再処理についても将来は民間企業で行うとの考え方をとるに至った。 〔放射性廃棄物対策〕
原子力委員会は、昭和31年の長期計画の中で、日本原子力研究所において、再処理に伴う放射性廃棄物の分離に関する研究に着手せしめることとした。また、昭和33年の「核燃料開発に対する考え方」及び昭和36年の長期計画において、再処理の事業化に備えた高レベル放射性廃棄物の処理方法に関する研究及びアイソトープ利用や発電分野等での原子力利用の拡大に伴う廃棄物の増加に備えた低レベル放射性廃棄物処理の研究を推進すべきことを決定した。更に、昭和42年の長期計画の改訂に当たっては、将来の放射性廃棄物の増大に対処するため環境の汚染を引き起こさないよう、適切な処理分技術の開発を動力炉・核燃料開発事業団で一層積極的に推進すべきことを決定した。 また、昭和47年の長期計画においては、低レベル放射性廃棄物の海洋投棄の実施方針を明らかにするとともに、実情に即した法令整備を行うべきことを指摘した。 原子力委員会は、昭和51年、「放射性廃棄物の対策について」と題する方針を決定したが、その中では、放射性廃棄物に関しての処理処分の基本的考え方、対策の目標、その推進方策等についての基本方針を明らかにしている。 原子力委員会としては、これらの施策を通じて、鋭意、研究開発を推進し、将来の最終的処分に備えてきたところであるが、今後更に一層の努力が必要と考えている。 (3) 動力炉等自主技術開発
〔発電用原子炉〕
原子力委員会は、昭和31年の長期計画の中で、原子炉技術についてはとりあえず海外の技術を吸収することによって速やかに我が国の技術水準の向上を図ることとし、将来的には動力炉を国産することを目標として研究開発を進めることを明らかにした。この場合、質源に乏しい我が国が目標とすべき国産動力炉としては増殖型動力炉が適しているとの考え方を示した。引き続きその具体化について検討を進め、昭和32年12月、「発電用原子炉開発のための長期計画」を決定し、まず、軽水炉技術の習得を目指した動力試験炉(JPDR)を日本原子力研究所に建設することとし、また、これに続く増殖型動力炉の研究開発については、熱中性子型及び高速中性子型の両型を並行的に進めることの必要性を指摘した。 以上の方針に基づき、日本原子力研究所においてはJPDRの建設、運転が開始されるとともに、各種炉型についての基礎研究が進められたが昭和36年の長期計画では当時の内外の原子力開発事情を踏まえた動力炉の研究開発における各種炉型の評価と優先度を位置付けた。同長期建画に基づき、日本原子力研究所ではJPDRを用いての軽水炉技術の習得に努めるとともに高温ガス炉を目標とした半均質炉、熱中性子増殖炉を目標とした水性均質炉をはじめ、重水減速炉、高速増殖炉など、幅広い基礎的研究が進められた。 これからの研究開発を支援するため、JRR-1に引き続きJRR-2、JRR-3、JRR-4、材料試験炉(JMTR)などの試験研究炉が日本原子力研究所で次々と建設、運転され、自主技術開発の基盤が整備された。 このような研究開発の進展に伴い、増殖型原子炉としては、プルトニウムを燃料とする金属ナトリウム冷却型が最も理想的であり、その実用化のために、一層の研究開発努力を必要とすること及びその実用化には、なお相当の期間を必要とするので、それまでの段階における補完的な炉型としては、転換比が高く、またプルトニウムの有効利用や必要な天然ウラン量の節減効果が期待される重水減速炉が有望なことが次第に明らかになった。 このような研究開発成果を踏まえ、原子力委員会は、昭和41年5月「動力炉開発の基本方針について」を内定し、更に昭和42年3月には、新しい長期計画を策定し、新型動力炉の自主技術による開発を早急に進め、国内の原子力技術の自立を促進する必要があること、そのため、高速増殖炉及び新型転換炉の2種類の炉型の実用化を進め、核燃料の有効利用を図り、軽水炉に続く、発電用原子炉とすることを決定した。 また、国内の関係各界の総力を結集してこの開発を計画的かつ効率的に推進するため、従来の原子燃料公社を発展的に組織替えすることにより新たに動力炉・核燃料開発事業団を設立した。 高速増殖炉及び新型転換炉の両新型動力炉の開発は、動力炉・核燃料開発事業団によって積極的に進められた結果、当初計画からは遅れを生じているものの、高速増殖炉実験炉「常陽」及び新型転換炉原型炉「ふげん」は、既にそれぞれ臨界に達し、両炉とも順調に試験運転を続け、所期の成果を挙げつつある。我が国独自の自主技術によるこれらの新型炉の開発は、その実用化に向けて、次の開発段階に移りつつあり、高速増殖炉については、世界的にも、米国、ソ連をはじめ、フランス、西ドイツ、イギリス等の先進諸国における高速増殖炉開発とほぼ比肩しうる水準に達している。 一方、高温ガス炉については、日本原子力研究所で引き続き研究開発が進められ、昭和47年に改訂した長期計画により、将来の原子力多目的利用に適した炉型として研究開発の促進を図ってきている。 〔原子力船〕
原子力船の開発については、原子力船の実用化時代に備えて、昭和38年、日本原子力船開発事業団を設立し、原子力第一船「むつ」の開発を進めてきたが、昭和49年の出力上昇試験中に遮へいの不備による微量の放射線漏れが発見された。このことが、大きな社会的問題となり、その結果、「むつ」の開発計画が遅れた。これを一つの契機として原子力行政について国民全般の信頼感を揺がしたことは、原子力委員会として遺憾とするところである。「むつ」の開発は、一時停滞したが、佐世保港への回航により、開発が進捗することとなった。今後総点検及び改修を行った上で実験航海等を実施し、所期の目的を達成させることとしている。 (4) 安全確保のための施策
原子力の研究開発利用に当たって、安全性の確保を第一条件とすることは、平和利用に徹することと並ぶ大前提であり、原子力委員会としては、昭和31年の発足以来、一貫してこの基本方針を貫いてきた。 昭和31年の長期計画において、まず、その研究開発利用に伴う危害及び障害の防止等を図るための法律並びに放射線障害の防止等を図るための法律の整備の促進が必要なことを指摘し、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年12月施行)、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」(昭和33年4月施行)の制定を促した。また、「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和37年3月施行)の制定を図った。 これらの法令の整備とあいまって、原子力施設の安全確保から、放射性同位元素や放射線の利用に伴う規制に至るまで、広範な安全施策を進めたが、原子力利用の本格化に備えて昭和42年に策定した長期計画においては、安全対策に関する基本的施策を示し、原子力平和利用の進展に伴う、原子力施設の安全確保、原子力関係作業従事者や周辺住民等一般人に対する放射線防護、そのための安全研究等を一層推進することを明らかにした。 また、「原子炉立地審査指針」、「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針」、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」等の各種指針の整備に努め、原子力施設の安全審査に万全を期すとともに、所要の安全規制を行ってきた。この結果、原子力発電所の運転に伴う故障等の発生は認められるものの原子力施設の周辺環境や周辺住民に影響を及ぼすような事故は、一度も発生していない。 しかしながら、近年の原子力研究開発利用の増大、とりわけ原子力発電の本格化に対応していくためには安全確保のための体制を一層強化することが必要となった。また、「むつ」の放射線漏れの事態も発生したことから、安全規制体制の見直しが「原子力行政懇談会」により行われ、原子力委員会を改組し、新たに原子力安全委員会を設置すること、原子力規制行政を一貫化すること等により原子力安全行政体制を改革強化すべしとの意見が出された。 政府としては、原子力に対する国民の一層の理解と協力を得て、原子力開発を進めていく上で、原子力の安全確保の体制を強化することは不可欠の措置であるとの判断の下に、昭和52年2月、「原子力基本法等の一部を改正する法律案」を第80回国会に提出した。 3 原子力基本法等の改正と新体制の発足
原子力基本法等の一部改正法案は、1年余にわたる審議を経て、昭和53年6月、第84回国会において成立した。この結果、新たに原子力安全委員会が設置され、原子力委員会は、原子力政策のうち、安全規制に関することを除く事項について企画、審議、決定することとされた。また、原子力安全委員会は、原子力政策のうち安全規制に関する事項を企画、審議、決定することとされ、具体的には、安全審査指針の策定等を横断的立場に立って行うほか、国民との積極的な意思の疎通を図るとの観点から公開ヒアリング等を開催して地元関係者の生の声を聴取するなどの施策を実施することとされている。 また、原子力安全委員会の中心的任務である原子力施設の安全規制については、従来の手続を改め、ダブルチェック方式を採用することとされている。これは、行政庁が原子力の研究、開発、利用の推進という立場にもあるため、安全の確保についての不信感を生ずることのないようにするとともに、行政庁の安全規制について、統一的評価を行うためのものであり、例えば原子炉の設置許可については申請を受けた行政庁が責任をもって審査を行い、その結果を原子力安全委員会が更に審査を行うなど、設置許可、設計及び工事方法の認可等の段階で安全確保に万全を期すこととされている。 一方、安全規制行政の一貫化が図られることとなったが、これは従来、原子炉の設置許可は、従来は内閣総理大臣が全ての原子炉につき、一元的に行い、その後の段階の規制は各原子炉の区分によって定められた所管大臣が行っていたものを、各原子炉について設置許可から運転管理に至るまで一貫して、同一の所管大臣が当たることとすべく、原子炉の区分に応じ、①実用発電用原子炉については、通商産業大臣、②実用船用原子炉については運輸大臣、③試験研究用原子炉及び研究開発段階にある原子炉については内閣総理大臣がそれぞれ規制を行うこととしたものである。これにより、原子炉設置者は、設置許可以降の設計工事方法の認可や検査、運転管理等全ての安全規制について同一の所管大臣の規制を受けることとなり、原子炉規制の責任の所在が規制の段階の如何を問わず、明確にされることとなった。 なお、核燃料施設は、従来どおり科学技術庁で一元的に規制される。 第2章 原子力研究開発利用の進展と新長期計画
昭和53年9月、原子力委員会は、新たな長期計画を決定した。 また前章で述べたように、原子力基本法等が改正され10月4日からは従来の原子力委員会が原子力委員会と原子力安全委員会に分離され、新体制が発足することとなった。 今後の我が国の原子力研究開発利用は、これらの新しい長期計画と体制の下で進められることとなるが、本章では、この新しい長期計画の背景となった原子力研究開発利用の進展の状況について、特に昭和54年4月以降の主要な動向を踏まえつつ、明らかにするとともに、新長期計画及び今後に残されている課題についての考え方を示すこととなる。 1 原子力発電
〔原子力発電の本格化とその見通し〕
昭和38年10月に、日本原子力研究所の動力試験炉で初めて試験発電が開始されて以来、我が国の原子力発電の歴史は満15歳を迎えた。この間、我が国における発電分野の原子力利用は急速に拡大しつつあり、昭和52年4月以降も新たに2基、135万キロワットが運転を開始した結果、昭和53年9月末現在、商業用原子力発電所は15基、発電設備容量で約880万キロワットとなり国内総発電設備容量の約8%を占めている。更に、昭和53年中には新たに3基272.4万キロワットが運転を開始する予定となっているので、その総計は18基、約1,150万キロワットに達し、世界第2位の原子力発電国となる。 また、昭和53年度上半期の原子力発電実績は、国内の総発電電力量の13%弱を占めるとともに、真夏期の渇水による水力発電電力量の低下もあって、昭和53年7月及び8月には、原子力発電電力量が初めて水力発電電力量を上廻り、石油に代替するエネルギー源として、我が国のエネルギー供給上欠くべからざる地位を確固たるものとするに至った。 一方、新しい原子力発電所の立地については、昭和52年度以降、国が定める電源開発基本計画に組み入れられた原子力発電所の建設計画は、昭和53年3月に、2基174万キロワット、7月に2基199万キロワットの総計4基、373万キロワットにとどまっており、9月末現在、計画として確定された我が国の原子力発電規模は、33基約2,560万キロワットとなっている。したがって、新しい長期計画で目標とした昭和60年度3,300万キロワット、昭和65年度6,000万キロワットの発電規模を大きな遅れなく達成していくためには、今後数年の間に更に3,500万キロワット相当(30基余)の原子力発電所の立地を進める必要がある。しかしながら、地元の同意が得られなかったり、既に同意が得られたものであっても一部地元住民の反対があったりするために、立地の遅れを招いた例も生じている。 このように原子力発電所の建設は、原子力発電の安全問題や、環境問題に対する地元住民の不安等の諸要因のため、少なからぬ遅延を招いており、今後とも、この傾向は変わらないと見込まれるので立地問題が当面の最大の問題となっている。 我が国の原子力発電の実績と見通し 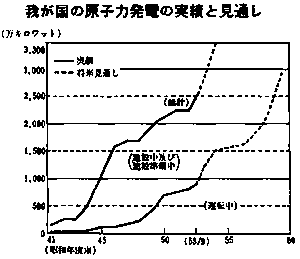 原子力発電の開発の必要性について国民の意識として、最近の調査結果では、賛成が増加しつつあるものの、原子力発電の立地問題に対しては、「居住地及びその周辺への原子力発電所の建設には反対する」との意見が多い。この問題には、単純な安全性に対する不安だけでは処理しきれない面があることも見受けられる。 〔立地対策と地域住民の理解〕
原子力発電所等を建設しようとする場合には、敷地の確保をはじめ、海浜の利用や埋立て、森林地の開発、道路の建設工事等が必要であり、また、地域の経済社会に与える影響も大きいこと等、様々な形での有形無形の地元の協力を必要としている。 これに応えるため、政府においては、昭和49年に成立した電源3法により、電源開発に伴う利益の地元への還元を図り、立地地域の地域振興との調和を図るとともに、その運用の改善を行いつつ、地元住民の福祉の一層の向上を図るべく努めてきている。 また、政府は、昭和52年3月以来、総合エネルギー対策推進閣僚会議を随時開催し、関係方面と密接な連携をとりつつ総合エネルギー対策の推進に関する重要問題について意見調整を行っている。この中で原子力発電所等、電力需給上重要な電源であって、特に、国による積極的な立地対策を進めることが必要と見られる地点を要対策重要電源として、政府自らが先頭に立って、より一層の地元への協力要請等に努めた。その結果、当初合意が得られていなかった地点においても地元における理解が得られ、今後も一層の協力が期待されるようになってきた。 これらの施策のほか、政府は原子力に関する正しい知識の普及啓発、原子力モニター制度による広聴に努めたが、今後とも更に、国民的合意の形成の推進及び地元における公開ヒヤリングの実施等、国と地元との意思の疎通ときめの細かい立地対策の推進のために一層の努力を払う必要があると考えられる。 〔原子力発電所における故障等と設備利用率〕
昭和52年度において、年度当初より、沸とう水型原子力発電所の配管の「ひび」等の故障が発見され、これらの点検、修理のため運転停止期間が長引き、原子力発電所設備利用率は、総平均で41.8%に低下した。 これらの故障は、いずれも、あらかじめ組み込まれている原子力発電所の安全計装機器によって発見され、あるいは法令に定める定期検査時に発見されたものであり、それぞれ入念な原因探求と慎重な補修が行われた。これらは、安全の確保に万全を期するために、いわば予防的な安全策を講じたものであり、周辺環境や住民はもちろん、原子炉本体に直接安全上の影響を及ぼすような性格のものではない。 また、これらの点検、修理等の結果、昭和53年度上半期の設備利用率は、総平均で59.6%と著しい回復を示している。 〔行政訴訟と異議申立て〕
昭和48年以来、原子力発電所の設置許可処分等に対して、地元住民から、行政不服審査法に基づく異議申立てや、司法判断を求める行政訴訟が行われてきたが、行政訴訟では、伊方発電所(一号炉)、同(二号炉増設)、東海第二発電所及び福島第二原子力発電所(一号炉)の4件が現在審理中である。このうち、伊方発電所(一号炉)訴訟については、昭和53年4月25日松山地方裁判所で第一審判決(請求棄却)が下り、これを不服として原告側が控訴し、高松高等裁判所で審理中である。 また、異議申立てについては、柏崎・刈羽原子力発電所及び川内原子力発電所(一号炉)の2件が現在審理中である。 2 核燃料サイクルの確立
昭和52年から昭和53年にかけては、核燃料サイクル分野での従来からの研究開発が実り、我が国の自主技術について大きな自信を得るに至るとともに、それらの研究開発の成果を得て自主的核燃料サイクルの確立のための準備が積極的に進められた。 〔天然ウラン〕
天然ウランについては、我が国の電気事業者はカナダ、フランス、オーストラリア等と長期及び短期の購入契約を締結しているほか、更に、ニジェールにおけるアクータ鉱山からの開発輸入(約2万ショート・トン)が昭和53年から開始された。 我が国を取りまくウラン資源国の動きについては、カナダは核不拡散の観点から、昭和52年以降、対日ウラン禁輸措置をとっていたが、昭和53年1月、日加原子力協力協定改訂交渉が妥結し、輸入が再開されている。また、オーストラリアにおいては、環境問題についてのオーストラリア政府と現地民との話し合いが解決し、ウラン鉱山の開発に目途がつき、我が国への輸入に明るい見通しが得られた。 一方、我が国の海外調査探鉱活動も、動力炉・核燃料開発事業団及び民間企業により活発に進められている。 また、昭和53年4月には、動力炉・核燃料開発事業団において、鉱石から六フッ化ウラン(UF6)への連続工程による一貫製錬転換法のパイロット・プラントの建設が着手された。 アクータ鉱山 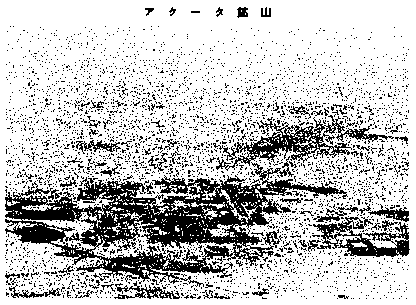 六フッ化ウラン転換施設 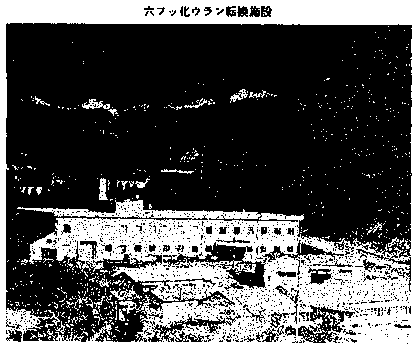 〔ウラン濃縮〕
濃縮ウランについては、日米原子力協力協定に基づき、米国から、順調な供給が続けられている。 また、昭和53年2月、米国から濃縮契約の新方式(調整可能確定量契約方式)を発表したことに伴い、我が国の電気事業者によって、現在の契約(長期確定量契約)を新方式に切り替えると同時に、濃縮ウランの引取りを現在の発電計画に合うようにするための交渉が米国との間で行われている。 一方、従来の研究開発成果を踏まえて、昭和52年8月、動力炉・核燃料開発事業団において、ウラン濃縮パイロット・プラントの建設が着手された。このパイロット・プラントは最終的には、遠心分離機7,000台の規模にすることが計画されており、昭和54年夏には1,000台による部分運転が行われる予定である。また、このパイロット・プラントの建設・運転及び、その後の実証プラントの建設運転経験を経て、その経済性等の確認を行っていけば、国内におけるウラン濃縮の新規需要の相当部分を国内で賄うことが十分に行いうる見通しとなった。 ウラン濃縮高性能機カスケード  〔再処理〕
我が国は、将来第二再処理工場の建設、運転が開始されるまでの間は、再処理の大部分は海外に委託して行う方針としているが、昭和52年9月、我が国の電気事業者とフランスのCOGEMA社との間で、昭和53年5月には、英国核燃料公社との間で新たな再処理委託契約が締結され、これにより、動力炉・核燃料開発事業団東海再処理施設による再処理と従来既に契約済みのものもあわせ、昭和65年頃までの再処理役務はほぼ確保されたといえる。なお、第二再処理工場の建設は、民間企業により実施せしめることとしており、それに必要な措置として、現在原子炉等規制法の改正案を国会に提出中である。 米国との東海再処理施設の運転に関する再処理交渉は、難航の末、昭和52年9月、解決をみた。これにより、国内での再処理が、2年間99トンの枠内で認められることとなり、我が国がエネルギー確保のため自主的核燃料サイクルの確立を目指すとの国の基本姿勢を一層明確にする結果となった。 東海再処理施設は、昭和52年9月から試験運転を開始し、ウラン試験、ホット試験と段階を踏んで、当初は順調に進捗した。しかしながら、昭和53年8月に発生した再処理工程内の蒸発缶内のトラブルのため、昭和53年9月末現在試験運転は停止している状況である。この停止までの段階では、ほぼ初期の予定どおりの成果を得ており、今後の点検、改修及びその後の運転を進めることにより我が国における再処理技術の確立に大きく貢献する見通しである。なお、再処理に伴う放射性物質の放出低減化の研究開発にも一層の努力を傾注した。また、日米再処理交渉における共同決定の際の了解事項に基づき、東海再処理施設の運転試験設備(OTL)によるウラン及びプルトニウムの混合抽出、混合転換の研究開発も進められた。 核燃料再処理施設 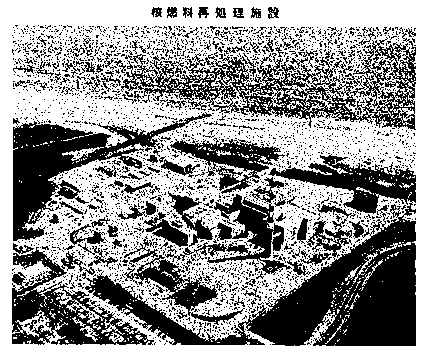 〔放射性廃棄物の処理処分〕
昭和53年6月の原子炉等規制法の一部改正に伴い、放射性廃棄物の廃棄については、原子力施設の事業所内と事業所外の廃棄に区分して規制されることとなった。これに伴い、放射性廃棄物の廃棄の基準を整備する必要があるため、原子力委員会において廃棄に関する技術的な基準の検討を行い、昭和53年8月、「放射性廃棄物の廃棄に関する技術的基準」を決定した。これを受けて、現在、関係省庁において関連規則等の改正が進められている。 低レベル放射性廃棄物については、試験的海洋処分を昭和54年度に実施することを目標に所要の準備が進められているが、その一環として、低レベル放射性廃棄物の固化体を封入した海洋投棄用固化体に関する基準作成及びその固化体の管理法についての試験研究を進めるとともに、投棄船の改造に関する設計研究が進められている。また、陸地処分についても現在調査が進められている。 アルファ廃棄物処理 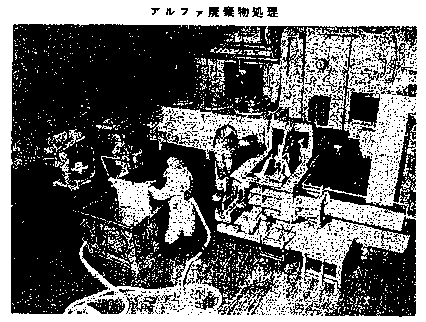 高レベル放射性廃棄物の処理については固化技術開発が動力炉・核燃料開発事業団において、既にコールド試験が実証規模で行われるとともに、群分離、消滅処理等の新処理技術に関する基礎的な研究及び固化体の安全評価試験が日本原子力研究所を中心に進められた。今後、これらの結果を踏まえて、ホット試験、固化及び工学貯蔵プラント実証試験へ進むこととなる。また、高レベル放射性廃棄物の処分に関しては、我が国の地質及び地層の特性を調査するとともに、地層処分時の安全評価試験を実験室規模で進めている。 3 安全研究と軽水炉の改良・標準化
〔安全研究〕
軽水炉の工学的安全研究については、日本原子力研究所を中心として、安全審査の基準、指針等の定量化及び精密化に資するため、反応度事故、冷却材喪失事故(LOCA)、燃料安全及び原子炉の安全構造に関する研究が進められ、またLOCA時の緊急炉心冷却装置の効果の実証(大型再冠水効果実証試験)のため、実物に近い大型モデルの建設が行われた。また、原子炉安全研究の国際協力については、従来からの日米間及び日独間における協力が順調に進展したが、更に、大型再冠水効果実証試験に関する協力の開始について、日本、米国及び西独間で協議が行われている。 環境放射能安全研究については、放射線医学総合研究所を主体として行われているが、同研究所においては、低線量放射線の晩発障害、遺伝障害及び内部被曝による障害に関する研究が重点的に進められた。 大型再冠水効果実証大型モデル 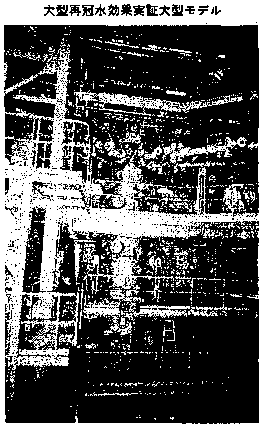 原子炉安全性研究炉(NSRR)炉心 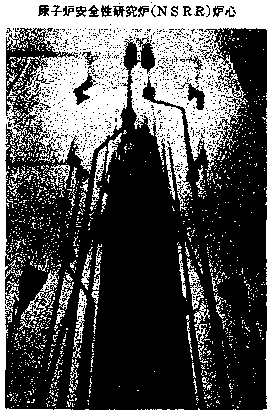 〔軽水炉の改良・標準化〕
軽水炉技術については、初期には、原子炉機器の国産化率は、50%程度であったが、最近の新しい原子力発電所では、95%以上にも達しているものもあり、軽水炉技術の消化習得と国産化は、現在ほぼ達成されつつある。一方、今日軽水炉の安全は、十分に確保されているが、信頼性向上、保守点検作業性の向上等の面からは、なお、改良の余地があり、この観点から、通商産業省においては、昭和50年度から改良・標準化計画が実施されてきた。昭和52年度には、第1次標準プラントの基本仕様をとりまとめ、第1次の改良・標準化計画を終え、現在は、昭和55年度終了を目途として一層の信頼性向上、検査の効率化等を目的とした第2次改良標準化計画が進められている。 4 新型動力炉、核融合等に関する研究開発
〔高速増殖炉〕
動力炉・核燃料開発事業団が開発中の高速増殖炉については、その実験炉である「常陽」が昭和52年4月に初臨界に達した。その後各種試験を進め、現在熱出力5万kwの定格運転を順調に行っている。これは、軽水炉に続く次代の原子炉の本命として期待されている高速増殖炉の自主技術による開発に明るい見通しを与える大きな成果である。また、その性能、信頼性等を確認すること等を目的とした原型炉「もんじゅ」についてもその設計をほぼ終了し建設準備が整えられた。今後は更にこれらの成果を踏まえ実証炉の開発の準備を進める必要がある。 高速増殖炉に関する国際協力については、日独間の協力が昭和46年以来続けられてきたが、昭和53年6月新たにフランスが参加することになり、3国間における幅広い協力体制が確立された。また、日・ソ間での高速増殖炉協力についても、昭和53年1月両国において日・ソ科学技術協力協定の枠内で進めることが合意され、昭和54年度から開始されることとなった。 高速増殖炉「常陽」 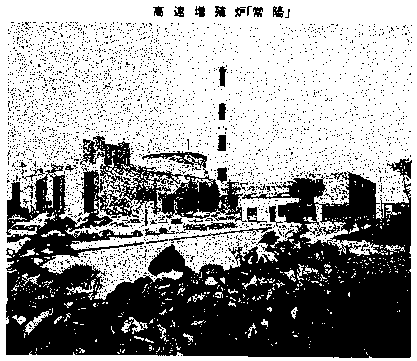 〔新型転換炉〕
同じく動力炉・核燃料開発事業団において開発中のプルトニウム、減損ウラン等を有効に利用できる新型転換炉については、その原型炉「ふげん」が昭和53年3月に初臨界に達するとともに7月には試験発電を開始し、現在昭和54年3月末の電気出力16万5キロワットの本格運転をめざし、順調に試験を進めている。これにより将来、高速増殖炉を補完するものとしての同型炉の技術的見通しが得られつつある。これらの成果は、我が国の完全な自主技術による原子炉開発がようやく根付きはじめたものといえる。 新型転換炉「ふげん」 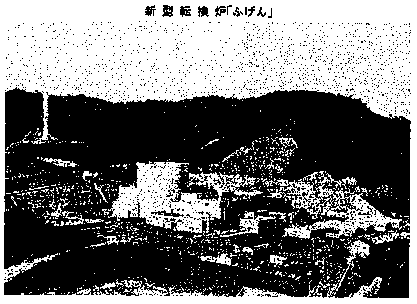 〔多目的高温ガス炉〕
日本原子力研究所等において実施されている核熱エネルギーを産業に供給する多目的高温ガス炉の開発については、高温ガスループによる試験が実施される等順調に進展した。また、直接製鉄などの利用系技術の開発も進められた。今後、次の開発段階としては、大型高温高圧ヘリウムガスループによる試験結果等を踏まえつつ、発生高温ガス温度1,000℃を目標とする実験炉の建設について検討を進める段階にきた。 また、昭和52年4月、日独両国により、高温ガス炉協力が合意され、現在、実施機関の間において、協力内容及び協力方法等に関して協議が行われている。 多目的高温ガス炉炉心構成ブロック  〔核融合〕
核融合の研究開発については、昭和50年に決定した第2段階基本計画の中核となる「臨界プラズマ試験装置(JT-60)」の設計仕様の検討が終了し、昭和53年4月から本体部分の製作が開始された。このJT-60が成功すれば核融合利用の実用化が原理的に可能であることが実証されることとなる。なお、日本原子力研究所はJT-60を含む核融合研究施設の用地として昭和53年7月茨城県那珂町を選定し、地元との折衝を行っている。この他中間ベータ値トーラス装置(JFT-2)等を使用した研究開発も着実に成果を挙げつつある。 昭和52年9月基本的に合意された日米核融合協力は、昭和53年5月の日米首脳会議に基づく「新エネルギー研究開発に関する日米科学技術協力構想」においても、最も優先度の高いものとして位置付けられた。今後、更に資金分担等の諸問題や具体的な協力の進め方等について、米側と協議を進めることとしている。本協力は、従来の研究協力に比較して、その規模の面において、また、その内容の面においても画期的なものであり、その成果が多いに期待されている。また、ソ連との協力についても、高速増殖炉協力と同様に昭和54年度から開始されることになった。この他、経済協力開発機構国際エネルギー機関(OECD-IEA)における核融合協力についても、超電導磁石に関する研究開発に参加する等新たな進展があった。 臨界プラズマ試験装置(JT-60) 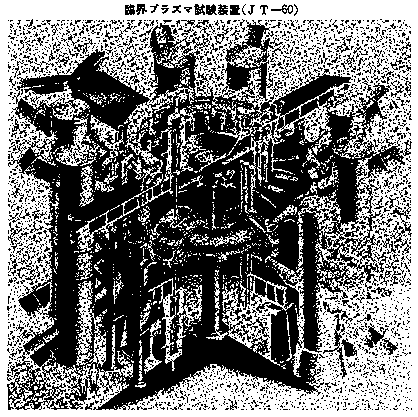 〔原子力船「むつ」〕
日本原子力船開発事業団における原子力第1船「むつ」の開発については、遮へい改修の基本設計を完了した。安全性の総点検のうち、設計面の再評価については、日本原子力研究所等の協力を得て作業を進めている。「むつ」の遮へい改修工事及び原子力プラントの設備面の点検については、今後約3年間にわたり佐世保港で行われることとなっている。 日本原子力船開発事業団法については、昭和52年11月、第82回国会において同事業団法の廃止するものとされる期限を、昭和55年11月30日までとするよう改正された。この改正の趣旨を踏まえ、原子力船の研究開発体制の整備を図ることにしている。また、「むつ」は、昭和53年10月、青森県むつ市の大湊港から佐世保港へ回航された。 原子力第1船「むつ」 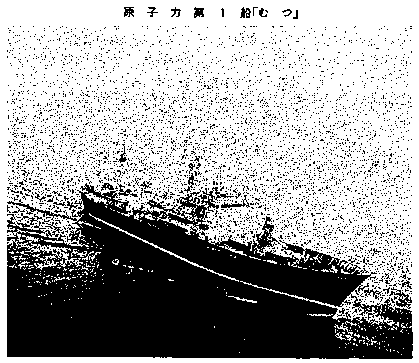 5 新長期計画と今後の課題
〔新長期計画の策定〕
原子力委員会は、昭和47年6月に、長期計画を決定して以来、その長期計画に基づき、関係各界の緊密な協力の下に我が国の原子力研究開発利用の推進を図ってきた。 しかし、その後5年余を経過し、その間に、①エネルギー源としての原子力の地位が一層高まったこと、②克服すべき現実の課題が多くなり、かつその厳しさが深まっていること、③核不拡散の強化を目的とする国際的制約が強まるなど国際環境が変化したことなど、原子力をとりまく内外の情勢は、大きく変化した。 このような背景の下に、原子力委員会は、長期計画を改訂することとし、昭和52年5月、原子力委員会の下に長期計画専門部会を設け、鋭意検討を進め、昭和53年9月12日、新しい長期計画を決定した。 〔原子力研究開発における基本方針〕
新長期計画では、今後約10年間における原子力研究開発利用の進め方と主要なプロジェクトについての課題とスケジュールを示したが、その基本方針は以下のとおりである。 ① 我が国は、原子力研究開発利用を、厳密に平和の目的に徹して進めるものとする。 原子力の平和利用を確保するため、原子力基本法及び核兵器の不拡散に関する条約(NPT)の精神にのっとり、原子炉等規制法をはじめとする関係法令に基づく厳重な規制を実施し、また国内保障措置体制の一層の充実を図るものとする。 ② 原子力開発利用は、安全の確保を大前提として進めるべきであるとする従来の方針を再確認するとともに、原子力基本法等の改正による原子力行政の新体制発足を期して、国民の健康の保持、環境の保全等、安全確保に係る各種対策の一層の充実に努めるものとする。かつ、この上に立って、原子力研究開発利用に対する広い国民的支持を得るよう努力するものとする。 ③ 原子力の研究開発における国際協力及び資源国との開発協力については、引き続き、積極的にこれを推進する必要がある。他方、技術の面では、自主的な原子力技術体系及び原子力産業の確立を目指し、また核燃料サイクルについては、外的な制約を極力少なくすることなどにより、内外にわたる我が国原子力研究開発利用の自主性を確保するものとする。 ④ 原子力研究開発プロジェクトを進めるに当たっては、総合的かつ長期的視野のもとに、計画的に推進するものとする。特に、資金の調達とその有効利用に十分配慮し、計画的推進の実効性を確保するよう努めるものとし、その推進につき政策運営全体のうちにおける調和に努めつつも、重点的配慮を払うべきものとする。 〔原子力研究開発利用の今後の進め方〕
今後の原子力研究開発利用の各分野につき、次のような長期的ビジョンと施策の重点を掲げている。 ① 原子力発電については、
昭和60年度3,300万キロワット、昭和65年度6,000万キロワットという原子力発電規模を大きな遅れなく実現させる必要がある。なお、軽水炉の改良・標準化を進める。 ② 将来の炉型選択と新型炉開発については、
高速増殖炉を将来の発電用原子炉の本命として導入していく。 新型転換炉は、この基本路線を補完する炉として実証炉以降の開発の進め方につき、早急に方針を決定する。 キャンドウ炉の導入については、評価検討を進め、結論を得る。 非電力部門において核熱エネルギーを利用しうる多目的高温ガス炉の開発を進める。 ③ 核燃料サイクルについては、
原子力平和利用と核拡散防止との両立をめざす国際的努力に協力しつつ、我が国の自主的な核燃料サイクルの確立を図る。特に、
(イ) 天然ウランについては、将来、年間所要量の3分の1程度を開発輸入により確保することを目標として、動力炉・核燃料開発事業団等の海外探鉱活動を推進するものとする。 (ロ) ウラン濃縮については、遠心分離法による自主的なウラン濃縮技術の開発を推進することとし、パイロットプラントの建設、運転を進めるとともに、昭和60年代中頃までに我が国において実用工場を稼働させるものとする。 (ハ) 使用済燃料の再処理については、再処理事業は国内で行うことを原則とし、昭和65年頃の運転開始を目途に民間が主体となって第二再処理工場の建設に速やかに着手する。このため、関係法令の設備、立地対策の推進等を進めるとともに、必要な研究開発を行う。 (ニ) 放射性廃棄物については、低レベルのものについては、今後、安全確保に留意しつつ、海洋処分、陸地処分を計画的に実施する。高レベル廃棄物の固化処理及び貯蔵については、昭和60年代初頭に実証試験を行うことを目標に研究開発を進めるとともに、処分については、国が中心となって計画的に調査研究を進める。 ④ 核融合については、
欧米諸国と雁行して、臨界プラズマ試験装置(JT-60)を建設する。 また、この分野における日米科学技術協力を積極的に推進する。 ⑤ 原子力船については、
「むつ」の遮蔽改修及び安全性総点検、実験航海等を行う。 これと並行して、将来に備えて所要の研究を進めることとし、このための研究開発体制の整備を図る。 ⑥ 原子力研究開発プロジェクトの推進
原子力研究開発の主要なプロジェクトについて、今後10年間の研究開発課題及びそのスケジュール等を示している。 これらのプロジェクトの推進に必要な所要資金は、今後10年間(昭和53年度~昭和62年度)で、合計約4兆円(昭和52年度価格)と見込まれる。この資金の確保については、研究開発という基本的性格から、財政面において適切な配慮がなされることが期待されるが、同時に、プロジェクトの性格に応じ各種の財源を配慮する必要があり、早急にその検討を進めるものとする。 〔今後の課題〕
新長期計画は、以上に述べたような背景の下に、今後約10年間における原子力研究開発利用に関する施策の重点とその方向を示したものであるが、石油代替エネルギー源開発という面から新長期計画の目標を達成していくことには、2つの使命がある。 第一は、この10年間から20年間における比較的短期的なエネルギー供給に対する貢献である。このためには、当面の最大の問題となっている立地の推進と、核燃料サイクルの確立が不可欠であるが、この開発規模が達成されなければ、5年後、10年後においてエネルギー確保のための一層困難な、かつ、より高価な努力が強いられることとなろう。 第二は、より長期的なエネルギー供給を確保するための研究開発成果の達成である。高速増殖炉や核融合等の研究開発は、21世紀以降のエネルギー供給の安定化を図ろうとするものであり、その成果は、次の世代に対する大きな社会資産となるものであるが、化石エネルギー資源を涸渇寸前まで大量に消費せざるを得ない現代人として、その達成は次の世代に対する絶対的な責務である。 これらの研究開発利用を進めるに当たって、新長期計画では今後10年間に必要とする資金を約4兆円と見込んでいるが、このような巨額の資金とそれに伴う大量の資材や人材を計画的かつ、効率的に活用し、その使命を果たしていくという責任は誠に大きいものがある。これらの使命に十分配慮しつつ、新長期計画の具体化とその推進に取り組む必要があるが、今回の長期計画の改訂に当たっては、結論の得られなかった問題もあり、今後の内外情勢の変化と施策の進展を十分に踏まえ、長期計画を柔軟に見直し、要すれば適時これに修正を加えるなどの弾力的措置をとりつつ、我が国の原子力研究開発利用の適切、かつ、積極的な推進を図っていくこととしている。この場合、
① プロジェクト間の連携を十分に確保しつつ、推進を図ること。 ② 一層効率的な開発体制の整備を図ること。 ③ 必要な資金を確保すること。 が極めて重要な課題であり、今後、早急に検討を進める必要がある。 なお、開発途上国への協力も重要な課題であり、昭和53年には、アジア、太平洋地域を対象とした「原子力科学技術分野における地域協力協定(RCA)」に加盟したが、今後、更に一層の貢献を行っていく必要がある。 また、原子力関係従事者の原子力損害補償体制の充実を図るため、原子力損害賠償法の改正を図ることも当面の課題のひとつである。 原子力施設の安全の確保についての基本的な考え方については、昭和52年原子力年報に詳細に記述したところであるが新体制により、原子力の安全確保は、原子力安全委員会の下で進められることとなる。第1章でも述べたとおり、我が国の原子力研究開発に伴う安全対策は、従来から万全の措置がとられてきたが、今後は原子力安全委員会による一層の充実が期待される。 原子力委員会としては、原子力安全委員会の意向を踏まえつつ、今後とも安全の確保を原子力研究開発利用の推進の大前提とし、工学的安全研究、環境放射能安全研究等の関連研究をはじめ、それを支える国内の自主技術の蓄積に一層努力する方針である。 第3章 核不拡散をめぐる国際的動向
国際的な核不拡散強化の動きの中で、米国においては、昭和53年3月、「1978年核不拡散法」が成立し、各国に大きな影響をもたらした。また、昭和52年10月に発足した「国際核燃料サイクル評価(INFCE)」が積極的に進められている。 一方、我が国にあっては、日米再処理交渉をはじめ、日加及び日豪原子力協力協定の改訂交渉が行われる等核不拡散をめぐる国際的動きは、ますます活発化した。 原子力委員会は、昭和52年8月15日、「原子力平和利用と核不拡散の両立をめざして」と題する原子力委員会委員長談話を発表したが、これは我が国が原子力基本法に基づき原子力の開発利用を平和目的に限ることとしていること、更に非核三原則を国是として堅持してきていることを踏まえ、核兵器廃絶に対する願いと、我が国の原子力平和利用の理念に対する不動の決意を示したものである。同時に、核不拡散それ自体が、原子力の平和利用を妨げるものであってはならないこと、恒久平和の理念と、それを達成するためのあらゆる努力を前提とするならば、核兵器の不拡散及びその将来における廃絶と原子力平和利用は両立しうるとの考えを明らかにしたものである。 原子力委員会としては、この考えに基づき、国際社会への貢献と我が国の原子力平和利用の促進に努めてきており、新長期計画においても、今後ともこのこと国際場裡において、一層積極的に主張し、各国のコンセンサスを得るよう努めることとした。また、INFCEに積極的に参加し、核不拡散のための新たな国際的秩序の形成に積極的に貢献するほか、より効果的な保障措置技術の研究開発、核物質防護のための国内体制の一層の強化を図ることも重要な課題である。 また、特に近年、核不拡散との関連において、原子力に関する重要技術の国際間移転は、とみに制約されてきており、安易な導入期待は許されなくなってきている。今後、単に技術水準において先進国に遅れをとることを防ぐのみならず、国際協力を有効に進め、また前述の核不拡散に関する我が国の基本方針にのっとって、機器の輸出、開発途上国への技術援助等が可能となるまでに、我が国の原子力技術と関連産業を発展せしめるためにも、原子力の研究開発における自主性を確立していくことが必要である。 1 米国の核不拡散政策と我が国の対応
〔東海再処理施設運転に係る日米交渉〕
動力炉・核燃料開発事業団では、東海再処理施設の試験運転の一貫として、昭和52年、米国において濃縮されたウラン燃料を再処理することに先立ち、日米原子力協力協定第8条C項に基づき、再処理の実施に関して米国の事前同意を得る必要があった。 一方、米国は、核不拡散政策及び経済性等の理由から、商業的再処理とプルトニウム・リサイクルの、期限を定めぬ延長及び高速増殖炉の商業化延期等を骨子とした新原子力政策を打ち出す状況にあったため、前述の事前同意の取り付けが難航した。 交渉に当たっては、我が国は、
① 核不拡散の強化には、積極的に協力する。 ② 原子力平和利用の推進と核不拡散は、両立しうる。 ③ 核不拡散条約においては、非核兵器保有国での原子力平和利用が阻害されないことが保証されており、核兵器保有国と非保有国の間で差別があってはならない。 ④ 米国と違って、エネルギー資源の乏しい我が国にとって、原子力開発利用は必要不可欠である。 との基本的立場で臨んだ。その結果、昭和52年9月1日に、ようやく、原則的合意が得られ、昭和52年9月12日、日米原子力協力協定第8条C項に基づく共同決定が行われた。 同再処理施設の運転に関しては、2年間に限り、99トンの範囲内で使用済燃料の再処理を行うことが合意された。 動力炉・核燃料開発事業団は、再処理施設の運転を昭和52年9月22日に開始するとともに、共同決定に当たっての両国の相互了解に基づき、核不拡散につながる各種の試験を同施設を中心として実施している。昭和53年9月には、これらの試験のうち、混合抽出法及び混合転換法に関する試験の中間成果を中心に情報交換を行うため、日米技術専門家会合が開催された。また、保障措置技術を進展させるための日本、米国、フランス及び国際原子力機関(IAEA)の共同研究(TASTEX)が進められた。 昭和54年9月には、2年間の期限が切れるため、再度共同決定が必要となるが、そのための次期交渉に当たっては、前述の核不拡散に対する我が国の基本政策等を堅持しつつ、INFCEの進捗状況、及び東海再処理施設で実施した各種試験成果等を十分踏まえて臨む必要がある。 〔米国の核不拡散法成立と日米原子力協力協定改訂交渉〕
昭和53年3月10日、米国で「1978年核不拡散法」が発効した。同法の目的は、
① 米国からの原子力関連資材、技術の輸出に際して、核不拡散のための措置を強化すること。 ② 同時に、核不拡散政策を遵守する国に対して、核燃料が安定して供給されるよう努力すること。 にあり、また、同法は、これらの目的を達成するため、米国行政府に対し、関係諸国と結んでいる現行原子力協力協定改訂等を行うこととを要求している。 同法の発効により、米国政府から我が国に対しても、原子力協力協定改訂交渉を開始したい旨申し入れがされることとなった。交渉に臨むに当たっては、前述の核不拡散に対する我が国の基本的な立場を堅持しつつ対処する必要がある。 〔使用済燃料の第三国移転〕
我が国が、米国において濃縮されたウラン燃料を再処理する等のために、海外に移転する場合には、現行日米原子力協力協定第10条A項による米国の事前同意が必要である。 従来、米国政府は、この事前同意に際しては、使用済燃料の船積み毎に、ケース・バイ・ケースに判断し、同意してきたが、前述の核不拡散法の発効及びそれに基づく輸出入基準の改正に伴い、より厳しい基準と手続きが定められた。 一方、我が国の電気事業者は、英国原子燃料公社(BNFL)又は、フランスCOGEMA社と、米国において濃縮されたウラン燃料の再処理委託契約を締結しており、これに基づく昭和53年分の使用済燃料の移転は、米国核不拡散法発効後、最初のケースとなり、その事前同意を取り付けることが難航した。 結局は、我が国の核不拡散に対する積極的姿勢が評価され、承認が得られたが、今後とも、我が国の原子力平和利用の推進が損われることのないよう、米国の理解と協力を求める必要がある。 2 INFCEへの対応
原子力平和利用と核不拡散の両立のための方途をめざして、核燃料サイクル全分野における技術的、分析的作業の実施を目的としたINFCEの設立総会が、昭和52年10月19日から3日間ワシントンにおいて開催され、その後2年間の予定で検討が進められている。 原子力委員会では昭和52年10月14日「INFCEに臨む我が国の基本的考え方」を発表するとともに、INFCEに対する我が国としての適切な対応策の確立に資するため、INFCE対策協議会を発足させた。 一方、INFCEに対しては、我が国は、再処理プルトニウムの取扱い及びリサイクルを検討する第4作業グループの共同議長国を務め、東海再処理施設における混合抽出試験成果の提供など積極的な貢献を行いつつ、原子力平和利用と核不拡散は両立しうるとの我が国の基本的立場が反映されるよう努めている。 なお、核不拡散に関する多国間協議の場としては、INFCEの他に、原子力平和利用先進国間会議(ロンドン協議)があるが、同会議においては、昭和53年1月、原子力関連資材、技術の輸出基準としてのガイドラインを公表した。 3 ウラン資源国との原子力協力協定改訂交渉
〔日加原子力協力協定改訂〕
カナダは、昭和49年12月及び昭和52年12月に発表したウラン輸出政策を実施するため、我が国に対しても原子力協力協定改訂交渉の申し入れを行い、昭和52年1月東京における第一次交渉を皮切りに、数次にわたる交渉が行われたが、交渉過程において、カナダは、対日ウラン禁輸措置を講ずる等強硬な姿勢を保ち、我が国は苦しい立場に立たされたものの、昭和53年1月、核物質の20%以上の濃縮及び高濃縮ウラン又はプルトニウムの貯蔵の事前同意事項等を新たに盛り込んだ改訂について合意に達した。なお、本交渉では、改訂内容が並行して進められていたカナダ・ユーラトム原子力協力協定改訂交渉結果の内容より我が国にとって不利になってはならないとの立場が基本的に堅持された。昭和53年8月、日加原子力協力協定改訂議定書の正式署名がなされ、同議定書は、今後国会の承認を得て発効することとなる。 〔日豪原子力協定改訂〕
ウラン資源国として、カナダと同様な立場にあるオーストラリアは、昭和52年5月、ウラン輸出に際して核不拡散のための措置を強化することを目的とし保障措置新政策を発表した。オーストラリアは、当該政策を実施するため、我が国に対しても原子力協力協定改訂交渉の申し入れを行ってきた。これを受けて、昭和53年8月、東京において第一次交渉が行われ、現在、継続中である。本交渉においても、我が国の原子力平和利用が損われないよう努める必要がある。 4 新しい保障措置体制と核物質防護措置の強化
昭和52年11月、国会において核兵器の不拡散に関する条約(NPT)に基づく国際原子力機関(IAEA)との間の保障措置協定が承認され、また、これに伴う原子炉等規制法の一部改正法等が成立した。これによって、我が国は、NPTに対応した新しい保障措置体制に移行することになり、所要の国内保障措置体制の整備を行った。 また、近年核不拡散強化という観点から核物質の防護に関する国際的関心が高まり、国際原子力機関の主催により昭和52年末以来、2回にわたり、核物質防護に関する国際条約についての政府間会議が開催され、我が国は、これらの会議に積極的に参加した。 更に、国内体制を整備するため、原子力委員会に核物質防護専門部会を設け、我が国の国情にあった核物質防護体制の検討を進めている。今日の我が国の主要な原子力施設の防護状況は、国際的水準に達していると考えられるが、今後の国際的情勢を踏まえつつ、法制面での所要の整備等一層の努力を払う必要があると考えられる。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |