| 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
放射性廃棄物の廃棄に関する技術的基準について 昭和53年8月29日
原子力委員会
原子力委員会は、昭和53年8月23日付けをもって放射性廃棄物対策技術専門部会から、放射性廃棄物の廃棄に関する技術的基準に関する報告書の提出を受けた。 同報告書について検討した結果、放射性廃棄物の廃棄の技術的基準として適当と認められるので、放射性廃棄物の廃棄に係る安全確保の重要性にかんがみ、同報告の趣旨に沿って関係各省庁において速やかに関係法令等の整備が図られるべきである。 (別紙)
昭和53年8月23日
原子力委員長
熊谷太三郎殿
放射性廃棄物対策技術専門部会長
左合 正雄
放射線廃棄物の廃棄に関する技術的基準について
放射性廃棄物対策技術専門部会は、昭和53年3月以降放射性廃棄物の廃棄に関する技術的基準について検討した結果次のとおり報告書をとりまとめたので報告する。 放射性廃棄物の廃棄に係る安全を確保することは極めて重要であるので、今後すみやかに関係法令の整備を図ることが望しいと考える。 放射性廃棄物の廃棄に関する技術的基準
放射性廃棄物の廃棄は、事業所内廃棄及び事業所外廃棄に区分され、放射性廃棄物を廃棄する場合は、放射性廃棄物の性状及び廃棄の方法に応じて、本基準に掲げる保安上の措置をとらなければならないこととする。(注)
(注)事業所内廃棄については、気体状、液体状、及び固体状の放射性廃棄物に区分して廃棄の方法を整理した。「放射性廃棄物の性状」とは、この3態様を指し、また、「廃棄の方法」とは、排出、保管廃棄、投棄(事業所外廃棄の場合)などを示す。 例えば、液体状、及び固体状の放射性廃棄物を焼却した場合、焼却残渣及び排ガスが発生するが、これらの二次的な廃棄物も、それぞれの性状に応じて本基準に従って廃棄されることとなる。 Ⅰ 工場又は事業所における廃棄 1 放射性廃棄物を廃棄する場合、廃棄作業及び当該作業に係る放射線防護について必要な知識を有する者に行わせるとともに、作業に当たっては、作業衣等を着用して作業させること。 2 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。 3 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 3.1 排気施設によって排出すること。 3.2 障害防止の効果をもった廃棄槽に保管廃棄すること。 4 排気施設によって排出する場合は、ろか、放射能の強さの時間による減衰、多量の空気による稀釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において、又は排気監視設備を設け当該設備において、排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が一定の許容濃度をこえないようにすること。 5 障害防止の効果をもった廃棄槽に保管廃棄する場合であって、崩壊熱等により著しい過熱が生ずるおそれがある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。 6 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 6.1 排水施設によって排出すること。 6.2 障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄するか、又は容器に封入し、若しくは容器に固型化して障害防止の効果をもった廃棄施設に保管廃棄すること。 6.3 障害防止の効果を持った焼却設備又は固型化設備で焼却し、又は固型化すること。 7 排水施設によって、排出する場合は、ろか、蒸発、イオン交換樹脂等による吸着、放射能の強さの時間による減衰、多量の水による稀釈等の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において、又は排水監視設備を設け当該設備において、排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の境界における水中の放射性物質が濃度の一定の許容濃度をこえないようにすること。
8 障害防止の効果をもった廃液槽に保管廃棄する場合であって、崩壊熱等により著しい過熱が生ずるおそれがある場合には、冷却について必要な措置を講ずること。 9 容器に封入する場合、当該容器は次に掲げる基準に適合するものであること。 9.1 水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。 9.2 きれつ又は破損が生ずるおそれがないものであること。 9.3 容器の蓋は容易にはずれないものであること。 10 容器に封入して障害防止の効果をもった廃棄施設に保管廃棄する場合、当該容器に、きれつ若しくは破損が生じた場合において、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で包むか、又は封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けることなどにより、汚染のひろがりを防止すること。 11 容器に固型化した場合の当該固型化した容器は、放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 12 容器に封入し、又は容器に固型化して障害防止の効果を持った廃棄施設に保管廃棄する場合、当該容器には、放射性廃棄物であることを示す標識を付けること。また、整理番号を付けることにより、当該封入され、又は固型化された液体状の放射性廃棄物に関して記録された内容と照合できるようにすること。 13 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。 13.1 障害防止の効果をもった焼却設備において焼却すること。 13.2 容器に封入し、又は容器に固型化して、障害防止の効果をもった廃棄施設に保管廃棄すること。ただし、大型機械等容器に封入し、若しくは容器に固型化することが著しく困難なもの又は放射能の強さの時間による減衰を行う必要のあるものを障害防止の効果をもった廃棄施設に保管廃棄する場合は、この限りではない。 14 容器に封入する場合、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。 14.1 水が浸透しにくい、腐食に耐え、かつ放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。 14.2 きれつ又は破損が生ずるおそれがないものであること。 14.3 容器の蓋は、容易にはずれないものであること。 15 放射性廃棄物を固型化した容器は、放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 16 容器に封入し、又は容器に固型化したものであって、崩壊熱等により著しい過熱が生ずるおそれがあるものは冷却について必要な措置を講ずること。 17 容器に封入し、又は容器に固型化して障害防止の効果を持った廃棄施設に保管廃棄する場合、当該容器には、放射性廃棄物であることを示す標識を付けること。また、整理番号を付けることにより、当該封入され、又は固型化された固体状の放射性廃棄物に関して記録された内容と照合できるようにすること。 18 液体状又は固体状の放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化して保管廃棄する廃棄施設(大型機械等容器に封入し、若しくは容器に固型化することが著しく困難な固体状の放射性廃棄物又は放射能の強さの時間による減衰を行う必要のある固体状の放射性廃棄物を保管廃棄する廃棄施設を含む。)の目につきやすい場所に、当該施設の管理上の注意事項を掲示すること。 Ⅱ 工場又は事業所の外における廃棄 1 放射性廃棄物を工場又は事業所の外において廃棄する場合は、障害防止の効果をもった廃棄施設に保管廃棄するか、又は次項以下に掲げる保安のために必要な措置を講じて海洋に投棄すること。 2 放射性廃棄物の海洋に投棄する場合は、安全の確保を図るため一定の方法により、容器に封入し、又は容器に固型化すること。 3 前項に定めるところにより放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器(以下「投棄物」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。 3.1 比重は、1.2以上であること。 3.2 放射能濃度は放射性物質の種類に応じ、一定の数量をこえないこと。 3.3 海面衝突時、海中降下時及び海底衝突時において、放射性廃棄物が容易に飛散せず、又は漏えいしないこと。 4 投棄物には、その表面の目につきやすい箇所に放射性廃棄物であることを示す標識及び表面線量率を示す一定の標識を付け(当該投棄物の表面線量率が50ミリレム毎時をこえる場合に限る)、投棄しようとする事業者名その他一定の事項を一定の方法により表示すること。また、一定の方法により整理番号を付けることにより、当該封入され、又は固型化された放射性廃棄物に関して記録された内容と照合できるようにすること。 5 投棄物を海洋に投棄する場合は、次に掲げるところに従って行うこと。 5.1 4,000m以深であって、一定の海域に投棄すること。 5.2 投棄率及び投棄作業時間を投棄作業の安全を損うおそれがないようにすること。 5.3 投棄物に関する放射線管理、投棄作業に従事する者の被ばく管理その他投棄物の保安のために必要な措置をとること。 6 投棄作業には、原子炉主任技術者免状若しくは核燃料取扱主任者免状を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者を立ち合わせ、次に掲げる事項について監視させること。 6.1 前項各号に掲げる措置が講じられていること。 6.2 目視点検上、投棄物には著しい破損がなく、また4に定めるところにより標識が付けられ、表示が行われ、及び整理番号が付けられていること。 Ⅲ 放射性廃棄物の海洋投棄に関する技術的細目等について 1 Ⅱ.2の放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化する方法は、次の各号に掲げるところにより水硬性セメントを用いて金属製容器に固型化することをいう。 なお固型化に当たっては、骨材、添加剤等の混和材料を用いることができるものとする。 1.1 水硬性セメントは、日本工業規格R5210若しくはR5211に定める水硬性セメント又はこれと同等以上の強度及び安定性を有するものであること。 1.2 金属製容器は、日本工業規格Z1600に定める金属製容器又はこれと同等以上の強度及び気密性を有するものであること。 1.3 固型化されたものの一軸圧縮強度は、150㎏/㎝2以上であること。 1.4 固型化に当たっては、放射性廃棄物と水硬性セメント若しくは水硬性セメント及び混和材料を均質に練りまぜ、又はあらかじめ均質に練りまぜた水硬性セメント若しくは水硬性セメント及び混和材料と放射性廃棄物を一体化させること。この場合において、容器内に有害な空隙が残らないようにすること。 2 Ⅱ.3.2の放射能濃度は、次の各号に掲げる放射性物質の区分ごとにそれぞれ当該各号に掲げる放射能濃度とする。この場合、放射能濃度は、そろ総重量の合計が1000トンを超えない投棄物について、当該投棄物中に含まれる放射性物質の数量を当該投棄物の重量の合計で除したものとする。 2.1 アルファ線を放出する放射性物質(次号に掲げる場合の226Ra、210Poを除く) 1キュリー毎トン
2.2 前号に掲げる放射性物質が226Ra、210Po(210Pbと共存する場合に限る)を含む場合、当該226Ra、210Po 0.1キュリー毎トン
2.3 アルファ線を放出しない放射性物質(3Hを除く)であって、半減期が6ケ月をこえる場合及び半減期が明らかでない場合 100キュリー毎トン
2.4 3H及びアルファ線を放出しない放射性物質であって半減期が6ケ月をこえない場合 1,000,000キュリー毎トン
3 Ⅱ.4に規定する表面線量率を示す一定の標識は、表面線量率の区分に応じて次のとおりとする。 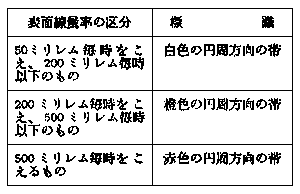 4 Ⅱ.4の一定の事項は、国籍、投棄物作成年とし、一定の方法は、文字の大きさが75ミリメートル以上であるものとする。 5 Ⅱ.5.1の一定の海域については、環境安全評価を行ったうえで指定されるものと考える。 放射性廃棄物対策技術専門部会構成員
基準分科会構成員
分科会開催日
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目次 | 次頁 |
 輝
輝 川 猛
川 猛