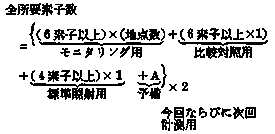| 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「環境放射線モニタリングに関する指針」について 昭和53年1月31日
原子力委員会
環境放射線モニタリング中央評価専門部会は環境放射線モニタリング結果の総合的評価と関係機関への指導助言等を行う立場から、その前提となるモニタリングの方法、測定結果の評価基準等の具体的計画を策定する際の指針の検討を行い、今回その結果を「環境放射線モニタリングに関する指針」としてとりまとめた。 当委員会は同指針の内容が適当であると認める。 したがって、今後環境放射線モニタリングを関係機関が実施するにあたってはこの指針を参考とすることが望ましいと考える。 環境放射線モニタリングに関する指針
まえがき
原子力開発利用の本格化に伴い、原子力施設周辺住民の健康を守り環境の保全を図るため、環境放射線モニタリングの方法、測定結果の評価基準等に係る指針の確立が、地方公共団体をはじめとして関係方面より要請されていた。 また、環境放射線モニタリングの計画、モニタリング結果の総合評価などを行うため、昭和49年12月に設立された原子力委員会の環境放射線モニタリング中央評価専門部会においても、環境放射線モニタリングの結果の総合評価を行う場合に、その前提となる指針作成の必要性があった。 原子力委員会はこのような情勢にかんがみ、環境放射線モニタリング中央評価専門部会にその指針作成について以前より要請していた。これを受けて本専門部会は、先の原子力委員会、環境安全専門部会の「環境放射能分科会報告」(昭和49年7月)にある環境放射線モニタリングのあり方を基本として考え、また、内外の事例も参考とし、さらに現地調査を行うなど、指針作成に必要な調査検討を行ってきた。 ここに、その結果を「環境放射線モニタリングに関する指針」として取りまとめた。 本指針は、原子力施設敷地境界の外側において、主として地方公共団体が実施する環境放射線モニタリングの技術的水準の向上を図るとともに、その斉一化を図るため、環境放射線モニタリングの計画の立案、実施及び結果の評価について基本的方法を示したのもである。 なお、本指針は主として、軽水型原子力発電所周辺のモニタリングに関するものであるが、その他の原子力施設周辺についても基本的にはこれを準用することができる。しかし、とくに使用済核燃料再処理施設については、その運転に伴い蓄積されるモニタリングデータ等の検討結果が得られたのち、適切な項目の追加等を必要とすることがある。 各地方公共団体が環境放射線モニタリングを計画、実施するにあたっては、本指針を参考とし、あわせて原子力施設、地域の特性等を考慮して決定することが望まれる。 原子力施設周辺の環境モニタリングは、地方公共団体が行うものも、施設者の行うものも、本質的に異るものではなく、それぞれの立場によって重点のおきかたや密度がいくらか異るだけであり、地域全体としてバランスが取れていればよい。 施設者の行うモニタリングは放出源から出発して、人の側に向う方向が取られる。これとは対照的に、地方公共団体の主たる立場は、施設周辺住民の健康と安全を直接守るところにあるので、住民の被ばく線量を評価することである。すなわち人から放出源に向う方向でなるべく人に近い対象、例えば食品や居住環境に重点がおかれる。 このようにモニタリングの実施主体によって重点のおきかたが異るので、地域全体としてバランスをとるためには、モニタリング計画の策定について施設者と地方公共団体との間で調整を行うことが必要である。 なお、本指針に述べられた事項は、今後の調査研究の進展等を考慮し、適宜、見直す必要があると考える。 第1章 環境放射線モニタリング計画
① 環境モニタリング計画は、ICRPの勧告(Publi-cation 7)にもあるように、(1)環境中に存在する放射性物質又は放射線による人の現実的あるいは潜在的被ばくを算定すること、又はこのような被ばくの上限値を推定すること、(2)被ばくの算定に関連した科学的調査を実施すること、(3)公衆の理解と協力を得ることを大きな目標として策定されるべきである。 ② 具体的な環境モニタリング計画を作成するための指針として、以下に環境放射線の測定、環境試料中の放射能の測定その他、被ばく線量を算定するに必要な情報の収集について示す。なお、操業に先立って行う調査については、その留意点を示した。 1-1 環境放射線レベルの測定
① 環境放射線による外部被ばく線量の寄与を評価するため、環境放射線レベルの測定を行う。環境放射線レベルの測定については、ガンマ線を対象とすれば十分であるが、異なる計測器による測定値の相互比較には注意を要する。(参考資料A参照)
② 原子力施設に起因する環境放射線は、通常原子力施設からの距離が遠くなるに従って減少するので、敷地境界の近傍、並びに人口の集中した地点に、連続記録式の放射線計測器を配置し、1時間あたりの平均値及び積算値を求めるとともに、多地点にTLD(熱ルミネッセンス線量計)等の積算型放射線計測器を配置し積算値を求める。 なお、その際、気体廃棄物による放射線レベルの上昇が予想されない地点にも、上記の地点のデータを比較対照するために、同種の計測器を配置する。 ③ 連続記録式の放射線計測器を配置した地点のうち、気象特性を考慮して、少くとも1点には連続気象観測装置(風向、風速、気温、降水量等)を配置する。 ④ 連続式計測器が重点的に配置されるのに対し、積算型計測器は特殊な環境条件を避け一様に配置する。 ⑤ 同種類の検出器は、地表から同一の高さに設置することが望ましい。 1-1-1 環境放射線の連続測定
① 環境放射線の連続測定(線量率)は、積算線量測定の場合と異なり、比較的短時間の変動の監視が可能である。このことはまた、気象観測データ等との比較対照によって異常の早期発見と原因調査に役立つ。 ② 計測器として電離箱、NaI(T1)、GM計数管等があるが、感度等からみて、NaI(T1)シンチレーション検出器又は、電離箱方式のいずれかによって測定する。 ③ また、テレメータシステムは放射線の連続測定データ及び、観測された気象データを伝送し、集中管理を行うのに役立つ。 1-1-2 積算線量測定
積算線量を測定するには種々の方法があるが、感度、取扱いの方法からみてTLDを用いる。連続記録式の放射線計測器による積算値は参考とする。注)
注)これは人工放射線の弁別、短時間の変動のチェックのために参考として使用するものである。 1-2 環境試料中の放射能レベルの測定
① 原子力施設から放出された放射性核種は、自然環境中に拡散されるが、その一部はいろいろな経路を経て人間に摂取される。このため環境試料中の放射能レベルを測定することにより内部被ばく線量評価の参考とする。 ② 陸上の環境試料を採取する地点は気体廃棄物の最大着地濃度地点、人口の分布等を考慮して定める。 ③ 環境試料を採取する場合、人の被ばくに直接関係を有するもの、また、人の被ばくに直接関係ないものでも、放射性核種の分布等全体の傾向の把握に役立つもの、さらに、食品に供されないものであっても蓄積傾向の把握等のため、濃縮の度合が大きく、簡易に採取できるもの等を選ぶ。 採取を行うには、同一種について定点を定めて行うことが望ましい。定点の設定に当っては、放射性核種の放出方法、環境条件に配慮する。対象試料の選定に際し、陸上にあっては、施設周辺の土地利用状況を、また米、野菜、牛乳等についてはその生産状況を考慮する。海産生物については定着性のものを選ぶのが望ましく、また漁獲高等をも考慮する。 ④ 測定の対象とする核種は、放出量、環境における蓄積、及び公衆の被ばくの観点から重要と考えられる核種とする。例えば、軽水型原子力発電所にあっては、60Co、137Cs、(90Srの推定根拠にもなる)、及び131Iと考えてよい。(使用済燃料再処理施設に対応する核種については参考資料D参照)
1-2-1 試料の採取
環境の放射能レベルを評価するためには、“確かな試料”を集めることは“正確な分析”と同じ位重要である。 適確なサンプリングを行うために必要と考えられる一般原則を次に記す。 1) 試料は代表性のあるものでなければならない。したがってサンプリングは調査の目的をよく理解した上で行わなければならない。 2) 試料採取量は、分析、評価に十分な量を採取することとし、そのうち、重要と考えられるものは、計測試料の形で、例えば、5年間くらいの保存が望ましい。 3) 試料の数を減らす目的で、長い期間と広い範囲を代表するようなコンポジット(合せ試料)を用いることができる。 コンポジットを用いることにより、独立した時間と場所で採取した単一のサンプルから得られる値より平均された値が得られる。 ① 農畜水産食品
放射能レベル測定の結果から他の情報と合わせて内部被ばく線量を推定するために役立つものであり、かつ、周辺住民が多く摂取するものとして農産食品では米及び野菜、畜産食品では牛乳、海産食品では、適宜可能なものを採取する。また、地域によっては、その地域の特産品を採取する。 ② 陸水
飲料水として用いられる河川水、地下水(井水)等を採取する。 ③ 大気中浮遊じん
大気中浮遊じんは、必要に応じて採取する。注)
注)例えば、後述する目安レベル(空間線量率)を超えた場合に採取する。 ④ 海水
海産食品、海底土などの放射能レベルの把握との関連において採取する。 ⑤ 土壌、海底土
長半減期放射性核種が環境中に蓄積されることを考慮し、これらの動向を把握するため土壌、海底土を採取する。 ⑥ 指標生物
食品として、供されないものであっても蓄積傾向の把握等のため、濃縮等の度合が大きく、かつ採取が容易な生物を採取する。 ⑦ その他
核爆発実験直後には、以上のほか、放射性降下物の影響が早期に現われる雨水、浮遊じん等を採取する。 1-2-2 採取の頻度
① 長期間にわたる蓄積傾向を把握するための試料、例えば土壌、海底土等については、半年ごとあるいは1年ごとの採取が適当である。 ② 人間の被ばく線量を推定するために利用する試料、例えば農畜水産食品、指標生物、陸水等は、原則的には4半期ごととするが、季節的な食品、生物については収獲期ごと、漁期ごととすることが適当である。 ③ 大型水盤による放射性降下物の調査は、核爆発実験による寄与を把握するため毎月行う。 ④ この他、核爆発実験直後のモニタリングに対応する試料は、わが国への影響の恐れのあることが判明した時点から、ほぼその影響が認められなくなるまで試料採取を行う。 1-2-3 試料中の放射性物質の測定
① 測定方法
環境試料中の放射性物質の測定方法には、機器分析、放射化学分析による放射性核種分析法及び全ベータ放射能測定法等があるが、試料の調整が比較的容易であり、かつ同時に多核種を精度よく分析できるGe(Li)半導体検出器による機器分析法を主として用いることが望ましい。しかし、場合によっては、NaI(T1)シンチレーション検出器による機器分析法を用いることができる。 放射化学分析はGe(Li)半導体検出器等がない場合、あるいは必要に応じて実施する。 なお、全ベータ放射能測定法は、被ばく線量の評価を直接目的としない環境試料の測定であって、迅速性が要求され、かつ、放射能濃度の比較的高い試料を測定、あるいは選定する必要がある場合有効である。(参考資料C参照)
② 検出可能レベルの例
現在用いられているGe(Li)半導体検出器、及びNaI(T1)検出器によるガンマ線スペクトル分析では、60Co、137Cs、131Iに対する検出可能なレベルはおおよそ第1表の通りである。 〔第1表〕検出可能レベルの例注) (pCi/試料) 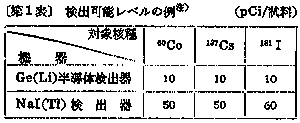 ③ 検出可能なレベルから推定できる被ばく線量の例
食物中にそれぞれの核種が、Ge(Li)半導体検出品による検出可能レベル(第1表)の濃度で存在する場合、その食物を1年間毎日摂取することによる、内部被ばく線量預託は第2表のような値になる。 〔第2表〕Ge(Li)半導体検出器による検出可能レベルに対応する内部被ばく線量預託の例注1),注2)(mrem/年) 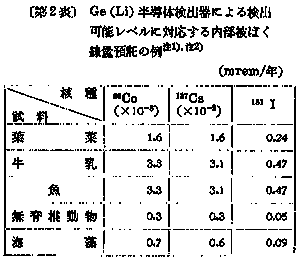 また表の値は60Coと137Csに対しては全身、131Iについては甲状腺についての値である。 このような測定によって得られた結果、それによる被ばくの線量からみて、モニタリングの目的には十分である。(食品中の核種濃度から内部被ばく線量算出のための線量換算係数は第4表を参照)
1-3 線量評価に係るその他情報の収集
環境放射線モニタリングデータから被ばく線量を推定するには、多くの情報、例えば内部被ばくに関する標準日本人のパラメータ、環境生物試料への放射性核種の濃縮係数や移行係数、また気象要素などについてつねに最新の情報の把握、収集に留意し、全体のモニタリング計画の改良に資する必要がある。 1-4 操業前調査
本調査は、①決定核種、決定経路、及び決定グループ注)に関する情報を得て、操業開始後の調査の立案をし、被ばく線量の推定に資すること、②環境放射線及び環境試料中の放射能のバックグラウンドと、その特性を把握し、かつ、環境試料を収集保存し、操業開始後における比較に資すること、③操業開始後のモニタリングの手法と手順を試し、必要な技術に習熟することを目的とする。 注)測定時間はともに、40,000秒~80,000秒である。 注1) 通常の食品摂取モデルとして成人が1日当り摂取する食品の量を葉菜100g、牛乳0.2l、魚200g、無脊椎動物20g、海藻類40g、とした。(発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針:原子力委員会、原子炉安全技術専門部会、昭和51年9月による)
注2) 測定試料の量は、牛乳以外の食品では生重量で約1㎏を用い、乾燥あるいは、灰化などして減容する。これらの試料を測定する測定容器は、Ge(Li)半導体検出器では直径5cm高さ5cmのプラスチック製容器(容積約100ml)を用い、牛乳の分析では2lのマリネリビーカを用いるのが標準である。 注)「決定-」という用語はここでは個人の主要な被ばく機構として第一に考えうるに値する核種、食品の種類および被ばく経路をあらわし、さらに被ばく集団内のグループで、その被ばくが均等であり、かつ、集団内で最も高度に被ばくする人々を代表するようなグループをあらわす場合に使用される。 1-4-1 操業前調査において留意すべき事項
① 環境放射線の変動状況把握のため操業開始後に環境放射線測定を予定する数地点で、その測定を行う。 ② 調査地点の中の少なくとも1地点で環境放射線の連続測定を行い、またその地点における風向、風速、気温、降水量等も調査する。 ③ 大気の浮遊じんに含まれる自然放射性核種のレベル、並びにその変動を知っておくため、1地点において大気試料(大気中浮遊じん)を少なくとも月1回採取し、測定する。 ④ 放射性核種のバックグラウンド濃度を知っておくために、土壌、海底土、主要な現地産食品の流通経路に沿って食品、水および生物の試料を集め機器による核種分析(40K、137Cs等の分析)を行う必要がある。試料によっては季節による差があるので、これを確認するために、4半期ごとに採取、分析しなければならない。操業後の予期しない事態に備え採取試料はできるだけ保存しておく。 なお、原子力施設の種類によっては、長半減期アルファ核種が検出されることもあるので、環境試料についてこれらのアルファ核種の測定をつけ加える必要がある。 ⑤ 以上の調査は操業開始前の1年以上に亘って実施する。 ⑥ 操業前のバックグラウンド試料採取の一環として、想定される操業開始後のモニタリング計画に含まれるよりも、広い範囲から多くの種類の環境試料をバックグラウンドの変動を把握できるていどの時間間隔、地点数での採取をする。 これらの試料については、操業開始後のモニタリング計画と関連させて機器分析等により放射性核種の定量を行う。 ⑦ 採取すべき試料の種類と採取地点の選定を行うために、施設周辺地域についての人口分布、また排気予定地点付近の気象要素、排水予定地点付近の海象の概況、現地産食品の流通経路、摂取状況等の概略データを集める。 第3表に、以上述べてきたことをまとめ、代表的な環境放射線モニタリング計画を示した。 〔第3表〕 環境放射線モニタリング計画注1) 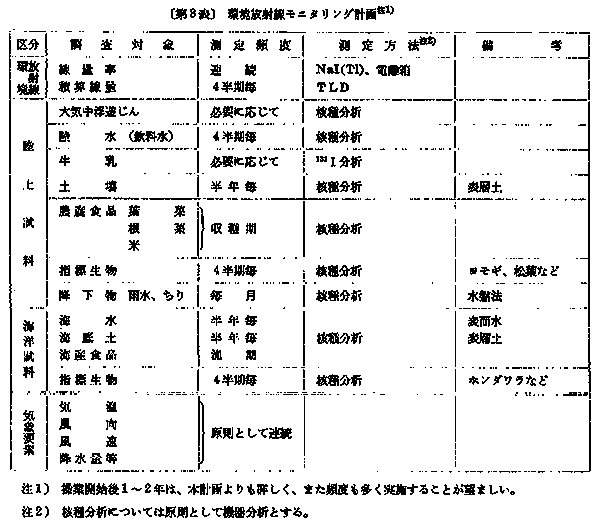 第2章 モニタリング結果の評価
モニタリング計画は原子力施設周辺住民の被ばく線量の推定だけでなく、周辺住民の正しい理解と協力を得ることを目的としている。従ってモニタリング結果は、(1)測定値の信頼性、及び(2)測定結果から被ばく線量を推定する際に用いた仮定の妥当性、(3)許容被ばく線量との関係において、推定された被ばく線量の持つ意味を考慮し、総合的に評価する必要がある。 2-1 測定値のチェック
① 環境放射線及び環境試料中の放射能の測定値のレベルは、核爆発実験による直接の影響があるような場合は別としても、降雨、降雪等の気象要因、昼、夜等の時間的要因、季節的要因、地理、地形上の要因等自然条件により変動するほか、サンプリング方法、試料の前処理の方法、測定器の性能及び測定方法等の物理的、化学的要因により、ある幅の変動を示す。測定値のレベルがこの変動幅に収まるかぎりこれを平常値とみなし、この変動幅を超える場合を異常値と称することとする。 ② 異常値は、(i)単なる測定の欠陥、(ii)自然環境の変化、(iii)核爆発実験の影響、(iv)原子力施設からの予期しない放出等によって出現すると考えられるが、異常値はその原因をよく調査検討する必要がある。 ③ 測定等の管理が確実に行われているかぎり、測定値が平均値(M)±3×標準偏差(σ)を外れる確率は小さいのでこのレベルを一つの目やすとなる値と考え、これを外れた場合のみ、その原因調査を実施することとする。 ④ 平常値であると判断する変動の範囲はM±3σを一応の目やすとする。平均値及び標準偏差は、環境放射線の線量率及び積算線量、環境試料中の放射能レベル等についての操業前の測定値から求めることができる。操業開始後にあっては、原子力施設の平常運転、あるいは核爆発実験等による人工放射線寄与がある場合は、Mおよびσを適時求め直す必要がある。 ⑤ あらゆる測定方法には、それぞれ固有の検出限界があり、また誤差もあるので測定値は変動するのが普通である。さらに、異る機器を使用し、あるいは複数の測定機関における測定値を比較する場合には、通常、測定値の変動幅はさらに大きくなるであろう。したがって平常値であることの判断を正しく行うためにはクロスチェック等が必要である。 ⑥ 目やすレベルは、原子力施設の安全性を評価するものではなく、多数の測定データをふるい分け、このレベルを超えたものについて、原因調査を行い、測定値のチェックを簡易にするためのものである。また、新規施設の操業開始に伴うモニタリングに関しては、操業前の測定値による目やすレベルをそのまま適用することは適当ではなく、操業が定常状態に入ってからさらに、当分の間、モニタリングデータの蓄積をまって定める必要がある。 2-2 測定結果に基づく環境放射線レベルの評価
2-2-1 環境放射線のレベル
① 測定値の解釈
測定値が目やすレベルM+3σを超えた場合は以下の項目について調査を行い、原因を明らかにするとともに、原子力施設からの寄与による環境への影響の判断に資する。 イ.測定系、データ伝送処理系の健全性
ロ.降雨等自然放射線による影響
八.核爆発実験の影響
測定値が目やすレベルM-3σ以下の場合は機器の故障が考えられるので点検する。 ② テレメータシステム
イ.標準ベータ収集間隔を10分程度とすること。 ロ.データの記録は1時間間隔で行うが、目やすレベルを超えた場合データ収集間隔を短くするとともに、過去1時間の短時間間隔のデータを記録できること。 2-2-2 環境試料中の放射能レベル注)
環境試料中の放射能レベルが、目やすレベルM±3σの範囲を超えて検出された場合、まず分析が正しく行われたかどうか、また、核爆発実験によるものでないかどうかについてチェックを行い、異常の原因を調査する。 注) 全ベータ放射能については、従来より多数のデータの蓄積があるので、目やすレベルを設定することも可能であるが、線量評価には直接結びつかないことに留意すべきである。しかし、環境試料中の放射性核種濃度が明らかにされたものについては、線量評価、蓄積傾向の把握に直接つながるので目やるレベルの設定は必要でない。 2-2-3 核爆発実験の影響の評価
環境放射線レベル及び環境試料中の放射能レベルが各々目やすレベルを超えた場合、往々にして放射性降下物による影響であるので、それが原因でないかについて調査する。(参考資料E参照)
核爆発実験による放射性降下物の性質、含まれている核種の時間変化、放射能レベルの連続した測定データなどを十分に把握しておけば、それらのデータとの比較対照から、施設起因のものかどうかを推定することができる。 したがって、核爆発実験が行われたこどうかについて、また放射性降下物に関するデータの入手に留意する。 2-2-4 蓄積傾向の把握
① 長年にわたる蓄積傾向の判定は主として、土壌及び海底土の核種分析に基づいて行う。なお、これ以外にも短期間における蓄積傾向の把握には陸上における松葉、海洋におけるムラサキイガイなど、放射性核種を取り込み易いものも効果的な試料であるが、通常は線量評価には結びつかないことに留意すべきである。 ② これらの対象試料における放射性核種の濃度は、2-1に示した変動要因のなかでも、とくにサンプリングに起因する変動が大きいことを忘れてはならない。しかも、この変動は分析、測定にもとづく変動より一般に著しく大きいものである。したがって経年変化について有意差の検定を可能にするためには、試料の代表性について十分な検討を行っておく必要がある。 ③ 蓄積傾向の判定においては、核爆発実験に伴う核種、施設放出核種のいかんにかかわらず、サンプリングによる誤差も含めての変動を考慮した上で、有意か否かの判定をする。 2-3 評価
2-3-1 被ばく線量の評価
被ばく線量の推定は、外部被ばく線量と内部被ばく線量に分けて別々に算定しその結果を総合してなされるが、前者はTLDにより推定する注1)(環境放射線量率の積算による値は参考とする)。 内部被ばく線量の推定は60Co、137Csによる全身被ばく線量、131Iによる甲状腺被ばく線量の推定を下記の表を用いて行う(他の核種については参考資料D参照)。 〔第4表〕 1pCiを経口摂取した場合(成人)の内部被ばく線量預託の例 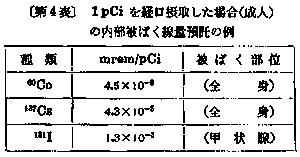 (なお、本表はICRPの計算法によっているが、131Iについては、甲状腺への移行比fwとして0.2を用いた。)
第4表の値を用いた標準的な食品摂取モデル注2)を設定すれば放射性核種濃度から内部被ばく線量を次式により算出できる。 〔mrem/年〕=第4表値〔mrem/pCi〕×1日の摂取量〔g(生)/日〕×放射性核種濃度〔pCi/g(生)〕×365〔日/年〕×摂取期間年間比
注1) 環境・安全専門部会の「環境放射能分科会報告書(昭和49年7月)」の「附録-4」“環境放射能による被ばく”を参照。 注2) 5ページの脚注の食品摂取のモデルを参照。 2-3-2 総合評価
原子力施設周辺の被ばく線量の推定値が許容被ばく線量を十分下まわっているかなど、環境放射線モニタリングの結果を総合評価するため、関係地方公共団体(都道府県を単位とすることが望ましい)において地域の実情に応じ地方公共団体、地元住民等関係者をまじえた監視、評価機構を組織することが望ましい。 またその公表に際しては、モニタリングの目的をふまえ、
① 被ばく線量の推定評価の結果がどうであるか、及び
② 放射性物質の蓄積傾向がどうであ扇か(環境放射能レベル)について、また併せて
③ モニタリング結果の評価に必要な原子力施設の稼働状況に関する情報等の公表が望まれる。 2-4 モニタリングデータの記録等について
この指針に準拠した計画によって得られたデータの記録は自動的データ処理にも適合した明確で均一な様式に従ってなされることが望ましい。 また、これらのデータは特定地域ばかりでなく広域的、長期的観点からの評価に対しても十分受け入れることができるよう、データの記録様式を定め、管理を行う。 また、個々のデータに対応する記録内容の他に、線量評価に係る人口分布、食品の流通経路、生産量、その他各種のパラメータ等についての情報の収集、保存等に留意する。 解説
〔Ⅰ〕本指針の基本的考え方
(1) 環境放射線モニタリングのあり方について、昭和49年7月に原子力委員会に答申された環境・安全専門部会の「環境放射能分科会報告書」に示されたが、そこで述べられた国の役割としての、これに係る「測定、分析、評価方法等の基準化」、「総合調整」、「地方公共団体への指導、助成」等の項目に従い、さらにICRPの諸勧告の精神を取り入れて、本指針を示すものである。 (2) 環境放射線モニタリングの基本目標は、同分科会報告書に述べられている通り、原子力施設周辺公衆の健康と安全を守るため、環境における放射線量が、公衆の個人に容認される線量限度を十分下まわっていることを確認することにある。同報告書はまた、原子力施設を中心とする全体的なモニタリング計画についての具体的な目的が示されており、また、地方公共団体としての役割が示されている。 (3) 前記基本目標の具体的達成は、次の三項目に要約される。 i) 公衆の被ばく線量を推定、評価すること。 ii) 環境における放射性物質の蓄積傾向を把握すること。 iii) 原子力施設からの予期しない放射性物質の放出による周辺環境への影響の判断に資すること。 そのための技術的手段としては、環境放射線(能)の測定、原子力施設からの放射性物質の放出源情報及び線量評価のためのパラメーター等に関する情報の収集が必要である。 (4) 国においては、原子力委員会におかれている環境放射線モニタリング中央評価専門部会において、国又は地方公共団体からモニタリングに関する指導、助言等の要請があるとき審議することとなっている。 また、地方公共団体は、地元住民の健康と安全を守る立場にあり、原子力施設周辺住民の理解を得るために必要な措置をとり易く、環境放射線モニタリングの実施に際して必要となる社会的、自然的条件を把握しやすい立場にある。したがって、関係地方公共団体(都道府県を単位とすることが適当と考えられる。)は、モニタリング結果等を評価するため、地域の実情に応じ地方公共団体、地元住民等関係者をまじえた監視、評価機構を組織することが望ましい。 また、総合評価、及び公表にあたっては、環境放射線モニタリング中央評価専門部会と十分な情報交換を行うことが望まれる。 〔Ⅱ〕一般的事項
(1) 本指針では、住民の健康・安全を確保することの担保として、公衆の個人に容認される線量限度500mrem/年を十分下まわっていることが確認できればよいと考えられるが、“十分下まわっていること”についての数量的表現は示されていない。しかし、指針に示されている放射線および放射能の測定法によれば500mrem/年を十分下まわる線量の評価が可能である。その際、とくに発電用軽水炉について定められている線量目標値(昭和50年5月13日原子力委員会が示した指針)については、当該指針の定められた趣旨からして、住民の健康・安全を直接おびやかす性質のレベルではないので、地方公共団体としてはこの意味でこのレベルにとらわれる必要はない。 (2) 本指針で示されているモニタリングの内容は、環境の管理という社会的要請に即応するのに必要な範囲に限られている。このほか、モニタリング計画の見直しの際に役にたたせるといった補足的な、あるいは研究的な調査も必要に応じて実施すべきである。ただ、その際注意すべきことは、前者は社会的要請に応ずるものであるから社会への公表を必要とするのに対し、研究的調査にはその必要は必ずしもないということである。 〔Ⅲ〕指針の適用にあたって
本指針の性格については指針のまえがきにも明らかにされているが、具体的な適用にあたっては次の事項に留意する必要がある。 (1) 今後、新規に原子力施設周辺の環境放射線モニタリング計画を立案し、所要の施設等を整備する場合には、本指針を参考にすることが望ましい。 (2) また、既に環境放射線モニタリング施設等を整備した関係地方公共団体にあっては、モニタリング計画等の見直し等を行う機会に、できるかぎり本指針の考え方を参考にして逐次改善に努めることが望ましい。 参考資料
A 環境放射線の測定
環境放射線線量(ふつうはガンマ線による照射線量)の計測は、被ばく線量の主な寄与分が知り得るということで重要であり、さらに連続計測による場合は、環境放射線レベルの変動を比較的すみやかに知ることができるという点で意義が大きい。 一般に環境放射線には、大地、大気からのガンマ線、宇宙線、また核爆発実験により広い地域に拡散した人工放射性核種からの放射線、原子力施設の放出物からのガンマ線、などが含まれる。この放射線線量は空間的な不均一性、時間的変動が比較的大きいこととともに、放射線の特性として広いエネルギー範囲を持ち、寄与放射線源によって方向が異なるなど複雑な様相を示す。 環境放射線モニタリングにあたっては、これらの特性を十分考慮してなされるべきであるが、技術的にも容易ではないので、ある程度選択的な計測にならざるを得ない。 ガンマ線の計測エネルギー範囲は検出器とその計測系の性能に応じて変って来る。対象エネルギーの上限として、一般的に3MeVの採用が無難であろう。もちろん検出器によっては、より広いエネルギー範囲の計測が可能であることに注意を要する。 検出器の方向依存性、自己汚染、エネルギー依存性の違いなどによって種々の検出器系によって計測値は異なる場合がある。したがって、種類の違った検出器による測定値の絶対値を比較することには注意が必要である。しかし、原子力施設からの寄与による線量の増加分を評価することは可能である。 また、計測器、特に検出器の配置等、例えば、設置高さ、付近の地形、付近の構造物の影響によって同種の計測器によっても計測値が違って来るので各設置点の周辺を含めた設置状況を同じにすることが望まれる。 なお、環境放射線レベルの測定には通常つぎのような名称の施設が使われる。 モニタリングステーション:ガンマ線線量率計に加えてダストサンプラ及び気象要素の測定機器を具備した野外固定施設等で多目的な用途をもつもの。 モニタリングポスト:ガンマ線線量率計を具備した野外固定施設等で主に、環境線量測定を対象とするもの。 モニタリングポイント:積算線量計を具備した野外固定施設等で、とくに積算線量の測定を目的としたもの。 A-1 空間ガンマ線量の連続測定法-(暫定指針)-
1 概要
現用の空間ガンマ線量計測器で検出感度の高いものは、0.2μR/hr程度の短期の変動を十分に検出し得る能力を持っている。 計測用モニタにはいくつかの種類があり、各々特長を持っている。しかし線量値を高感度に計測し得るということになれば、限られてくる。現用のものとしては、電離箱方式(加圧または大容量型)NaI(Tl)しンチレーション検出器を用いる方式(特殊遮蔽付、またはDBM方式)注)がある。これらを用いた計測結果の間には特性の違いによる差がある。電離箱方式では宇宙線のような高エネルギー成分が計測可能であるが、NaI(Tl)シンチレーション検出器を用いたものでは相対的に宇宙線の検出感度が低くなっている。宇宙線によるバックグラウンド線量寄与が小さいということで後者が有利のようであるが、高エネルギー放射線寄与があった場合不利になる。 両方式ともにその特長を生かせば、有効なモニタとなり得るものの両者による計測結果の比較には注意を要する。すなわち、上にあげた高エネルギー放射線の寄与の差があるために、通常は電離箱方式がほぼ宇宙線寄与分に相当するだけ高い値になる。 2 計測器
要求される基本性能は、高感度、高安定性、エネルギー特性の平担さである。このような性能が連続モニタとして満足されるものを現用のものに限って概略を〔表A-1〕に示した。 なおガンマ線モニタのみでなく、気象観測装置等も総合評価のために必要とされる。 〔表A-1〕計測器の概要 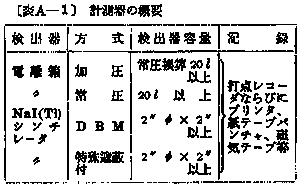 なお、これらは自動レンジ切換装置がついていることが望ましい。 3 設備
全体的な配置プランに従い、周囲が開放的な地点に、高温、高湿等の悪環境を避けて設置する。 もちろん立入りの容易さ等の一般条件も満たされていることが必要である。 4 操作
1) 装置は取扱い説明書にもとづいて、調整と正しい使用を行うこと。 2) 計測は連続を原則とし、常に作動させておくこと。 3) 計測レンジは、指針本文中の2-1の目やすレベルが把握できるていどにしておく。 4) 記録紙の送り速度は結果の見やすいように設定する。 5) 記録紙の時刻目盛りの合せ、記録の点検等はできるだけ頻繁に行うこと。 6) 標準線源による定距離チェックを、3ケ月に1度程度行なうこと。 7) 1年以上に亘る1時間平均値よりM及びσを求める。(指針2-1参照)
5 計測結果の記録と報告
1) 記録方式 2方式併用
① 各計測局での打点レコーダ記録
② ディジタルデータの記録
2) ディジタルデータ
各正時以前1時間の積算値、又は平均値をその時刻の値として記録する。 記録時間間隔が短いときは、積算、又は平均の手順は上に準じ、積算、又は平均の時間巾は記録時間間隔に合わせる。 3) 打点レコーダ記録の読みとり
常時読みとりは、通帯の場合必要ではないが、必要なときの読みとり方式は、ディジタルデータの記録方式に準ずる。 すなわち、瞬間値は読まないで定時間間隔の平均値を読みとる。 4) 報告
1ケ月間の計測値(1時間平均値または積算値の1ケ月間集積)の平均値、最大値及び最小値を報告する。 A-2 TLDによる空間ガンマ線量の測定法-(暫定指針)-
1 概要
環境計測用の積算線量計では、ふつう、1ケ月以上の長期にわたり積算された、いわゆる積算線量が計測される。環境の積算線量測定用のものは、一般に、エネルギー特性が平坦で、かつ高感度、高安定である必要がある。 TLDはフィルムバッジ等の他の線量計にくらべ、上記の要求される性能を比較的満足している。そのため空間ガンマ線量測定用としてTLDがよく用いられている。しかし、高感度とはいえ空間ガンマ線量連続モニタにくらべて検出感度が桁違いに低いため、環境用としては長期にわたる積算値を求めるのに用いられている。計測期間が長期に亘るため長期の計測安定性の確認が必要である。 現用のTLDの検出下限は理想的状態で5mRとなっており、かなり高い感度を持つこと、素子のくり返し使用が行なえること、検出器が小型であること、計測値の読みとり操作が極めて簡単であることの利点があるが、他検出器にくらべて非常に小さいとはいえ検出器自身、およびその他固有のバックグラウンドがはっきりさせにくいこと、宇宙線寄与分も併せて検出すること、フェーディングがあること、読みとりがくり返せないことなどの不利な点がある。 TLD素子にはいろいろの種類があるが、高感度の環境用のものなら性能上大きな差はなく、積算線量計としての利点を有効に用いれば種々の場面に使用し得る。 2 TLD素子の選択及び一般操作
材質、形状は種々のものが入手できるが、各々に合ったリーダ等を用い、環境放射線測定用で高感度のものを選ぶこと、この場合、JIS規格に合致したTLDを使用することが望ましい。 1回の測定に使用する素子は、モニタリング用、比較対照用、標準照射用を通じて同一ロットのものであることが要求される。それはロットの違いによる性能の差をできるだけ避けるためである。比較対照用の素子による計測値には明確な意味があるわけではない。モニタリング用素子による計測値に対し参考にするものである。 なお、定期的な照射による計測を行い、異常素子を除く操作を行っておけば、環境計測で得られる精度は向上する。 一般的操作としては、基本的には、各素子種類ごとにそれに相応した方式に従って操作を行うこととする。 3 環境での計測
1) 準備
アニーリング、加熱温度、加熱時間、アニーリング終了から計測開始までの時間等に注意すること。 その他、収納袋、収納箱(区別用記号付き)、比較的照素子の収納用鉛容器、標準線源等必要なものを準備しておく。 2) 環境での計測
① 素子数
モニタリングポイントに6素子の同時設置、標準照射用として4素子以上、比較対照用として6素子以上を用意することが望ましい。 以上の3種を含む同一時期の1回計測における全素子は、同一ロットのもの、又は感度が同じ程度であることがチェックされたものであること。全所要素子数
② 設置
モニタリングポイントに、巣箱様収納箱(ポール付)を設置するか、又は適当な器物を利用するかして、包装された素子を置けるようにしておく。素子はホルダに納め、その際設置された素子の温度が異常に高くならないよう注意する。 比較対照用素子は鉛容器内(厚さは約5cm以上)に置く。これは宇宙線、自己汚染の寄与分を知るためである。設置場所は代表的なモニタリングポイントとすることが望まれる。 設置の際は、上記の高温以外に、直射日光、降水、振動等を避けなければならない。標準照射用素子はアニーリング後、照射にいたるまでの期間鉛容器内に収納し、バックグラウンドが高くない場所に置く。 ③ 計測期間
通常は3ケ月に1回の割合で交換する。その期間は1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の4半期にすることが望ましい。 交換は、モニタリングポイント用、比較対照用両素子について行う。 ④ 標準照射用TLD素子
標準照射用TLD素子を所定のホルダ内に収め、計測対象とする程度までの線量について照射を行い、検量線を作成する。照射用TLDは、素子に応じた期間待った上でリーダで読み取る。 標準照射によるTLDシステムの校正は、各回の測定ごとに行う。すなわち3ケ月に1回の交換時に行なう。 ⑤ 読み取り
各TLD素子に合致したリーダを使用して、モニタリングポイント用、比較対照用、標準照射用各素子の読み値を得る。 ⑥ 線量換算
モニタリングポイント用、比較対照用素子の読み値から、標準照射による校正値を経て空間ガンマ線量相当値が得られる。 ⑦ 3年間以上に亘る、3ケ月積算値について、M及びσを求める。(指針2-1参照)
4 線量値の推定
1) 異常値の扱いと平均
上で求めた線量値をモニタリング地点ごとにまとめ、少数のいちじるしい異常値があればその値を除く。残りの平均をとり、その地点の積算線量値(相対値)とみなす。 かけ離れた値を出した素子は再使用しない。 2) 線量
各ポストごとの平均値は計測された線量に相当するが、その参考、又は比較対照用素子の平均値を併記する。 B テレメータシステム
1 概要
各測定点における空間ガンマ線量、大気中浮遊じん等の計測データを集中的に集計、記録、整理、解析するために、データを中央に送り、処理するシステムとしてテレメータシステムがある。 テレメータとは、伝送の意味で、間違いなくデータを伝送できればよいことは言うまでもないが、各地方公共団体が持つこのようなシステムは本来緊急時用ではない。線量の集中管理レベルに異常があるかどうかのチェック用である。しかし高いレベルの変動があるときは、緊急時用のチェック、管理システムとして有効である。 2 伝送様式
1) ディジタル・データの伝送がミスを少なくするという意味で現用されている。実際、そのような様式が望ましい。 2) 伝送の様式は有線、無線いずれでもよく、経済的問題、伝送の難易度等によって選ばれるべきである。 3) ただ、検出器の計数率、積算時間、高いレベル時の関係で、伝送の容量については十分注意をなすべきである。 4) 伝送のコードはできるだけパリティエラーチェックができるような形式にすべきである。 5) 伝送の入出については、できるだけ安定であることが望まれる。 3 伝送の内容
伝送の内容としてはデータが集中される中央局で計測器の異常、環境の異常、放射線量の大きな変動を把握できるようでなければいけない。 1) 環境放射線連続測定データ
線量率が主体であり、可能なら計数率も測る両者の伝送により電子回路のチェック、環境ガンマ線、エネルギー分布の違いの検出が可能になる。 2) 気象要素
モニタリングステーションに気象要素検出器がある場合、回線の許すかぎり、環境放射線量について伝送されることが望まれる。 気象データは環境放射線量に異常が見られた場合、気象等の環境条件の変動がその原因であるかどうかをチェックする目的のものである。 したがって、テレメータの重要性は次の順序で行うべきである。 ① 降水量
② 積雪量
③ 湿度
④ 雷
ただし、自動観測機器の能力によって、このうちの③、④が省かれることもある。 第二のグループは、
① 風向
② 風速
③ 日射量
④ 放射収支量
⑤ 気温
である。このうち③、④、⑤は省いてもかまわない。 4 中央制御装置
小型コンピュータを中心としてデータの受入れ、記録、整理、警報等の機能を持つ。 (構成)
1) 小型コンピュータ
コントロール用ソフトウエア、一時的なメモリーのために十分なメモリー容量を持つもの。 2) 補助メモリー
磁気テープが主となり、記録保存用として欠かせない。 3) 入出力装置
ラインプリンタ、CRTディスプレイ、ハードコピー装置、XYプロッタ、キーボード入力装置など、必要程度に応じ備える。 4) その他の装置
モニタリングステーションとの相互連絡装置等必要に応じ設置する。 停電対策用電源は備えておくことが望ましい。 C 放射線(能)測定法
指針の本文中に述べられている環境試料のモニタリングは、ガンマ線スペクトロメトリーによる機器分析法が主体となるが、放射化学分析による放射能測定法も科学技術庁で定めているので、指針中の測定法もこれに準ずるものとする。なお、放射化学分析による環境放射能の検出レベルを〔表C-1〕に示した。
〔表C-1〕放射化学分析による環境放射能のレベル 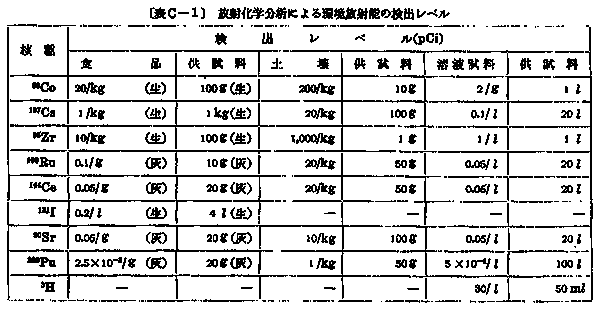 表の値は科学技術庁が定めた「放射能測定シリーズ」から採ったものである。239Pu、3H以外の放射性核種の測定は低バックグラウンドガスフロー(GM又は比例)計数装置で行なわれるが(測定時間はほぼ60分間)239Puはアルファ線スペクトロメータ(24時間測定)3Hは低バックグラウンド液体シンチレーション検出器(500分測定、100mlのバイアル(うち試料水は50ml)を使用)を使ったときの値である。 D 被ばん線量の推定と評価法
1 放射性物質の経口摂取による被ばく線量
ICRP第2委員会の被ばく線量計算式パラメータを用いて主な核種の単位量の経口摂取による成人の各種臓器の被ばく線量を求め、〔表D-1〕に示した。 なお、〔表D-1〕中の放射性ヨウ素の甲状腺への移行比fwには0.2を使用した。また、成人、小児、乳児に対する年間線量は、
merm/年=〔表値〕×〔核種の1日摂取量(pCi/日〕×365(日/年)×〔摂取期間年間比〕×年令補正
年令補正=1(成人)、5(小児)、10(乳児)
となる。 また、軽水炉原子力発電所から環境に放出される液体廃棄物中に含まれる主な放射性物質の核種組成を〔表D-2〕にまた、使用済核燃料再処理施設から環境に放出される液体廃棄物中に含まれる放射性核種の平均的割合の例を〔表D-3〕に示した。 〔表D-1〕1pCiを経口摂取した場合の成人の全身および臓器線量預託 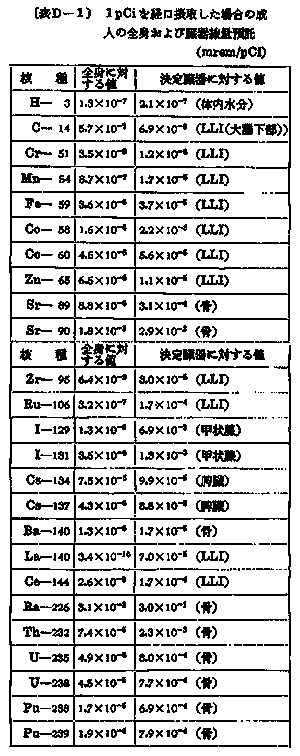 〔表D-2〕軽水炉原子力発電所から環境に放出される液体廃棄物中に含まれる放射性物質の核種組成注) 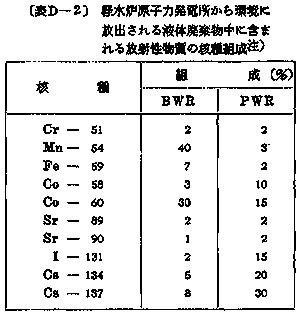 〔表D-3〕使用済核燃料再処理工場から環境に放出される液体廃棄物中に含まれる放射性物質の核種組成の平均的割合の例注) 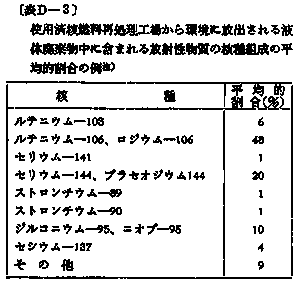 2 放射性ヨウ素による甲状腺被ばく線量
原子力委員会は先に「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」の中で放射性ヨウ素による甲状腺被ばく線量の評価方法および関連パラメータに対する標準的な値を示した。これを〔表D-4〕、〔表D-5〕に示した。これによると、地表附近大気中および海洋中の放射性ヨウ素年間平均濃度が10-6pCi/cm3の場合、甲状腺被ばく線量はつぎのようになる。 〔表D-4〕大気放出の場合 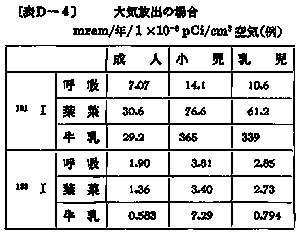 〔表D-5〕海洋放出の場合 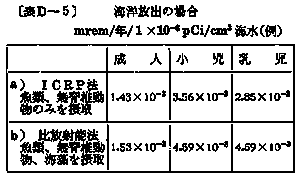 E 核爆発実験直後の放射性降下物
これは、核爆発実験が行なわれた場所によって、爆発後日本にその影響が、現われる時期が異なる。中国大陸で行なわれた大気圏内核爆発を例にとると、日本に影響が現われるのは、爆発後2~3日に第1の山があり、その後1週間~10日後に第2の山がある。第1の山は、対流圏に注入された核分裂片が直接到着したものであり、第2の山は日本上空を通過後地球を一周した後に到着したものである。また、地域差はあるが一般的に、到着時間は西日本が早く順次東に移動してゆくパターンをとる。これは、日本上空を流れる偏西風による。しかし、核爆発が行われると必ずこうなるとは限らず、爆発が行なわれた高さ、位置、規模、爆発の型、季節などによって、日本への影響の程度が異なるので、予断をしないことである。 1) 核爆発直後の放射性降下物核種
核爆発直後の放射性降下物核種は、短半減期の核種の占める割合が大きく、しかも爆発後の経過時間によって、その割合が大きく変る。この経過時間による割合は、〔図E-1〕のHunter-Ballouの図(Nucleonics.9、Nov、C-2、1951)を参考にして推定する。 厳密には、爆発に用いられた核物質、つまり235Uか239Puによって、また爆発の型、核分裂か核融合かによって、核分裂物質の生成割合は異なるが、実際にはその差はあまり問題にならない。爆発後数日から1週間位までの間に、例えば大気中浮遊じん及び雨水中に検出される主な核種は次のようなものである。 239Np、99Mo、132Te、131I、132I、133I、143Ce、91Sr、95Zr、97Zr、95Nb、140Ba、140La
2) 新たな核爆発実験がないときの放射性降下物
新しい核爆発によって大気圏に新たな核分裂片の注入がないときの放射性降下物は、比較的半減期の長い核種である。主な核種は、95Zr、95Nb、103Ru、106Ru、103Rh、106Rh、141Ce、144Ce、90Sr、137Csとその娘核種である。またときとして、60Co、54Mnなどの核種が検出される場合もある。これらの核種の地上への降下のパターンは、年間を通じて4月、5月、6月に最も高い降下量が出現し、11月、12月、1月に最低となる。このような季節変動が毎年出現し、最大と最小の幅は10倍以上になる。また降下量は地域によっても差がある。 このような放射性降下物に関するデータは日常のモニタリングデータの中で常に把握しておくことが必要である。そのデータから例えば放射性降下物中の核種間の比をあらかじめ求めておくことによって、その比が極端に変れば、それは放射性降下物以外の原因による核種の混入が推定できる。 しかし、放射性降下物中の核種は時間的、空間的な差が著しいので、そのデータの取り扱いには十分に注意する必要がある。 〔図E-1〕 ウラン235の熱中性子による核分裂に際して放出される主な核種と分裂後の放射能の推移/(Hunter-Ballouの図) 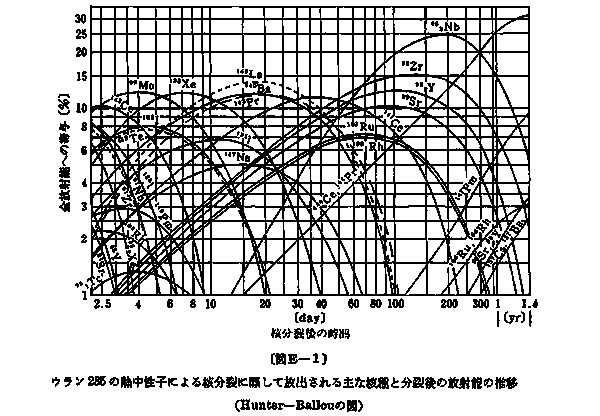 委員等名簿及び会議開催経過
1. 環境放射線モニタリング中央評価専門部会
(イ) 専門委員名簿(50音順)
(ロ) 特別に審議に参加する者
(ハ) 開催日
第6回 昭和51年10月14日(木)
第7回 昭和52年4月19日(火)
第8回 昭和52年12月13日(火)
2. 環境放射線モニタリング指針検討会
(イ) 構成員
(ロ) 開催日
第1回 昭和51年11月26日(金)
第2回 昭和52年2月18日(金)
第3回 昭和52年4月19日(火)
第4回 昭和52年6月23日(木)
第5回 昭和52年9月5日(月)
第6回 昭和52年10月5日(土)
第7回 昭和52年11月19日(土)
3. 環境放射線モニタリング指針検討会ワーキンググループ
(イ) 構成員
(ロ) 開催日
第1回 昭和51年12月24日(金)
第2回 昭和52年1月12日(水)
第3回 昭和52年1月28日(月)
第4回 昭和52年4月7日(木)
第5回 昭和52年4月26日(火)
第6回 昭和52年5月11日(水)
第7回 昭和52年5月30日(月)
第8回 昭和52年6月24日(金)
第9回 昭和52年10月15日(土)
第10回 昭和52年11月19日(土)
注) Discrimination Bias Modulationの略でエネルギー補償型式の一方式である。 注) 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」原子力委員会 原子炉安全技術専門部会、昭和51年9月
注) 「動力炉・核燃料開発事業団の再処理施設の安全性の確認について(昭和52年5月20日)」原子力委員会報告 別表1より引用
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||