| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||
|
取替炉心検討会報告書 昭和52年4月
原子炉安全専門審査会
取替炉心検討会
Ⅰ 検討目的 原子炉設置許可申請の審査にあたっては初装荷炉心のみならず、取替炉心も含めて当該原子炉の安全性が確保されていることが確認される必要がある。 一方、取替炉心に関するパラメータの一部は原子炉の運転履歴に依存するため、運転開始後においても、原子炉設置許可申請審査段階において提示された安全に係る諸基準が満足されていることを再確認する必要がある。 以上のような観点に立って当検討会は、取替炉心の安全性に影響する主要なパラメータや核的・熱的制限値について再検討し、さらに現行の原子炉設置許可申請書の取替炉心に関連する記載内容を吟味することとした。 Ⅱ 検討範囲 本検討会は軽水型動力炉の取替炉心を対象とし、以下の項目について検討した。 1 原子炉設置許可申請書の取替炉心に係る用語及び記載内容
2 取替炉心の安全性確認のための主要パラメータ及び核的・燃的制限値
3 取替炉心の安全性に関連した検討項目
3.1 スクラム反応度曲線
3.2 ガドリニア入り燃料に関する申請書記載内容(BWRの場合)
3.3 取替炉心におけるバーナブルポイズンの使用(PWRの場合)
Ⅲ 検討結果 1 取替炉心までを包含する申請書記載内容
従来の原子炉設置許可申請書では初装荷炉心と取替炉心に関する用語に多少の不統一があり、また主に添付書類中に表現上で初装荷炉心と取替炉心の区別が必ずしも明確でない部分がある。用語上の問題として例えば申請書では「初装荷炉心」と「平衡炉心」という用語を使用しているが、「平衡炉心」の定義が必ずしも明確になされておらず、従って「初装荷炉心」からいわゆる「平衡炉心」に移行する間の第2、第3サイクルなどについて記載が欠如しているかごとき印象をあたえる。 このような点の改善策として「平衡炉心」の代りに「取替炉心」という用語を用いることによって第2、第3サイクルなどのいわゆる移行炉心をも含めた表現にし、「取替炉心」という表現で正確を欠く場合には「第2サイクル」、「第3サイクル」、「それ以降の取替炉心」というように別々に記載することとした。このようにすることによって、通常燃料取替計画から多少変更のあった炉心についても包含した表現であることになる。 なお、炉心特性が平衡に達した炉心という意味で平衡炉心という言葉を用いることは差支えない。 「平衡炉心」も含め用語で変更すべきであると考えられるものを表1に示す。 次に記載内容の面で改善すべき点は基本的には以下の通りである。 (1)初装荷炉心と取替炉心とで変わり得るパラメータ等についての記述をする場合は、Ⅵ-2に述べる取替炉心の安全性確認項目との関連で取替炉心の安全性が確認され得ることがわかる記載内容とする。 (2)初装荷炉心と取替炉心とで変化がないパラメータ等については、あえて区別して記述する必要はない。 このような観点に立った申請書記載内容の変更が必要であると考える。 2 取替炉心の安全性確認のための主要パラメータ及び核的・熱的制限値
取替炉心の安全性は燃料交換によって生ずる炉心パラメータの変化が安全上許容できる範囲内に入っていることによって保証される。燃料交換によって変化し得るパラメータは数多いが、これらは必ずしも独立性を持ったパラメータばかりではないことと、安全上重要でないパラメータもあることなどから、これらのパラメータのうちから確認しなければならない必要十分なパラメータを選定し得る。 このような観点から、BWR及びPWRそれぞれについて確認の必要なパラメータを選定し、取替炉心の安全性確認項目として表2に示した。 これらの安全性確認項目は取替炉心毎に実測もしくは計算結果に基づいて確認すべき項目であると同時に取替炉心に係る原子炉設置許可変更申請があった場合に重点的に審査しなければならない項目である。 BWRにおけるボイド係数とドップラ係数については、検討を行った結果、これらについては取替炉心も含めて十分な安全余裕があり、取替炉心毎に確認する必要はないとの結論を得た。 PWRでのドップラ係数についても同様である。 また、BWRの原子炉起動時の最大制御棒価値については、制御棒引抜シーケンスの設定に関する基本的な考え方を明確にすることによって取替炉心も含めて安全上の設計基準が満足されるという結論を得た。 さらに事故解析に使用される核的・熱的パラメータが、初装荷炉心、取替炉心を含めて保守的に採られていることを確認した。また炉心の安全性に確認する試験項目、ならびに運転に入ってから安全に係るパラメータの確認状況について現状を調査し、それらが適切になされていることを確認した。 3 取替炉心に関連した検討項目
取替炉心の安全性に係る一般的事項であり、各部会で検討するよりは共通事項として検討した方が良い事項についての検討を行った。 3.1 スクラム反応度曲線
運転時の異常な過渡変化及び事故解析に使用するスクラム反応度曲線が初装荷炉心及び取替炉心に対して適切な安全余裕があることを確認するため以下の検討を行った。 3.1.1 BWRのスクラム反応度曲線
1)BWR-4、5型
BWR-4、5型の原子炉では設計用スクラム曲線として2種類の曲線(早期炉心用スクラム曲線及び平衡炉心未期用スクラム曲線)が用いられる。これらの曲線の適用期間は以下の通りである。 (1)早期炉心用スクラム曲線
初装荷炉心から第3サイクルまでの全期間と第4サイクル以降の各サイクルにおいてサイクル初期よりサイクル末期からさかのぼって炉心平均燃焼度で1,000MWd/t手前までの期間に適用される。 (2)平衡炉心末期用スクラム曲線
上記(1)以外の期間に適用される。 このように2種類のスクラム曲線を使いわける理由は、取替炉心サイクル末期の極く短い期間でスクラム特性が劣化することに起因しているが、2種類のスクラム曲線の適用期間について検討を行ない、その使いわけは適正に行われ得ることを確認している。 スクラム反応度曲線について制御棒挿入率50%までの積分値を指標として選ぶことにより、過渡解析結果を評価できると判断し、それぞれのスクラム反応度曲線の妥当性を確認した。 スクラム反応度曲線に大きな影響を持つ主な因子としてはスクラム直前の炉心内制御棒密度、軸方向出力分布及びスクラム速度がある。 スクラム直前の炉心内制御棒密度については制御棒密度の減少とともにスクラム反応度曲線は悪化するので制御棒全引抜きを仮定している。 軸方向出力分布については、出力分布の平担化とともにスクラム反応度曲線は悪化するが、2つのスクラム曲線のいずれに対してもサイクル末期の現実的な出力分布に比し平担である。このようなことからスクラム反応度曲線のサイクルの進行に伴なう変化とサイクル中での燃焼度に伴なう変化を考慮しても、それぞれの設計用スクラム反応度曲線が適用される期間において十分保守的であることが認められる。 さらにスクラム速度については90%挿入時間が解析では3.5秒を使用しているが、実測値によれば約2.6秒程度であることから、スクラム反応度曲線の潜在的余裕も十分あるといえる。 2)BWR-2、3型
BWR-2、3型では「早期炉心用スクラム曲線」相当の1本のスクラム反応度曲線だけを用いている。これはサイクル末期でも制御棒が炉心内に残っているか、軸方向出力分布が下に大きく歪んでいるという実績がすでに数サイクルにわたって得られており、今後の運転方式にも大幅な変更がないと云う見通しに基づいている。 実際の運転実績に基づいて評価したスクラム反応度曲線と設計用スクラム曲線とを比較した結果から、設計用スクラム曲線は十分な余裕を持って全期間を適用できるものと判断される。 そのほか、ワン・ロッド・スタックの効果、制御棒ボロン濃度劣化の効果についても検討したが、スクラム効果に対する影響はほとんどなく、また原子炉圧力が上昇した場合のスクラム速度についても検討し、問題ないことを確認している。 3.1.2 PWRのスクラム反応度曲線
PWRの場合、出力運転状態では制御棒クラスタはほぼ全引抜の状態にあり、従ってスクラム反応曲線に影響を与える因子としては軸方向出力分布とスクラム速度である。スクラム速度については一例をあげると実測に基づくものが85%挿入1.6秒程度であるのに対し解析では2.2秒を使用しており、スクラム反応度曲線の潜在的余裕と云える。 軸方向出力分布に関しては初装荷炉心にあってはサイクル初期、取替炉心にあってはサイクル末期に下方に最も歪んだ出力分布となり、スクラム曲線は劣化する。 解析に用いるスクラム反応度曲線を与える軸方向出力分布は出力分布調整用制御棒クラスタの現実にあり得ないような使い方をも考慮して極端に下方に歪ませた出力分布になっており、十分保守的である。 また過渡解析ではスクラム時のワン・ロッド・スタックに対しても十分な安全余裕を見込んでおり、これはスクラム反応度曲線に対する余裕と云える。 以上のことから取替炉心を考慮してもスクラム反応度曲線については何ら問題はない。 3.2 ガドリニア入り燃料に係る申請書記載方法(BWRの場合)
従来の設置許可申請書におけるガドリニア入り燃料の設計に関する記述は停止余裕、熱的制限値等の核燃設計基準を初装荷炉心及び取替炉心に適用することを前提として
① ガドリニア添加の目的、考え方
② 初期ガドリニア濃度の範囲
③ 燃料集合体当りのガドリニア燃料棒本数
を示している。これは一般にガドリニアの濃度、燃料棒本数、軸方向分布等の詳細設計と最適化が個々のプラントの運転計画や運転履歴に依存するため最終設計段階で行なわれること、および前記の核燃設計基準を満足しておれば、安全上それほど重要な因子にはならないことによる。 安全審査においては原子炉の基本設計段階での原子炉の安全を確保するという立場にあり、従って従来の記載範囲は妥当なものであると考える。 なお、初装荷炉心用ガドリニア入り燃料の詳細な内容に関する補足説明は各部会で審議することが妥当であると考える。 3.3 取替炉心におけるバーナブル・ポイズンの使用(PWRの場合)
PWR取替炉心におけるバーナブル・ポイズンの使用に関し、その妥当性を確認するため検討を行った。 取替炉心にバーナブル・ポイズンを使用することに関して熱水力設計上特に問題となる点はなく、核設計については、従来から使用され、その妥当性が認められている核計算コードを使用し、取替炉心を十分に包含する炉心の解析を行った結果、ピーキング係数、減速材温度係数、ドップラ係数、反応度停止余裕などについては、いずれも従来の核設計制限値を十分満足しており、また事故時のピーキング係数についても従来の解析値以内に入ることを確認した。 バーナブル・ポイズンを長期間にわたり使用するという観点から、その健全性についても検討を行った。バーナブル・ポイズン棒は、ステンレス鋼の被覆管を使用し、非加圧設計になっている。被覆管にかかる応力は、初装荷炉心寿命初期に最大となり、この時でも被覆管の許容応力を超えるような応力にはならない。 またホウケイ酸ガラスの温度も軟化点に比し十分低いことを確認した。被覆管の疲労、クリープ・コラプス、スウェリング及び歪について30年間使用した場合の評価を行い、健全性について確認した。また、バーナブル・ポイズン棒上下の溶接部の健全性についても、中性子照射量が比較的小さい位置にあるため、問題はないと考える。 以上の検討の結果、バーナブル・ポイズンを取替炉心において使用することには問題はないが、照射実績が得られるまでは十分保守的に対処する必要がある。バーナブル・ポイズンの使用期間は原則として15EFPY(換算全出力年)以内とするのが望ましく、5EFPYを超え使用するものにあっては、定期的に外観検査を行ない異常のないことを確認するのが妥当であると判断する。 なお、前記事項はバーナブル・ポイズン管理基準として保安規定等に盛込むのが妥当である。 Ⅳ 検討経緯 原子炉安全専門審査会は昭和51年9月20日第151回原子炉安全専門審査会において、次のメンバーからなる取替炉心検討会を設置し、取替炉心に関する原子炉設置許可申請書の記載、取替炉心におけるバーナブル・ポイズン棒の使用等についての検討を指示した。 (敬称略)
本検討会は、合計10回の会合を持って検討した結果、本報告書を作成した。 Ⅴ 参考文献 TLR-025
沸騰水型原子力発電所スクラム反応度曲線について
表1 変更すべき用語 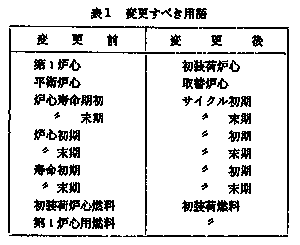 表2 取替炉心の安全性確認項目 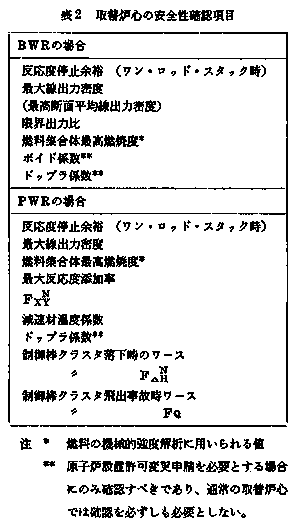 | |||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |